1. 概要

チャールズ・エドワード(1884年7月19日 - 1954年3月6日)は、イギリスのヴィクトリア女王とアルバート公の孫として生まれ、オールバニ公爵の称号を継承したイギリス王子であった。しかし、16歳でドイツのザクセン=コーブルク=ゴータ公位を継承し、その後はドイツの公爵として生活した。第一次世界大戦ではドイツ側を支持したため、イギリスの爵位や王族としての地位を剥奪され、戦後はドイツ革命によって公爵の座も失った。
ヴァイマル共和国時代には、ドイツにおける極右政治勢力、特にナチ党の熱心な支持者となり、積極的にナチスの活動に参加した。彼は1933年にナチ党に入党し、突撃隊(SA)の上級集団指導者を務めたほか、ドイツ赤十字社総裁、ライヒスターク議員といった要職を歴任した。特にドイツ赤十字社総裁としては、ナチス体制下での人権侵害や優生学思想の推進に関与し、障害者虐殺プログラムの事実を知りながらこれを黙認したとされている。さらに、ナチス・ドイツの非公式な外交官として、イギリスを含む各国を訪問し、ナチス体制のプロパガンダと外交的支援を目的とした活動を行った。
第二次世界大戦終結後、彼は連合国によって逮捕され、非ナチ化裁判において「同調者」と認定され多額の罰金刑を科された。また、所有していた財産の多くを失い、晩年は困窮の中で隠遁生活を送った。彼の生涯は、王族としての出自と、ナチズムへの深い関与という、複雑で論争の多い側面を持つ。特に、彼の行動が社会正義、人権、少数者保護に与えた否定的な影響は、現代において厳しく批判的に再評価されている。
2. 初期生活と背景
チャールズ・エドワードの初期の人生は、イギリス王族としての恵まれた環境で育ちつつも、父親の早逝や、その後のドイツ公国の後継者としての突然の移住といった大きな変化に直面したことが特徴である。
2.1. 出生と家族関係
チャールズ・エドワード・ジョージ・アルバート・レオポルドは、1884年7月19日にイングランドのサリー州にあるクレアモント・ハウスで生まれた。彼は主にチャールズ・エドワードの名を使用していた。彼の父は、イギリス女王ヴィクトリアの末息子であるレオポルド公爵であり、母はヴァルデック=ピルモント公ゲオルク・ヴィクトルの娘でオランダ王妃エンマの妹であるヘレーネ公女であった。歴史家のカリナ・ウルバッハはレオポルドを「ヴィクトリア女王の子供たちの中で最も知性的」と評している。
レオポルド公爵は血友病を患っており、チャールズ・エドワードが生まれる数ヶ月前の1884年3月28日に、カンヌで転倒して頭を打ち、急逝した。チャールズ・エドワードは誕生と同時に、夭逝した父の爵位であるオールバニ公爵位、クラレンス伯爵位、アークロー男爵位を継承し、「オールバニ公爵チャールズ・エドワード王子殿下」の称号で呼ばれた。男児は父親から血友病を遺伝することはないため、彼自身が血友病に罹患する危険はなかった。
彼の姉は、1歳半年上のアリス公女であった。極度の心配性であった彼は、しばしばアリスに頼り、この習慣は大人になっても続いた。二人は「結合双生児」とあだ名されるほど親密であった。
18世紀から19世紀にかけて、イギリス王室はヨーロッパ大陸のプロテスタント系、特にドイツの君主制家族と密接な家族関係を築いていた。ヴィクトリア女王の直系家族はザクセン=コーブルク=ゴータ家に属しており、女王の夫であるアルバート公は、子をなさなかったエルンスト2世公爵の弟であった。エルンスト2世はドイツ帝国の構成国であるザクセン=コーブルク=ゴータ公国を統治していた。ヴィクトリアとアルバートの長女であるヴィクトリア皇女は、ヴィルヘルム2世皇帝の母である。また、ヴィクトリアとアルバートの長男であるアルバート・エドワード王子はイギリス王位の法定推定相続人であった。そのため、彼らの次男であるアルフレート王子が1893年に叔父エルンスト2世の後を継いだ。王室伝記作家のセオ・アロンソンは、1887年のヴィクトリア女王の在位50周年を記念して描かれた家族の絵について次のようにコメントしている。
「これらの印象的な人物たちは、互いに『ダッキー』や『モッシー』、『ソッシー』といった愛称で呼ばれていたかもしれないが、その中には将来の多くの王、女王、皇帝、皇后が含まれていた。やがて、ヴィクトリア女王のこれらの直系子孫は、少なくとも10のヨーロッパの王座に就くことになるだろう。この老女王が『ヨーロッパの祖母』として知られるのは、もっともな理由であった。そして、君主がその見た目と同じくらい重要であると広く信じられていた時代において、それは当然のことであっただろう...[子供がそう思い込むのは]地上で最も強力な一族であったと。」
2.2. 幼少期と教育

チャールズ・エドワードは、出生から15歳までイギリスの王子として育てられた。幼少期は、病弱で繊細、神経質で疲れやすい子供と評された。王室に相談された医療専門家たちは、彼が未亡人となった母親が妊娠中に経験した悲しみによって永続的な影響を受けたと考えていた。チャールズ・エドワード自身の幼少期の記憶に関する記録は残っていないが、姉のアリスはこの時期を懐かしく回想している。
クレアモント・ハウスのオールバニ公爵家は「居心地が良く、快適で、整然としていた」と形容されている。夫の死後、イギリス議会は母ヘレーネに民生費から年間6000 GBPの補助金を支給した。これにより、結婚時ほどの富はなかったものの、子供たちの世話を担当する数人の使用人を含む、何人かの家政婦を雇うことができた。
子供たちの世話は主に乳母の責任であったが、毎日決まった時間には母親と共に過ごした。母親は子供たちに手編みのような実践的な技能を教え、日曜学校の授業も行っていた。ヘレーネは様々な19世紀の著名なイギリスおよびスコットランドの作家の文学作品を子供たちに読み聞かせた。彼女は愛情深い母親であったが、厳しい一面も持ち合わせており、子供たちを厳格な規律の下で育て、義務感を養うことを奨励した。しかし、チャールズ・エドワードはこの教育にうまく反応せず、母親やより広範な権威に対して恐れを抱くようになった。
チャールズ・エドワード、彼の母親、そして姉は、ヴィクトリア女王の近郊に住む広範な王室のメンバーに囲まれていた。彼らは頻繁に女王の様々な領地で時間を過ごした。チャールズ・エドワードはヴィクトリア女王のお気に入りの孫と評された。彼と姉はしばしばバルモラル城を訪れ、そこで将来の地位に備えた。ヴィクトリア女王は、子供たちが彼女が教え込みたかった宗教的価値観を反映した劇的な場面を演じるのを楽しんだ。家族の友人であったルイス・キャロルは、チャールズ・エドワードを宮廷の作法や儀式によく訓練された「完璧な小さな王子」と表現した。ヘレーネ公女はまた、子供たちを連れてドイツやオランダの親戚を訪問することもあった。

公務は王室の機能の一部であったが、アロンソンは、彼らが当時のイギリス国民の多くが暮らしていた非常に不快な状況については無知であったと示唆している。チャールズ・エドワードの母親は、ドイツの貴族としては珍しく社会問題に特に関心があり、アリスによれば、子供たちは他人に共感し、慈善活動に従事することを奨励されたという。
チャールズ・エドワードは幼い頃から軍事や王室の行事に興味を持つようになった。彼は子供の頃、イギリス陸軍のシーフォース・ハイランダーズ連隊で最初の儀礼的な役職を与えられた。ヴィクトリア女王は日記の中で、5歳の王子が「シーフォース・ハイランダーズの正式な制服」を着ていたことに言及している。13歳の誕生日の少し前、チャールズ・エドワードはヴィクトリア女王のダイヤモンド・ジュビリーのパレードに参加した。少年は行事の前にバッキンガム宮殿の屋根に登り、集まった群衆を見ていた。当時の報道では、彼は最も歓迎された参加者として記述された。
歴史家のフーベルトゥス・ビュシェルは、イギリス王室が若いメンバーの教育に高い期待を抱いていたと指摘している。チャールズ・エドワードの最初の教師は「ポッツ夫人」という女性家庭教師で、彼女は彼と姉に一緒に教えていた。姉弟は彼女の授業から歴史への生涯にわたる興味を抱き、歴史的な場面を演じて遊ぶことを許されていた。その後、彼は姉とは別々に学校に通うことになり、私立のパブリックスクール制度で学んだ。チャールズ・エドワードは、まずサリーのサンドロイド・スクール、次いでハンプシャー州リンドハーストのパーク・ヒル・スクールという2つのプレパラトリー・スクールに通った。1896年のヴィクトリア女王の日記には、後者の学校の校長「ローンスリー氏」とその妻と面会したことに触れ、「彼らが言ったことはすべて非常に満足のいくものであった。彼は非常に慎重で親切であるようだ」とコメントしている。1898年には、彼はイートン・カレッジに入学し、母親は彼が最終的にオックスフォード大学に進学することを望んでいた。イートン・カレッジはイギリスのエリート層と密接な関係を持つ寄宿学校であった。報道では、彼が学校で尊大に振る舞っていると非難されることもあった。彼はイートン校での生活に満足しており、生涯を通じてその時期を懐かしんだ。アロンソンは、10代前半の王子を「小柄で青い目を持ち、飛び抜けてハンサムで、非常に神経質」と描写している。彼は特に著名な人物に成長するとは期待されていなかった。
3. ザクセン=コーブルク=ゴータ公位継承
チャールズ・エドワードがザクセン=コーブルク=ゴータ公位を継承するに至った経緯と、ドイツでの適応期間は、彼が故郷イギリスを離れ、新しい国と文化に適応しなければならないという大きな転換点であった。
3.1. 後継者選定の経緯

アルフレート公爵の唯一の息子であるアルフレート公世子が1899年に死去した。アルフレート公爵自身も健康状態が悪く、誰が後継者となるかは家族にとって大きな問題となった。ドイツの統治エリートの多くはアルフレート公を不適切な外国人だと見ており、多くのドイツ諸侯は公国を分割したいと考えていた。
当初、ヴィクトリア女王とアルバート公の三男であるアーサー王子が推定相続人であった。しかし、ドイツの報道の一部は外国人が王位に就くことに反対し、ヴィルヘルム2世もイギリス軍で勤務した者がドイツ国家の統治者となることに異議を唱えた。アーサー王子の息子であるアーサー王子は、チャールズ・エドワードと同じイートン校に通っていた。ヴィルヘルム2世はこの少年がドイツで教育を受けることを要求したが、コノート公爵はこれを受け入れなかった。そのため、チャールズ・エドワードの叔父と従兄弟は公国への請求権を放棄し、チャールズ・エドワードが次期公爵位継承者となった。彼は家族からの圧力によって後継者に指名された。当時のアメリカの報道では、若いアーサーがチャールズ・エドワードに肉体的に暴行を加えたり、もし彼がその地位を受け入れなければそうすると脅したりしたという報告があった。
チャールズ・エドワードは、自分に課せられた状況の変化に不満を抱いているようであった。歴史家のアラン・R・ラシュトンは彼が「忌々しいドイツの王子にならなければならない」と言ったと引用している。ラシュトンは、彼を取り巻く大人たちがチャールズ・エドワードに新しい役割を受け入れるよう促したようだと示唆している。彼の姉アリスは、母親が「私は常にチャーリーを善良なイギリス人として育てようと努力してきたが、今度は彼を善良なドイツ人にしなければならない」と述べたことを覚えているという。陸軍元帥フレデリック・ロバーツは彼に「善良なドイツ人になろうとしなさい!」と言った。しかし、ビュシェルとアロンソンの両名は、彼の母親のコメントを新しい状況に対する苛立ちの表明と解釈している。当時14歳であったチャールズ・エドワードの若さ、そしてドイツ人の母親とイギリス人の父親がいないという事実から、彼は年長の男性では不可能であった方法でドイツ社会に同化できると見なされた。コーブルクの地元紙はこの選択を称賛した。ドイツではチャールズ・エドワードの動向に大きな関心が寄せられた。ラシュトンによれば、一部のドイツ人は「今やイギリス人少年がドイツ人男性となり、養子となった地の指導者となることが重要である」と感じていた。王子はドイツへ行く前に堅信を受けた。ヴィクトリア女王は日記の中で次のようにコメントしている。
「ベアトリスは私に儀式の詳細をすべて話してくれた。可哀想なヘレーネとチャーリーは礼拝の間はよく耐えていたが、その後はひどく打ちひしがれていた。このように引き離されるのは、可哀想な子供にとって非常に辛いことであり、彼にとっては当然ながら大きな苦痛である。そして母親にとっては、幸せで静かな家を一時的に手放し、父親のいない少年を未知の世界に行かせなければならないという、本当に恐ろしいことである!」
3.2. ドイツでの教育と適応

チャールズ・エドワードは15歳の時、母親と姉と共にドイツに移住した。彼はドイツ語をほとんど話せなかった。アルフレート公はチャールズ・エドワードを母親から引き離したいと考えていたため、母親は息子を義兄であるヴュルテンベルク王ヴィルヘルム2世の元に滞在させ、家庭教師を見つけた。
その後、ヘレーネは息子の教育について検討した。優先されたのは、彼が適切なドイツ式の方法で育てられていることをドイツ人に安心させることであった。拡大された家族の様々なメンバーが提案を行った。アルフレートは後継者の責任を与えられることを望んだが、あまりにもイギリス的であると見なされた。アリスによれば、ヴィクトリア皇女が提案した学校にはユダヤ人の生徒が多すぎると感じられたという。最終的にヘレーネはヴィルヘルム皇帝に息子の教育の管理を委ねた。
ウルバッハによれば、ヴィルヘルム皇帝は若き従兄弟を「プロイセンの将校」にしたいと考えていたという。彼は一家をポツダムに住むよう招いた。ポツダムはドイツ皇帝の夏の離宮として使われるベルリン近郊の町である。チャールズ・エドワードはベルリンのリヒターフェルデにあるプロイセン中央陸軍士官学校(ドイツ語: Preußische Hauptkadettenanstaltドイツ語)に通った。ヴィルヘルム皇帝はヴィクトリア女王に電報で、彼が「8人の行儀の良い少年を選んで彼のクラスを編成した」と伝えた。王子はドイツ語と軍事学を学んだ。1900年の16歳の誕生日には騎兵少尉となり、ポツダムの1. Garderegiment zu Fußドイツ語(第1歩兵近衛連隊)に入隊した。1903年にはアビトゥーア(大学入学資格)を修了したが、彼の成績は公表されなかった。その後、チャールズ・エドワードはプロイセン政府省庁で政府運営を学んだ。彼はボン大学に通い、法学を学んだが、特に学術的な青年ではなく、主にボルシア学生組合に参加することを楽しんでいた。
ヴィルヘルム2世はチャールズ・エドワードのドイツ社会への同化に非常に強い関心を示し、そのため後者は皇帝の宮廷で「皇帝の七男」として知られるようになった。王子は母親や姉と共に、余暇の多くをベルリンのドイツ宮廷で過ごし、そこで皇帝一家の一員として扱われた。ヴィルヘルム皇帝には7人の子供がおり、その年長者はオールバニ姉弟とほぼ同じ年齢であった。アリスは後に、彼らが「もう一人の兄弟姉妹のようであった」と書いている。女性たちはアウグステ・ヴィクトリア皇后と仲良く過ごし、ヴィルヘルム皇帝はチャールズ・エドワードにとってある種の代替父親となった。ヴィルヘルム皇帝はチャールズ・エドワードを感化されやすい人物と見ていた。彼は王子に自身の世界観を伝え、それには反ユダヤ主義、ドイツナショナリズム、そして議会(ドイツ語: Reichstagドイツ語)への敵意が含まれていた。1908年の政治スキャンダルの間、この若い男性がヴィルヘルム皇帝と同性愛行為に関わったという疑惑が浮上した。チャールズ・エドワードはベルリンでの時間を楽しんでいないことが多く、皇帝は彼に憤慨しているように見え、頻繁にいじめを行った。1905年のベルリン宮廷のホフマルシャル(宮廷長官)の日記には次のように記されている。
「皇帝は彼[チャールズ・エドワード]と楽しむことを好む。しかし、たいていの場合、彼は彼をつねったり、からかったりして、可哀想な小さな公爵は実際に殴打されることになる。最近、彼の婚約者であるヴィクトリア公女とその両親も同席していた。このことは、可哀想な小さな公爵にとって特に恥ずかしいことであっただろう。彼はほとんど涙をこらえており、夕方中ずっと、まるで翌朝絞首刑にでもなるかのように不幸な表情をしていた。」

チャールズ・エドワードは16歳の時、1900年7月に叔父アルフレートが55歳で死去したことに伴い、ザクセン=コーブルク=ゴータ公爵位を継承した。彼は葬儀で涙を流したが、ウルバッハはこの反応を、彼が比較的関係の薄い叔父への悲しみというよりも、自身の将来への不安の表明だと解釈している。ヴィルヘルム皇帝は、チャールズ・エドワードが21歳の誕生日を迎えるまで、エルンスト・フォン・ホーエンローエ=ランゲンブルク侯子を摂政に任命した。1901年、彼はヴィクトリア女王の葬儀にプロイセンのフサールの制服を着用して参列した。彼の長兄にあたる叔父で、ヴィクトリア女王の後を継いで国王となったエドワード7世は、葬儀でチャールズ・エドワードを抱擁している姿が目撃された。新しい国王は1902年に甥をガーター勲章のナイトに叙した。1903年、チャールズ・エドワードの母親は、彼がもう一人でやっていける年齢になったと判断し、アリスと共にドイツを去った。1905年5月、エドワード7世は彼をイギリス陸軍連隊であるシーフォース・ハイランダーズの名誉連隊長に任命した。
チャールズ・エドワードは、英国国教会の礼拝に参加するなど、イギリスとのつながりを維持しながら、可能な限り同化しようと努めた。ウルバッハは彼がドイツ語を急速に習得し、「軍事アカデミーでのドイツ語の作文はすぐに英語の作文よりも高い評価を得るようになった」とコメントしている。しかし、この時期の王子による様々な発言は、彼がホームシックであり、自身の状況に不満を抱いていたことを示唆している。彼の『オックスフォード英国人名事典』(ODNB)の項目を執筆したシャーロット・ジープザットは、彼を「芸術と音楽の趣味を持つ勤勉な青年」と描写し、この時期にコーブルクで人気を博したと述べている。アロンソンも同様に、チャールズ・エドワードが「やかましいプロイセン軍国主義の雰囲気の中で成人した」にもかかわらず、「洗練され...音楽や演劇を好み、歴史や建築に興味を持っていた」とコメントしている。ウルバッハは若い公爵を「未熟」と評した。当時のニュース報道では、彼が「スポーツと冒険」を好んだと記されている。1905年のイギリスの外交問題に焦点を当てた新聞『ロンドン・アンド・チャイナ・エクスプレス』の記事には次のようにコメントされている。「すべての[ドイツ]新聞が若い公爵を称賛し、彼の同情的な性格と態度を描写している。とりわけ、彼がいかにドイツ人になったか、いかに初期のイギリスでの訓練を完全に忘れ、ドイツの利益とあらゆる面で一体化したかを強調するのに飽きることがない。」
4. ザクセン=コーブルク=ゴータ公としての統治
ザクセン=コーブルク=ゴータ公としてのカール・エドゥアルトの在位期間は、彼の家族生活、公爵としての統治スタイル、そして第一次世界大戦という激動の時代における彼の忠誠心の試練によって特徴づけられる。
4.1. 結婚と子供たち

ウルバッハによれば、チャールズ・エドワードは女性に対する「曖昧な」態度を持っていたと見なされたため、家族は若い年齢で政略結婚させることを決定した。ヴィルヘルム2世は、自身の妻の姪であるシュレースヴィヒ=ホルシュタイン=ゾンダーブルク=グリュックスブルク公女ヴィクトリア・アデライデをチャールズ・エドワードの妻として選んだ。彼女は順応性があり、ヴィルヘルム皇帝のホーエンツォレルン家に忠実であると信じられていた。彼女の国籍は重要視され、ヴィクトリア・アデライデには非ドイツ系またはユダヤ系の祖先がいないとされた。若い男性はプロポーズするように言われ、彼はそれに従った。若い二人の間にはある程度の愛情が存在したと見られている。
二人は1905年10月11日にシュレースヴィヒ=ホルシュタインのグリュックスブルク城で結婚し、5人の子供をもうけた。彼らの子供は以下の通りである。
- ヨハン・レオポルド王子(1906年 - 1972年)
- シビラ公女(1908年 - 1972年)
- フーベルトゥス王子(1909年 - 1943年)
- カロリーネ・マティルデ公女(1912年 - 1983年)
- フリードリヒ・ヨシアス王子(1918年 - 1998年)
当時の上流階級の家庭に期待されたように、子供たちの世話は大部分が使用人に委ねられていた。家族は主に家庭で英語を話したが、子供たちはドイツ語を流暢に話せるようになった。フーベルトゥスは公爵のお気に入りの子供であった。1914年にイギリスの新聞『ザ・スフィア』に掲載された家族の特集記事では、子供たちについて次のようにコメントされている。「コーブルク家の子どもたちは、明るく幸せな子供たちで、城の素晴らしい敷地で多くの時間を屋外で過ごすなど、自然な生活を送っている。彼らは乗馬がとても好きである。冬はザクセン=コーブルク=ゴータでは厳しいが、スキーや雪の天候に適した他の屋外での娯楽を楽しんでいる。」
ウルバッハは晩年の家族について考察している。彼女はチャールズ・エドワードの子供たちが父親を恐れ、彼が子供たちを「軍隊の部隊のように」扱ったとコメントしている。彼女は、家族が写真でしばしば不幸そうに見えることを指摘した。彼の末娘、カロリーネ・マティルデ公女は、父親が自分を性的虐待したと主張し、この疑惑は彼女の兄弟の一人によって裏付けられた。チャールズ・エドワードは、王家の失墜した名声を戦略的な結婚によって改善しようと試みていた時期に、子供たちの恋愛関係の選択にしばしば失望した。
4.2. 統治と関心事

チャールズ・エドワードは1905年7月19日、21歳の誕生日を迎えて成人し、完全な憲法上の権力を掌握した。就任式ではドイツ帝国への忠誠を誓う演説を読み上げ、地元の食事を公衆の前で試食すると観衆から喝采を浴びた。彼は自身の新しい領地を美しいと感じ、満足していた。彼は自身の忠誠心を強調するために様々な愛国団体に参加した。しかし、ウルバッハによれば、公爵は人気を欠いていた。特にゴータでは、貧しい町で左翼的な傾向があり、彼を絶対主義者と見なしていた。一方、豊かで保守的、そして強烈なナショナリズムで知られるコーブルクの人々は、チャールズ・エドワードに対して概ね同情的であったが、彼に感じる異国的な感覚を嫌っていた。彼はイギリス訛りを持ち続け、スコティッシュ・テリア犬を飼っていたことや、常に警察の護衛を伴って公の場に現れたことでも批判された。
歴史家のフリードリヒ・ファキウスは、チャールズ・エドワードを当初はリベラルであったが、後に権威主義的な方向に変化したと描写している。彼は皇帝を支持し、政府機関を理解していた。新しい公爵は、保守的な傾向を持つプロイセン政府官僚であるエルンスト・フォン・リヒターを首相に任命した。ラシュトンによれば、公爵の政治的世界観はヴィルヘルム2世によって教え込まれたものを反映しており、「保守的でナショナリスト的」であった。彼は統治のほとんどを任命した内閣に任せた。彼らはその方針を「すべてはこれまで通り」というモットーで表現した。
チャールズ・エドワードは頻繁に地元のイベントを訪れた。彼は地元の市民生活において著名な人物であり、多くの文化団体や慈善団体の議長を務め、後援を行った。公爵は新しい交通手段、特に自動車と飛行船に興味を持っていた。彼はゴータに新しい飛行船ドックの建設に投資し、これは商業的に賢明な決定に見えた。1913年、彼はドイツ皇帝にゴータの民間飛行学校を秘密裏に軍事学校に転換するよう要請し、ヴィルヘルム皇帝はこれに同意した。彼は両町の宮廷劇場を熱心に支援し、1908年から1924年にかけて行われたコーブルク城の修復を組織した。1910年には、君主制支持の政治組織であるReichsverband gegen die Sozialdemokratieドイツ語(社会民主主義反対帝国連盟)に参加した。チャールズ・エドワードは人々が自分をどう見ているかについて不安を抱いており、彼の官僚は世論調査を行っていた。公爵は、クリスマスのお祭りや伝統衣装などの文化的習慣を披露することで、ドイツへの忠誠心を頻繁に強調しようと努めた。
チャールズ・エドワードはイギリス王室と良好な関係を維持し、定期的にイギリスを訪れていた。1910年、イギリスの『デイリー・ミラー』紙は、彼がシーフォース・ハイランダーズの退役軍人の視察でその制服を着ている写真を掲載した。彼はドイツにいる間も個人的にイギリスの活動に頻繁に参加した。公爵夫妻はスコティッシュ・カントリー・ダンスをバグパイプに合わせて踊った。彼の直系家族は英語の愛称を使っていた。チャールズ・エドワードはアリスと義理の弟であるアレクサンダー・オブ・テック王子からの定期的な訪問を受けていた。彼は1910年代初頭にエドワード王太子(当時のプリンス・オブ・ウェールズ)と親密な絆を育んだ。公爵は一般的に政治、特にイギリスとドイツ間の外交問題には関わろうとしなかった。ビュシェルは、この時期のチャールズ・エドワードのドイツ人としての振る舞いは、自身のアイデンティティの表現というよりも、ヴィルヘルム2世やドイツのナショナリストたちを喜ばせるための努力であった可能性が高いと推測している。

ドイツの政治エリートたちは、公爵がイギリスと密接な関係を続けていることにしばしば苛立ちを覚えていた。特に激しい批判はフランケン地方の下級貴族から寄せられた。彼らはしばしば自身をドイツ貴族の中で最も純粋なドイツ人だと見なしていたからである。例えば、コンスタンティン・フォン・ゲブザッテル男爵は、ドイツの称号を持つ「外国人」は、ユダヤ主義、「SPD」(ドイツの左翼政党)、そして「自由」という「癌」との必要な戦いを妨げるため、「厄介な存在」だと主張した。帝政ドイツ政府はそれほど過激ではなかったが、チャールズ・エドワードのいくつかの行動には不満を抱いていた。1910年のエドワード7世の葬儀で、彼の儀礼的なイギリス連隊の制服を着用したことは特に不快感を与えた。在ロンドンドイツ大使館の職員は、彼が頻繁にイギリスを訪問することに不審を抱いていた。
公爵はまた、主要な地元の土地所有者となり、年間約250.00 万 DEMの収入があった。1918年までに彼の資産は推定5000.00 万 DEMから6000.00 万 DEMに達した。彼は毎年数ヶ月間コーブルクとゴータの両方で生活し、山小屋や狩猟小屋も訪れた。通常、午前中は仕事をし、午後はハイキングなどの余暇活動に費やした。余暇が彼の時間の大部分を占め、彼は頻繁に海外やドイツの他の地域に滞在した。チャールズ・エドワードは人との交流、特に自分とは異なる人々との交流に苦労した。彼は地元の住民が彼の城の周囲の田園地帯に入ることを禁じ、彼の孤立を深めた。彼は宮廷人たちに囲まれて多くの時間を過ごし、彼らは常に彼を称賛した。歴史家のジュリエット・ニコルソンは、これらの年を「完璧な夏」と表現している。これは、特権階級の人々が、政治や労働運動に現れ始めていた彼らの生活様式への脅威を否定しながら、富と社会的優位性を享受していた時期である。ラシュトンは、この時期の公爵の個人的な状況について次のようにコメントしている。
「チャールズ・エドワードは、健康な家族の成長、最小限の公務、非常に豊かな生活を送り、ヨーロッパ社会の上層部で友人や親戚と交流する機会など、彼の人生に満足するあらゆる理由があった...1914年が始まる頃、チャールズ・エドワードはヨーロッパ貴族の黄金時代が最高潮に達しつつあることを全く知らなかった。彼は狩猟や旅行を続け、絶対君主として行動していた...彼の君主としての生活は、彼の臣民の大多数とはほとんど共通点のない並行世界に存在しているようであった。」
4.3. 第一次世界大戦と英国との関係

第一次世界大戦はチャールズ・エドワードに忠誠心の葛藤を引き起こしたが、彼はドイツ帝国を支持することを選択した。彼はフランツ・フェルディナント大公暗殺事件の際、オックスフォード大学で名誉博士号(民法)を授与されるため、イギリスに滞在していた。彼は姉に、イギリスのために戦いたいが、公国に戻る義務を感じていると語った。公国では、彼のイギリス出身であることから世論が彼に敵対し始めた。彼は7月9日にドイツに戻った。戦後、彼は1914年の出来事を姉への手紙で彼の個人的な「幸福」の終わりとして描写した。
開戦当初、ドイツの報道はドイツ貴族の外国とのつながりを批判し、チャールズ・エドワードは特に激しく攻撃され、「半イギリス人」と非難された。公爵は公にイギリスを非難し、ドイツを攻撃していると非難して、シーフォース・ハイランダーズの名誉連隊長の地位を放棄した。彼はイギリスの軍事勲章を返還せず売却したが、ビュシェルはこれを家族に対する侮辱のジェスチャーであり、見せかけのものであった可能性が高いと指摘している。彼はイギリスおよびベルギーの宮廷にいる家族との関係を断ち切ったが、これはドイツにおける彼の忠誠心に対する疑念を払拭するには不十分であった。彼の態度は戦争が進むにつれてより真摯に親ドイツ的になっていった。
チャールズ・エドワードはそりの事故で脚に永久的な損傷を負っていたため、戦闘に参加することはできなかった。彼は自領の軍団に対し非戦闘支援を提供し、彼らと共に戦闘が行われている地域へ赴いた。彼は当初、1914年のドイツによるベルギー侵攻に参加した。ここで公爵は、数百人のベルギー市民が殺害されたドイツ兵によるディナン略奪を目撃した。彼の副官であるマルセル・フォン・シャック(ベルギー市民は適切に扱われたと感じていた)は、この出来事が公爵に「忘れられない印象」を与えたと書いている。彼は1914年9月上旬に東部戦線に転属となった。彼は東部戦線で出会った地元の人々の生活様式を嫌い、特にユダヤ人の家は汚いと考えていた。チャールズ・エドワードは1914年末に「勇敢さ」に対して鉄十字勲章を授与された。戦争中盤には、チャールズ・エドワードは西部戦線とバルカン半島の紛争地域を何度か訪れた。
公爵が指揮を執ることはなかった。彼の公国出身の兵士たちには、Carl-Eduard-Kriegskreuzドイツ語(カール・エドゥアルト戦争十字章)が授与された。公爵の副官は彼の活動について日記を書き、これはドイツ軍司令部に報告され、プロパガンダ目的でドイツの報道機関に配布された。これらの報告は、彼が兵士たちの困難な生活条件を共有し、彼らとクリスマスを過ごしたと描いている。しかし実際には、彼はリウマチと強直性脊椎炎という一種の関節炎を患い、体調がすぐれなかった。彼は通常、前線からかなり離れた場所に滞在し、定期的にドイツに戻って治療を受けていた。これは、若い兵士は病気を抑えることができるべきだと考える一部のドイツのエリート層の間で不満の原因となった。ウルバッハによれば、チャールズ・エドワードは「カジノで食事をしたり、『彼の』コーブルク部隊を訪問したりしてほとんどの時間を過ごす、多かれ少なかれお飾りの兵士であった」。
公爵はドイツ政府と、中央同盟国の一員であったブルガリア王国の支配者、親戚であるフェルディナント1世との仲介役を務めた。フェルディナントは1908年にオスマン帝国からのブルガリア独立を宣言し、第二次バルカン戦争後、ブルガリア王国は経済危機に陥っていた。チャールズ・エドワードは、財政支援を含め、それらの出来事を通じてフェルディナントに多大な援助を提供していた。1916年、フェルディナントはオスマン帝国との戦争を望んでいたが、ドイツはオスマン帝国と同盟関係にあったためこれを望まなかった。チャールズ・エドワードはヴィルヘルム皇帝のためにブルガリアの首都ソフィアへ赴き、フェルディナントを説得して戦争を断念させた。
チャールズ・エドワードはイギリスで裏切者として非難された。彼はイギリスの爵位を持ちながら中央同盟国側についたドイツやオーストリアに住む貴族の一員であり、イギリスの報道では頻繁に「裏切りの貴族」として報道された。例えば、戦争終結直後、『サンデー・ポスト』紙は「我々の裏切りの公爵たち」に関する記事を掲載した。その中には、チャールズ・エドワードの人生に関する否定的で個人的な悪意に満ちた描写が含まれており、彼の戦争における役割を「彼の不名誉な経歴の中で最も暗い章の一つ」と呼んだ。ビュシェルは、公爵が依然としてイギリス臣民であり、イギリスと戦っていたことから、彼を裏切者と記述するのは正確であると指摘した。彼は正式にはドイツ国民にはなっていなかった。
1915年、ジョージ5世国王は、彼の名前をガーター勲章の登録簿から削除するよう命じた。1917年、コーブルクで法律が改正され、チャールズ・エドワードのイギリス人親族が公国を継承することが事実上禁止された。この決定はドイツの新聞に称賛され、ある新聞は彼が故国との関係を「引き裂いた」と宣言した。1917年夏、ゴータで製造され、この町にちなんで名付けられた爆撃機が、ロンドンやイギリス南東部で複数の空襲を行い、数百人のイギリス人市民が殺害された。同年、チャールズ・エドワードの数百万ポンド相当のイギリスの財産が没収された。チャールズ・エドワードは、イギリス人親族が彼の他の財産を継承することを阻止する法律改正を導入することで対応した。イギリス王室は後に、ドイツ風のザクセン=コーブルク=ゴータ家からウィンザー家に名称を変更した。1917年称号剥奪法は、彼のイギリスの爵位を剥奪するプロセスを開始した。ウルバッハは、チャールズ・エドワードが、メアリー王妃の保護下でロンドンに住んでいた彼の母親が報復の危険にさらされるかもしれないことを気にかけていなかったようだと述べている。

チャールズ・エドワードは、戦争の末期には西部戦線の軍事参謀本部で勤務した。彼は自身の個人資産から25.00 万 DEMを、彼の領地出身の戦死した兵士の家族への財政支援として拠出した。戦後数年後に『タイムズ』紙に掲載された報告書は、彼がしばしばイギリスの捕虜を援助したことに言及し、これを彼の「配慮と人道主義」の表れであると記述している。公爵は1918年のロシア皇室殺害事件に動揺した。アレクサンドラ皇后は彼のはとこであった。彼は自分の家族にも同じことが起こるのではないかと心配した。ラシュトンは、これが彼の今後の政治活動を決定づける共産主義への恐怖の始まりであったと書いている。彼はドイツ皇帝の支持者の組織であるPreußenbundドイツ語(プロイセン連盟)に参加したが、指導者としてはドイツの将軍で事実上の軍事独裁者であったパウル・フォン・ヒンデンブルクを好んだ。ビュシェルは、チャールズ・エドワードの第一次世界大戦の経験が「ナショナリズム、暴力、反ユダヤ主義の学校」であったと主張した。
戦争はドイツ国民に厳しい負担を課し、1918年半ば以降、帝国の軍事状況は崩壊した。同年末には休戦協定が締結され、ドイツで革命が勃発した。1918年11月11日、コーブルクで公爵に対する平和的なデモが行われた。公国の首相ヘルマン・クヴァルクは、比較的裕福なメンバーを多く含む地元のSPDに対し、さらなる暴動は町の景観にとって危険であると説得した。人々が飢えていたゴータの政治情勢はより過激であり、労働者・兵士評議会が事実上支配権を掌握した。チャールズ・エドワードは、他の多くの統治者よりも状況への対応が遅れた。彼は11月14日に「統治を停止した」と発表したが、明確に退位はしなかった。ラシュトンによれば、チャールズ・エドワードの退位が遅かったのは、殺されるのではないかという不安のためであったという。しかし、コーブルクにおける権力移行は、ドイツの他の地域と比べて非常に穏やかで秩序だったものであった。ドイツ貴族は革命中に物理的な攻撃を受けることはなかったが、この状況は彼らにとって深く恐ろしいものであり、多くの恨みの原因となった。
5. 戦後およびヴァイマル共和国時代
第一次世界大戦後、チャールズ・エドワードは激動のヴァイマル共和国時代を生き抜き、イギリスにおける地位と財産を失いながらも、ドイツでの極右政治活動に傾倒していった。
5.1. 英国の爵位と財産の喪失
ウルバッハは、チャールズ・エドワードが人気がなく、一部の人々からは依然としてイギリス人と見なされていたと記している。戦争終結までに、左翼的で反王制的な報道機関は、彼の外国出身であることに言及し、彼を「オールバニ氏」とあだ名していた。しかし、彼は比較的満足してコーブルクに住み続けることができた。ラシュトンによれば、彼はその威信の多くを保持しており、元臣民からは基本的にまだ公爵と見なされていた。コーブルクは政治的に保守的な町であり、新しい戦後の世界は多くの人々にとって恐ろしいものであった。住民はチャールズ・エドワードに指導を求め続けた。
戦後まもなく、コーブルクはドイツのバイエルン州の一部となり、ゴータはテューリンゲン州の一部となった。バイエルンはコーブルクがうまく適合する保守的な政治文化を持っていたが、文化的にはこの移転は大きな変化を意味した。これにより、元公爵とその家族が依然としてコミュニティの自然な指導者であるという感覚が高まった。
1919年には、彼はイギリスの爵位も失った。しかし、ティーンエイジャーの頃にドイツへ行くことを強制されたという経緯から、イギリスの政治層の間では彼に対する個人的な同情が残っていた。彼は残りの生涯にわたり、イギリス王室に関連する図像や称号の一部を使い続けた。1921年には母親と姉をロンドンに訪れたが、一般的にはイギリスでは望まれていなかった。チャールズ・エドワードの母親が1922年に死去すると、当時のイギリス政府は彼がクレアモント・ハウスを相続することを阻止し、これは彼をひどく落胆させた。
1919年、コーブルクにあった彼の財産とコレクションは、現在も存在するCoburger Landesstiftungドイツ語(コーブルク州財団)に移管された。ゴータについても同様の解決策が取られるまでには時間がかかり、テューリンゲン自由州との法廷闘争の末、1928年から1934年にかけて設立された。1919年以降も、家族はカレンベルク城やその他の財産(オーストリアのものを含む)、そしてコーブルク城に住む権利を保持した。また、失われた所有物に対して多額の財政的補償も受け取った。コーブルク城の改修は国費で完了した。1925年には、テューリンゲン州の一部の追加不動産が公爵家に戻された。
戦後の民主的なドイツ国家は彼の財産にほとんど脅威を与えなかったが、チャールズ・エドワードは共産主義革命について偏執的な不安を抱き続けた。彼は1928年に姉への手紙で次のように書いている。「冬は静かなままであってほしいが、ロシアが共産主義者を動かしているようだ...ドイツの各地で彼らはナショナリストを攻撃し始めたが、幸いにも痛手を負って撃退された。指導者たちが労働者たちを放っておいてくれさえすれば良いのに。彼らは非常に賢明なのだ、『wenn sie nicht verhetzt werdenドイツ語』(煽られなければ)。」
5.2. 極右政治活動とナチ党支援
チャールズ・エドワードは、第一次世界大戦後の期間も自らを君主主義者と称し続けた。彼は「テューリンゲン王」として政治権力に復帰することを望んでいたと言われる。しかし実際には、彼の王政復古への熱意はかなり冷淡であった。ドイツ皇帝に対する彼の感情的な愛着は、ヴィルヘルム皇帝の亡命とともに大部分が終わりを告げた。元公爵は、廃位されたドイツ皇帝に代わるより強力な政治的選択肢を探し始めた。
廃位後、チャールズ・エドワードは政治に公然と関与するようになり、ナショナリスト的で保守的な右翼を支持した。元公爵は戦前のドイツ、特にその軍国主義に懐かしさを感じ、共産主義を恐れていた。ウルバッハはまた、彼が自身の身体的な弱さから生じる男性的な身体的強さへの執着を持っていたことも示唆している。元公爵は様々な右翼系の準軍事組織や政治組織と関係を持つようになった。
彼は準軍事組織であるCoburg Einwohnerwehrドイツ語、Bund Wikingドイツ語、そして退役軍人団体であるDer Stahlhelmドイツ語のメンバーおよび後援者となった。Bund Wikingドイツ語は以前、1920年代初頭のコンスル機関であり、彼もまたその組織に資金提供し参加していた。この組織は、政治的動機による政治家カール・ガライスやヴァルター・ラーテナウの殺害に関与していた。ウルバッハは「カール・エドゥアルト自身は殺人を行わなかったが、彼は殺人者たちに資金提供した」とコメントしている。当時の警察の報告書には、彼とヴィクトリア・アデライデが極右テロリズムを支持する演説が行われる酒場に出席したことが記されている。
チャールズ・エドワードはまた、様々な反ユダヤ主義の国家主義団体に資金提供した。1922年、彼は地元のギムナジウムを卒業する優秀な生徒がスピーチをする伝統的なイベントに招待された。その年の生徒はハンス・モーゲンソーというユダヤ人の若者であった。元公爵は、モーゲンソーがスピーチをしている間ずっと背を向け、鼻をつまむことで不満を表明した。1922年10月14日、ナチ党はコーブルクで「Deutscher Tagドイツ語」(ドイツの日)と呼ばれる国家主義的なイベントに参加し、かなりの暴力行為を伴った。その夜、チャールズ・エドワードは党が開催した食事会に出席し、そこでヒトラーが演説した。翌日、彼はヒトラーと握手を交わし、公然と彼を支持した最初の貴族となった。警察は、元公爵が長男レオポルドを反ユダヤ主義の準軍事組織である若きドイツ騎士団に参加させたかどうかを調査した。1923年秋、レオポルドがコーブルク周辺でユダヤ人に対する一連の攻撃を主導したと報道された。特に、アウテンハウゼン村でユダヤ人農民が重傷を負ったいくつかの事件が注目された。元公爵が息子を起訴から守るために証人を買収したとされている。
1920年、彼はカップ一揆失敗後、政府に対するフライコール司令官で後にコンスル機関の指導者となったヘルマン・エアハルトを、武器の備蓄と共に自身の城の一つに匿った。ビュシェルは、ヴィルヘルム皇帝とその跡継ぎであるヴィルヘルム皇太子に不満を持っていたエアハルトが、チャールズ・エドワードをドイツ全土の君主にしようと望んでいた可能性があると示唆している。1923年、ドイツマルクの価値が暴落した。政治の急進左派と右派はともにこれを政府体制を変える機会と見なした。共産主義者はテューリンゲン州とザクセン州で革命を開始しようとした。エアハルトと彼の5000人の支持者(チャールズ・エドワードの長男を含む)は、テューリンゲン州に進軍する準備を進めることで対応した。連邦ドイツ政府はその後、これらの地域の左翼州政府を排除し、世論の観点からその権限を再確立した。チャールズ・エドワードは、ナチ党による失敗に終わったミュンヘン一揆に苛立ちを覚えた。これはヒトラーがエアハルトに対するクーデターを開始する前に、バイエルンの指導者グスタフ・フォン・カールがエアハルトと共に連邦政府に対するクーデターを計画していたためである。しかし、元公爵はその後、ナチ党員を自身の城の一つに匿った。
1929年以降、チャールズ・エドワードはナチ党に財政的支援を提供した。1932年、カレンベルク城は改修され、塔にはハーケンクロイツが追加された。元公爵は党の軍国主義と反共主義に魅力を感じていた。ヒトラーも王室財産の収用には反対を表明していた。チャールズ・エドワードは、ナチスが権力を握る前の時期において、フランケン地方やドイツ全土に広範なつながりを持つ有用な協力者であった。
1929年、彼の支援により、コーブルクはドイツで初めてナチ党評議会を選出する町となった。この選挙は、ユダヤ人を攻撃したナチス支持者が職場を解雇されたことに関する紛争が原因で発生した。チャールズ・エドワードのナチ党のイベントへの訪問は地元紙で報じられ、党の知名度と威信を高めた。
1929年のナチ党の地方選挙後、政治的動機に基づく反対派への暴力が一般的となり、地元警察によって容認された。コーブルクのユダヤ人人口も、身体的虐待や差別の増加を経験した。ラシュトンは、元公爵が公に表明した信念と財政的支援が、コーブルクとドイツ全体におけるユダヤ人に対する憎悪の増大に貢献したと書いている。チャールズ・エドワード夫妻が反ユダヤ主義者であることは広く知られていた。ラシュトンによれば、チャールズ・エドワードは自身が関与した運動の暴力的な行動を認識していたはずだが、決して異議を唱えなかった。第一次世界大戦は、彼に政治的暴力の利点を確信させた。
1931年、彼はヴァルデマール・パブストと共に「ファシズム研究協会」を設立した。この組織は、イタリアのファシズムを例としてドイツを統治する計画を策定することを目的としていた。ムッソリーニの独裁は、チャールズ・エドワードや彼のような他の人々を興味を惹きつけた。彼らには、ファシズムは伝統的な貴族と新しいエリートを融合させることができる国家運営の方法であるように思われた。元公爵は1932年にNational Klubドイツ語(国民クラブ)のリーダーに選出された。これは、戦後の政府体制を嫌うビジネスマンが主にメンバーで構成される社交クラブであった。彼は彼らにナチ党に入党するよう促し、年末までに70%がそうした。また1932年には、ハルツブルク戦線の創設に参加し、これによりドイツ国家人民党や同様の見解を持つ他のグループがナチ党と連携するようになった。彼はまた、1932年の大統領選挙でヒトラーを支持するよう有権者に公に呼びかけた。ナチ党はドイツ全土ではその選挙で敗北したが、コーブルクでは勝利した。

1932年、チャールズ・エドワードの娘シビラは、スウェーデン王位継承順位第2位であるヴェステルボッテン公グスタフ・アドルフ王子と結婚した。この結婚は、シビラがスウェーデン王妃となることが期待されることを意味した(しかし、それは実現しなかった)。チャールズ・エドワードはこの出来事を、自身のイデオロギーを公に示す場として、また公爵家の傷ついた威信を向上させるために利用した。第一次世界大戦から10年以上が経ち、彼らが再び国際的な王室圏で重要な存在として現れる機会であった。コーブルクはスウェーデン国旗とナチ党旗で飾られた。5000人のナチス制服を着た男たちがコーブルク城の外を行進した。アドルフ・ヒトラーとヘルマン・ゲーリングは結婚を祝福した。
ジョージ5世はチャールズ・エドワードの政治的見解への反対から、プリンス・オブ・ウェールズであったエドワードが結婚式に出席することを禁じたが、チャールズ・エドワードのイギリス人親戚の一部は出席した。スウェーデンでは、政治的に不安定な状況で共和主義運動が高まっていたこともあり、この結婚式は使用された象徴性やグスタフがナチスに同情的であると知られていたことから、かなりの論争を巻き起こした。スウェーデン政府はイベントのプログラムにいくつかの変更が加えられることを約束されたが、これは実行されなかった。この結婚式はドイツ内外の報道で大きく取り上げられた。
6. ナチ体制下での活動
カール・エドゥアルトはナチ党入党後、ナチ体制内で多くの重要な役割を担った。彼は高位の役職に就き、ドイツ赤十字社をナチスの目的のために利用し、特に優生学思想とその実践に深く関与した。また、非公式な外交官として、ナチス体制の国際的宣伝と外交的支援に貢献した。
6.1. ナチ党への入党と主要な役職

1933年、ナチ党が権力を掌握した。チャールズ・エドワードはコーブルク城にナチ党旗を掲げ始めた。彼は1933年3月に正式にナチ党に入党し、同時に突撃隊(SA)の上級集団指導者となった。一方、コーブルクの中心部には、ユダヤ人や体制の反対者を拷問する臨時の刑務所が設置されたが、これは秘密にされることはなかった。
元公爵はすぐに様々な儀礼的な称号を与えられ、複数の企業の役員会にも参加した。新しい体制の要人たちの写真集では、彼が43番目に掲載された。チャールズ・エドワードは1934年に「永遠にヒトラーに盲目的に従う」と公言した。
ウルバッハによれば、元公爵は党の「非常に名誉ある」メンバーとなり、幹部たちとの写真に写り、関係を築くためのベルリンの事務所を設置した。彼女は、彼がナチ党員であることに誇りを感じており、SAの制服を着ることで戦前の自分に戻ったように感じたと記している。長いナイフの夜の後、彼はSAの制服を使用する権利を失い、これは彼をひどく落胆させたが、政治的動機による殺害を受け入れた。彼は後に国防軍の将軍の制服を与えられた。
ナチ党内の一部の人物は、元公爵に対して疑念を抱いており、彼が野心に駆られているか、君主制を復活させようとしているのではないかと疑っていた。彼は1936年に体制によって阻止されるまで、多くのナチス支持者に自身の個人的な勲章を授与した。
チャールズ・エドワードは国家社会主義自動車協会の総裁に就任したが、この組織はホロコーストの実行に使用された車両を含む、ドイツ国家に車両を提供するものであった。1936年から1945年まで、彼はナチ党を代表してライヒスタークの議員を務めた。彼が1932年から1940年までつけていたアポイントメント日記には、しばしば党への熱烈な支持が表明されていた。例えば、彼は1936年の一党制選挙の結果を詳細に記録し、その結果を称賛した。ビュシェルは、この段階で元公爵は自分自身を完全にドイツ人であると見なしているようであったとコメントしている。
ビュシェルは、この時期のチャールズ・エドワードのライフスタイルについて次のように記述している。「カール・エドゥアルトがヒトラー政権にとって重要であったことは、彼の地位にふさわしい豪華なアパート、そして大量の車両、勤勉な副官、行政官、使用人、豊富な外貨といった設備からも明らかであった...カール・エドゥアルトは、ヴァイマル共和国時代よりもナチス体制下で、コーブルク城や彼の他の多くの城で、より穏やかに暮らしていた。第一次世界大戦終結後に国家当局によって没収されたテューリンゲン州やオーストリアの財産に関する紛争は、高位の国家社会主義党員の介入によって、遅滞なく公爵家に有利に解決された。」
6.2. ドイツ赤十字社総裁としての役割
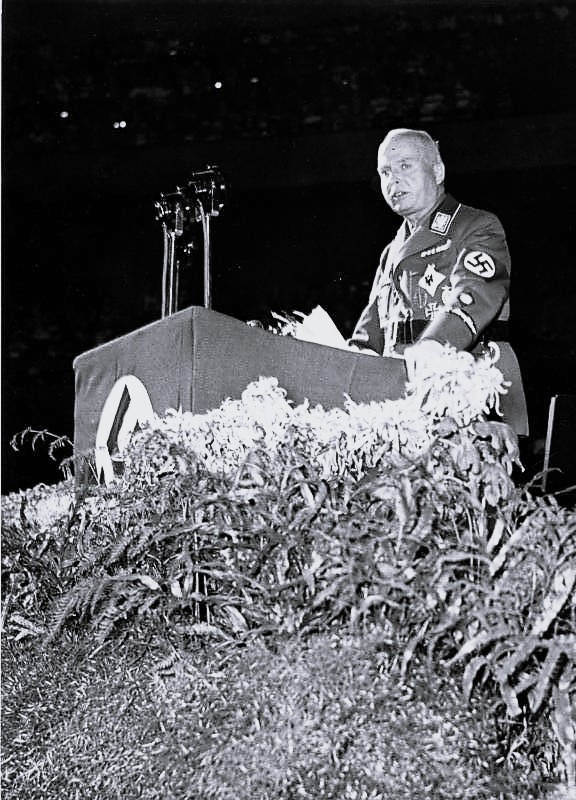
1933年12月1日、チャールズ・エドワードはDeutsches Rotes Kreuzドイツ語(ドイツ赤十字社)の総裁に任命された。ヒトラーはこの任命を承認した。彼は元公爵をよく知っており、チャールズ・エドワードがナチスの人種および優生学に関する思想を支持していると信じていたからである。元公爵の任命は、貴族が人道主義活動に参加するという歴史的な伝統も反映していた。
ヨーロッパの王室とのつながりがあったため、彼は海外で組織の有用な名目上の代表者と見なされた。彼はドイツ赤十字社の副総裁であるパウル・ホッハイゼン博士と権力を分かち合うことが期待された。チャールズ・エドワードの総裁就任初期の数ヶ月間、総裁が組織内での権限を主張しようとしたため、両者の間で権力闘争が起こった。1934年夏、党はドイツ赤十字社の統制をほぼホッハイゼンに移管した。
この組織は、政府の目標に沿うよう迅速に統制された。ラシュトンは「新体制の設立から2年後、ドイツ赤十字社は、紛争時に兵士を支援することを目的とした準軍事組織に再編された」とコメントしている。
ドイツの政治犯(ナチスが政権を握った後に投獄された反対派)の処遇は、体制初期の数年間で国際的な議論の的となった。1934年にスウェーデン赤十字社がこの件について調査を要求した後、国際赤十字が調査を開始した。ドイツ赤十字社は、囚人の状況は彼らの通常の生活水準よりも良いと主張した。チャールズ・エドワードは、彼の友人である国際赤十字総裁カール・ヤーコプ・ブルクハルトが、1935年にダッハウ強制収容所を含む強制収容所への厳しく管理された視察を行う手助けをした。ブルクハルトは個人的には収容所を「残忍」だと感じていたが、彼の報告書は厳しく検閲され、状況は適切であると述べられていた。ブルクハルトは元公爵に視察を組織してくれたことに感謝の手紙を送った。
1937年、エルンスト=ロベルト・グラヴィッツが副総裁に任命され、組織とSSとの連携が強化された。チャールズ・エドワードは「総統官邸の将校」に任命され、政府業務に関する秘密情報へのアクセス権を得た。ドイツ赤十字社の高位の役職はますますナチ党員で占められるようになり、組織のメンバーは「ユダヤ人、スラヴ人、慢性疾患患者、障害者...は価値のない存在にすぎない」と教え込まれた。
チャールズ・エドワードは、体制初期の数年間、ドイツ国内での公的な場での露出が次第に減少し、1937年にグラヴィッツが任命されてからは、国内での公的な活動をほとんど完全に停止した。体制はますます過激化しており、元公爵を過去の象徴と見なすようになっていた。
6.3. 優生学およびナチズム思想への関与
優生学とは、人間集団は一部の人々が子供を産むことを奨励し、他の人々を discouraged することによって、何世代にもわたって「改善」できるという疑似的な理論である。この概念は19世紀に生まれ、ナチスが権力を握る前の数十年間に、ドイツの学術界で人気が高まっていった。20世紀初頭には、貧しい家庭に生まれた子供たちは、裕福な家庭の子供たちに比べて、健康状態が悪く、破壊的と見なされる行動を発展させる可能性が高かった。したがって、社会階級間の違いが遺伝的であるという考えは、一部の人々にとって暗黙の理にかなっていた。第一次世界大戦中には、多数の健全な男性が殺害されたり、身体障害者になったりした一方で、戦闘不能な男性が本国に残されたため、ドイツ国民の遺伝的健康に対する不安が高まった。
その後数年間で優生学に関する科学研究が増加し、ヒトラーは1920年代にこの思想を支持した。世界恐慌は、障害者が公共資源の重荷であるという懸念を強め、科学者や非ナチス政治家は、これらのグループに対する自発的な不妊手術の考えをますます議論するようになった。ナチ党は1930年代初頭に優生学への強い支持を表明した。20世紀初頭、優生学の思想は政治的スペクトルを超えて広く国際的な支持を受け、いくつかの国では「欠陥者」の強制的な不妊手術などの優生学的政策が導入された。この理論は、ナチスが大量殺戮を正当化するために使用したため、第二次世界大戦後には主流の支持を失った。
チャールズ・エドワードは1933年から1945年までカイザー・ヴィルヘルム協会の理事を務めた。1934年から1937年まではその執行委員会の幹事を務めた。これらの役職において、彼はドイツ国民、特にドイツ社会の権力を持つ個人に優生学の思想を推進することに関与していた。
遺伝病子孫防止法は、ドイツ国民にとって望ましくない負担と見なされた特定のグループの人々に対する強制不妊手術を導入した。ドイツ政府は、政権の後半期に障害者を殺害するための複数の計画を組織した。最初の計画は子供を対象とし、1939年から戦争終結まで実施され、5,300人の障害を持つ子供を殺害した。第二の計画であるT4作戦は、1939年後半から1941年半ばまで実施され、ドイツおよびオーストリアの6つの殺害センターで、主にガス室によって70,000人以上の障害者を殺害した。グラヴィッツはこの計画に深く関与していた。1941年8月、この計画はドイツ国民を動揺させ、戦時の動機付けを損なうと感じられたため停止された。戦争末期の第三の計画は、より秘密裏な方法、大部分が意図的な餓死を用いたものであった。これにより10万人から18万人が殺害されたと推定されている。
ドイツ赤十字社がこれらの出来事にどの程度関与していたかを明確にできるほとんどの証拠は、戦争終結までに偶然または意図的に破壊された。犠牲者の輸送のほとんどは、その目的のために設立された代理組織によって行われたが、ドイツ赤十字社もその一部の輸送に関与していた。障害者を殺害することに関与した看護師の多くは、ドイツ赤十字社の職員であり、組織によって教化されていた。
ラシュトンは、チャールズ・エドワードがこれらの計画について知っていたはずだと考えている。彼はメディアの大量の利用者であり、多くの社会的つながりを持っていた。当時の体制によって収集された証拠と後の研究は、それがドイツ国民の間で広く知られていたことを示唆している。元公爵の遠縁にあたるマリア・カロリーネ公女は1941年にこのプログラムによって殺害された。上流階級の障害者は一般的に、私的な医療を利用したり、家族の政治的つながりがあったりするため、ある程度の保護を受けていたにもかかわらずである。ラシュトンによれば、チャールズ・エドワードは「彼女に何かが起こることを心配していなかった」ため介入しなかったという。彼は彼女が自然死したという弔慰の手紙を受け取ったが、それを信じなかった。家族行事をめったに欠席しない彼としては珍しく、葬儀には出席しなかった。
6.4. 非公式外交官としての活動

ナチス体制はチャールズ・エドワードを非公式の外交官として大いに活用した。ドイツ赤十字社は実質的に体制の支配下にあったが、外国の聴衆には独立した人道組織として提示された。元公爵は国内統治においてはほとんど権力を持たなかったが、重要な国際的な名目上の代表として行動した。チャールズ・エドワードは1934年に新ドイツ政府を代表して最初の世界周遊を行った。
彼は日本を訪問し、戦争中の民間人保護に関する会議に出席し、昭和天皇にヒトラーの誕生日の挨拶を伝えた。この会議により、チャールズ・エドワードは世界中の聴衆に人道主義者として見られることになり、体制の国際的な評判を向上させた。ヒトラーは日本政府との同盟に興味を持っており、チャールズ・エドワードはこの訪問を利用して日本の皇室との関係を築いた。彼がヒトラーのために作成した視察報告書の中で、元公爵はしばしば偏見に満ちた見解を表明し、アメリカにおけるユダヤ人の影響力に対する不満を述べた。


チャールズ・エドワードは、ドイツがイギリス貴族の間で親ドイツ感情を培おうとする試みにおいて、特に重要な役割を果たした。ウルバッハは、チャールズ・エドワードが1930年代に「イギリスへの無限の偵察旅行」を行ったとコメントしている。彼はドイツ政府がイギリスとの同盟を確立するのを助けたいと考え、個人的にはクレアモント・ハウスを取り戻したいとも望んでいた。ウルバッハは、チャールズ・エドワードが姉の助けを借りてイギリスの貴族社会生活に再統合し、著名な貴族や政治家と交際したと記している。これらの人々には、1937年にイギリス首相となったネヴィル・チェンバレンや、特に親ドイツ的な見解を持っていたイギリス王室のエドワード王子が含まれていた。元公爵は独英協会(ドイツ語: Deutsch-Englische Gesellschaftドイツ語)の会長を務め、親ドイツ的と見なされるイギリス人に働きかけた。彼は体制がこの協会を十分に親ナチスではないと判断した後、そのトップに任命された。彼はジョージ5世の葬儀にドイツ軍の制服とヘルメットを着用して参列した。彼はまた、イギリスの退役軍人会にも参加した。
国防大臣のダフ・クーパーは、1936年にアリスの田舎の家でチャールズ・エドワードのために開かれたパーティーについて説明している。「それは彼の兄弟であるコーブルク公爵に会うためのものであった。それは陰鬱な小さなパーティーで、まるでドイツの中流家庭のようであった...昼食後、公爵がドイツの現状を説明し、ヒトラーの平和的意図を私に保証できるよう、私は巧みに彼と二人きりにされた。会話の途中で、公爵夫人[ヴィクトリア・アデライデ]が再び現れ、ひどいリボンの見本を持ってきて、[ジョージ5世の]葬儀に送る花輪をどのように結ぶべきか相談してきた。彼は一連のドイツ語のつぶやきで彼女を解雇し、その後は議論の糸口を見つけることができなかった。」
ジープヴァートは、チャールズ・エドワードの擁護活動はほとんど成功せず、彼が育った環境の人々が、この頃には彼を外国人だと見ていた程度を理解できなかったと主張している。対照的に、ウルバッハは2015年の著書で、戦間期にイギリス社会が経験した緊張がイギリスのエリート層の一部を過激化させ、貴族の間ではファシズム(特にナチズムに対しては不快感があったものの)に対してかなりの同情があったと主張した。彼女は、チャールズ・エドワードが1930年代のドイツに対する宥和政策、例えば英独海軍協定、ドイツのラインラント進駐容認、ミュンヘン協定などに何らかの影響を与えた可能性があると示唆した。
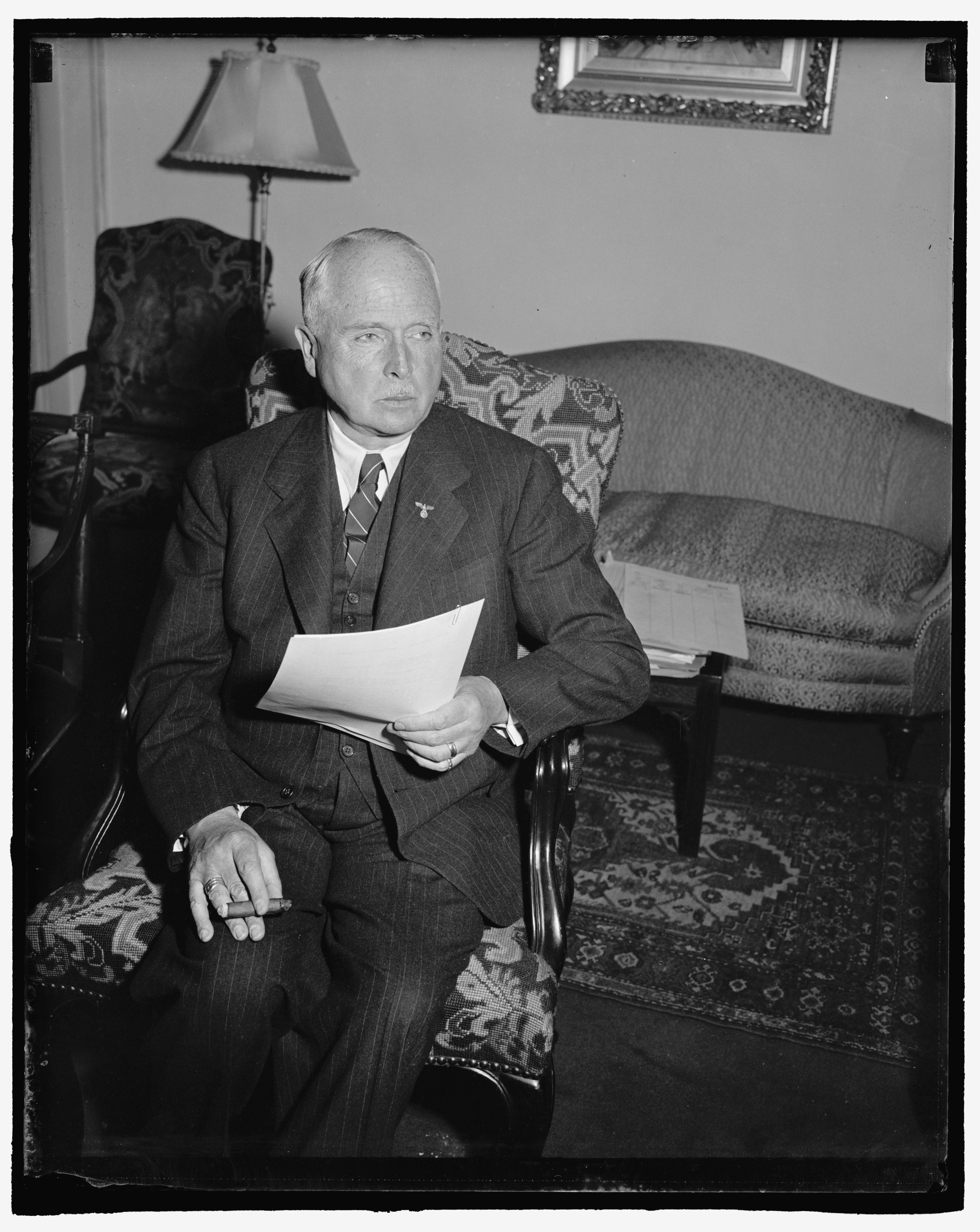
チャールズ・エドワードは1937年にウィンザー公爵夫妻のドイツ訪問に関連する国際記者ツアーを主催した。彼はまた、訪問中にエドワードとウォリス・シンプソン自身をもてなした。1938年にはイタリアを訪れ、ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世国王と独裁者ベニート・ムッソリーニに面会した。彼はポーランドへの旅行に出かけ、ドイツとソビエト連邦による侵攻の半年前にポーランド当局者と会談した。
1940年、チャールズ・エドワードはモスクワと日本を経由してアメリカ合衆国へ渡り、ホワイトハウスでルーズベルト大統領と面会した。彼はドイツ赤十字社が最近征服されたポーランド国民の福祉を保護していると主張した。アメリカ赤十字社はこの訪問にかなり敵対的であり、アメリカの新聞には一部批判もあったものの、全体的にはアメリカの報道でかなり好意的に受け入れられた。在ワシントン・ドイツ大使館の私的な報告書では、公爵個人の魅力が、ドイツにとって外交的に悲惨な結果になることを防いだと主張している。元公爵はアメリカ赤十字社とポーランドへの人道援助を許可する協定に署名したが、その多くは最終的にSSによって没収された。日本においては、モロトフ=リッベントロップ協定が両国間に紛争を引き起こした後、ドイツと日本政府間の関係改善に尽力した。彼は日本占領下の満州国を訪問し、ジャーナリストと共に病院などの施設を視察した。ビュシェルは、これはおそらく日本の当局が、満州国の人々が新しい支配者から適切な人道支援を受けていることを世界の世論に納得させようとする試みであったと示唆している。
6.5. 第二次世界大戦中の行動

1939年に第二次世界大戦が勃発した際、チャールズ・エドワードは再び生誕国とは敵対する側に立った。このことが彼に苦痛を与えたり、政治的信念を疑わせたりした証拠はない。元公爵は現役勤務には高齢であったが、彼の3人の息子は国防軍に勤務した。1941年、彼は戦争に関するニュースを日記に書き留め始め、情報源ごとに異なる色のペンを使用した。1943年に息子フーベルトゥスが飛行機事故で亡くなった際、彼は日記に「Hubertus † fürs Vaterlandドイツ語」(フーベルトゥスは祖国のために死んだ)と記し、国防軍の報告に使用していた色で死を意味する略式の十字を強調した。
1942年、チャールズ・エドワードは親戚であるエウシェン王子から、高齢のユダヤ人女性マルタ・リーバーマンの米国への移住許可を手配するよう依頼された。しかし、彼は何も助けず、リーバーマンは強制送還を命じられた後、テレージエンシュタット・ゲットーで自ら命を絶った。

チャールズ・エドワードのナチズムへの支持は戦争中にますます強まり、決して揺らぐことはなかった。ヒトラーは戦後、彼をノルウェー王にすることを検討していた。元公爵は1940年以降、非公式な外交官としての活動を停止した可能性が高い。彼の健康は衰えつつあり、実年齢よりも老けて見えた。彼は制服を着続け、ドイツ占領下の国々、枢軸国の加盟国、または中立国を旅行した。1941年のフランスのニュース映画『Les Actualités mondialesフランス語』は、彼が無名戦士の墓を訪れ、フランスでドイツ赤十字社の活動を行っていることを報じた。戦時中、少数のドイツ民間人しか海外旅行の特権を与えられていなかった。チャールズ・エドワードがその期間に政治的に何をしていたかは不明だが、彼はヒトラーが彼に有用であると考えた関係者のために組織した基金から、毎月4000 RMをドイツ政府から支払われていた。1940年、チャールズ・エドワードは捕虜の待遇に関するイギリスとドイツ政府間の外交紛争を仲介し、双方の捕虜が手枷をつけられることを阻止した。1943年、ヒトラーの命令により、チャールズ・エドワードは国際赤十字にカティンの森事件の調査を依頼した。
1945年4月、ブレッチリー・パークの暗号解読者たちは、ヒトラーからの「チャールズ・エドワードを捕らえさせてはならない」という命令を解読した。ウルバッハによれば、これはヒトラーが彼を殺害したかったことを意味する。その月、チャールズ・エドワードはコーブルク城をアメリカ軍に降伏させることに同意した。彼は城の博物館で爆撃によって発生した火災の消火に彼らの支援を得た。彼はアメリカ陸軍の戦争犯罪人容疑者リストに載っており、自宅軟禁に置かれた後、11月には捕虜収容所に移送された。彼は尋問を受け、城の居間で拘束者たちとワインを飲んだ。彼の尋問官は彼を無知で不愉快な人物、そしておそらく精神的に不安定な人物と見ていた。彼はインタビューで、新しいドイツ政府に参加するという申し出を受け入れるだろうと述べ、そのアイデアに関連する一連の要求を行い、「ドイツ人はいかなる戦争犯罪も犯していない」と主張した。これらのコメントは連合国のプロパガンダにとって非常に有用であると見なされ、1945年4月のラジオ放送で利用された。彼はまた、ユダヤ人を公的生活から排除したのは正しかったという見解や、ドイツ人は生まれつき民主主義には不向きであるという見解も表明した。
7. 戦後期と死
カール・エドゥアルトの戦後は、非ナチ化裁判、財産の没収、そして健康問題に苦しむ晩年という、困難な時期であった。
7.1. 戦犯裁判と非ナチ化プロセス
第二次世界大戦終結後、チャールズ・エドワードは1945年から1946年までアメリカ軍当局に抑留された。彼の姉アリスは、健康上の理由から彼の釈放を求めてロビー活動を行い、成功した。釈放後、彼とヴィクトリア・アデライデはカレンベルク城の郊外にある小さな家に移り住んだ。カレンベルク城は難民の家として使われていた。アリスは1948年に夫妻を訪れた。彼女の記録によれば、彼らは貧しく、弟は重度の関節炎でひどく病んでいたという。彼女は当局を説得し、姉のヴィクトリア・アデライデが食料を購入しやすいように、彼らの住居の一部に引っ越すことを許可させた。

1946年4月、チャールズ・エドワードの娘シビラは息子カール・グスタフを出産した。彼は出生時、スウェーデン王位継承順位第3位であった。1947年1月、シビラの夫が飛行機事故で死去し、1950年10月にはグスタフ5世が死去した。これにより、チャールズ・エドワードの孫カール・グスタフはスウェーデン皇太子となり、後にカール16世グスタフ国王となった。
チャールズ・エドワードの裁判は4年間続き、2度の上訴が含まれた。アリスや他の多くの関係者は、彼の体制への関与を最小限に見せるため、不誠実にも彼の弁護を行った。戦争終結から約1年後、西側連合国の優先事項は、元ナチスを処罰することから、冷戦中に彼らの占領地域を西側陣営の一部とする準備へと移行していた。1950年(ODNBの項目によれば1949年8月)に、元公爵は非ナチ化裁判で「Mitläuferドイツ語」(同調者)および「Minderbelasteterドイツ語」(軽度責任者)と認定された。元公爵の伝記作家カール・ザントナーはこの結果を「茶番」と呼んだ。チャールズ・エドワードは第二次世界大戦への関与により、多くの財産を失った。ソ連占領地域にあったゴータの財産は没収され再分配された。
7.2. 晩年の生活と健康問題
チャールズ・エドワードは晩年を隠遁して過ごし、非ナチ化裁判で課せられた罰金と、ソ連によって財産の多くを没収されたことにより、比較的貧困に陥った。しかし、彼のライフスタイルは裁判後、おおむね通常の状態に戻った。
1953年、彼は救急車と車椅子でコーブルクの映画館へ運ばれ、エリザベス2世女王の戴冠式を鑑賞した。報道によると、彼は姉を含む親族の姿を見て涙を流しそうになっていたという。同年『スコッツマン』紙のコラムによれば、元公爵はかつての名誉連隊長を務めたイギリス陸軍連隊であるシーフォース・ハイランダーズ(現在はドイツに駐留)との関係を再構築していたという。コラムには次のように記されている。「連隊の舞踏会の際、公爵に招待状が送られた。そこには連隊長(P・J・ジョンストン中佐)からのメモが添えられており、距離のために彼が出席できるかどうかは疑わしいが、連隊の全将校が彼らの古い名誉連隊長にぜひ来てほしいと願っている、とあった。公爵は、健康上の理由で辞退せざるを得ないが、『長年にわたってシーフォース・ハイランダーズと私との間に存在した古い絆が、再び途絶えることがないよう心から願い、望む』という招待に深く感動したと返答した。彼は、コーブルクに住むどんな仲間でも客として喜んで迎え入れると述べ、『チャールズ・エドワード、ザクセン=コーブルク=ゴータ公爵、オールバニ公爵』と署名した。」
7.3. 死

チャールズ・エドワードは1954年3月6日、コーブルクの自宅で癌のため69歳で死去した。彼は息子フリードリヒ・ヨシアスに、ヴィクトリア女王は常に彼が「善良なドイツ人」になることを望んでいたと語ったと言われている。『タイムズ』紙の死亡記事には、「...彼はヒトラーの人間であった...彼がナチス一味の内部評議会にどの程度まで認められていたかは、まだ未解決の問題である」と記されている。ヨーロッパ各地の王室から弔電が寄せられたが、イギリス王室はコメントしなかった。
チャールズ・エドワードの葬儀は3月10日に行われ、ナチス政権下で教会の役人であったルター派の首席司祭が執り行った。司祭はチャールズ・エドワードを、他人によって操られ、連合国によって不当に扱われた善良な人物であったと述べた。元公爵の死はコーブルクで公式に追悼された。彼の葬儀で半旗を掲げることを拒否した公務員は、バイロイトの地区議会に報告され、バイエルン州議会の議員によって非難された。ヴィクトリア・アデライデは夫の死後数週間にわたり、元ナチス高官を含む多くの支持の手紙を受け取った。チャールズ・エドワードの埋葬は10月12日に行われ、多くの参列者が見守った。彼はコーブルクのバイアースドルフ地区、カレンベルク城近くのヴァルトフリートホーフ墓地(Waldfriedhof Beiersdorfドイツ語)に埋葬されている。
8. 遺産と評価
カール・エドゥアルトの生涯と行動は、家族や同時代人、そして現代の歴史家やメディアによって、大きく異なる評価を受けている。特にナチス体制への関与は、彼の遺産を巡る主要な論争点となっている。
8.1. 家族および同時代人による評価
彼の姉アリスが1966年に出版した自叙伝『For My Grandchildren』は、チャールズ・エドワードの生涯について触れている。彼女は弟が第一次世界大戦中に偏見の犠牲になり、家族のためにドイツに留まることを選んだだけだと感じていた。彼女は、彼がナチス体制において果たした役割は最小限であったと示唆している。ウルバッハは、この自叙伝が意図的に誤解を招くように書かれており、選択的であると主張した。
アリスの1981年の伝記において、アロンソンは、一部のイギリス王室メンバーがチャールズ・エドワードが「ヒトラーがドイツを共産主義から救ったと確信していたため」に体制を支持したと感じていたと述べている。彼は、アリスが弟が戦後投獄中にひどい扱いを受けたと感じていたと書いている。「彼はほとんど耐えられない状況にいた...。彼の仲間の囚人の多くはそこで亡くなった...」と。しかし、彼女はまた彼に「間違いなく、彼らの看守たちは恐ろしいドイツの強制収容所を見ており、これらの年老いた将校たちを最大限の厳しさで扱うことを決意していたのだろう」と語ったという。
コーブルクのアマチュア歴史家であるルドルフ・プリースナーは、1977年にチャールズ・エドワードの最初の伝記を執筆した。元公爵の息子フリードリヒ・ヨシアスはプリースナーに手紙を送り、その本を批判した。彼は、その本が父親に過度に同情的であることなど、いくつかの誤りを指摘し、父親がホロコーストについて知っていたと信じていた。彼は、兄フーベルトゥスがユダヤ人の絶滅収容所への強制送還を目撃し、家族とこの件について頻繁に話していたと記している。フリードリヒ・ヨシアスは父親の伝記を執筆する計画を立てていたが、実現することはなかった。
8.2. 現代的再評価と批判
2007年12月、イギリスのチャンネル4は、チャールズ・エドワードに関する1時間のドキュメンタリー番組『Hitler's Favourite Royal』を放映した。『ガーディアン』紙の批評は、この映画を「弱々しい男と哀れな家族についての堅実なドキュメンタリー」と評した。『デイリー・テレグラフ』の別の批評は、このドキュメンタリーがチャールズ・エドワードに過度に同情的であったと示唆し、「物語は純粋な悲劇として現れた。確かにその部分もあったが、彼が公爵位に昇格し、それを失ったトラウマによって、善悪の判断能力が奪われたかのように描かれている」と述べた。
ウルバッハは、2007年のドキュメンタリーの制作チームの間で、チャールズ・エドワードを、彼にとって異国であるドイツの政治に苦しむ人物として描くべきか、それともイデオロギー的なナチス党員として描くべきかについて意見の相違があり、それが彼の性格の矛盾した描写につながったと記している。彼女は、2007年から2015年の期間に新たな証拠が発見され、彼が「明らかに状況の naive な犠牲者ではなく、ヒトラーの非常に積極的な支持者であった」ことが示されたと述べた。ウルバッハは、チャールズ・エドワードがヒトラーと類似した性格を持っていたと主張し、二人が「イデオロギー、そしてもちろん彼らの自己愛的な性格(二人とも好意を示したのは彼らの犬だけであった)」を共有していたとコメントしている。彼女はまた、彼の人生を「彼が育った立憲君主制から独裁制への徹底的な再教育の例」と描写した。
ウルバッハの2015年の著書『Go Betweens for Hitler』は、チャールズ・エドワードを含む様々な貴族が、どのようにしてナチス・ドイツの非公式外交官として活動したかについて論じている。『タイムズ』紙の批評は、チャールズ・エドワードについて次のようにコメントしている。「それから長年にわたり、カール・エドゥアルトは単なる歴史の脚注、20世紀初頭の地殻変動によって打ち上げられた、無害で風変わりな老貴族と見なされてきた。しかし、その穏やかな解釈は最近見直された。現在では、カール・エドゥアルトがナチ党員であり、準軍事テロリズムの支援者であり、そしてウルバッハの優れた本が示しているように、ヒトラーにとって重要な『仲介者』であったことが分かっている。」
ビュシェルは2016年のチャールズ・エドワードの伝記で、幼少期から第一次世界大戦の結末に至るまで、この貴族にかけられた様々な圧力が、彼が多重人格障害と自己愛を発症した原因となった可能性があると示唆している。著者は、ナチス体制が元公爵に第一次世界大戦後に失った地位の多くを取り戻させたのだと主張する。彼は、チャールズ・エドワードが「強制、恐怖、教化、優位に立とうとする努力、そしておそらくは内面的な居場所のなさや孤独」によって影響を受けたとコメントしている。彼はこれが公爵の同時代の多くのドイツ人と同様であったと示唆している。しかし、ビュシェルは、チャールズ・エドワードがドイツを離れるという選択肢が比較的容易であったにもかかわらず、ナチス体制を支持することを自由に選択したと信じている。彼は、元公爵が体制の貴族支持者の中で最も積極的で熱心であったと記述している。彼はチャールズ・エドゥアルトを「二級の加害者」と表現している。それは、体制の中心人物ではなかったが、何百万人もの人々の死につながる政策を隠蔽するのに貢献した人物である。
ラシュトンは2018年の著書で、元公爵と障害者殺害の関係について、「王族に生まれた人間が、人間の破壊の政治に巻き込まれていく物語である。それは悲劇的な物語である」と記述している。ラシュトンは、もしチャールズ・エドワードが体制の行動に異議を唱えることを選択していたら、彼と彼の家族に危険が及んだであろうと示唆し、迫害された他の元貴族の例を挙げている。ラシュトンは、チャールズ・エドワードがすでにイギリス王子およびドイツ公爵としての地位を失っていたため、ナチ党指導者としての新しいアイデンティティが彼にとって深く感情的に重要であったと指摘している。ラシュトンは、チャールズ・エドワードの行動に影響を与えた要因が、多くのドイツ人と類似していたと主張している。しかし、この歴史家はまた、元公爵がヒトラーと親密な友情を持っていたことにも言及し、彼がヒトラーに特定の残虐行為を止めるよう促すことができたはずだと主張している。著者は、チャールズ・エドワードが遠縁の家族の殺害に反応しなかったことは、彼が「意志薄弱」であったことを示していると感じている。彼はこれが「...道徳的性格の欠陥...低い自尊心とほとんどない自己尊重...[行動の欠如はしばしば]コミュニティにおける他者の意見への恐れと、自身の快適で安全なライフスタイルへのリスクに起因する」と主張した。
2015年、コーブルクでマックス・ブローゼというナチス体制と関係のあったビジネスマンに通りを命名すべきかどうかを巡る地元住民間の紛争が発生した。これに対応して、コーブルク市議会は歴史家グループに、コーブルクでナチスの支持が異常に急速に発展した理由と、その期間の町の出来事を調査するよう委託した。2024年に調査結果を報告したこの委員会は、チャールズ・エドワードが町の影響力のある人物であり、彼のフェルキッシュ(ドイツ語: Völkischドイツ語)組織への支持が極右政治の成長に貢献したことを指摘した。
8.3. 社会的影響と論争
カール・エドゥアルトの生涯は、彼の行動が社会正義、人権、そして少数者保護に及ぼした否定的な影響という点で、歴史的な論争の対象であり続けている。彼がナチ党に積極的に関与し、ドイツ赤十字社総裁としてそのイデオロギーを推進した事実は、彼の道徳的責任を浮き彫りにしている。特に、優生学思想を支持し、それが障害者虐殺プログラムに結びついたことへの彼の関与は、社会的に脆弱な人々に対する甚大な被害をもたらした。彼は、ナチスが数万人の障害者や病者を「生きるに値しない命」として組織的に殺害したことを知りながら、その体制内で要職を務め、時にはこれを隠蔽する役割を果たしたとされている。
彼の「非公式外交官」としての活動は、ナチス体制の国際的イメージを向上させ、宥和政策を通じてその拡大を助長する一因となった可能性が指摘されている。これは、彼の出身地であるイギリスとの関係悪化や爵位剥奪という代償を払ってまで、彼がナチスの理想に深く傾倒していたことを示している。
戦後の非ナチ化裁判における「同調者」という比較的軽い判決は、当時の社会情勢や、彼が王族であったという背景が影響した可能性があり、彼の責任の重さに対して十分に裁かれたとは言えないという批判も存在する。彼の晩年の困窮は、戦争とナチスへの協力の結果ではあるが、彼が自らの行為の倫理的重みを十分に理解していたかは定かではない。
現代においては、彼の生涯は、権力と特権がどのようにして全体主義的なイデオロギーと結びつき、結果として人道に対する罪に加担しうるかを示す悲劇的な教訓として再評価されている。彼の物語は、過去の行為に対する説明責任、そして歴史の暗部から学ぶことの重要性を強調するものである。