1. 生涯
丁汝昌は、貧しい家庭に生まれ、学問の機会に恵まれなかったが、軍人としての才能を開花させ、清朝の近代化に尽力した。
1.1. 幼少期と教育
丁汝昌は1836年11月18日(道光16年10月10日)、現在の安徽省巣湖市の一部である廬江(現・廬江県)で生まれた。家が裕福ではなかったため、わずか3年ほど私塾に通っただけで、10歳になる頃には学問の機会を失ってしまった。
1.2. 初期経歴
1854年(咸豊4年)、太平天国軍が廬江を占領すると、丁汝昌も葉芸来の太平天国軍に参加した。しかし、1861年には曽国藩率いる湘軍に安慶が包囲されると、程学啓と共に清朝に投降した。安慶攻略で功績を挙げたことで、正六品官である千総(清朝の緑営の下士官)として召し抱えられた。
1862年(同治元年)、李鴻章の淮軍に編入され、太平天国軍との戦いに身を投じた。その勇敢さが認められ、劉銘伝の部隊に引き抜かれた。1864年に太平天国が滅亡すると、今度は劉銘伝に従って北上し、捻軍と戦った。1868年に東捻軍を撃退した功績により、従一品官である提督総兵官(その省の緑営軍官を束ねる長官)の官位と、満州語で「勇者」を意味する「協勇巴図魯」(武功があった者へ与えられる満州族の勇者称号)の勇者称号を授与された。
しかし、1874年(同治13年)に清朝が軍縮を決定すると、丁汝昌は自身の部隊縮小に猛烈に抗議する手紙を劉銘伝に送った。これに激怒した劉銘伝は丁汝昌の暗殺を企てるが、計画を耳にした丁汝昌はすぐに職を辞して帰郷し、難を逃れた。
2. 海軍建設と指揮
丁汝昌は李鴻章の招聘に応じ、清朝の近代化運動の一環として、最新鋭の北洋艦隊の建設と指揮に深く関与した。
2.1. 近代化運動への参加
1875年(光緒元年)、北洋通商大臣兼直隷総督となっていた李鴻章が洋式海軍の創設を進めていることを知り、丁汝昌は李鴻章を頼った。李鴻章は丁汝昌と劉銘伝の間の確執を考慮し、丁汝昌を湘軍に戻さず、新海軍創設の参与に据えた。丁汝昌は洋務運動の支持者であり、李鴻章に対し、外国からの輸入に頼るのではなく、中国国内で近代的な装甲巡洋艦を建造できる造船所を建設するよう強く求めた。また、威海衛と旅順口の海軍基地建設にも積極的に関与した。
2.2. 海外での艦船購入と視察
1880年(光緒6年)、丁汝昌は新海軍初の巡洋艦としてイギリスのアームストロング社に発注していた「超勇」と「揚威」の受け取りのため、林泰曽や鄧世昌ら乗組員を率いてイギリスのニューカッスル・アポン・タインを訪れた。彼はまた、ドイツやフランスも訪問し、それぞれの国の造船技術を習得した。
2.3. 北洋艦隊司令官
1888年(光緒14年)に北洋艦隊が正式に発足すると、丁汝昌は提督(水師提督、艦隊司令長官の意味)に任命された。1888年から1894年まで北洋艦隊を指揮し、1894年には海軍副大臣の地位に昇進した。
1891年(光緒17年)7月から8月にかけて、丁汝昌は艦隊を率いて日本を訪問した。この訪問は、最新鋭の巨大艦を率いることで日本を威嚇する目的も含まれていた。当時の記録によれば、瀬戸内海を遊弋中、周囲に広がる段々畑を見て、「丘の中腹を耕すがごとき貧窮の小国が、沃野無辺の大清帝国に戦を挑むがごときは笑止なり」と日本を嘲笑ったという逸話も残っている。滞在中には、芸妓のおしかと恋仲になったという話もある。
1891年以降、清朝の海軍予算は大幅に削減された。これは頤和園の改修などに予算が振り分けられたためと言われている。いずれにせよ、丁汝昌は厳しい財政状況の中で艦隊を運営しなければならず、これ以降北洋艦隊は新たな軍艦の購入を行うことができなかった。
3. 主要な軍事活動と事件
丁汝昌は日清戦争以前にも、清朝の軍事力と外交的影響力を示すため、いくつかの重要な軍事作戦や外交事件に関与した。
3.1. 壬午事変
1882年(光緒8年)、朝鮮で壬午事変が勃発すると、清朝の艦長呉長慶の命令により、丁汝昌は北洋艦隊の軍艦5隻を率いて朝鮮に派遣され、事変の鎮圧を支援した。呉長慶は興宣大院君(高宗の父)を捕らえて清へ連行した。これにより朝鮮には親清政権が復帰し、清は旧来の宗主国としての存在感をアピールし、朝鮮への日本の進出を阻止することに成功した。また、丁汝昌は朝鮮とアメリカ合衆国間の貿易正常化交渉におけるオブザーバーも務めた。
3.2. 長崎事件
1886年、丁汝昌は北洋艦隊を率いて香港、日本の長崎、朝鮮の釜山と元山、ロシアのウラジオストクを巡る示威行動に参加した。同年8月13日、長崎滞在中、旗艦「鎮遠」の複数の酔った水兵が地元の遊廓で乱闘騒ぎを起こし、日本人巡査1名が刺殺される事件が発生した。2日後の8月15日には、地元住民、警察、丁汝昌の率いる水兵の間で暴動が起こり、中国人水兵6名が死亡、45名が負傷し、日本人巡査5名が死亡、16名が負傷した。この事件は長崎事件として外交問題に発展したが、丁汝昌は1891年に再び北洋艦隊を率いて日本を訪問することができた。
3.3. 清仏戦争
1884年の清仏戦争中、丁汝昌は清の皇帝から「黄馬褂」を授与された。これは清朝において伝統的に最高の軍事褒賞とされていた。
4. 日清戦争
日清戦争が勃発すると、丁汝昌は北洋艦隊の司令官として、黄海海戦と威海衛攻防戦という主要な戦闘に直面した。
4.1. 黄海海戦
1894年(光緒20年)に日清戦争が勃発した際、北洋艦隊は当時世界で8位に評価される強力な艦隊であった。当初、李鴻章は艦隊を温存しつつ、陸上戦を中心に日本を撃破する方針を考えていた。これは、予算不足の北洋艦隊が既に広東艦隊から巡洋艦を借り入れて編入しており、万一北洋艦隊が壊滅した場合、清の制海権を守る艦が残っていなかったためと言われている。
しかし、日本が連合艦隊を組織して陸上部隊の輸送支援などに参加すると、清国内では「なぜ北洋艦隊は出撃しないのか」という世論が高まった。8月10日に日本の連合艦隊が黄海に侵入すると、光緒帝までもが李鴻章に対し「丁汝昌は日本海軍を恐れているのか」と叱責した。ここに至り、李鴻章は已む無く北洋艦隊に出動命令を出した。
同年9月17日、鴨緑江河口沖で日本の連合艦隊と遭遇し、黄海海戦が行われた。丁汝昌は艦隊司令官として旗艦「定遠」の艦橋で指揮を執っていたが、主砲発射時の事故(艦の構造欠陥または艦長の故意の誤射によるという説もある)で艦橋が破壊された際に負傷してしまった。この時、北洋艦隊には問題が生じた。旗艦が指揮不能状態に陥った際の権限委譲の手順が定められていなかったため、北洋艦隊の各艦は個別に戦闘を開始した。結局、約5時間にも及ぶこの戦闘の結果、北洋艦隊は主力12隻のうち5隻を失い、威海衛へと後退した。
4.2. 威海衛攻防戦
黄海海戦後、丁汝昌は李鴻章の命令で残った北洋艦隊を本拠地の威海衛に移し、座乗艦を「鎮遠」に替えてひたすら防備を固めた。丁汝昌は威海衛を防衛する陸上部隊の戦力に不安を感じていたが、陸上の砲台は北洋艦隊の管轄ではなかったため、この不安は改善されなかった。
1895年1月20日(光緒21年)、日本軍は山東半島の栄成(現山東省威海市栄成市)に上陸した。日本の連合艦隊司令長官である伊東祐亨は丁汝昌に降伏を勧告したが、丁汝昌はこれを拒否した。日本軍は陸路から威海衛の陸上砲台を攻略し、海と陸から北洋艦隊を包囲した。状況は絶望的となり、日本陸軍が沿岸要塞を占領し、港を囲む防材を降ろして日本の水雷艇による攻撃を可能にした。
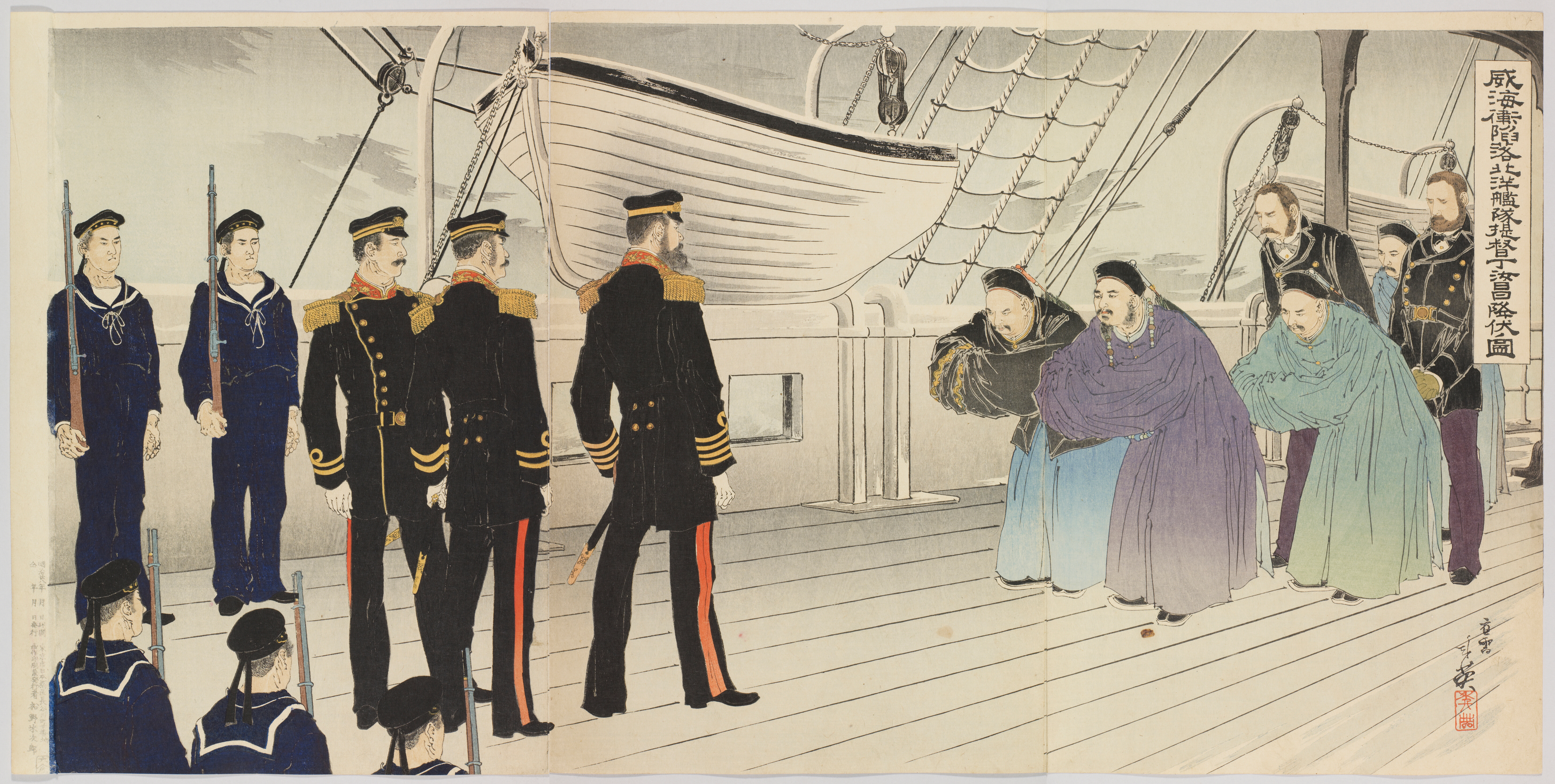
5. 最期
威海衛攻防戦の末、丁汝昌は兵員の命を救うため、自らの命を絶った。
5.1. 自決
数日間の戦闘の後、1895年2月12日(光緒21年1月18日)、丁汝昌は兵員の助命を条件に降伏に応じた。しかし、自身は「鎮遠」の艦内、あるいは劉公島の司令部にある執務室で阿片を過剰摂取し、服毒自決を遂げた。享年58歳であった。彼の副官である劉歩蟾も、自身の軍艦を爆破して自沈させた後、自決した。残存する北洋艦隊は日本軍に降伏した。
丁汝昌の死後、北洋艦隊は正式に降伏した。兵員たちは許され、残った艦艇は日本軍に鹵獲された。丁汝昌の遺体はジャンク船で後送されることになったが、伊東祐亨の独断的な計らいにより、貨物船「康済号」一隻が鹵獲処分を解かれ、丁汝昌の遺体を本国へ運ぶために使用された。遺体を乗せた船は、日本海軍の敬礼の列に見送られながら、助命された兵員とともに本国へ帰還した。

6. 死後評価と復権
丁汝昌の死後、清政府は彼に敗戦の責任を転嫁したが、後にその功績と犠牲が再評価され、名誉が回復された。
6.1. 清政府による責任転嫁
「北洋艦隊消滅」の知らせを聞いた光緒帝は激怒し、丁汝昌の財産没収を言い渡し、葬儀を執り行うことすら許さなかった。清政府は彼を敗戦の責任者として非難し、全ての官職と階級を死後に剥奪した。
6.2. 名誉回復
しかし、丁汝昌の自決という最期は、日本人だけでなく、多くの清国軍人からも尊敬を集めた。彼の名誉回復がなされたのは1910年、当時の海軍大臣である愛新覚羅載洵(光緒帝の実弟)や南北洋水師兼広東水師提督の薩鎮氷らの嘆願によるものであった。そして、辛亥革命によって清朝が打倒された後の1912年には、彼の家族によって正式な埋葬が行われ、名誉が完全に回復された。