1. 概要
孝貞顕皇后(こうていけんこうごう、ᡥᡳᠶᠣᠣᡧᡠᠩᡤᠠ ᠵᡝᡴᡩᡠᠨ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡥᡡᠸᠠᠩᡥᡝᠣhiyoošungga jekdun iletu hūwangheo満州語、1837年8月12日 - 1881年4月8日)は、清の咸豊帝の皇后であり、同治帝と光緒帝の摂政を務めた皇太后である。一般には「東太后」(東太后ドンタイホウ中国語)または「慈安皇太后」(慈安皇太后ツーアンホワンタイホウ中国語)として知られる。紫禁城の東部に位置する鍾粋宮に居住したため東太后と通称され、生母である西太后(懿貴妃)が西部に居住したことから西太后と対比された。
彼女は温和で慈愛に満ちた人柄で知られ、咸豊帝や同治帝、光緒帝からも深く敬愛された。特に同治帝は生母である西太后よりも嫡母である東太后に懐いていたとされる。政治への介入は控えめであったが、宦官安徳海の処刑においては果断な決断を下し、その影響力を示した。西太后との関係は、当初は協力的であったものの、同治帝の皇后選定や安徳海事件、そして光緒帝時代の摂政期には対立が生じ、その突然の死は毒殺説という歴史的論争を巻き起こした。清朝末期の激動期において、彼女は西太后と共に国政を担い、同治中興と呼ばれる安定期を築いた一方で、その政治的役割や人物像については、肯定的な評価と批判的な見解が併存している。
2. 初期生涯と背景
孝貞顕皇后は、清朝の伝統的な貴族階級に属する名門の家系に生まれた。彼女の出自と家族構成は、その後の宮廷生活における地位と役割に大きな影響を与えた。
2.1. 家族と出自
孝貞顕皇后の個人名は歴史に記録されていない。彼女は満洲鑲黄旗のニオフル氏(ᠨᡳᠣᡥᡠᡵᡠ ᡥᠠᠯᠠNiohuru hala満州語、鈕祜禄氏)の出身である。父は穆揚阿(穆揚阿Muyang'a中国語、穆楊阿)で、広西右江道道員を務め、後に三等承恩公の爵位を授けられた。母は穆揚阿の妾であった姜佳氏(姜佳氏Giyanggiya中国語、姜氏)である。孝貞顕皇后は道光帝17年旧暦7月12日(1837年8月12日)に生まれた。彼女には広科(廣科Guangke中国語)という兄と、荘侯親王奕仁(奕仁Yiren中国語)の正室となった姉妹がいた。また、叔母は咸豊帝の側近であった鄭親王端華の正室であり、孝哲毅皇后の母方の祖母にあたる。
2.2. 家系と血統
ニオフル氏は、清朝の創始者ヌルハチに仕えた「五大臣」の一人であるエイドゥ(1562年 - 1621年)の子孫であり、エイドゥの三男である車爾格(車爾格Celge中国語、1647年没)の系統に属する。この家系は弘毅公府鈕祜禄氏の16の房系の一つで、孝貞顕皇后の系統は車爾格の六男である巴喀(巴喀Ba Khe中国語)に由来する。車爾格は清朝初期に戸部尚書を務め、騎都尉兼一雲騎尉の爵位を得ており、弘毅公府の16房系の中でも比較的高い地位にあった。
彼女の曽祖父である福克精阿(福克精阿Fukejing'a中国語)は西寧で管理官を務め、男爵の爵位を有していた。祖父の策布坦(策布坦Cebutan中国語、1794年没)は山西省で二品指揮官を務め、同じく男爵であった。父の穆揚阿は広西省で官職に就き、三等承恩公の爵位を授けられた。穆揚阿の正室はヌルハチの曾孫である慶恆(慶恆Qingheng中国語、1779年没)の孫娘であった。
この家系は、康熙帝や雍正帝の時代には一時的に官職が振るわなかったものの、婚姻を通じて再び栄光を取り戻した。例えば、策布坦の二人の娘は宗室貴族と婚姻し、長女は荘王府輔国将軍永蕃(永蕃Yong Fan中国語)に、次女は粛慎親王敬敏(敬敏Jing Min中国語)の継福晋となった。これにより、彼女の家族は一等世家の仲間入りを果たした。孝貞顕皇后の叔母は鄭親王端華の嫡福晋となり、これは孝哲毅皇后の母方の祖父母にあたる。このように、彼女の家系は名門であり、宗室貴族との婚姻関係も深く、これが彼女が皇后に選ばれる重要な要因となった。
3. 後宮入りと皇后時代
孝貞顕皇后は、咸豊帝の後宮に入り、その才能と品格によって急速に昇進し、皇后の座に就いた。しかし、彼女には子がなかったため、後宮におけるその役割は独特なものとなった。
3.1. 咸豊帝後宮への入内と皇后冊立

道光帝が1850年2月15日に崩御した後、その四男である奕詝が咸豊帝として即位した。咸豊帝の正室であった孝徳顕皇后は即位の約1ヶ月前に亡くなっていたため、新たな皇后の選定が急務となったが、道光帝の服喪期間のため遅延した。
1851年に紫禁城で行われた咸豊帝の妃嬪選定において、ニオフル氏は道光帝の妃嬪で最高位であった康慈皇太妃(孝静成皇后)によって候補に選ばれた。1852年旧暦2月、ニオフル氏は後宮に入り、まず妃嬪の第四位である貞嬪に冊封された。この「貞」(ᠵᡝᡴᡩᡠᠨjekdun満州語)という漢字は、満洲語で「貞節」を意味し、漢語では「正直」や「正当」といった意味も持つ。
貞嬪に冊封されたわずか1ヶ月後の1852年旧暦5月25日には貞貴妃に昇進し、さらにその翌月である旧暦6月8日には皇后に冊立される旨の詔が発せられた。そして、同年旧暦10月17日、大学士の裕誠を正使、礼部尚書の奕湘を副使として、正式に皇后として冊立された。この時、彼女は16歳であった。この異例の速い昇進は、彼女が最初から皇后候補として見なされていたことを示唆している。咸豊帝の皇后となる以前に、彼の正室が崩御していたため、ニオフル氏は大婚の儀式ではなく、妃嬪として入宮し、段階的に皇后に冊封されるという形式が取られた。
3.2. 皇后としての役割
皇后として、孝貞顕皇后は咸豊帝の後宮を統括する役割を担った。彼女は咸豊帝との間に子をもうけることはなかった。1856年4月27日、咸豊帝の妃嬪である懿貴妃(後の西太后)が皇帝の長男である載淳(後の同治帝)を出産した。孝貞顕皇后は載淳の生母ではなかったものの、皇后として咸豊帝の全ての子女の名目上の母であり、彼らの養育と躾の責任を負った。懿貴妃は載淳の養育においてほとんど発言権を持たず、孝貞顕皇后が子供たちの罰を決定する権限を持っていた。懿貴妃は後に、孝貞顕皇后との関係について「彼女とはかなりの問題があり、良好な関係を保つのが非常に難しかった」と回想している。しかし、咸豊帝は孝貞顕皇后を深く信頼し、敬愛しており、彼女は後宮において揺るぎない地位を確立していた。
4. 皇太后と摂政
咸豊帝の崩御後、孝貞顕皇后は皇太后として、幼い同治帝と光緒帝の摂政を務めた。この時期は清朝が内外の危機に直面する中で、彼女が西太后と共に政治の表舞台に立つこととなった重要な時代である。
4.1. 咸豊帝の崩御と皇太后冊立

1861年8月22日、第二次アヘン戦争の最中、咸豊帝は北京の北東約230 kmに位置する熱河行宮で崩御した。彼は唯一の存命の息子である載淳に帝位を継がせた。載淳は当時わずか5歳であり、同治帝として即位した。咸豊帝は死の床で、側近の粛順を含む8人の顧命大臣を摂政に任命した。しかし、同治帝の生母である懿貴妃(後の西太后)も摂政の座を望んだ。孝貞顕皇后は当初、粛順らと協力することに同意したが、懿貴妃に説得され、考えを改めた。
咸豊帝の崩御に伴い、皇后であったニオフル氏は皇太后に冊立され、「母后皇太后」(母后皇太后Mu Hou Huang Tai Hou中国語)の尊号を授けられた。一方、懿貴妃は同治帝の生母として「聖母皇太后」(聖母皇太后Sheng Mu Huang Tai Hou中国語)に尊崇され、慈禧(慈禧Cixi中国語)の尊号を授けられた。母后皇太后の孝貞顕皇后には慈安(慈安Ci'an中国語)の尊号が与えられ、慈禧皇太后よりも上位に位置づけられた。孝貞顕皇后は紫禁城の東部に位置する鍾粋宮に居住したため「東太后」と通称され、西部に居住した慈禧皇太后は「西太后」と呼ばれた。
4.2. 辛酉政変と摂政権掌握

1861年11月、孝貞顕皇后と懿貴妃は、咸豊帝の六弟である恭親王奕訢と七弟である醇親王奕譞(懿貴妃の妹、葉赫那拉婉貞の夫)の支援を得て、顧命八大臣に対するクーデターを敢行した。これは歴史的に「辛酉政変」として知られる。この政変により、八大臣は失脚し、孝貞顕皇后と懿貴妃は摂政権を掌握した。
この政変の背景には、咸豊帝崩御後の権力闘争があった。懿貴妃は、自身と孝貞顕皇后が女性であり、幼い皇帝が摂政大臣に抑圧されることを懸念し、共同で政権を握ることを孝貞顕皇后に提案した。クーデターは綿密に計画され、咸豊帝の棺が北京に運ばれる際、両皇太后と幼帝は先行して北京に戻り、恭親王奕訢と連絡を取り、八大臣が到着次第逮捕する手はずを整えた。1861年11月2日、八大臣が北京に到着すると、両皇太后は直ちに政変を発動し、彼らを逮捕・投獄した。粛順は「この卑しい女どもを早く始末しなかったことを後悔する!」と叫んだとされる。最終的に粛順、載垣、端華の3名が処刑され、他の5名は職を解かれた。これにより、両皇太后は清朝史上初めて「垂簾聴政」(摂政として簾の裏から政務を執ること)を行うこととなった。
4.3. 同治帝時代の摂政

同治帝の即位後、孝貞顕皇后と慈禧皇太后は共同で摂政を務めた。女性が朝廷の会議に姿を現すことが許されなかったため、彼女たちは幼い皇帝と共に、会議中は簾の裏に座って政務を執った。原則として孝貞顕皇后が慈禧皇太后よりも上位にあったが、実際には孝貞顕皇后は政治にあまり介入せず、控えめな性格であったため、慈禧皇太后が実質的に朝廷を掌握した。しかし、孝貞顕皇后も政治を学ぶ必要があったため、両皇太后は共に歴史を学び、1861年11月からは満洲族の先祖の記録を参考にし、1863年6月には『通鑑輯覧』の内容を説明させた。また、1866年11月まで2年以上にわたり、翰林院の学者たちによる『治平宝鑑』の講義に出席した。
多くの伝記作家は、慈禧皇太后が実質的な権力者であったと考えている。しかし、摂政初期の20年間は、慈禧皇太后が単独で決定を下すことは許されず、全ての詔勅は両摂政の承認を必要とした。孝貞顕皇后の印章には「御賞」(皇帝の賞賜)と刻まれ、慈禧皇太后の印章には「同道堂」(道に合致する殿堂)と刻まれていた。
咸豊帝の死後、清朝は「同治中興」と呼ばれる比較的平和な時期を迎えた。太平天国の乱やアヘン戦争が終結し、数十年間枯渇していた財政も回復し始めた。この時期、孝貞顕皇后が政治に介入した唯一の顕著な事例は、1869年の宦官安徳海事件であった。
4.4. 光緒帝時代の摂政

1875年1月、同治帝が18歳で崩御し、後継者がいなかったため、慈禧皇太后の甥である載湉が新たな皇帝として選ばれ、光緒帝として即位した。光緒帝も即位時にはまだ幼かったため、両皇太后は再び摂政となった。この時、孝貞顕皇后は鍾粋宮に、慈禧皇太后は長春宮に住居を移した。
1870年代後半には、慈禧皇太后が肝臓の病で体調を崩したため、孝貞顕皇后が単独で政務を執る時期があった。この間、彼女はロシア帝国とのイリ問題(ジュンガル蜂起後のイリ地方の占領と清朝による奪還、そして1881年のサンクトペテルブルク条約による解決)に対処しなければならなかった。
孝貞顕皇后は紫禁城を離れることは稀であったが、夫や先祖に敬意を表するため、清東陵の陵墓を訪れることはあった。1880年、清東陵滞在中、孝貞顕皇后は恭親王の勧めもあってか、全ての儀式において慈禧皇太后よりも上位に立ち、自らの権利を主張した。咸豊帝の陵墓では、孝貞顕皇后が中央に立ち、慈禧皇太后には右に立つよう命じ、咸豊帝が生きていた頃は慈禧が単なる側室であったことを改めて示唆した。左の空席は、咸豊帝の最初の正室であった孝徳顕皇后のために象徴的に空けられていた。この時の慈禧皇太后の反応は不明である。
5. 政治活動と主要な決定
皇太后として、孝貞顕皇后は清朝の重要な政治的決定や事件に介入し、その影響力を発揮した。特に、宦官安徳海事件における彼女の果断な行動は、その政治的手腕を示すものとして知られている。
5.1. 宦官安徳海事件


1869年、宦官の安徳海(安德海An Dehai中国語)は、慈禧皇太后の側近であり、彼女に気に入られていたことを笠に着て傲慢な振る舞いをしていた。同年7月、安徳海は慈禧皇太后の命により、同治帝の結婚式の衣装を調達するため南下した。しかし、清朝には「宦官は許可なく皇城を出てはならない」という厳格な法度があり、安徳海は正式な手続きを経ずに山東省を訪れ、その権威を濫用して人々に金銭を強要し、騒動を引き起こした。
山東巡撫の丁宝楨は安徳海の不法行為を朝廷に報告した。孝貞顕皇后はこの報告を受け、直ちに丁宝楨に対し、現地で安徳海を処刑するよう命じる詔勅を起草した。詔勅には、安徳海が許可なく北京を離れ、無法な行為を犯したことに対する驚きと、彼を厳しく処罰することで宮廷の綱紀を粛正し、悪行を戒める必要性が述べられていた。
安徳海は1869年9月12日に斬首された。この処刑は孝貞顕皇后としては異例の果断な行動であり、慈禧皇太后を大いに不快にさせたと言われている。一部の史料によれば、恭親王奕訢が孝貞顕皇后に独立した決定を下すよう促したともされる。この事件は、孝貞顕皇后が単に慈禧皇太后の言いなりではなかったことを示す重要なエピソードとして知られている。
5.2. 同治帝の婚姻と皇后選定

1872年、孝貞顕皇后と慈禧皇太后は、同治帝が結婚する時期が来たと判断した。紫禁城で最高位の女性である孝貞顕皇后は、同治帝の皇后と妃嬪を選定する責任を負った。最終的に、モンゴルのアルテ氏(後の孝哲毅皇后)の娘が新たな皇后となることが決定された。アルテ氏の母は孝貞顕皇后の父方の従姉妹であった。
この皇后選定の過程では、両皇太后の間で意見の対立があった。慈禧皇太后は、鳳秀の娘である富察氏を推していたが、同治帝は孝貞顕皇后が選んだアルテ氏を皇后に、富察氏を慧妃に選んだ。アルテ氏の母方の祖父は辛酉政変で処刑された鄭親王端華であり、慈禧皇太后はこれを嫌っていた。また、アルテ氏は孝貞顕皇后の親戚でもあったため、慈禧皇太后は介入する余地がなかった。同治帝が孝貞顕皇后とアルテ氏に親密であったことは、生母である慈禧皇太后に裏切りと屈辱を感じさせ、両皇太后間の確執を深める一因となった。
結婚後、両皇太后は共同摂政の職を辞したが、1874年12月の同治帝の病気中に摂政に復帰した。
5.3. 対外関係と政策
孝貞顕皇后は、政治への介入は控えめであったものの、清朝の対外関係や主要な政策決定において一定の役割を果たした。特に、1870年代後半に慈禧皇太后が病に伏した際には、彼女が単独で政務を執り、ロシア帝国とのイリ問題に対処した。
イリ問題は、1871年に新疆で発生したドンガン蜂起(同治回変)に乗じてロシアがイリ地方を占領したことに端を発する。清朝は1877年に新疆の支配権を取り戻したが、ロシアはイリ地方での強い存在感を維持しようとした。清朝政府は1879年にイリの返還を要求したが、ロシアはこれを拒否し、両国間の緊張が高まった。この紛争は、1881年2月にサンクトペテルブルク条約が締結されることで終結した。
また、孝貞顕皇后は、清朝の近代化を目指す「洋務運動」(自強運動)を支持したとされる。この運動は、西洋の技術や知識を導入し、軍事力や産業を強化しようとするものであった。孝貞顕皇后は恭親王奕訢や曾国藩といった改革派の指導者たちと共に、この運動を推進した。彼女は、漢民族の官僚を要職に任命することにも同意し、清朝の行政機構の改革にも関与した。両皇太后は、御史の意見を受け入れ、官僚の綱紀粛正や倹約の奨励、賞罰の厳格化などを実施した。
6. 私生活と人物像
孝貞顕皇后は、その温和な人柄と文学への深い関心で知られている。彼女の人間関係、特に同治帝や西太后との関係は、彼女の人物像を理解する上で重要な側面である。
6.1. 人柄と人間関係

孝貞顕皇后は、温和で慈愛に満ちた人柄で知られていた。彼女は常に落ち着いており、決して癇癪を起こすことはなく、誰に対しても親切に接したため、咸豊帝からも深く尊敬された。同治帝と光緒帝は、生母である慈禧皇太后よりも孝貞顕皇后に懐いていたと伝えられている。同治帝は、厳しく叱る慈禧皇太后とは対照的に、常に自分を庇ってくれる孝貞顕皇后を実の母親のように慕っていた。
慈禧皇太后が権力を掌握しようとする中で、孝貞顕皇后の善良で素直な性格は、彼女が慈禧皇太后に利用されたという見方も生んだ。しかし、両皇太后の関係は、必ずしも一方的なものではなかった。孝貞顕皇后は、安徳海事件のように、時には果断な意志を示すこともあった。
アメリカの画家キャサリン・カールは、慈禧皇太后と9ヶ月間を過ごしたが、孝貞顕皇后には会ったことがなかったものの、彼女を「文学皇后」と評している。カールによれば、慈禧皇太后が全ての国政を処理する一方で、孝貞顕皇后は文学的な追求に没頭し、学究的な生活を送っていたという。彼女は非常に優れた文学的才能を持ち、北京大学の最高文学栄誉を目指す者の論文を自ら審査することもあった。また、彼女自身も著名な作家であった。カールは、孝貞顕皇后と慈禧皇太后は友好的に共存し、互いの長所を認め合い、長きにわたる関係の中で真摯な愛情を育んでいたと述べている。この友好的な関係は、1881年の孝貞顕皇后の死によって終わりを告げた。
シンガポールの学者リム・ブーン・ケンは、孝貞顕皇后を旧約聖書のサラに例え、自身の不妊を補うために夫に妾を勧めたと指摘している。孝貞顕皇后は、懿貴妃が皇帝の息子と後継者の母となることに大きな関心を示した。慈禧皇太后は短気で、おそらく皇后に嫉妬していたが、同治帝が生まれる直前、その短気と傲慢さのために降格寸前になった際、孝貞顕皇后が彼女を弁護して介入した。この対照的な性格にもかかわらず、両者は長年にわたり友好的な関係を築いていたとされる。
6.2. 文学的関心
孝貞顕皇后は「文学皇后」として知られ、文学に深い関心を持っていた。彼女は文学的な追求に時間を費やし、学究的な生活を送っていた。その文学的才能は非常に高く、北京大学の最高文学栄誉を目指す者の論文を自ら審査することさえあった。彼女はまた、著名な作家でもあったと伝えられている。
7. 死と評価
孝貞顕皇后の突然の死は、清朝末期の宮廷に大きな衝撃を与え、その死因をめぐっては様々な憶測と論争が巻き起こった。彼女に対する歴史的評価もまた、その人物像と同様に多角的である。
7.1. 死
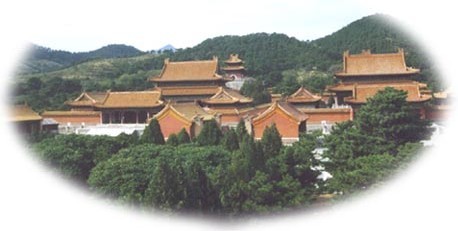
1881年4月8日(光緒7年旧暦3月10日)、孝貞顕皇后は朝廷の会議に出席中に体調を崩し、私室に運ばれた後、数時間以内に急死した。享年45歳。彼女の突然の死は多くの人々に衝撃を与えた。公式な死因は脳出血による突然の卒中とされている。光緒帝の教育係であった翁同龢の日記によれば、孝貞顕皇后は以前にも卒中と思われる重篤な病気を少なくとも3回経験していた。1863年3月には突然意識を失い、約1ヶ月間話すことができなくなったと記録されており、聴衆の前で「ゆっくりと、困難そうに話す」という彼女の評判は、この卒中の後遺症であった可能性がある。2度目の卒中は1870年1月に記録されている。
彼女の死から30年後、慈禧皇太后による毒殺説が広まり始めた。しかし、そのような主張はこれまで裏付けられておらず、新たな証拠も現れていない。さらに、慈禧皇太后自身も当時病気で公務を遂行できないほどであったため、孝貞顕皇后の死に関与した可能性は低いとされている。
最も広まった噂の一つは、咸豊帝が死の直前に秘密の詔勅を孝貞顕皇后に託し、慈禧皇太后が権力を掌握しようとした場合には、彼女を排除する権限を与えていたというものである。孝貞顕皇后は慈禧皇太后が自分を傷つけることはないだろうと信じ、その秘密の詔勅を慈禧皇太后に見せ、共同摂政に対する信頼を示すためにそれを焼却した。しかし、その日のうちに彼女は謎の死を遂げたという。また、慈禧皇太后から贈られた揚げミルクパンを食べた直後に倒れたという話も存在する。
7.2. 諡号と陵墓
孝貞顕皇后に贈られた諡号は、生前の尊号と死後に加えられた新たな諡号を合わせたもので、「孝貞慈安裕慶和敬誠靖儀天祚聖顕皇后」(孝貞慈安裕慶和敬誠靖儀天祚聖顯皇后Xiàozhēn Cí'ān Yùqìng Héjìng Chéngjìng Yītiān Zuòshèng Xiǎn Huánghòu中国語)である。略称は「孝貞顕皇后」(孝貞顯皇后Xiàozhēnxiǎn Huánghòu中国語)である。この長い諡号は、現在も彼女の陵墓で見ることができる。
孝貞顕皇后は、北京の東約125 kmに位置する清東陵に埋葬された。彼女は夫である咸豊帝の定陵の隣に埋葬されることは許されず、慈禧皇太后と共に定東陵の墓域に埋葬された。具体的には、孝貞顕皇后は普祥峪定東陵(普祥峪定東陵Pǔxiángyù Dìngdōnglíng中国語)に、慈禧皇太后はより大規模な菩陀峪定東陵(菩陀峪定東陵Pútúoyù Dìngdōnglíng中国語)に埋葬されている。
7.3. 歴史的評価
孝貞顕皇后に対する大衆的な評価は、彼女が非常に尊敬される人物であり、常に穏やかで、決して短気ではなく、全ての人に親切に接したというものである。咸豊帝、同治帝、光緒帝のいずれもが慈禧皇太后よりも彼女を好んだとされる。彼女の善良な性格は、素朴で率直な孝貞顕皇后を脇に追いやった慈禧皇太后には及ばなかったという見方が中国では今もなお一般的である。この穏やかな孝貞顕皇后のイメージは、彼女の尊号の意味に由来しているのかもしれない。
しかし、一部の歴史家は異なる見解を示している。彼らは、孝貞顕皇后が自己中心的で怠惰であり、国政や勤勉さよりも紫禁城での享楽的な生活を好んだと主張する。対照的に、慈禧皇太后は抜け目がなく聡明で、最高権力を得るために犠牲を払い、当時の中国を悩ませていた複雑な問題に立ち向かったとされる。現実には、この二つの極端な評価の中間に真実がある可能性があり、孝貞顕皇后もまた気質や意志の強さを示したと主張する者もいる。孝貞顕皇后が善良で単純な女性であるという一般的な見方は、改革派の康有為や伝記作家のジョン・ブランド、エドモンド・バックハウスによって、彼女と慈禧皇太后との対比を強調するために誇張されたものである。慈禧皇太后が1900年以降多くの外国人と会見したのに対し、孝貞顕皇后と外国人の会見記録は存在しない。
7.4. 肯定的な評価
孝貞顕皇后は、その温和な人柄と慈愛に満ちた性格で肯定的に評価されている。同治帝との良好な関係は、彼女の人間的な魅力の証とされた。政治への介入は控えめであったが、宦官安徳海事件における彼女の果断な決断は、その影響力と正義感を高く評価される一因となった。また、彼女が洋務運動を支持し、漢民族の官僚を要職に登用したことは、清朝の近代化と安定に貢献した側面として肯定的に捉えられている。
7.5. 批判と論争
一方で、孝貞顕皇后に対する批判的な見方や論争も存在する。彼女の政治への消極性や、私的な享楽への傾倒が指摘されることもある。また、彼女が慈禧皇太后の権力確立のために利用されたとする見解もある。最も大きな論争は、彼女の突然の死をめぐる毒殺説である。この説は、咸豊帝が慈禧皇太后を排除する秘密の詔勅を孝貞顕皇后に託したが、孝貞顕皇后が慈禧皇太后を信じてそれを焼却した後に毒殺されたというものである。この物語は、民間の物語や一部の歴史書に記され、清朝末期における最も有名な未解決事件の一つとなっている。しかし、これらの説の多くは、文学作品や政治的な動機による慈禧皇太后への誹謗中傷に影響されたものであり、確固たる証拠に裏付けられたものではないという批判も存在する。
8. 大衆文化において
孝貞顕皇后は、その生涯と西太后との関係から、多くの映画やテレビドラマで描かれている。
| 年 | 映画/ドラマ名 | 演者 |
|---|---|---|
| 1964 | 西太后と珍妃 (西太后與珍妃) | 林静 |
| 1981 | 双印伝奇 (雙印傳奇) | 尹宝蓮 |
| 1983 | 火焼円明園 (火燒圓明園) | 陳燁 |
| 1983 | 垂簾聴政 (垂簾聽政) | |
| 1983 | 少女慈禧 (少女慈禧) | 麦翠嫻 |
| 1986 | 慈禧外伝 (慈禧外傳) | 尹宝蓮 |
| 1987 | 両宮皇太后 (兩宮皇太后) | 劉冬 |
| 1989 | 一代妖后 (一代妖后) | 陳燁 |
| 1990 | 清宮十三皇朝 (滿清十三皇朝之血染紫禁城) | 森森 |
| 1993 | 戯説慈禧 (戲說慈禧) | 何晴 |
| 2005 | 咸豊王朝之一簾幽夢 (咸豐王朝之一簾幽夢) | 高丹丹 |
| 2005 | 一生為奴 (一生为奴) | 宋佳 |
| 2012 | 女人花 (女人花) | 林韦君 |
| 2012 | 紅墻緑瓦 (红墙绿瓦) | 陳莉娜 |
| 2012 | 大太監 (大太監) | 邵美琪、梁麗瑩 |
| 2015 | 瀛寰之志 (瀛寰之志) | 秦丽 |