1. 生涯と背景
蘇轍は、学問と政治の道に進むための強固な基盤を、その出生と教育の中で築き上げた。
1.1. 出生と家族
蘇轍は宝元2年2月26日にあたる1039年3月23日、眉州眉山県(現在の四川省眉山市東坡区)で生まれた。父は著名な文人である蘇洵、兄は彼より3歳年上の蘇軾である。彼ら「三蘇」は、中国文学史において傑出した存在として知られ、後世に多大な影響を与えた。蘇氏一家がかつて住んでいた場所は、1984年に「三蘇祠博物館」として再建され、現在では有名な文化観光名所の一つとなっている。
1.2. 教育と科挙
蘇轍は幼少期から父の蘇洵に学び、また劉純(字は輝之)にも師事した。彼は17歳で結婚し、1057年(嘉祐2年)、18歳(または19歳)の時に兄の蘇軾と共に科挙の進士試験に合格し、官僚への道を歩み始めた。この進士の学位は、高位の官職に就くための必須条件であった。さらに1061年には制科にも合格したが、父の蘇洵を養うことを理由に、すぐには官職に就かず、兄の蘇軾が任地から戻ってきてから初めて大名府推官となった。
2. 政治的経歴
蘇轍の政治的経歴は、その卓越した才能と、当時の政治的変動、特に新法と旧法の対立の中で、波乱に満ちたものであった。
2.1. 初期の官職
科挙合格後、蘇轍は商州軍事推官に任命された。その後、神宗の時代には三司條例司の属官を務めた。この時期、彼は地方官としての経験を積み、社会の実情に触れる中で、後の政治的見解の基礎を形成していった。
2.2. 新法への反対と左遷
1070年、王安石が宰相となり、一連の「新法」(変法)を施行すると、蘇轍はこれに強く反対した。彼は皇帝に上書し、法制度の根本的な変更は賢明ではないと主張した。また、王安石に対しても直接書簡を送り、新法を批判した。彼は、新法が民衆に与える影響、特に貧困層への負担増大に深い懸念を抱き、社会正義の観点からその不適合性を訴えた。
皇帝は彼を召して議論させた後、改革への参加を命じたが、蘇轍は新法の多くの側面が不適切であると感じ、再び上書して新法を公然と攻撃した。これにより、新法派の首領である王安石の怒りを買ったが、陳昇之の弁護により罪を免れた。しかし、河南推官に転出させられ、その後も斉州掌書記、著作佐郎と職を転々とした。
1079年には、兄の蘇軾が詩の中で朝廷を批判したとして投獄される「烏台詩案」に連座した。蘇轍は兄を深く尊敬し、兄弟の絆も強かったため、兄を救うべく自らの官職と引き換えに兄の釈放を願い出た。しかし、この嘆願は聞き入れられず、彼自身もこの事件に巻き込まれ、筠州塩酒税監、績渓知県へと左遷された。この一連の左遷は、彼の政治的信念と民衆への関心が、当時の権力構造といかに衝突したかを示すものであった。
2.3. 復帰と後期の官職
哲宗が即位すると、旧法党が勢力を盛り返し、蘇轍は朝廷に召還された。彼は秘書省校書郎に任じられ、その後、右司諫、起居郎、中書舎人、戸部侍郎と昇進した。1089年には翰林学士となり、権吏部尚書、御史中丞、尚書右丞を歴任し、最終的には門下侍郎という要職にまで昇り詰めた。この時期、彼は趙君錫と共に遼への使節も務めた。
しかし、哲宗が再び新法を支持するようになると、蘇轍は1094年に再び上書してこれを諌めたため、帝の意に反し、汝州知州に左遷された。その後も袁州知州、南京、筠州、化州別駕、雷州、循州、永州、岳州と地方への転任が続き、政治的な浮沈を繰り返した。徽宗の時代になっても地方回りは続いたが、後に大中大夫に復帰し、提挙鳳翔上清・太平宮として許州に移った。
2.4. 隠棲と晩年
崇寧年間(1102年 - 1106年)、蘇轍は62歳で官職を辞し、ついに政治の世界から身を引いた。彼は許州(現在の河南省)に室を築き、自らを「潁浜遺老」と称して隠遁生活を送った。社会との交流を絶ち、終日黙座して経書や歴史書、諸子百家の研究に没頭すること10年。この時期は、彼の学問的探求と精神的な充実の時であった。彼はこの地で平穏な晩年を過ごし、1112年に73歳でその生涯を閉じた。
3. 文学的業績と思想
蘇轍の文学は、その政治的見解や哲学と深く結びついており、彼の思想的基盤が作品に色濃く反映されている。
3.1. 文学的特徴と主要著作
蘇轍は散文、詩、詞、賦など多岐にわたる文学形式に秀でていた。彼の散文は特に政治評論や歴史評論に優れ、その文体は「鷹揚淡泊にして、沈静簡潔」と評される。彼は社会の主要な問題を見抜き、歴史上の経験から解決策を見出そうと試みた愛国的な作家であった。
彼の代表的な著作には、以下のものがある。
- 『欒城集』(らんじょうしゅう):彼の文集であり、政治評論や歴史評論が多数収められている。
- 『応詔集』(おうしょうしゅう):皇帝の詔に応えて書かれた文章を集めたもの。
- 『六国論』(りっこくろん):父の蘇洵と同じ題名で書かれた歴史評論。
- 『三国論』(さんごくろん):劉備と劉邦を比較し、劉備は知恵と勇気に欠けていたと論じている。
- 『新論』(しんろん):当時の社会情勢について「今日の天下の事、治まるも安きに至らず、乱るるも危きに至らず、紀綱粗立するも挙がらず、急変無くして緩病有り」と述べ、統治の不徹底が社会問題を引き起こすと指摘した。
- 『春秋集解』(しゅんじゅうしゅうかい)
- 『詩集伝』(ししゅうでん):『詩経』の研究に重要な革新をもたらした。
- 『論語拾遺』(ろんごしゅうい)
- 『孟子解』(もうしげ)
- 『古史』(こし)
- 『龍川略志』(りゅうせんりゃくし)
- 『別志』(べつし)
- 『道徳経解』(どうとくきょうかい)
彼の散文のスタイルは、その人生の時期によって変化したと分析されている。政治に携わる以前の文章は、『六国論』のように鋭く、『三国論』のように生き生きとしていた。地方官として働くようになると、評論的な要素から情熱を表現する方向へと変化し、構造へのこだわりが薄れた。この時期、彼の情熱は内面に秘められ、風景や人物を鮮やかに描写することができた。朝廷に戻ってからは、政治改革の提言を主とする実用的な文章が多くなった。晩年には、読書と経験に基づいた思索が文章の主軸となった。
詩作においては、兄の蘇軾には及ばないものの、鷹揚淡泊で沈静簡潔な人柄が表れていると評される。また、書にも長けていた。
3.2. 思想的影響
蘇轍の思想的・哲学的背景は、儒教に深く根ざしており、特に孟子を深く尊敬していた。彼は孟子の思想を自身の世界観や政治的見解の形成において重要な基盤とした。また、彼は多くの異なる思想家からも学び、当時の社会が抱える主要な問題を見抜き、先人たちの経験から解決策を見出そうと試みた。この姿勢は、蘇轍が愛国的な作家であったことを示している。彼の作品は、社会の動揺の最も重要な原因が、民衆が長期間にわたって貧困にあえでいることにあると指摘するなど、当時の社会状況を批判することを目的としていた。彼は「皇帝への書簡」の中で、「今日の世の患いは、財が乏しいことに急ぐものはない」(今世之患,莫急于無財こんせいのうれい、ざいなきにきゅうするものなし中国語)と述べている。
3.3. 文学理論(気論)
蘇轍は文学創作において「気(き)」の重要性を説いた。彼は「文とは、気の形する所なり。然るに文は学ぶべからずして能くすべし、気は養うべし而して致すべし」(文は気の現れである。しかし文は学んで習得できるものではなく、気は養うことで得られる)と述べた。彼の見解では、気こそが偉大な作品を生み出す鍵であり、それは内面の涵養だけでなく、可能な限り多くの経験を積むことによっても高められるとされた。
4. 評価と遺産
蘇轍は、その生涯と業績を通じて、中国文学史および政治史に重要な足跡を残した。
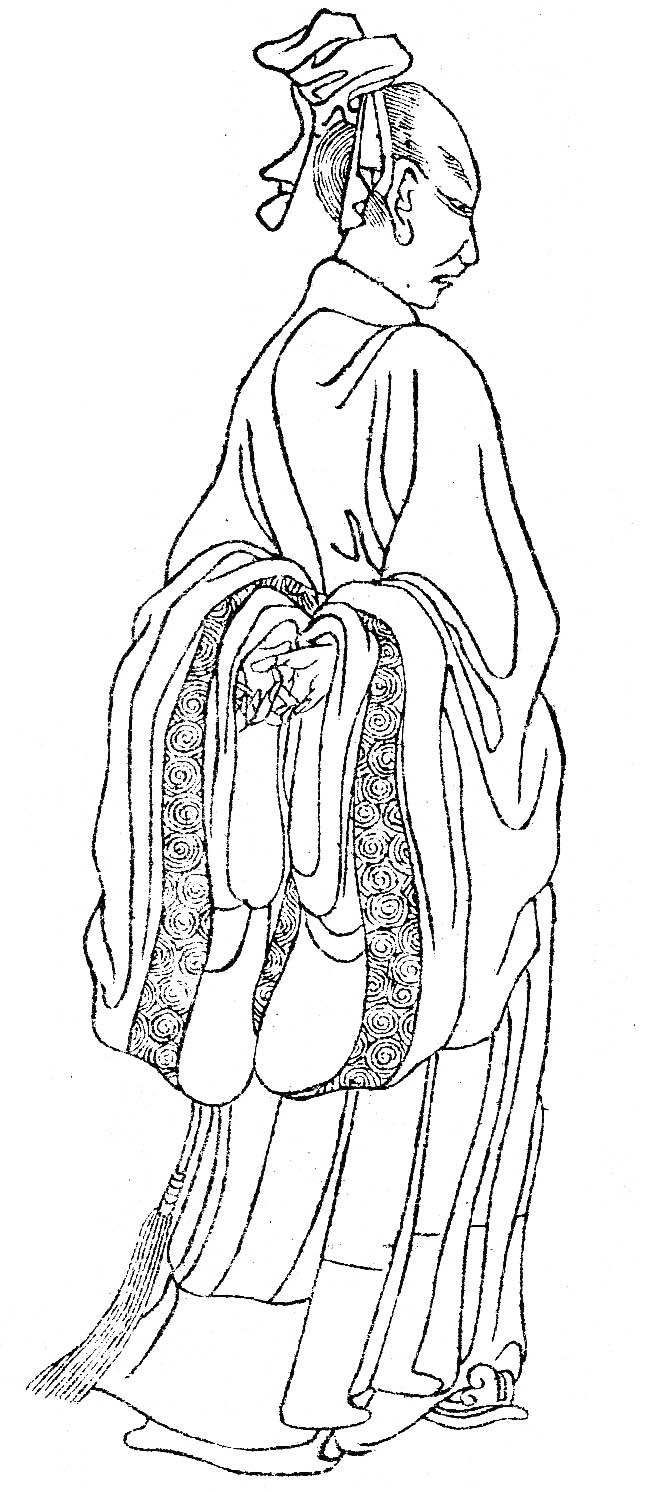
4.1. 唐宋八大家としての地位
蘇轍は、父の蘇洵、兄の蘇軾と共に「唐宋八大家」の一人に数えられ、中国文学史において確固たる地位を確立している。彼らの散文は、その後の文学に大きな影響を与え、宋代散文の規範とされた。特に、政治評論や歴史評論における彼の卓越した才能は、宋代において特別な地位を築いた。
4.2. 後世の評価と影響
蘇轍の文学作品、政治的立場、そして思想は、後世の歴史家や社会から高く評価されている。彼の散文は、兄の蘇軾の才能と比較されることもあったが、蘇軾自身が蘇轍の散文の達成が尽きることがないと評したように、その深遠さと広がりは高く評価された。特に『春秋集解』や『詩集伝』は、『詩経』の研究に重要な革新をもたらした。
彼はまた、公正を愛し、常に他者の意見を尊重する人物として知られていた。彼の作品には仏教の影響が色濃く見られるものもある。南宋の淳熙年間には「文定」と諡された。また、現代中国の著名な随筆家・小説家である蘇雪林は彼の末裔の一人である。
5. 私生活
蘇轍は17歳で結婚した。彼は兄の蘇軾を深く慕っており、その人生において兄に関する多くの作品を残した。特に、兄が亡くなった際には、その遺骸を葬るために長文の墓誌銘「亡兄子瞻端明墓誌銘」を執筆し、兄弟の深い絆と蘇轍の兄への敬愛の念を示している。
6. 死去
蘇轍は政和2年10月3日にあたる1112年10月25日に死去した。享年73歳(数え年で74歳)。彼の死後、端明殿学士(たんめいでんがくし)を追贈され、その功績が称えられた。