1. 生涯初期と即位
エグバートの出自については歴史家の間で議論がありますが、若くしてフランク王国への亡命を余儀なくされ、その後ウェセックスの王位に就くという波乱に満ちた経緯を辿りました。
1.1. 家族と血統
エグバートの血統については、歴史家の間で意見が分かれています。『アングロサクソン年代記』の初期の写本であるパーカー年代記は、彼の息子のエゼルウルフの系譜を、エグバート、ケント王のエルムンド、そして詳細不明のエアファとエオッパを経て、726年に退位したウェセックス王イネの兄弟であるイングギルドにまで遡らせています。さらに、ウェセックス王家の創始者であるチェルディッチにまで繋がると記されています。歴史家のフランク・ステントンはイングギルドからの系譜は受け入れたものの、それ以前のチェルディッチへの系譜には懐疑的でした。ヘザー・エドワーズはエグバートがケント出身であり、ウェセックスの血統は彼の統治の正当性を与えるために捏造された可能性を指摘しています。これに対し、ロリー・ネイスミスはケント出身である可能性は低いとし、エグバートは「立派なウェセックス王室の出身であった可能性が高い」と述べています。
エグバートの妻の名前は不明です。15世紀の年代記には、彼女がレドブルガという名で、エグバートがフランク王国に亡命中に結婚したカール大帝の親戚であるとされていますが、その記録が後世のものであるため、現代の歴史家たちはこの説を退けています。彼らの間で知られている唯一の子供はエゼルウルフです。
また、エグバートにはウィルトン修道院の創設者として後に聖人となった異母妹アルブルガがいたとされています。彼女はウィルトシャーのエアルドルマンであったウルフスタンと結婚し、802年にウルフスタンが死去すると尼僧となり、ウィルトン修道院の女子修道院長となりました。
1.2. 政治的背景と亡命
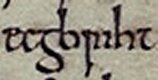
8世紀後半のアングロサクソン・イングランドでは、757年から796年まで在位したマーシア王オファが支配的な勢力でした。757年から786年までウェセックス王であったキュネウルフとオファの関係は十分に記録されていませんが、キュネウルフはマーシアの宗主権からある程度の独立を維持していた可能性が高いです。772年のオファの勅許状にはキュネウルフが「西サクソン人の王」として署名しており、779年にはオファによってベンジントンの戦いで敗れていますが、キュネウルフがオファを宗主と認めたことを示唆する証拠はありません。
オファは南東部で影響力を行使しており、764年の勅許状では彼がケントのヘアベオルトと共にいることが示されており、オファの影響がヘアベオルトの即位を助けたと考えられています。770年代にはケントをエグバート2世という別のエグバートが統治しており、彼が最後に言及されるのは779年の勅許状です。784年にケントの新王エルムンドが『アングロサクソン年代記』に登場します。年代記の欄外には「この王エルムンドはエグバート(ウェセックス王のエグバート)の父であり、エグバートはエゼルウルフの父であった」と記されています。
エルムンドが長く権力を維持した記録はなく、784年以降の彼の活動に関する記録はありません。しかし、780年代後半にはオファがケントを支配していた広範な証拠があり、その目的は宗主権を超えて王国の完全な併合にあったとされています。おそらく若きエグバートは785年頃にウェセックスへ逃亡したと考えられます。後の年代記の記述で、キュネウルフの後継者であるベオルトリッチがエグバートを追放する際にオファを助けたとあることは示唆的です。
キュネウルフは786年に殺害され、彼の後継を巡ってエグバートが王位を要求しましたが、ベオルトリッチに敗れました。おそらくオファの支援があったと考えられます。『アングロサクソン年代記』は、エグバートが王となる前にベオルトリッチとオファによって追放され、フランク王国で3年間過ごしたと記録しています。「iii」(3)と記されていますが、これは写字生のエラーで、「xiii」(13)年であった可能性が指摘されています。ベオルトリッチの治世は16年間続いたため、多くの現代の記述ではエグバートが実際にフランク王国で13年間過ごしたと仮定しています。しかし、年代記のすべての写本で「iii」と一致していることから、この仮定に異議を唱える歴史家もいます。いずれにせよ、エグバートはおそらく789年に、競争相手であったベオルトリッチがマーシア王オファの娘と結婚した際に追放されたとされています。
エグバートが亡命していた当時、フランク王国はカール大帝によって統治されており、カール大帝はノーサンブリアに対するフランクの影響力を維持し、南部のオファの敵を支援していたことが知られています。この時期、ガリアにはエアドバートという聖職者も亡命しており、彼は後にケント王となった人物とほぼ確実に同一人物です。後の年代記編者マルムズベリーのウィリアムによれば、エグバートはガリアでの滞在中に統治の術を学んだとされています。
1.3. ウェセックス王国の即位
ベオルトリッチのマーシアへの従属は、オファの死から数ヶ月後にマーシア王となったケンウルフの治世まで続きました。ベオルトリッチは802年に死去し、エグバートはウェセックスの王位に就きました。おそらくカール大帝、そしておそらく教皇庁の支援があったと考えられます。
マーシア人はエグバートに反抗し続けました。エグバートの即位の日、フイッキ(元々は独立した王国でしたが、当時はマーシアの一部でした)がエアルドルマンのエゼルムンドの指揮の下、攻撃を仕掛けました。ウェセックスのエアルドルマン、ウェオフスタンはウィルトシャーの兵を率いてこれに応戦しました。15世紀の史料によれば、ウェオフスタンはエグバートの妹アルブルガと結婚しており、義兄弟の関係でした。フイッキは敗れましたが、ウェオフスタンとエゼルムンドの両名が戦死しました。この戦いから20年以上、エグバートとマーシアの関係についてはそれ以上の記録はありません。エグバートは自国の境界外には影響力を持たなかったようですが、一方で彼がケンウルフの宗主権に服したという証拠もありません。ケンウルフはイングランド南部の他の地域を支配していましたが、ケンウルフの勅許状には「南部イングランドの宗主」という称号は一度も現れず、これはおそらくウェセックス王国の独立の結果だと考えられています。
2. 勢力拡大と覇権確立
エグバートの治世において、ウェセックス王国は領土を拡大し、アングロサクソン・イングランド内で支配的な地位を確立していきました。
2.1. ウェセックス初期統治
815年、『アングロサクソン年代記』は、エグバートが残るブリテン人王国であるドゥムノニア(年代記編者には西ウェールズとして知られ、現在のコーンウォールにほぼ相当する領土でした)の全域を荒廃させたと記録しています。10年後の825年8月19日付の勅許状は、エグバートが再びドゥムノニアで遠征を行っていたことを示しており、これは823年にガウフルフォードの戦いでデヴォン人とコーンウォールのブリテン人との間で記録された戦いと関連している可能性があります。
2.2. エランドゥンの戦いと南東部征服
825年にはアングロサクソン史において最も重要な戦いの一つであるエランドゥンの戦いが起こり、エグバートはマーシア王ベオルンウルフを破りました。この戦いはマーシアによるイングランド南部支配の終わりを告げるものでした。年代記はエグバートが勝利をどのように追求したかを記しています。「その後、彼は息子エゼルウルフと司教エアハルスタン、エアルドルマンのウルフヘアルドを大部隊と共にケントへ送った。」エゼルウルフはケント王のボールドレッドをテムズ川の北へ追いやりました。年代記によれば、ケント、エセックス、サリー、サセックスの人々は皆エゼルウルフに臣従しました。「なぜなら彼らは以前、彼の親族から不当に引き離されていたからである」とあります。これは、エグバートの父エルムンドが王位に就いた頃のオファによるケントへの介入を指している可能性があり、もしそうであれば、年代記編者のこの記述はエルムンドがイングランド南東部の他の地域とも関係を持っていたことを示している可能性があります。
年代記の記述では、ボールドレッドが戦いの直後に追放されたように見えますが、実際はそうではなかった可能性があります。ケントに残る文書によれば、826年3月の日付がベオルンウルフの治世の3年目とされており、ベオルンウルフがこの時点でもケントに権威を持っていたことを示唆しています。したがって、ボールドレッドは依然として権力を握っていたと考えられます。エセックスでは、エグバートは王シゲレドを追放しましたが、その日付は不明です。これは829年まで遅れた可能性があり、後の年代記編者はこの追放をその年のマーシアに対するエグバートの遠征と結びつけています。
『アングロサクソン年代記』はエランドゥンでどちらが攻撃側だったか述べていませんが、ある近年の歴史書はベオルンウルフが攻撃した可能性が非常に高いと主張しています。この見方によれば、ベオルンウルフは825年夏のエグバートのドゥムノニア遠征を利用した可能性があります。ベオルンウルフが攻撃を開始した動機は、南東部での動揺や不安定化の脅威であったと考えられます。ケントとの王朝的なつながりがウェセックスをマーシアの支配にとって脅威としました。
エランドゥンの戦いの結果は、南東部におけるマーシアの権力の即時喪失に留まりませんでした。年代記によれば、825年にイーストアングリア人がマーシア人からの保護をエグバートに求めましたが、実際にこの要請があったのは翌年である可能性もあります。826年、ベオルンウルフはイーストアングリアに侵攻しましたが、おそらく宗主権を回復するためであったとみられますが、彼は殺害されました。彼の後継者であるルデカも827年に同じ理由でイーストアングリアに侵攻しましたが、やはり殺害されました。マーシアはケントからの支援を期待していた可能性もあります。カンタベリー大司教のウルフレドが西サクソン人の支配に不満を抱いていた可能性も示唆されています。というのも、エグバートはウルフレドの通貨発行権を停止し、ロチェスターとカンタベリーで独自の貨幣を鋳造し始めており、エグバートがカンタベリーに属する財産を押収したことも知られています。イーストアングリアでの結果はマーシアにとって壊滅的であり、南東部におけるウェセックスの権力を確固たるものにしました。
2.3. マーシア征服とブレトワルダの称号
829年、エグバートはマーシアに侵攻し、マーシア王ウィグラフを追放しました。この勝利により、エグバートはロンドン造幣所を支配し、マーシア王として貨幣を発行しました。この勝利の後、西サクソン人の写字生は『アングロサクソン年代記』の有名な一節で彼を「ブレトワルダ」(広域統治者、あるいは「ブリテン支配者」)と記しました。年代記のC写本における関連部分は以下の通りです。
「同年、エグバート王はマーシア王国とハンバー川以南の全てを征服し、彼はブレトワルダとなった8番目の王であった。」

ブレトワルダとして年代記に挙げられている以前の7人の王は、ベーダが『イングランド教会史』で「インペリウム」(支配権)を保持したとして挙げている7人と同じ名前であり、サセックスのエラから始まり、ノーサンブリアのオスウィで終わっています。このリストは不完全であるとよく考えられており、ペンダやオファといった支配的なマーシア王が省略されています。この称号の正確な意味については多くの議論があり、「賛辞の詩的表現」と評されることもありますが、明確な軍事指導者の役割を意味するという証拠もあります。
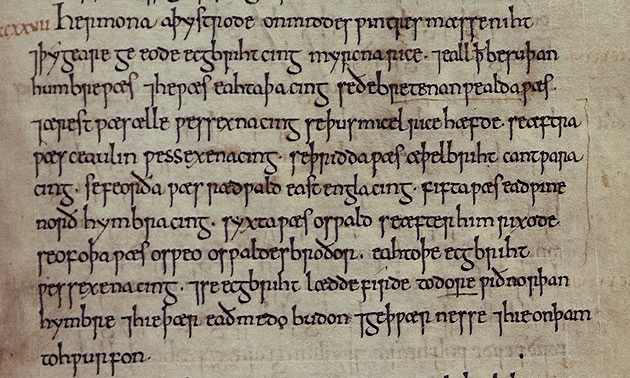
2.4. ノーサンブリア服属とウェールズ遠征
829年の後半、『アングロサクソン年代記』によれば、エグバートはシェフィールド郊外のドアでノーサンブリア人の服属を受け入れました。当時のノーサンブリア王はおそらくエアヌレドでした。後の年代記編者であるロジャー・オブ・ウェンドーヴァーによれば、エグバートはエアヌレドが服従する前にノーサンブリアに侵攻し、略奪しました。「エグバートが全ての南部の王国を獲得した後、彼は大軍をノーサンブリアに率い、その地方を激しい略奪で荒廃させ、エアヌレド王に貢物を支払わせた。」ロジャー・オブ・ウェンドーヴァーはノーサンブリアの年代記を彼の版に組み込んだことが知られています。年代記にはこれらの出来事は記載されていませんが、エアヌレドの服属の性質については疑問が呈されており、ある歴史家はドアでの会談が主権の相互認識を表していた可能性が高いと示唆しています。
830年、エグバートはウェールズに対して成功裏の遠征を行いました。これはほぼ間違いなく、以前マーシアの勢力圏内にあったウェールズの地へのウェセックスの影響力を拡大することを意図したものでした。この出来事はエグバートの影響力の頂点を記すものでした。
q=Wessex, England|position=right
3. 危機と支配力の減少
エグバートの統治後期には困難が生じ、特にマーシアの再独立とヴァイキングとの衝突がウェセックスの支配力に影響を与えました。
3.1. マーシアの独立再確保
830年、マーシアはウィグラフの下で独立を回復しました。『年代記』は単にウィグラフが「再びマーシア王国を獲得した」と述べていますが、最も有力な説明はこれがウェセックスの支配に対するマーシアの反乱の結果であったというものです。
エグバートのイングランド南部に対する支配は、ウィグラフの権力回復によって終わりを告げました。ウィグラフの復帰の後には、ウェセックスからの独立を示す証拠が続いています。勅許状は、ウィグラフがミドルセックスとバークシャーで権威を持っていたことを示しており、836年の勅許状では、ウィグラフが「私の司教、公爵、治安官」という言葉を使って、ウェセックス領内の司教座の司教を含むカンタベリー管区の11人の司教を含む集団を表現しています。ウィグラフがこのような notable な人物の集団を招集できたことは重要であり、ウェセックス人は、たとえそれが可能であったとしても、そのような評議会を開催しませんでした。ウィグラフはまた、王位を回復した後の数年間にエセックスを再びマーシアの勢力圏に戻した可能性もあります。イーストアングリアでは、エアルスタン王がおそらく827年、あるいはウィグラフがマーシアで権力を回復し、エグバートの影響力が減少した後の830年頃に貨幣を鋳造しました。イーストアングリア側によるこの独立の表明は驚くべきことではありません。なぜなら、ベオルンウルフとルデカの両方を打ち破り殺害したのはエアルスタンであった可能性が高いからです。
820年代後半のウェセックスの急激な権力上昇と、その後の支配的地位の維持の失敗は、歴史家によってその根本原因が探求されてきました。これらの出来事の説得力のある説明の一つは、ウェセックスの運命がカロリング朝の支援に多かれ少なかれ依存していたというものです。フランク人は808年にノーサンブリアの王位を回復したエアードウルフを支援したため、彼らが802年のエグバートの即位も支援した可能性は十分にあります。839年の復活祭、エグバートの死の少し前、彼はフランク王ルートヴィヒ敬虔帝と連絡を取り、ローマへの安全な通過を手配していました。したがって、フランク人との継続的な関係は、9世紀前半のイングランド南部政治の一部であったと考えられます。
カロリング朝の支援は、エグバートが820年代後半に軍事的成功を収めるのに役立った要因の一つであったかもしれません。しかし、ラインラントとフランクの商業ネットワークは820年代か830年代のある時期に崩壊し、さらに830年2月にはルートヴィヒ敬虔帝に対する反乱が勃発しました。これは830年代以降も続く一連の内部紛争の最初のものでした。これらの混乱はルートヴィヒがエグバートを支援するのを妨げた可能性があります。この見方では、フランクの影響力の撤退は、イーストアングリア、マーシア、ウェセックスが外部の援助に依存しない勢力均衡を見出すことになったでしょう。
支配力の喪失にもかかわらず、エグバートの軍事的成功はアングロサクソン・イングランドの政治情勢を根本的に変えました。ウェセックスはエセックスを除いて南東部の王国を支配し続け、マーシアはイーストアングリアの支配を回復しませんでした。エグバートの勝利は、ケント王国とサセックス王国の独立した存在の終焉を告げるものでした。征服された領土はしばらくの間、サリーと場合によってはエセックスを含む属王国として統治されました。エゼルウルフはエグバートの下の属王でしたが、彼が自身の王室を維持し、王国中を巡行していたことは明らかです。ケントで発行された勅許状では、エグバートとエゼルウルフが「西サクソン人とケントの人々の王」と記述されています。エゼルウルフが858年に死去した際、彼の遺言ではウェセックスをある息子に、南東部王国を別の息子に残しており、王国が完全に統合されたのは858年以降であったことが明らかになっています。しかし、マーシアは依然として脅威であり、ケント王に任命されたエグバートの息子エゼルウルフは、マーシアがそこで依然として持つ可能性のある影響力に対抗するため、カンタベリーのクライストチャーチに領地を与えました。
3.2. ヴァイキングおよびコーンウォール地域との衝突
836年、エグバートはカーハンプトンでデーン人に敗れましたが、838年にはコーンウォールのヒングストン・ダウンの戦いで彼らと西ウェールズ(ドゥムノニア)の連合軍を破りました。この後もドゥムノニアの王統は続きましたが、この時点で最後のブリテン人王国の一つであったドゥムノニアの独立は終わったと見なすことができます。アングロサクソン人によるコーンウォールへの拡大の詳細は記録が貧弱ですが、地名からいくつかの証拠が得られます。ローンセストン近くのテイマー川に東流するオッタリー川は境界となっていたようです。オッタリー川の南では地名が圧倒的にコーンウォール語の影響を受けているのに対し、北では新たに流入してきたイングランド人の影響が強く見られます。
8世紀末から、ヴァイキングからの襲撃はイングランドに恐怖をもたらし始めました。836年にはカーハンプトンの戦いでデーン人に敗れたエグバートでしたが、838年のヒングストン・ダウンの戦いではヴァイキングと西ウェールズの連合軍を破り、ウェセックスの防衛力を示しました。しかし、ヴァイキングの脅威は彼の死後も続くことになります。
4. 継承と死
エグバートはウェセックス王国の継続的な安定を確保するため、自身の王位継承の準備を着実に行い、息子エゼルウルフへの円滑な移行を実現しました。
4.1. 王位継承の準備
838年、キングストン・アポン・テムズで開催された評議会において、エグバートとエゼルウルフはウィンチェスターとカンタベリーの司教座に土地を寄進し、その見返りとしてエゼルウルフの王位継承に対する支持を約束させました。カンタベリー大司教チェオルノスもまた、エグバートとエゼルウルフをチェオルノスの支配下にある修道院の領主および保護者として受け入れました。これらの合意と、後にエゼルウルフが教会の特権を認めた勅許状は、教会がウェセックスを対処すべき新しい政治勢力として認識したことを示唆しています。聖職者は戴冠式で王を聖別し、王の相続人を指定する遺言の作成を助けました。彼らの支援は、ウェセックスの支配を確立し、エグバートの血統による円滑な継承を保証する上で実質的な価値を持っていました。キングストン評議会の記録と、その年の別の勅許状には、まったく同じ文言が含まれています。それは、寄進の条件が「私たち自身と私たちの相続人は、今後常にチェオルノス大司教とそのクライストチャーチの信徒から堅固で揺るぎない友情を得るものとする」というものでした。
他に王位継承を主張する者がいたかどうかは不明ですが、チェルディッチ(ウェセックスの全王の祖先とされる人物)の子孫で王国を争う可能性のある者が他にもいた可能性は十分にあります。
4.2. 死と埋葬
エグバートは839年に死去しました。孫のアルフレッド大王の遺言に残された彼の遺言の記述によれば、彼は土地を家族の男性成員にのみ残し、結婚によって王室から財産が失われることがないようにしました。エグバートが征服によって獲得した富は、彼が南東部の教会組織の支持を得ることができた理由の一つであったことは間違いありません。彼の遺言の倹約ぶりは、彼が王にとって個人の富の重要性を理解していたことを示しています。ウェセックスの王権は王家の異なる系統間で頻繁に争われてきましたが、エグバートがエゼルウルフの円滑な継承を確保できたことは注目すべき業績です。さらに、エゼルウルフがエグバートの南東部での征服によって形成された属王国で王権を経験したことは、彼が王位に就いたときに貴重なものとなったでしょう。

エグバートはウィンチェスターに埋葬され、彼の息子エゼルウルフ、孫アルフレッド大王、曾孫エドワード長兄王も同様に埋葬されました。9世紀にはウィンチェスターは都市化の兆候を示し始め、一連の埋葬はウィンチェスターがウェセックス王家から高く評価されていたことを示していると考えられます。彼の遺骨は後の時代、特に17世紀のイングランド内戦中に、クロムウェルの兵士たちによってウィンチェスター大聖堂のステンドグラスの窓を壊すために使用され、他のアングロサクソン王や司教の墓標、さらにはノルマン朝の王ウィリアム2世の墓標にも散乱して付着していることが確認されています。
5. 遺産と歴史的評価
エグバートは、イングランド南部をウェセックスの支配下に統合し、後のイングランド統一国家の形成に重要な役割を果たしました。しかし、彼の統一が一時的であったことや、ヴァイキングの脅威が継続したという限界点も存在します。
5.1. イングランド統一の礎
エグバートは、アングロサクソン・イングランドにおいて重要な転換点をもたらした人物として評価されています。彼はマーシアの覇権を打ち破り、イングランド南東部をウェセックスの直接的な支配下に置き、その後マーシアとノーサンブリアを服従させることで、実質的にイングランド南部を統一しました。この業績は、彼が『アングロサクソン年代記』で「ブレトワルダ」と称されたことにも表れています。彼の支配下で、ウェセックスはイングランドの主要な政治勢力としての地位を確立し、後のアルフレッド大王やアゼルスタンによるイングランド統一国家の基礎を築いたと見なされています。特に、彼の息子エゼルウルフへの円滑な王位継承は、ウェセックス王権の安定化に寄与し、統一に向けた重要な一歩となりました。
5.2. 批判と限界
エグバートの統一は画期的なものでしたが、その支配は一時的な側面も持っていました。彼が征服したマーシアは、わずか1年後にウィグラフによって独立を回復し、イーストアングリアもウェセックスの影響力が弱まる中で独立を維持しました。これは、彼の支配がまだイングランド全体にわたる完全な統一国家の形成には至っていなかったことを示しています。
また、彼の治世の終わり頃には、ヴァイキングの襲撃が激化し、ウェセックスもデーン人との戦いを強いられるようになりました。836年のカーハンプトンの戦いでの敗北は、この新たな脅威に対するアングロサクソン王国の脆弱性を示唆するものでした。ヒングストン・ダウンの戦いでの勝利は重要であったものの、ヴァイキングの侵略という継続的な脅威は、彼が築いた支配体制の限界を示しており、後の時代に大きな影響を与えることになります。エグバートの業績は、統一への道を開いたものとして評価される一方で、その支配が完全なものではなく、依然として多くの課題を抱えていたという客観的な視点も重要です。