1. 生涯
ゴットロープ・フレーゲの生涯は、彼の学術的キャリアと密接に結びついており、幼少期から晩年まで、論理学と哲学の発展に多大な影響を与えた。
1.1. 幼少期と背景
フレーゲは1848年、当時メクレンブルク=シュヴェリーン大公国の一部であったヴィスマール(現在のメクレンブルク=フォアポンメルン州)に生まれた。彼の父カール・アレクサンダー・フレーゲ(1809年 - 1866年)は、女子高等学校の共同創設者であり校長を務めていた。父の死後、学校は母アウグステ・ヴィルヘルミーネ・ゾフィー・フレーゲ(旧姓ビアロブロツキー、1815年 - 1898年)によって運営された。母方の祖母はアウグステ・アマリア・マリア・バルホルンで、フィリップ・メランヒトンの子孫であり、母方の祖父はヨハン・ハインリヒ・ジークフリート・ビアロブロツキーで、17世紀にポーランドを離れたポーランド人貴族の家系に属していた。フレーゲはルター派の信徒であった。
幼少期に、フレーゲは後の科学的キャリアを導くことになる哲学と出会った。例えば、彼の父は9歳から13歳の子ども向けにドイツ語の教科書『ドイツ語教授のための補助書』(Hülfsbuch zum Unterrichte in der deutschen Sprache für Kinder von 9 bis 13 Jahrenドイツ語)を執筆しており、その最初の章では言語の構造と論理について扱っていた。
1.2. 教育
フレーゲはヴィスマールのギムナジウムで学び、1869年に卒業した。彼の数学と自然科学の教師であったグスタフ・アドルフ・レオ・ザクセ(1843年 - 1909年)は、フレーゲの将来の科学的キャリアを決定する上で重要な役割を果たし、彼自身の母校であるイェーナ大学で研究を続けるよう奨励した。
フレーゲは1869年春に北ドイツ連邦の市民としてイェーナ大学に入学した。4学期にわたり、彼は約20の講義に出席し、そのほとんどが数学と物理学に関するものであった。彼の最も重要な教師はエルンスト・カール・アッベ(1840年 - 1905年)であった。アッベは重力理論、ガルヴァーニ電流と電気力学、複素変数関数の複素解析理論、物理学の応用、力学の選ばれた部門、固体力学に関する講義を行った。アッベはフレーゲにとって教師以上の存在であり、信頼できる友人であった。また、光学機器メーカーカール・ツァイス社の取締役として、フレーゲのキャリアを推進する立場にあった。フレーゲの卒業後、彼らはより密接な文通を交わすようになった。
彼の他の著名な大学教師には、クリスティアン・フィリップ・カール・シュネル(1806年 - 1886年、主題:幾何学における無限小解析の利用、平面の解析幾何学、解析力学、光学、力学の物理的基礎)、ヘルマン・シェファー(1824年 - 1900年、解析幾何学、応用物理学、代数解析、電報およびその他の電子機械)、そして哲学者クーノ・フィッシャー(1824年 - 1907年、カント哲学および批判哲学)がいた。
1871年からは、ドイツ語圏で数学の主要大学であったゲッティンゲン大学で研究を続け、アルフレート・クレプシュ(1833年 - 1872年、解析幾何学)、エルンスト・クリスティアン・ユリウス・シェーリング(1824年 - 1897年、関数論)、ヴィルヘルム・エドゥアルト・ヴェーバー(1804年 - 1891年、物理学研究、応用物理学)、エドゥアルト・リーケ(1845年 - 1915年、電気理論)、そしてヘルマン・ロッツェ(1817年 - 1881年、宗教哲学)の講義に出席した。フレーゲの成熟期の哲学的教義の多くはロッツェの思想と類似点があり、ロッツェの講義への出席がフレーゲの見解に直接的な影響を与えたかどうかは学術的な議論の対象となっている。
1873年、フレーゲはエルンスト・クリスティアン・ユリウス・シェーリングのもとで「平面における虚数図形の幾何学的表現について」(Ueber eine geometrische Darstellung der imaginären Gebilde in der Ebeneドイツ語)と題する論文で博士号を取得した。この論文では、射影幾何学の無限遠点(虚点)の数学的解釈といった幾何学の根本的な問題を解決することを目指した。
1.3. 結婚と家族
フレーゲは1887年3月14日にマルガレーテ・カタリーナ・ゾフィー・アンナ・リーゼベルク(1856年2月15日 - 1904年6月25日)と結婚した。夫婦には少なくとも2人の子供がいたが、残念ながら幼くして亡くなった。数年後、彼らはアルフレートという息子を養子に迎えた。フレーゲの家庭生活についてはこれ以上の詳細はほとんど知られていない。
1.4. 学術的経歴
1874年、フレーゲはイェーナ大学で大学教授資格論文を提出し、数学科の私講師として採用された。1879年にはイェーナ大学の員外教授に昇進し、1896年には正名誉教授に昇進した。彼は1918年にイェーナ大学を退職し、1925年にバート・クライネンで死去した。
2. 論理学および数学への貢献
フレーゲは、現代論理学と数学の基礎を確立する上で革新的な業績を残した。彼の研究は、論理学を新たな次元へと引き上げ、数学の厳密な基礎付けに挑戦した。
2.1. 《論理記号》と現代論理学の基礎

フレーゲの教育と初期の数学研究は主に幾何学に焦点を当てていたが、彼の研究はすぐに論理学へと転じた。1879年に出版された彼の著書『論理記号: 純粋思考の算術に倣った形式言語』(Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkensドイツ語)は、論理学の歴史における転換点となった。『論理記号』は、関数と変数の厳密な扱いを含む、新たな地平を切り開いた。フレーゲの目標は、数学が論理から生じることを示すことであり、その過程で彼はアリストテレスの三段論法から離れ、ストア派の命題論理にかなり近い手法を考案した。
事実上、フレーゲは公理的述語論理を発明した。これは主に、量化された変数の発明によるもので、これは最終的に数学と論理学において遍在するようになり、多重普遍性の問題を解決した。以前の論理学は論理定数「かつ」「または」「もし...ならば...」「でない」、そして「いくつか」と「すべて」を扱っていたが、これらの操作の繰り返し、特に「いくつか」と「すべて」はほとんど理解されていなかった。例えば、「すべての少年はいくつかの少女を愛している」という文と「いくつかの少女はすべての少年に愛されている」という文の違いでさえ、非常に人為的にしか表現できなかったのに対し、フレーゲの形式主義は、「すべての少年は、いくつかの少年を愛するいくつかの少女を愛している」といった文の異なる読み方を、例えば「すべての少年は愚かである」という文の扱いと完全に並行して表現するのに何の困難もなかった。
頻繁に指摘される例として、アリストテレスの論理学は、無限に多くの素数が存在するという数論の基本的な命題であるユークリッドの定理のような数学的記述を表現できないことが挙げられる。しかし、フレーゲの「概念記法」は、そのような推論を表現することができる。バートランド・ラッセル(1872年 - 1970年)とアルフレッド・ノース・ホワイトヘッド(1861年 - 1947年)による『プリンキピア・マテマティカ』(3巻、1910年 - 1913年)、ラッセルの記述理論、クルト・ゲーデル(1906年 - 1978年)のゲーデルの不完全性定理、そしてアルフレッド・タルスキ(1901年 - 1983年)の真理の理論に不可欠な論理的概念の分析と形式化の仕組みは、最終的にフレーゲに由来する。
フレーゲの目的の一つは、推論の真に論理的な原理を分離することであった。これにより、数学的証明の適切な表現において、「直観」に訴えることが一切なくなるようにした。もし直観的な要素があるならば、それは分離され、公理として別途表現されるべきであり、そこから先の証明は純粋に論理的で隙間がないものとされるべきであった。この可能性を示した上で、フレーゲのより大きな目的は、算術が論理学の一分野であるという見解、すなわち論理主義を擁護することであった。幾何学とは異なり、算術は「直観」に基づくものではなく、非論理的な公理を必要としないことを示すべきだとされた。すでに1879年の『論理記号』では、例えば三分割律の一般化された形式など、重要な予備定理がフレーゲが純粋論理と理解していた範囲内で導出されていた。
フレーゲが《概念記法》で用いた記法は、現代の論理学で用いられる記法とは異なるものの、その概念は現代論理学の基礎を築いた。彼の記法の一部を以下に示す。
| 概念 | 『概念記法』の表記 | 現代の表記 |
|---|---|---|
| 否定 |  | |
| 含意 |  | |
| 全称記号 | ||
| 存在記号 | ||
| 同値 |
2.2. 論理主義と《算術の基礎》
この考えは、彼の著書『算術の基礎: 数の概念に関する論理学的・数学的探求』(Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahlドイツ語、1884年)で非記号的に定式化された。この著作において、フレーゲは数学が論理に帰着できるとする論理主義を提唱し、数の概念に対する心理主義的なアプローチを批判しながら、論理的な定義を試みた。彼は、数が主観的な心理的プロセスではなく、客観的な論理的概念であると主張した。
2.3. 《算術の基本法則》と論理主義プログラム
後に、彼の著書『算術の基本法則』(Grundgesetze der Arithmetikドイツ語、第1巻1893年、第2巻1903年、第2巻は自費出版)において、フレーゲは自身の記号体系を用いて、算術のすべての法則を彼が論理的であると主張する公理から導出しようと試みた。これらの公理のほとんどは彼の『論理記号』から引き継がれたものであったが、いくつかの重要な変更が加えられていた。唯一真に新しい原理は、彼が基本法則Vと呼んだものであった。これは、関数f(x)の「値域」が関数g(x)の「値域」と同じであるのは、∀x[f(x) = g(x)]である場合に限るというものであった。
この法則の重要なケースは、現代の記法では次のように定式化できる。述語Fxの外延、すなわちすべてのFの集合を{x|Fx}で表し、同様にGxについても表す。このとき、基本法則Vは、述語FxとGxが同じ外延を持つのは、∀x[Fx ↔ Gx]である場合に限ると述べる。Fの集合がGの集合と同じであるのは、すべてのFがGであり、すべてのGがFである場合に限る。(このケースは特殊である。なぜなら、ここで述語の外延、または集合と呼ばれているものは、関数の「値域」の一種にすぎないからである。)
有名な出来事として、バートランド・ラッセルは『算術の基本法則』第2巻が印刷されようとしていた1903年にフレーゲに手紙を書き、ラッセルのパラドックスがフレーゲの基本法則Vから導出できることを示した。フレーゲの体系では集合や外延の「帰属」関係を容易に定義できる。ラッセルは、「xがxの要素ではないようなxの集合」に注意を促した。『算術の基本法則』の体系は、このように特徴づけられた集合がそれ自身の要素であると同時に要素でないことを含意し、したがって矛盾している。フレーゲは急遽、第2巻の最後に付録を加え、矛盾を導出し、基本法則Vを修正することでそれを解消することを提案した。フレーゲは付録を次のような非常に正直なコメントで始めた。「科学的著述家にとって、著作が完成した後にその基礎の一つが揺さぶられるほど不幸なことはほとんどない。この状況は、この巻の印刷が完了に近づいていたまさにその時、バートランド・ラッセル氏からの手紙によって私に突きつけられたものである。」
フレーゲが提案した修正案は、その後、談話領域にただ一つの対象しか存在しないことを含意することが示され、したがって無価値であることが判明した(実際、これは真と偽が異なる対象であるという、彼の議論の根本にある考えを公理化していたならば、フレーゲの体系において矛盾を引き起こすことになっただろう)。しかし、最近の研究では、『算術の基本法則』のプログラムの多くが他の方法で救済できる可能性が示されている。
- 基本法則Vは他の方法で弱めることができる。最もよく知られているのは、フレーゲの研究の専門家であった哲学者で数理論理学者のジョージ・ブーロス(1940年 - 1996年)によるものである。「概念」Fは、Fの下に属する対象が談話領域と一対一に対応できない場合、すなわち、∃R[Rは一対一であり、∀x∃y(xRy & Fy)]でない場合に限り、「小さい」とされる。ここでVをV*に弱める。概念Fと概念Gが同じ「外延」を持つのは、FもGも小さくないか、または∀x(Fx ↔ Gx)である場合に限る。V*は二階算術が整合的であれば整合的であり、二階算術の公理を証明するのに十分である。
- 基本法則Vは、ヒュームの原理に置き換えることができる。これは、Fの数がGの数と同じであるのは、FとGが一対一に対応できる場合に限ると述べる。この原理も、二階算術が整合的であれば整合的であり、二階算術の公理を証明するのに十分である。この結果はフレーゲの定理と呼ばれている。これは、算術を展開する際に、フレーゲが基本法則Vを用いたのはヒュームの原理の証明に限定されており、そこから算術的原理が導出されていることが後に気づかれたためである。
- フレーゲの論理学(現在では二階論理として知られている)は、いわゆる述定的二階論理に弱めることができる。述定的二階論理と基本法則Vは、有限的または構成的な方法によって整合的であることが証明可能であるが、算術の非常に弱い断片しか解釈できない。
フレーゲの論理学における研究は、1903年にラッセルが『数学の原理』の付録でフレーゲとの相違点を述べた時まで、国際的な注目をほとんど集めなかった。フレーゲが使用した図式的な記法は前例がなく(そしてその後も模倣者がいない)。さらに、ラッセルとホワイトヘッドの『プリンキピア・マテマティカ』(3巻)が1910年 - 1913年に登場するまで、数理論理学への支配的なアプローチは依然としてジョージ・ブール(1815年 - 1864年)とその知的後継者、特にエルンスト・シュレーダー(1841年 - 1902年)のものであった。しかし、フレーゲの論理学的思想は、彼の学生であるルドルフ・カルナップ(1891年 - 1970年)や、特にバートランド・ラッセルやルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889年 - 1951年)といった他の崇拝者たちの著作を通じて広まった。
2.4. 数理論理学への影響
フレーゲの論理体系は、バートランド・ラッセル、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド、クルト・ゲーデル、アルフレッド・タルスキといった後世の論理学者や哲学者に深遠な影響を与えた。彼の概念記法は、現代の述語論理の基礎を築き、量化の概念を導入したことで、数学的命題の厳密な形式化を可能にした。これにより、数学の基礎を論理に還元しようとする論理主義のプログラムが具体的に推進された。ラッセルのパラドックスによって彼の体系に矛盾が発見されたものの、その後の研究によって彼の論理主義の核心部分が再評価され、現代論理学の発展に不可欠なものとなっている。
3. 言語哲学への貢献
フレーゲは分析哲学の創始者の一人であり、彼の論理学と言語に関する研究は、哲学における言語論的転回を引き起こした。彼の言語哲学への貢献には、以下のようなものがある。
- 命題の関数と引数の分析
- 概念と対象(Begriff und Gegenstandドイツ語)の区別
- 構成性原理(Principle of Compositionality)
- 文脈原理(Context Principle)
- 名前やその他の表現の意義と意味(Sinn und Bedeutungドイツ語)の区別。これは時に媒介指示理論を含むと言われる。
数学の哲学者として、フレーゲは判断の内容や文の意味に対する心理主義的な精神的説明への訴えを批判した。彼の本来の目的は、意味に関する一般的な問いに答えることからはかけ離れていた。むしろ、彼は算術の基礎を探求するために自身の論理学を考案し、「数とは何か?」や「数詞(『一』『二』など)は何を指示するのか?」といった問いに答えようと試みた。しかし、これらの問題を追求する中で、彼は最終的に意味とは何かを分析し説明することになり、その結果、分析哲学と言語哲学のその後の進路に極めて重大な結論を導き出した。
3.1. 意義と意味対象 (Sinn und Bedeutung)
フレーゲの1892年の論文「意義と意味について」(Über Sinn und Bedeutungドイツ語)は、彼の影響力のある「意義」(Sinnドイツ語)と「意味」(Bedeutungドイツ語、これは「指示対象」や「指示」とも訳される)の区別を導入した。意味に関する従来の考え方が、表現がただ一つの特徴(指示対象)を持つとしていたのに対し、フレーゲは表現がその意義と指示対象という二つの異なる側面を持つという見解を導入した。
「意味」(または「指示対象」)は固有名詞に適用され、与えられた表現(例えば「トム」という表現)は、単にその名前を持つ実体(トムという名前の人物)を指示する。フレーゲはまた、命題がその真理値と指示的関係を持つとも考えた(言い換えれば、文はその取る真理値を「指示する」)。対照的に、完全な文に関連付けられる「意義」(または「Sinn」)は、その文が表現する思考である。表現の意義は、指示される対象の「提示様式」であると言われ、同じ指示対象に対して複数の提示様式が存在しうる。
この区別は次のように例示できる。通常の用法において、論理的な目的のために分析不可能な全体である「チャールズ・フィリップ・アーサー・ジョージ・マウントバッテン=ウィンザー」という名前と、有意義な部分「ξの王」と「イギリス」を含む機能的表現「イギリスの王」は、同じ「意味」を持つ。すなわち、チャールズ3世として最もよく知られている人物である。しかし、「イギリス」という言葉の「意義」は後者の表現の意義の一部であるが、チャールズ王の「フルネーム」の意義の一部ではない。
これらの区別はバートランド・ラッセルによって、特に彼の論文「指示について」で異論が唱えられた。この論争は、特にソール・クリプキの有名な講義「名指しと必然性」によって煽られ、現在まで続いている。
3.2. 概念と対象 (Begriff und Gegenstand)
フレーゲの1892年の論文「概念と対象について」(Über Begriff und Gegenstandドイツ語)では、論理的な概念と現実の対象との関係を分析し、両者を厳密に区別した。彼は、概念は関数のように不飽和な性質を持ち、対象は飽和した完全な存在であると主張した。この区別は、彼の論理主義の基礎をなし、後の存在論や形而上学に影響を与えた。
3.3. その他の言語哲学的概念
フレーゲの言語哲学における主要な概念には、構成性原理(Principle of Compositionality)がある。これは、文全体の意味が、その構成要素の意味とそれらの結合方法によって決定されるという考え方である。また、文脈原理(Context Principle)は、『算術の基礎』で提示されたもので、「単語の意味は、文脈の中で初めて与えられる」というものであり、単語を孤立して理解するのではなく、文全体の中でその役割を理解することの重要性を強調した。これらの概念は、現代言語哲学の基礎を形成している。
4. 哲学と思想
フレーゲの全体的な哲学的立場は、論理と数学に対する彼の根本的な思想に深く根ざしている。
4.1. 心性主義批判
フレーゲは、論理や数学的思考において心理主義的な説明を徹底的に排し、客観性を強調した。彼は、論理法則や数学的真理が、個人の精神状態や心理的プロセスに依存するものではなく、普遍的かつ客観的なものであると主張した。この立場は、彼が数の概念の心理主義的定義を批判した『算術の基礎』で明確に示されている。彼は、論理と数学が心理学から独立した、それ自身の客観的な領域を持つべきだと考えた。
4.2. プラトン主義
フレーゲは、数、命題、概念などの抽象的対象に対する実在論的(プラトン主義的)な見解を持っていた。彼はこれらの抽象的対象が、人間精神から独立して客観的に存在すると考えた。この見解は、彼の心理主義批判と密接に関連しており、論理的・数学的真理の客観性と普遍性を保証するための基盤となった。彼にとって、数は物理的対象でも心理的観念でもなく、それ自体で存在する第三の領域の対象であった。
4.3. 個人的政治見解と論争
フレーゲの公表された哲学的著作は非常に専門的で、実践的な問題とはかけ離れていたため、フレーゲ研究者のマイケル・ダメットは「フレーゲの日記を読んで、彼のヒーローが反ユダヤ主義者であったことを知り衝撃を受けた」と述べている。1918年から1919年のドイツ革命後、彼の政治的見解はより過激になった。晩年の1920年代の日記には、議会制、民主主義者、自由主義者、カトリック教徒、フランス人、そしてユダヤ人に反対する政治的見解が記されており、彼はユダヤ人が政治的権利を剥奪され、できればドイツから追放されるべきだと考えていた。
フレーゲは「かつては自分を自由主義者と考え、オットー・フォン・ビスマルクを崇拝していた」が、その後エーリヒ・ルーデンドルフ将軍に共感したと告白している。1924年5月5日の日記には、ヒューストン・スチュワート・チェンバレンの『ドイツの再生』(Deutschlands Erneuerungドイツ語)に掲載されたアドルフ・ヒトラーを称賛する記事に同意する旨が記されている。フレーゲは、ドイツのユダヤ人が「いなくなるか、あるいはドイツから消えてくれるのが一番良い」という信念を記している。日記には普通選挙と社会主義への批判も含まれている。
しかし、フレーゲは実生活ではユダヤ人と友好的な関係を持っていた。彼の学生の中にはゲルショム・ショーレムがおり、彼はフレーゲの教えを高く評価していた。また、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがバートランド・ラッセルのもとで学ぶためにイギリスへ行くことを奨励したのはフレーゲであった。この1924年の日記は1994年に死後出版された。
5. 人物像
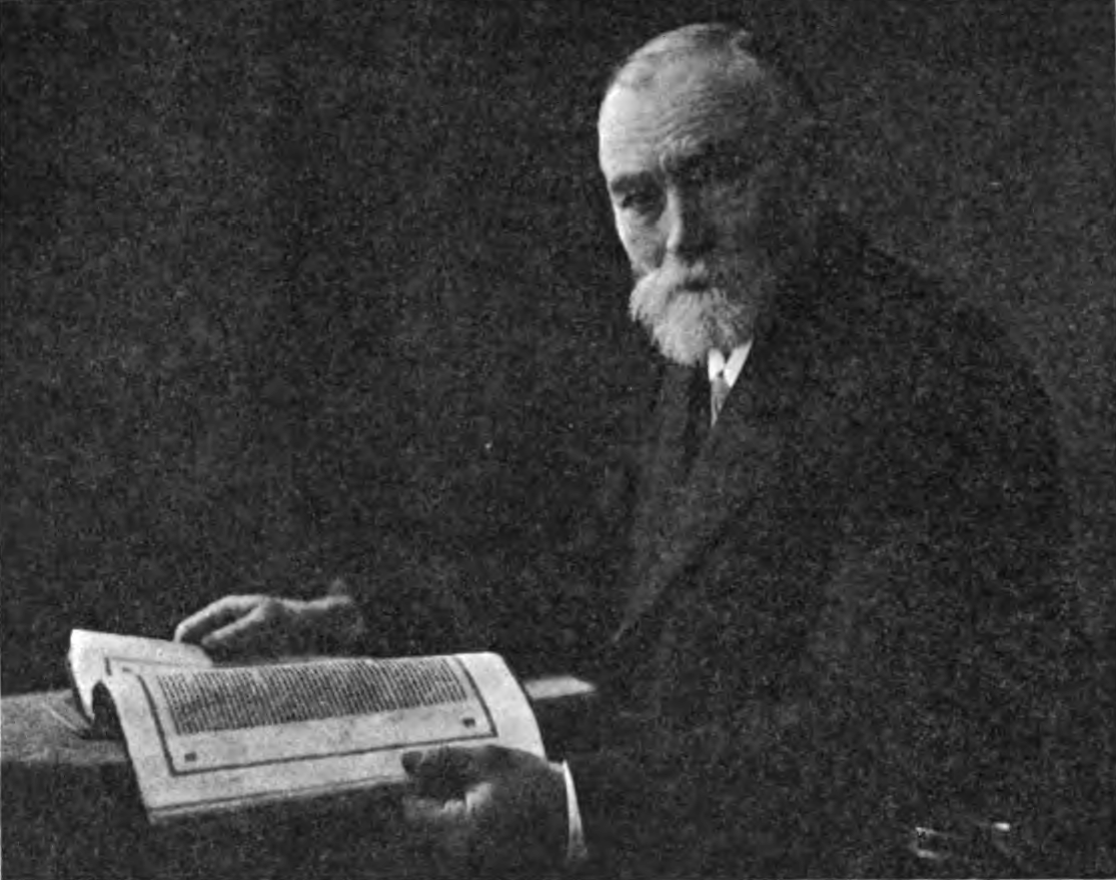
フレーゲは学生たちによって、非常に内向的な人物として描写されており、他人と対話することはめったになく、講義中はほとんど黒板に向かっていたという。しかし、彼は授業中に時折、機知に富んだ発言や、時には辛辣な皮肉を見せることでも知られていた。
6. 遺産と評価
フレーゲの思想は学界に計り知れない影響を与え、その評価は時代とともに変化してきた。彼の論理主義は、ラッセルのパラドックス以降も現代論理学において再評価されている。
6.1. 初期における無視と後世の再評価
フレーゲの業績は、生前はほとんど正当に評価されなかった。彼の記号体系は当時の主流であったブール論理とは異なり、その革新性が理解されにくかったためである。しかし、ジュゼッペ・ペアノやバートランド・ラッセルといった後続の論理学者たちが彼の研究を発見し、その重要性を認識するにつれて、フレーゲの思想は再評価されるようになった。特にラッセルが彼の著作を研究し、自身の『数学の原理』で言及したことで、フレーゲの貢献は広く知られるようになり、彼の思想は分析哲学の土台を築くことになった。
6.2. 分析哲学および後世の思想家への影響
フレーゲは、分析哲学の創始者の一人とされている。彼の論理学と言語哲学における貢献は、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン、バートランド・ラッセル、ルドルフ・カルナップ、エトムント・フッサールなど、後世の主要な哲学者たちに具体的な影響を与えた。ウィトゲンシュタインはフレーゲの「意義と意味」の区別や「思考」の概念から影響を受け、ラッセルは彼の論理体系を自身の『プリンキピア・マテマティカ』に統合しようと試みた。カルナップはフレーゲの講義に出席し、彼の思想を論理実証主義の発展に役立てた。
6.3. 論理主義の現代的再評価
ラッセルのパラドックスによって、フレーゲの論理主義プログラムは一時的に挫折したかに見えた。しかし、その後、チャールズ・パーソンズ、ジョージ・ブーロス、リチャード・ヘックらによって、彼の体系が完全に破綻したわけではないことが示された。特に、彼の「ヒュームの原理」が、矛盾を招くことなく算術の公理を導出できることが明らかになったことで、フレーゲの論理主義は現代論理学において再評価されている。これにより、数学の基礎を論理に還元しようとする彼の試みが、新たな形でその妥当性を証明されつつある。
7. 主要な年譜
フレーゲの生涯における重要な出来事を年代順に整理して提示する。
- 1848年11月8日:ヴィスマール(メクレンブルク=シュヴェリーン大公国)で出生。
- 1854年:ヴィスマールのギムナジウムに進学。
- 1866年:父カール・アレクサンダーが死去。
- 1869年:ヴィスマールのギムナジウムを卒業し、イェーナ大学に進学。
- 1871年:ゲッティンゲン大学へ転学。
- 1873年:幾何学の博士号をゲッティンゲン大学で取得。
- 1874年:イェーナ大学で大学教授資格論文を提出し、数学科の私講師に採用される。
- 1879年:『論理記号』(Begriffsschriftドイツ語)を刊行。イェーナ大学の員外教授に昇進。
- 1884年:『算術の基礎』(Die Grundlagen der Arithmetikドイツ語)を刊行。
- 1887年3月14日:マルガレーテ・リーゼベルクと結婚。
- 1891年:イェーナ医学・自然科学協会で「関数と概念」(Funktion und Begriffドイツ語)を講演。
- 1892年:論文「意義と意味について」(Über Sinn und Bedeutungドイツ語)、「概念と対象について」(Über Begriff und Gegenstandドイツ語)を発表。
- 1893年:『算術の基本法則』(Grundgesetze der Arithmetikドイツ語)第1巻を刊行。
- 1896年:イェーナ大学の正名誉教授に昇進。
- 1898年:母アウグステ・ビアロブロツキー死去。
- 1902年:バートランド・ラッセルからラッセルのパラドックスを知らせる手紙が届く。
- 1903年:『算術の基本法則』第2巻を刊行。
- 1905年:妻マルガレーテ死去。
- 1911年:ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインがフレーゲを訪ねる。
- 1918年:イェーナ大学を退職し、バート・クライネンに引退。
- 1925年7月26日:バート・クライネン(現在のメクレンブルク=フォアポンメルン州)で死去。
8. 主要著作
フレーゲの主要な著作は、現代論理学、数学の基礎、そして言語哲学に革新をもたらした。
- 『論理記号: 純粋思考の算術に倣った形式言語』(Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkensドイツ語、1879年)
- 述語論理と量化の概念を初めて導入し、現代論理学の基礎を築いた画期的な著作。
- 『算術の基礎: 数の概念に関する論理学的・数学的探求』(Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahlドイツ語、1884年)
- 数の概念に対する心理主義的アプローチを批判し、論理主義の立場から数の客観的な定義を試みた。
- 「関数と概念」(Funktion und Begriffドイツ語、1891年)
- 関数と概念の区別、およびそれらが飽和・不飽和の性質を持つという考え方を提示した論文。
- 「意義と意味について」(Über Sinn und Bedeutungドイツ語、1892年)
- 固有名詞や文が持つ「意義」(Sinn)と「意味」(Bedeutung、指示対象)を区別する、彼の最も有名な言語哲学的理論を提示。
- 「概念と対象について」(Über Begriff und Gegenstandドイツ語、1892年)
- 概念と対象の厳密な区別を論じ、論理におけるそれらの役割を明確にした。
- 『算術の基本法則』(Grundgesetze der Arithmetikドイツ語、第1巻1893年、第2巻1903年)
- 算術の法則を論理から導出しようと試みた、フレーゲの論理主義プログラムの集大成。ラッセルのパラドックスによって矛盾が発見されたが、その重要性は依然として高い。
- 「関数とは何か?」(Was ist eine Funktion?ドイツ語、1904年)
- 関数という概念の性質について考察した論文。
- 『論理探求』(Logische Untersuchungenドイツ語、1918年 - 1923年、死後出版)
- 「思想」(Der Gedankeドイツ語)、「否定」(Die Verneinungドイツ語)、「複合思想」(Gedankengefügeドイツ語)の三つの論文からなり、思考、判断、真理といった概念を論理的に探求した。
9. 関連項目
- 概念記法
- 論理主義
- 記号論理学
- 命題論理
- 述語論理
- 集合論
- 言語論的転回
- ラッセルのパラドックス
- バートランド・ラッセル
- ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン
- ジュゼッペ・ペアノ
- エトムント・フッサール
Category:ゴットロープ・フレーゲ