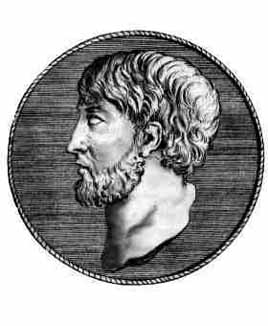1. Overview
アポロニアのディオゲネスは、紀元前5世紀に活動した古代ギリシアの哲学者で、トラキア地方にあるミレトスの植民都市アポロニア(現在のソゾポル)の出身です。彼は、空気こそが万物の唯一の根源であり、それは単なる物質ではなく、神聖で知性を持つ原理であると主張しました。この思想は、先行するアナクシメネスの唯物一元論と、アナクサゴラスなどの多元論を統合したもので、彼は「自然哲学者」の最後の世代と見なされています。
ディオゲネスは、空気の凝縮と希薄化によって森羅万象が形成されると考え、宇宙の成り立ちや生命の機能、さらには人間の思考や生理現象に至るまで、全てを空気の作用によって説明しようとしました。彼の生理学に関する記述、特に人体内の血管の分布に関する詳細な説明は、プレ・ソクラテス期の哲学者としては珍しい科学的探求の例として評価されています。
彼の思想は、同時代のアテナイで活動した劇作家アリストパネスの喜劇『雲』の中で、ソクラテスに風刺的に投影される形で言及されました。また、デルベニ・パピルスに保存されているオルフェウス教の哲学的注釈書に影響を与えた可能性も指摘されています。彼の著作は完全な形では現存していませんが、その思想は主にシンプリキオスの著作からの引用や、アリストテレス、テオプラストス、アエティウスによる要約を通じて今日に伝えられています。
2. Life
ディオゲネスの個人的な生涯については多くの詳細が不明ですが、彼の生い立ち、成長背景、そしてアテナイでの活動など、彼の活動の舞台となった場所や経験した出来事が知られています。
2.1. Background and Early Life
ディオゲネスは、黒海に面したトラキア地方のミレトス人植民地アポロニア・ポンティカ(現在のソゾポル)の出身です。ただし、この「アポロニア」がクレタ島のエレウテルナにあった都市であるという別の見解も存在しますが、現代の多くの学者はこれを認めていません。彼の父親の名前はアポロテミスと伝えられています。
ディオゲネス・ラエルティオスの記述によれば、ディオゲネスはアナクシメネスの弟子であるとされていますが、これは時代的な混乱がある可能性があり、むしろ彼はアナクサゴラスと同時代に生きたと考えられています。彼は、他の多くの自然哲学者(physiologoi)と同様に、イオニア方言で執筆活動を行いました。
2.2. Activities in Athens
ディオゲネスは、紀元前430年から紀元前420年頃にかけてアテナイで生活し、哲学的な活動を行いました。アテナイでの彼の活動は、困難を伴うものであったことが知られています。ディオゲネス・ラエルティオスは、「アテナイで大きな嫉妬によって彼の命が危うくなる寸前だった」と述べており、この記述は、当時のアテナイにおいて彼の思想が敵対的に受け止められていたことを示唆しています。特に、彼の無神論的見解が反感を買った可能性が指摘されています。
3. Philosophy
アポロニアのディオゲネスは、テオプラストスによって「自然哲学者(physiologoi)」の最後の人物として位置づけられています。彼は、先行する一元論者であるアナクシメネスやヘラクレイトスの業績と、アナクサゴラスやエンペドクレスの多元論を統合し、空気を万物の根源とする唯物一元論を展開しました。
3.1. Air as the Fundamental Principle
ディオゲネスは、アナクシメネスと同様に、空気が万物の唯一の根源であると考えました。彼は、他のすべての物質が空気の凝縮と希薄化によって派生し、最終的には再び空気へと戻ると主張しました。この思想は、彼が「存在するものから無が生じることはなく、また存在するものから無に還元されることもない」と考えていたためです。
彼はさらに、同時代のアナクサゴラスの理論を取り入れ、万物の根源である空気が単なる物質ではなく、神聖で知性を持つ存在であると主張しました。彼は空気を「宇宙を秩序づける原理」と見なし、それは神であり、万物を統治し、あらゆるものに行き渡り、すべてのものを配置し、何一つとしてそれにあずからないものはないと述べました。空気は無限で永遠の存在であり、その性質が凝縮と希薄化によって変化することで、様々な存在が生じると考えました。また、彼は「目的論の創始者」とも呼ばれるほど、空気の働きに合目的的な運動を見出しました。
3.2. Cosmology
ディオゲネスによれば、宇宙は空気の作用、すなわちその凝縮と希薄化の過程によって形成されました。彼は、宇宙には無限の数の世界が存在し、それらを包む無限の空虚(ヴォイド)があると考えました。地球に関しては、その形状を球体であるとし、宇宙の中心に位置しているとしました。地球は、暖かい蒸気の旋回によってその形を得て、冷えることによって凝固し、硬化したと説明しました。
3.3. On Living Beings
ディオゲネスは、空気は人間や動物にとって不可欠な要素であると主張しました。空気は生物の生命を維持し、思考活動を可能にするために必要であり、空気がなくなれば生物は死に、思考も停止すると考えました。
彼は、生物間の違いや、生物と無生物の間の違いは、それらを構成する空気の性質に由来すると考えました。例えば、動物の体内の空気は外部の空気よりも暖かく、しかし太陽の空気よりは冷たいと述べました。また、動物それぞれの違いも、体内の空気の性質の違いに起因すると考え、これは人間にも当てはまるとしました。
3.4. On Human Physiology
ディオゲネスは、人間の生理学についても詳細な見解を持っていました。彼の著作の最も長い現存断片は、アリストテレスの著書『動物誌』に引用されており、そこには人体内の血管分布に関する詳細な記述が含まれています。
3.4.1. On Anatomy
ディオゲネスは、人体には二つの大きな血管が存在すると説明しました。これらは腹部を通って脊柱に沿って伸び、一方は右側へ、もう一方は左側へと分かれます。これらの血管は腕の方向へと向かい、さらに喉頭を通って上へと伸びます。そして、右側の血管は体の右半分全体に、左側の血管は左半分全体にそれぞれ分枝して広がります。彼は、この二つの大きな血管が心臓を通過し、そこから全身へと巡る詳細な経路を描写しました。これは、プレ・ソクラテス期の思想家としては、物理的世界の構造と組織を科学的に詳細に記述しようとした珍しい試みとして注目されます。
3.4.2. On Disease and Pleasure
ディオゲネスは、人間の病気や快楽も空気の作用によって生じると考えました。彼によると、空気が血液に適切に混ざり合い、血液が軽くなると、快楽が生じます。反対に、空気が血液に混ざらず、血液が濃く、弱くなると、それが病気の原因となると説明しました。
3.4.3. On Thinking
ディオゲネスは、乳児が成人と同じように思考できない理由についても考察しました。彼は、乳児の体内には大量の蒸気が存在するため、空気が体全体に入り込むことができず、その結果、空気が胸部に滞留してしまうからだと考えました。
同様に、人間が何かを忘却する現象も、空気が体内に適切に循環しないことに起因すると説明しました。この考えを裏付ける証拠として、何かを思い出そうとするときに胸部が収縮し、思い出したときにリラックスして安堵を感じることを挙げました。
4. Works
アポロニアのディオゲネスは複数の著作を残したとされていますが、そのほとんどは失われ、現在まで完全な形では残っているものはありません。
4.1. Surviving and Lost Works
ディオゲネスの著作の大部分は失われており、その思想は主にシンプリキオスの著作から知られています。シンプリキオスはアリストテレスの『自然学』に対する注釈書の中で、ディオゲネスの著作から多くの長い引用を行っています。また、アリストテレス、テオプラストス、アエティウスの著作にも、彼の思想の要約がいくつか含まれています。
彼の代表作は『自然について』(De naturaラテン語)であると広く認識されています。現代の学者の間では、この『自然について』が『人間の本性について』、『気象学について』、『ソフィストに反対して』といった内容を含む単一の著作であったのか、あるいはこれらがそれぞれ独立した著作であったのかについて議論があります。
5. Legacy and Reception
アポロニアのディオゲネスの思想は、古代においても現代においても、その独創性と影響力によって評価されてきました。
5.1. Ancient Reception and Influence
ディオゲネスの思想は、古代世界において様々な形で受け止められました。特に、劇作家アリストパネスの喜劇『雲』では、彼の見解がソクラテスの描写に風刺的に投影されていると現代の学者は概ね同意しています。これは、当時のアテナイ社会で彼の思想がある程度の認知度を持っていたことを示しています。また、詩人フィレモンの断片にも彼の思想への言及が見られます。
さらに、ディオゲネス隕石(ディオゲナイト)という名称は、アポロニアのディオゲネスにちなんで名づけられました。彼は、隕石の起源について、目に見えない「石の星」が他の星と共に回転し、時には地上に落下して消滅するという、宇宙空間由来説を初めて示唆した人物だからです。この考えは、アエティウスによって「アイゴスポタモイで火を噴いて落下した石の星のように」と引用されています。
5.2. Modern Studies and Rediscovery
現代の学術研究においては、ヘルマン・ディールスによる初期の評価以来、ディオゲネスの思想は過去数十年間まで、それほど頻繁に研究されてきたわけではありませんでした。
しかし、デルベニ・パピルスの発見以降、彼の思想は再評価されることになります。このパピルスは、ディオゲネスとアナクサゴラスの哲学と多くの類似点を持つオルフェウス教の哲学的詩篇であり、その発見によって、多くの学者がディオゲネスの著作を分析し、古代ギリシアの宗教と哲学との関連性をより深く理解するための手掛かりとしています。