1. 生涯
1.1. 幼少期と教育
フントは1896年2月4日にカールスルーエで生まれた。彼はマールブルク大学とゲッティンゲン大学で数学、物理学、地理学を専攻した。特にゲッティンゲン大学では、その後の彼の学術的キャリアの基礎を築く重要な研究環境に身を置いた。1923年にはゲッティンゲン大学で学位論文「一部の希ガスの極低速電子に対する高い透過性の解釈の試み(Versuch einer Deutung der großen Durchlässigkeit einiger Edelgase für sehr langsame Elektronen一部の希ガスの極低速電子に対する高い透過性の解釈の試みドイツ語)」を提出し、博士号を取得した。
1.2. 学術経歴
フントは1925年にゲッティンゲン大学の私講師として理論物理学のキャリアをスタートさせた。この時期、彼はマックス・ボルンの助手として、二原子分子のスペクトルバンドの量子論的解釈に取り組んでいた。彼はエルヴィン・シュレーディンガー、ポール・ディラック、ヴェルナー・ハイゼンベルク、ボルン、ヴァルター・ボーテといった著名な物理学者たちと共同研究を行った。
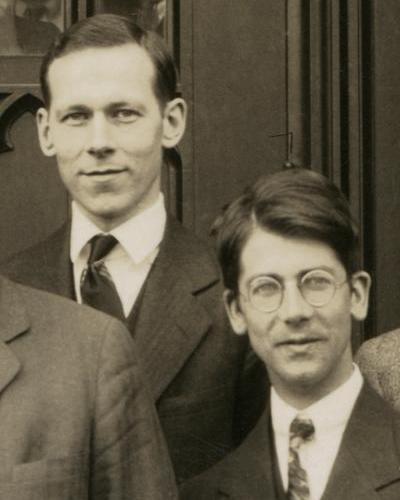
その後、フントはいくつかの大学で教授職を歴任した。
- ロストック大学教授(1927年、理論物理学)
- ライプツィヒ大学教授(1929年、数理物理学)
- イェーナ大学教授(1946年、理論物理学)
- フランクフルト大学教授(1951年、理論物理学)
- 再びゲッティンゲン大学教授(1957年、理論物理学)
この間、1926年にはニールス・ボーアとともにコペンハーゲンに滞在し、1928年にはハーバード大学で原子に関する講義を行った。彼は生涯で250報以上の論文や報文を執筆し、量子論、特に原子および分子のスペクトル構造に関して多大な貢献を残した。
分子軌道理論で1966年にノーベル化学賞を受賞したロバート・マリケンは、フントの研究が自身に与えた大きな影響を常に公言しており、もし可能であればノーベル賞をフントと分かち合いたかったと述べている。フントの貢献の重要性を認識し、分子軌道理論はしばしば「フント-マリケン分子軌道理論」と呼ばれている。
1.3. 私生活
フントは1931年3月17日にバルメンで数学者のインゲボルグ・ザインシェ(Ingeborg Seynscheインゲボルグ・ザインシェドイツ語、1905年 - 1994年)と結婚した。夫婦には6人の子供がいた。
- ゲルハルト(Gerhard Hundゲルハルト・フントドイツ語、1932年 - 2024年):チェス選手、数学者
- ディートリッヒ(Dietrichディートリッヒドイツ語、1933年 - 1939年)
- イルムガルト(Irmgardイルムガルトドイツ語、1934年生)
- マルティン(Martinマルティンドイツ語、1937年 - 2018年)
- アンドレアス(Andreasアンドレアスドイツ語、1940年生)
- エルヴィン(Erwinエルヴィンドイツ語、1941年 - 2022年)
彼の孫娘には、チェスのグランドマスターであるバーバラ・フント(Barbara Hundバーバラ・フントドイツ語、1959年生)と、同じくチェス選手であるイザベル・フント(Isabel Hundイザベル・フントドイツ語、1962年生)がいる。
フントはミュンヘン・ヴァルトフリートホーフに埋葬されている。

2. 主要な科学的貢献
フントの科学的業績は、原子や分子の構造に関する画期的な理解をもたらし、特に「フントの規則」や「フントの分類」の提唱、ロバート・マリケンとの分子軌道理論の共同確立、そして量子トンネル効果の発見を通じて、量子力学と化学の基礎を築いた。
2.1. フントの規則と分類
フントは、原子の電子配置を予測するための「フントの規則」を提唱した。特に、電子が同一のエネルギー準位(軌道)を占めるとき、可能な限り平行スピンを持ち、独立した軌道を占める傾向があるという「フントの最大多重度の規則」(通称「フントの第一規則」)は、分光学や量子化学において最も重要な基本則の一つとされている。
また、フントは二原子分子の角運動量カップリングに関する詳細な型分けを行った「フントの分類」も確立した。この分類は、分子のスペクトル構造を解析し、その特性を理解するために不可欠な枠組みを提供した。
2.2. 分子軌道理論(フント-マリケン理論)
フントは、アメリカの化学者ロバート・マリケンとの共同研究を通じて、分子軌道理論の発展に決定的な貢献をした。この理論は、「フント-マリケン分子軌道理論」として知られ、分子の電子が原子核の周りの個々の原子軌道ではなく、分子全体に広がる分子軌道に存在するという概念に基づいている。この理論は、分子の構造、結合、および化学反応性を理解するための強力なツールとなり、現代化学の基礎の一つを形成している。マリケンがノーベル賞を受賞した際、フントのこの理論への貢献の重要性を繰り返し強調している。
2.3. 量子トンネル効果
フントは1926年に、現在「量子トンネル効果」として知られる現象を最初に示唆した科学者の一人である。これは、量子粒子が古典力学では乗り越えられないエネルギー障壁を透過する現象を指す。この発見は、量子力学の基本的な概念の一つとして確立され、核融合、走査型トンネル顕微鏡、半導体デバイスなど、幅広い分野でその重要性が認識されている。
3. 著作および論文
フリードリッヒ・フントは、その長い学術的キャリアを通じて、物理学の基礎概念から専門分野に至るまで、多岐にわたる著作と論文を発表した。以下はその主要なものの一部である。
- 『一部の希ガスの極低速電子に対する高い透過性の解釈の試み』(Versuch einer Deutung der großen Durchlässigkeit einiger Edelgase für sehr langsame Elektronen一部の希ガスの極低速電子に対する高い透過性の解釈の試みドイツ語)、学位論文、ゲッティンゲン大学、1923年
- 『線スペクトルと元素の周期系』(Linienspektren und periodisches System der Elemente線スペクトルと元素の周期系ドイツ語)、ハビリテーション論文、ゲッティンゲン大学、シュプリンガー、1927年
- 『原子および分子構造の一般量子力学』(Allgemeine Quantenmechanik des Atom- und Molekelbaues原子および分子構造の一般量子力学ドイツ語)、『Handbuch der Physik』、第24巻/1、第2版、561-694頁、1933年
- 『場としての物質』(Materie als Feld場としての物質ドイツ語)、ベルリン、シュプリンガー、1954年
- 『理論物理学入門』(Einführung in die Theoretische Physik理論物理学入門ドイツ語)、全5巻、1944年 - 1951年、マイヤーズ・クライネ・ハンドビューヒャー、ライプツィヒ、ビブリオグラフィッシェス・インスティテュート、1945年、1950/51年(第1巻: 力学、第2巻: 電気と磁気の理論、第3巻: 光学、第4巻: 熱の理論、第5巻: 原子および量子論)
- 『理論物理学』(Theoretische Physik理論物理学ドイツ語)、全3巻、シュトゥットガルト、トイブナー、初版1956年 - 1957年(第1巻: 力学、第5版1962年、第2巻: 電気と光の理論、相対性理論、第4版1963年、第3巻: 熱理論と量子論、第3版1966年)
- 『物質構造の理論』(Theorie des Aufbaues der Materie物質構造の理論ドイツ語)、シュトゥットガルト、トイブナー、1961年
- 『物理学の基本概念』(Grundbegriffe der Physik物理学の基本概念ドイツ語)、マンハイム、ビブリオグラフィッシェス・インスティテュート、1969年、第2版1979年
- 『量子論の歴史』(Geschichte der Quantentheorie量子論の歴史ドイツ語)、1967年、第2版、マンハイム、ビブリオグラフィッシェス・インスティテュート、1975年、第3版1984年
- 『原子の量子力学』(Quantenmechanik der Atome原子の量子力学ドイツ語)、『Handbuch der Physik/Encyclopedia of Physics』、第XXXVI巻、ベルリン、シュプリンガー、1956年
- 『ゲッティンゲン物理学の歴史』(Die Geschichte der Göttinger Physikゲッティンゲン物理学の歴史ドイツ語)、ヴァンデンフック・ウント・ルプレヒト、1987年(ゲッティンゲン大学演説集)
- 『物理概念の歴史』(Geschichte der physikalischen Begriffe物理概念の歴史ドイツ語)、1968年、第2版(全2巻)、マンハイム、ビブリオグラフィッシェス・インスティテュート、1978年(第1巻: 機械的自然観の誕生、第2巻: 今日的自然観への道)、スペクトル出版、1996年
- 『回顧録:ゲッティンゲン、コペンハーゲン、ライプツィヒ』(Göttingen, Kopenhagen, Leipzig im Rückblick回顧録:ゲッティンゲン、コペンハーゲン、ライプツィヒドイツ語)、フリッツ・ボップ(編)『ヴェルナー・ハイゼンベルクと我々の時代の物理学』(Werner Heisenberg und die Physik unserer Zeitヴェルナー・ハイゼンベルクと我々の時代の物理学ドイツ語)、ブラウンシュヴァイク、1961年
フントの著作リストには、約300の項目が含まれている。
4. 受賞と栄誉
フントは、その卓越した科学的貢献に対して数多くの賞と栄誉を受けた。
- マックス・プランク・メダル(1943年):ドイツ物理学会が授与する最高の栄誉の一つ。
- コテニウス・メダル(1971年):ドイツ自然科学者アカデミー・レオポルディーナが授与するメダル。
- オットー・ハーン物理・化学賞(1974年):ドイツ化学会とドイツ物理学会が隔年で授与する著名な賞。
また、フントは国際量子分子科学アカデミーの会員でもあった。
彼の功績を称え、以下のような栄誉も与えられた。
- イェーナ名誉市民:彼は長年イェーナ大学で教授を務め、その地元のコミュニティから尊敬を集めた。
- イェーナ市内の通りにその名を冠する:イェーナには彼の名を冠した通りがある。
- ゲッティンゲン大学物理学科の新しい建物の住所がフリードリッヒ・フント広場1番地となる(2004年6月)。
- ゲッティンゲン大学理論物理学研究所にフリードリッヒ・フントの名前が冠される。
5. 遺産と影響
フリードリッヒ・フントの科学的遺産は、現代の物理学と化学において深く根付いている。彼の研究は、原子と分子の構造および挙動に関する理解の基礎を形成し、特に量子化学と分光学の分野に計り知れない影響を与えた。
「フントの規則」は、今日でも化学教育における中心的な概念であり、原子の電子配置を予測するための不可欠なツールとして、高校から大学院まで教えられている。また、「フントの分類」は、二原子分子のスペクトル解析において依然として重要な枠組みを提供している。
ロバート・マリケンとの共同研究によって確立された「フント-マリケン分子軌道理論」は、分子構造の理論的理解における画期的な進歩であり、計算化学および物質科学の発展に道を切り開いた。この理論がなければ、今日の分子設計や新素材開発の多くは不可能であっただろう。
1926年の量子トンネル効果の発見は、量子力学の最も奇妙で重要な現象の一つを明らかにした。この概念は、半導体デバイス、核融合、走査型トンネル顕微鏡など、現代の科学技術の多くの側面で応用されている。
彼の100歳の誕生日を記念して、著書『物理概念の歴史』(Friedrich Hund: Geschichte der physikalischen Begriffeフリードリッヒ・フント:物理概念の歴史ドイツ語、ISBN 3-8274-0083-X)が刊行されたことは、彼が科学史にも深い関心を持っていたことを示している。この本は、彼の物理学における概念形成の歴史的視点を反映しており、ヴェルナー・クッツェルニックによる書評も発表された。また、クラウス・ヘンチェルとレナーテ・トービエスによるインタビューでは、彼の研究と科学史への関心が深く議論された。
彼の名がイェーナの通りやゲッティンゲン大学の理論物理学研究所の住所に冠されていることは、ドイツにおける彼の永続的な影響と尊敬の証である。フントの業績は、今後も数世代にわたる科学者たちの研究のインスピレーションとなり続けるだろう。
6. 外部リンク
- [http://www.teleschach.de/teleschach/f_hund_en.htm フントの略歴、論文・受賞等一覧、写真など]