1. 概要
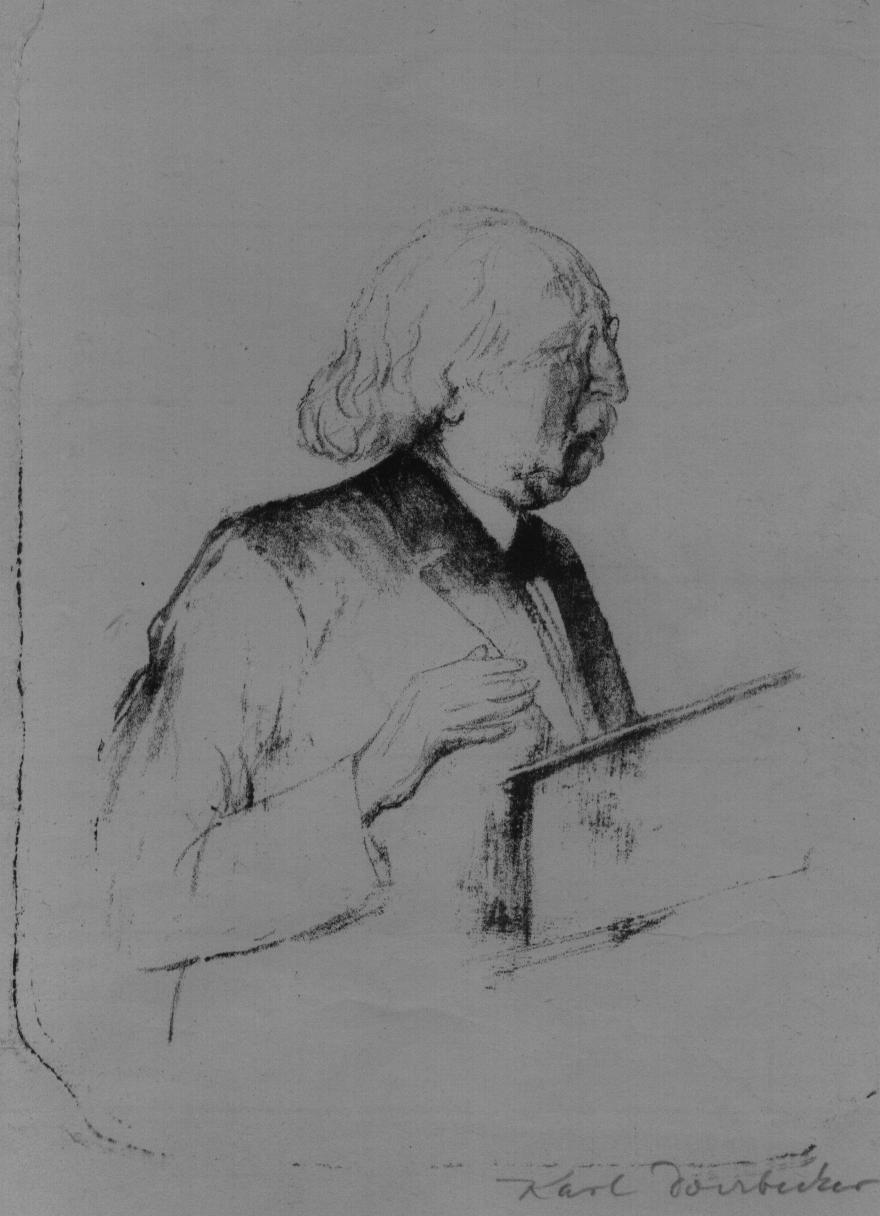
ヘルマン・コーエンは、19世紀後半から20世紀初頭にかけてドイツで活躍した、新カント主義マールブルク学派の創設者であり、その思想は哲学、倫理学、ユダヤ思想に多大な影響を与えた。彼の哲学は、イマヌエル・カントの批判哲学を厳密に解釈し、論理学、倫理学、美学へと体系的に発展させたものであり、特に純粋な理性に基づく普遍的な倫理の構築を目指した。社会的な自由主義の立場から、彼はユダヤ教の倫理的・普遍的側面を強調し、ナショナリズム、特にシオニズムに対しては批判的な姿勢を示した。コーエンの思想は、普遍的な理性と倫理を通じて社会の統合と進歩を追求するものであり、マイノリティのアイデンティティと宗教的価値の共存に哲学的基礎を与えた。
2. 生涯
ヘルマン・コーエンの生涯は、学術的な探求とユダヤ人としてのアイデンティティの探求が深く結びついていた。
2.1. 出生と初期の生活
コーエンは1842年7月4日、アンハルト=ベルンブルク侯国のコースヴィヒで、熱心なユダヤ教徒の家庭に生まれた。彼の父は、コーエンが3歳半の時からユダヤ教の教育を始めた。この幼少期の宗教的背景は、後の彼の哲学、特にユダヤ哲学への関心に大きな影響を与えた。
2.2. 教育
コーエンはデッサウのギムナジウムで教育を受けた後、1859年にヴロツワフのブレスラウ・ユダヤ教神学院に入学し、ラビとなるべく学んだ。しかし、彼の興味は神学から哲学へと移り、ヴロツワフ大学、ベルリン大学、そしてハレ大学で哲学を深く学んだ。ハレ大学では特にアリストテレスの研究に没頭し、学位を取得した。この時期、彼は数学と自然科学の研究にも専念し、その中でイマヌエル・カントの哲学に深く傾倒していった。
2.3. 学術的経歴
1871年、コーエンはカントの『純粋理性批判』の注釈書である『Kants Theorie der Erfahrungカンツ・テオリー・デア・エアファールングドイツ語』(カントの経験の理論)を執筆した。この著作は、当時の著名な哲学者であるフリードリヒ・アルベルト・ランゲに高く評価され、その推薦により、1873年にマールブルク大学哲学部の私講師(Privatdozentプリヴァートドーチェントドイツ語)となった。彼の教授資格論文(Habilitationハビリタツィオーンドイツ語)のテーマは「Die systematischen Begriffe in Kant's vorkritischen Schriften nach ihrem Verhältniss zum kritischen Idealismusディ・ズィステマーティッシェン・ベグリッフェ・イン・カンツ・フォークリティッシェン・シュリフテン・ナッハ・イーレム・フェルヘルトニス・ツム・クリティッシェン・イデアリスムスドイツ語」(カントの批判以前の著作における体系的概念と批判的観念論との関係)であった。
その後、1875年にはマールブルク大学の員外教授(Professor extraordinariusプロフェッサー・エクストラオルディナリウスドイツ語)に選出され、翌1876年にはランゲの講座を引き継ぎ、哲学正教授(Professor ordinariusプロフェッサー・オルディナリウスドイツ語)に就任した。この時期、彼は1880年にマールブルクに赴任したパウル・ナトルプと共に、新カント派マールブルク学派の形成に大きく貢献した。この期間の彼の著名な弟子には、後に独自の哲学を展開するエルンスト・カッシーラーがいる。
コーエンはカント哲学の解釈に精力的に取り組み、1877年には『実践理性批判』の注釈書である『Kants Begründung der Ethikカンツ・ベグリュンドゥング・デア・エーティクドイツ語』(カントの倫理学の基礎付け)を、1889年には『判断力批判』の注釈書である『Kants Begründung der Ästhetikカンツ・ベグリュンドゥング・デア・エステティクドイツ語』(カントの美学の基礎付け)を出版した。また、1902年には「ユダヤ学振興協会」(Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judenthumsゲゼルシャフト・ツア・フェルデルング・デア・ヴィッセンシャフト・デス・ユーデントゥムスドイツ語)の創設者の一人となり、同年11月にベルリンで最初の会議が開催された。彼はまた、フリードリヒ・アルベルト・ランゲの最後の哲学的著作である『Logische Studienロギッシェ・シュトゥーディエンドイツ語』(1877年)を編集・出版し、ランゲの『Geschichte des Materialismusゲシヒテ・デス・マテリアリスムスドイツ語』の長大な序論と批判的補遺の複数バージョンを編集・執筆した。
2.4. 後期の活動とベルリン
1912年、コーエンは当時のアカデミズムにおける反ユダヤ主義勢力の影響を受け、マールブルク大学を辞職し、ベルリンへ移住した。この移住後、彼の関心は哲学体系の構築から、より深く宗教、特にユダヤ教の源泉からの理性の宗教へと向かっていった。
1913年からはユダヤ教学アカデミー(Hochschule für die Wissenschaft des Judentumsホーホシューレ・フュア・ディ・ヴィッセンシャフト・デス・ユーデントゥムスドイツ語)で教鞭を執り、ユダヤ哲学の研究と教育に専念した。この時期の彼の弟子には、後に独自のユダヤ思想を展開するフランツ・ローゼンツヴァイクがいる。彼は1915年に『哲学体系における宗教の概念』を執筆し、彼の代表的なユダヤ哲学の著作となる遺著『Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentumsレリギオーン・デア・フェルヌンフト・アウス・デン・クヴェレン・デス・ユーデントゥムスドイツ語』(ユダヤ教の源泉からの理性の宗教)は、彼の死後1919年に出版された。
3. 哲学
ヘルマン・コーエンの哲学は、カントの批判哲学を基礎としつつ、それを独自の体系へと発展させたものであり、特に倫理学とユダヤ哲学において顕著な貢献をした。
3.1. 新カント主義とマールブルク学派
コーエンは、19世紀後半にドイツで興隆した新カント主義哲学運動において、その最も重要な代表者の一人であり、マールブルク学派の創設者として知られる。マールブルク学派は、カントの哲学を「認識論的理想主義」として再解釈し、特に自然科学の基礎付けとしてのカント哲学の重要性を強調した。彼らは、哲学の課題を経験の根源的な条件を探求することに置き、純粋な思考の法則から知識の客観性を導き出そうとした。コーエンは、カントの「物自体」の概念を、認識の限界を示すものとしてではなく、思考が常に目指すべき理念的な目標として捉え、無限の課題としての認識の進展を強調した。
3.2. カント哲学の解釈
コーエンはカント哲学の深い解釈者として、その主要著作を通じてカントの思想を再構築した。彼はカントの『純粋理性批判』を、経験の客観的妥当性を保証する純粋認識の論理学として捉え、その基礎を徹底的に分析した。また、『実践理性批判』からは純粋意志の倫理学を導き出し、普遍的な道徳法則の根拠を追求した。さらに、『判断力批判』を純粋感情の美学として解釈し、芸術や自然の美が持つ規範的な意味を探求した。これらの解釈は、単なるカント研究に留まらず、彼自身の体系哲学の基礎を築く上で不可欠なものであった。
3.3. 体系哲学
コーエンは、カント哲学の解釈に基づいて、独自の体系哲学を構築した。この体系は、知識、意志、感情という人間の精神の三つの主要な領域に対応する形で、「純粋認識の論理学」「純粋意志の倫理学」「純粋感情の美学」の三部作として展開された。
- 純粋認識の論理学(Logik der reinen Erkenntnisロギク・デア・ライネン・エアケントニスドイツ語、1902年):この著作では、科学的知識の客観性と妥当性の根拠を、純粋な思考の法則の中に求めた。彼は、知識は与えられた対象を単に受動的に受容するのではなく、思考が自ら対象を構成する能動的な活動であると考えた。数学、特に無限小解析の原理を重視し、知識の無限の課題としての性格を強調した。
- 純粋意志の倫理学(Ethik des reinen Willensエーティク・デス・ライネン・ヴィレンスドイツ語、1904年):コーエンの倫理学は、カントの道徳法則の概念を継承しつつ、それを社会的な実践へと拡張した。彼は、道徳は個人の内面的な義務に留まらず、普遍的な正義と連帯の実現を目指すものであると主張した。特に、社会主義的な理想や人権の尊重といった社会的・政治的課題に倫理的基礎を与え、法哲学や国家哲学にもその思想を適用した。
- 純粋感情の美学(Ästhetik des reinen Gefühlsエステティク・デス・ライネン・ゲフュールスドイツ語、1912年):この著作では、美的な経験を単なる感覚的な快楽としてではなく、純粋な感情の領域における認識と倫理の統合として捉えた。芸術や自然の美は、人間が普遍的な理念を直観し、感情的に把握する手段であり、倫理的な理想の実現にも寄与すると考えた。
計画されていた心理学に関する第四巻は、彼の生涯中に執筆されることはなかった。
3.4. ユダヤ哲学と宗教哲学
コーエンの哲学は、晩年になるにつれてユダヤ教の源泉から導き出された宗教哲学へと深く傾倒していった。彼はユダヤ教を単なる歴史的な宗教としてではなく、普遍的な理性と倫理の教えを内包する「理性の宗教」として捉え直した。この視点から、彼はユダヤ教の倫理的一神教を人類全体の道徳的進歩の基礎と見なし、特に預言者の倫理とメシアニズムの概念を重視した。
彼の最も有名なユダヤ哲学の著作は、遺著として出版された『Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentumsレリギオーン・デア・フェルヌンフト・アウス・デン・クヴェレン・デス・ユーデントゥムスドイツ語』(ユダヤ教の源泉からの理性の宗教、1919年)である。この中で彼は、ユダヤ教の神概念を、倫理的な理想としての神、すなわち無限の課題としての善の源泉として解釈した。また、ユダヤ教における「隣人愛」の概念を深く考察し、特に『Die Nächstenliebe im Talmudディ・ネヒステンリーベ・イム・タルムートドイツ語』(タルムードにおける隣人愛)というエッセイは、マールブルクの王立地方裁判所の要請で執筆された。
その他のユダヤ哲学関連の著作には、『Die Kulturgeschichtliche Bedeutung des Sabbatディ・クルトゥールゲシヒトリッシェ・ベドイトゥング・デス・ザバートドイツ語』(安息日の文化史的意義、1881年)、『Ein Bekenntniss in der Judenfrageアイン・ベケントニス・イン・デア・ユーデンフラーゲドイツ語』(ユダヤ人問題に関する告白、1880年)、『Das Problem der Jüdischen Sittenlehreダス・プロブレーム・デア・ユーディッシェン・ズィッテンレーレドイツ語』(ユダヤ教道徳論の問題、1899年)、『Liebe und Gerechtigkeit in den Begriffen Gott und Menschリーベ・ウント・ゲレヒティヒカイト・イン・デン・ベグリッフェン・ゴット・ウント・メンシュドイツ語』(神と人間という概念における愛と正義、1900年)、『Autonomie und Freiheitアウトノミー・ウント・フライハイトドイツ語』(自律と自由、1900年)、『Deutschtum und Judentumドイチュトゥム・ウント・ユーデントゥムドイツ語』(ドイツ性とユダヤ性)、『Die Ethik des Maimonidesディ・エーティク・デス・マイモニデスドイツ語』(マイモニデスの倫理学)などがある。これらの著作を通じて、コーエンはマイノリティとしてのユダヤ人のアイデンティティと、その宗教的価値が普遍的な倫理に貢献しうることを示し、当時の反ユダヤ主義が台頭する社会において、ユダヤ教の精神的・道徳的使命を哲学的に擁護した。
4. 主要著作
ヘルマン・コーエンの主要な哲学書、論文、およびユダヤ哲学関連著作は以下の通りである。
4.1. 原著
- 『Die Platonische Ideenlehre Psychologisch Entwickeltディ・プラトーニッシェ・イデーエンレーレ・プシュヒッシュ・エンヴィッケルトドイツ語』(プラトン的イデア論の心理学的発展)、1866年
- 『Mythologische Vorstellungen von Gott und Seeleミュートロギッシェ・フォアシュテルングエン・フォン・ゴット・ウント・ゼーレドイツ語』(神と魂に関する神話的観念)、1869年
- 『Die dichterische Phantasie und der Mechanismus des Bewusstseinsディ・ディヒテリッシェ・ファンタズィー・ウント・デア・メカニスムス・デス・ベヴストザインスドイツ語』(詩的想像力と意識のメカニズム)、1869年
- 『Zur Kontroverse zwischen Trendelenburg und Kuno Fischerツア・コントロフェルゼ・ツヴィッシェン・トレンデレンブルク・ウント・クーノ・フィッシャードイツ語』(トレンデレンブルクとクーノ・フィッシャーの論争について)、1871年
- 『Kants Theorie der Erfahrungカンツ・テオリー・デア・エアファールングドイツ語』(カントの経験の理論)、ベルリン、1871年、第2版1885年
- 『Kants Begründung der Ethikカンツ・ベグリュンドゥング・デア・エーティクドイツ語』(カントの倫理学の基礎付け)、ベルリン、1877年
- 『Platon's Ideenlehre und die Mathematikプラトンズ・イデーエンレーレ・ウント・ディ・マテマティークドイツ語』(プラトンのイデア論と数学)、マールブルク、1878年
- 『Die Kulturgeschichtliche Bedeutung des Sabbatディ・クルトゥールゲシヒトリッシェ・ベドイトゥング・デス・ザバートドイツ語』(安息日の文化史的意義)、1881年
- 『Ein Bekenntniss in der Judenfrageアイン・ベケントニス・イン・デア・ユーデンフラーゲドイツ語』(ユダヤ人問題に関する告白、1880年)
- 『Das Prinzip der Infinitesimalmethode und seine Geschichte: ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritikダス・プリンツィープ・デア・インフィニテズィマールメトーデ・ウント・ザイネ・ゲシヒテ・アイン・カピテル・ツア・グルントレーグング・デア・エアケントニスクリティクドイツ語』(無限小解析法の原理とその歴史:認識批判の基礎付けに関する一章)、ベルリン、1883年
- 『Von Kant's Einfluss auf die Deutsche Kulturフォン・カンツ・アインフルス・アウフ・ディ・ドイチェ・クルトゥールドイツ語』(ドイツ文化に対するカントの影響について)、ベルリン、1883年
- 『Kants Begründung der Aesthetikカンツ・ベグリュンドゥング・デア・エステティクドイツ語』(カントの美学の基礎付け)、ベルリン、1889年
- 『Zur Orientierung in den Losen Blättern aus Kant's Nachlassツア・オリエンティールング・イン・デン・ローゼン・ブレッテルン・アウス・カンツ・ナッハラスドイツ語』(カントの遺稿からの散逸した論文の方向性について)、1890年
- 『Leopold Schmidtレオポルト・シュミットドイツ語』(レオポルト・シュミット)、1896年
- 『Das Problem der Jüdischen Sittenlehreダス・プロブレーム・デア・ユーディッシェン・ズィッテンレーレドイツ語』(ユダヤ教道徳論の問題)、1899年
- 『Liebe und Gerechtigkeit in den Begriffen Gott und Menschリーベ・ウント・ゲレヒティヒカイト・イン・デン・ベグリッフェン・ゴット・ウント・メンシュドイツ語』(神と人間という概念における愛と正義)、1900年
- 『Autonomie und Freiheitアウトノミー・ウント・フライハイトドイツ語』(自律と自由)、1900年
- 『Logik der reinen Erkenntnisロギク・デア・ライネン・エアケントニスドイツ語』(純粋認識の論理学)、1902年
- 『Ethik des reinen Willensエーティク・デス・ライネン・ヴィレンスドイツ語』(純粋意志の倫理学)、1904年
- 『Ästhetik des reinen Gefühlsエステティク・デス・ライネン・ゲフュールスドイツ語』(純粋感情の美学)、1912年
- 『Spinoza über Staat und Religion, Judentum und Christentumスピノーザ・ユーバー・シュタート・ウント・レリギオーン・ユーデントゥム・ウント・クリステントゥムドイツ語』(スピノザの国家と宗教、ユダヤ教とキリスト教について)、1915年
- 『Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentumsレリギオーン・デア・フェルヌンフト・アウス・デン・クヴェレン・デス・ユーデントゥムスドイツ語』(ユダヤ教の源泉からの理性の宗教)、1919年(遺著)
- 『Jüdische Schriftenユーディッシェ・シュリフテンドイツ語』(ユダヤ著作集)、ブルーノ・シュトラウス編、ベルリン、1924年(死後出版)
4.2. 日本語訳
- 村上寛逸訳『ヘルマン・コーヘン哲学の体系』全3巻、第一書房
- 第1巻『純粋認識の論理学』1932年
- 第2巻『純粋意志の倫理学』1933年
- 第3巻『純粋感情の美学』1939年
- 児玉達童訳『新理想主義哲学序論』大村書店、1921年
- 高田三郎訳『プラトンのイデア論と数学』岩波書店、1928年
5. 思想と批判
コーエンの思想は、普遍的な理性と倫理の追求に焦点を当てており、当時の社会・政治的課題に対しても明確な立場を示した。
5.1. シオニズムへの批判
ヘルマン・コーエンは、シオニズムに対して明確な批判的立場を取った。彼は、シオニズムがユダヤ国家の創設を目指すことは、「ユダヤ人を歴史に回帰させる」ことにつながると主張した。コーエンの哲学において、ユダヤ教は本質的に「非歴史的」な性格を持つものであり、その精神的・道徳的使命は、特定の民族国家を形成するというナショナリズム的目標をはるかに超えるものだと考えた。彼は、ユダヤ教の普遍的な倫理的教えが、いかなる民族主義的排他性も超越し、人類全体の進歩に貢献すべきであると主張した。この見解は、彼の普遍主義的な哲学と深く結びついており、社会統合とマイノリティの権利擁護に対する哲学的含意を持つものであった。彼は、ユダヤ人がドイツ社会に完全に統合されることを理想とし、宗教的アイデンティティと国民的アイデンティティの調和を追求した。
5.2. その他の活動
コーエンは、哲学研究および普及のために様々な学術団体設立や編集活動に貢献した。彼は「ユダヤ学振興協会」の創設者の一人であり、ユダヤ学の学術的研究を推進した。また、フリードリヒ・アルベルト・ランゲの遺稿を編集・出版するなど、同時代の学者の業績の保存と普及にも尽力した。これらの活動は、彼の哲学的探求が単なる思弁に留まらず、学術コミュニティの発展と知識の共有にも深く関与していたことを示している。
6. 評価と影響
ヘルマン・コーエンの哲学的業績は、同時代および後世の学界に多大な影響を与え、その思想は今日に至るまで様々な形で評価され続けている。
6.1. 学界による評価
コーエンは、新カント主義マールブルク学派の創設者として、カント哲学の厳密な解釈と体系化に貢献したことで高く評価されている。彼の哲学は、知識の客観性、普遍的な倫理、そして美の規範的意味を純粋な理性から導き出そうとする試みとして、多くの学者に影響を与えた。彼は「19世紀で最も重要なユダヤ人哲学者」と称されることもあり、ユダヤ思想を普遍的な理性哲学の中に位置づけようとしたその試みは、特にユダヤ学の分野で重要な意義を持つ。彼の弟子であったエルンスト・カッシーラーやフランツ・ローゼンツヴァイクは、それぞれ異なる形でコーエンの思想を受け継ぎ、発展させていった。
6.2. 後世への影響
コーエンの哲学は、後代の哲学者や思想家、特にドイツ観念論以降の哲学、倫理学、ユダヤ哲学の分野に具体的な影響を与えた。彼の倫理学は、普遍的な道徳法則と社会正義の追求を強調し、20世紀の社会倫理や人権思想の発展に間接的に貢献した。また、彼のユダヤ哲学は、ユダヤ教を単なる民族的宗教ではなく、普遍的な理性の教えとして再評価する動きを促し、現代ユダヤ思想の形成に大きな影響を与えた。イスラエルには彼のシオニズム批判にもかかわらず、テルアビブにヘルマン・コーエン通りが存在するなど、彼の思想が持つ普遍的な価値が認識されていることを示している。彼の批判的思考と、理性に基づいた社会変革への情熱は、後世の多くの思想家にインスピレーションを与え続けている。
7. 死没
ヘルマン・コーエンは1918年4月4日、ベルリンで75歳で死去した。彼の遺体はベルリンのヴァイセンゼー墓地に埋葬された。