1. 概要
ムハンマド・アラムは、1826年から1828年にかけてブルネイ・ダルサラーム国のスルターンであったとされる人物である。その強硬で厳格な態度から、「火の王(Raja Apiラジャ・アピマレー語)」や「Sultan Marak Berapiスルターン・マラック・ベラピマレー語」といった異名で知られている。彼の統治は、その独裁的かつ強圧的な性格により、ブルネイ国民の広範な反発を招き、正統な後継者であるペンギラン・ムダ・オマル・アリ・サイフディン2世との間に深刻な王位継承紛争と内戦を引き起こした。この内戦は、彼の死によって終結したとされている。
彼の治世は、ブルネイが脆弱で保護を必要とする王国と認識されていた時代にもかかわらず、タンジュン・ダトゥからキマニスに至る広大な領土を維持した時期と重なる。しかし、その強権的な統治は、国内外において多くの批判と論争を巻き起こし、特に外国の使節団からは冷酷で扱いがたい人物と評された。民衆の間では、彼が火を吐き、空を飛び、不死身となるために血を求めるという神話的な伝承が生まれ、その残忍な統治を象徴する存在として語り継がれた。
本稿では、ムハンマド・アラムの生い立ちから統治、そしてその死に至るまでの生涯を、彼の強圧的な統治がブルネイ社会に与えた影響と、それが引き起こした内戦に焦点を当て、その歴史的評価を多角的に分析する。
2. 初期生い立ちおよび背景
ムハンマド・アラムは、スルターン・ムハンマド・カンズル・アラムの長男として生まれた。彼の生母はペンギラン・アナク・サラマ・イブヌ・ペンギラン・セリ・ラマであり、父の第二夫人であった。父ムハンマド・カンズル・アラムは、スルターン・オマル・アリ・サイフディン1世の息子であるスルターン・ムハンマド・タジュディンの異母兄弟にあたるため、ムハンマド・アラムはスルターン・ムハンマド・タジュディンの甥にあたる。
2.1. 家族関係
ムハンマド・アラムの父はムハンマド・カンズル・アラム、母はペンギラン・アナク・サラマ・イブヌ・ペンギラン・セリ・ラマである。父の最初の妻であるペンギラン・アナク・サレハとの間には、ラジャ・イステリ・ノララムという異母姉がおり、彼女は後にスルターン・オマル・アリ・サイフディン2世の母となる。兄弟にはペンギラン・ムダ・ハシムとペンギラン・バダルディンがいる。
妻はペンギラン・ラジャ・イステリ・ヌルラナ・アブドゥッラーであった。子供たちには、ペンギラン・アナク・ヌル・アラム、ペンギラン・アナク・サラマ、ペンギラン・ムダ・ムハンマド・オマル・ジャヤがいた。彼の子孫は現在も存続しているとされており、特にサバ州のカンポン・セガリウードでその系譜が確認されている。
2.2. 初期活動および影響
ムハンマド・アラムは、父の治世中に国内外でその名を知られるようになった。彼は父と共にブルネイの商業問題において大きな経済的影響力を持ち、ウィリアム・ファーカアと直接書簡を交わすなど、商業活動に深く関与していた。彼は富裕であったにもかかわらず、父の権威を尊重し、ファーカアとの書簡の返信を父に委ねることで、当時のスルターンへの服従を示した。アンナベルの分析によれば、父との協力関係は、王室内で彼が影響力を持つ一方で、従順な役割を果たしていたことを示している。ムハンマド・カンズル・アラムは彼を「我らの友(sahabat kitaサハバット・キタマレー語)」と呼び、「我らの息子(anakanda kitaアナカンダ・キタマレー語)」とは呼ばなかったことから、父の政権において彼がかなりの権威を持っていたことが示唆される。
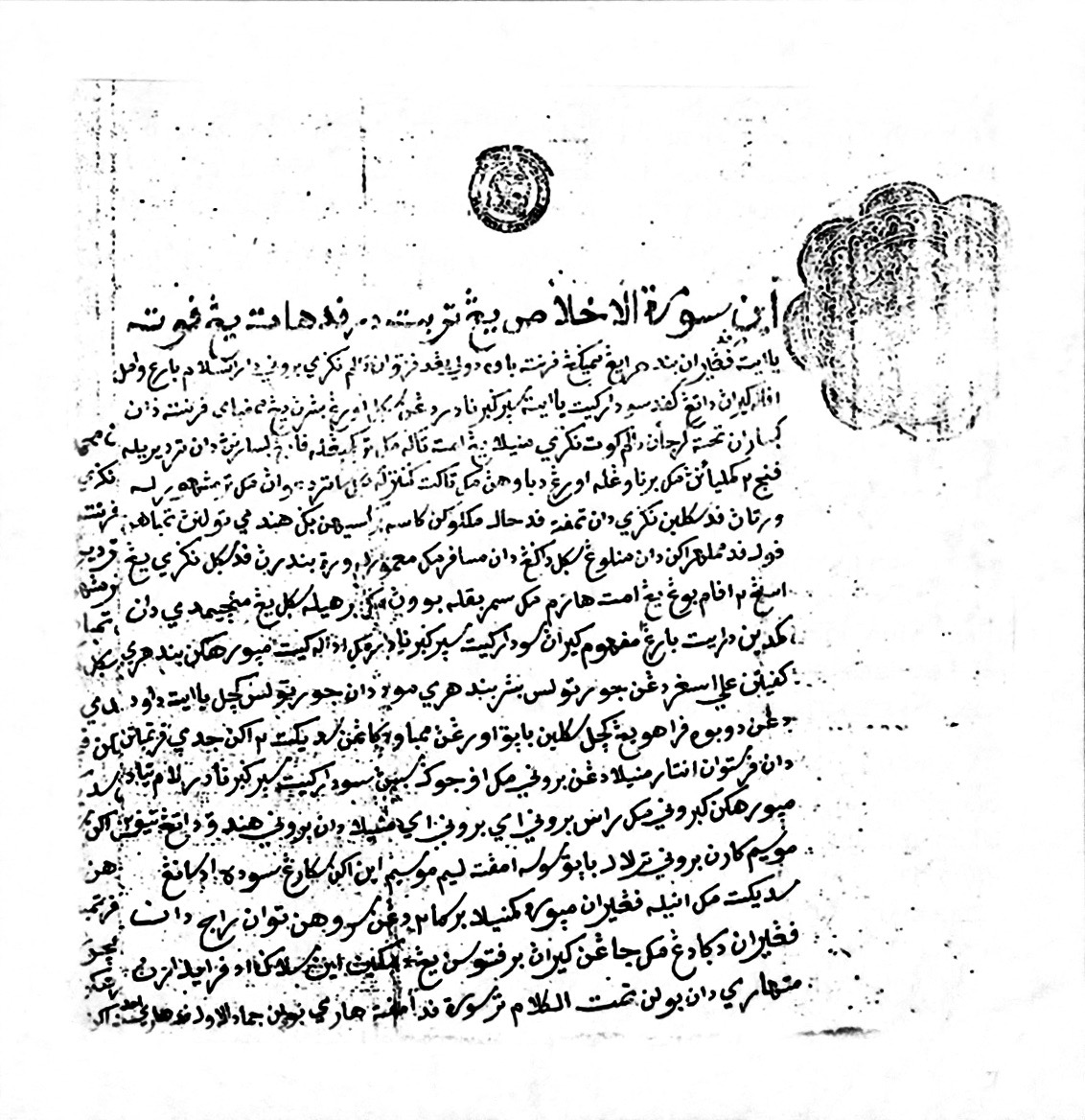
1809年に発生したシ・メラの挑戦として知られる事件では、イギリスの士官がブルネイを訪れた際、スルターンを介さずに直接ムハンマド・アラムのもとへ向かうという王室の慣習を破った。この士官がラパウでの謁見中に物理的に介入し、中尉を数フィート投げ飛ばしたことで緊張が高まった。現地の伝承によれば、この行動は、ブルネイの領土を奪うという野心を象徴するとされる「コマース」という名の猟犬を巡るシ・メラの挑戦への報復として行われたという。彼の断固たる対応は、植民地主義に対するブルネイの利益の保護と、父の尊厳の擁護として解釈された。
ハドラマウトのシャリフ・ハサン・アル・ハブシが、ブルネイを半日で占領できると主張してムハンマド・アラムに挑戦した際も、彼はブルネイの主権維持における自身の重要性を示した。彼は兄弟や地元の指導者たちの助けを借りて、ウジュン・サポ・ムアラ・ブサールでアル・ハブシに挑戦した。アル・ハブシは彼の粘り強さを見て降伏し、以前の脅迫にもかかわらずスルターンとムハンマド・アラムに許しを請い、赦免された。この時期、彼は父であるスルターン・ムハンマド・カンズル・アラムよりも大きな影響力を持っているかのように見えた。
19世紀を通じて、ボルネオ島の沿岸都市や港では海賊行為が横行し、交易路や地域の安定を深刻に脅かしていた。これに対し、イギリス政府はロバート・C・ガーナム船長を派遣し、ポンティアナック、バンジャルマシン、ブルネイを除くボルネオの港を封鎖する措置を講じた。この行動の目的は、海賊行為を減らし、商業を集中させることにあった。ガーナムや他の外国使節は、ムハンマド・アラムを厳しく気難しい人物と見ており、彼らは任務中に彼から抵抗を受けた。1813年、ガーナムは父であるスルターンに、これら3つの場所に公認港を建設するよう援助を求めた。謁見式でのムハンマド・アラムの観察的な態度はガーナムを不安にさせ、彼は急いで用事を済ませたという。
ムハンマド・アラムは父の政権において絶大な権威と支配力を持っていたようで、父の死に先立ち、副スルターンの地位に就いていた可能性さえある。1826年の父の病気や、1823年にスルターンの代理としてオランダ大使を受け入れたことなど、この時期に彼がブルネイ統治においてより大きな責任と権力を引き継いだことを示す兆候がある。父は彼が王位を継ぐことを望んだが、クリス・シ・ナガといった象徴的な品々は手元に留め、両者の間の権力分担を維持した。
ムハンマド・アラムの性格は、H・R・ヒューズ=ハレットが指摘した「スピアーズ事件」によっても示されている。この事件は、スピーズ船長がムハンマド・アラムを王族の一員としてではなく、単なる商人仲間として扱ったことが原因で起こり、これは無礼な行為であった。スピーズ船長の自己中心的な行動、具体的には予定されていた午後2時の取引時間前にブルネイを出発したことに対し、ムハンマド・アラムは父に、ブルネイがイギリスに弄ばれているのではないかと調査するよう求めた。スルターンは外国貿易に対し「行儀よくする」よう求める強い声明で応じたが、ファーカアはスピーズ船長を懲戒処分のためベンガルのイギリス政府に報告させることで事態を収拾した。
3. 統治期間および主要活動
ムハンマド・アラムがスルターンとして統治した時期は、ブルネイの歴史において激動の時代であった。特に1826年から1828年の間、彼は王位を巡る激しい紛争と内戦に直面した。
3.1. 王位継承紛争
ムハンマド・アラムは、父の承認を得て自身の即位を確信していたが、完全なスルターン権力を象徴する伝統的な王冠とクリス・シ・ナガを欠いていた。彼の即位はブルネイ国民の間で不評であった。15年前に父が、当時の推定後継者がまだ未成年であった時に権力を握ったのとは対照的に、ペンギラン・ムダ・オマル・アリ・サイフディンは、王位に就くのにふさわしいと広く認識される有能な若者に成長していた。ムハンマド・アラムの支持基盤は、ブルネイ内の商業関係者にほぼ限定されており、彼の権威主義的な傾向は彼と臣民との間の亀裂を深め、彼の治世に対する広範な敵意を助長した。父の治世中、ブルネイを外国の欺瞞から守る彼の厳格な態度が評価され、恐るべき指導者として描かれていたにもかかわらず、彼の行動は外国の使節団をも遠ざけ、国内の不満を悪化させ、最終的には彼を帝国で最も嫌われ、恐れられる人物として孤立させた。
この紛争は、ムハンマド・アラムが正統な後継者であるペンギラン・ムダ・オマル・アリ・サイフディンの代わりに王位に就くことを選択したときに始まった。この対立の起源は1804年に遡る。この年、スルターン・ムハンマド・タジュディンは息子のスルターン・ムハンマド・ジャマルル・アラムに王位を譲った。しかし、スルターン・ムハンマド・タジュディンは間もなく死去し、幼い息子であるペンギラン・ムダ・オマル・アリ・サイフディンを推定後継者として残した。スルターン・ムハンマド・タジュディンは、孫のために王位を再開した後、1806年に「ペンギラン・ディガドン・アヤ」の摂政を求め、ペンギラン・ムダ・オマル・アリが成人するまで助言者を選ぶことを約束した。これはタジュディンの健康が悪化していたためである。しかし、「ペンギラン・ディガドン・アヤ」は、スルターン・ムハンマド・タジュディンの死後、1807年に自らをスルターンと宣言し、条約の条件を破った。彼は息子であるムハンマド・アラムと共に、自身の死である1826年まで統治した。スルターン・ムハンマド・カンズル・アラムが死去した際、彼は絶対的な権威を示す王室の記章を身につけていなかったにもかかわらず、ムハンマド・アラムを後継者に選んだ。これがムハンマド・アラムとオマル・アリ・サイフディン2世の支持者との間で公然たる紛争を引き起こした。
3.2. 内戦
父の死後、およそ1826年から1828年の間にブルネイで内戦が勃発した歴史的背景がある。ペンギラン・ムダ・オマル・アリ・サイフディンとその同盟者たちは、1826年2月15日にケイガンガン島へ移動し、おそらく自身の安全を懸念してスルターンを自称し、防衛体制を築いた。内戦中のムハンマド・アラムの専制政治、特に彼が不死身を保つために血の儀式を要求したという報告は、この移動につながった可能性がある。これは、ムハンマド・アラムがスルターン・オマル・アリ・サイフディン2世の支持者を威嚇するために残虐行為や人質取りを利用し、冷酷な「火の王」としての彼のイメージを固めたものと見なすことができる。

ブルネイの人々、特にカンポン・ブロン・ピンガイ(現在のカンポン・ブロン・ピンガイ・アイル)とその周辺地域の住民は、ほとんどがオマル・アリ・サイフディン2世を支持していた。「ペヒン・ダト・ペルダナ・メンテリ」アブドゥル・ハクが率いるムハンマド・アラムに対する反乱は、オマル・アリ・サイフディンが王位に対する正統な主張を持っているという彼らの確信によって動機づけられた。カンポン・ブロン・ピンガイは、イスラム教の教義と正義の価値観を遵守する宗教的学者を含む、高度な教育を受けた住民が多いことで知られていた。このことが、これらの人々がオマル・アリ・サイフディンを支持した理由を説明するのに役立った。過去には、彼らは積極的な交易を通じてペンギラン・ムダ・ムハンマド・ユソフとムハンマド・アラムを支持し、ブルネイ経済に貢献していた。しかし、彼が権力を握ると、村人たちは彼に反感を抱き、オマル・アリ・サイフディンの支持者たちと共にケイガンガン島に集結し、彼の支配に対する封鎖を築いた。一方、彼の支持は親しい仲間や家族に限定されており、彼の厳しく独裁的な統治が一般大衆の支持を失わせたことを浮き彫りにしている。
3.3. 領土防衛および統治
ムハンマド・アラムの統治期間中、彼はブルネイの領土を防衛するための活動を行った。彼は1822年から1824年の間、スルターンとして統治したとも伝えられている。この時期、タンジュン・キドゥルン地域がスルクの海賊集団によって攻撃されようとしているという情報が届いた際、彼は軍隊を率いてビントゥルへ向かい、この地域を守った。タンジュン・キドゥルンで海賊を撃退した後、彼はビントゥルにあるクアラ・セガンに要塞を築くことを決定した。そこが彼と彼の従者たちが最初に立ち寄った場所であり、その後クアラ・セガンに定住した。
彼は従者たちと共にタタウまで航海し、そこでタタウの統治者であるラジャ・カヤ・ジャバンとその妻マイイング・ラビアと出会った。そこで彼は妻となるラナと出会い、ラナはペンギラン・イステリ・ヌル・ラナ・アブドゥッラーの称号を与えられ、当時の宗教大臣であったペンギラン・サヒブル・ハティブ・ハジ・ダミット・イブニ・ハティブ・ベキルによって結婚の儀式が執り行われた。敬虔なブルネイの統治者として、彼はラナを妻に迎えた。彼はまた、「スルターン・パンジ・アラム」および「パドゥカ・ラジャ」の称号を持っていたとされ、1895年に即位したと伝えられる。サラワク周辺の地域社会では、彼がサラワクのビントゥルにあるクアラ・セガン村のブキット・セルウェイに埋葬されたという話があるが、これはまだ不明瞭である。
3.4. 統治終了および事後
ムハンマド・アラムの1828年の死は、ブルネイの内戦の終結を告げるものであったが、その死の経緯については諸説ある。広く受け入れられている説によれば、ムハンマド・アラムはチェルミン島にいた際、彼を暗殺するために刺客が送られたという。ラジャ・イステリ・ノララムはスルターン・オマル・アリ・サイフディン2世の母であり、ムハンマド・アラムの異母姉であった。

これらの刺客は、任務の重大性を認識しつつ彼に近づいた。驚くべきことに、彼は協力し、自身の見かけ上の不死身を打ち破る方法を彼らに助言した後、島で埋葬され、絞殺されたという。しかし、彼のよく知られた怒りや目撃証言の欠如から、歴史家ペヒン・ジャミルはこの話を疑問視している。
ムハンマド・アラムの統治終焉に関するもう一つの解釈は、第二の物語によって提供されている。この説では、彼は刺客に暗殺されたのではなく、敗北を認めて自らブルネイを去ったとされている。彼はよりシンプルな生活を送るためにサバ州のプタタンに移住したと言われている。ブルネイ歴史センターによる2009年の調査で、プタタンでムハンマド・アラムのものとされる墓石が発見されたことで、この説には信憑性が与えられた。チェルミン島や王室霊廟に彼の埋葬の具体的な証拠は発見されていないものの、同センターは、その墓石がブルネイで発見された王室の墓石に匹敵すると指摘している。
ムハンマド・アラムの治世を巡る出来事の年表は、ブルネイにおける政治的混乱と継承紛争を示しており、これらが内戦と呼べるかどうかを判断するために必要である。この時期の内部の混乱、派閥間の争い、正統性への挑戦を明らかにする重要な情報源には、地元の年代記やペヒン・ジャミルなどの学術的評価が含まれる。言及された兆候は、指導者を巡る顕著な内部対立と暴力的な紛争を示しており、これは一般的に内戦と関連付けられる特徴と一致する。しかし、確固たる結論を導き出すには、さらなる歴史的記録の調査が必要である。
ムハンマド・アラムの弟であるペンギラン・ムダ・ハシムは、1820年代の失敗した反乱に参加したが、彼の失脚はブルネイにおける安定した、しかし厳格な統治システムの終焉を意味したと述べている。彼の死後、兄弟や他の親族は散り散りになり、一部はサラワクに移住した。
4. 評判および評価
ムハンマド・アラムの評判は、その強硬な性格と独裁的な統治によって形成された。彼は「火の王」という異名が示すように、民衆から恐れられ、その行動は多くの論争を巻き起こした。
4.1. 別名および象徴性
ムハンマド・アラムは、その厳しく強硬な態度から、マレー語で「火の王(Raja Apiラジャ・アピマレー語)」、または「Sultan Marak Berapiスルターン・マラック・ベラピマレー語」という異名で知られている。マレー語の資料では、「Ria Apuiリア・アプイマレー語」とも呼ばれ、これは彼が生まれた際に火に囲まれていたという伝説に由来するとも言われている。
口頭伝承では、ムハンマド・アラムは暴君として描かれ、怒ると火を吐き、不死身の力を得るために血を求めて空を飛ぶといった超自然的な力を持つとされた。これは、彼が民衆にとってどれほど恐ろしく、不安な存在であったかを示唆している。歴史家たちは、これらの民間伝承が「ブルネイ王家系譜(Silsilah Raja-Raja Bruneiシルシラ・ラジャ・ラジャ・ブルネイマレー語)」やヨーロッパの記録と共通の要素を持つことを指摘し、彼の時代の状況を裏付けるものとして利用している。彼はまた、「スルターン・タンズル・アラム」という称号も持っていたとされ、これは1960年代にペンギラン・ベサール・イブニ・ペンギラン・アナク・サプトゥ・イブニ・スルターン・ハシム・ジャリルル・アラム・アカマディンによって確認されたという。
4.2. 批判および論争
ムハンマド・アラムは、その実際の能力よりも、厳しく容赦ない指導者としての評判によって否定的に描かれることが多い。この呼称は、彼の残酷な君主制が国民に苦痛を与えたことを示唆しており、これは不人気な王を静かに批判するマレーの慣習への言及である。さらに、彼が持つとされる飛行能力や人血への渇望といった超自然的特性が、民間伝承の中で「Raja Bersiongラジャ・ベルションマレー語」のような神話上の人物と比較されることは、彼の権力乱用と厳格な統治に対する比喩的な非難として機能している。
ムハンマド・アラムの性格には、あらゆる交流において真剣で厳格であること、そしてしばしば命令に従うことを拒否したり、無礼な態度を示したりする傾向があった。これらの特性は、彼の統治における不寛容さの一因となった可能性がある。彼はまた、自分の思い通りにならないことすべてに対して全く不寛容であったと描写されることもある。いくつかの記述における彼の行動は、彼が独占的な性質を持っていることを示しており、これはある程度正確である。
4.3. ヨーロッパ資料および伝承
スタンフォード・ラッフルズやファーカアの著作のようなヨーロッパの情報源は、地元の物語を裏付け、さらなる視点を提供している。伝聞や二次情報が含まれる可能性はあるものの、ヨーロッパの直接的かつ客観的な文献は、地元の主観的な情報源とは対照的である。アンナベル・テー・ギャロップによる、父の治世中のイギリスの記録に関する広範な研究は、ムハンマド・アラムの厳しい性格を明らかにしている。彼は外国の使節団に対して疑念を抱き、ブルネイとその王室の保護者としての役割を自らに課していた。これが、彼が多くの外国使節団に対して冷酷で厳しい態度を取った理由を説明している。
5. 子孫および遺産
ムハンマド・アラムの子孫は、ブルネイの歴史と文化に長期的な影響を与え、その系譜は現在も続いている。
5.1. 子孫の確認
ムハンマド・アラムの子供たちには、ペンギラン・アナク・ヌル・アラム、ペンギラン・アナク・サラマ、ペンギラン・ムダ・ムハンマド・オマル・ジャヤがいた。特にペンギラン・アナク・ヌル・アラムは、その敬虔さと勇敢さからイバン族の戦士たちに恐れられたと伝えられており、ブルネイの40の王国の旗を携えて海賊を打ち破ったこともあるという。
ムハンマド・アラムの子孫は今日まで存続しており、いくつかの記録に基づいている。ペンギラン・ベサール・イブニ・ペンギラン・アナク・サプトゥ・イブニ・スルターン・ハシム・ジャリルル・アラム・アカマディンは、当時のブルネイの統治者であったスルターン・オマル・アリ・サイフディン3世の代理として、1960年代にサバ州サンダカンのカンポン・セガリウードを自ら訪れた。そこで、ムハンマド・アラムの息子であるペンギラン・セルディン(サイフディン)の子孫が、カンポン・セガリウードの村人として現在も生活していることが発見された。
これは、スルターン・オマル・アリ・サイフディン3世の代理による調査の結果である。ヤン・ムリア・トゥアン・ハジ・オマル・カビグ・ビン・ペンギラン・スライマンという住民が発見され、彼の祖先の物語や村の起源について語られた。ペンギラン・ベサール・イブニ・ペンギラン・アナク・サプトゥ・イブニ・スルターン・ハシム・ジャリルル・アラム・アカマディンは、ヤン・ムリア・トゥアン・ハジ・オマル・カビグ・ビン・ペンギラン・スライマンをブルネイ・ダルサラーム国に連れて行き、1961年頃にイスタナ・ダルル・ハナでスルターン・オマル・アリ・サイフディン3世の前で、ペンギラン・ゴマラン・キソル・エマスからの口頭による系譜を提出した。この系譜の提出の結果、ヤン・ムリア・トゥアン・ハジ・ペンギラン・ハジ・オマル・カビグ・ビン・ペンギラン・スライマンは、ダトゥ・パンリマ・ガランと刻まれた短剣の鞘が付属する黒い王宮の衣装一式を授与された。
以下は、ムハンマド・アラムの子孫とされる人物の系譜である。
- ペンギラン・セルディン(サイフディン)
- ペンギラン・デラマン(ドゥラマン)・リアウ
- ペンギラン・ゴマラン・キソル・マス
- ペンギラン・タバロン
- ペンギラン・ムダ
- ペンギラン・テロック
- ペンギラン・タリブ(タリド)
- ペンギラン・スライマン
- ペンギラン・ハジ・オマル・カビグ