1. Biography
ハインリヒ・フリードリヒ・ヴィルヘルム・ゲゼニウスの生涯は、学問への深い献身と、当時の保守的な神学界との間の論争に彩られたものであった。

1.1. Early life and education
ゲゼニウスは1786年2月3日にノルトハウゼンで生まれた。1803年、彼はヘルムシュテット大学で哲学とキリスト教神学を学び始めた。この時期、ハインリヒ・フィリップ・コンラート・ヘンケが彼に最も大きな影響を与えた教師であった。その後、彼はゲッティンゲン大学に移り、そこでヨハン・ゴットフリート・アイヒホルンとトーマス・クリスティアン・ティヒセンから指導を受けた。1806年にゲッティンゲン大学で博士号を取得し、その後すぐに同大学のレペテント(Repetent)および私講師(Privatdozent)となった。彼は後に、アウグスト・ネアンダーが彼のヘブライ語における最初の生徒であったことを誇りにしていたと語っている。
1.2. Academic career
1810年2月8日、ゲゼニウスはハレ大学の神学の員外教授となり、翌1811年6月16日には正教授に昇進した。彼はその後、他からの多くの好条件の招聘を断り、残りの生涯をハレで過ごした。彼は30年以上にわたり非常に規則的に教鞭を執り、その講義は非常に興味深く、講義室は常に満員であった。1810年までに彼の講義には500人以上の学生が出席し、これは大学全体の学生数の約半分に相当した。晩年には約500人の学生が彼の講義に出席するようになった。
彼の教授活動が中断されたのは、1813年から1814年にかけてのドイツ解放戦争による大学の閉鎖期間、そして二度の長期にわたる学術調査旅行の際のみであった。最初の旅行は1820年で、同僚のヨハン・カール・ティーロ(1794年-1853年)と共にパリ、ロンドン、オックスフォードを訪れ、希少な東洋写本の調査を行った。二度目は1835年にフェニキア語研究の一環としてイギリスとオランダを訪れた。彼はドイツで最も人気のあるヘブライ語および旧約聖書導入・聖書釈義の教師となった。彼の著名な弟子には、ペーター・フォン・ボーレン、C. P. W. グランベルク、A. G. ホフマン、ヘルマン・フプフェルト、エミル・レーディガー、J. C. F. トゥーフ、J. K. W. ファートケ、テオドール・ベンフェイなどがいる。
1.3. Later life and death
1827年、ゲッティンゲン大学でアイヒホルンの後任となる誘いを断った後、ゲゼニウスはConsistorialratコンシストリアルラートドイツ語(教会参事官)に任命された。しかし、1830年には、友人であり同僚のユリウス・アウグスト・ルートヴィヒ・ヴェグシャイダーと共に、エルンスト・ヴィルヘルム・ヘングステンベルクとその一派から『Evangelische Kirchenzeitungドイツ語』誌上で激しい口頭攻撃を受けた。これは彼の合理主義的な見解と、聖書に記述された奇跡の記述を軽視した講義内容が原因であった。
その後、彼は個人的な苦難に悩まされた。1833年には肺の病により危篤状態に陥り、1835年には3人の子供を亡くした(一部の記述では「数人」の子供が亡くなったとされている)。これらの出来事に続き、彼は様々な身体的な不調に苦しめられた。彼は1842年に胆石による長きにわたる苦痛の末、ハレで亡くなった。彼の墓は大学の近くにあり、伝統によれば、ハレ大学の神学生たちは試験の前に敬意を表して彼の墓に石を置くという慣習がある。
2. Major works
ゲゼニウスは、東洋学および文献学の分野において画期的な多くの学術活動と著作を残した。
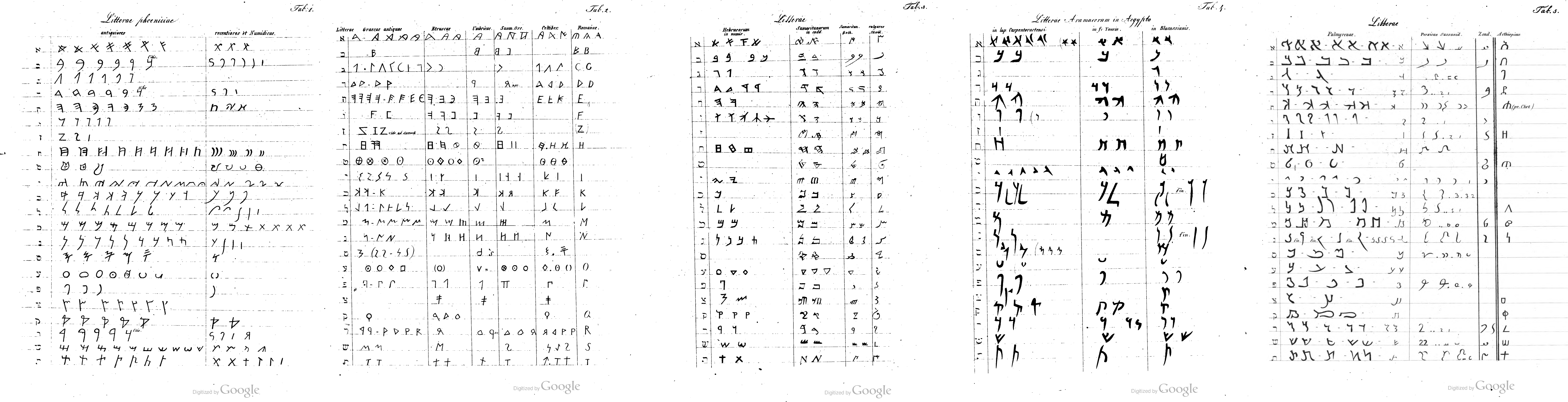
2.1. Lexicography and grammar
ゲゼニウスはヘブライ語およびアラム語の辞書と文法書の編纂に多大な貢献をした。
彼の最初のヘブライ語辞典(ドイツ語テキスト)は1806年から1807年の冬に作成され、数年後にライプツィヒのF. C. W. フォーゲル社から出版された。この出版社は以降、彼の辞典の全版を刊行することとなる。1815年には最初の辞典を約半分に短縮しつつも大幅に改善した版が出され、これはドイツ語版で4版を重ね、ラテン語版も1版刊行された。これらの版はそれぞれ、以前の版よりも内容が大幅に増補され、改善されたものとなった。
彼の『Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testamentドイツ語』(『ヘブライ語・カルデア語ハンド辞典』)は1829年に初版が出版され、彼の死後もエミル・レーディガーの監修のもと、1858年まで改訂・増補が続けられた。この辞典は、旧約聖書のヘブライ語とカルデア語(アラム語)を網羅したものであり、その後のヘブライ語辞書編纂に大きな影響を与えた。特に、タルムードの著作やラシ、アブラハム・イブン・エズラ、ダビデ・キムヒなどのユダヤ聖書注解者への言及も含まれている。また、この辞典は、現代の英語圏の読者にもよく知られている『Brown-Driver-Briggs』辞典(1907年)の基礎となった。
彼のヘブライ語文法書『Hebräische Grammatikドイツ語』(『ヘブライ語文法』)は1813年にわずか202ページの小冊子として初版が出版された。ゲゼニウスの生前に13版を重ね、没後も多くの版が刊行された。第14版から第21版は彼の弟子であるレーディガーによって、第22版から第28版はエミル・カウチによって最新の研究が反映されて改訂された。特に第28版(1909年)はアーサー・アーネスト・カウリーによって英語に翻訳され、1910年にオックスフォード大学出版局から刊行された。さらに、より学術的な文法書として『Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache mit Vergleichung der verwandten Dialekteドイツ語』を1817年に出版した。
2.2. Studies on ancient Semitic languages
ゲゼニウスは様々な古代セム語に関する先駆的な研究を行った。
彼はフェニキア語研究の創始者の一人として位置づけられている。1810年の著書『Versuch über die maltesische Spracheドイツ語』(『マルタ語に関する試論』)では、当時のマルタ語がフェニキア語の子孫であるという見解に反論し、マルタ語がアラビア語の方言であることを論じた。この著作の中で、彼はマルタ語がフェニキア語の後裔ではないことを示すために、フェニキア語の文法、用例集、語彙を収集した。そして1837年には、彼の代表作の一つである『Scripturae Linguaeque Phoeniciae Monumenta quotquot supersunt edita et inedita ad autographorum optimorumque exemplorum fidem edidit additisque de scriptura et lingua phoenicum commentariisラテン語』を出版した。これは当時入手可能であった70種類のフェニキア語碑文を集めたもので、フェニキア語研究の基礎を築いた。
また、サマリア人とそのモーセ五書の版についても幅広く執筆した。彼の著作には『De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritateラテン語』(1815年)、『De Samaritanorum theologia ex fontibus ineditis commentatioラテン語』(1822年)、『Programma. Commentatio de Samaritanorum theologiaラテン語』(1824年)、そしてサマリア人の詩歌を集めた『Carmina samaritana e Codicibus Londinensibus et Gothanisラテン語』(1824年)などがある。
さらに、ゲゼニウスはレーディガーと共にヒムヤル語(古代南アラビア語)の文字解読の先駆者でもあった。この研究の成果は、1841年の論文『Über die Himjaritische Sprache und Schriftドイツ語』(『ヒムヤルの言語と文字』)として発表された。
2.3. Other writings and editorial work
ゲゼニウスは上記以外にも数多くの著作と編集活動を行った。
彼は聖書注解の分野でも活動し、有名な『イザヤ書』(Der Prophet Jesaiaドイツ語)の注解書(3巻、1820年-1821年、第2版1829年)や、『ヨブ記』(Liber Job ad optima exemplaria accuratissime expressusラテン語)(1829年)などを出版した。また、ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルトの『Travels in Syria and the Holy Land英語』のドイツ語訳に貴重な地理的注釈を加え、エルシュとグルーバーの百科事典にも広範に寄稿した。長年にわたり、『Halle Allgemeine Litteraturzeitungドイツ語』(ハレ一般文学新聞)の編集者も務めた。
3. Legacy and evaluation
ゲゼニウスの学術的遺産は、セム語文献学と聖書学の分野に深く刻まれており、その業績は今日でも高く評価されている。
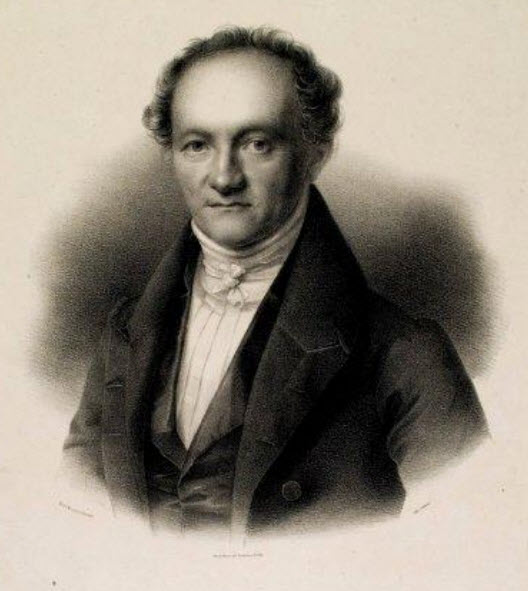
3.1. Academic contributions
ゲゼニウスは、セム語文献学を神学的・宗教的な先入観の束縛から解放し、厳密な科学的かつ比較的な方法論を確立した功績の大部分を担っている。この方法論はその後も非常に実り多い成果をもたらした。彼以前の聖書ヘブライ語辞典が、単にヘブライ語の表現を他の聖書翻訳(主に七十人訳聖書やウルガタ訳聖書)の同箇所での解釈に基づいて翻訳するだけだったのに対し、ゲゼニウスは他の古代言語や非セム語の研究から得られた知見を積極的に取り入れた。これにより、テトラグラマトンの「ヤハウェ」という発音の再構築に大きく貢献したとされている。
彼は聖書釈義学者としても、神学的探求に強力な影響を与えた。彼の業績は聖書解釈の客観性を高め、歴史的・文献学的文脈に基づいた理解を促進した。また、彼はフェニキア語研究の創設者とも見なされている。
彼の友人であり主要な英語翻訳者・伝記作家であるエドワード・ロビンソンは、ゲゼニウスについて次のように評している。「彼の概念はあまりに明晰であったため、彼の言葉、いや文章は、どんなに鈍い知性を持つ者でも即座に理解できた。この点において、彼は現代ドイツの学者の中でほとんど唯一無二の存在と言える。...彼自身の研究分野においては、彼は決して他者の権威に頼ることなく、ドイツ学術界が称賛されるような細部にわたる正確さ、綿密さ、そして倦むことのない勤勉さをもって、自ら探求した。彼の唯一の大きな目標は文献学的真理であった。彼は先入観のある理論を持ち合わせず、それに固執して真理を追い求めることもなかった。これらの特質は、彼の広範な学識と相まって、ヘブライ語文献学に関連する彼の研究や見解に対する信頼を、他の少数の学者にしか寄せられないほどのものとした。」
3.2. Controversies and criticisms
ゲゼニウスの学術的アプローチは、当時の保守的な神学界から厳しい批判と論争に直面した。特に彼の合理主義的な見解、そして聖書における奇跡の記述を軽く扱ったとされる講義内容は、エルンスト・ヴィルヘルム・ヘングステンベルクとその一派からの激しい攻撃の的となった。この対立は、1830年に『Evangelische Kirchenzeitungドイツ語』誌上での激しい口頭攻撃という形で顕在化した。
彼の合理主義的な解釈方法は、伝統的な信仰に基づく聖書理解と相容れないと見なされ、保守的な神学者たちからは危険な思想とされた。例えば、彼の辞典の英語翻訳版の一つであるサミュエル・プライドー・トレゲレスによる1857年版では、「学生へ」と題された箇所で、ゲゼニウスの合理主義の危険性やキリスト教信仰への学術的攻撃について、特別な警告が記されている。これらの論争は、当時のドイツ神学界における啓蒙時代の合理主義と伝統的信仰との間の緊張関係を浮き彫りにするものであった。
4. Tributes
ゲゼニウスの学術的貢献に対する敬意は、彼の死後も様々な形で示された。特に顕著なのは、ハレ大学の神学生たちの間に受け継がれている伝統である。毎年、彼らは試験に臨む前に、ゲゼニウスの墓に敬意のしるしとして石を置くという慣習を守っている。これは、彼がヘブライ語学と旧約聖書学に残した偉大な遺産に対する継続的な感謝と尊敬の念を表すものである。