1. 概要

閻立本(閻立本Yán Lìběn中国語、601年頃 - 673年11月14日)は、唐初期の中国の建築家、画家、政治家である。太宗および高宗の治世において、宮廷画家としての芸術的才能と、宰相級の官僚としての政治的手腕を兼ね備え、多岐にわたる活動を行った。
彼の最も有名な作品は『歴代帝王図巻』であり、これは現存する彼の唯一の真作である可能性も指摘されている。また、太宗の治世に貢献した24人の功臣を記念する『凌煙閣功臣図』や、秦王時代の太宗に仕えた18人の大学士を描いた作品も手掛けた。唐代の文人である朱景玄や張彦遠からは「古今の絵画の栄光の一つ」と高く評価された。669年から673年にかけては、高宗のもとで宰相を務めるなど、その生涯は芸術と政治の両面で顕著な業績を残した。
2. 背景と初期の生涯
閻立本の生年は正確には不明であるが、601年頃とされている。彼の祖先は元々馬邑(現在の山西省朔州市)の出身であったが、閻立本の数世代前に長安周辺の関中地域、具体的には雍州万年県(現在の陝西省西安市長安区)に移住した。
2.1. 家族と出自
閻立本の父である閻毗(閻毘中国語)は、隋の時代に宮廷の副長官を務めた人物であり、その技工の巧みさで知られていた。彼の母は北周の第3代皇帝武帝の娘である清都公主であり、これにより閻立本は北周の第4代皇帝宣帝の甥にあたり、第5代皇帝静帝の従弟にあたるという高貴な出自を持っていた。兄の閻立徳(閻立徳中国語)もまた、閻立本と同様に唐の太宗に仕え、橋梁の構築において大きな功績を挙げたことで知られている。
2.2. 芸術的訓練と初期の影響
閻立本は幼少期から学問を好み、詩文にも通じていたが、特に絵画の才能に恵まれていた。彼は父や兄から芸術的な影響を受け、特に兄の閻立徳は線のみで描く「白画」を得意としていたとされる。閻立本自身は鄭法士などの影響を受け、人物画を好んで描いた。
しかし、画家という職業に対する社会的な評価は、当時の中国の貴族階級においては必ずしも高くなかった。ある時、太宗が宮中の池で侍従の学者たちと舟遊びをしていた際、鳥が飛んできた。太宗は学者たちに詩を詠ませ、閻立本を召してその光景を描かせようとした。当時、閻立本はすでに主爵郎中という中級官僚の地位にあったが、伝令が「画師閻立本を召せ!」と叫んで彼を呼び出した。この時、閻立本は汗まみれで池のほとりにうつ伏せになり、絵の具を手に描かざるを得なかった。この光景を目の当たりにした閻立本は、居並ぶ賓客の前で画家としてのみ知られることへの恥ずかしさを強く感じ、顔を赤らめたという。彼は退朝後、子供たちに「私は幼い頃から学問に励み、幸運にも官職に就くことができた。しかし、今では絵画の技芸だけで名を知られ、召使いのような仕事をさせられるのは、これ以上ないほどの恥辱である。お前たちはこのことを深く戒めとし、この技芸を学ぶべきではない」と語った。しかし、彼自身はその後も絵画を愛し続け、制作を続けた。
3. 芸術的経歴
閻立本は、唐代の宮廷画家として、その卓越した技量と独特の画風で数々の重要な作品を残し、後世の中国絵画に大きな影響を与えた。
3.1. 主要作品
閻立本は、その生涯で多くの作品を制作したと伝えられているが、現存するものは少ない。1120年の記録には彼の作品42点の題名が記されているが、『十三皇帝図巻』はそこには含まれていない。記録された作品のうち、仏教題材は4点、道教題材は12点、残りは肖像画や宮廷の出来事を記録したものであった。
- 『十三皇帝図巻』(歴代帝王図巻)

『十三皇帝図巻』(ボストン美術館蔵)は、前漢の昭帝から隋の煬帝までの歴代13人の皇帝の肖像を描いた作品として特に有名である。この作品は、その大部分が後世に加筆されたものと見られるが、一部は閻立本の真作であると広く認められている最初の作品とされている。
以下に、図巻に描かれた歴代皇帝の肖像を示す。


漢代の皇帝に続き、三国時代の君主たちが描かれている。



三国時代の後には、西晋の皇帝が続く。

南北朝時代の陳の皇帝たちも含まれる。




さらに、北周と隋の皇帝の肖像も描かれている。



- 『凌煙閣功臣図』(寧遠閣人物図)
643年に太宗皇帝の命により制作された。太宗の治世に多大な貢献をした24人の功臣を記念して描かれた肖像画である。
- 『秦府十八学士図』
626年に太宗が秦王であった時代に仕えた18人の大学士を描いた作品で、褚亮が賛を書いた。
- 『昭陵六駿図』の図案
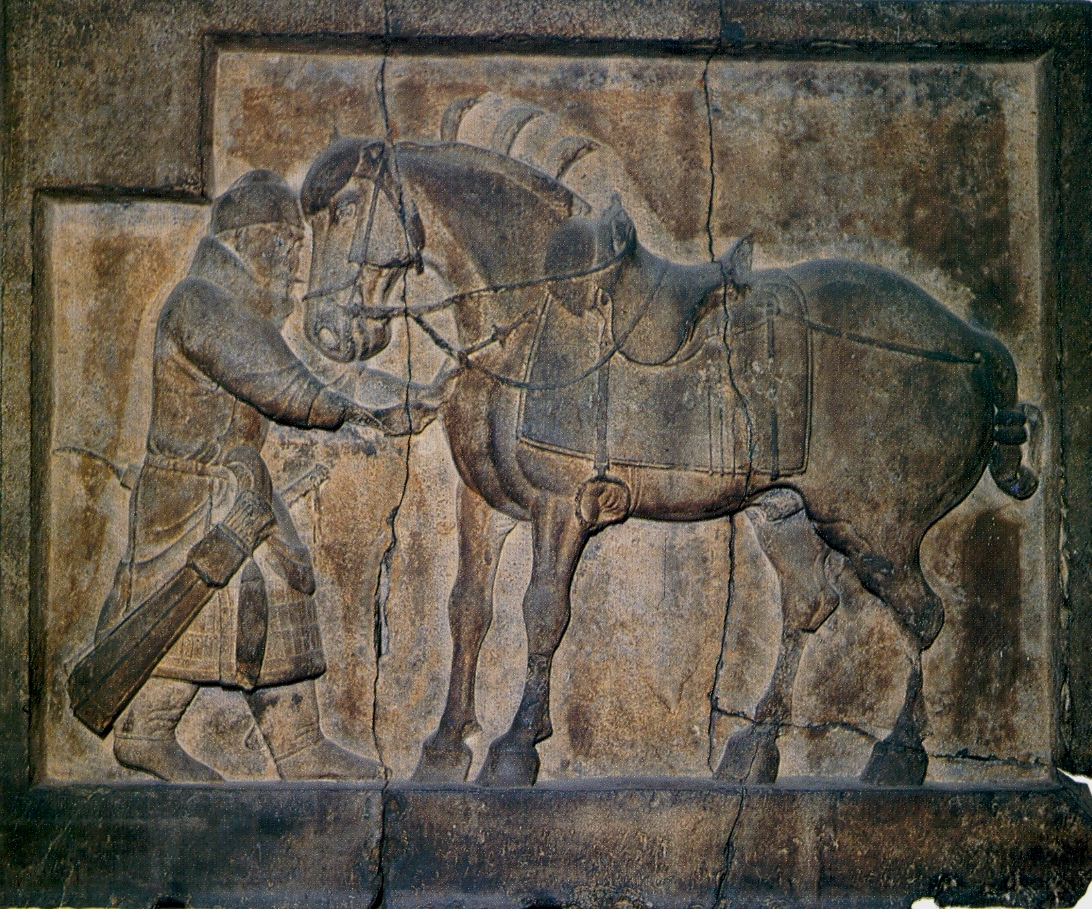
太宗の昭陵にある6頭の愛馬の石刻浮彫りの図案は、閻立本が手掛けたものとされている。この浮彫りは非常に平坦で線的であり、彼の描いた図面や絵画に基づいて彫刻された可能性が高い。閻立本は、この陵墓のために他の失われた作品も制作しており、陵墓全体の設計にも関与した可能性がある。
- 『歩輦図』(唐太宗がチベット使節を迎える場面)

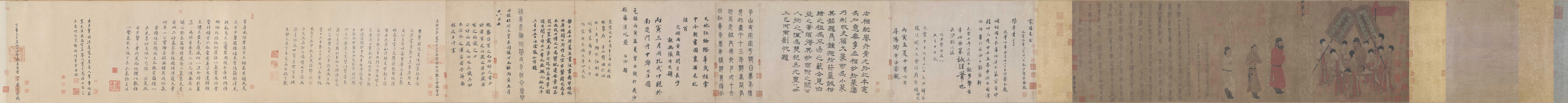
太宗の治世に制作されたと考えられている。チベット使節を迎える太宗の姿を描いたもので、現存するものは宋代の模写である。
- 『王会図』(職貢図)

外国からの使節と貢物を捧げる人々を描いたもので、現存するものは宋代の模写である。
- 『蕭翼賺蘭亭図』

蕭翼が蘭亭序を騙し取る場面を描いた作品。
- 『功臣二十四人図』
太宗の命により描かれた功臣の肖像画。
また、莫高窟第200窟の壁画に描かれた皇帝像は、642年の制作とされており、閻立本の筆による可能性が指摘されている。
3.2. 芸術様式と特徴
閻立本の絵画様式は、細く力強い綿密な線が連綿と続く伝統的な描法を特徴としている。この時代の絵画は、王の権威を示す社会的な機能が重視されたため、個性の表現は抑えられ、伝統的な絵画技法が用いられた。彼の作品もまた、このような伝統に則ったものであった。
唐代初期には、西域画派が台頭し始め、尉遅乙僧(うっち いっそう)などが新たな画風を導入していた。これに対し、閻立本は伝統的な画法を堅持し、その綿密な線描は後の世代、特に薛稷(せつ しょく)らに継承され、中国絵画史における重要な位置を占めた。彼の絵画は、単なる写実性を超え、描かれた人物の内面や品格をも表現しようとするものであった。
4. 政治的経歴
閻立本は、その芸術的才能だけでなく、政治家および官僚としても唐の宮廷で重要な役割を果たした。彼は建築技術にも優れており、公共事業にも深く関与した。
4.1. 官職
閻立本は、以下のような主要な官職を歴任した。
- 主爵郎中(ちゅうしゃくろうちゅう)
太宗の治世下で務めた中級官僚の職。この時期に、画家としてのみ知られることへの恥辱を感じたという逸話が残っている。
- 工部尚書(こうぶしょうしょ)
公共事業を管轄する部署の長官。兄の閻立徳もこの職を務めており、閻立本は兄の後を継いでこの要職に就いた。
- 右相(ゆうしょう)
669年頃に代理として就任。政府の試験局(西臺、西臺中国語)の長官であり、宰相級の地位と見なされた。この時、高宗により博陵県男(博陵文貞男)に封じられた。
- 中書令(ちゅうしょれい)
670年に正式に就任。立法局の長官であり、これも宰相級の要職であった。
4.2. 太宗皇帝の治世における奉仕
太宗皇帝の治世下において、閻立本は宮廷画家として皇帝からの依頼を多く受けた。彼は『凌煙閣功臣図』や『秦府十八学士図』といった、太宗の功績を称え、その治世を記念する重要な作品群を制作した。これらの絵画は、単なる芸術作品としてだけでなく、皇帝の権威を宣揚し、歴史的出来事を記録する役割も果たした。また、彼は公共事業にもその建築技術を活かして貢献した。
4.3. 高宗皇帝の治世における奉仕
太宗の子である高宗皇帝の治世、咸亨年間(656年 - 661年)には、閻立本は宮廷建築家を務めた。その後、兄の閻立徳の後を継いで工部尚書に就任した。
669年の正月頃には、代理の右相(宰相級)となり、博陵県男に封じられた。同時期に、戦功によって宰相に昇進した同僚の姜恪(きょうかく、代理の左相)との間に、「左相は砂漠で権力を確立し、右相は絵筆で名声を確立した」という半ば揶揄的な対句が詠まれたという逸話が残っている。これは、姜恪が軍事的な功績で名を上げたのに対し、閻立本が芸術的な才能で宰相の地位にまで上り詰めたことを示している。670年には、正式に立法局の長官である中書令に就任し、高宗のもとで政治の中枢を担った。
5. 評価と影響
閻立本は、その芸術作品と官僚としての生涯を通じて、中国の美術史および政治史において重要な足跡を残した。
5.1. 同時代および後世の評価
閻立本の作品は、同時代の唐代の文人たちから高く評価された。特に、朱景玄や張彦遠といった著名な美術史家は、彼の絵画を「古今の絵画の栄光の一つ」と称賛した。張彦遠が著した『歴代名画記』には、閻立本の芸術に対する詳細な記述と、彼が画家として直面した社会的な葛藤に関する逸話が記されており、これは後世に彼の芸術的・人間的側面を伝える貴重な資料となっている。
5.2. 美術史的意義
閻立本は、中国絵画史において、特に人物画と肖像画の分野で極めて重要な地位を占めている。彼の作品にみられる細く力強い綿密な線描は、古来の描法を継承しつつ、独自の洗練された様式を確立した。これは、当時の宮廷絵画における写実性と表現力の高まりを示すものであった。
彼は、太宗や高宗といった歴代皇帝の治世を記録し、その権威を視覚的に表現する役割を担った。彼の作品は、単なる記録画に留まらず、描かれた人物の性格や品格をも伝える深い洞察力に満ちていた。彼の伝統的な画風は、当時の西域画派の台頭という新たな潮流の中で、中国絵画の伝統を守り、後の世代(例えば薛稷)に大きな影響を与えた。閻立本の絵画は、唐代の宮廷文化と芸術の精華を今に伝える貴重な遺産となっている。
6. 死去
閻立本は、673年11月14日に死去した。