1. 概要

アンドリュー・メルヴィル(Andrew Melvilleアンドリュー・メルヴィル英語、1545年8月1日 - 1622年)は、スコットランドの卓越した学者、神学者、詩人、そして宗教改革者である。彼の生涯は、スコットランド教会と教育制度の発展に多大な影響を与え、特に長老主義の確立とその擁護において中心的な役割を担った。
メルヴィルは、スコットランドの大学教育にフランスのピエール・ド・ラ・ラミュが提唱した新しい教授法と哲学を導入し、グラスゴー大学とセント・アンドルーズ大学の改革を主導した。これにより、スコットランドの学術水準は飛躍的に向上し、多くの学者が彼の教えを求めて集まった。
宗教改革者としては、ジョン・ノックスの後継者としてスコットランド教会における長老制の確立に尽力し、特に1578年に採択された第二教理問答書の承認に大きく貢献した。彼は監督制(主教制)に断固として反対し、「監督の鞭」(Episcopomastixエピスコポマスティクス英語)として知られるほど、教会における階級制度を批判し、教会の自律性と精神的自由を強く擁護した。
その信念から、国王ジェームズ6世(後のイングランド王ジェームズ1世)との度重なる対立を経験した。特に有名なのは、彼がジェームズ王を「神の愚かな家臣」(God's silly vassalゴッズ・シリー・ヴァサル英語)と呼び、国王もまたキリストの王国の一員に過ぎないことを説いたエピソードである。この対立は最終的に彼の投獄とフランスへの亡命につながったが、彼の揺るぎない姿勢はスコットランドの長老派教会の独立と教会の自由の象徴となった。メルヴィルの貢献は、スコットランドの神学、教育、そして知的・宗教的自由の発展に永続的な影響を与え続けている。
2. 初期生と教育
2.1. 誕生と家族
アンドリュー・メルヴィルは、スコットランドのアンガス地方モントローズ近郊のバルドーヴィで、1545年8月1日にリチャード・メルヴィル(ディーサートのメルヴィルの兄弟)の末息子として生まれた。彼は14人兄弟の末弟とも言われているが、1612年の書簡では「14人の兄弟より長生きした」と述べている。彼の父はアンドリューがわずか2歳の時にピンキーの戦いで命を落とし、母もその直後に死去したため、彼は長兄のリチャード・メルヴィル(後のマリトン牧師)によって育てられた。リチャードはアンドリューに最高の教育を受けさせるために尽力した。
2.2. 幼少期と学校教育
メルヴィルは幼い頃から学問への強い関心を示し、モントローズ文法学校でラテン語の基礎を学んだ。この学校を卒業した後、ダン・ジョン・アースキンがモントローズに招いたフランス人ピエール・ド・マルシリエールの下で2年間ギリシア語を学んだ。彼の語学力は非常に高く、セント・アンドルーズ大学に入学した際には、大学の教授陣を驚かせるほど、当時誰も理解できなかったアリストテレスのギリシア語原文を読んでいた。
2.3. 大学での学問
セント・アンドルーズ大学での学業を終える頃には、メルヴィルは「国内で最も優れた詩人、哲学者、ギリシア学者」としての名声を得ていた。彼は19歳になった1564年、さらなる教育を修めるためフランスへ向かった。
3. ヨーロッパでの学問と活動
メルヴィルは1564年秋にフランスに渡り、パリ大学で学んだ。彼はその後、ポワティエ大学で法学を学ぶなど、ヨーロッパ各地で学問を深め、当時の主要な知識人たちと交流した。
3.1. フランスでの学問
パリ大学では、ギリシア語を流暢に操る能力をさらに向上させ、東洋言語を習得し、数学と法学を学んだ。特に、彼はピエール・ド・ラ・ラミュ(ペトルス・ラムス)の直接的な影響を受け、彼の新しい教授法と哲学を後にスコットランドの大学に導入することになる。また、メルヴィルは当時を代表するヘブライ学者の一人であるジャン・メルシエの下でヘブライ語も学んだ。
1566年からはポワティエへ移り、民法を学んだ。彼は当時まだ21歳だったにもかかわらず、サン・マルセオン大学の学寮長(レゲント)に任命されたようである。ポワティエがユグノーから防衛された際にはその防衛戦に参加した。
3.2. ジュネーヴでの生活と活動
しかし3年後、フランス国内の政治的混乱により、メルヴィルはフランスを離れざるを得なくなり、ジュネーヴへ向かった。ジュネーヴではテオドール・ド・ベーズに歓迎され、彼の勧めによりジュネーヴ・アカデミーの人文学教授に任命された。
ジュネーヴでの教育活動に加え、メルヴィルは東洋文学の研究を続け、同僚教授の一人であるコルネリウス・ベルトランからシリア語の知識を習得した。1572年にはジョゼフ・スカリジェやフランソワ・オットマンと出会い、彼らはサン・バルテルミーの虐殺の後、ジュネーヴに滞在していた。サン・バルテルミーの虐殺は、メルヴィルがジュネーヴに滞在中に発生し、膨大な数のプロテスタント難民がジュネーヴに流入した。これには当時フランスの最も著名な文学者や、民法と政治学に長けた多くの学者が含まれており、彼らとの交流はメルヴィルの知識を深め、市民的・教会的自由に関する彼の思想をさらに拡大させた。
4. スコットランドへの帰還と学術経歴
1574年、メルヴィルはスコットランドに帰国し、ほぼ直ちにグラスゴー大学の総長に任命され、大学の再建に着手した。総長としての職務の傍ら、近隣のゴヴァン教会の牧師も兼務した。
4.1. グラスゴー大学総長
メルヴィルはグラスゴー大学に優れた教育システムを確立することに尽力した。彼はカリキュラムを拡充し、語学、科学、哲学、神学の講座を新設し、これらは1577年の勅許によって承認された。彼の名声は広まり、スコットランド全土だけでなく国外からも学生が殺到した。
彼は1575年にはアバディーン大学の再建を支援した。
4.2. セントメアリーズ・カレッジ(セント・アンドルーズ大学)総長
メルヴィルはグラスゴーで行った改革をセント・アンドルーズ大学にも適用するため、1580年にはセント・アンドルーズ大学のセントメアリーズ・カレッジの総長に任命された。そこでの職務には、神学、ヘブライ語、カルデア語、シリア語、およびラビ言語の講義が含まれた。彼の教えは、多数の若手学生だけでなく、他のカレッジの教員も聴講に訪れるほどであった。
メルヴィルはギリシア文学研究の流行を生み出した。しかし、彼の新しい教授法がもたらした改革、そしてアリストテレスの教えに誤謬があるという彼の新しい教義の一部は、大学内の他の教師たちとの間で衝突を引き起こすことになった。
5. 宗教的・政治的指導力
メルヴィルはスコットランド教会の総会の一員として、監督制に反対するあらゆる措置に積極的に参加した。彼はこの教会統治形態に断固として反対したため、「Episcopomastixエピスコポマスティクス英語」(「監督の鞭」の意)という異名を得た。
5.1. 総会議長
メルヴィルは、1578年4月24日にエディンバラで開催された総会の議長を務め、この総会で第二教理問答書が承認された。総会はこの頃、大学の改革と改善に注目し、メルヴィルは1580年12月、グラスゴーからセント・アンドルーズのセント・メアリーズ・カレッジに転任させられ、同カレッジの学長に就任した。ここで彼は神学の講義を行うだけでなく、ヘブライ語、カルデア語、シリア語、ラビ言語を教え、彼の講義は通常の数を超える若い学生だけでなく、他のカレッジの教員からも聴講された。
彼は1582年4月24日にセント・アンドルーズで開かれた総会、および同年6月27日にエディンバラで開催された臨時総会の議長を務めた。この臨時総会は、特にロバート・モンゴメリー元グラスゴー大司教の破門に関連する国王の恣意的な措置を受けて開催されたものであった。メルヴィルは開会の説教で、政府が教会問題で主張する絶対的な権威に対して大胆に批判を浴びせた。総会が活発な抗議書を採択すると、メルヴィルらがパースの宮廷にいる国王に提出するよう任命された。抗議書が枢密院の面前で国王に読み上げられた際、国王の寵臣アラン伯爵は脅すように叫んだ。「誰がこの反逆的な条項に署名するのか!」すると、メルヴィルは「我々がだ!」と臆することなく答え、ペンを取って即座に署名した。他の委員たちもこれに続き、レノックスとアランは彼らの不敵さに威圧され、穏便に彼らを解散させた。
メルヴィルは1587年6月に再び総会の議長に選出され、議会の審議に出席する委員の一人に指名された。1590年5月17日の女王の戴冠式には出席し、この機会のために作られたラテン語詩「ステファニスキオン(Stephaniskionステファニスキオン英語)」を朗読し、国王の要望により直ちに発表された。同年、彼はセント・アンドルーズ大学の学長に選出され、その職を数年間再選によって保持し続けた。1594年5月には再び総会の議長に選出された。その直後、彼は教会の代表として貴族会議の前に姿を現し、カトリック貴族たちの財産没収を強く主張した。そして甥と他の二人の牧師と共に、国王の明確な要請により、彼らに対する遠征に同行した。1594年10月にはハントリー城で国王と共にあり、その解体を主張した。
5.2. 長老主義の擁護
メルヴィルは約3年間、甥の助けを得てセント・アンドルーズの教区教会で説教を行っていた。1584年2月、彼は反逆罪の容疑で枢密院に召喚された。この容疑は、前月に開かれた断食日にダニエル書第4章に関する説教で、国王の母を追放されたネブカドネザルになぞらえ、再び王国に復帰すると発言したとされる扇動的な表現に基づいていた。出頭した際、彼はそのような言葉は使っていないと否定し、実際に使った言葉については全面的に弁明し、自身の裁判は教会裁判所で行われるべきだと主張する抗議書と辞退書を提出した。国王と枢密院の前に出た際、彼は大胆にも、自分たちよりも偉大で、はるかに上に立つ王と評議会の使者や伝達者の教義を裁き、責任を問うことは彼らの管轄を超えていると述べた。そして、ベルトから小さなヘブライ語の聖書を外し、彼らの前のテーブルに投げつけて言った。「あなた方自身の弱さ、見落とし、そして軽率さを見てほしい。あなた方がすべきでも、できるはずもないことを引き受けたのだから。これが私の指示と権限だ。あなた方の誰がこれを判断したり、私が指示に従わなかったと咎めたりできるか見せてみろ。」アランはヘブライ語の聖書を見つけ、国王の手に渡しながら言った。「陛下、彼は陛下と枢密院を嘲笑しています。」「いいえ、陛下」とメルヴィルは答えた。「私は嘲笑しているのではありません。私はイエス・キリストとその教会の目的のために、全身全霊を込めて、真剣に、厳粛に立ち向かっているのです。」
枢密院は彼に対する容疑を証明できなかったが、彼を解放する気はなく、管轄権の辞退と彼らの前での無礼な振る舞いを理由に有罪とし、エディンバラ城に投獄し、さらに国王の意のままに身体と財産に懲罰を与えることを宣告した。しかし、彼が投獄される前に、彼の監禁場所はアランの従属者が管理するブラックネス城に変更されるよう命じられた。夕食中、国王のメイス(杖役人)が入ってきて、24時間以内にそこに入るよう命じたが、彼は密かにエディンバラから退去することでそこへの送致を免れた。しばらくベリック・アポン・ツイードに滞在した後、彼はロンドンへ向かい、翌7月にはオックスフォード大学とケンブリッジ大学を訪問し、両大学で彼の学識と名声にふさわしい歓迎を受けた。
5.3. 「監督の鞭」(エピスコポマスティクス)
1577年10月、メルヴィルと摂政モートンとの間で行われた会談で、彼の不屈の精神を示す注目すべき事例が発生した。総会の進行に苛立ったモートンは、「この国が静まるには、お前たち数人を絞首刑にするか追放するしかない!」と叫んだ。メルヴィルは「聞きなさい、殿下!」と言い返した。「宮廷の者たちをそのように脅しなさい!私にとっては、空中で腐ろうと、地面で腐ろうと変わりはない。大地は主のものだ。Patria est ubicunque est beneラテン語(どこに善があるか、そこに祖国がある)。神の御心に従い、これほどの価値がない場所であっても命を捨てる覚悟はできています。私はこの国で10年間、外で暮らしても、この国で暮らしても同じです。神が栄光を受けられますように。神の真理を吊るしたり追放したりする力は、あなた方にはないでしょう。」この大胆な言葉に対し、モートンはあえて反発しなかった。
6. 国王との対立
メルヴィルは20ヶ月の不在の後、1585年11月にスコットランドに戻り、1586年3月にはセント・アンドルーズでの講義を再開し、そこで20年間教え続けた。彼は1590年に同大学の総長となった。
6.1. ジェームズ6世との対立
アラン伯爵の失脚により、メルヴィルは1585年11月に追放された貴族たちと共にスコットランドに帰還した。グラスゴー大学の再編を支援した後、翌3月にはセント・アンドルーズでの職務を再開した。4月に開催されたファイフのシノドスは、教会における長老制統治を覆そうとしたパトリック・アダムソンセント・アンドルーズ大司教を破門した。これに対し、アダムソン大司教はメルヴィルとその甥のジェームズ・メルヴィル、そして他の兄弟たちを破門する判決を下した。大司教とのこの対立の結果、メルヴィルは国王からテイ川以北に居住を限定する書面による命令を受け、翌8月まで大学での職務に復帰できなかった。しばらく後、アダムソンが大司教職を剥奪され、国王に見捨てられ大貧困に陥った際、彼はかつての敵対者であるメルヴィルに手紙を送り、過去の行動への後悔を表明し、助けを求めた。メルヴィルはすぐに彼を訪ね、友人たちの間で彼の救済のための寄付を募っただけでなく、数ヶ月間、自らの資金で彼を支援し続けた。
翌年、追放されていたカトリック貴族たちを呼び戻す提案がなされると、メルヴィルは他の牧師たちと共にセント・アンドルーズの身分制議会に赴き、その計画に反対する抗議を行ったが、国王から退去を命じられた。彼は最も断固とした返答をした後、退去した。総会の委員会がファイフのクーパルで開かれると、彼らはメルヴィルと他のメンバーを国王に派遣し、抗議させた。私的な謁見が許されると、ジェームズ・メルヴィルは非常に穏やかで敬意をもって国王に語りかけたが、国王が苛立ち、彼らを扇動罪で告発すると、アンドリューは国王の袖を掴み、彼を「神の愚かな家臣」と呼び、こう述べた。「これはお世辞を言う時ではなく、はっきりと語る時です。我々の使命は生ける神からのものであり、国王もまたその神に従属しています。我々は常に公の場では陛下に謙虚に敬意を払いますが、陛下の私的な場にいる機会がある以上、我々は職務を全うしなければなりません。さもなくばキリストの敵となるでしょう。そして今、陛下にお伝えしなければなりません。スコットランドには二つの王国が存在します。一つはキリストの王国であり、それは教会です。ジェームズ6世陛下はその教会の臣民であり、その王国の頭でも主でもなく、一人の成員に過ぎません。そして、キリストが彼の教会を監視し、その霊的王国を統治するために召し、命じられた者たちは、彼からそうするための十分な力と権威を有しており、いかなるキリスト教徒の国王や君主もこれを制御したり解除したりすべきではなく、むしろ支援し、支持すべきです。さもなくば、彼らはキリストの忠実な臣民でも成員でもないでしょう。」国王はこの大胆な忠告に辛抱強く耳を傾け、彼が決して守るつもりのない多くの甘い約束をして彼らを解散させた。その後数年間、ジェームズ国王は自らの恣意的な考えに従って教会を支配しようと繰り返し試みたが、常にアンドリュー・メルヴィルの強固な抵抗に遭遇した。そして最終的に国王は、この長老主義の擁護者をスコットランドから完全に排除するために、彼が「王の技」の真髄と考えた策略の一つに頼ることになった。
メルヴィルは終始、政府のいかなる侵略に対してもスコットランド教会の自由を守った。彼が主に教会の憲法上保証された権利のために戦っていたことは一般的に受け入れられている。メルヴィルに対する主な批判は、その情熱ゆえに「聖別された君主」に対する敬意を忘れがちであったということである。国王が恣意的で違法な行動を取った際、彼は「たとえ人々の上に立つ王であっても、彼は単なる『神の愚かな家臣』である」ということを思い出させる必要があった。メルヴィルの無礼さ(もしそう呼ぶなら)は、宗教の純粋さに熱心で、自分自身への結果を顧みない男の正当な怒りの爆発であった。
彼の甥であるジェームズ・メルヴィルは、後にイングランド王ジェームズ1世となるスコットランド王ジェームズ6世に対し、ファークランドで私的に行われた有名な発言を記録している。彼は国王を「神の愚かな家臣」と呼び、袖を掴んでこう言った。「陛下、我々は常に陛下を敬虔に敬います、特に公の場では。しかし、今こうして陛下と私的に会う機会を得たからには、真実をお伝えしなければなりません。というのは、陛下はご自身のお命と王冠を極度の危険に晒しておられます。そして陛下と共に、この国とキリストの教会は破滅に瀕しています。真実を申し上げず、忠実な助言を差し上げなければ、我々は職務を全うしなければなりません。さもなくば、キリストと陛下双方に対する裏切り者となるでしょう!ですから陛下、これまで何度も申しましたが、今改めて申し上げます。スコットランドには二人の王と二つの王国が存在します。キリスト・イエスこそが王であり、その王国は教会です。ジェームズ6世陛下はその教会の臣民であり、その王国の王でも、主でも、頭でもなく、一人の成員に過ぎません!そして、キリストが召し、その教会を監視し、その霊的王国を統治するよう命じられた者たちは、彼からそうするための十分な力と権威を、共同でも個別でも有しています。いかなるキリスト教徒の国王や君主も、これを制御したり解除したりすべきではなく、むしろこれを強化し、支援すべきです。さもなくば、彼らはキリストの忠実な臣民でも成員でもないでしょう。」
6.2. 投獄と亡命
1599年、メルヴィルは大学総長職を剥奪されたが、神学部の学部長に任命された。スコットランドにおけるメルヴィルのキャリアの終焉は、ついにジェームズ王によって彼の特徴的なやり方で引き起こされた。1606年5月、メルヴィルは甥と他の6人の兄弟と共に、国王が教会問題について彼らと協議したいという口実のもと、国王からの書簡でロンドンに召喚された。到着後まもなく、彼らは9月23日にハンプトン・コート宮殿で国王の面前で開催された有名な会議に出席し、メルヴィルはそこで長時間、イギリスの貴族や聖職者を驚かせるほど大胆に発言した。ミカエル聖堂の日、メルヴィルと彼の兄弟たちは王室礼拝堂に出席するよう命じられたが、その儀式のカトリック的性格に憤慨し、宿に戻るとその怒りをラテン語のエピグラムで表現した。その写しが国王に渡り、彼はホワイトホール宮殿の枢密院に召喚された。「scandalum magnatumスカンダルム・マグナトゥムラテン語」(大権に対する侮辱罪)で有罪とされ、最初はセント・ポール大聖堂の首席司祭の監視下に置かれ、次にウィンチェスター司教ビルソンの責任下に置かれた。しかし、最終的にはロンドン塔に送られ、そこで4年間囚人として過ごした。
彼が書いたエピグラムは以下の通りである。
Cur stant clausi Anglis libri duo regia in ara,
Lumina casca duo, pollubra sicca duo?
Num sensum cultumque Dei tenet Anglia clausum,
Lumine exca suo, sorde sepulta sua?
Romano an ritu, dum regalem instruit aram,
Purpuream pingit religiosa lupam ?ラテン語
これは古訳では次のように表現されている。
Why stand there on the altar high
Two closed books, blind lights, two basins dry?
Doth England hold God's mind and worship close.
Blind of her sight, and buried in her dross?
Doth she, with chapel put in Romish dress,
The purple whore religiously express?英語
このエピグラムのためにメルヴィルはロンドン塔に送られたのである。当初、彼は最も厳しく扱われ、ペン、インク、紙の使用さえも禁じられた。しかし彼の精神は屈することなく、靴のバックルの舌を使って監獄の壁にラテン語の詩を刻み、孤独な時間を過ごした。宮廷の友人たちの介入により、約10ヶ月後には彼の監禁は厳しさが軽減された。1607年末頃、ラ・ロシェルのプロテスタントたちは彼をその大学の神学教授として招こうと試みたが、国王は彼の釈放を許可しなかった。
7. 晩年と死
1611年2月、ついにブイヨン公の執り成しにより、彼はフランスのセダン公国アカデミーの神学教授になることを条件に釈放された。彼はそこで残りの生涯を過ごし、77歳の高齢で1622年にセダンで死去した。
自国への帰還を許されなかったものの、彼はセダン・アカデミーの教授職に招かれ、そこで人生の最後の11年間を過ごした。
8. 人となり
メルヴィルの伝記作家であるマクリー博士は、彼が「広範な神学の知識に加えて、優雅な文学の趣味を持った最初のスコットランド人」であったと述べている。彼は同時代の重要な公的出来事の全てにおいて顕著な役割を担ったが、党派の指導者であったわけでも、そう見せようとしたわけでもなかった。私生活では、彼は陽気で親切な性格で、愉快な仲間であった。彼は生涯独身であった。身長が低いという記述以外に、彼の身体的な外見に関する詳細な記述や既知の肖像画は残されていない。
9. 著作
彼の著作の大半はラテン語詩で構成されている。1824年に2巻で出版されたマクリー博士の『アンドリュー・メルヴィルの生涯』には、彼の出版された作品および手稿の全ての名前が挙げられており、その中に非常に大規模なものはない。
ヒュー・スコットが挙げた著作には以下のものが含まれる。
- Carmen Mosisラテン語(バーゼル、1573年)、Delitice Poetarum Scotorumラテン語(アムステルダム、1637年)に再版
- Julii Ccesaris Scaligeri Posmataラテン語(ジュネーヴ、1575年)
- Zre^aviaKiov, Ad Scotice Regem, habitumラテン語 in Coronatione Regince, etc.(エディンバラ、1590年)
- Carmina Sacra duoラテン語, etc.(ジュネーヴ、1590年)
- [https://www.dps.gla.ac.uk/delitiae/display/?pid=d2_MelA_010&aid=MelA Principis Scoti-Britannorum Nataliaラテン語] (エディンバラ:ロバート・ウォルデグレーブ、1594年;ハーグ、1594年)
- Theses Theological de Libero Arbitrioラテン語(エディンバラ、1597年)
- Scholastica Diatriba de Rebus Divinisラテン語(エディンバラ、1599年)
- Inscriptiones Historical Regum Scotorum . . . Joh. Jonston . . . Author e . . . Prcefixus est Gathelus, sive de Gentis Origine Fragmentum, Andreas Melviniラテン語(アムステルダム、1602年)
いくつかの詩:
- In Obitum Johannis Wallasiiラテン語(ライデン、1603年)
- Pro supplici Evangelicorum Ministrorum in Anglia . . . Apologia, sive Anti- Tami - Garni - Categoriaラテン語(1604年?;カルダーウッドのParasynagma Perthenseラテン語(エディンバラ、1620年)とAltare Damascenumラテン語(1623年)に再版)
- デヴィッド・ヒュームのLusus Poeticiラテン語(エディンバラ、1605年)における4つの書簡
- ジョン・ジョンストンのSidera Veteris JEviラテン語(ソミュール、1611年)にはメルヴィルの詩2編が含まれる
- Comment, in Apost. Acta M. Johannis Malcolmiラテン語(ミデルブルフ、1615年)にはメルヴィルの詩が冒頭に付される
- Duellum Poeticum contendentibus G. Eglisemmio et G. Buchananoラテン語(ロンドン、1618年)にはメルヴィルのCavillum in Aram Regiamラテン語(チャペルロイヤルに関するエピグラム)が掲載
- ジェームズ・センピル卿のSacriledge Sacredly Handled英語(ロンドン、1619年)における3つのエピグラム
- Viri clarissimi A. Melvini Musasラテン語(エディンバラ、1620年)
- De Adiaphoris, Scotitov tvxovtos, Aphorismiラテン語(1622年)
- ジェームズ・メルヴィルのAd Serenissimum Jacobum Primum . . . Libellus Supplexラテン語(ロンドン、1645年)における彼のエピタフ
- Andrew Melvini Scotiaラテン語
- ブライエのAtlas Majorラテン語(アムステルダム、1662年)におけるTopographiaラテン語
- コールマンのDe Diebus Festisラテン語(ユトレヒト、1693年)における5つの詩
- Commentarius in Divinam Pauli Epistolam ad Romanosラテン語(ウッドロー協会、エディンバラ、1850年)
10. 遺産と影響力


アンドリュー・メルヴィルは、スコットランドの神学、教育、そして長老主義の発展に計り知れない、持続的な影響を与えた。彼はジョン・ノックスの後継者として、スコットランド教会における長老制統治の基礎を築き、その後の教会形成の方向性を決定づけた。彼の監督制に対する断固たる反対と、教会の自律性への情熱は、スコットランドの長老派教会が国家権力から独立した存在として確立される上で不可欠な要素であった。国王ジェームズ6世との激しい対立は、彼の信念の強さと、宗教的自由と教会の憲法上の権利を守るための勇敢な姿勢を際立たせるものであった。彼は国王を「神の愚かな家臣」と呼び、世俗の権力もまたキリストの教会の臣民であるという、教会と国家の関係における彼の根本的な理解を明確に示した。
また、メルヴィルはスコットランドの大学教育に革命をもたらした。グラスゴー大学とセント・アンドルーズ大学の総長として、彼はカリキュラムを拡充し、新しい教授法と学問分野を導入した。特に、ピエール・ド・ラ・ラミュの哲学の導入や、ギリシア語、ヘブライ語といった古典言語の研究を奨励したことは、スコットランドの学術水準を飛躍的に向上させ、多くの優秀な学生や学者を惹きつけた。彼の教育への貢献は、スコットランドをヨーロッパにおける学術的中心地の一つへと押し上げる一因となった。
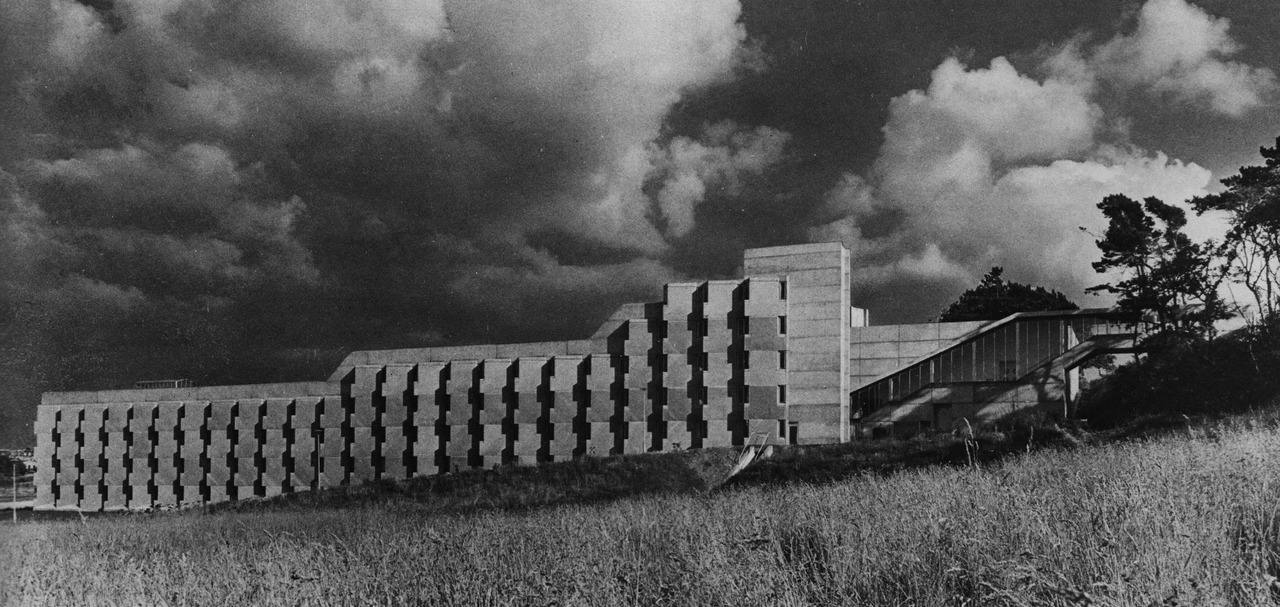
メルヴィルの生涯は、知的自由と宗教的良心の擁護者としての役割を強調している。彼の投獄と亡命は、彼の信念が世俗の権力によって抑圧されることを拒んだ証しであり、後の世代に続く教会と国家の間の闘争において、重要な先例となった。彼は単なる神学者や学者に留まらず、スコットランド社会の知的・精神的基盤を形成する上で決定的な役割を果たした人物として記憶されている。