1. 概要
ダニエル・ベルヌーイ(Daniel Bernoulliダニエル・ベルヌーイドイツ語)は、1700年2月8日にオランダのフローニンゲンで生まれ、1782年3月17日にスイスのバーゼルで亡くなったスイスの数学者および物理学者である。彼はバーゼル出身の著名なベルヌーイ家の一員であり、その中でも特に優れた才能を持つと評された。ベルヌーイは、数学を力学、特に流体力学に応用した功績と、確率論や統計学における先駆的な研究で知られている。彼の名は、エネルギー保存の法則の具体例であるベルヌーイの原理に冠されており、この原理は気化器や航空機の翼といった20世紀の重要な技術の基盤となっている。また、彼は医学、生理学、天文学、海洋学など多岐にわたる分野の研究を行い、その科学的業績は今日でも世界中の教育機関で研究されている。
2. 生涯
ダニエル・ベルヌーイの生涯は、著名な学術的成果と、家族、特に父ヨハン・ベルヌーイとの複雑な関係に彩られていた。彼は若くして多岐にわたる学問分野に才能を示し、そのキャリアを通じて数々の重要な貢献を行った。
2.1. 家族と出自
ダニエル・ベルヌーイは、1700年2月8日にオランダのフローニンゲンで、著名な数学者の家系であるベルヌーイ家に生まれた。ベルヌーイ家は元々、当時スペイン領ネーデルラントであったアントウェルペンの出身であったが、プロテスタントに対するスペインの迫害から逃れるため、フランクフルトに短期間滞在した後、スイスのバーゼルに移住した。
彼の父は微積分学の初期開発者の一人であるヨハン・ベルヌーイであり、伯父は確率論の初期研究者であり数学定数eの発見者であるヤコブ・ベルヌーイである。ダニエルにはニコラウス2世・ベルヌーイとヨハン2世・ベルヌーイという2人の兄がおり、彼らも後に数学者や物理学者となった。ダニエルが5歳の時、バーゼル大学にいた伯父ヤコブが死去し、父ヨハンがその後任となったため、一家はバーゼルへ帰郷した。W. Rouse Ballはダニエルを「若いベルヌーイ家の中で最も有能な人物」と評している。
2.2. 幼少期と教育
父ヨハンは、数学者の経済的報酬が低いことを理由に、ダニエルに実業家になることを勧めた。ダニエルは当初これを拒否し、数学への強い関心を示したが、後に父が個人的に数学を教えるという条件で、ビジネスと医学を学ぶことに同意した。
13歳でバーゼル大学に入学し、論理学と哲学を学んだ。大学在学中も父と兄から微積分学を学び続け、15歳で学士号、16歳で修士号を取得した。彼はバーゼル、ハイデルベルク、ストラスブールで医学を学び、1721年にはエネルギー保存の法則を応用した呼吸のメカニズムに関する博士論文を提出し、解剖学と植物学の博士号を取得した。
2.3. 父との関係
ダニエル・ベルヌーイは父ヨハンとの間に複雑で緊張した関係を築いていたとされている。父ヨハンは、ダニエルが自分と同等と見なされる「不名誉」に耐えられないとして、ダニエルを家から締め出したと伝えられている。この対立は、両者がパリ大学の科学コンテストで共同1位となった際に顕著になった。
さらに、父ヨハンはダニエルの著書『流体力学』(Hydrodynamica)の主要なアイデアを盗用し、自身の著書『Hydraulica』にその内容を盛り込み、出版年を『流体力学』以前の1732年と偽って1739年に出版したとされる。ダニエルは父との和解を試みたものの、父は死ぬまで一方的に息子を逆恨みし、その努力は実を結ばなかった。
3. 学術・職業経歴
ダニエル・ベルヌーイは、その生涯を通じて多岐にわたる学術分野で活躍し、特にサンクトペテルブルクとバーゼルでの教授職、そして数々の重要な著作を通じて、科学界に大きな足跡を残した。
3.1. 教授職と初期の著作
博士号取得後、バーゼル大学で職を得られなかったダニエルは、実務的な医学研修のためヴェネツィアに移った。ヴェネツィアでは、クリスティアン・ゴルトバハの協力を得て、1724年に最初の数学的著作である『数学演習』(Exercitationes)を出版した。この著作には、ヤコポ・リッカチが提出した微分方程式の解法が含まれていた。2年後の1726年には、複合運動を並進運動と回転運動に分解することの頻繁な有用性を初めて指摘した。また、航海用の砂時計を設計し、1725年にはパリ・アカデミー賞を受賞した。
これらの実績を基に、ダニエルは兄ニコラウス2世とともに、1725年からサンクトペテルブルク科学アカデミーの数学教授職を得て、サンクトペテルブルクに移住した。しかし、兄はその8ヵ月後に死去した。ダニエルはサンクトペテルブルクでの生活に不満を抱き、一時的な病気やロシア正教会による検閲、給与に関する意見の相違などを理由に、1733年に同地を離れた。
1734年、彼は植物学の教授職を得て故郷のバーゼル大学に戻った。バーゼル大学では、その後も医学、形而上学、自然哲学の教授職を歴任し、1750年からは念願の物理学の教授職に就き、1766年まで16年間物理学を教えた。彼は生涯で10回にわたりパリ・アカデミー大賞を受賞している。
3.2. オイラーとの協力
ダニエル・ベルヌーイは、同時代の偉大な数学者レオンハルト・オイラーと親しい友人であり、緊密な学術交流を行った。オイラーは1727年に父ヨハンの手配でサンクトペテルブルク科学アカデミーに移り、ダニエルが1733年に同地を離れるまで、両者は助け合いながら生産的な共同研究を行った。
彼らは特に弾性理論とオイラー・ベルヌーイ梁方程式の開発において協力した。オイラーはまた、ベルヌーイの原理を洗練させ、今日のベルヌーイの定理の基礎を築いた。ダニエルがサンクトペテルブルクを去った後も、オイラーは同地に留まったが、両者は終生にわたって親しく交流を続けた。
3.3. 主要著作
ダニエル・ベルヌーイの最も重要な著作は、1738年に出版された『流体力学』(Hydrodynamica)である。この著作は、ジョゼフ=ルイ・ラグランジュの『解析力学』(Mécanique Analytique)と同様に、すべての結果を単一の原理、すなわちエネルギー保存の法則から導き出す構成となっている。
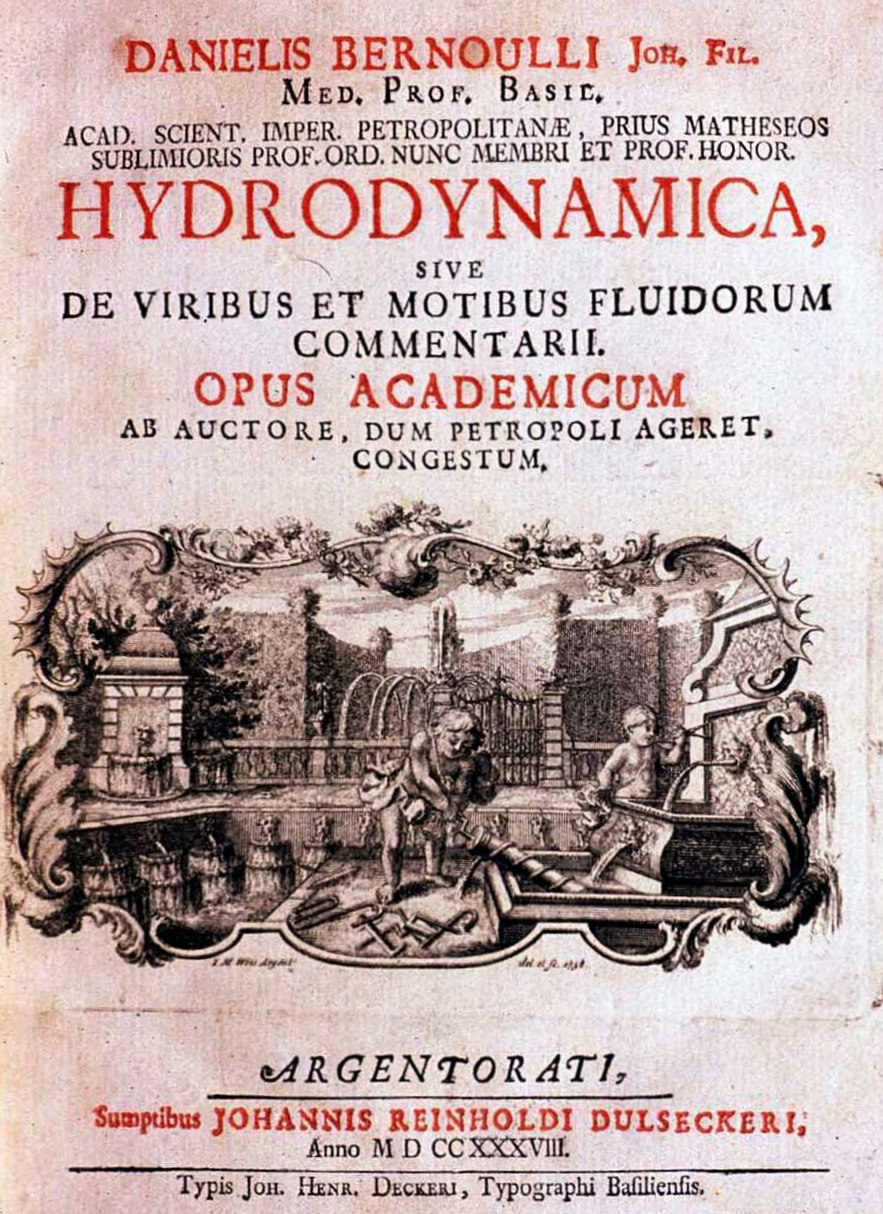
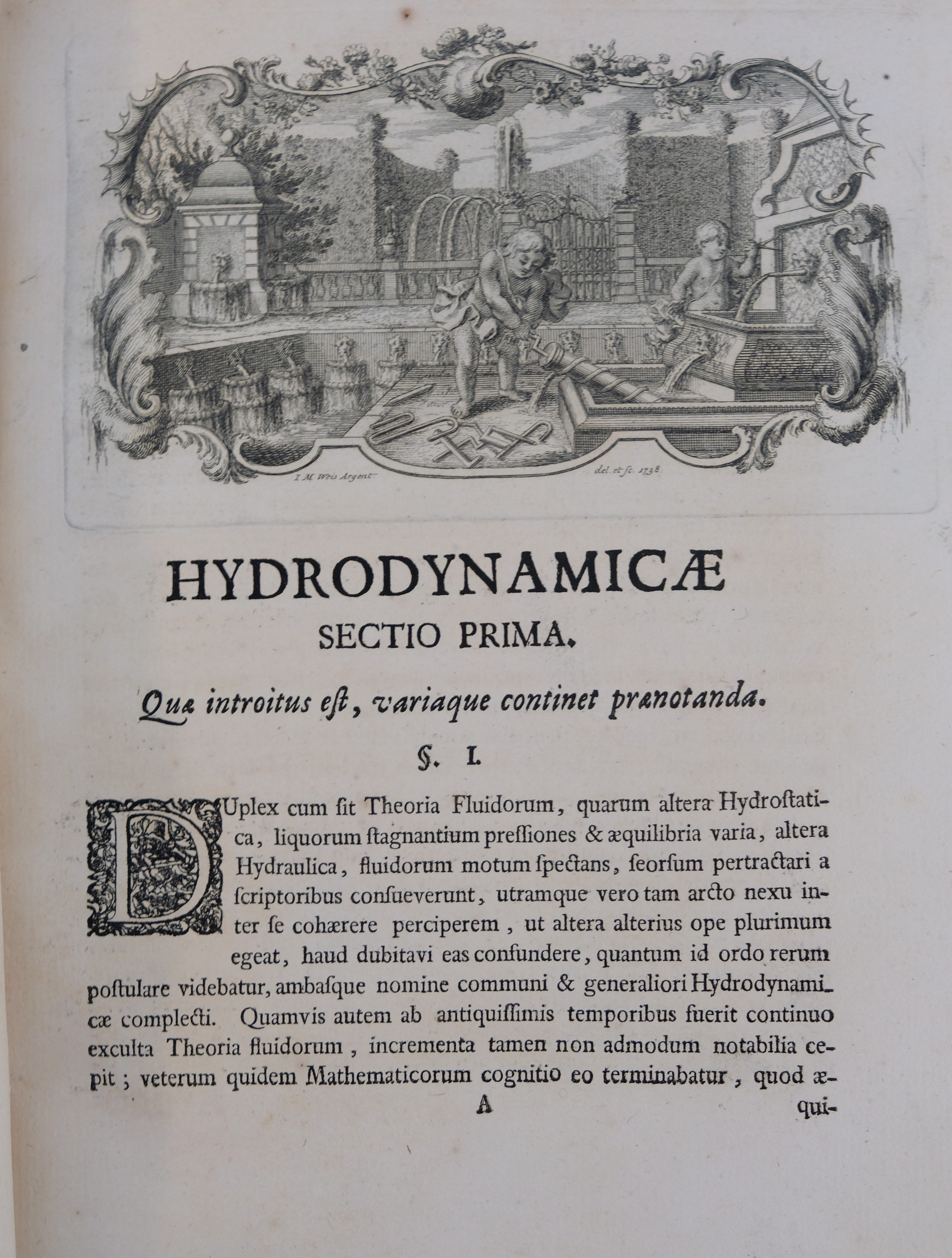
『流体力学』に続いて、彼は潮汐の理論に関する論文を発表し、これはオイラーとコリン・マクローリンの論文とともにフランス科学アカデミーから賞を授与された。これら3つの論文は、アイザック・ニュートンの『自然哲学の数学的諸原理』(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)の出版からピエール=シモン・ラプラスの研究までの間にこの主題に関して行われたすべての議論を含んでいる。
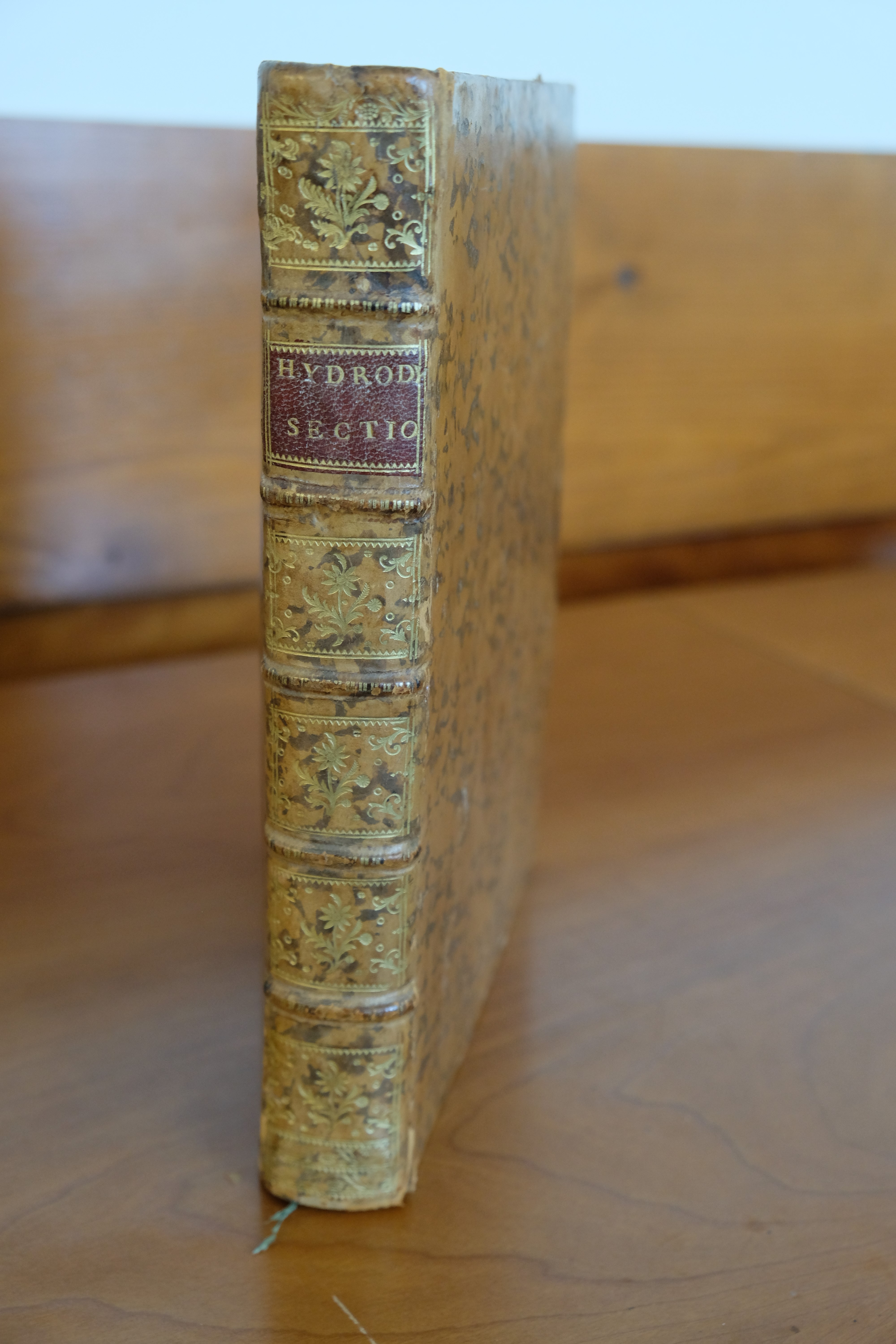
また、ベルヌーイは様々な力学的な問題、特に弦の振動に関連する問題について多数の論文を執筆し、ブルック・テイラーやジャン・ル・ロン・ダランベールによる解法も論じた。
彼の経済学における主要著作は、1738年に学術雑誌『ペテルブルク帝国アカデミー論集』に掲載されたラテン語論文『リスクの測定に関する新しい理論』(Specimen theoriae novae de mensura sortis)である。
4. 科学的貢献
ダニエル・ベルヌーイは、物理学、経済学、統計学の各分野において、画期的な貢献を行った。彼の業績は、後の科学的発展に多大な影響を与えた。
4.1. 物理学
4.1.1. 流体力学とベルヌーイの原理
ダニエル・ベルヌーイは、1738年の著作『流体力学』において、気体運動論の基礎を築き、この理論を用いてボイルの法則を説明した。彼は、自然界の現象が微小な粒子の概念を通じて理解できるという見解を持っていた。
ベルヌーイの原理は、ダニエル・ベルヌーイによって確立された物理学の重要な原理の一つである。この原理は、流体の速度と圧力の間に逆の関係があることを示している。すなわち、流体が速く流れるほどその圧力は低くなり、逆に流体が遅く流れるほど圧力は高くなる。この原理は、圧縮性流体と非圧縮性流体の両方に適用される。
ベルヌーイは、流体が流れる管の壁に小さな穴を開けてストローを差し込むと、流体がストローを伝って上昇する高さが管内の流体の圧力と関連することを発見した。この方法を用いて、彼は血圧を測定する手法を開発し、この方法は1896年にイタリアの医師がより苦痛の少ない方法を発見するまで170年間使用された。現在でも、彼の圧力測定方法は、航空機における空気の速度測定に応用されている。
ベルヌーイの原理は、数学的には以下のように表現される。
ここで、Pは圧力、ρは流体の密度、uは速度である。この原理は、航空機の翼が空気の速度と圧力に応じて揚力を生み出す仕組みや、気化器、ド・ラバル・ノズルなどの設計に利用されている。後に、彼の友人であるレオンハルト・オイラーがこの原理を洗練させ、今日のベルヌーイの定理の基礎を築いた。
4.1.2. その他の物理学的貢献
ダニエル・ベルヌーイは、オイラーとともに弾性理論の研究に取り組み、オイラー・ベルヌーイ梁方程式の開発に貢献した。この方程式は、梁の荷重支持能力とたわみを計算するために用いられる。
彼はまた、弦の振動に関する多数の論文を執筆し、ブルック・テイラーやジャン・ル・ロン・ダランベールによる解法も論じた。彼は気体運動論の先駆者であり、ロバート・ボイルとエドム・マリオットの法則を解釈した。さらに、反動推進による船舶の推進という着想も提示した。
レオン・ブリルアンによれば、重ね合わせの原理は1753年にダニエル・ベルヌーイによって初めて提唱された。「振動系の一般的な運動は、その固有振動の重ね合わせによって与えられる」と彼は述べた。
4.2. 経済学・統計学
4.2.1. リスク回避と効用理論
ダニエル・ベルヌーイは、1738年の論文『リスクの測定に関する新しい理論』(Specimen theoriae novae de mensura sortis)において、サンクトペテルブルクのパラドックスに対する解決策を提示した。この解決策は、リスク回避、リスクプレミアム、そして効用に関する経済理論の基礎となった。
彼は、人々が不確実性を伴う意思決定を行う際、必ずしも可能な金銭的利益を最大化しようとするのではなく、むしろ個人の満足度や便益を含む経済用語である「効用」を最大化しようとすることに気づいた。ベルヌーイは、人間にとって獲得した金銭と効用の間には直接的な関係があるものの、獲得する金銭が増加するにつれてその効用は逓減すること、すなわち限界効用逓減の法則が働くことを認識した。例えば、年間所得が1.00 万 USDの人にとって、追加の100 USDの所得は、年間所得が5.00 万 USDの人よりも大きな効用をもたらすだろうと彼は述べた。
サンクトペテルブルクのパラドックスは、期待値が無限大となるゲームにもかかわらず、人々が参加を拒否するという矛盾を提示する。ベルヌーイはこれを、人が「利益」として考慮すべきは各賞金額の期待値を合計することではなく、各賞金額から得られる「効用」の期待値を合計することであると説明した。限界効用が著しく低下する場合、ゲーム参加の期待効用の総量は有限値となり、参加料から獲得可能な効用量を下回るため、合理的な人々はゲームに参加しないという結論になる。
「ごくわずかな富の増加から得られる満足度(効用)はそれまで保有していた財の数量に反比例する」という彼の発想、つまりかかった費用ではなく限界効用に重きを置くこの考え方は、100年以上経ってからウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズによってベルヌーイとは別に確立された。期待効用理論が完全に復権するのは、200年後に出版された数学者ジョン・フォン・ノイマンと経済学者オスカー・モルゲンシュテルンの大著『ゲームの理論と経済行動』(1944年)においてである。
4.2.2. 統計分析
ダニエル・ベルヌーイによる1766年の天然痘の罹患率および死亡率データの分析は、統計学における打ち切りデータを含む問題を分析する最も初期の試みの一つであった。この研究は、種痘の有効性を実証するために行われた。彼は実証データを活用した初期の統計学的アプローチと方法論を示した。
5. 評価と遺産
ダニエル・ベルヌーイは、その画期的な科学的貢献により、後世の科学に多大な影響を与え、数々の栄誉に輝いた。しかし、彼の遺産には、家族、特に父との複雑な関係にまつわる論争も含まれている。
5.1. 認定と栄誉
ダニエル・ベルヌーイは、その学術的功績が広く認められ、数々の栄誉を受けた。
- 1750年5月には王立協会のフェローに選出された。
- 2002年には、サンディエゴ航空宇宙博物館の国際航空宇宙殿堂に殿堂入りした。
- 彼のキャリアを通じて、パリ科学アカデミー大賞を10回受賞している。
5.2. 歴史的評価と影響
ダニエル・ベルヌーイの力学への貢献は、アイザック・ニュートンの理論とゴットフリート・ライプニッツの微積分法を組み合わせ、運動方程式のエネルギー積分(エネルギー保存の法則)を強力に活用した点に特徴がある。特に、海洋や船舶への応用を含む流体力学に大きく貢献した。彼の潮汐、弦の振動、気体運動論、反動推進に関する研究は、それぞれの分野の発展に寄与した。
経済学における彼の先駆的な貢献、特にリスク回避、効用理論、そしてサンクトペテルブルクのパラドックスの解決は、後の経済学者たちの研究の基礎を築いた。また、天然痘の罹患率および死亡率データの統計分析は、実証データを用いた初期の統計学的アプローチとして高く評価されている。
一方で、彼の家族史的な文脈では、父ヨハン・ベルヌーイとの複雑で緊張した関係、特に『流体力学』の内容を父が盗用したとされる論争は、彼の生涯における批判的な側面として歴史的に評価されている。父ヨハンが息子と同等と評価されたことに激怒し、ダニエルを家から締め出し、死ぬまで一方的に逆恨みしていたという経緯は、彼の個人的な苦悩と学術界の競争の厳しさを示している。
6. 死
ダニエル・ベルヌーイは、1782年3月17日にスイスのバーゼルで亡くなった。彼は生涯を通じてバーゼル大学で教授職を務め、その地で最期を迎えた。