1. 概要
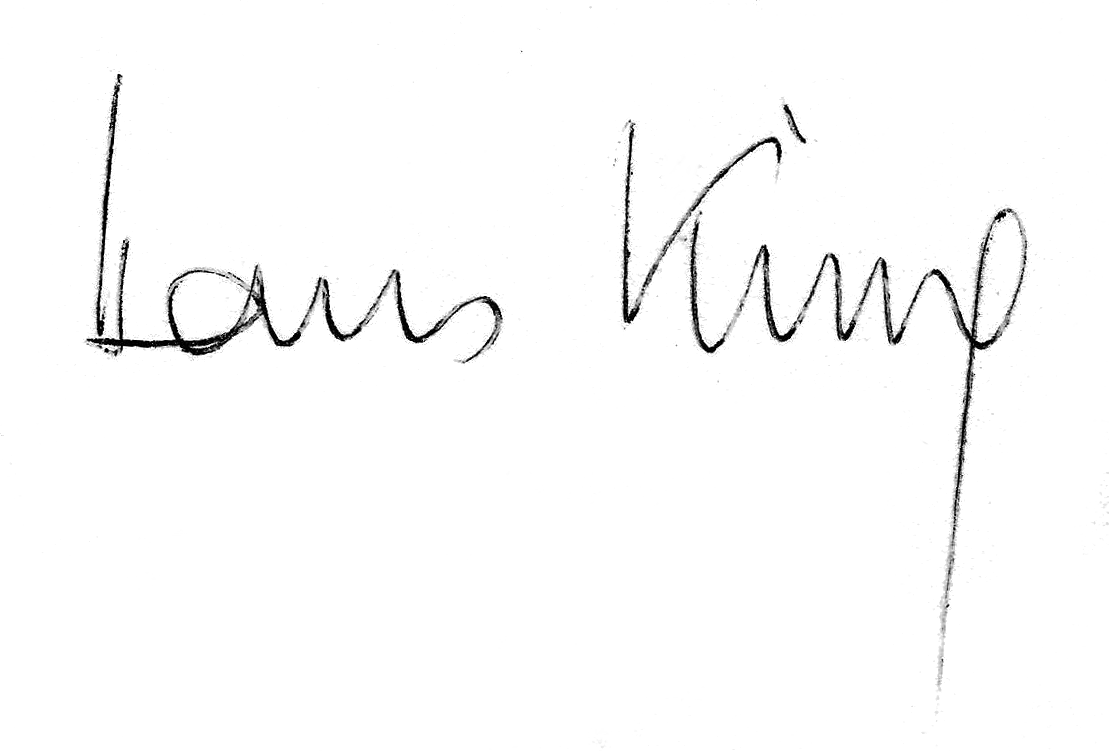
ハンス・キュング(Hans Küngドイツ語、1928年3月19日 - 2021年4月6日)は、スイス出身のカトリック司祭であり、著名な神学者、そして多作な著作家でもありました。彼は、伝統的な教義としてのキリスト教を問い直しつつ、宗教の精神的本質を擁護する立場を取りました。特に、教皇不可謬説に対する彼の批判的見解はバチカンとの激しい論争を巻き起こし、1979年にはカトリック神学を教えるための教員資格を剥奪されましたが、司祭としての地位は維持されました。
キュングは、1960年にテュービンゲン大学の教授に就任し、第2バチカン公会議では最年少の神学顧問を務め、公会議の改革精神に大きく貢献しました。教員資格剥奪後も、彼はテュービンゲン大学でエキュメニカル神学の教授として活動を続け、1995年からは世界倫理構想財団(Stiftung Weltethos)の会長を務めました。この「世界倫理構想」は、世界の諸宗教間の共通点を見出し、普遍的に受け入れられる行動規範を策定しようとする画期的な試みでした。
彼はまた、尊厳死の容認をキリスト教の観点から主張し、安楽死も容認する立場をとるなど、倫理的な問題についても進歩的な見解を示しました。彼の思想は、教会改革、宗教間対話、そして科学と宗教の関係性の再構築に大きな影響を与え、数々の国際的な賞や名誉博士号を授与されました。キュングは生涯にわたり、教皇庁に対する「批判的な忠誠」を貫き、教会内部からの根本的な改革を訴え続けました。
2. 生涯
2.1. 幼少期と教育
ハンス・キュングは1928年3月19日、スイスのルツェルン州シュールゼーで7人兄弟の長男として生まれました。彼の父親は靴店を経営していました。1935年から1948年までシュールゼーとルツェルンの小中学校で学び、1948年に中学校を卒業しました。
1948年から1951年までローマ教皇庁立グレゴリアン大学で哲学を、1951年から1955年まで神学を学びました。彼は特に、非キリスト教徒や異端者に対する救済論の授業に強い関心と熱意を抱いていました。ローマ留学中、キュングはポンティフィシウム・コレギウム・ゲルマニクム・エト・フンガリクム・デ・ウルベという神学校の朝の授業に出席し、朝食前には毎日30分間、前夜に準備された「瞑想の点」に基づき、聖体拝領の教義について熟考しました。さらに、毎年3日から8日間、聖書とキリスト教の内容について静寂の中で黙想する「霊操」と呼ばれる教会活動にも取り組みました。
キュングは、7年間のローマ滞在中に、祈りの実践を献身的に深め、同時にその範囲を広げていきました。彼は、聖ペトロ大聖堂で司教が主宰するミサや教皇の高位ミサで、ラテン語の聖歌やドイツ語の賛美歌が響き渡る中で、完全な静寂の中での祈りを月々、日々にわたって真剣に体験しました。また、日々の聖体拝領に加え、ポンティフィシウム・コレギウム・ゲルマニクムの神学生としての義務も果たしました。これには、朝と夕方の祈り、昼食後と夕食後の共同礼拝室での聖体拝領、修道院の食堂での食事前の祈りが含まれました。夕食前には連祷を唱え、時には晩の祈りや終の祈りも唱えました。彼にとって、学業の過程で祈りを怠ることは許されず、他の修道会共同体でも同様に、祈りが重要視されるべきだと考えていました。
学業の過程で、キュングは徐々に高レベルの祈りの方法に接するようになりました。彼はこれらの方法を熱心に学び、特に「単独で祈る」というレベルに到達することを目指しました。キュングは「神の満ち溢れる臨在と内なる喜びの充足感」をもって、この境地に何度か到達できたと述べています。これは高レベルの祈りの形式を実践するために不可欠でしたが、キュング自身もその達成には多くの困難があったことを認めています。彼は、時には神秘的で高尚、そして霊的な罪深い思想に感染し、これが祈りを困難にし、さらには恐怖を感じさせる原因となり、まだ最高段階に達することができていなかったからだと告白しています。
1954年には、スイスのバーゼル教区の司祭に叙階されました。彼はまた、カール・バルトが編纂した『教会教義学』を何年もかけて研究しました。ローマでの哲学と神学の課程を修了した後、1955年から1957年までソルボンヌ大学とパリ・カトリック学院(Institut Catholique de Paris - ICP)で学びました。ICPで彼は「義認。カール・バルトの教義とカトリックの考察」(Justification. La doctrine de Karl Barth et une réflexion catholiqueフランス語)と題する博士論文を完成させました。後に彼は1999年に発表された「義認に関する共同宣言」の起草者の一人となります。パリでの学業を終えた後も、アムステルダム、ベルリン、マドリード、ロンドンで学び続けました。卒業後、彼はゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの哲学の研究に没頭しました。
2.2. 初期キャリアと第2バチカン公会議
キュングは1年間ミュンスター大学で教鞭を執った後、1960年にドイツのテュービンゲン大学の基礎神学教授に任命されました。彼は同年、『公会議、改革、再一致』を出版し、この著作はいくつかの国でベストセラーとなり、来たる公会議のプログラムの多くを概説しました。
1962年から1965年の第2バチカン公会議では、教皇ヨハネ23世によって「ペリトゥス」(専門家諮問委員)に任命され、34歳という最年少の神学顧問として公会議参加者に助言を行いました。キュングの働きかけにより、テュービンゲン大学のカトリック学部は、後に教皇ベネディクト16世となるヨーゼフ・ラッツィンガーを教義神学の教授に任命しました。しかし、ラッツィンガーが1968年のドイツ学生運動に反発してより保守的な立場に転じたため、両者の協力関係は終焉を迎えました。
1963年のアメリカ合衆国ツアー中、キュングは「教会と自由」と題する講演を国内の複数の大学で行い、25,000人以上の熱狂的な聴衆を集めました。しかし、彼はアメリカ・カトリック大学では登壇を許可されませんでした。同年、彼はイエズス会運営のセントルイス大学から、その後の多くの名誉博士号の最初のものを受け取りましたが、大学はローマからの許可を得なかったとして叱責されました。1963年4月には、ジョン・F・ケネディ大統領の招待を受け、ホワイトハウスを訪問しました。ケネディは彼を政治家グループに紹介し、「この方がカトリック教会の新たなフロンティアの人物だと私は思います」と述べました。
彼の博士論文は、1964年に『義認:カール・バルトの教義』(Justification: The Doctrine of Karl Barth英語)として英語で出版されました。この中で、キュングはバルト神学とカトリック神学における義認の教義に多くの合意点を見出し、その相違は根本的ではなく、教会の分裂を正当化するものではないと結論付けました。この本には、バルト自身がキュングの神学の解釈に同意することを示す手紙が添えられていました。ただし、バルトは、宗教改革は過剰反応であったというキュングの結論には同意しませんでした。キュングはこの本で、バルトがマルティン・ルターと同様に、その不完全さにもかかわらずキリストの体であり続けたカトリック教会に対して過剰に反応したと主張しました。ジャーナリストのパトリシア・レフェベールは、『ナショナル・カトリック・レポーター』誌で、キュングがこの本を執筆した後すぐに、聖務省が「キュングに関する秘密ファイル(悪名高い399/57i)を開設した」と記しています。
2.3. 教皇不可謬説論争と教員資格剥奪
1960年代後半、キュングは19世紀後半の復古カトリック教会のシスマ以来、初めて教皇不可謬説を公に拒否する主要なカトリック神学者となりました。これは彼の著書『無謬か?疑問』(1971年)で表明されました。この本は、バチカンがキュングに以前の著作『教会』に対する疑惑に対処するよう初めて求めた3年後に刊行されました。『無謬か?疑問』の出版後、バチカン当局はキュングにローマへ出頭して告発に答えるよう求めました。キュングは自身の立場を堅持し、教会が集めたファイルの閲覧と、自身の著作を評価している人物との面談を要求しました。
しかし、キュングはこれ以前にも司祭の独身制を批判し、女性聖職者や女性助祭の開放を望んでいました。また、司祭職を離れることを望む司祭への免除禁止を「人権侵害」と呼び、現在のカトリック教会の実践は「福音書と古代カトリックの伝統に矛盾しており、廃止されるべきである」と記述していました。
その結果、1979年12月18日、彼はカトリック神学の教員資格を剥奪されました。アメリカとカナダの60人の神学者がバチカンのこの措置に抗議し、「私たちは公に、彼が間違いなくローマ・カトリック神学者であることを認めます」とバチカンの決定に反論しました。テュービンゲン大学の学生1,000人も抗議のキャンドルナイトを行いました。キュングは後にバチカンの裁定を「私個人の異端審問の経験」と表現しました。レフェベールは次のように記しています。
「彼の3巻からなる回顧録の第2巻『論争の真実』で、キュングは彼に対する告発に80ページを費やしています。ドイツの司教たちとバチカン当局者によるドイツ国外での秘密会議、テュービンゲン大学の同僚11人のうち7人による裏切り、そしてバチカンの告発に答えつつ、公立大学での地位を維持しようとする彼の努力による肉体的・精神的な消耗寸前の状態でした。」
教員資格剥奪後も、彼は司祭であり続けました。テュービンゲン大学のカトリック学部では教えることができなくなったため、大学はキュングが設立し1960年代から主宰していた教会一致神学研究所と、彼の教授職をカトリック学部の管轄外に移しました。キュングは1996年に引退するまで、エキュメニカル神学の終身教授として教え続けました。
2.4. エキュメニカル神学と世界倫理構想
教員資格剥奪後も、キュングはエキュメニカル神学の分野で活発な活動を続けました。1981年にシカゴ大学で3ヶ月間客員教授を務めましたが、カトリック系機関ではノートルダム大学からのみ招かれました。彼はフィル・ドナヒュー・ショーにも出演しました。
1986年10月には、インディアナ州ウェスト・ラファイエットのパデュー大学で開催された第3回仏教徒・キリスト教徒神学会議に参加しました。キュングは、彼の異教間研究が「生きるキリストへの信仰における自身の根源を固めた」と述べ、この信仰が彼のキャリア全体を通じて持続したと語りました。「実際、キュングは長い間、自身の信仰における堅固さと、異なる信仰を持つ人々との対話能力が相補的な美徳であると主張していました。」
1990年代初頭、キュングは「世界倫理構想」(Weltethos)と呼ばれるプロジェクトを開始しました。これは、世界の諸宗教を隔てるものではなく、共通するものを記述し、誰もが受け入れられる最小限の行動規範を作成しようとする試みです。彼の世界倫理のビジョンは、「世界倫理に向けて:初期宣言」という文書に具体化されました。この宣言は、1993年に開催された世界宗教者会議で、世界中の宗教指導者や精神的指導者によって署名されました。後にキュングのプロジェクトは、国連文明間対話年(2001年)へと発展し、キュングは19人の「著名人」の一人として任命されました。このプロジェクトは9月11日のテロ攻撃(2001年9月)の直後に完了したにもかかわらず、米国のメディアでは報道されなかったことにキュングは不満を述べました。引退後も、彼は2011年に世界倫理構想財団の共同設立者として活動しました。
2.5. ローマ教皇庁との関係と批判
キュングは生涯にわたり、ローマ教皇庁、特に教皇ヨハネ・パウロ2世と教皇ベネディクト16世に対して、時に和解的でありながらも、複雑で批判的な関係を維持しました。
1986年、キュングは当時カトリック神学の教員資格剥奪の危機に瀕していた神学者チャールズ・カランと直接面会し、彼に活動を続けるよう励まし、同僚からの支援と裏切りの経験を共有しました。1990年代には、キュングと同様に教義的構造に異議を唱えたためにカトリック神学の教員資格を剥奪され、司祭職を停止された神学者オイゲン・ドリューマンを擁護しました。1992年にテュービンゲン大学でドリューマンがヘルベルト・ハーク教会自由賞を受賞した際、キュングは賛辞を述べました。
数年後、ヨハネ・パウロ2世の列福が検討された際、キュングは「女性と神学者の双方の権利を抑圧した権威主義的な教皇職」であったとして異議を唱えました。彼は、ヨハネ・パウロ2世によるグスタボ・グティエレスやレオナルド・ボフのような解放の神学者たちへの対応は非キリスト教的であると述べました。キュングはヨハネ・パウロ2世をその名前で呼ぶことは一度もなく、常に「教皇ヴォイティワ」と呼び続け、そこに彼の怒りが込められていました。2003年には、教皇ピウス9世の列福を「教会政治のジェスチャー」への堕落の証拠と見なしました。
キュングはヨハネ・パウロ2世との面会を12回以上試みましたが、成功しませんでした。しかし、2005年9月26日、彼はカステル・ガンドルフォにある教皇の邸宅で、かつての同僚である教皇ベネディクト16世と友好的な夕食の議論を行いました。彼らは明白な意見の相違がある話題を避け、代わりにキュングの宗教間および文化に関する活動に焦点を当てました。教皇は、宗教間の対話および世俗的理性との出会いにおいて、人類の重要な道徳的価値の新たな認識に貢献しようとするキュングの努力を認めました。キュングは、会談に関するバチカンの声明をベネディクト16世自身が作成し、彼が「一言一句承認した」と報告しました。
2009年の『ル・モンド』紙のインタビューで、キュングは聖ピオ十世会の4人の司教に対する破門解除を巡る教皇ベネディクト16世の行動を強く批判しました。彼は教皇の生涯にわたる現代社会からの孤立を非難し、ベネディクトの「より小さく、より純粋な教会」への願望の結果として、「教会はセクトになる危険性がある」と述べました。この発言は、枢機卿団の首座であるアンジェロ・ソダーノ枢機卿からの叱責を招きました。
2010年4月、キュングはすべてのカトリック司教に宛てた公開書簡を発表し、教皇ベネディクト16世の典礼、教会協力、宗教間問題の扱い、そしてカトリック教会における性的虐待スキャンダルを批判しました。彼はさらに、司教たちに、発言することや地域での解決策に取り組むことから、別のバチカン公会議の開催を求めることまで、6つの提案を検討するよう呼びかけました。彼は、カトリック神学教授たちによって公布されたカトリック教会の改革を求めるドイツ語の覚書「教会2011:新たな始まりの必要性」の署名者の一人でした。
3. 主要な著作と思想
3.1. 主要著作
キュングの主な著作は以下の通りです。
- 『公会議、改革、再一致』(1960年)
- 『義認:カール・バルトの教義』(1964年)
- 『教会』(1967年)
- 『無謬か?疑問』(1971年):この本では、キュングは教皇不可謬説に対する批判的な見解を公に表明し、その結果、バチカンとの激しい論争を引き起こしました。
- 『キリスト教徒であることについて』(1974年):キュングは、キリスト教をその根源にまで遡り、現代の学術研究を広範に用いて、福音書から歴史上のイエスについて知りうることを抽出しました。教会の公会議の教えや人間当局から提唱された高度に発達した神学的命題から始めるのではなく、彼は別の可能性を問いました。「最初の弟子たちのように、実在の人間イエス、彼の歴史的なメッセージと顕現、彼の生と運命、彼の歴史的な現実と歴史的な活動から出発し、それからこの人間イエスと神の関係、彼と父との一致について問う方が、新約聖書の証拠や現代人の歴史的思考様式に合致するのではないか?」
- 『神は存在するか?』(1980年)
- 『永遠の生命?』(1984年)
- 『キリスト教と世界の諸宗教:イスラム教、ヒンドゥー教、仏教との対話の道』(1986年)
- 『キリスト教と中国宗教』(ジュリア・チンとの共著、1988年)
- 『神の受肉:未来のキリスト論へのプロレゴメナとしてのヘーゲルの神学的思想への序論』(1988年)
- 『第三千年紀のための神学:エキュメニカルな見解』(1990年)
- 『地球規模の責任:新しい世界倫理を求めて』(1991年)
- 『ユダヤ教:昨日と明日』(1992年)
- 『信仰:現代のために説明された使徒信条』(1993年)
- 『偉大なキリスト教思想家たち』(1994年)
- 『キリスト教:その本質と歴史』(1995年)
- 『世界政治と経済のための世界倫理』(1997年)
- 『尊厳ある死』(ヴァルター・イェンスとの共著、1998年):この本で、キュングはキリスト教の観点から安楽死の受容を肯定しました。
- 『カトリック教会:簡潔な歴史』(2001年)
- 『女性とキリスト教』(2001年、改訂版2005年)
- 『自由への私の闘い:回顧録』(2003年)
- 『すべてのものの始まり:科学と宗教』(Der Anfang aller Dingeドイツ語、2005年):テュービンゲン大学での一般教養講義に基づいて、彼は科学と宗教の関係性について論じました。量子物理学から神経科学に至る分析の中で、彼は米国での進化論に関する議論にもコメントし、進化論の教育に反対する人々を「ナイーブで未開」と断じました。
- 『なぜ私はまだクリスチャンなのか』(2006年)
- 『イスラム教:過去、現在、未来』(2007年)
- 『論争の真実:回顧録II』(2008年)
- 『私が信じるもの』(Was ich glaubeドイツ語、2010年):この本で、キュングは自然との個人的な関係、そしてそれを正しく観察する方法について記述しました。これは、誤った狂信的な自然愛に陥ることなく、神の創造物から力を引き出すことを意味しました。
- 『経験された人間性』(Erlebte Menschlichkeitドイツ語、2013年):キュングは、身体的な病気、痛み、または認知症によって生活が耐え難くなった場合、人々は自らの命を終わらせる権利があると信じていると述べました。彼は自身がパーキンソン病を患い、視力と書く能力を失いつつあったため、自殺幇助の選択肢を検討していることを示唆しました。キュングは、ヨハネ・パウロ2世の例に倣いたくないと記しました。
3.2. 神学的・哲学的見解
キュングの神学的・哲学的見解は、カトリック教会内外における広範な議論と改革の推進に影響を与えました。
- 教会改革**: 彼は、司祭の独身制の強制、教会が信頼を失っていること、女性司祭の禁止、そしてローマ教皇庁が「クレムリンのような状態になっている」ことに対して批判を繰り返しました。彼は、教皇の権威を人間が作ったものであり、したがって変更可能であると主張し、神によって定められたものではないと見なしました。キュングは、神性が男性と女性の両方の特性を含み、同時にそれらを超越していることを理解できない場合、深刻な結果を招くと指摘しました。特にローマ教皇庁とオコナー枢機卿が女性司祭を拒否する根拠として、神が父でありイエスがその子であり、イエスの弟子がすべて男性であったことなどを挙げ、父権的な教会を父権的な神と共に擁護していると批判しました。
- 教会一致と宗教間対話**: キュングは教会一致運動に深く関与し、プロテスタントや正教会との対話を推進しました。また、彼の「世界倫理構想」は、世界の諸宗教が共通して持つ価値観を探求し、普遍的な行動規範を提唱するものでした。彼は、自らの信仰に堅固であることと、異なる信仰を持つ人々との対話能力は相補的な美徳であると強調しました。
- 科学と宗教の関係**: キュングは科学と宗教の間の対話を重視し、両者の関係性を調和的に捉えました。彼は『すべてのものの始まり』の中で、進化論の教育に反対する人々を「ナイーブで啓蒙されていない」と批判し、科学的発見と神学的理解の統合を主張しました。
- 生命倫理**: 彼の倫理的見解は特に尊厳死や安楽死の分野で物議を醸しました。キュングは、重度の病気や苦痛、認知症によって生活が耐え難くなった場合、人々は自らの命を終わらせる権利があると主張しました。彼は、自身がパーキンソン病を患い、視力や書く能力を失いつつあったため、自殺幇助の選択肢を検討していると公言し、教皇ヨハネ・パウロ2世が人生の終焉に示した態度とは異なる立場を取りました。
4. 私生活
キュングは生涯独身を通し、司祭としての公的な立場を維持しました。しかし、2021年10月、彼の親友で同僚であったヴァルター・イェンスの未亡人であるインゲ・イェンスは、キュングが彼の自宅に住む人生の伴侶がいたことを確認しました。
5. 死去
ハンス・キュングは2021年4月6日、ドイツのテュービンゲンの自宅で93歳で死去しました。
彼の死去に際し、教皇庁生命アカデミーは「前世紀の偉大な神学者が消滅した。彼の思想と分析は、カトリック教会、諸教会、社会、文化について常に熟考させるものとなるだろう」と追悼の意を表明しました。同様にバチカンから処遇を受けた同僚の神学者チャールズ・カランは、キュングを「過去60年間におけるカトリック教会改革のための最も力強い声」と評し、彼の著作があまりにも多作であったため「彼が書いたものを全て読めた人物を私は知らない」と述べました。
6. 評価と影響
6.1. 肯定的な評価と貢献
ハンス・キュングは、その神学的洞察力、教会改革に向けた勇気ある努力、そしてエキュメニカル運動および宗教間対話における先駆的な貢献によって、広く肯定的な評価を受けました。
彼は第2バチカン公会議において最年少の神学顧問として、公会議の改革精神の形成に重要な役割を果たしました。特に、当時のジョン・F・ケネディ大統領から「カトリック教会の新たなフロンティアの人物」と評されたことは、彼の進歩的な姿勢が広く認められていたことを示しています。
キュングの最も画期的な貢献の一つは、「世界倫理構想」です。これは、異なる宗教間および世俗的な合理性の対話を通じて、人類の基本的な道徳的価値の新たな認識に貢献しようとする彼の努力として、教皇ベネディクト16世からも認められました。彼の異宗教間研究は、自身のキリストへの生きた信仰の根源を強固にしたとキュング自身が述べており、自身の信仰への堅固さと異なる信仰を持つ人々との対話能力が相補的な美徳であるという彼の信念を裏付けています。
また、キュングは多作な著作家であり、彼の膨大な著作は、教会改革の必要性、科学と宗教の調和、そして人類共通の倫理的基盤の探求といったテーマを深掘りしました。彼の著作は、読者や他の神学者に深い影響を与え、カトリック教会内外での議論を活性化させました。
6.2. 批判と論争
キュングの神学的立場は、特に教皇不可謬説に対する批判以外にも、いくつかの論争を引き起こしました。
最も顕著なのは、彼の教皇不可謬説に対する公開の批判であり、これが1979年にカトリック神学の教員資格剥奪という結果を招きました。この出来事は、キュング自身が「私個人の異端審問の経験」と述べたように、彼にとって大きな個人的苦痛をもたらし、広範な学術的・宗教的抗議を呼び起こしました。彼は、司祭の独身制、女性司祭の禁止、そして司祭職を離れることを望む司祭への免除禁止を「人権侵害」と呼び、これらのカトリック教会の慣行が「福音書と古代カトリックの伝統に矛盾しており、廃止されるべきである」と強く主張しました。
また、彼の安楽死や尊厳死に対する見解も物議を醸しました。キュングは、身体的な病気、痛み、または認知症によって生活が耐え難くなった場合、人々は自らの命を終わらせる権利があると公に主張し、自身もパーキンソン病の進行により自殺幇助を検討していることを示唆しました。これは、カトリック教会の伝統的な生命倫理観とは異なる立場であり、教会内外で批判的な議論を引き起こしました。
さらに、キュングは教皇ヨハネ・パウロ2世の列福に異議を唱え、彼の教皇職を「女性と神学者の権利を抑圧した権威主義的なもの」と非難しました。彼は解放の神学者たちへの対応が非キリスト教的であったと主張し、教皇の行動が教会の問題を悪化させたと見なしました。教皇ベネディクト16世に対しても、聖ピオ十世会の司教たちの破門解除や、彼の「より小さく、より純粋な教会」への願望が教会を「セクト」化する危険があると批判しました。これらの批判は、枢機卿団からの反論を招くなど、教皇庁との緊張関係を維持し続けました。
7. 受賞と栄誉
ハンス・キュングは、その生涯において学術的および社会的な貢献を称えられ、数々の賞や名誉学位、市民名誉称号を受けました。
| 年 | 賞・栄誉 |
|---|---|
| 1991 | スイス文化賞 |
| 1992 | カール・バルト賞 |
| 1998 | テオドール・ホイス財団賞 |
| 1998 | ロンドン国際キリスト教ユダヤ教評議会からの異教徒間金メダル |
| 1999 | ルター派都市連盟賞 |
| 2003 | ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章 |
| 2005 | 庭野平和賞 |
| 2005 | バーデン=ヴュルテンベルク州功労勲章 |
| 2006 | レフ・コペレフ賞 |
| 2007 | ドイツフリーメイソン文化賞 |
| 2007 | テュービンゲン市名誉市民 |
| 2008 | ハインリヒ・ハイネ友の会(デュッセルドルフ)市民的勇気名誉賞 |
| 2008 | ドイツ国連協会(DGVN)より「平和と国際理解への傑出した貢献、特に人類、寛容、そして世界の主要な宗教間の対話への模範的な取り組み」に対しオットー・ハーン平和メダル金メダル |
| 2009 | ポツダム大学アブラハム・ガイガー・コレグからのアブラハム・ガイガー賞 |
| 2017 | 2005年にヴィンチェンツォ・カズッリによって発見された小惑星190139 ハンスキュングが彼にちなんで命名されました。 |
また、彼は以下のような名誉博士号を多数授与されました。
| 年 | 授与大学・機関 |
|---|---|
| 1963 | セントルイス大学(法学博士) |
| 1966 | パシフィック・スクール・オブ・レリジョン(神学博士、カリフォルニア州バークレー) |
| 1970 | ロヨラ大学シカゴ校(文学博士) |
| 1971 | グラスゴー大学(神学博士) |
| 1984 | トロント大学(法学博士) |
| 1985 | ケンブリッジ大学(神学博士) |
| 1985 | ミシガン大学(人文学博士、アン・アーバー) |
| 1995 | ダブリン大学(神学博士) |
| 1999 | ウェールズ大学スウォンジー校(神学博士) |
| 1999 | ラマポ・カレッジ・オブ・ニュージャージー(人文学博士) |
| 2000 | ヘブライ・ユニオン・カレッジ・ジューイッシュ・インスティチュート・オブ・レリジョン(文学博士、シンシナティ) |
| 2002 | フロリダ国際大学(神学博士) |
| 2003 | エキュメニカル神学校(神学博士、デトロイト) |
| 2004 | ジェノヴァ大学(名誉博士) |
| 2011 | マドリード国立通信教育大学(名誉博士) |
8. 大衆文化における言及
ハンス・キュングは、文学作品においても言及されています。
- ジュリアン・メイの『旧石器時代追放者の叙事詩』シリーズの第3巻『非誕生の王』では、脇役のサリヴァン・トンがかつて「フォーダム大学のキュング道徳神学教授」であったとされています。
- ルイーズ・エルドリッチの『リビング・ゴッドの未来の家』では、シーダー・ホーク・ソングメーカーのお気に入りの神学者としてキュングが挙げられています。