1. Overview

ベン・ロイ・モッテルソン(Ben Roy Mottelson英語、1926年7月9日 - 2022年5月13日)は、アメリカ合衆国出身のデンマーク系核物理学者である。彼は原子核の非球形幾何学に関する研究、特に原子核における集団運動と粒子運動の関連性の発見、およびこの関連性に基づいた原子核構造理論の開発に貢献した。この業績により、1975年にオーゲ・ニールス・ボーア、レオ・ジェームス・レインウォーターと共にノーベル物理学賞を共同受賞した。彼の研究は、原子核の振る舞いをより深く理解するための新たな理論的・実験的研究を刺激し、核物理学の発展に大きな影響を与えた。また、彼は科学者としての社会的責任を重視し、「Bulletin of the Atomic Scientists」の理事を務めるなど、科学界と社会への貢献も行った。
2. 初期生と教育
ベン・ロイ・モッテルソンの初期の人生と教育は、彼の後の輝かしい科学的キャリアの基礎を築いた。
2.1. 出生地と家族背景
モッテルソンは1926年7月9日にアメリカ合衆国イリノイ州シカゴで生まれた。父親は技術者のグッドマン・モッテルソン、母親はジョージア(ブルーム)である。彼の家族はユダヤ人であった。イリノイ州ラ・グランジュにあるライオンズ・タウンシップ高等学校を卒業した。
2.2. 学歴と学位
高校卒業後、モッテルソンはアメリカ合衆国海軍に入隊し、パデュー大学の士官訓練に派遣された。彼は1947年に同大学で学士号を取得した。その後、ハーバード大学に進学し、1950年に核物理学の博士号(Ph.D.)を取得した。彼の博士論文指導教員は、後に量子電磁力学の研究で1965年にノーベル賞を受賞する理論物理学者ジュリアン・シュウィンガーであった。
3. 経歴と研究
モッテルソンは、ハーバード大学からコペンハーゲンに移り、ニールス・ボーア研究所や北欧理論物理学研究所(Nordita)で核物理学者としてのキャリアを確立した。彼の研究は、原子核の集団運動と粒子運動の関連性を解明し、原子核構造の理論的モデルを構築することに焦点を当てた。
3.1. コペンハーゲンでの研究
コペンハーゲンに移った後、モッテルソンは核物理学者として研究を開始した。1953年には、コペンハーゲンに拠点を置いていたCERNの理論研究グループのスタッフに任命され、1957年に新設された北欧理論物理学研究所(Nordita)の教授に就任するまでその職を務めた。
3.2. 主要学術機関での活動
彼は北欧理論物理学研究所(Nordita)の教授として長期にわたり活動した。また、1959年春にはカリフォルニア大学バークレー校の客員教授を務めた。1971年にはデンマークに帰化し、デンマーク国籍を取得した。1993年から1997年まで、イタリアのトレントにある欧州理論研究センター(ECT*)の所長を務めた。
3.3. 原子核構造理論の研究
モッテルソンの主要な科学的貢献は、原子核の構造に関する理論の開発である。彼は、原子核内の集団運動と個々の粒子の運動の関連性を解明し、原子核の非球形幾何学的構造を説明するモデルを構築した。
3.3.1. 集団運動と粒子運動の関連性
1950年から1951年にかけて、ジェームス・レインウォーターとオーゲ・ニールス・ボーアは、個々の核子の振る舞いを考慮し始めた原子核のモデルを開発した。これらのモデルは、原子核を内部構造がほとんどないものとして扱う単純な液滴模型を超え、特定の原子核における電荷の非球形分布を含む多くの核的特性を説明できる最初のモデルであった。モッテルソンはオーゲ・ボーアと協力し、これらの理論モデルと実験データを比較した。1952年から1953年にかけて、ボーアとモッテルソンは一連の論文を発表し、理論と実験の間に密接な一致があることを示した。例えば、特定の原子核のエネルギー準位が回転スペクトルによって記述できることを示した。この研究は、新たな理論的および実験的研究を刺激した。
3.3.2. 原子核構造モデルの開発
1957年夏、デイヴィッド・パインズがコペンハーゲンを訪れ、ボーアとモッテルソンに超伝導の理論で開発されたペアリング効果を紹介した。これにより、彼らは偶数原子核と奇数原子核間のエネルギー準位の差を説明するために、同様のペアリング効果を原子核に導入する着想を得た。彼らは、殻模型によって記述される核子の独立粒子運動と、液滴模型によって記述される核子の集団運動を統一的に記述する集団運動模型を1953年に構築した。また、1958年には原子核における超流動状態の発現を指摘し、高スピン状態での超流動状態から常流動状態への相転移の可能性を示唆するなど、「有限量子多体系としての原子核」という概念を生み出した。
4. 主要著作と受賞歴
モッテルソンの業績は、重要なモノグラフや数々の権威ある賞によって広く認められている。
4.1. 単著書「Nuclear Structure」
モッテルソンはオーゲ・ボーアと共同で、核構造物理学における重要なモノグラフ「Nuclear Structure」を執筆した。この著作は全2巻からなり、第1巻「Single-Particle Motion」は1969年に、第2巻「Nuclear Deformations」は1975年に出版された。これらの巻は、核構造物理学における「バイブル的な教科書」として広く読まれ、その分野の発展に不可欠な貢献を果たした。
4.2. ノーベル物理学賞(1975年)
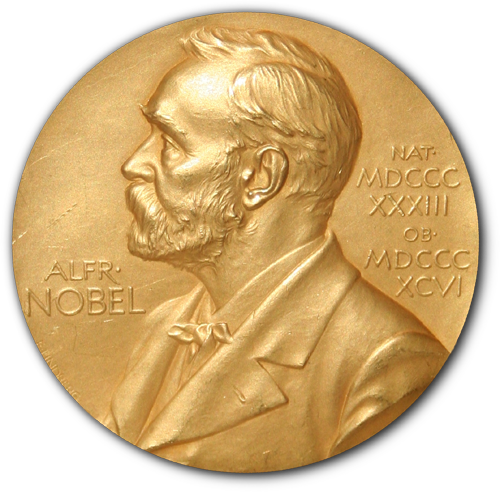
モッテルソンは、ジェームス・レインウォーター、オーゲ・ニールス・ボーアと共に、原子核構造理論への貢献により、1975年のノーベル物理学賞を共同受賞した。受賞理由は、「原子核における集団運動と粒子運動の間の関連性の発見、およびこの関連性に基づいた原子核構造理論の開発」であった。この受賞は、原子核物理学における彼の画期的な研究が国際的に認められたことを示すものであり、原子核の複雑な振る舞いを理解するための新たな道を開いた。
4.3. その他の受賞と名誉
モッテルソンはノーベル賞以外にも数々の栄誉を受けている。1969年には原子力平和賞を受賞した。彼はフィンランド科学文学協会の名誉会員、アメリカ哲学協会の会員、バングラデシュ科学アカデミーおよびノルウェー科学文学アカデミーの外国人フェローであった。
5. 思想と社会活動
モッテルソンは単なる科学者にとどまらず、その科学哲学と社会に対する責任感においても特筆すべき人物である。
5.1. 科学哲学と研究アプローチ
モッテルソンの研究アプローチは、原子核内の集団的な動きと個々の粒子の動きという異なるスケールの現象を統一的に記述しようとするものであった。これは、複雑な量子多体系としての原子核を深く理解しようとする彼の科学哲学を反映している。彼の理論は、液滴模型や殻模型といった既存のモデルの限界を超え、原子核の非球形幾何学的構造や超流動状態といった現象を説明することを可能にした。
5.2. 社会参加と科学界への貢献
モッテルソンは、科学界および社会における積極的な参加と貢献でも知られている。彼は「Bulletin of the Atomic Scientists」の理事会の後援者の一員であった。この組織は、核兵器の脅威やその他の地球規模の課題について、科学的知見に基づいた情報提供と議論を行うことを目的としており、彼の核物理学の専門知識と平和への関与を示している。
6. 個人的な生活
モッテルソンはデンマークとアメリカ合衆国の二重国籍を保持しており、コペンハーゲンに居住していた。彼は1948年にナンシー・ジェーン・レノと結婚し、彼女が1975年に亡くなるまで連れ添い、2人の息子と1人の娘をもうけた。その後、1983年にブリッタ・マーガー・シーグムフェルトと再婚した。
7. 死去
ベン・ロイ・モッテルソンは2022年5月13日にコペンハーゲンで、95歳で死去した。
8. 遺産と影響力
モッテルソンの科学的遺産は、核物理学の分野に深く根ざしており、その影響力は現在も続いている。
8.1. 核物理学分野への影響
彼の原子核構造理論、特に集団運動と粒子運動の関連性の解明は、核物理学の分野に革命をもたらした。彼の研究は、原子核が単純な液滴ではなく、複雑な内部構造を持つ量子多体系であることを明らかにし、非球形電荷分布や回転スペクトルといった現象を説明する初のモデルを提供した。また、超伝導理論から着想を得たペアリング効果の導入や、原子核における超流動状態の指摘は、原子核物理学における新たな研究分野を開拓した。彼の理論的枠組みは、後続の多くの実験的・理論的研究の基礎となり、現代の核物理学の発展に不可欠な貢献を果たした。
8.2. 科学界による評価
モッテルソンの業績は、科学界から高く評価されている。彼がオーゲ・ボーアと共著した「Nuclear Structure」は、核構造物理学の標準的な教科書として広く認識されており、その分野の学生や研究者にとって不可欠な文献となっている。ノーベル賞の受賞は、彼の研究が原子核物理学の最も重要な進歩の一つであるという国際的な合意を裏付けるものである。彼の理論は、原子核の振る舞いを予測し、理解するための強力なツールを提供し、その後の核物理学の進歩に計り知れない影響を与えた。
9. 関連項目
- ノーベル物理学賞受賞者の一覧
- ユダヤ系ノーベル賞受賞者の一覧
- 核物理学
- 原子核
- 集団運動模型
- オーゲ・ニールス・ボーア
- ジェームス・レインウォーター
- ニールス・ボーア研究所
- 北欧理論物理学研究所
- ジュリアン・シュウィンガー