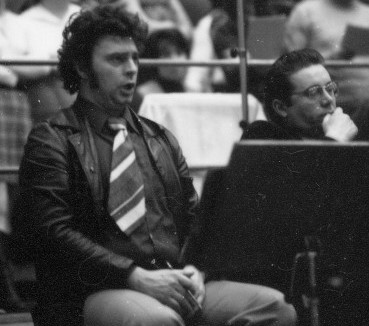1. 少年時代と教育
1.1. 幼少期と教育
ペーター・シュライアーは1935年7月29日にザクセン自由州マイセンで生まれた。マイセン近郊のガウエルニッツという小さな村で育ち、父親はそこで教師、カントル(教会楽長)、そしてオルガン奏者を務めていた。
1945年6月、ドレスデン空襲による壊滅的な被害からわずか数ヶ月後、10歳になる直前のシュライアーは、著名な少年合唱団であるドレスデン聖十字架合唱団の寄宿学校に入学した。当時、合唱団は再編の途上にあり、シュライアーは他の少年合唱団員たちと共にドレスデン郊外の地下室で生活していた。合唱団の指揮者であったルドルフ・マウアースベルガーは、すぐにシュライアーの才能を見抜き、彼に多くのアルトのソロパートを任せただけでなく、彼の声に合わせて楽曲を創作することもあった。この時期(1948年から1951年)に録音されたアルトソロの音源は、後にCDとして再発売されている。
16歳で声変わりを迎え、彼はかねてから熱望していたテノール歌手となった。これは、J.S.バッハの受難曲や『クリスマス・オラトリオ』に登場する福音史家が全てテノールであったことに深く影響されていた。プロの歌手になることを決意したシュライアーは、1954年から1956年まで個人的に声楽のレッスンを受け、その後ドレスデン音楽大学に進学して声楽を学ぶ傍ら、指揮も専攻した。
2. 音楽家としての経歴
シュライアーはオペラ歌手として、またコンサートやリートの解釈者として、多岐にわたる輝かしいキャリアを築き上げた。その知的なアプローチと深い表現力は、彼を20世紀を代表するテノール歌手の一人とした。
2.1. オペラでの経歴
シュライアーのプロとしての舞台デビューは1957年、ドレスデン国立歌劇場でベートーヴェンのオペラ『フィデリオ』の第一の囚人役だった。彼のブレイクスルーは1962年、モーツァルトの『後宮からの誘拐』におけるベルモンテ役で訪れた。また、同じくモーツァルトの『魔笛』ではタミーノ役でも成功を収めた。特に、戦後最高のモーツァルト指揮者であったカール・ベームのもとで数々のモーツァルト作品を歌い、彼自身もまた最高のモーツァルト歌手の一人として広く認識されている。
1963年にはベルリン国立歌劇場の団員となり、同歌劇場の主要な歌手として活躍した。1966年からは長年にわたりウィーン国立歌劇場の年間ゲスト歌手を務め、同年にはカール・ベーム指揮のワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』で若い水夫役としてバイロイト音楽祭に初出演した。これは彼のキャリアで唯一のバイロイト音楽祭への出演となった。1967年からは25年間にわたり、毎年ザルツブルク音楽祭のプログラムに参加した。
1969年にはエンゲルベルト・フンパーディンクのオペラ『ヘンゼルとグレーテル』の魔女役でCD録音に参加し、シュターツカペレ・ドレスデンと共演した。彼はキャリアを通じて60以上のオペラ役を演じた。特に重要視していたのは、ハンス・プフィッツナーのオペラ『パレストリーナ』のタイトルロールであった。彼はこの役を、世界初演の地であり、過去にナチスとの関係が深かった旧西ドイツ(当時)のミュンヘン(バイエルン国立歌劇場)だけでなく、反ナチズムを国是としていた旧東ドイツの東ベルリンでも歌い、当時の東ドイツでは論争を巻き起こした。シュライアーが演じたワーグナー作品には、『ラインの黄金』のローゲや『ジークフリート』のミーメなどがある。
2.2. コンサートおよびリート
シュライアーは、J.S.バッハの受難曲における福音史家役で特に高い評価を得た。彼は『マタイ受難曲』、『ヨハネ受難曲』、そして『クリスマス・オラトリオ』でこの役を歌い、数多くの録音を残した。ルドルフ・マウアースベルガーやエルハルト・マウアースベルガー、カール・リヒター、クラウディオ・アバド、ヘルベルト・フォン・カラヤンといった著名な指揮者たちと共演した録音は特に有名である。また、ヘルムート・リリングともバッハの受難曲やオラトリオを録音している。1979年に東ベルリンで行われた『マタイ受難曲』250周年記念演奏会(メンデルスゾーンによる復活蘇演150周年記念も兼ねていた)では、その見事な歌唱を披露した。
彼はまた、定期的にトーマナー合唱団やゲヴァントハウス管弦楽団とバッハのカンタータを録音し、アデーレ・シュトルテ、アンネリース・ブルマイスター、テオ・アダムといったソリストたちと共演した(例: 1970年録音の聖霊降臨祭のためのカンタータBWV 172『響きわたれ、歌よ、弦よ!』)。
コンサート活動に加え、シュライアーはドイツ歌曲の優れた解釈者としても知られていた。彼はキャリアを通じて、シューベルトやシューマンの歌曲集を歌い続け、数々の録音を残した。テキストを深く理解し、それを音楽表現へと昇華させる彼の知的なアプローチと情熱的な演奏は、高く評価された。
2.3. 国際的な活動
シュライアーは、旧ドイツ民主共和国(東ドイツ)出身の芸術家としては極めて稀なほど、国際的な舞台で活躍した。彼はメトロポリタン歌劇場など、世界有数の歌劇場に定期的に出演し、その類稀な才能を世界に知らしめた。
特にウィーン国立歌劇場では、1967年にタミーノ役でデビューして以来、ベルモンテ、モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』のドン・オッターヴィオ、『イドメネオ』のタイトルロール、リヒャルト・シュトラウスの『カプリッチョ』のフラマン、チャイコフスキーの『エフゲニー・オネーギン』のレンスキー、ロッシーニの『セビリアの理髪師』のアルマヴィーヴァ伯爵、ワーグナーの『ラインの黄金』のローゲなど、数多くの役を演じ、合計で200回もの公演に出演した。彼の国際的な活動は、東ドイツの芸術家が西側の主要な音楽シーンで成功を収めることが困難であった時代において、特筆すべきものであった。
3. 指揮者としての経歴
歌手としての輝かしいキャリアと並行して、シュライアーは1970年代初頭から指揮者としても活動を開始した。彼は特にモーツァルト、J.S.バッハ、そしてハイドンの作品に深い関心を持ち、これらの作曲家の解釈において才能を発揮した。
彼はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やニューヨーク・フィルハーモニックといった世界的に有名なオーケストラを指揮した。バッハのオラトリオの演奏では、しばしば指揮と福音史家の歌唱を同時にこなすという、並外れた能力を示した。
日本においては、2005年2月4日に石川県立音楽堂で行われたオーケストラ・アンサンブル金沢の定期公演に登場し、J.S.バッハの『マタイ受難曲』を全て暗譜で指揮しながら、自らエヴァンゲリスト役を歌い上げた。これは彼が日本でエヴァンゲリストとして歌唱した最後の機会となった。
4. 引退と晩年の活動
ペーター・シュライアーは2000年6月をもってオペラの舞台から引退した。ベルリン国立歌劇場での最後のオペラ出演は『魔笛』のタミーノ役であったが、彼はもはや若い王子を演じきれないと感じ、それが引退の理由であったと述べている。
歌手としてのキャリアは2005年12月22日に終止符を打った。チェコのプラハにあるルドルフィヌム(芸術家の家)のドヴォルザーク・ホールで行われたチェコ・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会で、J.S.バッハの『クリスマス・オラトリオ』第1部から第3部を指揮し、自らも福音史家を歌った。これは、シュライアーの歌手としての完全引退公演であり、前日の公演と同様に約1100人収容のホールは満員であった。
引退前には世界各地でお別れ公演を行い、日本では2005年11月に4回の公演を行った。11月10日には大阪のザ・シンフォニーホール、11月12日と14日には東京の東京オペラシティ・コンサートホール、そして11月16日にはカノラホール(岡谷市)で演奏を行った。特に岡谷で行われたシューベルトの歌曲集『冬の旅』の演奏会は、彼が日本で歌手として舞台に立った最後の機会となった。
歌手活動から引退した後、彼は指揮活動と後進の指導に重点を置いた。自身の出身であるドレスデン聖十字架合唱団の指揮なども積極的に行い、若手音楽家の育成に尽力した。
5. 私生活
ペーター・シュライアーはレナーテ夫人と結婚しており、トーシュテンとラルフの二人の息子がいた。彼は1945年から亡くなるまでドレスデンのロシュヴィッツ地区に居住していた。
長期間の闘病生活の末、シュライアーは2019年12月25日のクリスマスの日に、ドレスデンで84歳で亡くなった。葬儀は2020年1月8日にドレスデン聖十字架教会で行われた。
6. 評価と遺産
シュライアーは極めて知的な歌手であり、歌唱するテキストに対する深い共感を抱いていた。その芸術性は批評家たちから高く評価された。「ペンギン・CDガイド」の評価では、シューベルトの『白鳥の歌』の後期の録音について、「圧力をかけた時のシュライアーの声はもはや美しくないかもしれないが...音色の幅と歌詞の意味合いに対する抑揚の強さは、これまでで最も魅力的な録音の一つとなっている」と評された。また、同ガイドはシューベルトの『冬の旅』についても、「これは強烈に心を揺さぶる解釈であり、感情の移り変わりが鮮やかに、そして前向きに、電撃的に伝えられている」と記している。
ドイツ連邦政府文化・メディア担当大臣のモニカ・グリュッタースは、彼の死に際して、シュライアーは「我が国で最も印象的な声の一つ」であったと述べ、世界中のオペラハウスで「文化国家ドイツ」を代表し、バッハの受難曲における福音史家として記憶され、40年間のキャリアを通じて音楽史を築き上げた人物であると総括した。
バッハの音楽においては、シュライアーは歌手としても指揮者としても一流であり、現代における最高のバッハ演奏家の一人であると広く認識されている。彼の演奏は、テキストの深い洞察と音楽的な表現力が融合したものであり、多くの後進の音楽家たちに影響を与え、クラシック音楽界に大きな遺産を残した。
7. 受賞歴
ペーター・シュライアーは、歌手および指揮者としての長年の功績に対し、国内外から数多くの賞や栄誉、名誉会員資格を授与された。
- 宮廷歌手の称号(傑出した歌手に与えられる): 1963年(東ドイツ)、1980年(オーストリア)、1982年(バイエルン州)
- 国家一等賞(東ドイツ): 1967年
- ロベルト・シューマン賞(ツヴィッカウ市): 1969年
- ヘンデル賞(ハレ市): 1972年
- 国家賞(東ドイツ): 1972年
- 祖国功労勲章金章(東ドイツ): 1984年
- エルンスト・フォン・ジーメンス音楽賞: 1988年
- レオンシー・ソニング音楽賞(デンマーク): 1988年
- ウィーン楽友協会名誉会員: 1986年
- 人民友好星章(東ドイツ): 1989年
- スウェーデン王立音楽アカデミー会員: 1989年
- ドイツ連邦共和国功労勲章1等功労十字章: 1993年
- ベルリン芸術アカデミー会員: 1993年
- ウィーンの笛時計賞: 1994年
- ゲオルク・フィリップ・テレマン賞(マクデブルク市): 1994年
- ドイツ聖書賞(バッハの偉大な受難曲演奏とJ.S.バッハ作品の解釈における功績に対して): 1998年
- ヨーロッパ教会音楽賞: 2000年
- マイセン市名誉市民(市街復興のための資金調達における尽力に対して)
- 王立音楽アカデミー/コーン財団バッハ賞: 2009年
- フーゴ・ヴォルフ・メダル(フーゴ・ヴォルフ・アカデミー、シュトゥットガルト): 2011年
- 国際メンデルスゾーン賞(フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ財団、ライプツィヒ): 2011年
- バッハ・メダル(ライプツィヒ・バッハ音楽祭、バッハの解釈に対して): 2013年
- ザクセン功労勲章: 2016年
- ドレスデン州都芸術賞: 2016年
8. ディスコグラフィー
ペーター・シュライアーは、歌手および指揮者として膨大な数の録音を残し、その多くが現在も入手可能である。以下に主なアルバムや演奏記録を概説する。
8.1. 歌手として
- 『80周年記念エディション』、ベルリン・クラシックス (Edel)、2015年
- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ:
- 『マタイ受難曲』(福音史家およびアリア)、指揮: カール・リヒター、アルヒーフ・プロダクション (Universal Music)、1989年
- 『ヨハネ受難曲』、指揮: ハンス=ヨアヒム・ロッチュ、RCAクラシック (Sony Music)、1998年
- 『クリスマス・オラトリオ』、指揮: マルティン・フレーミヒ、ドレスデン・フィルハーモニー、ドレスデン聖十字架合唱団、ルカ教会、1974年
- ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン: 『遥かなる恋人に寄す』、ピアノ: アンドラーシュ・シフ、デッカ (Universal Music)、1996年
- エクトル・ベルリオーズ: 『レクイエム』、指揮: シャルル・ミュンシュ、ドイツ・グラモフォン (Universal Music)、2009年
- ヨハネス・ブラームス: 『美しきマゲローネ』、ピアノ: アンドラーシュ・シフ、ベルヴェデーレ (Harmonia Mundi)、2015年
- ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト:
- 『オペラ・アリア集』、ポリグラム・レコーズ、1990年
- 『魔笛』(タミーノ)、指揮: ヴォルフガング・サヴァリッシュ、EMI (Warner Classics)、1987年
- 『愛の息吹。モーツァルト・テノールとしてのペーター・シュライアー』、指揮: オトマール・スウィトナー、エテルナ、1973年
- 『プロコフィエフ - ヒンデミット: リート集』、ベルリン・クラシックス (Edel)、2004年
- フランツ・シューベルト:
- 『美しき水車小屋の娘』(ギター: コンラート・ラゴスニヒ)、ベルリン・クラシックス (Edel)、2004年
- 『冬の旅』(声楽と弦楽四重奏版)、プロフィール (Naxos)、2015年
- 『シューベルト歌曲集』、ピアノ: アンドラーシュ・シフ、ウィグモア・ホール・ライヴ (CODAEX Deutschland)、2006年
- ハインリヒ・シュッツ: 『ヨハネ受難曲』SWV 481 / 『ダビデ詩篇集』、指揮: マルティン・フレーミヒ、ベルリン・クラシックス (Edel)、1997年
- ロベルト・シューマン:
- 『詩人の恋』、ピアノ: クリストフ・エッシェンバッハ、テルデック・クラシックス・インターナショナル、1991年
- 『詩人の恋 / リーダークライス』、ピアノ: ノーマン・シェトラー、ベルリン・クラシックス (Edel)、2007年
- 『少年アルトから叙情テノールへ』、ベルリン・クラシックス (Edel)、1995年
- リヒャルト・ワーグナー: 『トリスタンとイゾルデ』(メロート)、指揮: ヘルベルト・フォン・カラヤン、EMI - His Masters Voice、1988年
- フーゴ・ヴォルフ:
- 『ゲーテ歌曲集』、ピアノ: ヴォルフガング・サヴァリッシュ、アリオラ・ユーロディスク、1986年
- 『メーリケ歌曲集』、ピアノ: カール・エンゲル、オルフェオ (Naxos Deutschland)、1998年
8.2. 指揮者として
- ヨハン・ゼバスティアン・バッハ:
- 『クリスマス・オラトリオ』(抜粋)、シュターツカペレ・ドレスデン。MC、エテルナ・デジタル、1985年
- 『ヨハネ受難曲』、シュターツカペレ・ドレスデン、ニュートン・クラシックス (Membran)、2011年
- 『2つの結婚カンタータ』、『わが喜びは陽気な狩りのみ』BWV 208 / 『おお、幸いなる時、待望の時』BWV 210、ベルリン室内管弦楽団、ブリリアント・クラシックス (c. 2000年)
- 『世俗カンタータ集』、わが魂は満たされり』BWV 204、ブリリアント・クラシックス (c. 2000年)
- 『マタイ受難曲』、ライプツィヒ放送合唱団、シュターツカペレ・ドレスデン、VEBシャルプラッテン、東ベルリン、1984年
- 『ミサ曲 ロ短調』、ライプツィヒ放送合唱団、シュターツカペレ・ドレスデン、フィリップス・クラシックス・プロダクション、1992年
- ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト:
- 『レクイエム』、マーガレット・プライス、トゥルーデリーゼ・シュミット、フランシスコ・アライサ、テオ・アダム; ライプツィヒ放送合唱団 & シュターツカペレ・ドレスデン、フィリップス、1983年
9. 文献
ペーター・シュライアーの生涯や業績に関する伝記、評論、ドキュメンタリー映画などの関連資料を以下に紹介する。
- ゴットフリート・シュミーデル: 『ペーター・シュライアー あなたのための肖像』、VEBドイツ音楽出版社ライプツィヒ、1976年
- ペーター・シュライアー: 『私の視点から。思考と記憶』、東ベルリン、1983年、207ページ
- ヴォルフ=エーバーハルト・フォン・レヴィンスキー: 『ペーター・シュライアー: インタビュー、事実、意見』、ミュンヘン、マインツ、パイパー、ショット、1992年
- ユルゲン・ヘルフレヒト: 『ペーター・シュライアー - ある人生の旋律』、クンスト・ドレスデン出版社、フズム、2008年
- レナーテ・レッツ: 「シュライアー、ペーター」、『誰が東ドイツにいたか?』第5版、第2巻、Ch.リンクス、ベルリン、2010年
- マンフレート・マイヤー、ペーター・シュライアー: 『バックミラーにて: 思い出と見解』、マンフレート・マイヤーによる記録、ウィーン: シュタインバウアー、2005年
9.1. ドキュメンタリー映画
- 『ペーター・シュライアー - 全てにはその時がある』。83分、監督・製作: ハイデ・ブルーム。ドイツ、2006年