1. 概要
ロベール=フランソワ・ダミアン(Robert-François Damiensʁɔbɛʁ fʁɑswa damjɛフランス語、1715年1月9日 - 1757年3月28日)は、フランス国王ルイ15世に対する暗殺未遂事件を起こしたフランスの召使いである。彼は1757年1月5日に国王をナイフで刺したが、国王の厚着によって傷は軽微に留まり、暗殺は未遂に終わった。ダミアンは現場で逮捕され、その後の尋問と裁判を経て、王殺しの罪で有罪判決を受けた。
彼の処刑は、18世紀フランスのアンシャン・レジームにおける死刑の残虐性を示す象徴的な出来事として歴史に刻まれている。特に、八つ裂きの刑という極めて残酷な方法で処刑された最後の人物として知られる。この事件と処刑は、当時の社会に大きな衝撃を与え、後世の思想家や作家たちに拷問、刑罰、国家権力、そして人権に関する重要な議論を提起するきっかけとなった。本記事では、ダミアンの生涯、暗殺未遂事件の詳細、裁判と処刑、そして事件が後世に与えた多大な影響について、社会的な観点を踏まえて深く掘り下げる。
2. 生涯と背景

ロベール=フランソワ・ダミアンの初期の人生は、フランス北部の貧しい家庭に生まれ、軍務と召使いとしての職を転々とした。彼の国王暗殺未遂という極端な行動の背後には、当時の宗教的・政治的対立と個人的な不満が複雑に絡み合っていた。
2.1. 出生と幼少期
ダミアンは1715年1月9日、フランス北部のアラス近郊にあるラ・ティユロワ村で、10人兄弟姉妹の8番目の子として生まれた。彼の父親は日雇い農夫や刑吏として生計を立てていた。幼少期はベチューヌの叔父のもとで育った。
2.2. 軍務と召使い時代
若い頃に軍隊に入隊し、1734年のフィリップスブルク包囲戦に一兵卒として参加した。軍を退役した後、彼はパリのイエズス会のリセ・ルイ=ル=グランで召使いとして働いた。しかし、不正行為、特に金銭の持ち逃げにより解雇され、他の職も失った。このため、彼は「Robert le Diableフランス語(悪魔ロベール)」というあだ名で呼ばれるようになった。
2.3. 犯行の動機
ダミアンの犯行の動機については、歴史家の間で議論が続いている。一部の歴史家は彼が精神疾患を患っていた可能性を指摘している。尋問での彼の供述によると、フランスのカトリック聖職者がジャンセニスム派の信徒に秘跡を与えることを拒否したことに対する世間の騒動が、彼を激しい興奮状態に陥らせたようである。彼はこの問題の最終的な責任を国王に負わせ、国王を罰する計画を立てた。当時の宗教観から、国王を切りつけてその血の色を確認しようとしたとも言われている。また、ローマ教皇クレメンス11世によるジャンセニスムとその一派である痙攣派への弾圧に対する反感も、彼の動機の一つであったとされる。
3. 暗殺未遂事件
1757年1月5日、ロベール=フランソワ・ダミアンによるフランス国王ルイ15世への暗殺未遂事件が発生した。この事件は、国王の身の安全に対する脅威だけでなく、当時の政治的・社会的な緊張を浮き彫りにした。
3.1. 事件の概要と経過

1757年1月5日の午後4時、ルイ15世がヴェルサイユ宮殿で馬車に乗ろうとした際、ダミアンは警護兵を駆け抜け、ペンナイフで国王を刺した。ダミアンは逃亡を試みることなく、その場で即座に逮捕された。国王が厚手の冬服を着ていたため、ナイフは胸にわずか1 cmほど食い込む程度の軽傷で済んだ。しかし、国王は出血し、死を恐れて告解師を呼び寄せた。マリー・レクザンスカ王妃がルイ15世のもとに駆けつけた際、国王は自身の数々の不倫について許しを求めたという。
3.2. 逮捕と尋問
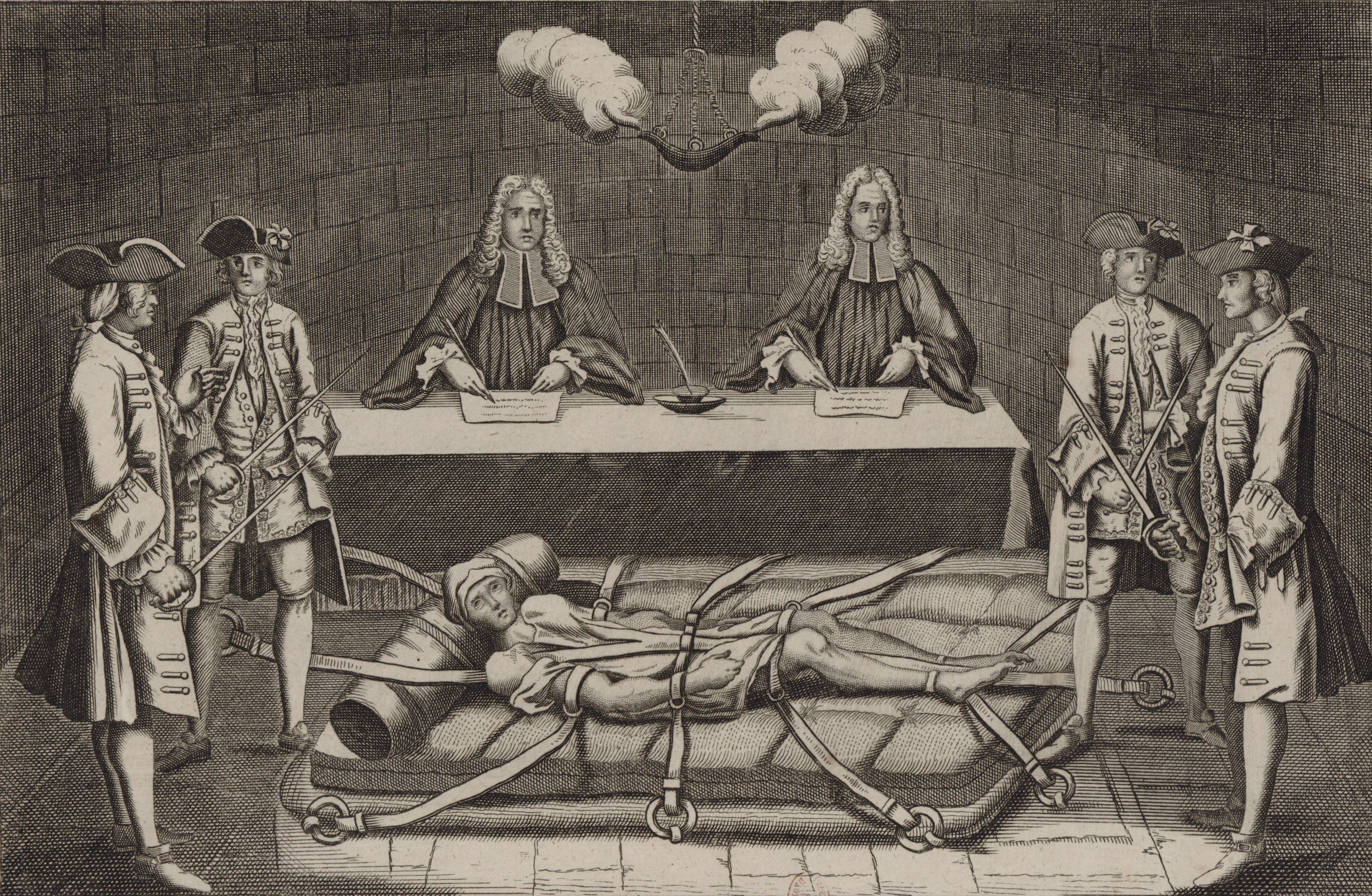
事件直後、ダミアンは現場で逮捕された。彼は共犯者や背後にいる人物の身元を明かすよう強要するため、拷問にかけられた。しかし、この尋問は成功せず、彼は共犯者や後ろ盾を持たない単独犯であったため、苦し紛れにでたらめな名前を答えるに留まった。その後、ダミアンはコンシェルジュリーに移送され、約150年前にアンリ4世を刺殺したフランソワ・ラヴァイヤックと同じ独房に幽閉された。
4. 裁判と処刑
ロベール=フランソワ・ダミアンは、国王暗殺未遂という重大な罪により、当時のフランスで最も残虐な刑罰である八つ裂きの刑を宣告された。彼の処刑は、その残酷さゆえに多くの人々に衝撃を与え、後世にまで語り継がれることとなった。
4.1. 裁判と死刑判決
ダミアンはパリ高等法院によって王殺しの罪で裁判にかけられ、有罪判決を受けた。彼にはフランスで最も重い刑罰である八つ裂きの刑が宣告された。処刑場所は、パリのグレーヴ広場(現在のパリ市庁舎前広場)と定められた。
4.2. 拷問
処刑執行日の1757年3月28日の朝、監獄の独房から連れ出されたダミアンは、「La journée sera rudeフランス語(今日は厳しい一日になるだろう)」と語ったと伝えられている。彼はまず「ブーツ」と呼ばれる装置で脚を圧迫され、激しい痛みを伴う拷問を受けた。次に、赤熱したペンチで肉を引きちぎられ、国王を刺した右腕は硫黄で焼かれた。さらに、溶けた蝋、溶けた鉛、煮えたぎる油が彼の傷口に注ぎ込まれた。
4.3. 処刑執行

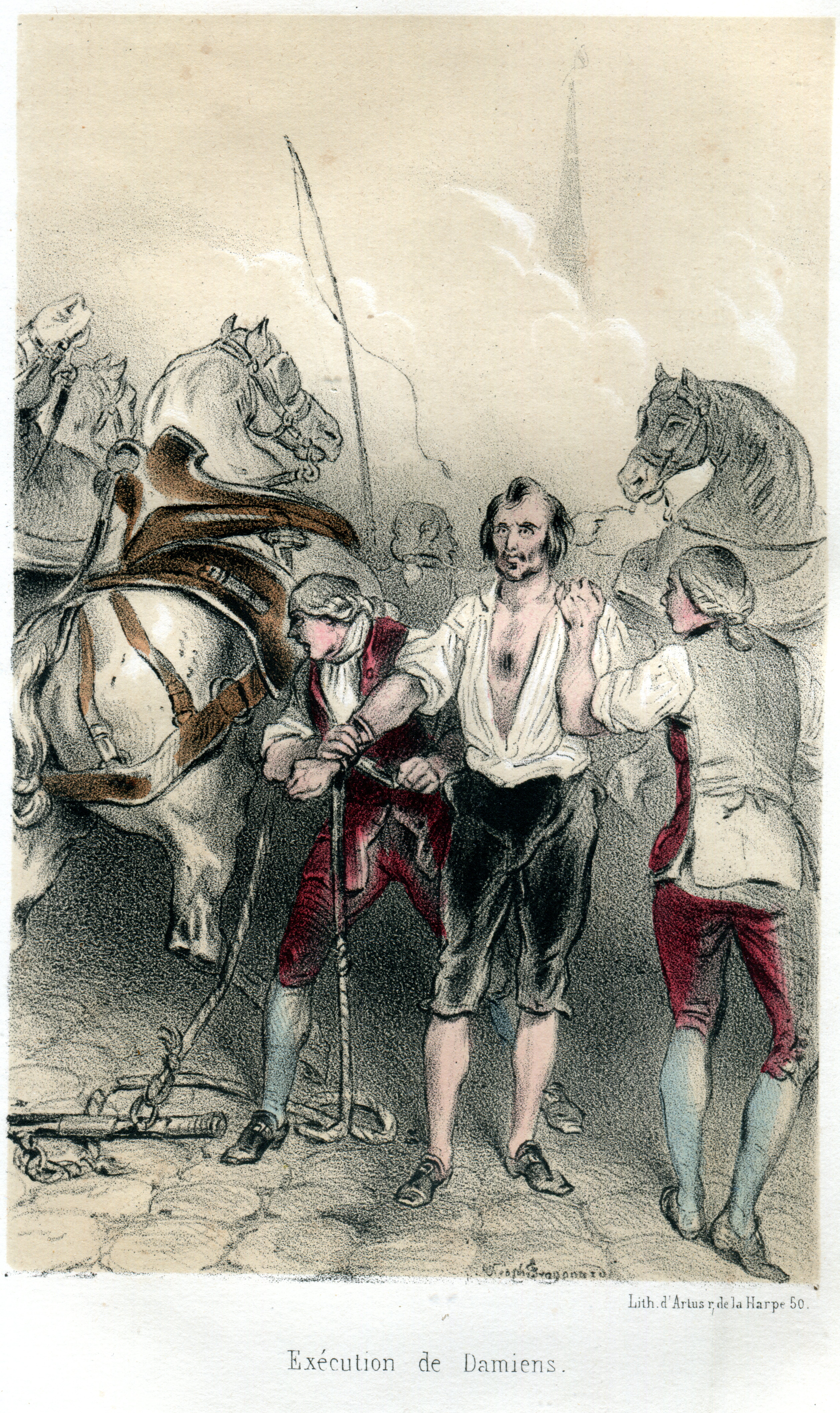
ダミアンは、後にルイ16世の処刑も執行することになる王室の死刑執行人シャルル=アンリ・サンソンに引き渡された。サンソンはダミアンを去勢した後、彼の四肢に馬を繋いで八つ裂きにしようとした。しかし、ダミアンの四肢は容易には分離しなかったため、執行官はサンソンにダミアンの腱を切断するよう命じた。腱が切断されると、ようやく馬たちは彼の体を八つ裂きにすることができた。群衆の拍手喝采の中、報道によればまだ生きていた彼の胴体は火あぶりにされた。一部の証言では、ダミアンは最後に残った腕が引きちぎられた時点で絶命したとされている。
ダミアンの最期の言葉は定かではない。ある情報源では「おお、死よ、なぜかくも長く来ないのか?」と述べたとされているが、別の情報源では、主に神への慈悲を求める様々な言葉であったと主張されている。彼の処刑を目撃した人々は、彼をイングランドで同様の罪で処刑されたガイ・フォークスになぞらえた。
5. 事件後の影響
ロベール=フランソワ・ダミアンの処刑は、彼の家族に過酷な運命をもたらしただけでなく、フランス社会と後世の歴史に深い影響を残した。この事件は、アンシャン・レジームの司法制度の残酷さを象徴するものとして、長く記憶されることとなる。
5.1. 家族と財産への処罰
ダミアンの死後、彼の遺体は灰になるまで焼かれ、その灰は風に撒かれた。彼の家屋は完全に破壊され更地となり、彼の兄弟姉妹は改名を強制された。さらに、彼の父親、妻、そして娘はフランスから追放された。
5.2. 歴史的文脈と評価
フランスでは、1610年のアンリ4世殺害以来、国王暗殺未遂事件は発生していなかった。ダミアンの悪名は長く語り継がれた。彼の死から40年後、故郷アラスの最も悪名高い市民であるダミアンの記憶は、同じアラス出身のマクシミリアン・ロベスピエールを攻撃するために利用された。フランス革命の指導者であったロベスピエールは、敵によって頻繁にダミアンの甥であると誹謗中傷された。これは事実ではなかったものの、王党派や外国の同調者の間ではかなりの信憑性を持って受け止められた。一方で、ダミアンの処刑は、アンシャン・レジームの野蛮さを象徴する「cause célèbre」(世間を騒がせた事件)となった。
6. 遺産と後世への影響

ダミアン事件は、その残虐な処刑方法と国王暗殺未遂という特異性から、後世の思想家、作家、そして文化に多大な影響を与えた。この事件は、拷問、刑罰、国家権力、そして人権といった普遍的なテーマについて考察する契機となった。
6.1. 目撃者の証言
18世紀の冒険家ジャコモ・カサノヴァは、偶然にも事件発生と同じ日にパリに到着しており、ダミアンの処刑を目撃した一人である。彼は自身の回顧録にその詳細な様子を記録している。
「我々は4時間もの間、恐ろしい光景を勇敢にも見続けた...ダミアンは狂信者であり、善行を行い天国の報いを得るという考えのもと、ルイ15世を暗殺しようとした。その試みは失敗し、国王に軽傷を負わせたに過ぎなかったが、彼はあたかもその罪が完遂されたかのように八つ裂きにされたのだ...。彼の耳をつんざくような叫び声を聞くたびに、私は何度も顔を背け、耳を塞がざるを得なかった。彼の体の半分が引き裂かれていたにもかかわらず、ランベルティーニと太った叔母は微動だにしなかった。彼らの心が硬化したためだろうか?彼らは私に、悪人の邪悪さに対する彼らの恐怖が、彼の前代未聞の苦痛が引き起こすべき同情の念を妨げたのだと語った。私はそれを信じたふりをした。」
- カサノヴァ『回顧録』第2巻第5部第3章
6.2. 哲学的・政治的考察
批評家のイアン・ヘイウッドは、エドマンド・バークが1775年の著書『崇高と美の観念の起源に関する哲学的探求』の中で、「危険や苦痛が『あまりにも近くに迫る』とき、それらは何の喜びも与えず、ただ恐ろしいだけである。しかし、ある程度の距離を置き、ある程度の修正が加えられれば、それらは喜ばしいものとなりうるし、実際にそうである」と記した際に、ダミアンの苦難を指す「圧迫(press)」という言葉をかけて、彼の拷問を暗示していると論じている。
哲学者チェーザレ・ベッカリーアは、1764年の論文『犯罪と刑罰』の中で、拷問と死刑を非難する際にダミアンの運命を明確に引用している。トマス・ペインは1791年の『人間の権利』の中で、ダミアンの処刑を専制的な政府の残酷さの例として挙げ、これらの残虐な方法がフランス革命時に民衆が囚人を同様に残酷な方法で扱った理由であると主張した。
ミシェル・フーコーは、彼の著書『監獄の誕生』の中でダミアンの処刑について詳細に記述し、論じている。彼はこの事件を、その後の世紀に西洋文化における刑罰観の変化を考察する上で重要な事例として取り上げ、アレクサンドル・ゼヴァエスの著作『王殺しダミアン』を引用している。フーコーは、この処刑が身体への刑罰から魂への規律へと刑罰の焦点が移り変わる過渡期を象徴していると分析し、近代社会における権力と規律のメカニズムを批判的に考察する出発点とした。
6.3. 文学的・文化的影響
ヴォルテールは、1759年の小説『カンディード』の中で、ダミアンの処刑を巧妙に隠喩的に記述している。チャールズ・ディケンズは1859年の『二都物語』第2巻第15章でこの処刑に言及している。
「ある老人は噴水で、ナイフを握った彼の右腕が目の前で焼かれ、腕、胸、脚に作られた傷口には煮えたぎる油、溶けた鉛、熱い樹脂、蝋、そして硫黄が注がれ、最後に彼は四頭の屈強な馬によって八つ裂きにされるだろうと語る。その老人は、これら全てがかつて故国王ルイ15世の命を狙った囚人に対して実際に行われたのだと言う。しかし、彼が嘘をついているかどうか、どうして私にわかるだろう?私は学者ではない。」
「ではもう一度聞け、ジャック!」落ち着きのない手と飢えたような表情の男が言った。「その囚人の名はダミアン。そしてそれは全て白昼堂々、このパリの開かれた街路で行われたのだ。そしてそれを見た膨大な群衆の中で、最も注目されたのは、上流階級の貴婦人たちが、最後まで-そう、最後まで、ジャック、夜になるまで、彼が両足と片腕を失い、それでもなお息をしていた時に至るまで、熱心に注目していたことであった!」
マーク・トウェインは1889年の『アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー』の中で、ダミアンの襲撃と処刑、そしてカサノヴァのその記述を引用し、貴族の権力の残酷さと不正義を示唆している。バロネス・オルツィは1940年の『マムゼル・ギロチン』(紅はこべシリーズの一部)でこの事件に触れており、そこにはダミアンの架空の娘ガブリエル・ダミアンが登場する。また、ペーター・ヴァイスの1963年の戯曲『マラー/サド』にも、ダミアンの死の描写が含まれている。