1. 生涯
大野治長は、その生涯を通じて豊臣氏に忠実に仕え、特に大坂の陣では豊臣家の存続のために尽力した。彼の出生から最期までの道のりは、豊臣政権の栄枯盛衰と深く結びついている。
1.1. 出生と家系
大野治長は、永禄12年(1569年)頃に誕生したと考えられている。出生地については諸説あるが、『尾張群書系図部集』は『尾張志』や『張州雑志』などを根拠に、尾張国葉栗郡大野村(現在の愛知県一宮市浅井町大野)で生まれた城主一族であるとする説が有力である。これは、所領であった丹後国大野城との混同による誤伝を指摘している。
治長の父は大野定長(佐渡守)とされ、母は大蔵卿局である。大蔵卿局は浅井長政とお市の方の娘である淀殿の乳母を務めたため、治長は淀殿の乳兄弟にあたる。この関係性から、治長と淀殿は同い年か、それに極めて近い年齢であったと推測される。兄弟には、大野治房(主馬首)、大野治胤(道犬/道見)、大野治純(壱岐守)がいたが、治純については系図に名前がない場合もあり、治長と治房、あるいは治長・治房・道犬の三兄弟として語られることが多い。
大野氏はもともと石清水八幡宮の神職の家系であったが、神職を失い美濃国に流れてきた大野治定(伊賀守)が、織田信長の命令で尾張国葉栗郡に大野城を築いて居城とした。この治定は治長の祖父にあたり、定長はその子である。大野城を継いだ大野治久は定長の弟(治長から見れば叔父)にあたる。『南路志』によれば、尾張葉栗郡の同郷の毛利勝永とは従兄弟の関係にあったという。
大蔵卿局と治長らは、小谷城以来、淀殿に付き従っていたと考えられているが、天正11年(1583年)の越前国北ノ庄城の落城後は淀殿の所在すら不明であり、大野一族がどのような経緯をたどったかは明らかではない。この間、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは、本家の大野治久が豊臣秀吉に逆らって所領を失い、大野城も失っている。
治長が秀吉の馬廻衆となった時期も不明であるが、淀殿が秀吉の庇護下に入り、側室となった天正16年(1588年)頃か、その少し前と推測される。確かな史料に治長が登場するのは、天正19年(1591年)11月、秀吉の三河国吉良狩猟に随兵した頃からである。
天正17年(1589年)には、父と母の功績により、太閤蔵入地から和泉国佐野(現在の泉佐野市)と丹後国大野に合計1万石を与えられ、丹後大野城を拠点として領国を運営した。これは、同年淀殿が豊臣鶴松を出産したことに関連する褒美または祝賀の加増であったと考えられている。
1.2. 豊臣秀吉時代
治長は豊臣秀吉に馬廻衆として仕え、当初は3,000石の俸禄を受けていた。文禄元年(1592年)の文禄・慶長の役では、肥前国名護屋城に在陣していたことが『松浦古事記』に記されている。この時期、秀吉は淀殿や松の丸殿などの側室を連れており、淀殿は名護屋城で再び懐妊し、翌年に豊臣秀頼(幼名:拾)を出産している。
文禄3年(1594年)には伏見城の普請を分担し、この頃には1万石の知行を有していた。慶長3年(1598年)、秀吉の死に際しては遺物として金子十五枚を賜った。慶長4年(1599年)には豊臣秀頼に伺候し、詰衆二番之組の筆頭として側近の地位にあった。
しかし同年9月7日、重陽の賀のために大坂城へ登城した徳川家康に対し、五奉行の一人である増田長盛が家康暗殺計画を密告した。この計画は、前田利長が首謀者で、浅野長政・土方雄久・治長が共謀し、城内で家康を暗殺する企てであるとされた。家康は厳重な警備のもと祝賀を乗り切ると、大坂城西の丸に入り天守閣を造営して、自らが秀頼に並ぶ存在であることを誇示した。さらに謀議者の摘発に乗り出し、10月2日、治長は罪を問われて流罪となり、下総国の結城秀康のもとに預けられた。雄久も同様に常陸国水戸の佐竹義宣のもとに預けられ、母の大蔵卿局も大坂を追放された。
1.3. 関ヶ原の戦いとその後
慶長5年(1600年)7月24日、徳川家康は土方雄久と治長に引見し、その罪を許した。治長は関ヶ原の役では東軍に与して参戦し、本戦では先鋒である福島正則隊に属して武功を挙げた。『関原軍記大成』によれば、宇喜多秀家隊の鉄砲頭・香地七郎右衛門を討ち取ったという。
戦後、治長は家康の命を受け、「豊臣家への敵意なし」という家康の書簡を携えて大坂城の豊臣家へ使者を務めた。その後、江戸には戻らず、そのまま大坂に留まることとなった。これは、家康が豊臣家への配慮を示しつつも、治長を豊臣家の監視役として利用しようとした意図があったとも解釈できる。
1.4. 豊臣秀頼家臣としての活動
慶長19年(1614年)6月22日、治長は片桐且元の弟である片桐貞隆とともに、家康の口添えで秀頼より5,000石を加増された。その返礼のために貞隆と、家康のいる駿府、次いで江戸の将軍・徳川秀忠を訪ねた。
同年、豊臣氏の家老であった片桐且元が追放されると、大野治長は豊臣家を主導する立場となった。その後、豊臣家内部では主戦派が主流となり、各地から浪人を召し抱えて大坂冬の陣に至る。治長は渡辺糺とともに鬮取奉行となって豊臣方の中心の一人として籠城戦を指揮した。
徳川方から和睦が持ちかけられると、治長は織田有楽斎とともに徳川方の本多正純および後藤光次との交渉を行った。交渉は12月8日から12日にかけて行われ、淀殿が江戸に人質に行くこと、豊臣家の浪人衆への俸禄のため加増すること、大坂城本丸のみを残して二丸三丸を壊すことなどの双方の提案をまとめて和議を成立させた。和睦の保証として人質を出すことになり、治長は次男の大野治安(弥七郎)を家康に差し出した。治安は戦後に処刑された。
しかし、城内では和睦に反対する意見も多かった。和睦後の4月9日夜、治長は大坂城の楼門で闇討ちに遭い、護衛2名が死傷し、治長自身も一刀を浴びて負傷した。これは主戦派の弟・治房による襲撃ともいわれるが、襲撃犯は治房の家臣・成田勘兵衛の手下とされ、成田は襲撃に失敗すると自宅を放火して自殺し、逃げた手下は片桐邸や長宗我部邸に逃げ込み、一部は長宗我部盛親が捕らえたという。
1.5. 大坂の陣(夏の陣)
慶長20年(1615年)の大坂夏の陣では、出撃する諸将に対して、治長は大坂城本丸の守備を預かった。4月28日、紀伊国和歌山城の浅野長晟への攻撃を前にして、治長は家臣の北村善大夫、大野弥五左衛門を紀伊へ潜入させて一揆を扇動したが、この計画は失敗に終わった。
5月6日の誉田合戦では、治長は後詰めを指揮し、膠着状態になった後、豊臣諸隊と撤収した。翌7日の天王寺口の戦いでは、全軍の後詰として四天王寺北東の後方、毘沙門池の南に布陣し、通説では秀頼の出馬を待っていたとされる。しかし、最終的に治長は戦闘に参加することなく、城内へ退却した。
総崩れとなって敗戦した後、茶臼山から撤退してきた治長は重傷を負っていた。出馬して討死しようとする秀頼を速水守久が諫めたため、本丸へ引き上げて立て籠もることになった。治長は最後の策として、独断で将軍・徳川秀忠の娘で秀頼の正室であった千姫を脱出させ、彼女を使者として家康と秀忠に秀頼母子の助命を嘆願させようとした。この際、治長は自らの切腹を条件として提示した。
翌8日、徳川方では審議が行われた。家康は孫である千姫の願いにためらいを見せたが、秀忠は千姫が秀頼とともに自害しなかったことに激怒し、秀頼母子の助命嘆願を拒否した。一縷の望みが絶たれると、治長らは秀頼とともに大坂城の山里曲輪で自害した。享年47。母親の大蔵卿局、長男の大野治徳も共に自害している。『春日社司祐範記』には「大野修理沙汰して最後に切腹なり。手前の覚悟比類なし」と記されており、彼の最期の覚悟が並々ならぬものであったことがうかがえる。
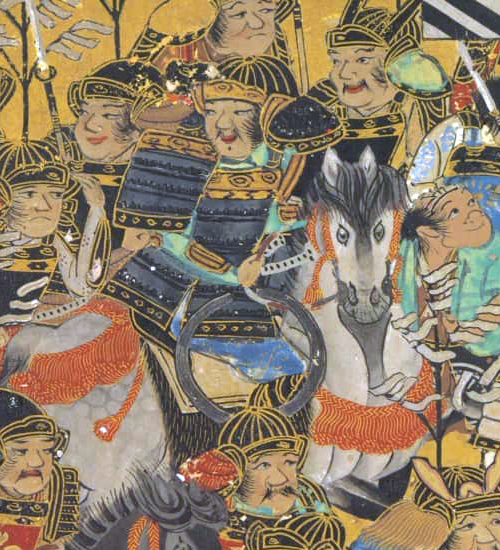
2. 人物・逸話
大野治長は、武将としての顔だけでなく、文化的な才能も持ち合わせていた。また、彼の人物像は、後世の歴史的解釈によって大きく左右されてきた。
治長は能書家であり、古田重然(織部)に茶の湯を学んだ茶人でもあった。
真田信繁(幸村)とは、秀吉の馬廻りを務めていた頃からの旧知の間柄であった。大坂の陣で信繁を豊臣方に招いたのも治長であったとされる。信繁に兵力を預け、その指揮を任せたことを考えると、治長が決して愚かな人物であったとは思えないと評価されている。
治長が後世に「憎まれ役」として描かれることが多かったのは、徳川家康に逆らった豊臣家の首脳であったため、江戸時代に徳川幕府の正当性を強調する目的で「悪役」に仕立て上げられたという見方が強い。これは、勝者による歴史の再解釈の一例であり、治長の忠誠心や平和への努力といった側面が意図的に軽視された可能性を示唆している。
3. 評価と噂
大野治長に関する最も有名な噂の一つに、淀殿との密通説がある。この噂は江戸時代初期から流布し、いくつかの書物に記されている。
例えば、慶長4年(1599年)10月1日付の内藤元家宛内藤隆春書状には、治長が淀殿と密通していたという噂が記されている。同様の記述は『多聞院日記』にも見られ、これらの噂が当時存在したことは確かである。さらに、姜沆による『看羊録』では、秀吉の遺命によって家康が淀殿を娶ろうとしたが、治長の子を宿していた淀殿が拒否したとまで書かれている。ただし、『看羊録』には家康による朝鮮出兵の再開を明言するなど、奇妙な噂話が多く収録されており、その信憑性には疑問符が付く。
江戸時代の『明良洪範』では、豊臣秀頼は秀吉の実子ではなく、治長と淀殿の子であると記されている。しかし、同書は淀殿が歌舞伎役者の名古屋山三郎という美男を寵愛して不義を働いていたとも書いており、これらの風説は、桑田忠親が指摘するように、「悪口を書けば書くほど歓迎された江戸時代」の劇作者によるものに過ぎず、「人口に膾炙した」に過ぎないと考えられる。
治長と淀殿は乳兄弟という極めて近しい関係であったため、その関係性が噂の温床となった可能性は否定できない。しかし、豊臣家の没落とそれに伴う「滅びの美学」という観念の中で、治長を「悪人」として描くことで、徳川幕府の正当性を強調しようとする意図があったと考えることもできる。儒教的な観点から「姦通の罪」という形で彼を悪者に仕立て上げることで、豊臣家の滅亡を必然的なものとして正当化しようとした、という歴史的再解釈の過程が存在した。これらの噂は、治長個人の評価だけでなく、豊臣家全体の歴史的イメージに大きな影響を与えたと言える。