1. Biography
アンドレイ・ニコラエヴィッチ・コルモゴロフの生涯は、幼少期の恵まれない環境から始まり、数学的才能を開花させていく過程、学術的な飛躍、そしてソビエト連邦の社会政治的変動の中での彼の役割と個人的な側面が交錯しています。
1.1. Early Life and Education
アンドレイ・コルモゴロフは1903年4月25日、ロシア帝国のタンボフ(モスクワの南東約500 km)で生まれました。彼の未婚の母、マリア・ヤコブレヴナ・コルモゴロワは出産時に亡くなりました。アンドレイはヤロスラヴリ近郊のトゥノシュナにある、裕福な貴族であった祖父の邸宅で、二人の叔母によって育てられました。彼の父親についてはあまり知られていませんが、ニコライ・マトヴェーエヴィチ・カタエフという名の農学者であったとされています。カタエフは、ツァーリに対する革命運動に参加したため、サンクトペテルブルクからヤロスラヴリ州に追放されていました。彼は1919年に姿を消し、ロシア内戦中に殺害されたと推定されています。
アンドレイは叔母ヴェラの村の学校で教育を受けました。彼の初期の文学的努力や数学論文は、学校のジャーナル「春のツバメ」に掲載されました。5歳にしてこのジャーナルの数学セクションの「編集者」を務め、このジャーナルで彼の最初の数学的発見が発表されました。5歳の時、彼は奇数の数列の合計における規則性、すなわち1 = 12、1 + 3 = 22、1 + 3 + 5 = 32など、を発見しました。
1910年、彼の才能を見出した叔母が彼を養子にし、彼らはモスクワに移住しました。そこで彼は1920年に高校を卒業しました。
1.2. University and Early Research
1920年、コルモゴロフはモスクワ大学とメンデレーエフ・モスクワ化学技術研究所で学び始めました。彼はこの時期について「モスクワ大学には数学に関するかなりの知識を持って到着した。特に集合論の初歩を知っていた。『ブロックハウス・エフロン百科事典』の記事で多くの疑問を学び、これらの記事で簡潔に提示されていた内容を自分自身で補完した」と記しています。
コルモゴロフは、その広範な学識で名声を博しました。大学の学部生時代には、ロシアの歴史家S. V. バフルーシンのセミナーに出席し、15世紀から16世紀のノヴゴロド公国における土地所有慣行に関する最初の研究論文を発表しました。また、同じ時期(1921年-1922年)に、集合論とフーリエ級数の理論においていくつかの結果を導出し、証明しました。1922年には、ほとんどいたる所で発散するフーリエ級数を構成したことで国際的な評価を得ました。この頃、彼は生涯を数学に捧げることを決意しました。
1925年、コルモゴロフはモスクワ大学を卒業し、ニコライ・ルージンの指導の下で研究を始めました。この頃、彼はルージンの同門生であったパヴェル・アレクサンドロフと生涯にわたる親密な友情を結びました。1925年には、直観論理に関する「排中律の原則について」という論文を発表し、ある解釈の下で古典形式論理のすべての命題が直観主義論理の命題として定式化できることを証明しました。1929年、コルモゴロフはモスクワ大学で博士号を取得しました。
1.3. Overseas Activities and Professorship
1930年、コルモゴロフは初の長期海外旅行に出発し、ドイツのゲッティンゲンとミュンヘン、そしてフランスのパリを訪れました。ゲッティンゲンでは、リチャード・クーラントとその学生たち(拡散過程が離散確率過程の極限であることを示す極限定理に取り組んでいた)と、直観主義論理ではヘルマン・ワイルと、関数論ではエドムント・ランダウと科学的な交流を持ちました。彼の先駆的な著作『確率論における解析的手法について』は1931年にドイツ語で出版されました。同年、彼はモスクワ大学の教授に就任しました。
1.4. Establishing the Foundations of Probability Theory
1933年、コルモゴロフは彼の画期的な著書『確率論の基礎概念』を出版しました。この著作は、現代確率論の公理的基礎を築き、彼をこの分野における世界的な第一人者としての名声確立に貢献しました。彼は「数学の一分野としての確率論は、幾何学や代数学と全く同じように公理を起点として発達させることができるし、またそうであるべきだ」という信念を持っていました。この著作により、彼はそれまでばらばらに発展していた確率論と測度論を統合し、現代確率論の強固な基盤を確立しました。
1935年、コルモゴロフはモスクワ大学確率論講座の初代主任教授に就任しました。また、1936年には生態学の分野にも貢献し、ロトカ=ヴォルテラ・モデルを捕食者-被食者系の文脈で一般化しました。1939年、彼はソビエト連邦科学アカデミーの正会員に選出されました。
1.5. Major Research Areas
コルモゴロフは、多岐にわたる数学的および科学的分野に深く貢献しました。
1.5.1. Stochastic Processes and Applications
1938年の論文で、コルモゴロフは「定常確率過程の平滑化と予測のための基本的な定理」を確立しました。この研究は、後に冷戦期の軍事応用において重要な役割を果たしました。特にマルコフ過程に関する彼の研究は、イギリスの数学者シドニー・チャップマンと独立して、チャップマン=コルモゴロフ方程式として知られる一連の極めて重要な方程式を開発することにつながりました。
第二次世界大戦中、コルモゴロフはソビエト連邦の戦時努力に貢献しました。彼は砲撃に統計理論を応用し、モスクワの戦いでドイツ軍爆撃機からモスクワを守るための弾幕気球の確率的配置スキームを開発しました。彼の確率過程に関する業績は、工学、物理学、経済学など多くの分野で現在も広く応用されています。
1.5.2. Analysis and Logic
解析学の分野では、1922年にほとんどいたる所で発散するフーリエ級数の例を構成したことで国際的な注目を集めました。これは、彼の初期の決定的な業績の一つです。また、論理学においては、1925年に「排中律の原則について」と題する研究を発表し、ある解釈の下で古典形式論理のすべての命題が直観主義論理の命題として定式化できることを証明しました。これはブラウワー=ヘイティング=コルモゴロフ解釈(BHK解釈)としても知られ、論理学における重要な進展でした。
1.5.3. Turbulence and Classical Mechanics
後に、コルモゴロフは研究の焦点を乱流に移し、1941年からこの分野での論文発表を開始しました。乱流における彼の研究は、現在「コルモゴロフのマイクロスケール」や「コルモゴロフの乱流則」として知られる概念を含む、この分野の基本的な理解を深めました。
古典力学の分野では、彼はコルモゴロフ=アーノルド=モーザーの定理(KAM定理)で最もよく知られています。この定理は、1954年の国際数学者会議で初めて発表され、摂動されたハミルトン系における準周期運動の永続性に関するものです。1957年には、弟子のウラジーミル・アーノルドと共同で、ヒルベルトの第13問題のある特定の解釈を解決しました。
1.5.4. Algorithmic Information Theory and Complexity
1957年頃、コルモゴロフはアルゴリズム情報理論の開発に着手し、この分野の創始者の一人と見なされています。この理論は、しばしばコルモゴゴロフ複雑性理論と呼ばれ、グレゴリー・チャイティンやレイ・ソロモノフといった研究者たちと独立に、あるいは共同で、1960年代から1970年代にかけて発展しました。コルモゴロフ複雑性とは、ある文字列を生成する最も短いコンピュータプログラムの長さとして定義され、情報量と計算可能性の間の深遠な関係を示しています。
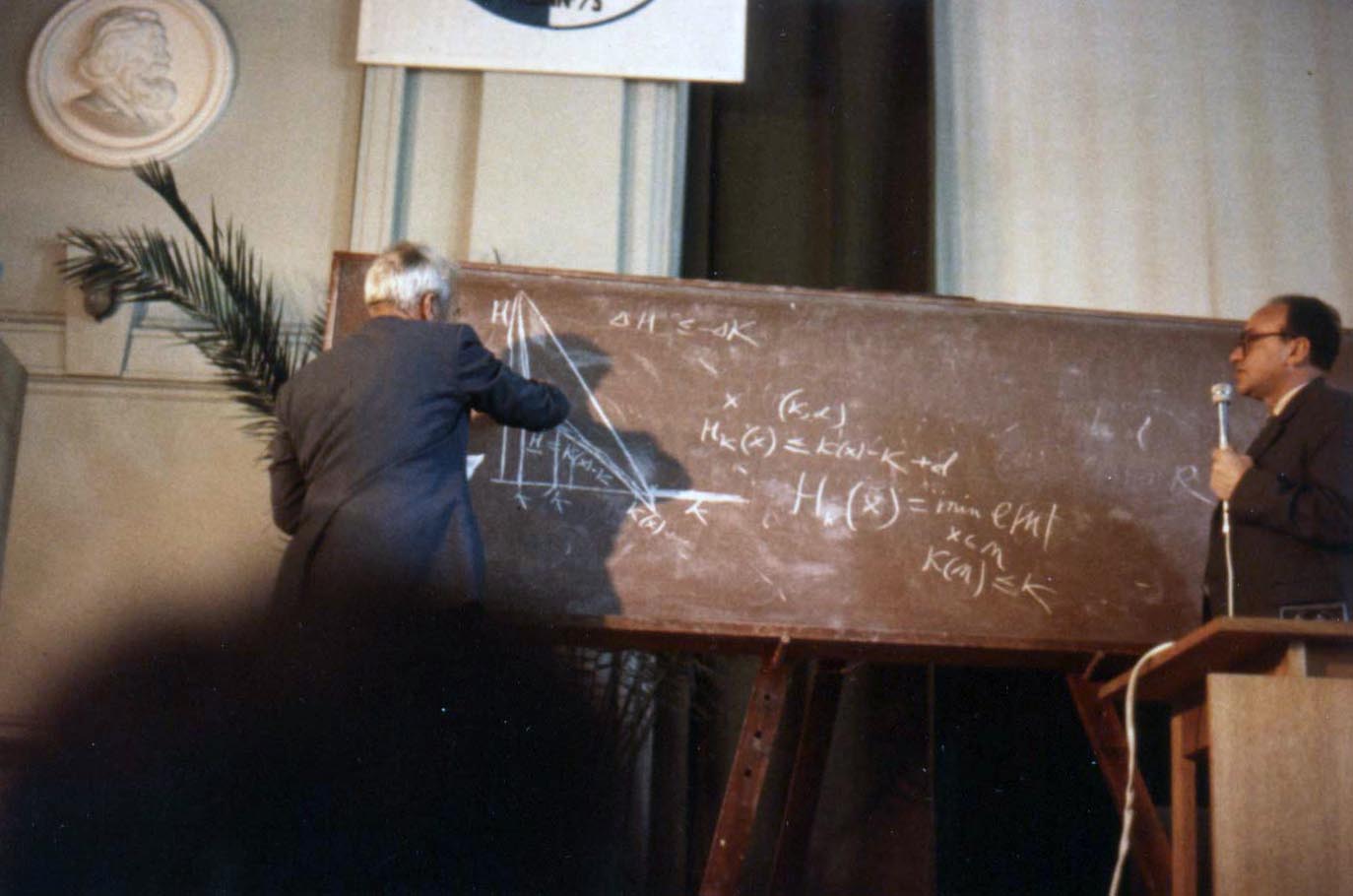

1.6. Educational Activities and Students
コルモゴロフは生涯を通じて、大学レベルだけでなく、幼い子供たちに対しても熱心な教育活動を行いました。彼は数学だけでなく、文学や音楽の分野で才能ある子供たちのための教育学の開発に積極的に関与しました。彼の尽力はソビエト連邦の英才教育の改革につながり、彼の名を冠したモスクワ大学付属コルモゴロフ物理数学学校(フィジコ=マテマティチェスカヤ・シュコラ・イメニ・A・N・コルモゴロヴァ)が設立されました。
モスクワ大学では、コルモゴロフは確率論、統計学、確率過程、数理論理学など、いくつかの学部の学部長を務めました。また、彼はモスクワ大学力学・数学部の学部長も務めました。彼の指導のもと、イズライル・ゲルファントやウラジーミル・アーノルドをはじめとする、数多くの優れた数学者が育ちました。
1.7. Personal Life
コルモゴロフは1942年にアンナ・ドミトリエヴナ・エゴロワと結婚しました。彼はまた、生涯にわたり親密な友情を保ったパヴェル・アレクサンドロフとの関係も特筆されます。彼らは1929年にアルメニアのセヴァン湖の島で約1ヶ月間滞在しました。
1971年には、調査船「ドミトリー・メンデレーエフ号」に乗船して海洋学探検に参加しました。彼は『ソビエト大百科事典』のために多くの記事を執筆しました。晩年、彼はその努力の多くを、抽象的および応用分野における確率論の数学的および哲学的関係の解明に捧げました。
1.8. The Luzin Affair
1936年の大粛清の最中、コルモゴロフの博士論文指導教官であるニコライ・ルージンが、「ルージン事件」として知られるスターリン政権の高位標的となりました。コルモゴロフを含むルージンの数人の教え子たちは、ルージンが盗作、縁故主義、その他の不正行為を行ったとして証言しました。公聴会は最終的に、ルージンが「ファシスト的科学」の僕であり、ソビエト人民の敵であると結論づけました。ルージンは学術的地位を失いましたが、奇妙なことに逮捕もソビエト連邦科学アカデミーからの追放もされませんでした。
コルモゴロフらが師に対して証言するよう強制されたかどうかは、歴史家の間でかなりの憶測の対象となっています。関係者全員が、事件について公に議論することを生涯拒否しました。ソビエト・ロシアの数学者セミョーン・サムソノヴィチ・クテラゼは、1990年代に公開された文書やその他の現存する証言を検討した後、2013年に、ルージンの教え子たちが個人的な悪感情からルージンに対する告発を開始したと結論づけました。学生たちが国家によって強制されたという明確な証拠も、彼らの学術的不正行為の申し立てを裏付ける明確な証拠もありませんでした。ソビエトの数学史家A・P・ユシュケビッチは、その時代の他の多くの高位な迫害とは異なり、スターリンがルージンの迫害を個人的に開始したわけではなく、最終的に彼が政権にとって脅威ではないと結論づけたため、他の同時代の人物と比較して異例に軽い処罰で済んだと推測しました。
2. Awards and Honours
コルモゴロフは、その生涯において数多くの国内外の学術賞と栄誉を受けました。
- ソビエト連邦科学アカデミー会員
- スターリン賞(1941年)
- アメリカ芸術科学アカデミー名誉会員(1959年)
- アメリカ哲学協会会員(1961年)
- バルザン賞(1962年)
- オランダ王立芸術科学アカデミー外国人会員(1963年)
- 王立協会外国人会員(1964年)
- レーニン賞(1965年)
- 全米科学アカデミー会員(1967年)
- ヘルムホルツ・メダル(1975年)
- ウルフ賞数学部門(1980年)
- ロバチェフスキー賞(1986年)
- 社会主義労働英雄(ソビエト労働英雄)
- レーニン勲章(7回受章)
3. Achievements and Influence
コルモゴロフの業績は、数学および科学全般に計り知れない影響を与えました。彼は確率論の現代的な基礎を築き、その後の発展の道を切り開きました。彼の広範な貢献は、以下に示す彼の名を冠した多くの概念、定理、方程式に表れています。
- フィッシャー=コルモゴロフ方程式
- ジョンソン=メール=アヴラミ=コルモゴロフ方程式
- コルモゴロフの公理
- コルモゴロフ方程式(拡散の文脈におけるフォッカー=プランク方程式としても知られる)
- コルモゴロフ次元(ミンコフスキー=ブリガンディ次元、アッパーボックス次元)
- コルモゴロフ=アーノルドの定理
- コルモゴロフ=アーノルド=モーザーの定理
- コルモゴロフの連続性定理
- コルモゴロフの判定条件
- コルモゴロフの拡張定理
- コルモゴロフの三級数定理
- フーリエ級数の収束性
- グネデンコ=コルモゴロフの中心極限定理
- 準算術平均(コルモゴロフ平均とも呼ばれる)
- コルモゴロフホモロジー
- コルモゴロフの不等式
- ランダウ=コルモゴロフの不等式
- コルモゴロフ積分
- ブラウワー=ヘイティング=コルモゴロフ解釈
- コルモゴロフのマイクロスケール
- コルモゴロフの正規化基準
- フレシェ=コルモゴロフの定理
- コルモゴロフ空間
- コルモゴロフ複雑性
- コルモゴロフ=スミルノフ検定
- ウィーナーフィルター(ウィーナー=コルモゴロフフィルタリング理論とも呼ばれる)
- ウィーナー=コルモゴロフ予測
- コルモゴロフ自己同型
- コルモゴロフの可逆拡散の特性化
- ボレル=コルモゴロフのパラドックス
- チャップマン=コルモゴロフ方程式
- ハーン=コルモゴロフの定理
- コルモゴロフ=シナイエントロピー
- 天体視程におけるコルモゴロフの乱流則
- コルモゴロフ構造関数
- コルモゴロフ=ウスペンスキーマシンモデル
- コルモゴロフの0-1法則
- コルモゴロフ=ズルベンコフィルター
- コルモゴロフの二級数定理
- ラオ=ブラックウェル=コルモゴロフの定理
- ヒンチン=コルモゴロフの定理
- コルモゴロフ個体群モデル
- コルモゴロフの強大数の法則
コルモゴロフが残した言葉として、「すべての数学者は自分が他人よりも優れていると信じている。誰もこの信念を公言しないのは、彼らが知的な人々だからである」というものがあります。また、彼の弟子であるウラジーミル・アーノルドはかつて、「コルモゴロフ、アンリ・ポアンカレ、カール・フリードリヒ・ガウス、レオンハルト・オイラー、アイザック・ニュートンは、我々の科学の源からわずか五つの生涯しか隔てていない」と述べ、彼の業績の偉大さを示しています。
4. Works
アンドレイ・ニコラエヴィッチ・コルモゴロフは、その多岐にわたる研究成果を多くの著作として残しました。彼の代表的な主要著作、論文集、教科書は以下の通りです。
- 『Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung』(確率論の基礎概念)、1933年、ユリウス・シュプリンガー、ベルリン(ドイツ語)
- 英語翻訳: 『Foundations of the Theory of Probability』、第2版、1956年、チェルシー、ニューヨーク
- 『Selected works of A.N. Kolmogorov』、3巻、V. M. チホミロフ編、V. M. ヴォロソフ訳、1991年-1993年、クルーワー学術出版社、ドルドレヒト
- 第1巻: 『Mathematics and Mechanics』(数学と力学)、1991年
- 第2巻: 『Probability Theory and Mathematical Statistics』(確率論と数理統計学)、1992年
- 第3巻: 『Information Theory and the Theory of Algorithms (Mathematics and its Applications)』(情報理論とアルゴリズム理論)、1993年
- 「On the principle of the excluded middle」(排中律の原則について)、1925年、Jean van Heijenoort『A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931』所収
- 「On Tables of Random Numbers」(乱数表について)、『Sankhyā Ser. A』25巻、369-375頁、1963年
- 『Selected works』(選集)、6巻、モスクワ(ロシア語)、2005年
- 共著・教科書**
- A. N. コルモゴロフ、ボリス・ヴラディミロヴィチ・グネデンコ共著、『Limit distributions for sums of independent random variables』(独立同分布確率変数の和の極限分布)、1954年
- A. N. コルモゴロフ、セルゲイ・フォミン共著、『Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis』(関数論と関数解析の要素)、1999年(出版)、2012年(出版)
- ロシア語原題: 『Элементы теории функций и функционального анализа』
- A. N. コルモゴロフ、セルゲイ・フォミン共著、『Introductory real analysis』(入門実解析)、1975年(1970年初版)、ドーヴァー出版、ニューヨーク
5. Death
アンドレイ・ニコラエヴィッチ・コルモゴロフは、1987年10月20日にソビエト連邦のモスクワで死去しました。彼の遺体は、多くの著名なロシア人やソビエト人が埋葬されているノヴォデヴィチ墓地に埋葬されました。