1. 生涯
1.1. 幼少期と教育
メルカダンテはプーリア州バーリ近郊のアルタムーラで非嫡出子として生まれました。正確な生年月日は記録されていませんが、1795年9月17日に受洗した記録が残っており、別の記録では1797年6月26日にナポリで受洗したともされています。彼はまず腹違いの兄から音楽を学び、1808年にナポリのサン・セバスティアーノ音楽院(現ナポリ音楽院)に入学しました。音楽院ではフルート、ヴァイオリン、作曲(1813年以降)など様々な楽器の演奏と作曲を学びました。若くしてその才能を発揮し、同僚たちとの間で演奏会を企画・開催しています。1817年には音楽院の管弦楽団の指揮者に任命され、この頃から多数の交響曲や様々な楽器のための協奏曲を書き始めました。特に1818年から1819年頃にかけては6曲のフルート協奏曲を作曲しており、その自筆譜はナポリ音楽院に保管されています。オペラ作曲家ジョアキーノ・ロッシーニはメルカダンテの才能を高く評価し、音楽院の監督であったニコロ・ジンガレッリに対して「わが賛辞、マエストロ--あなたの若い弟子メルカダンテは、我々が終わるところから始まるのだ」と述べたと言われています。

1.2. 初期活動とオペラデビュー
ロッシーニからの励ましが、メルカダンテをオペラ作曲へと導きました。1819年8月19日にナポリのサン・カルロ劇場で上演された『ヘラクレスの神格化』(L'apoteosi d'Ercoleラポテオーシ・デルコレイタリア語)が彼の最初のオペラ作品でした。続く1820年1月19日にナポリのテアトロ・ヌオーヴォで上演された2番目の作品『暴力と不変』(Violenza e Costanzaヴィオレンツァ・エ・コスタンツァイタリア語)で大きな成功を収めました。彼のその後の3作のオペラはほとんど忘れ去られていますが、1821年5月29日にボローニャのコミュナーレ劇場で上演された『スコットランド女王メアリー・ステュアート』(Maria Stuarda, Regina di Scoziaマリア・ストゥアルダ、レジーナ・ディ・スコツィアイタリア語)は、フリードリヒ・フォン・シラーの戯曲を原作とした現代的な作品として注目を集めました。そして、同年10月30日にミラノのスカラ座で初演された『エリーザとクラウディオ』(Elisa e Claudioエリーザ・エ・クラウディオイタリア語)は絶大な成功を収め、メルカダンテの名はイタリア全土に知れ渡ることになりました。この作品は20世紀にも時折再演され、近年では1988年のウェックスフォード・フェスティバル・オペラでも上演されています。
メルカダンテはその後もイタリア各地でオペラを上演し、1822年にヴェネツィアのフェニーチェ劇場で上演された『アンドロニコ』(Andronicoアンドロニコイタリア語)や、1823年にマントヴァで上演された『アルフォンソとエリーザ』(Alfonso ed Elisaアルフォンソ・エド・エリーザイタリア語)では、当時最後のカストラートであったジョヴァンニ・バッティスタ・ヴェッルーティを主役に起用しています。1823年にロッシーニがフランスへ移ると、興行主のドメニコ・バルバイアはメルカダンテをロッシーニの後継者としてサン・カルロ劇場の常任作曲家に任命しました。しかし、翌年にはバルバイアとの契約が破棄され、メルカダンテはウィーンのケルントナートーア劇場で作曲するように依頼されましたが、ウィーンでの彼の作品は成功を収めませんでした。
1826年2月21日、フェニーチェ劇場で初演された『スペインの女王カリテア』(Caritea regina di Spagnaカリテア・レジーナ・ディ・スパーニャイタリア語)が大成功を収め、この作品中のアリア「祖国のために死する者」(Chi per la patria muorキ・ペル・ラ・パトリア・ムオルイタリア語)は、後のイタリア統一運動を象徴する歌として、1831年のボローニャ蜂起や1844年のバンディエラ兄弟によって歌い継がれました。この後、メルカダンテはマドリードのイタリアオペラの音楽監督の職を得て、マドリード、カディス、リスボンといったイベリア半島の都市で作品を上演しました。この期間には、イベリア半島の民族音楽から影響を受けたことも指摘されています。1833年にはジェノヴァのソフィア・ガンバーロと結婚し、またノヴァーラの教会の合唱団長の職も得て、1840年まで教会音楽も作曲しました。
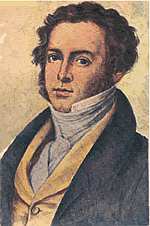
1.3. ヨーロッパでの活動と作風の変化
1836年、メルカダンテはロッシーニに招かれ、パリへ滞在しました。この時期に彼はフリードリヒ・フォン・シラーの戯曲に基づくオペラ『群盗』(I brigandiイ・ブリガンディイタリア語)をパリのテアトロ・イタリアーノで上演しましたが、パリでは成功しませんでした。しかし、このパリ滞在中に彼はジャコモ・マイアベーアやフロマンタル・アレヴィの作品、特にアレヴィの『ユダヤの女』といったフランス・グランド・オペラに触れ、その影響を強く受けました。この経験が彼の作曲スタイルに大きな変化をもたらし、劇的効果への重点、より豊かなオーケストレーション、そして壮大な合唱の導入といった特徴が見られるようになりました。また、声楽においても、それまでのベルカント様式に見られた装飾が減り、よりドラマティックな表現を重視するようになりました。
メルカダンテが関与した「改革運動」の萌芽は、1836年にジュゼッペ・マッツィーニが発表した『音楽の哲学』(Filosofia della musicaフィロソフィア・デッラ・ムージカイタリア語)という宣言にも関連しています。
帰国後、この新しい作風による最初の作品として、1837年3月11日にミラノのスカラ座で初演された『誓い』(Il giuramentoイル・ジュラメントイタリア語)が発表されました。このオペラは、当時のイタリアオペラとしては画期的な特徴を持っていました。すなわち、プリマドンナや他のスター歌手が、これまで当たり前のように舞台を独占していた最後の場面での権利を奪うという、イタリアで初演されたイタリアオペラとしては初の試みであったことが指摘されています。これにより、メルカダンテはベルカント時代の終焉を告げる存在となりました。『誓い』はメルカダンテの最良の作品の一つとされています。
1839年1月1日にナポリのサン・カルロ劇場で初演された『フェルトレのエレーナ』(Elena da Feltreエレナ・ダ・フェルトレイタリア語)は、この改革をさらに推し進めた作品でした。メルカダンテはフランチェスコ・フロリモに宛てた手紙の中で、前作『誓い』で始めた「革命」について自身の考えを述べています。「私は『誓い』で始めた革命を続けた。それは、多様な形式、カバレッタの追放、クレッシェンドの排除、声楽線の単純化、繰り返しの削減、カデンツァにおけるより大きな独自性、ドラマへの適切な配慮、声部を圧倒しない豊かなオーケストレーション、アンサンブルでの長いソロの廃止(これは他のパートを活動停止させ、アクションを阻害するだけである)、バスドラムの減少、そして金管楽器のさらなる削減である」。この作品は、その和声の大胆さ、繊細さ、独創的なオーケストレーションにおいて高く評価され、メルカダンテとヴェルディを比較する際の根拠となるほど、後のヴェルディ中後期作品に見られる全体的な整合性を驚くほど先取りしていました。これらの改革は、一時的にメルカダンテを当時のイタリアの作曲家の最前線に押し上げましたが、間もなくジョヴァンニ・パチーニの『サッフォー』やジュゼッペ・ヴェルディの数々のオペラ、特に『エルナーニ』によってその地位は追い抜かれました。
1.4. ナポリ音楽院長と晩年
1840年、メルカダンテはナポリ音楽院の院長に就任し、その後30年間にわたりその職を務めました。この時期には、視力の衰えと音楽院の職務の多忙さにより、作曲の速度は以前に比べて落ちました。彼が最後に作曲した舞台作品は、1857年2月12日にサン・カルロ劇場で初演された『ペラジオ』(Pelagioペラジオイタリア語)です。イタリア王国が成立すると、彼はヴィットーリオ・エマヌエーレ2世やジュゼッペ・ガリバルディを讃える楽曲も作曲しました。1862年からはほとんど完全に失明しましたが、口述筆記によって作曲活動を続けました。メルカダンテは19世紀前半の主要なオペラ作曲家のほとんど誰よりも長生きしましたが、1870年12月17日にナポリでその生涯を閉じました。1840年3月10日にナポリで初演された彼のオペラ『ヴェスタの巫女』(La vestaleラ・ヴェスターレイタリア語)は、後にヴェルディの『アイーダ』に強い影響を与えたと考えられています。しかし、ヴェルディがその地位を確立すると、メルカダンテのオペラは次第に時代遅れと見なされるようになっていきました。
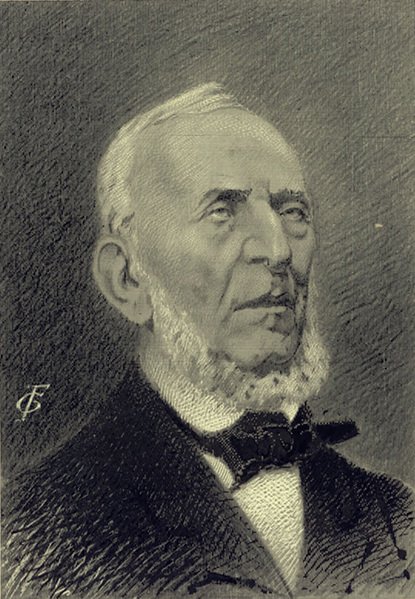
2. 主要作品
2.1. オペラ
メルカダンテは生涯に60曲ものオペラを作曲しました。彼の作品は、前述の「改革オペラ」の特徴、すなわち劇的効果の強調、多様な形式、豊かなオーケストレーション、壮大な合唱、そして声楽線の単純化といった革新的な要素を多く含んでいます。
代表作としては以下のものが挙げられます。
- 『暴力と不変』(Violenza e Costanzaヴィオレンツァ・エ・コスタンツァイタリア語、1820年)
- 『エリーザとクラウディオ』(Elisa e Claudioエリーザ・エ・クラウディオイタリア語、1821年)
- 『スコットランド女王メアリー・ステュアート』(Maria Stuarda, Regina di Scoziaマリア・ストゥアルダ、レジーナ・ディ・スコツィアイタリア語、1821年)
- 『スペインの女王カリテア』(Caritea regina di Spagnaカリテア・レジーナ・ディ・スパーニャイタリア語、1826年)
- 『群盗』(I brigandiイ・ブリガンディイタリア語、1836年)
- 『誓い』(Il giuramentoイル・ジュラメントイタリア語、1837年)
- 『フェルトレのエレーナ』(Elena da Feltreエレナ・ダ・フェルトレイタリア語、1839年)
- 『暗殺者』(Il bravoイル・ブラーヴォイタリア語、1839年)
- 『ヴェスタの巫女』(La vestaleラ・ヴェスターレイタリア語、1840年)
- 『ホラティウスとクリアティウス』(Orazi e Curiaziオラツィ・エ・クリアツィイタリア語、1846年)
- 『ペラジオ』(Pelagioペラジオイタリア語、1857年)
彼のオペラは、19世紀を通じて頻繁に上演されました。例えば、『誓い』は400回、『ヴェスタの巫女』は150回の上演を数えるなど、同時期のヴェルディ初期のオペラ(『ジャンヌ・ダルク』、『ドン・カルロ』、『アロルド』がいずれも約90回)よりもはるかに多く上演された作品もありました。
以下は、メルカダンテが作曲したオペラの一覧です。
| タイトル | ジャンル | 幕数 | 台本 | 初演日 | 初演場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 『ヘラクレスの神格化』 (L'apoteosi d'Ercoleラポテオーシ・デルコレイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | ジョヴァンニ・シュミット | 1819年8月19日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | |
| 『暴力と不変、または偽金作り』 (Violenza e costanza, ossia I falsi monetariヴィオレンツァ・エ・コスタンツァ、オッシア・イ・ファルシ・モネタリイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | アンドレア・レオーネ・トットラ | 1820年1月19日 | ナポリ、テアトロ・ヌオーヴォ | 1825年3月14日リスボンで『精霊の城』(Il castello dei spiritiイル・カステッロ・デイ・スピリティイタリア語)として改訂上演。 |
| 『サモスのアナクレオン』 (Anacreonte in Samoアナクレオンテ・イン・サーモイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | ジョヴァンニ・シュミット | 1820年8月1日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | ジャン=アンリ・ギーの『ポリクラテスのアナクレオン』に基づく。 |
| 『賢明な嫉妬者』 (Il geloso ravvedutoイル・ジェローゾ・ラッヴェドゥートイタリア語) | メロドラマ・ブッフォ | 2幕 | バルトロメオ・シニョリーニ | 1820年10月 | ローマ、テアトロ・ヴァッレ | |
| 『カルタゴのスキピオ』 (Scipione in Cartagineシピオーネ・イン・カルタジネイタリア語) | メロドラマ・セーリオ | 2幕 | ヤコポ・フェッレッティ | 1820年12月26日 | ローマ、テアトロ・アルジェンティーナ | |
| 『スコットランド女王メアリー・ステュアート』 (Maria Stuarda, regina di Scoziaマリア・ストゥアルダ、レジーナ・ディ・スコツィアイタリア語) | ドラマ・セーリオ | 2幕 | ガエターノ・ロッシ | 1821年5月29日 | ボローニャ、ボローニャ市立劇場 | |
| 『エリーザとクラウディオ、または友情に守られた愛』 (Elisa e Claudio, ossia L'amore protetto dall'amiciziaエリーザ・エ・クラウディオ、オッシア・ラモーレ・プロテット・ダルラミチツィアイタリア語) | メロドラマ・セミセーリオ | 2幕 | ルイージ・ロマネッリ | 1821年10月30日 | ミラノ、スカラ座 | フィリッポ・カサーリの『ロゼッラ、または愛と残酷』に基づく。 |
| 『アンドロニコ』 (Andronicoアンドロニコイタリア語) | メロドラマ・トラジコ | 2幕 | ジョヴァンニ・クレグリアノヴィチ | 1821年12月26日 | ヴェネツィア、フェニーチェ劇場 | |
| 『見捨てられた場所、またはアデーレとエメリコ』 (Il posto abbandonato, ossia Adele ed Emericoイル・ポスト・アッバンドナート、オッシア・アデーレ・エド・エメリコイタリア語) | メロドラマ・セミセーリオ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1822年9月21日 | ミラノ、スカラ座 | |
| 『ハムレット』 (Amletoアムレートイタリア語) | メロドラマ・トラジコ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1822年12月26日 | ミラノ、スカラ座 | ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『ハムレット』に基づく。 |
| 『アルフォンソとエリーザ』 (Alfonso ed Elisaアルフォンソ・エド・エリーザイタリア語) | メロドラマ・セーリオ | 2幕 | 不明 | 1822年12月26日 | マントヴァ、テアトロ・ヌオーヴォ | ヴィットーリオ・アルフィエーリの『フィリッポ』に基づく。1823年4月23日にレッジョ・エミリアのテアトロ・プッブリコで『アミンタとアルジーラ』(Aminta ed Argiraアミンタ・エド・アルジーライタリア語)として改訂上演。 |
| 『見捨てられたディドーネ』 (Didone abbandonataディドーネ・アッバンドナータイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | アンドレア・レオーネ・トットラ | 1823年1月18日 | トリノ、トリノ王立劇場 | ピエトロ・メタスタジオに基づく。 |
| 『スキタイ人』 (Gli scitiグリ・シーティイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | アンドレア・レオーネ・トットラ | 1823年3月18日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | ヴォルテールの『スキタイ人』に基づく。 |
| 『コスタンツォとアルメリスカ』 (Costanzo ed Almeriskaコスタンツォ・エド・アルメリスカイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | アンドレア・レオーネ・トットラ | 1823年11月22日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | |
| 『シラクサの友人たち』 (Gli amici di Siracusaグリ・アミーチ・ディ・シラクサイタリア語) | メロドラマ・エロイコ | 2幕 | ヤコポ・フェッレッティ | 1824年2月7日 | ローマ、テアトロ・アルジェンティーナ | プルタルコスに基づく。 |
| 『ドラリーチェ』 (Doraliceドラリーチェイタリア語) | メロドラマ | 2幕 | 不明 | 1824年9月18日 | ウィーン、ケルントナートーア劇場 | |
| 『テレマコとアンティオペの婚礼』 (Le nozze di Telemaco ed Antiopeレ・ノッツェ・ディ・テレマコ・エド・アンティオペイタリア語) | アツィオーネ・リリカ | 7幕 | カリスト・バッシ | 1824年11月5日 | ウィーン、ケルントナートーア劇場 | 他の作曲家による音楽を含むパスティッチョ。 |
| 『ブルゴスのポデスタ、または村の領主』 (Il podestà di Burgos, ossia Il signore del villaggioイル・ポデスタ・ディ・ブルゴス、オッシア・イル・シニョーレ・デル・ヴィッラッジョイタリア語) | メロドラマ・ジョコーソ | 2幕 | カリスト・バッシ | 1824年11月20日 | ウィーン、ケルントナートーア劇場 | ナポリのテアトロ・デル・フォンドで1825年5月28日に『村の領主』のタイトルで上演。1828年ナポリのテアトロ・デル・フォンドで『エドゥアルドとアンジェリカ』(Eduardo ed Angelicaエドゥアルド・エド・アンジェリカイタリア語)として上演。 |
| 『ニトクリス』 (Nitocriニトクリイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | ロドヴィコ・ピオサスコ・フェイズ | 1824年12月26日 | トリノ、トリノ王立劇場 | アポーストロ・ゼーノによるレチタティーヴォを含む。 |
| 『ヒペルムネストラ』 (Ipermestraイペルムネストライタリア語) | ドラマ・トラジコ | 2幕 | ルイージ・リッチューティ | 1825年12月29日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | アイスキュロスに基づく。 |
| 『ヘロデ、またはマリアンネ』 (Erode, ossia Mariannaエロード、オッシア・マリアンナイタリア語) | ドラマ・トラジコ | 2幕 | ルイージ・リッチューティ | 1824年12月12日 | ヴェネツィア、フェニーチェ劇場 | ヴォルテールに基づく。 |
| 『スペインの女王カリテア、またはポルトガル王ドン・アルフォンソの死』 (Caritea regina di Spagna, ossia La morte di Don Alfonso re di Portogalloカリテア・レジーナ・ディ・スパーニャ、オッシア・ラ・モルテ・ディ・ドン・アルフォンソ・レ・ディ・ポルトガッロイタリア語) | メロドラマ・セーリオ | 2幕 | パオロ・ポーラ | 1826年2月21日 | ヴェネツィア、フェニーチェ劇場 | |
| 『エツィオ』 (Ezioエツィオイタリア語) | ドラマ・ペル・ムジカ | 2幕 | ピエトロ・メタスタジオ | 1827年2月2日 | トリノ、トリノ王立劇場 | |
| 『山男』 (Il montanaroイル・モンタナーロイタリア語) | メロドラマ・コミーコ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1827年4月16日 | ミラノ、スカラ座 | アウグスト・ラフォンテーヌに基づく。 |
| 『ブロンズの頭、または孤独な小屋』 (La testa di bronzo, ossia La capanna solitariaラ・テスタ・ディ・ブロンゾ、オッシア・ラ・カパンナ・ソリタリアイタリア語) | メロドラマ・エロイコミーコ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1827年12月3日 | リスボン、テアトロ・プリヴァート・デイ・バローニ・キンテーラ・ア・ラランジェイラス | |
| 『シリアのアドリアーノ』 (Adriano in Siriaアドリアーノ・イン・シリアイタリア語) | ドラマ・エロイコ | 2幕 | ピエトロ・メタスタジオ | 1828年2月24日 | リスボン、サン・カルロス国立劇場 | |
| 『ヴェルジのガブリエッラ』 (Gabriella di Vergyガブリエッラ・ディ・ヴェルジイタリア語) | ドラマ・トラジコ | 2幕 | アントニオ・プロフーモ | 1828年8月8日 | リスボン、サン・カルロス国立劇場 | ドルモン・ド・ベロワの『ヴェルジのガブリエル』に基づく。1832年6月16日にジェノヴァのカルロ・フェリーチェ劇場でジョヴァンニ・エマヌエーレ・ビデラの台本により改訂上演。 |
| 『報復』 (La rappresagliaラ・ラップレザーリアイタリア語) | メロドラマ・ブッフォ | 2幕 | チェーザレ・ステルビーニ | 1829年2月21日 | カディス、テアトロ・プリンシパル | |
| 『ガマチョの婚礼におけるドン・キホーテ』 (Don Chisciotte alle nozze di Gamaccioドン・キショッテ・アッレ・ノッツェ・ディ・ガマッチョイタリア語) | メロドラマ・ジョコーソ | 1幕 | ステファノ・フェッレーロ | 1830年2月10日 | カディス、テアトロ・プリンシパル | ミゲル・デ・セルバンテスに基づく。 |
| 『リミニのフランチェスカ』 (Francesca da Riminiフランチェスカ・ダ・リミニイタリア語) | メロドラマ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1831年 | マドリードのために作曲されたが、おそらくそこで上演されなかった。 | |
| 『ザイラ』 (Zairaザイライタリア語) | メロドラマ・トラジコ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1831年8月31日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | ヴォルテールに基づく。 |
| 『パリのノルマン人』 (I normanni a Parigiイ・ノルマンニ・ア・パリジイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 4幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1832年2月7日 | トリノ、トリノ王立劇場 | |
| 『イスマリア、または愛と死』 (Ismalia, ossia Amore e morteイスマリア、オッシア・アモーレ・エ・モルテイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1832年10月27日 | ミラノ、スカラ座 | |
| 『エセックス伯爵』 (Il conte di Essexイル・コンテ・ディ・エセックスイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1833年3月10日 | ミラノ、スカラ座 | |
| 『アンティオキアのエマ』 (Emma d'Antiochiaエンマ・ダンティオキアイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 3幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1834年3月8日 | ヴェネツィア、フェニーチェ劇場 | |
| 『デンマークのウッジェーロ』 (Uggero il daneseウッジェーロ・イル・ダネーゼイタリア語) | メロドラマ | 4幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1834年8月11日 | ベルガモ、テアトロ・リッカルディ | |
| 『ヘンリー5世の青春』 (La gioventù di Enrico Vラ・ジョヴェントゥ・ディ・エンリーコ5世イタリア語) | メロドラマ | 4幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1834年11月25日 | ミラノ、スカラ座 | 一部シェイクスピアに基づく。 |
| 『二人のフィガロ』 (I due Figaroイ・ドゥエ・フィガロイタリア語) | メロドラマ・ブッフォ | 2幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1835年1月26日 | マドリード、テアトロ・プリンシペ | オノレ=アントワーヌ・リショー・マルテリーの『二人のフィガロ』に基づく。1826年作曲。 |
| 『フランチェスカ・ドナート、または破壊されたコリンティア』 (Francesca Donato, ossia Corinto distruttaフランチェスカ・ドナート、オッシア・コリンティア・ディストゥルッタイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1835年2月14日 | トリノ、トリノ王立劇場 | バイロンに基づく。1845年1月5日にナポリのサン・カルロ劇場でサルヴァトーレ・カンマラーノによって改訂上演。 |
| 『群盗』 (I brigantiイ・ブリガンディイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | ヤコポ・クレスチーニ | 1836年3月22日 | パリ、テアトロ・イタリアーノ | シラーの『群盗』に基づく。1837年11月6日にミラノのスカラ座で改訂上演。 |
| 『誓い』 (Il giuramentoイル・ジュラメントイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | ガエターノ・ロッシ | 1837年3月11日 | ミラノ、スカラ座 | 1839年ローマで『愛と義務』(Amore e dovereアモーレ・エ・ドヴェーレイタリア語)のタイトルで上演。 |
| 『二人の著名なライヴァル』 (Le due illustri rivaliレ・ドゥエ・イルストリ・リヴァーリイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | ガエターノ・ロッシ | 1838年3月10日 | ヴェネツィア、フェニーチェ劇場 | 1839年12月26日にスカラ座で改訂上演。 |
| 『フェルトレのエレーナ』 (Elena da Feltreエレナ・ダ・フェルトレイタリア語) | ドラマ・トラジコ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1839年1月1日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | 1837年秋に完成。 |
| 『暗殺者、またはヴェネツィアの女』 (Il bravo, ossia La venezianaイル・ブラーヴォ、オッシア・ラ・ヴェネツィアーナイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | ガエターノ・ロッシ | 1839年3月9日 | ミラノ、スカラ座 | オーギュスト・アニセ=ブルジョワの『ヴェネツィアの女』とジェイムズ・フェニモア・クーパーの『ブラーヴォ』に基づく。 |
| 『ヴェスタの巫女』 (La vestaleラ・ヴェスターレイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1840年3月10日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | 1842年秋にローマで『エミリア』(Emiliaエミリアイタリア語)のタイトルで上演。1851年ローマで『サン・カミッロ』(San Camilloサン・カミッロイタリア語)として上演。 |
| 『アストゥリアスの孤独な女、または再征服されたスペイン』 (La solitaria delle Asturie, ossia La Spagna ricuperataラ・ソリターリア・デッレ・アストゥーリエ、オッシア・ラ・スパーニャ・リクペラータイタリア語) | メロドラマ | 5幕 | フェリーチェ・ロマーニ | 1840年3月12日 | ヴェネツィア、フェニーチェ劇場 | |
| 『追放者』 (Il proscrittoイル・プロスクリットイタリア語) | メロドラマ・トラジコ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1842年1月4日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | F.スーリエの『追放者』に基づく。 |
| 『摂政』 (Il reggenteイル・レッジェンテイタリア語) | ドラマ・リリコ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1843年2月2日 | トリノ、トリノ王立劇場 | ウジェーヌ・スクリーブの『ギュスターヴ3世、または仮面舞踏会』に基づく。1843年11月11日にトリエステで変更を加えて改訂上演。 |
| 『レオノーラ』 (Leonoraレオノーライタリア語) | メロドラマ | 4幕 | マルコ・ダリエンツォ | 1844年12月5日 | ナポリ、テアトロ・ヌオーヴォ | ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーのバラード『レノーレ』に基づく。1859年マントヴァで『アルプスの猟師たち』(I cacciatori delle Alpiイ・カッチャトーリ・デッレ・アルピイタリア語)として編曲。 |
| 『ヴァスコ・ダ・ガマの船』 (Il Vascello de Gamaイル・ヴァスチェッロ・デ・ガマイタリア語) | メロドラマ・ロマンティコ | 1プロローグ、3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1845年3月6日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | デノワイエ・ド・ビエーヴィルの『メデューサの難破』に基づく。 |
| 『ホラティウスとクリアティウス』 (Orazi e Curiaziオラツィ・エ・クリアツィイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1846年11月10日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | ピエール・コルネイユの『オラース』に基づく。 |
| 『サラセンの女奴隷、または十字軍の野営地』 (La schiava saracena, ovvero Il campo dei crociatiラ・スキアーヴァ・サラチェーナ、オヴェーロ・イル・カンポ・デイ・クロチャーティイタリア語) | メロドラマ・トラジコ | 4幕 | フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ | 1848年12月26日 | ミラノ、スカラ座 | 1850年10月29日にナポリのサン・カルロ劇場で改訂上演。 |
| 『メデア』 (Medeaメデアイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ、フェリーチェ・ロマーニ | 1851年3月1日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | |
| 『スタティラ』 (Statiraスタティライタリア語) | トラジェディア・リリカ | 3幕 | ドメニコ・ボロニェーゼ | 1853年1月8日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | ヴォルテールの『オリンピー』に基づく。 |
| 『ヴィオレッタ』 (Violettaヴィオレッタイタリア語) | メロドラマ | 4幕 | マルコ・ダリエンツォ | 1853年1月10日 | ナポリ、テアトロ・ヌオーヴォ | |
| 『ペラジオ』 (Pelagioペラジオイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 4幕 | マルコ・ダリエンツォ | 1857年2月12日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | |
| 『ヴィルジニア』 (Virginiaヴィルジニアイタリア語) | トラジェディア・リリカ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | 1866年4月7日 | ナポリ、サン・カルロ劇場 | アルフィエーリに基づく。1849年12月から1850年3月にかけて作曲。 |
| 『ブローノの孤児、またはメディチ家のカテリーナ』 (L'orfano di Brono, ossia Caterina dei Mediciロルファーノ・ディ・ブローノ、オッシア・カテリーナ・デイ・メディチイタリア語) | メロドラマ | 3幕 | サルヴァトーレ・カンマラーノ | (未上演) | 未完成。第1幕のみ現存。1869年から1870年に作曲。 |
2.2. 器楽曲と宗教音楽
メルカダンテはオペラ作曲家として活躍した一方で、同時代の多くの作曲家と比べて、より多くの器楽曲を創作しました。これは、彼の生涯にわたるオーケストレーションへの強い関心と、1840年以降30年間にわたってナポリ音楽院の院長を務めたことが背景にあります。
彼の残した器楽曲や宗教音楽には、約30曲のミサ曲を含む教会音楽、約60曲の交響曲、約20曲の協奏曲、そして数々の室内楽曲が含まれます。特に、フルートやクラリネットのための協奏曲やソナタを多数作曲しており、彼のオペラが一時顧みられなくなった現代においては、むしろこれらの器楽曲によってその名が記憶される存在となっています。
中でも、5曲あるフルート協奏曲のうち、特にホ短調の曲(第2番)は、その壮大さとロマンティックな性格から、現代においてメルカダンテのもっとも有名な曲の一つとなっています。フランスの著名なフルート奏者ジャン=ピエール・ランパルがメルカダンテのいくつかのフルートと弦楽オーケストラのための協奏曲を録音したことで、これらの作品はコンサートフルート奏者の間で人気を博しました。協奏曲の中には弦楽オーケストラのためのものだけでなく、より大規模なアンサンブルのためのものも含まれています。
3. 音楽的遺産と評価
3.1. オペラ改革とヴェルディへの影響
メルカダンテは、19世紀イタリアオペラの形式とスタイルに重要な改革をもたらしました。彼の「オペラ改革」は、劇的効果の強調、カバレッタのような伝統的な形式の排除、より豊かなオーケストレーション、声楽線の単純化、そしてドラマへのより深い配慮を特徴としていました。これらの革新的なアプローチは、後の作曲家、特にジュゼッペ・ヴェルディの作品に具体的な影響を与えたとされています。例えば、メルカダンテのオペラ『ヴェスタの巫女』は、ヴェルディの『アイーダ』に強い影響を与えたと考えられています。メルカダンテがベルカント時代の慣習を打破し、ドラマティックな真実を追求した姿勢は、ヴェルディがその後のオペラで目指した方向性と共通するものであり、メルカダンテはイタリアオペラの変革期における重要な架け橋となりました。しかし、ヴェルディがその地位を確立すると、メルカダンテの作品は次第に時代遅れと見なされ、その評価は一時的に低下しました。
3.2. 現代における再評価
メルカダンテの死後数十年間、彼の膨大な作品群はほとんど忘れ去られていました。しかし、第二次世界大戦以降、特に20世紀後半になると、彼の作品に対する再評価の動きが始まりました。これにより、彼のオペラ作品の一部は時折再演され、録音されるようになりました。特に、彼の器楽曲、中でもフルート協奏曲は現代において再び注目を集め、演奏会で取り上げられたり、録音されたりすることで、より広い聴衆に知られるようになりました。これは、彼の音楽が持つ独自の魅力と、時代を超えた普遍的な価値が再認識された結果と言えます。
4. トリビア
- メルカダンテの生まれた場所であるアルタムーラの生家には、彼の業績を称える銘板が設置されていますが、これはファシスト時代に設置されたものであることが指摘されています。
- 彼のオペラ『スペインの女王カリテア』に含まれるアリア「祖国のために死する者」(Chi per la patria muorキ・ペル・ラ・パトリア・ムオルイタリア語)は、当時のイタリア統一運動において愛国的な象徴として歌い継がれました。これは、音楽が社会的な運動に影響を与えた一例として興味深い事実です。
- 晩年、メルカダンテは視力をほとんど失いましたが、彼は諦めることなく、口述筆記によって作曲活動を続けました。これは彼の音楽への情熱と強い意志を示す逸話です。
- ロッシーニはメルカダンテの才能を非常に高く評価しており、まだ学生であった彼に対して「私の賛辞、マエストロ--あなたの若い弟子メルカダンテは、我々が終わるところから始まるのだ」という言葉を残しました。これはメルカダンテの初期の才能がどれほど突出していたかを示すものです。