1. 生涯
ジョージ・グリーンは、その生涯の大半をノッティンガム州スネイントン(現在はノッティンガム市の一部)で過ごした。彼の父も同名のジョージで、パン職人であり、穀物を挽くためのレンガ造りの風車を所有していた。
1.1. 幼少期と教育
グリーンは1793年7月14日にスネイントンで生まれ、同日に洗礼を受けた(誕生日はその前日の可能性もある)。幼少期のグリーンは虚弱体質であり、父のパン屋での仕事を嫌っていたとされているが、当時の慣習として5歳頃から生計を立てるために働くことを余儀なくされた。
当時のノッティンガムでは、子供たちの25%から50%程度しか学校に通えず、その大半は教会が運営する日曜学校で、通学期間も通常1~2年程度であった。グリーンの父親は、息子の並外れた知性を認め、また自身のパン屋の成功により経済的に恵まれていたことから、1801年3月にアッパー・パーラメント・ストリートにあったロバート・グッドエーカー学院に彼を入学させた。ロバート・グッドエーカーは当時著名な科学啓蒙家であり教育者であった。彼は『若者の教育に関するエッセイ』を出版し、その中で「少年の利益ではなく、将来の人間を育てる」と記している。専門家でない者から見れば、彼は科学と数学に深く精通しているように見えたが、彼の論文やカリキュラムを詳しく調べると、数学の教授範囲は代数学、三角法、対数に限定されていた。したがって、グリーンが後に示した、当時の最先端の数学的発展に関する知識は、グッドエーカー学院での教育から得られたものではない。グリーンは同学院にわずか4学期(1年間)しか在籍しなかったが、同時代の人々は彼がそこで教えられることを全て習得し終えたためだと推測している。
1.2. 独学と初期の活動
1807年、父ジョージ・グリーン・シニアは、人口増加と産業革命の兆しにより劣悪なスラムと化しつつあったノッティンガムを離れ、スネイントンに土地を購入した。そこに建てられたのが、現在「グリーンの風車」として知られるレンガ造りの風力粉砕機である。これは当時としては技術的に印象的なものであったが、ほぼ24時間体制の維持管理が必要であり、これがグリーンにとって20年間の重荷となった。

パン屋の仕事と同様に、グリーンは製粉所の運営責任を煩わしく退屈に感じていた。畑から穀物が絶えず運び込まれ、強風による損傷を防ぎ、弱風時には回転速度を最大化するために、風車の帆を常に風速に合わせて調整しなければならなかった。また、互いに絶えず穀物を挽く石臼は、穀物がなくなると摩耗したり火災を引き起こしたりする可能性があった。毎月、1 tを超える石臼を交換または修理する必要があった。
グリーンが30歳の時、彼はノッティンガム購読図書館の会員となった。この図書館は現在も存在しており、グリーンの高度な数学的知識の主要な源であったと考えられている。一般的な図書館とは異なり、この購読図書館は100人ほどの会員に限定されており、会員リストの筆頭にはニューカッスル公爵が名を連ねていた。この図書館は、会員の特定の関心を満たす専門書や学術雑誌の要望に応えていた。
近年の歴史研究では、グリーンの数学教育において重要な役割を果たした人物としてジョン・トプリス(1774年頃-1857年)が挙げられている。トプリスはケンブリッジ大学で数学の11位の優等生として卒業した後、1806年から1819年までノッティンガム・ハイ・スクールの前身校の校長を務め、グリーン一家と同じ地域に住んでいた。トプリスは大陸派の数学を支持しており、フランス語に堪能で、ピエール=シモン・ラプラスの有名な『天体力学』を翻訳していた。トプリスがグリーンの数学教育に果たした可能性のある役割は、グリーンの数学的知識の源に関する長年の疑問を解決するものである。例えば、グリーンは当時イギリスではほとんど知られておらず、あるいは積極的に奨励されていなかったゴットフリート・ライプニッツに由来する微積分学の一形式である「数学的解析」を利用していた。この形式の微積分学や、シルヴェストル・フランソワ・ラクロワやシメオン・ドニ・ポアソンといったフランスの数学者たちの発展は、ノッティンガムはもちろんケンブリッジ大学でさえ教えられていなかったにもかかわらず、グリーンはこれらの発展を知っていただけでなく、それらをさらに発展させた。
2. 主要な業績と活動
ジョージ・グリーンは、その短いながらも集中的な研究期間において、数学と物理学の分野に多大な貢献をした。彼の業績は、後の科学者たちによって再評価され、現代物理学の基礎を形成する上で不可欠なものとなった。
2.1. 1828年のエッセイ発表

1828年、グリーンは現在最もよく知られている論文、『電気および磁気理論への数学的解析の応用に関するエッセイ』(An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism英語)を自費出版した。彼は、数学の正式な教育を受けていない自分が確立された学術誌に論文を提出するのは僭越だと考えたためである。この論文は予約販売形式で51人に販売されたが、そのほとんどは論文の内容を理解できなかったであろう友人たちであった。
裕福な地主で数学者であったエドワード・ブロムヘッド卿は、この論文を購入し、グリーンにさらなる数学研究を奨励した。グリーンは当初、ブロムヘッド卿の申し出が本気であるとは信じず、2年間も返事をしなかった。しかし、このエッセイは、現代のグリーンの定理に類似した定理、物理学で現在使用されているポテンシャル関数の概念、そして現在グリーン関数と呼ばれる概念など、いくつかの重要な概念を導入した。グリーンは電気と磁気の数学的理論を創出した最初の人物であり、彼の理論はジェームズ・クラーク・マクスウェルやウィリアム・トムソンなどの科学者たちの研究の基礎を形成した。
2.2. ケンブリッジ大学時代
1829年に父が死去すると、父は相当な財産と土地を蓄積しており、その約半分を息子であるグリーンに、残りの半分を娘に残した。これにより、当時36歳であったグリーンは、その財産を使って製粉所の仕事を辞め、数学研究に専念することが可能となった。
ノッティンガム購読図書館の会員たちは、グリーンに適切な大学教育を受けるよう繰り返し勧めた。特に、図書館の最も著名な会員の一人であったエドワード・ブロムヘッド卿は、グリーンと多くの書簡を交わし、ケンブリッジ大学へ進学するよう強く勧めた。
1832年、グリーンは40歳近くになってケンブリッジ大学のゴンヴィル・アンド・キーズ・カレッジに学部生として入学した。彼は、入学要件であった古代ギリシア語とラテン語の知識不足に特に不安を感じていたが、実際に求められる習熟度が予想ほど高くなかったため、習得は彼が考えていたほど困難ではなかった。数学の試験では、1年次の数学賞を受賞した。彼は1838年に4位のラングラー(卒業クラスで4番目に高い成績を収めた学生であり、ジェームズ・ジョセフ・シルベスターが2位であった)として学士号を取得した。
卒業後、グリーンはケンブリッジ哲学協会のフェローに選出された。彼の優れた学業成績がなくても、同協会はすでに彼のエッセイと他の3つの論文を読み、注目していたため、グリーンは歓迎された。その後の2年間は、グリーンにとって科学的アイデアを読み、書き、議論する比類のない機会となった。この短い期間に、彼は流体力学、音響学、光学への応用に関するさらに6つの論文を発表した。
2.3. 数学および物理学の研究
グリーンは、電気と磁気に関する数学的理論の創始者として知られている。彼の研究は、ポテンシャル理論の基礎を確立し、現在「グリーン関数」や「グリーンの定理」として知られる概念を導入した。これらの概念は、電磁気学、量子力学、流体力学など、多くの物理学分野で不可欠な道具となっている。
彼の「電気および磁気理論への数学的解析の応用に関するエッセイ」は、クーロンの法則とアンペールの法則を数学的に記述し、電磁現象を統一的に扱う枠組みを提供した。また、ラプラス方程式の解法におけるグリーン関数の導入は、境界値問題の解決に革命をもたらした。
グリーンはまた、波動力学や光学の分野でも研究を行った。運河における波の運動に関する彼の研究(「グリーンの法則」として知られる)は、量子力学のWKB近似を先取りするものであった。また、光波の研究やエーテル理論の特性に関する研究からは、現在「コーシー=グリーンテンソル」として知られるものが生まれた。グリーンの定理と関数は古典力学において重要なツールとなり、ジュリアン・シュウィンガーが1948年に行った量子電磁力学に関する画期的な研究によって再評価され、シュウィンガーは1965年にリチャード・ファインマン、朝永振一郎と共にノーベル賞を共同受賞した。グリーン関数はその後、超伝導の解析にも有用であることが証明された。
3. 私生活
1823年、グリーンは父が製粉所の管理者として雇っていたウィリアム・スミスの娘、ジェーン・スミスと関係を持った。グリーンとジェーン・スミスは決して結婚しなかったが、ジェーンはやがてジェーン・グリーンとして知られるようになり、二人の間には7人の子供が生まれた。最初の子供を除く全員が、洗礼名としてグリーンを名乗った。末の子供はグリーンの死の13ヶ月前に生まれた。グリーンは遺言で、内縁の妻と子供たちのために財産を残した。

4. 死去
ケンブリッジ大学での晩年、グリーンはかなり病気がちになり、1840年にスネイントンに戻ったが、その1年後に死去した。彼がケンブリッジで「アルコールに屈した」という噂があり、エドワード・ブロムヘッド卿のような初期の支援者の中には、彼から距離を置こうとした者もいたとされる。
グリーンは1841年5月31日にノッティンガムで47歳で死去した。彼の遺体は、グリーンの風車の近くにある聖ステファン教会の墓地に埋葬された。

5. 死後の評価と影響
グリーンの研究は、彼の生前には数学界で広く知られていなかった。グリーン自身を除けば、彼の1828年の著作を最初に引用した数学者は、イギリスのロバート・マーフィー(1806年-1843年)が1833年に発表した論文であった。
グリーンの死から4年後の1845年、当時21歳であった若きウィリアム・トムソン(後にケルヴィン卿として知られる)によってグリーンの著作は再発見され、後の数学者たちの間で広められた。D.M.カンネルの著書『ジョージ・グリーン』によれば、ウィリアム・トムソンはマーフィーがグリーンの1828年のエッセイを引用していることに気づいたが、その著作を見つけるのに苦労し、最終的に1845年にウィリアム・ホプキンスからグリーンの著作のコピーを入手したという。
1871年、N. M. フェラーズは『故ジョージ・グリーンの数学論文集』を編集し、出版した。
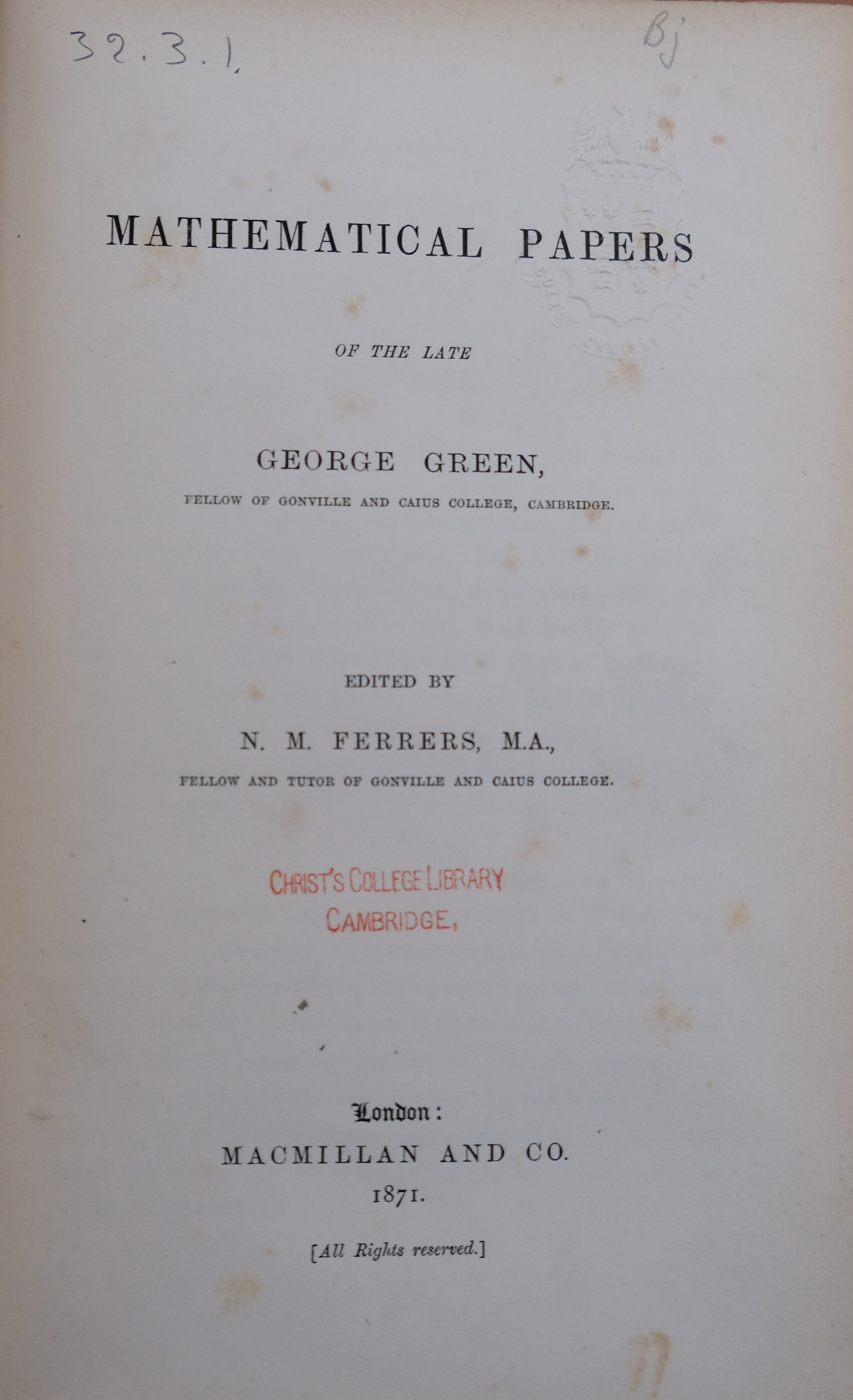
1930年にノッティンガムを訪れたアルベルト・アインシュタインは、グリーンが時代を20年先取りしていたとコメントした。彼の画期的な研究でグリーン関数を用いた理論物理学者ジュリアン・シュウィンガーは、1993年に「量子場理論のグリーン化:ジョージと私」と題する追悼文を発表している。
ノッティンガム大学のジョージ・グリーン図書館は彼の名にちなんで名付けられており、同大学の科学・工学コレクションの大部分を所蔵している。また、ノッティンガム大学工学部の研究グループである「ジョージ・グリーン電磁気学研究所」も彼の名にちなんでいる。1986年には、ノッティンガムのスネイントンにあるグリーンの風車が修復され、稼働状態に戻された。現在は19世紀の風車の実例としてだけでなく、グリーンを記念する博物館および科学センターとしても機能している。
ウェストミンスター寺院の身廊には、アイザック・ニュートン卿とケルヴィン卿の墓に隣接して、グリーンの記念石が設置されている。彼の19世紀の応用物理学への業績と影響は、1993年にメアリー・カンネルによる伝記が出版されるまで、ほとんど忘れ去られていた。
6. 著作リスト
ジョージ・グリーンが発表した主要な論文は以下の通りである。
- 『電気および磁気理論への数学的解析の応用に関するエッセイ』(An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism). By George Green, Nottingham. Printed for the Author by T. Wheelhouse, Nottingham. 1828. (Quarto, vii + 72 pages.)
- 『電気流体に類似した流体の平衡法則に関する数学的調査、およびその他の類似研究』(Mathematical investigations concerning the laws of the equilibrium of fluids analogous to the electric fluid, with other similar researches). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 5, Part I, pages 1-63. 1835年. (1832年11月12日発表)
- 『変数密度を持つ楕円体の外部および内部引力の決定について』(On the determination of the exterior and interior attractions of ellipsoids of variable densities). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 5, Part III, pages 395-429. 1835年. (1833年5月6日発表)
- 『流体媒体における振り子の振動に関する研究』(Researches on the vibration of pendulums in fluid media). Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Volume 13, Part I, pages 54-62. 1836年. (1833年12月16日発表)
- 『音の反射と屈折について』(On the reflexion and refraction of sound). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 6, Part III, pages 403-413. 1838年. (1837年12月11日発表)
- 『小深度および小幅の可変運河における波の運動について』(On the motion of waves in a variable canal of small depth and width). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 6, Part III, pages 457-462. 1838年. (1837年5月15日発表)
- 『二つの非結晶性媒体の共通表面における光の反射と屈折の法則について』(On the laws of the reflexion and refraction of light at the common surface of two non-crystallized media). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 7, Part I, pages 1-24. 1842年. (1837年12月11日発表)
- 『運河における波の運動に関する覚書』(Note on the motion of waves in canals). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 7, Part I, pages 87-95. 1842年. (1839年2月18日発表)
- 『光の反射と屈折に関する論文への補遺』(Supplement to a memoir on the reflection and refraction of light). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 7, Part I, pages 113-120. 1842年. (1839年5月6日発表)
- 『結晶性媒体における光の伝播について』(On the propagation of light in crystallized media). Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Volume 7, Part II, pages 121-140. 1842年. (1839年5月20日発表)
7. 外部リンク
- [http://www.nottingham.ac.uk/physics/gg/ George Green Society]
- [http://www.nottingham.ac.uk/physics/gg/essay1.pdf 1928年の論文(pdf)]
- [http://www.greensmill.org.uk/ グリーン風車科学センター公式サイト]
- [http://www.sixtysymbols.com/videos/georgegreen.htm George Green & Green's Functions - Sixty Symbols (ノッティンガム大学)]