1. 概要
スペウシッポス(Σπεύσιッポススペウシッポス古代ギリシア語、Speusippusスプーシッパス英語、紀元前408年頃 - 紀元前339年/338年)は、古代ギリシアの哲学者であり、プラトンの甥にあたる人物である。プラトンの姉妹であるポトネの息子としてアテナイに生まれた。プラトンの死後、紀元前348年頃にアカデメイアの第2代学頭となり、約8年間その職を務めた。
スペウシッポスは、アカデメイアの学頭としてプラトンの後を継いだものの、その哲学においてはプラトンの教えから大きく逸脱したことで知られる。彼はプラトンのイデア論を拒絶し、プラトンが「善」を究極の原理と見なしたのに対し、スペウシッポスは善を単に二次的なものと位置づけた。また、彼はピタゴラス学派の数論に深く傾倒し、数学的対象を第一義的な実在と解する独自の形而上学を展開した。この数学中心的な傾向は、彼の哲学が「数学的諸学が哲学であることになってしまった」とアリストテレスに批判される一因となり、アリストテレスがアカデメイアを去るきっかけにもなったとされる。彼の認識論においては、ある事柄について満足のいく知識を得るには、それが他のあらゆるものと区別されるすべての相違を知ることが不可欠であると主張した。倫理学においては、快楽そのものを悪と見なすなど、プラトンとは異なる独自の視点を示した。晩年は麻痺性の病に苦しみ、中風で死去し、後任にはクセノクラテスが就いた。
2. 生涯
スペウシッポスは、アテナイで生まれ、プラトン・アカデメイアの第2代学頭として、その生涯を哲学に捧げた。
2.1. 出自と家族
スペウシッポスは、紀元前408年頃にアテナイのミュリヌス区で生まれた。彼の父親はエウリメドン、母親は哲学者プラトンの姉妹であるポトネであり、彼はプラトンの甥にあたる。偽名で書かれた『プラトン第13書簡』によれば、スペウシッポスは自身の姪(彼の母親の孫娘)と結婚したとされている。
2.2. プラトンとの関係とシラクサ訪問
スペウシッポスの生涯については、叔父であるプラトンがシラクサへ3度目の旅をした際に彼が同行するまで、ほとんど知られていない。このシラクサ訪問において、彼はディオンとの友好的な関係を通じて、その優れた能力と慎重さを示した。彼の道徳的価値は、ティモンによっても認められているが、ティモンは彼の知性に対しては容赦ない嘲笑を浴びせた。彼が突然激怒したり、貪欲であったり、放蕩であったりしたという報告は、おそらく非常に不確かな情報源に由来している。アテナイオスやディオゲネス・ラエルティオスは、これらの報告の典拠として、スペウシッポスがディオンと協力して追放した小ディオニュシオスの偽作とみられる書簡における罵倒以外にほとんど挙げることができない。
2.3. アカデメイアの学頭
プラトンは自身の後継者としてスペウシッポスを選び、紀元前348年/347年に彼がアカデメイアの学頭(スコラルコス)に就任した。彼は約60歳で学頭職を継ぎ、その後の8年間(紀元前348年/347年 - 紀元前339年/338年)にわたり学園を率いた。
2.4. 死去と後継者
晩年のスペウシッポスは、長引く麻痺性の病、おそらくは脳卒中に苦しんだとされている。彼は紀元前339年/338年に死去した。彼の死後、アカデメイアの学頭職はクセノクラテスが引き継いだ。
3. 哲学
スペウシッポスの哲学は、プラトン主義から逸脱しつつも、独自の体系を築き上げた。彼の思想は、特に形而上学、認識論、倫理学において、プラトンの教えとは異なる独自の傾向を示している。
3.1. 哲学的な傾向
スペウシッポスは、プラトンのイデア論を拒絶し、プラトンが「善」を究極の原理と見なしたのに対し、善は単に二次的なものに過ぎないと主張した。彼はピタゴラス学派の数論に深く影響を受け、数学的対象を第一義的な実在と解する傾向が強かった。このため、アリストテレスは彼の哲学を「今の人々にとっては数学的諸学が哲学であることになってしまった」と批判し、スペウシッポスがアカデメイアの学頭に就任した後、アリストテレスがアカデメイアを去る一因となった。スペウシッポスは、多様な科学に共通する要素やそれらがどのように関連しうるかに関心を持ち、哲学を弁証術、倫理学、自然学の三つの部門に分けるというプラトンが基礎を築いた区分をさらに推進した。
3.2. 形而上学
スペウシッポスは、プラトンのイデア論を拒絶し、プラトンが理想数(数のイデア)と数学的数を区別したのに対し、彼は理想数を、ひいてはイデアそのものを否定した。彼は、実体の概念をより明確に定義しようと試み、その種類を、それらが基づく「原理」(archai)の違いによって区別されると考えた。したがって、彼は数の実体、大きさの実体、魂の実体を区別した。プラトンはこれらを別個の存在として理想数に帰していた。
スペウシッポスは、「一者」から始まり、各実体の種類ごとに異なる原理、すなわち数には数の原理、空間的な大きさには大きさの原理、そして魂には魂の原理を仮定することで、より多くの種類の実体を設けた。しかし、彼はこれらの異なる種類の実体の中に共通の何かを認識していたに違いない。第一に、彼は絶対的な一者から出発し、それを共通の形式的原理と見なした。第二に、彼は多数性と多様性をそれらの構成における共通の第一要素として仮定したようである。しかし、彼がプラトン主義の教義からこのような逸脱をすることになった困難は明確に理解できるものの、彼が異なる種類の原理を区別することでこれらの困難を回避したと考える方法は不明瞭である。アリストテレスによる批判は、スペウシッポスが元のプラトン主義の教義の修正にほとんど満足していなかったことを示している。
このプラトン主義からの逸脱には、より広範な影響を持つ別の側面も関連している。究極の原理として、スペウシッポスはプラトンが認めた「善」を認めず、むしろ古の「神学者たち」に立ち返り、宇宙の原理は善と完全なものの原因として位置づけられるべきであり、それ自体が善や完全なものではないと主張した。むしろ、善と完全なものは、植物や動物の種子が完全に形成された植物や動物そのものではないように、生成された存在や発展の結果として見なされるべきだと考えた。彼は、最高の美と善は始まりには存在せず、植物や動物の始まりが原因であるように、美と完全さはそれらの結果の中に存在すると仮定した。
彼は究極の原理をプラトンと同様に絶対的な一者と呼んだが、それは存在する実体とは見なされなかった。なぜなら、すべての実体は発展の結果としてのみ存在しうるからである。しかし、彼がピタゴラス学派と同様に「一者」を「善いもの」の系列に含めたとき、彼はおそらくそれを「多数者」との対立においてのみ捉え、善と完全なものは「一者」から導かれるのであって、「多数者」からではないことを示そうとしたのであろう。それにもかかわらず、スペウシッポスは、原初的な統一性(一者)に生命活動が不可分に属すると考えたようである。これはおそらく、それがどのように自己発展の過程を経て、善や精神へと成長しうるかを説明するためであろう。彼は精神も一者や善とは区別し、善を快楽や苦痛とは区別した。プラトンの不定の二元性という物質的原理に対して、より適切な表現を見つけようとするスペウシッポスの試みや、ピタゴラスの数に関する彼の論文の抜粋に見られる彼のピタゴラス的な数論の扱いは、あまり注目に値しない。特に、彼は「10」という整数を、魂の完全性に到達する真理の数として強調し、この数体系の中に真理を発見できる媒介があると主張した。
3.3. 認識論
スペウシッポスは、哲学的な考察において類似する事柄を結びつけ、類と種の概念を導き出し、確立することに関心を持っていた。彼は様々な科学に共通する要素や、それらがどのように関連しうるかを探求した。彼は、定義されるべき事柄が他のあらゆるものと区別されるすべての相違を知らなければ、完全な定義に到達することはできないと主張した。
プラトンと同様に、スペウシッポスは思考の対象と感覚的知覚の対象、すなわち理性の認識と感覚的知覚を区別した。しかし、彼は、理性的真理に参加することによって知識の段階にまで高められる知覚を仮定することで、知覚がいかにして知識として取り込まれ、変容しうるかを示そうと試みた。このことによって彼は、直接的(第一義的には美学的)な概念の様式を理解していたようである。なぜなら、彼はこの見解を支持するために、芸術的技能が感覚的活動ではなく、その対象を正確に区別する誤りのない力、すなわちそれらの合理的な知覚に基づいているという考察に訴えかけたからである。
彼は「美」を分類する作用においても理性の力が絶対的であることを強調するために、感覚的認知と理性的認知である「思惟」をさらに細分化した。彼は、感覚的認知は思惟の過程を伴わず、一方的かつ即時的なものであり、単純な刺激に過ぎず、善と悪を判断したり、幸福と不幸を判断したり、美と醜を判断したりするような高次の認識領域には属さないと考えた。彼は、すでに特定の対象に対して「美しさ」や「醜さ」などを感じるということは、判断が前提となっているのであり、判断が生じたのであれば、それはすでに美醜を判断したことであり、このような判断は結局、思惟の結果として生じるものだと考えた。最終的に、彼の論理によれば、詩や芸術を含む様々な美的活動も、結局は思惟の支配下に置かれる領域とならざるを得ない。この見解は、プラトンの「詩と芸術は情熱を煽るため排除すべきである」という論理と衝突する側面がある。
3.4. 倫理学
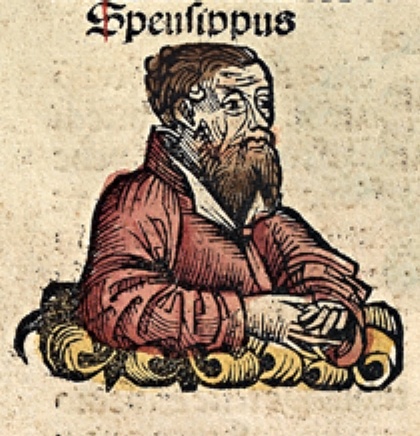
ディオゲネス・ラエルティオスが挙げたスペウシッポスの著作リストには、「正義」「友情」「快楽」「富」に関する題名が含まれている。アレクサンドリアのクレメンスによれば、スペウシッポスは幸福を「自然に合致する事柄において完全な状態であり、すべての人間が望む状態である」と見なした。また、「善は心の平静を目指し、徳は幸福を生み出す」とも述べた。この証言は、スペウシッポスの倫理学が、ストア派(意志の自然との合致)やエピクロス派(「心の平静」、aochlēsiaとアタラクシアの概念を比較)の倫理思想の重要な背景となった可能性を示唆している。
現代の学者は、スペウシッポスとクニドスのエウドクソスの間で、善に関する論争があったことを指摘している。エウドクソスもまた、善はすべての人が目指すものであると認めたが、これを快楽と同一視した。これに対し、スペウシッポスは道徳的善にのみ焦点を当てた。アリストテレスやアウルス・ゲッリウスの文献によれば、スペウシッポスは快楽を善とは認めず、善は「快楽と苦痛という対立するものの間に存在する」と主張した。スペウシッポスとエウドクソスの間のこの論争は、プラトンの『ピレボス』(特に53c-55a)に影響を与えた可能性がある。
スペウシッポスはまた、プラトンの正義や市民の概念、そして立法の基本原則をさらに発展させたようである。彼は、善は事物を派生させる原理ではなく、事物がある最終的な形へと転換されたときに規定されるものだと考えた。この意味で、彼は自然物の一部である事物にも善の原理が派生していると見なした。彼は、善が「一者」に強く依存していることを論理的に解明しようと試み、一者から派生した「二者」もまた善の一部であると考えた。さらに、快楽はこのような自然から遠く離れた希薄なものであるため、それ自体が「悪」であるという論理を展開した。
4. 著作
ディオゲネス・ラエルティオスは彼の著作の一部を挙げ、そのすべての著作が43,475行の写本に相当すると付け加えている。
- 『キュレネのアリスティッポス』
- 『富について』(1巻)
- 『快楽について』(1巻)
- 『正義について』
- 『哲学について』
- 『友情について』
- 『神々について』
- 『哲学者』
- 『ケファロスへの反論』
- 『ケファロス』
- 『クリノマコス、あるいはリュシアス』
- 『市民』
- 『魂について』
- 『グリュロスへの反論』
- 『アリスティッポス』
- 『諸芸術の批判』(各芸術につき1巻)
- 『回想録』(対話形式)
- 『体系論』(1巻)
- 『科学における類似性に関する対話』(10巻)
- 『類似性に関する区分と仮説』
- 『典型的な類と種について』
- 『匿名作品への反論』
- 『プラトン賛歌』
- 『ディオン、ディオニュシオス、ピリッポスへの書簡』
- 『立法について』
- 『数学者』
- 『マンドロボロス』
- 『リュシアス』
- 『定義』
- 『解説の配置』
- 『類似性』
- 『ピタゴラスの数について』
5. 影響と評価
スペウシッポスの思想は、プラトン・アカデメイアの発展に重要な影響を与えたが、同時にアリストテレスからの批判も受けた。
5.1. アリストテレスによる批判
スペウシッポスの哲学、特に数学の哲学的役割に対するアリストテレスの批判は顕著である。アリストテレスは、スペウシッポスが数学的対象を第一義的な実在と見なし、数を真理に到達する媒介と捉えたことに対して、「今の人々にとっては数学的諸学が哲学であることになってしまった」と述べ、その傾向を批判した。この批判は、スペウシッポスがプラトンの伝統的なイデア論から逸脱し、ピタゴラス学派の数論に傾倒したことが、アリストテレスがアカデメイアを去る決定的な要因となったことを示唆している。アリストテレスは、スペウシッポスが異なる種類の「原理」を区別することで、プラトン主義の教義の修正を試みたことに対して、ほとんど満足していなかったとされる。
5.2. アカデメイアにおける継承
スペウシッポスの死後、アカデメイアの学頭職はクセノクラテスに引き継がれた。クセノクラテスはスペウシッポスの思想の一部を継承しつつも、アカデメイアの哲学はさらなる変化を遂げた。スペウシッポスの形而上学的な方法論は、依然としてかなり神秘主義的なものとして残されており、彼の思想はアカデメイアのその後の発展に影響を与え続けた。