1. 概要
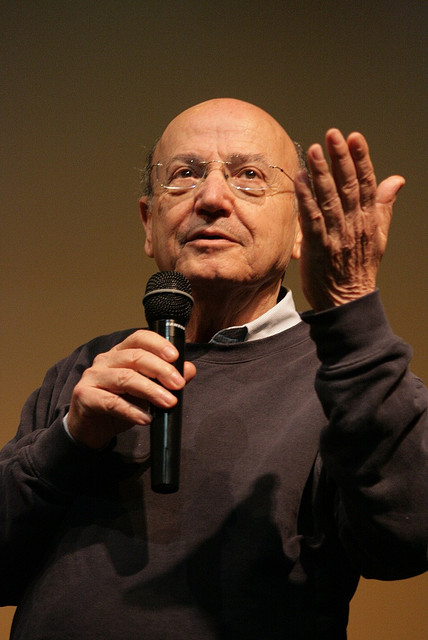
テオドロス・アンゲロプロス、通称テオ・アンゲロプロスは、ギリシャを代表する映画監督、脚本家、映画プロデューサーです。彼は1975年以降のギリシャのアート映画界を牽引し、世界で最も影響力があり、広く尊敬される映画製作者の一人として評価されています。彼の作品は、わずかな動き、距離の微細な変化、ロングテイク、そして複雑で緻密に構成されたシーンによって特徴づけられ、その映画的手法はしばしば「雄大で催眠的」と評されます。
1998年には、彼の映画『永遠と一日』が第51回カンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞しました。アンゲロプロスの作品は、現代ギリシャの歴史や社会問題を深く掘り下げ、移民や亡命といった普遍的なテーマを扱っています。
2. 生涯と背景
テオ・アンゲロプロスの生涯は、現代ギリシャの激動の歴史と深く結びついており、彼の映画製作に多大な影響を与えました。
2.1. 出生と幼少期
テオドロス・アンゲロプロスは1935年4月27日にギリシャのアテネで生まれました。彼の父スパイロスはペロポネソス半島のアンペリオナ出身です。幼少期に第二次世界大戦と、それに続く1940年代後半のギリシャ国内の政治的混乱、特にギリシャ内戦を経験しました。彼が9歳の時、父は人質として連れ去られ、アテネでの「デケンブリアナ」の際に、死体の中から父を探した経験は、後の彼の映画製作に大きな影響を与えたと述べています。この個人的な経験は、彼の作品に繰り返し現れる歴史的記憶や政治的激動のテーマの源泉となりました。彼は1980年にΦοίβη Οικονομοπούλουフォイヴィ・エコノモロウ現代ギリシア語と結婚し、3人の子供をもうけました。
2.2. 教育と初期のキャリア
アンゲロプロスはまずアテネ大学で法律を学びましたが、兵役を終えた後、フランスのソルボンヌ大学に進学しました。しかし、すぐに退学して高等映画学院(IDHEC)で映画を学びました。ギリシャに帰国後、彼はジャーナリストや映画評論家として約4年間活動しました。この期間は、彼が映画芸術に対する深い理解を培い、独自の視点を確立する上で重要な時期となりました。1967年に発生した陸軍大佐政権によるクーデターの後、彼は映画製作を開始し、1968年に初の短編ドキュメンタリー映画『放送』を自主製作し、映画監督としてのキャリアをスタートさせました。
3. 映画製作キャリア
アンゲロプロス監督は、その独特な映画製作スタイルと深いテーマ性で知られています。彼の作品は、しばしば現代ギリシャの歴史的背景と社会的な現実を反映しています。
3.1. 映画製作スタイルと特徴
アンゲロプロス監督の作品は、ゆっくりとしたペース、エピソード的な構成、そして多義的な物語構造が特徴です。特に彼のトレードマークとも言えるのが、ロングテイクの多用です。例えば、『旅芸人の記録』は4時間近い上映時間にもかかわらず、わずか80ショットで構成されています。これらのロングテイクは、緻密に計算され、多くの俳優が関わる複雑なシーンを伴うことが多く、「時間と空間が一体となる」ような独特の映像美を生み出しています。彼の映画では、動作や音楽の間の「間」も、全体の効果を生み出す上で重要な要素とされています。
マーティン・スコセッシはアンゲロプロスを「卓越した映画監督」と評し、「彼の作品には、わずかな動き、わずかな距離の変化が、映画全体、そして観客に波紋を広げる場面がある。その全体的な効果は催眠的で、雄大で、深く感情的だ。彼のコントロール感覚は、ほとんどこの世のものとは思えないほどだ」と述べています。
アンゲロプロスは、自身のスタイル形成において、オーソン・ウェルズのプラン・シークエンスとディープフォーカスの使用、そして溝口健二の時間とオフカメラ空間の使用から具体的な影響を受けたと語っています。また、アンドレイ・タルコフスキーの1979年の作品『ストーカー』も影響源として挙げています。
3.2. 主要作品とフィルモグラフィー
アンゲロプロスは1968年に短編『放送』でデビューした後、数々の長編映画を監督しました。彼の作品の多くは、特定のテーマや時代を巡る三部作として構想されています。
| 年 | ギリシャ語原題(翻字) | 英語タイトル | 日本語タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Η εκπομπήI Ekpombi現代ギリシア語 | Broadcast | 放送 | 短編映画 |
| 1970 | ΑναπαράστασηAnaparastasi現代ギリシア語 | Reconstitution | 再現 | |
| 1972 | Μέρες του '36Meres tou '36現代ギリシア語 | Days of '36 | 1936年の日々 | 「歴史の三部作」第1部 |
| 1975 | Ο ΘίασοςO Thiassos現代ギリシア語 | The Travelling Players | 旅芸人の記録 | 「歴史の三部作」第2部 |
| 1977 | Οι ΚυνηγοίI Kinighi現代ギリシア語 | The Hunters | 狩人 | 脚本共同執筆、「歴史の三部作」第3部 |
| 1980 | Ο ΜεγαλέξανδροςO Megalexandros現代ギリシア語 | Alexander the Great | アレクサンダー大王 | |
| 1983 | Αθήνα, επιστροφή στην ΑκρόποληAthina, epistrofi stin Akropoli現代ギリシア語 | Athens, Return to the Acropolis | アテネ、アクロポリスへの帰還 | オムニバス『Capitali culturali d'Europa』の一編 |
| 1984 | Ταξίδι στα ΚύθηραTaxidi sta Kythira現代ギリシア語 | Voyage to Cythera | シテール島への船出 | 脚本共同執筆、「沈黙の三部作」第1部 |
| 1986 | Ο ΜελισσοκόμοςO Melissokomos現代ギリシア語 | The Beekeeper | 蜂の旅人 | 脚本共同執筆、「沈黙の三部作」第2部 |
| 1988 | Τοπίο στην ομίχληTopio stin Omichli現代ギリシア語 | Landscape in the Mist | 霧の中の風景 | 脚本共同執筆、「沈黙の三部作」第3部、1989年ヨーロッパ最優秀映画賞受賞 |
| 1991 | Το Mετέωρο Bήμα Tου ΠελαργούTo Meteoro Vima tou Pelargou現代ギリシア語 | The Suspended Step of the Stork | こうのとり、たちずさんで | 「境界の三部作」第1部 |
| 1995 | Το βλέμμα του ΟδυσσέαTo Vlemma tou Odyssea現代ギリシア語 | Ulysses' Gaze | ユリシーズの瞳 | 脚本共同執筆、「境界の三部作」第2部 |
| 1995 | Lumière et compagnie | Lumière and Company | キング・オブ・フィルム/巨匠たちの60秒 | 共同監督・共同脚本、オムニバス『リュミエールと仲間たち』の一編 |
| 1998 | Μια αιωνιότηταと μια μέραMia aioniotita kai mia mera現代ギリシア語 | Eternity and a Day | 永遠と一日 | 脚本共同執筆、「境界の三部作」第3部、1998年パルム・ドール受賞 |
| 2004 | Τριλογία: Το λιβάδι που δακρύζειTrilogia I: To Livadi pou dakryzi現代ギリシア語 | Trilogy: The Weeping Meadow | エレニの旅 | 「現代ギリシャ三部作」第1部(「20世紀三部作」第1部) |
| 2007 | Chacun son cinéma | To Each His Own Cinema | それぞれのシネマ | 共同監督・共同脚本、オムニバス『それぞれのシネマ』の一編 |
| 2008 | Η Σκόνη του ΧρόνουI skoni tou chronou現代ギリシア語 | The Dust of Time | エレニの帰郷 | 「現代ギリシャ三部作」第2部 |
| 2011 | Mundo Invisivel | Invisible World | インビジブル・ワールド | 共同監督・共同脚本、オムニバス『インビジブル・ワールド』の一編 |
| 未完 | I alli thalassa | The Other Sea | もう一つの海 | 2012年の監督の急逝により未完成、「現代ギリシャ三部作」第3部 |
アンゲロプロスは、ギリシャ現代史を題材にした「歴史の三部作」(『1936年の日々』、『旅芸人の記録』、『狩人』)で世界的な名声を確立しました。その後、「沈黙の三部作」(『シテール島への船出』、『蜂の旅人』、『霧の中の風景』)、「境界の三部作」(『こうのとり、たちずさんで』、『ユリシーズの瞳』、『永遠と一日』)と続く連作を発表しました。
特に日本で「20世紀三部作」とも呼ばれる「現代ギリシャ三部作」は、当初『トリロジア』という一本の長編として構想されていましたが、上映時間が膨大になりすぎるため、三部作として製作されることとなりました。
3.3. 作品のテーマと協力者
アンゲロプロスの作品には、一貫して特定のテーマが繰り返し現れます。主要なテーマとして、移民、亡命、祖国からの逃亡と帰還、そして20世紀のギリシャの歴史と政治的激動が挙げられます。彼の映画は、個人的な物語を通して、これらの普遍的な人間的経験と歴史的出来事を深く探求しています。
彼の映画製作において、長年にわたり重要な協力者たちがいました。特に著名なのは、長編映画の多くで撮影監督を務めたヨルゴス・アルヴァニティス(Giorgos Arvanitis)、脚本家として共同で作品を執筆したトニーノ・グエッラ(Tonino Guerra)、そして多くの作品で音楽を担当した作曲家のエレニ・カラインドルー(Eleni Karaindrou)です。彼らとの緊密な協力関係が、アンゲロプロス作品の独特な芸術的スタイルと世界観を築き上げる上で不可欠でした。
4. 影響と評価
テオ・アンゲロプロスは、その独特な映画的言語と深い洞察力により、世界の映画界に計り知れない影響を与え、批評家から高く評価されています。
4.1. 映画界への影響力
アンゲロプロスの作品は、世界中の著名な映画監督たちから絶賛されています。前述のマーティン・スコセッシに加え、ヴェルナー・ヘルツォーク、エミール・クストリッツァ、黒澤明、イングマール・ベルイマン、ヴィム・ヴェンダース、ドゥシャン・マカヴェエフ、ウィリアム・フリードキン、マノエル・ド・オリヴェイラ、ミケランジェロ・アントニオーニなど、数多くの巨匠たちが彼の作品を高く評価し、その影響を認めています。イギリスの映画批評家であるデレク・マルコムやデヴィッド・トムソンは、アンゲロプロスを世界で最も偉大な監督の一人と見なしていました。彼の映画的言語、特にロングテイクの巧みな使用と、詩的で哲学的とも言える語り口は、後世の映画製作者たちに多大なインスピレーションを与え続けています。
5. 受賞歴と栄誉
テオ・アンゲロプロスは、その傑出した芸術的業績に対して、数々の国際的な映画祭で主要な賞を受賞し、また学術界や文化界からも多大な栄誉を受けています。
5.1. 主な映画祭での受賞歴
アンゲロプロスは、世界有数の映画祭で高く評価されました。特に、1998年の『永遠と一日』でカンヌ国際映画祭の最高賞であるパルム・ドールを受賞したことは、彼のキャリアにおける最大の栄誉の一つです。
| 年 | 映画祭 | 賞 | 作品 |
|---|---|---|---|
| 1968 | テッサロニキ国際映画祭 | ヘレニック映画批評家協会短編フィクション賞 | 『放送』 |
| 1970 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャアート映画賞 | 『再現』 |
| 1970 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ新人監督賞 | 『再現』 |
| 1970 | テッサロニキ国際映画祭 | ヘレニック映画批評家協会最優秀映画賞 | 『再現』 |
| 1971 | ベルリン国際映画祭 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI)特別賞 | 『再現』 |
| 1971 | ジョルジュ・サドゥール賞 | フランスで上映された年間最優秀映画賞 | 『再現』 |
| 1971 | イエール国際映画祭 | 最優秀外国映画賞 | 『再現』 |
| 1972 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ監督賞 | 『1936年の日々』 |
| 1973 | ベルリン国際映画祭 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI)新人映画フォーラム賞 | 『1936年の日々』 |
| 1975 | カンヌ国際映画祭 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI)賞(並行部門) | 『旅芸人の記録』 |
| 1975 | ベルリン国際映画祭 | インターフィルム賞新人映画フォーラム | 『旅芸人の記録』 |
| 1975 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ映画賞 | 『旅芸人の記録』 |
| 1975 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ監督賞 | 『旅芸人の記録』 |
| 1975 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ脚本賞 | 『旅芸人の記録』 |
| 1975 | BFI | サザーランド・トロフィー | 『旅芸人の記録』 |
| 1977 | カンヌ国際映画祭 | パルム・ドール | 『狩人』 |
| 1978 | シカゴ国際映画祭 | 最優秀映画ゴールデン・ヒューゴー賞 | 『狩人』 |
| 1980 | キネマ旬報 | 最優秀外国語映画監督賞 | 『旅芸人の記録』 |
| 1980 | 日本アカデミー賞 | 最優秀外国語作品賞 | 『旅芸人の記録』 |
| 1980 | ヴェネツィア国際映画祭 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI)賞 | 『アレクサンダー大王』 |
| 1980 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ映画賞 | 『アレクサンダー大王』 |
| 1980 | テッサロニキ国際映画祭 | ヘレニック映画批評家協会最優秀映画賞 | 『アレクサンダー大王』 |
| 1984 | カンヌ国際映画祭 | パルム・ドール | 『シテール島への船出』 |
| 1984 | カンヌ国際映画祭 | 脚本賞 | 『シテール島への船出』 |
| 1984 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI) | 国際批評家賞 | 『シテール島への船出』 |
| 1984 | リオ | 批評家賞 | 『シテール島への船出』 |
| 1986 | ヴェネツィア国際映画祭 | 金獅子賞 | 『蜂の旅人』 |
| 1988 | ヴェネツィア国際映画祭 | 銀獅子賞 | 『霧の中の風景』 |
| 1989 | ベルリン国際映画祭 | インターフィルム賞新人映画フォーラム | 『霧の中の風景』 |
| 1989 | ヨーロッパ映画賞 | 最優秀映画賞 | 『霧の中の風景』 |
| 1991 | カンヌ国際映画祭 | パルム・ドール | 『こうのとり、たちずさんで』 |
| 1991 | シカゴ国際映画祭 | 最優秀監督ゴールデン・ヒューゴー賞 | 『霧の中の風景』 |
| 1995 | カンヌ国際映画祭 | パルム・ドール | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1995 | カンヌ国際映画祭 | 審査員特別グランプリ | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1995 | カンヌ国際映画祭 | 国際批評家賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1995 | ヨーロッパ映画賞 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI)批評家賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1996 | フランス映画批評家組合賞 | レオン・ムシナック賞最優秀外国映画賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1996 | イタリア国立映画ジャーナリスト組合 | ナストロ・ダルジェント最優秀外国映画監督賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1997 | ゴヤ賞 | 最優秀ヨーロッパ映画賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1997 | 毎日映画コンクール | 最優秀外国語映画賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1997 | サン・ジョルディ賞 | 最優秀外国映画賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1997 | トゥリア賞 | 最優秀外国映画賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1998 | カンヌ国際映画祭 | パルム・ドール | 『永遠と一日』 |
| 1998 | カンヌ国際映画祭 | エキュメニカル審査員賞 | 『永遠と一日』 |
| 1998 | サンパウロ国際映画祭 | 観客賞最優秀長編映画賞(3位) | 『ユリシーズの瞳』 |
| 1998 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ映画賞 | 『永遠と一日』 |
| 1998 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ監督賞 | 『永遠と一日』 |
| 1998 | テッサロニキ国際映画祭 | 最優秀ギリシャ脚本賞 | 『永遠と一日』 |
| 1999 | アルゼンチン映画批評家協会 | 最優秀外国映画シルバー・コンドル賞 | 『ユリシーズの瞳』 |
| 2001 | アルゼンチン映画批評家協会 | 最優秀外国映画シルバー・コンドル賞 | 『永遠と一日』 |
| 2004 | ベルリン国際映画祭 | 金熊賞 | 『エレニの旅』 |
| 2004 | ヨーロッパ映画賞 | 最優秀ヨーロッパ映画賞 | 『エレニの旅』 |
| 2004 | ヨーロッパ映画賞 | 観客賞 | 『エレニの旅』 |
| 2004 | ヨーロッパ映画賞 | 国際映画批評家連盟(FIPRESCI)ヨーロッパ映画アカデミー批評家賞 | 『エレニの旅』 |
| 2005 | ファジル国際映画祭 | 特別審査員賞精神部門 | 『エレニの旅』 |
5.2. 生涯功労賞と名誉学位
アンゲロプロスは、その長きにわたるキャリア全体に対しても多くの栄誉を受けています。
| 年 | 授与機関/映画祭 | 賞/栄誉 |
|---|---|---|
| 1995 | ブリュッセル自由大学 | 名誉博士号 |
| 1996 | イタリア国立映画ジャーナリスト組合 | ナストロ・ダルジェント・ヨーロッパ・シルバーリボン賞 |
| 2001 | エセックス大学 | 名誉卒業生 |
| 2003 | コペンハーゲン国際映画祭 | 名誉賞 |
| 2003 | フライアーノ映画祭 | 名誉賞 |
| 2004 | モントリオール世界映画祭 | グランプリ・スペシャル・デザメリーク |
| 2004 | 釜山国際映画祭 | ハンドプリンティング |
| 2008 | 西マケドニア大学 | 名誉卒業生 |
| 2009 | エーゲ大学 | 名誉卒業生 |
| 2010 | エレバン国際映画祭 | 生涯功労賞 |
| 2010 | ドクズ・エイリュル大学 | 名誉博士号 |
アンゲロプロスは、1995年にベルギーのブリュッセル自由大学、フランスのパリ西大学ナンテール・ラ・デファンス、2001年7月にイギリスのエセックス大学、2008年12月にギリシャの西マケドニア大学、2009年12月にギリシャのエーゲ大学から名誉博士号を授与されました。また、2003年のコペンハーゲン国際映画祭やフライアーノ映画祭での名誉賞、2004年のモントリオール世界映画祭でのグランプリ・スペシャル・デザメリーク、同年釜山国際映画祭でのハンドプリンティング、そして2010年のエレバン国際映画祭での生涯功労賞など、数多くの栄誉が彼の功績を称えています。
6. 死去
テオ・アンゲロプロス監督は、2012年1月24日火曜日の深夜、最新作『もう一つの海』(The Other Sea)の撮影中に交通事故に遭い、数時間後に亡くなりました。この事故はアテネ近郊のピレウスに近いドラペツォナ地域で発生しました。
当時76歳だった監督は、撮影クルーと共に同地域にいた際に、オートバイにはねられました。未確認情報によれば、そのオートバイは非番の警察官によって運転されていたとされます。アンゲロプロスは交通量の多い道路を横断しようとした際に事故に遭い、病院に運ばれ集中治療室で手当てを受けましたが、数時間後に重傷がもとで息を引き取りました。彼の葬儀は、1月27日にアテネの第一墓地で公費をもって執り行われました。
7. 外部リンク
- [https://www.imdb.com/name/nm0000766/ テオ・アンゲロプロス - IMDb]
- [http://archive.sensesofcinema.com/contents/directors/03/angelopoulos.html Great Directors: Theo Angelopoulos - Senses of Cinema]
- [http://www.musicolog.com/angelopoulos.asp Theo Angelopoulos in musicolog]
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Theo_Angelopoulos ウィキメディア・コモンズには、テオ・アンゲロプロスに関連するカテゴリがあります。]