1. 概要
ハーベイ・ミルトン・クレックリー(Hervey Milton Cleckleyハーベイ・ミルトン・クレックリー英語、1903年9月7日 - 1984年1月28日)は、アメリカ合衆国の精神科医であり、精神病質研究のパイオニアである。彼の代表作である1941年出版の『精神の仮面』(The Mask of Sanity精神の仮面英語)は、精神病質の最初の臨床的記述を提供し、20世紀においてこの障害に対する最も影響力のある臨床的説明となった。この著作でクレックリーは、精神病質者が表面上は正常で魅力的でさえあるように見えるが、その「仮面」の下には破壊的な行動を伴う精神障害が隠されているという「精神の仮面」という概念を提唱した。
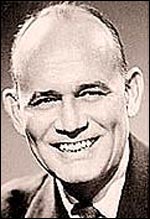
クレックリーはまた、1956年に出版され、1957年には映画化もされた女性患者の鮮やかな事例研究『イブの三つの顔』(The Three Faces of Eveイブの三つの顔英語)でもよく知られている。この事例報告は、当時精神医学ではあまり用いられなくなっていた多重人格障害(現在の解離性同一性障害)の診断をアメリカで再普及させたことで論争を巻き起こした。彼の精神病質に関する概念は、その後も反社会性パーソナリティ障害の診断や、ロバート・ヘアによるサイコパス・チェックリストの開発、そして一般社会の精神病質に対する認識に大きな影響を与え続けている。映画監督のエロール・モリスは、クレックリーを「20世紀の知られざる人物の一人であり、20世紀の二つの永続的な神話を生み出した。これらのアイデアはクレックリーに端を発するものではないが、彼がそれを普及させ、築き上げ、あたかもブランドのように売り込んだ」と評している。
2. 生涯とキャリア
ハーベイ・M・クレックリーは、アメリカ合衆国南東部のジョージア州オーガスタで生まれ、その生涯を通じて学術的および医療的なキャリアを築いた。
2.1. 出生と初期の生活
クレックリーは1903年9月7日にジョージア州オーガスタで、ウィリアムとコーラ・クレックリー夫妻の間に生まれた。彼の妹であるコナー・クレックリーは、一時的にイングランド(オックスフォードのヘディングトン・スクールなど)で教育を受け、後にアクイラ・J・ダイエスと結婚した。ダイエスは、アメリカで民間人および軍人に対する最高栄誉であるカーネギー・ヒーロー・ファンドのメダルと、第二次世界大戦後に追贈された名誉勲章の両方を受章した唯一の人物として知られている。
2.2. 教育
クレックリーは1921年にリッチモンド郡アカデミー高校を卒業した。その後、ジョージア大学(UGA)に進学し、1924年に最優等(summa cum laude最優等ラテン語)で理学士号を取得して卒業した。大学では、ジョージア・ブルドッグス・フットボールチームのフットボールおよび陸上競技チームの代表選手としても活躍した。
大学卒業後、クレックリーはローズ奨学金を得てイングランドのオックスフォード大学に留学し、1926年に学士号を取得した。さらに、1929年にはオーガスタにあるジョージア大学医学部(現在のジョージア医科大学)で医学博士号(M.D.)を取得した。
2.3. 学術および医療キャリア
医学博士号取得後、クレックリーは退役軍人省で数年間精神科医として勤務した。1937年には、ジョージア医科大学の精神科および神経科の教授に就任し、同時にオーガスタの大学病院で精神科および神経科の部長を務めた。1955年には、同医科大学の精神科および神経科の臨床教授に任命され、精神医学・健康行動学科の創設主任となった。
彼はまた、オーガスタの退役軍人省病院およびキャンプ・ゴードンの米陸軍病院の精神科コンサルタントとしても活動した。精神医学進歩グループの法医学委員会のメンバーであり、米国精神神経医学委員会および生物学的精神医学会のフェローでもあった。さらに、コーベット・H・ティグペン、後にベンジャミン・モス、ジェレ・チェンバース、シーボーン・マクガリティらと共に精神科の個人開業医としても活動した。
2.4. 私生活
クレックリーの最初の妻はルイーズ・マーティンであったが、彼女の死後、エミリー・シェフタルと再婚した。
3. 主要著作と学術的貢献
クレックリーは、精神病質と多重人格障害に関する画期的な著作を通じて、精神医学の分野に多大な影響を与えた。
3.1. 『精神の仮面』と精神病質(サイコパシー)
1941年にクレックリーが著した『精神の仮面:いわゆる精神病質人格に関するいくつかの問題を明確にする試み』(The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues About the So-Called Psychopathic Personality精神の仮面:いわゆる精神病質人格に関するいくつかの問題を明確にする試み英語)は、彼の主著であり、精神医学における症例研究の金字塔となった。この著作はその後も版を重ねて増刷され、クレックリー自身も版を重ねるごとに改訂・増補を行った。特に、1950年に出版された第2版は、事実上新しい書籍であるとクレックリー自身が述べている。
3.1.1. 執筆と核心理論
『精神の仮面』は、精神病質者が標準的な精神医学的基準から見れば正常な機能を果たしているにもかかわらず、個人的には破壊的な行動に従事するという中心的なテーゼによって特徴づけられる。この本は、捉えどころのない精神病質者の発見と診断を目的としており、症状の緩和を意図していたが、病気そのものの治療法は提示しなかった。道徳的または倫理的な制約を秘かに持たない「欺瞞の達人」が、公の場では極めて優れた機能を発揮するという彼のアイデアは、アメリカ社会を熱狂させ、心理学的内省と社会に潜む精神病質者の発見に対する関心を高めた。これにより、「精神病質者」という言葉自体が、よりスティグマの少ない「ソシオパス」という用語へと洗練されることにつながった。
3.1.2. 意味論的理論
クレックリーは、精神病質の中心的な欠陥を「意味論的」なもの(物事の「意味」)として一貫して記述した。初期にはこれを「意味論的認知症」または「アドルフ・マイヤーの用語で生理学的基盤を暗示する「dysergasiaディスエルガシア英語」と呼び、後に「障害」と表現した。彼は、これが抽象的な人生の意味を指すのではなく、日常生活の目的や忠誠心が形成され、経験される感情的な基盤を指すと説明した。この広範な社会心理学的意味で「意味論的」という用語を使用するにあたり、彼はアルフレッド・コージブスキーの一般意味論の理論を参照した。しかし、クレックリーはまた、表面上は正しい機能を示しているにもかかわらず、意味における根本的な欠陥があることを説明するために、「意味論的失語症」と呼ばれる言語障害とのアナロジーを別個に用いた。このため、彼の中心的な異常が言語の使用にあると誤解されることが繰り返されたが、彼はこれを誤解であると述べている。今日、「意味論的認知症」という用語は、意味記憶の喪失を伴う特定の神経変性疾患を指し、「意味論的障害」は一般的に自閉症に関連する意味論的・語用論的障害を指す。
3.1.3. 軍事的応用
『精神の仮面』を出版したのと同じ1941年、クレックリーは第二次世界大戦中の徴兵検査において「いわゆる精神病質人格」が直面する問題について警告する演説を行った。彼は、そのような兵士は失敗しやすく、規律がなく、時間と資源を浪費する可能性が高いと主張した。彼は、過去の法執行機関との接触や、意識を失うまで飲酒した経験を定期的に確認することを推奨した。『精神の仮面』の「単一のスパイとしてではなく、大隊として」と題されたサブセクション、および付録でさらに詳しく述べられているが、クレックリーは1937年から1939年の間に、南東海岸にある大規模な連邦退役軍人省(VA)病院で、彼自身が第一次世界大戦の退役軍人である元兵士の精神科医の一人として行った調査について記述している。クレックリーは、神経衰弱、ヒステリー、精神衰弱、心的外傷後神経症、または脳外傷(頭蓋骨損傷や脳震盪による)といった問題に疑念を抱き、より多くの精神病質人格を診断しないVAの「温情主義的な方針」を批判した。彼は、精神病質人格が「長年にわたる極度の愚行、悲惨さ、無為の記録」を持っていると結論付け、親族によって保護されている地域社会の数も考慮すると、「この障害の有病率は恐ろしいもの」であると述べた。
3.1.4. 貢献者と影響
クレックリーは『精神の仮面』の中で、「長年の医療パートナーであるコーベット・H・ティグペン博士が、この著作の発展と改訂に主要な役割を果たした」と述べている。彼はまた、彼とティグペンの妻(二人とも「ルイーズ」という名前)にも感謝の意を表し、「シデンストリッカー博士から神経精神医学科への絶え間ない励まし、寛大な援助、そして主要なインスピレーション」にも言及している。クレックリーはまた、イギリスの医師で多重人格の症例研究も発表したバーナード・ハートの著作『精神病の心理学』から自身の本の構成のインスピレーションを得たことにも触れている。
クレックリーの研究に基づき、しかし根本的な変更を加えて、1970年代から心理学者のロバート・D・ヘアは、主に刑事司法制度において精神病質を評価するための影響力のある「サイコパス・チェックリスト改訂版」(PCL-R)を考案した。このチェックリストの開発に伴い、精神病質の概念は大きく進化し、『精神の仮面』で議論された15人の精神病質者に関する記述は、より現代的な精神病質の理解に基づいて最近再評価された。著者らは、「クレックリーの精神病質者は、しばしば大胆で恐れ知らずであり、搾取的で、魅力的で、不正直で、自己中心的で、後悔がなく、浅薄であった。彼らは、判断力の欠如や不適切な人生計画と一致する、不十分に動機付けられた(すなわち、些細で計画性のない)広範な犯罪行動を示した。彼らは特に残酷であったり、冷酷であったり、身体的に攻撃的であったりすることはなく、これは現代の、あるいはメディアで描かれる典型的な精神病質者の描写とは矛盾するかもしれない」と指摘している。したがって、現代の精神病質の理解は、クレックリーが当初構想したものと比較して、残酷さや身体的攻撃性により重点を置いている。
3.2. 『イブの三つの顔』と多重人格
クレックリーのもう一つの重要な著作は、彼の個人開業のパートナーであり、ジョージア大学精神医学科の同僚であるコーベット・H・ティグペンと共著で1956年に出版された『イブの三つの顔』(The Three Faces of Eveイブの三つの顔英語)である。
3.2.1. 事例研究と出版
この本は、ティグペンが数年にわたり治療にあたった患者、クリス・コストナー・シズモアの事例に基づいている。彼らは1954年にこの症例に関する研究論文を発表し、セッションの記録と、それを「多重人格」の症例として捉えるに至った経緯を文書化した。この際、モートン・プリンスによる以前の論争の的となったクリスティーン・ボーシャンの症例研究にも言及している。彼らはまた、「人格」や「アイデンティティ」が何を意味するのかについても議論し、それが日常的な意味合い(「新しい人になる」や「自分らしくない」など)でも変化しうることを指摘した。このような診断は精神医学では比較的使われなくなっていたが、ティグペンとクレックリーは稀な症例を特定したと感じていた。しかし、他の研究者たちは、催眠や暗示が、全てではないにしても、一部の性格描写を作り出す上で用いられた可能性について疑問を呈している。
3.2.2. 診断と大衆文化への影響
この本は、ジョアン・ウッドワードが主演し、リー・J・コッブが最初の治療精神科医を、エドウィン・ジェロームがコンサルタントを演じた1957年の大ヒット映画『イブの三つの顔』の原作となった。ティグペンとクレックリーは脚本のクレジットを受け、報道によると100万ドル以上の収益を得た。本と映画では「イブ」が交代人格から解放されたとされているが、シズモア自身は、何年も経つまでそれらから解放されなかったと述べている。彼女はまた、セッションの報告書が医療関係者以外に公開されることや、自身の人生の権利を永久に譲渡する契約(マグロウヒルへの書籍化権として3 USD、映像化権として5000 USD-親族は2000 USDを受け取った)に署名したことを知らなかったと主張している。彼女は自身の治療セッションのビデオ公開を阻止しようと奮闘したが失敗した。しかし、1989年には、20世紀フォックスが映画のパロディリメイクを制作しようとした際、ティグペンを介して法的代理人なしで署名した1956年の契約を利用して、シシー・スペイセクがシズモア自身の出版した自伝のオプションを取得するのを阻止しようとしたため、同映画スタジオを訴え、勝訴した。シズモアが1982年に講演ツアーのためにオーガスタに戻った際、ティグペンもクレックリーも出席せず、彼女も彼らを訪れることはなかったが、2008年には自身の診断と治療を勇敢なものだったと評している。1984年、ティグペンとクレックリーは国際催眠ジャーナルに短い通信文を発表し、多重人格障害の診断の過剰使用に対して警告を発した。
3.3. 『愛のカリカチュア』と病的な性愛
クレックリーは1957年に『愛のカリカチュア:病的な性愛の社会的、精神医学的、文学的側面に関する考察』(The Caricature of Love: A Discussion of Social, Psychiatric, and Literary Manifestations of Pathologic Sexuality愛のカリカチュア:病的な性愛の社会的、精神医学的、文学的側面に関する考察英語)という本も著した。この本は、出版直後にある医学評論家によって「私たちの文化における同性愛の影響と、彼がそれらの影響を支持すると信じるフロイト派の教義に対する激しい論争」と評された。
4. 医学的実践と理論
クレックリーは、当時の精神医学界で議論の的となっていた治療法や、栄養学と精神疾患の関連性についても研究を行った。
4.1. ビタミンと栄養学
クレックリーは、医学教授であり血液学と栄養学の国際的に認められた専門家であるバージル・P・シデンストリッカーと共同で研究を行った。彼らとクレックリーが発表した論文は、当時南部諸州で風土病であったペラグラ(現在のナイアシン欠乏症)の非定型的な形態を初めて記述したものの1つであった。1939年と1941年には、ニコチン酸(ナイアシンまたはビタミンB3)を異常な精神状態や精神疾患の治療に用いることに関する論文を発表した。しかし、これらの研究は、統合失調症などの精神疾患におけるメガビタミン療法の使用を正当化するために誤って利用されることがあった。
4.2. 昏睡療法と電子麻酔
クレックリーは、論争の的となっていた「昏睡療法」を実践した。これは、インスリン、メトラゾール、または他の薬物の過剰投与によって、精神科患者を数週間にわたり繰り返し昏睡状態に陥れる治療法である。時に致命的な合併症が発生したことを受け、クレックリーは1939年と1941年に、理論的根拠に基づいて様々なビタミン、塩類、ホルモンの予防的投与を推奨する論文を発表した。1951年には、電子麻酔(脳に電流を流すことで発作を起こさずに深睡眠療法を誘発する治療法)を様々な病状に用いることを示唆する症例研究を共著で発表した。彼はまた、電気けいれん療法も使用した。
5. 刑事責任と法医学精神医学
クレックリーは法医学精神医学の分野でも活動し、刑事責任能力に関する議論に貢献した。
5.1. 心神喪失弁護と責任能力
1952年、クレックリーはウォルター・ブロムバーグと共に心神喪失弁護に関する論文を発表した。彼らは、その文言を「被告は精神疾患を患っていたか、もしそうであれば、それが告発された犯罪に対して法の下で彼を無責任にするのに十分であったか?」と変更することを提案した。「責任能力」(accountabilityアカウンタビリティ英語)という概念は、マクノートン・ルールにおける「責任」の狭い定義(善悪の道徳的知識の欠如を要求し、実質的に精神病(妄想、幻覚)のみを対象とする)に代わるものとして意図された。彼らは、精神疾患は心のあらゆる部分に関与しうるものであり、心神喪失のテストは、被告の心が全体として、何らかの内的な病理(「明白なものか隠されたものか」にかかわらず)のために、法に従って行動できなかった程度に焦点を当てるべきだと主張した。
しかし、10年後、クレックリーは「精神医学:科学、芸術、そして科学主義」と題された章で、精神医学が診断や治療に関して持つ能力、特に刑事責任能力に関する能力を誇張することに対して他者に警告を発した。この点に関して、クレックリーはハキームの批判に同意を表明したが、ハキームはクレックリーの精神病質に関する主張を、精神科医が診断用語の明確さを互いに誇張している例として引用していた。
5.2. テッド・バンディ事件
クレックリーは、1979年の連続殺人犯テッド・バンディの裁判において、検察側の精神科医を務めた。この裁判はアメリカで初めて全国的にテレビ中継された。バンディを面接し、以前の2つの報告書を検討した後、クレックリーは彼を精神病質者と診断した。責任能力鑑定の公聴会では、弁護側の精神科医もバンディを精神病質者であると主張したが、彼はバンディが裁判を受ける能力や自己弁護する能力がないと結論付けたのに対し、クレックリーは彼にその能力があると主張した。
6. 評価と影響
クレックリーの業績は、精神医学の発展に大きな足跡を残したが、その理論や臨床事例は後世において批判的な検討と再評価の対象となっている。
6.1. 精神医学分野への影響
クレックリーの精神病質に関する研究と概念は、反社会性パーソナリティ障害の診断、サイコパス・チェックリスト(PCL)の開発、そして一般社会の精神病質に対する認識を通じて、現在も影響力を持ち続けている。映画監督のエロール・モリスは、クレックリーを「20世紀の知られざる人物の一人」と評し、「彼は20世紀の二つの永続的な神話を生み出した。これらのアイデアはクレックリーに端を発するものではないが、クレックリーがそれらを普及させ、築き上げ、あたかもブランドのように売り込んだ」と述べている。
6.2. 批判と再評価
クレックリーの理論や臨床事例、特に『イブの三つの顔』の事例に対しては、批判的な見解も存在する。例えば、クリス・コストナー・シズモアの事例においては、催眠や暗示が性格描写の一部または全てを作り出したのではないかという疑問が呈された。シズモア自身も、セッション報告書の公開や自身の人生の権利譲渡に関する契約について知らされていなかったと主張し、後に映画スタジオを訴えるなど、その治療プロセスと公開方法には倫理的な問題が指摘されている。ティグペンとクレックリー自身も、1984年には多重人格障害の診断の過剰使用に対して警告を発している。
また、クレックリーが記述した精神病質者(『精神の仮面』に登場する15人の事例)は、現代の精神病質の理解とは異なる側面を持つことが再評価によって示されている。現代の精神病質の典型的な描写やメディアでの表現では、残酷さや身体的攻撃性がより強調される傾向があるが、クレックリーの精神病質者は、大胆で恐れ知らず、搾取的、魅力的、不正直、自己中心的、後悔がなく、浅薄であったものの、特に残酷であったり、冷酷であったり、身体的に攻撃的であったりすることはなかったとされている。この比較は、精神病質の概念が時代とともにどのように進化してきたかを示している。