1. 生い立ちと教育
1.1. 出生と家族背景
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、1923年5月2日にブルネイのツトン地区にあるカンポン・カンダンで生まれた。
1.2. 学歴と戦時体験
彼はツトン町のムダ・ハシム中学校の前身であるマレー語学校で学び、その後1940年にスルタン・イドリス教育大学の前身であるスルタン・イドリス師範学校(SITC)で研修を受けたが、1941年後半の太平洋戦争における日本軍の侵攻により学業を中断された。1942年12月にブルネイに戻り、ブルネイ・タウンで日本語の授業に参加し、その後クチンでも学んだ。1943年末には、ボルネオ各地の数名の学生とともに日本への留学に選抜された。彼は東京の国際学友会日本語学校で語学コースに登録し、研修中に東京大空襲を経験した。その後1945年4月には広島文理科大学 (旧制)(現在の広島大学)に入学し、教育学を専攻した。
18歳だった彼は、第二次世界大戦中に日本によって訓練されたブルネイ人学生の一人であり、「南方特別留学生」プログラムに選抜された。彼は日本で訓練を受け、広島大学に通い、1945年8月6日の原子爆弾投下時には爆心地から約1.5km離れた大学構内(広島高等師範学校ピアノ室)に滞在しており、ハジ・アブドル・ラザク・ビン・アブドル・ハミドと戸田清教授とともに数学の授業を受けていた際に被爆した。木造2階建ての建物が全壊したが、机とピアノに守られて3人とも無事だった。被爆後、彼は大学の校庭で野宿しながら他の日本人被爆者の救助に尽力した。これにより放射線障害を負った。当時広島で被爆した南方特別留学生は9人おり、ユスフは唯一のブルネイ人被爆者であり、最後に亡くなった人物であった。彼は1946年3月にブルネイに帰国し、戦後のブルネイの政治発展に尽力した。彼はジャミル・アル・スフリらとともに、SITCでの訓練を通じて、日本占領後のブルネイにおける政治活動の最前線に立った。
2. 初期キャリアと政治活動
2.1. 教師としてのキャリア
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、1939年1月1日にツトンのブキト・ベンデラ・マレー語学校で教師としてのキャリアを始めた。戦後は、クアラ・ブライトのマレー語学校教育学部で教鞭をとった。その後、1954年までテンブロン地区に赴任した。
2.2. 青少年運動とBARIP
彼は1946年4月12日に結成された青年党(Barisan Pemudaマレー語、BARIP)の副党首に選出された。BARIPはブルネイの独立達成とマレー人コミュニティの社会的・経済的進歩を目的としていたが、インドネシアのナショナリズムの影響を受けつつも、ブルネイの独立を最優先とはしなかった。代わりに、このグループは若いブルネイ人を団結させ、移民に対する地元の権利を保護することに焦点を当て、マレー人の利益を守るためにイギリス保護領の復活を提唱し、これが1946年7月の民政復帰につながった。彼は、抗議のスローガン変更を命じたイギリス駐在官に対し、BARIPを率いて拒否し、スルタン・アハマド・タジュディンに「アーチ」の問題を提起する上で重要な役割を果たした。スルタンは介入し、イギリス駐在官の命令を覆し、BARIPの側に立った。これは、スルタンがブルネイにおける中国の影響力増大への懸念を共有していたため、彼にとって驚きではなかった。彼の転勤は、他の指導者たちの転勤とともにBARIPを弱体化させ、その衰退につながった。
1953年には、憲法諮問委員会である「トゥジュ・セランカイ」の書記に任命された。彼は、スルタン・オマール・アリ・サイフディン3世の憲法提案に対する国民の圧倒的な反応を目の当たりにし、特に若い教育を受けたブルネイ人、特に教師たちが民主主義と独立についての議論に参加した。1954年初頭までに、委員会はブルネイ全土の視察を終え、マラヤの憲法と行政手続きを研究する任務を与えられた。書記として、彼は4つの地区への訪問から50ページの報告書を作成し、1954年にスルタン・オマール・アリ・サイフディン3世に提出した。
2.3. 国歌作詞への貢献
1947年、ペンギラン・ムハンマド・ユスフはBARIPのために『アッラー・ペリハラカン・スルタン』の歌詞を作詞した。この曲は後にブルネイの国歌として採用された。国歌はアワン・ブサル・サガップによって作曲された。
3. 公職キャリア
3.1. 初期行政職
3.1.1. 情報局と行政実務
1954年に情報局に異動した後、ペンギラン・ムハンマド・ユスフはイギリスのトーキーにあるサウス・デヴォン・テクニカル・カレッジに送られ、1957年まで公共行政と社会行政を学んだ。帰国後、彼は情報局に復帰し、1957年1月1日に同国初の情報官に選出された。同年後半には、新たな憲法が制定されるまでブルネイ国務評議会の非公式メンバーに任命された。同年、彼はスルタンとともにロンドンを訪れ、植民地省との重要な憲法に関する協議に参加した。これらの協議中、彼は憲法の施行に合わせて首席大臣、国務長官、国家財務官を任命するというスルタンの要求を強く支持した。彼は、この変更が1953年以来遅れており、国民の願いを反映していると主張した。
1958年2月、ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、ペンギラン・アリ、マルサル・マウンとともに、ブルネイとイギリス間の協定草案を検討し、国務評議会がアンソニー・アベル不在で議論することを主張した後に、新版を提案する委員会に任命された。その後、1958年5月、アベルは彼を、ペンギラン・アリ、マルサルとともに、国務評議会で発言力のある3人の主要人物の一人として特定した。E. R. ベヴィントンは、彼らがしばしばスルタンの代弁者として行動し、憲法制定と協定草案の両方の修正を提唱する上で重要な役割を果たしたと述べた。

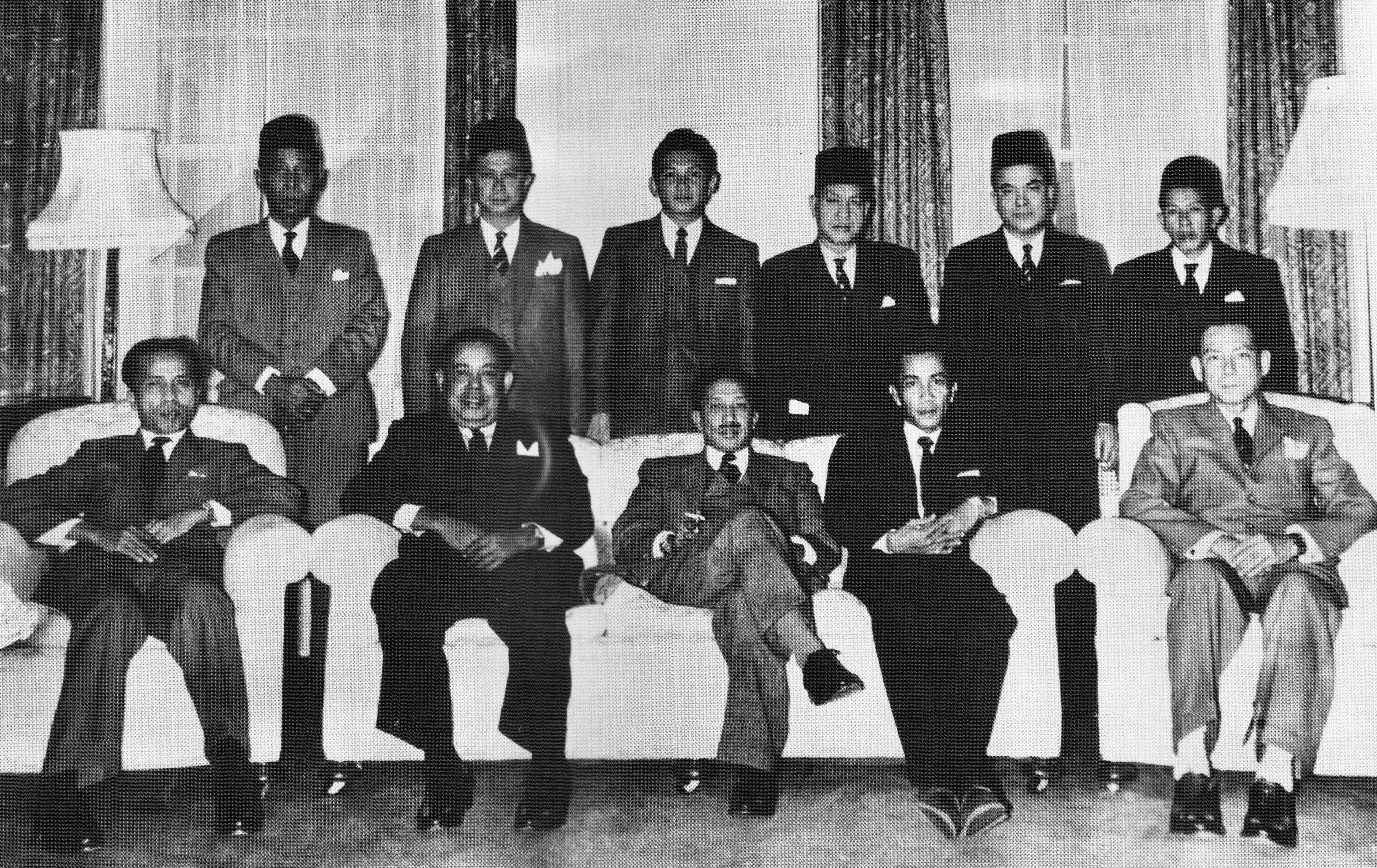
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、1959年のロンドンでの憲法交渉におけるブルネイ代表団の一員であり、代表団にはすべてのマレー国務評議会メンバーが含まれていた。2人の弁護士の助言を受け、代表団はイギリス駐在官の権限移譲、国籍、ブルネイ立法評議会の資格、防衛、高等弁務官の留保権限などの主要な問題を議論した。3月23日、ロンドン会議で、彼は国務長官が議長を務める6回の本会議に参加した。彼はブルネイの法務顧問とともに、ブルネイのサラワクからの行政分離を含む主要な憲法事項の議論に関与した。
1959年10月、ペンギラン・ムハンマド・ユスフは日本で開催された青年会議でブルネイを代表し、そこで原子エネルギーを破壊のためではなく、世界の平和と繁栄のために利用することを提唱するという重要な決定がなされた。彼は、世界中の若者が科学を学び、原子時代に適応することの重要性を強調し、彼らが国家の指導者としてだけでなく、平和と繁栄を擁護する世界の指導者として準備するよう促した。25カ国の代表が参加したこの会議は、日本の文部大臣によって公式に開会された。その後、彼は1959年9月29日にラパウでブルネイの憲法の交付と署名を証言した。署名後、彼は立法評議会と執行評議会の両方のメンバーに任命された。
1960年12月、立法評議会の非公式メンバーが、マレー人役人の影響力増大に対する地元住民とマラヤ連邦派遣団との間の敵意の高まりを受けて、彼らの意見が拒否されたことに抗議してウォークアウトした後、ペンギラン・ムハンマド・ユスフは国家情報官に確認された。1961年7月、彼はマルサル・マウンの後任として副国務長官に昇進した。高等弁務官は、彼とマルサルの任命が、彼らのナショナリスト的傾向とブルネイ人民党(PRB)との密接な関係のために、以前は懸念を抱かせただろうと指摘した。ペンギラン・ムハンマド・ユスフはマルサルとともに、任命後4ヶ月以内に国務長官室で約600件の未処理の行政業務を処理し、ブルネイにおけるかなりの行政上の滞りを解消したことで称賛された。1961年8月の彼の昇進は、副国務長官および放送情報局長としての役割を含み、スルタンとの同盟を強化し、上級政府職におけるブルネイ人役人の登用への転換を示し、マラヤ人役人への依存を減らした。

同年同月、ジョージ・ダグラス=ハミルトンがブルネイを訪問し、スルタンとマレーシア計画について議論したが、彼のコミットメントを得ることはできなかった。トゥンク・アブドゥル・ラーマンがブルネイからの役人引き上げを脅したことに裏切られたと感じたスルタンは、孤立主義的アプローチを支持する伝統的な顧問であるマルサル、ペンギラン・アリ、ペンギラン・ムハンマド・ユスフに頼った。スルタンは憲法上および条約上の制約を理由に、マレーシア計画の議論を拒否した。しかし、1961年11月下旬、スルタンは執行評議会にマレーシア計画を受け入れる決定を通知し、この件に関する議論や投票は行われなかった。彼はマルサル、ペンギラン・アリ、ペンギラン・ムハンマド・ユスフ、そしてアブドゥル・アジズ・ザインの支持を得ていたと信じられており、彼らをこの問題について助言するために任命していた。ペンギラン・ムハンマド・ユスフはその後、1961年12月中旬にクチンで開催された第2回マレーシア連帯諮問委員会(MSCC)会議にオブザーバーとして出席し、連邦代表、移民、経済発展などの主要な問題が議論された。
1962年2月7日にシンガポールで開催されたMSCC最終会議で、ボルネオ地域への特別な保護を伴うマレーシア計画が合意された。ブルネイ代表を含むすべての代表団が署名した覚書が、マラヤ政府とイギリス政府によって設置されたコボルド委員会に提出された。ブルネイ代表団は、ペンギラン・ムハンマド・ユスフ、ペンギラン・アリ、ジャミル、リム・チェン・チュー、そして顧問としてアブドゥル・アジズで構成されていた。3月には、ペンギラン・アリとペンギラン・ムハンマド・ユスフが公然とマレーシア計画を支持し、MSCCの覚書に署名した一方で、アブドゥル・アジズはデニス・ホワイトに対し、ダトー・マルサルとイブラヒム・モハマド・ジャファルが計画への支持を揺るがせていると伝えた。ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、4月にマレーシア提案に関するブルネイ政府の議論に関与し、特にマルサルとペンギラン・アリの間の亀裂を調停することで、政府内の緊張を解決する上で重要な役割を果たした。彼はマレーシアを支持するグループの一員であり、他の人々を提案の承認へと導くのに貢献した。

ペンギラン・ムハンマド・ユスフは1962年7月、ラジオ・ブルネイで国民の懸念に対し、ブルネイがマレーシアに加盟した場合、ブルネイの行政とスルタンの地位が廃止されるという噂を否定した。彼は、少数のグループがスルタンに対する反対を扇動し、虚偽情報を広めていると警告した。7月28日、政府を代表して、彼は『ボルネオ・ブルテン』と立法評議会における医師不足に関する懸念に対し、この問題を否定し、ブルネイには12人の医師がおり、平均して7,000人あたり1人の医師がいると述べた。同じ放送で、彼は再び国民をスルタンに反抗させようとする動きについて警告した。これは警察と特別支部が知らなかったにもかかわらず、宮殿の承認を得たメッセージであるように見えた。個人的には、彼はインドネシアがプロパガンダの背後にいると示唆した。彼の警告は異例であり、ブルネイ政府は通常、そのような直接的なコミュニケーションを避けていた。また、彼の警告は銃器盗難の増加と一致していた。北カリマンタン国民軍(TNKU)との関連は確認されなかったが、『ボルネオ・ブルテン』はこれらの犯罪の異例な性質を指摘し、TNKUの反乱準備と関連しているという疑念を強めた。
1962年9月25日、マルサルが率いるブルネイ代表団は、ペンギラン・ムハンマド・ユスフ、ペンギラン・アリ、ジャミル、ペンギラン・モハマド・アブドゥル・ラフマン・ピウト、そして法務顧問のニール・ローソンとアブドゥル・アジズを伴い、クアラルンプールへ、マラヤ政府との予備協議のために向かった。彼らの提案には、完全な自治、外交と防衛の連邦責任、スルタンの地位とブルネイ憲法の連邦保証、州が管理する移民を伴う連邦市民権モデル、マラヤ政府への代表権、および財政的貢献が含まれていた。しかし、彼らはマラヤの条件を「受け入れがたい」と感じた。12月までに、代理高等弁務官W. J. パークスは、ブルネイ政府、特にペンギラン・ムハンマド・ユスフがTNKUの活動を認識していた可能性があると指摘した。7月には、彼はラジオ放送でスルタンに対する不安を扇動する少数のグループについて警告していたが、当時政府はTNKUに関する具体的な情報を持っていなかったようである。
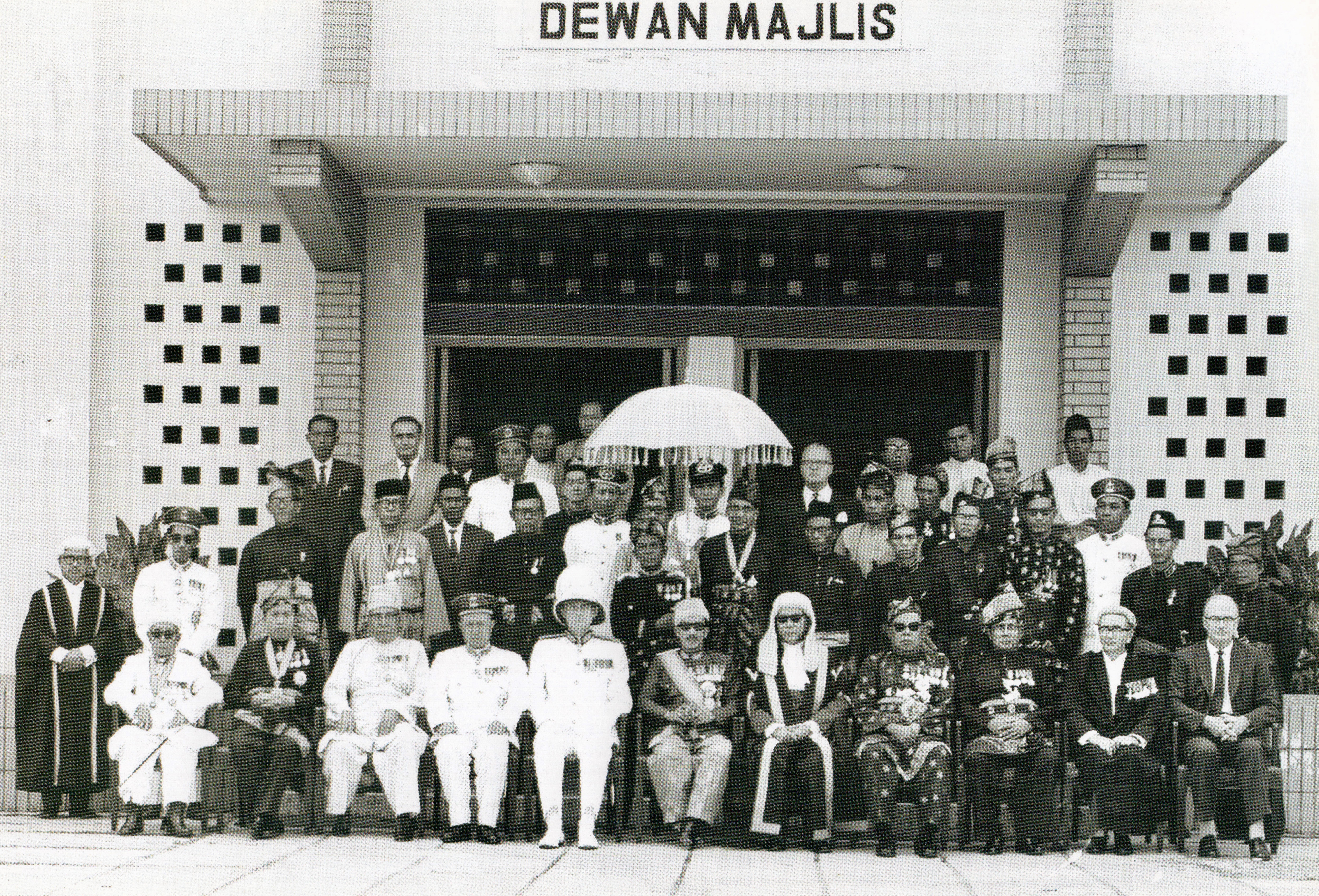
1963年3月、スルタンは拘束されたPRB指導者たちを利用してブルネイのマレーシア参加を提唱しようとし、ホワイトは彼らの誠実さを評価した。ホワイトは、彼らがペンギラン・ムハンマド・ユスフのもとで新しい政党を結成し、憲法改革とマレーシアに焦点を当てることを助けることができると示唆した。彼はアブドゥル・ハピズを信頼できる、テンガ・ハシップは有益だが指導者ではない、ペンギラン・メトゥシンはまず独立を支持すると評価し、運動を支援するために拘束者たちを仮釈放することを推奨した。しかし、PRB穏健派とペンギラン・ムハンマド・ユスフを巻き込んだ新しい政党を創設しようとするホワイトの努力は最終的に失敗した。主な障害は、反乱後特に、スルタンが自身の支配外での政治活動を許可することに抵抗があったことであった。この不信感は、ブルネイのマレーシアに関するクアラルンプールでの交渉から政党代表が排除されたことにも及んだ。この時期にはブルネイ動乱も発生している。1963年12月、彼の副国務長官としての任期が完了した。
3.1.2. ブルネイ国務長官
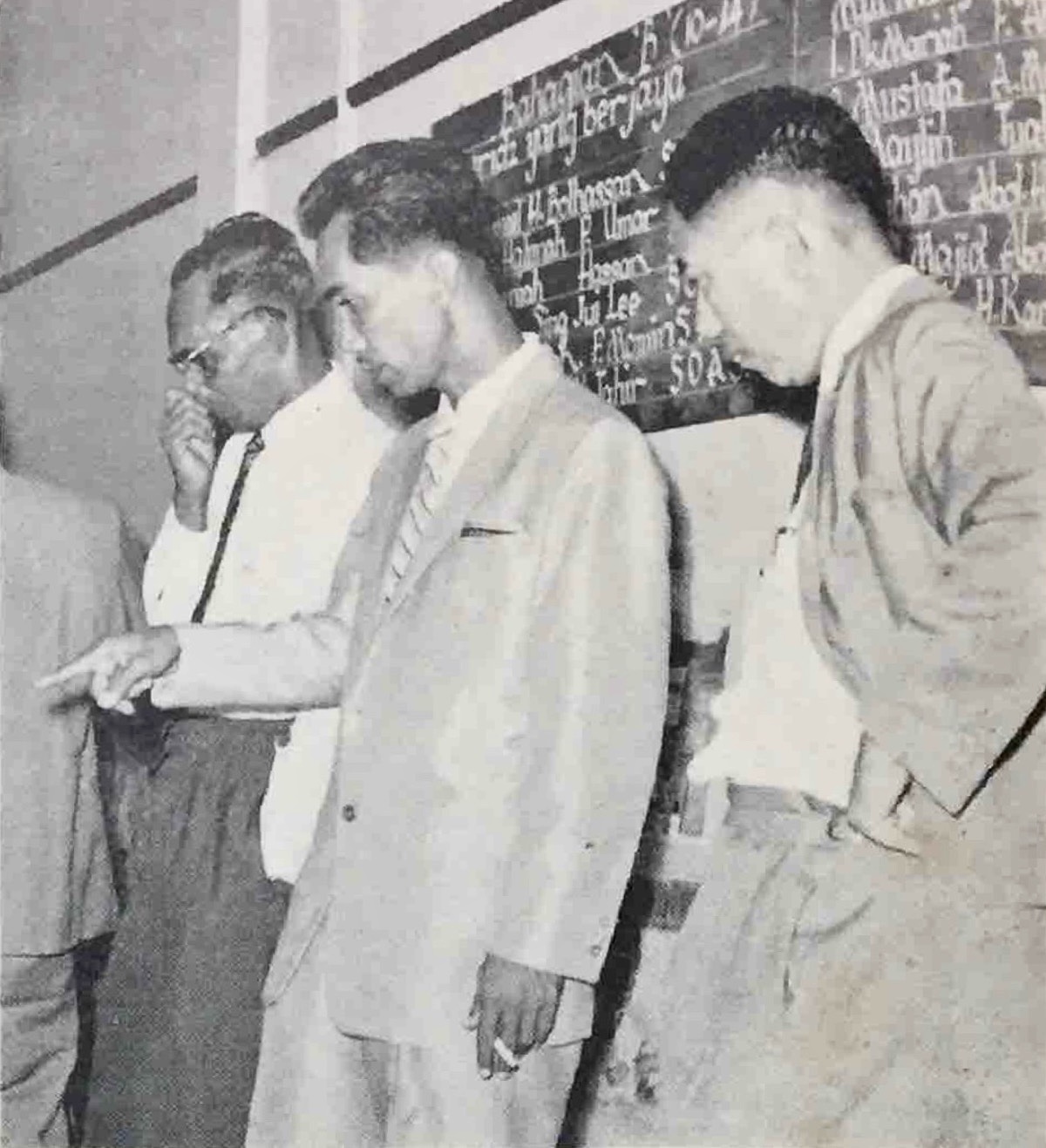
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、1964年1月18日にブルネイの国務長官に就任した。これにより、彼はイブラヒム・モハマド・ジャファル以来、同職に就任した初の生粋のブルネイ・マレー人となった。この時期には、ブルネイ産天然ガスの対日輸出が始まっている。1965年4月19日、彼はツトン地区評議会会議の開会を主宰し、そのメンバーに対し、ブルネイの将来にとって政治的進歩と安定が重要であることを強調しながら、法的および憲法上の範囲内で権限を行使するよう助言した。健康上の懸念から、首席大臣マルサルは10月1日に休暇を取り、彼は一時的に首席大臣代理に任命された。
1966年、彼はブルネイのリンバン領有権主張の取り組みに関与し、ブルネイ政府はイギリス政府とマレーシアにこの問題に関する書簡を送った。イギリスは主張を認め、ペンギラン・ムハンマド・ユスフにマレーシアがこの問題を検討していると伝えたが、その後の進展はなかった。同年、彼とペンギラン・アナク・モハマド・アラムは、4月10日にクアラルンプールで行われたヤン・ディ・ペルトゥアン・アゴン、トゥアンク・イスマイル・ナシルディン・シャーの戴冠式でブルネイのスルタンを代表した。12月には、国務長官としての短い任期を終えた。1967年3月27日、彼はブルネイ・タウンにあるブルネイ宗教省のマドラサ(イスラム学校)の建物の開会式を主宰した。
3.2. ブルネイ首相
3.2.1. 任命と在任期間

1967年6月1日、当時の首席大臣がスルタンから長期休暇を与えられ、それが引退まで続いたため、ペンギラン・ムハンマド・ユスフは再び首席大臣代理を務め、タイブ・ブサルが国務長官代理となった。1968年11月4日、マルサル・マウンの引退後、彼は首席大臣に就任した。彼の首相在任中には、国王オマール・アリ・サイフディン3世の退位とハサナル・ボルキアの即位が行われている。彼は1973年12月に首席大臣としての任期を終え、政府を引退した。
3.2.2. 主要な行政・政策貢献
1967年7月、彼はボルネオ3地域の進展に喜びを表明し、13年間で直面した課題と変化を強調した。サラワクとサバはマレーシアに加わったが、ブルネイは独立を維持することを選択した。彼はまた、9月16日にカンポン・ムラウト、カンポン・タンジョン・ナンカ、カンポン・ベバティックを結ぶ新しい地方道路の開通式で、国民に対し、食料生産を増やし生活水準を向上させるために地方の土地を農業用に開発するよう促し、その重要性を強調した。
1967年10月5日のスルタン・ハサナル・ボルキアの即位式では、ペンギラン・ムハンマド・ユスフは政府高官と国民を代表して揺るぎない忠誠を誓い、その声は感情で震えた。彼はスルタンが父親の例に倣ってブルネイを統治すると確信を表明した。1967年12月11日、彼は立法評議会開会中のスルタンの演説を一部の代表者が誤解しようとしたことに遺憾の意を表明した。
1968年1月8日、ペンギラン・ムハンマド・ユスフはラジオ・ブルネイでスルタン・ハサナル・ボルキアの戴冠式の日程を発表し、それを国家と国民に繁栄をもたらす伝統的な式典であると述べた。
1970年10月4日、彼は数千人が出席した式典で、ブルネイ・タウンをバンダルスリブガワンに改名することを公式に発表し、新スルタンの指導の下でのブルネイの発展における重要な節目となった。1970年10月23日、彼はセリアのトゥグ・チェンデラマタの基礎石を据え、ブライト地区の住民に、ブルネイの発展に対するスルタン・オマール・アリ・サイフディン3世の貢献を記念して感謝の意を表した。首相として、彼は民生安定と国民生活改善に尽力した。1972年7月15日、ペンギラン・アブドゥル・モミンが首席大臣代理に任命され、一時的にペンギラン・ムハンマド・ユスフの職務を引き継いだ。
3.3. 外交官としての経歴
3.3.1. マレーシア高等弁務官
彼は1995年11月17日に駐マレーシア高等弁務官に任命され、2001年までその職を務めた。
3.3.2. 駐日大使
彼は2001年9月から2002年9月まで駐日大使を務め、日本とブルネイの関係発展に貢献した。
3.4. 立法評議会議員
引退後、ペンギラン・ムハンマド・ユスフはいくつかの要職を歴任し、1974年にはアダット・イスティアダット評議会のメンバーを、1989年2月にはブルネイ枢密院のメンバーを務めた。また、1989年から2000年までブルネイ・プレス社の取締役を、1994年から2000年6月までバイドゥリ銀行およびバイドゥリ証券の取締役を務めた。1992年には、ブルネイ憲法の見直しと改正案の作成を担当する委員会に任命された。
彼は2004年9月6日に立法評議会(LegCo)議員に任命された。2011年3月14日、彼は意思決定における慎重な判断の重要性を強調し、立法評議会の同僚たちの知恵を称賛した。ブルネイ立法評議会議長のイサ・イブラヒムは、彼を「議会の父」であり、ブルネイの歴史の生き証人であると評価した。2013年3月26日、彼はブルネイの若者のエンパワーメントに関する懸念を提起し、若者育成を目的とした様々な政府の取り組みについての議論につながった。彼は2016年に亡くなるまでその職を務めた。
4. 文学活動
4.1. ペンネームと代表作
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは1930年代に執筆活動を開始し、「トゥナス・ネガラ」「セクナル・ハヤット」「ユラ・ハリム」など様々なペンネームを使用した。彼の作品は詩、短編小説、エッセイなど多岐にわたる。彼は特に1951年に出版された『Mahkota Berdarahマレー語』で知られており、これはブルネイにおける現代小説の始まりを告げ、マレーの伝統に根ざした同国の文学シーンの発展に貢献した。彼の『Sekayu Tiga Bangsiマレー語』(1965年)は、ブルネイ初の出版された詩集であり、ブルネイ初の小説でもあった。
4.2. 文学への貢献と評価
彼の注目すべき作品には、『Antologi Sajak bersama Puisi Hidayat IIマレー語』(1976年)、『Antologi Sajak bersama Pakatanマレー語』(1976年)、『Antologi Puisi bersama Hari Depanマレー語』(1980年)、『Antologi Puisi bersama Bunga Rampai Sastera Melayu Bruneiマレー語』(1984年)、『Antologi Sastera ASEAN, Puisi Moden Brunei Darussalamマレー語』(1994年)がある。長年にわたり、彼は数多くの書籍を執筆し、その多くがブルネイの文学界を形成する上で重要な役割を果たした。
5. 称号、スタイル、および栄誉
5.1. 王室称号とスタイル

1968年1月12日、ペンギラン・ムハンマド・ユスフはスルタン・ハサナル・ボルキアからチェテリアの称号である「ペンギラン・ジャヤ・ネガラ」(Pengiran Jaya Negaraペンギラン・ジャヤ・ネガラマレー語)を授与された。その後、1969年5月16日には「ペンギラン・セティア・ネガラ」(Pengiran Setia Negaraペンギラン・セティア・ネガラマレー語)の称号に昇格した。これらの称号にはそれぞれ「ヤン・アマッ・ムリア」(Yang Amat Muliaヤン・アマッ・ムリアマレー語)の敬称が伴う。
5.2. 国内の栄誉と賞
彼は以下の賞を授与されている。
| 年 | 賞の名称 |
|---|---|
| 1987 | ASEAN賞 |
| 1993 | 東南アジア文学賞 |
| 1996 | ブルネイ・ダルサラーム大学名誉博士号 |
| 2006年8月1日 | Pemimpin Belia Berjasaマレー語 |
| 2008年12月28日 | Tokoh Jasawan Ugama Negara Brunei Darussalamマレー語 |
| 不明 | スルタン・ハジ・オマール・アリ・サイフディン教育賞 |
| 不明 | ブルネイ宗教勲功サービス賞 |
彼は以下の勲章を授与されている。
| 年 | 勲章の名称 | 略称・等級 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1968 | ライラ・ウタマ王室勲章 | DK | ダトー・ライラ・ウタマ |
| 1963年9月23日 | ブルネイ王冠勲章 | SPMB (一等) | ダトー・セリ・パドゥカ |
| 1958年9月23日 | ブルネイ王冠勲章 | SMB (三等) | |
| 1960年11月24日 | ブルネイ国家忠誠勲章 | DSNB (二等) | ダトー・セティア |
| 1962 | オマール・アリ・サイフディン・メダル | POAS | |
| 1970年7月15日 | ハサナル・ボルキア・スルタン・メダル | PHBS (一等) | |
| 1959年9月23日 | 功労勲章 | PJK | |
| 1959年9月23日 | 長期勤務勲章 | PKL | |
| 2008 | Pingat Bakti Laila Ikhlasマレー語 | PBLI | |
| 1968 | 戴冠式メダル | ||
| 1963 | 戦役メダル |
5.3. 外国の栄誉と賞

- カナダ:
- バンクーバー国際アカデミー名誉博士号(1960年)
- 日本:
- 勲一等旭日大綬章(1985年)
- 広島大学名誉博士号(2013年)
- イギリス:
- 大英帝国勲章コマンダー(CBE; 1969年)
- アメリカ合衆国:
- 南インディアナ大学名誉博士号(2002年)
6. 私生活
6.1. 家族
ペンギラン・ムハンマド・ユスフはダティン・ハジャ・サルマ・ビンティ・モハマド・ユソフと結婚し、7人の息子と4人の娘をもうけた。彼らの子供には、ペンギラン・ユラ・ハリム、ペンギラン・ユラ・ケステリア、ペンギラン・ユラ・ライラ、ペンギラン・ユラ・ペルカサ(ペンギラン・アナク・ハジャ・マストゥラと結婚)、ペンギラン・ユラ・ドゥパ・コダダット、ペンギラン・ユラ・ムハンマド・アバイ、ペンギラン・ユラ・アライティ(アダナン・ブンターと結婚)、ペンギラン・ユラ・ムリアティ、ペンギラン・ユラ・ヌルルハヤティがいる。
6.2. 親族
彼はブルネイ博物館の初代館長であるペンギラン・シャリフディンの叔父にあたる。また、異母兄弟にペンギラン・ジャヤ・ネガラ・ペンギラン・ハジ・アブドゥル・ラフマンがおり、ペンギラン・アナク・イステリ・ペンギラン・ノルハヤティの叔父でもある。
7. 遺産
7.1. 彼にちなんで命名された場所
- ペンギラン・セティア・ネガラ・ペンギラン・モハマド・ユソフ小学校 - セリアにある彼の名を冠した学校。
- デワン・ペンギラン・セティア・ネガラ - ブラカスの情報局本部にあるホール。
- ジャラン・セティア・ネガラ - クアラ・ブライトとパンダンを結ぶ道路。
7.2. 歴史的・社会的影響
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、ブルネイの統治、行政、文化、文学の発展に生涯にわたる多大な貢献をした。特に、憲法制定への関与、国歌の作詞、そして首相としての国民生活向上への取り組みは、ブルネイの近代国家形成において重要な役割を果たした。また、広島での被爆者としての経験は、平和への彼の貢献を象徴するものであり、国際的な交流においてもその存在感を示した。彼は「議会の長老」として、晩年まで国の発展に関する議論に貢献し、ブルネイの歴史における重要な人物として記憶されている。
8. 死去
ペンギラン・ムハンマド・ユスフは、2016年4月11日午前9時37分、ツトン地区カンポン・センカライにある自宅「テラタク・ユラ」で、92歳で永眠した。スルタン・ハサナル・ボルキアは最後の敬意を表し、ブルネイ国務宗務庁長官のアブドゥル・アジズ・ジュネドが導く集団礼拝に参加した。彼はセンカライ・ムスリム墓地に埋葬された。彼の息子であるペンギラン・ハジ・ユラ・ハリムは、日本の外務大臣岸田文雄からブルネイの日本大使館を通じて弔慰状を受け取った。