1. 概要
二代目市川猿翁(にだいめ いちかわ えんおう、本名:喜熨斗 政彦(きのし まさひこ))は、1939年12月9日に東京府で生まれ、2023年9月13日に東京都内で逝去した日本の著名な歌舞伎役者、俳優、演出家である。澤瀉屋(おもだかや)の屋号を持ち、俳名に華果(かか)がある。生前は「三代目市川猿之助」として49年間にわたり活動し、その革新的な舞台表現で知られた。彼は、歌舞伎の伝統的な規範に挑戦し、エンターテインメント性を高めることで大衆的魅力を広げることに多大な貢献をした人物として高く評価されている。

特に、舞台装置や特殊効果を駆使する「ケレン」技法の復活・大衆化に尽力し、観客の頭上を飛行する「宙乗り」の公演を5000回以上も成功させ、ギネス世界記録に登録された。「スーパー歌舞伎」を創始し、哲学者の梅原猛らとの協業を通じて、古典芸能としての歌舞伎に現代的な息吹を吹き込んだ。また、『伊達の十役』のような忘れ去られた伝統演目を復活させ、「早替り」の技法を駆使して一人で多数の役を演じ分けるなど、伝統の継承と革新を両立させた。
私生活では、女優の浜木綿子との結婚と離婚、そして長年の同棲を経て女優の藤間紫との再婚という複雑な人生を送り、長男である俳優の香川照之(九代目市川中車)との関係も、初期の疎遠から晩年の和解へと変化した。晩年は健康問題に見舞われ、2003年にはパーキンソン症候群を発症し、舞台活動が減少した。2012年には隠居名である二代目市川猿翁を襲名し、甥である二代目市川亀治郎に三代目市川猿之助の名跡を譲った。2023年9月、不整脈のため83歳で死去。死没日付で従四位に叙され、旭日中綬章が贈られた。彼の功績は文化功労者顕彰など多数の賞と栄典で認められ、歌舞伎界のみならず日本の舞台芸術全体に大きな遺産を残した。身長約165 cm、体重約68 kg、血液型はA型であった。
2. 生涯と背景
二代目市川猿翁は、日本の歌舞伎界に多大な影響を与えた革新的な俳優であり演出家であった。その生涯は、幼少期の舞台デビューから晩年の引退に至るまで、歌舞伎に対する情熱と挑戦に満ちていた。
2.1. 出生と幼少期
1939年(昭和14年)12月9日、東京都に、三代目市川段四郎の長男として生まれた。母は映画女優の高杉早苗である。本名は喜熨斗 政彦(きのし まさひこ)。
1947年(昭和22年)1月、わずか8歳で東京劇場において『二人三番叟』の附千歳(つけじざい)の役で初舞台を踏み、「三代目市川團子」を襲名した。この頃、二代目松本白鸚(当時の六代目市川染五郎)や二代目中村吉右衛門(当時の中村萬之助)と共に「十代歌舞伎」と呼ばれる人気を博し、将来を嘱望される存在となった。
2.2. 学歴
学業においては、千代田区立番町小学校を卒業後、慶應義塾中等部、慶應義塾高等学校へと進学した。1962年(昭和37年)には慶應義塾大学文学部国文学科を卒業している。
2.3. 襲名と初期のキャリア
大学卒業後の1963年(昭和38年)5月、歌舞伎座での『義経千本桜』の忠信(吉野山)や『黒塚』の鬼女などの役を演じ、正式に「三代目市川猿之助」を襲名した。しかし、襲名後間もなく、同年6月には祖父である初代市川猿翁(二代目市川猿之助)を、同年11月には父である三代目市川段四郎を相次いで亡くすという悲運に見舞われた。
これにより後ろ盾を失い、「梨園の孤児」と呼ばれる状況に置かれたが、彼は他門の庇護を受けることを潔しとせず、自らの力で道を切り開くことを決意した。祖父から受け継いだ革新的な芸術志向と、関西歌舞伎の伝統的なケレンの技法を結びつけることで、歌舞伎界に新たな風を吹き込むという自身の芸術的方向性を確立した。
3. 歌舞伎におけるキャリアと芸術的革新
二代目市川猿翁は、歌舞伎役者としてのみならず、演出家としてもその才能を如何なく発揮し、数々の革新的な活動を通じて歌舞伎界に大きな足跡を残した。彼の取り組みは、伝統芸能としての歌舞伎に新たな可能性をもたらした。
3.1. ケレンと宙乗り技法の革新
猿翁は、明治以降に邪道として扱われ、顧みられなかった「ケレン」(舞台トリック)の演出を積極的に復活させ、大衆化に貢献した。特に、観客の頭上を空中移動する「宙乗り」の技法は、彼の代名詞ともいえるものとなった。
1968年(昭和43年)、『義経千本桜』の「四ノ切」における狐忠信の役で宙乗りを初披露して以来、その回数は飛躍的に増加した。2000年には、関羽の役で5000回目の宙乗りを達成し、この功績はギネス世界記録に登録されている。
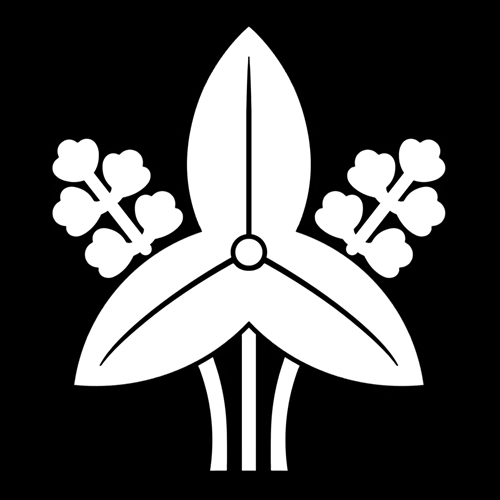
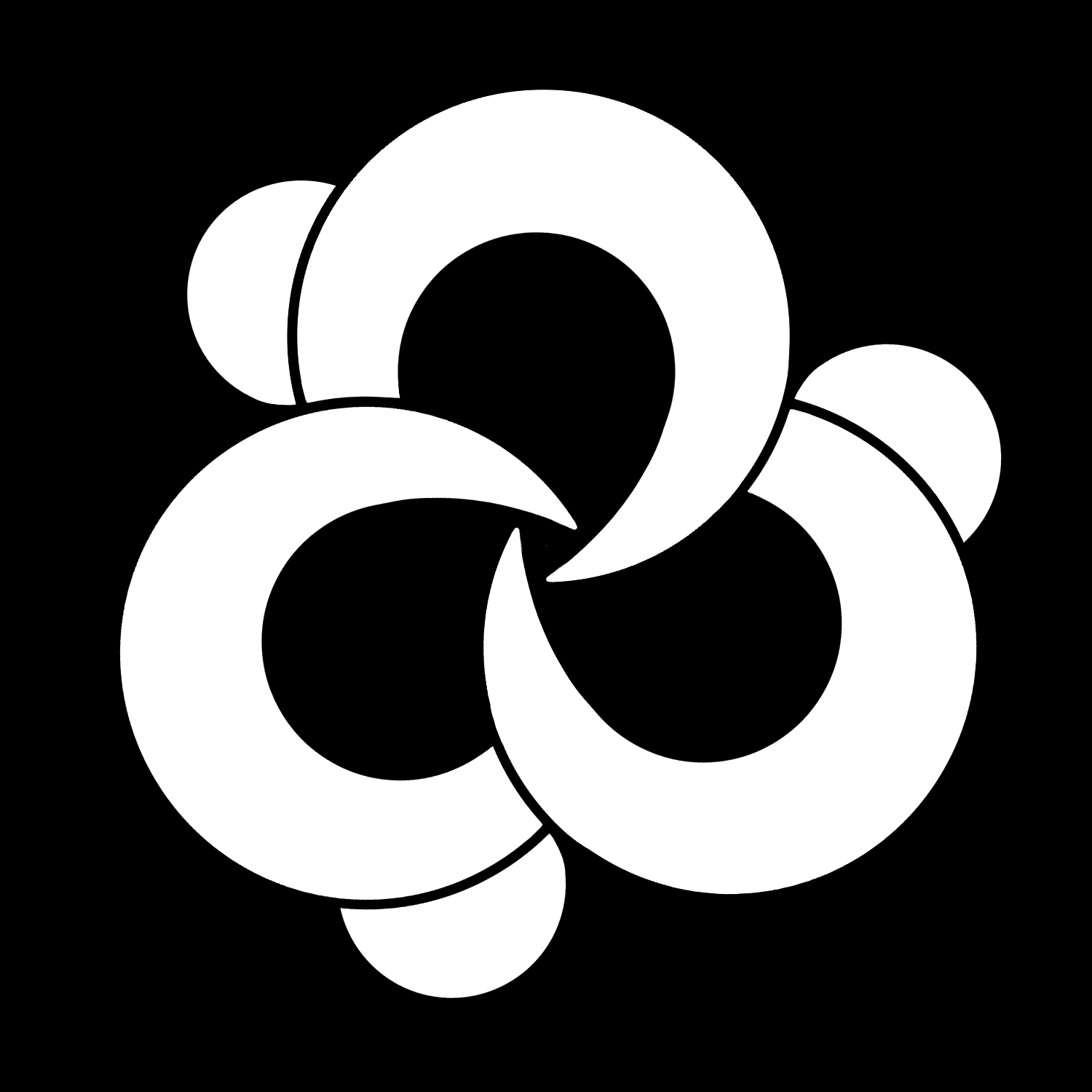
彼の革新的な試みは当初、保守的な歌舞伎役者や劇評家からは「喜熨斗サーカス」と揶揄されるなど、厳しい批判に晒された。十一代目市川團十郎の実弟で、市川宗家の重鎮であった二代目尾上松緑は、猿翁の歌舞伎を本名の「喜熨斗」(きのし)に引っ掛けてそう評した。しかし、猿翁はそうした逆境を乗り越え、宙乗りはその後、七代目尾上菊五郎、十二代目市川團十郎、九代目松本幸四郎、十八代目中村勘三郎など、多くの後進の歌舞伎役者にも取り入れられる主流の演出技法となった。
1984年(昭和59年)に中日劇場で上演された「當世流小栗判官」では、通常は花道の上を飛ぶ宙乗りを、日本の歌舞伎として初めて客席を対角線上に横断する形で行い、大きな話題を呼んだ。このようにエンターテインメント性に富む「猿之助歌舞伎」は、観客からは高い支持を集めた。
3.2. スーパー歌舞伎の創出
猿翁は、古典芸能と化した歌舞伎に新たな息吹を吹き込むため、1986年(昭和61年)に「スーパー歌舞伎」を創設した。これは、SF、ファンタジー、歴史、神話など多様な題材を、現代的な感覚と最新の舞台技術で表現する、従来の歌舞伎の枠を超えた新しい形態の歌舞伎であった。
哲学者の梅原猛に脚本を依頼した『ヤマトタケル』を新橋演舞場で上演し、その幕開けを飾った。スーパー歌舞伎は、新しい観客層を開拓し、歌舞伎の現代化に大きな影響を与えた。猿翁が病で倒れて以降も、その門弟筋である三代目市川右團次(初代市川右近)、二代目市川笑也、二代目市川春猿(現・河合雪之丞)らによって継承され、進化を続けている。
3.3. 伝統演目の復活と再創造
猿翁は、革新的な活動の一方で、忘れ去られた伝統的な歌舞伎演目の復活と再創造にも尽力した。特に有名なのが『伊達の十役』で、この演目では、彼は一人で十役を演じ分け、その過程で「早替り」(迅速な衣装替え)の技法を革新的に使用した。彼の精力的な活動は、古劇の復活から古典の再創造まで多岐にわたり、舞台芸術に新たな領域を切り開いた。彼の代表的な当たり役としては、『義経千本櫻』の狐忠信、『慙紅葉汗顔見勢』(伊達の十役)における十役早替り、『スーパー歌舞伎 ヤマトタケル』のヤマトタケル、『オグリ』の小栗判官などが挙げられる。自身の当たり役を集めた「猿之助十八番」を「猿之助四十八撰」として2010年(平成22年)3月にまとめた。
3.4. 他芸術分野での演出活動
歌舞伎の枠を超え、他の芸術形式にも積極的に進出した。1992年(平成4年)には、バイエルン国立歌劇場によるリヒャルト・シュトラウスのオペラ『影のない女』の日本来日公演(翌年には本拠地プレミエ)で演出を担当した。2002年(平成14年)には、ニコライ・リムスキー=コルサコフのオペラ『金鶏』の演出も手掛けた。
また、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)では副学長を務め、学内の劇場である春秋座の芸術監督としても、病に倒れるまで指導にあたっていた。
4. 私生活と人間関係
二代目市川猿翁の私生活は、その舞台キャリアと同様に波瀾に富んでいた。特に二度の結婚と、長男である香川照之(九代目市川中車)との複雑な関係は、公に議論される側面であった。
4.1. 結婚と家族関係
猿翁には二度の結婚歴がある。最初の妻は、元宝塚歌劇団雪組のトップ娘役で女優の浜木綿子である。二人は1965年(昭和40年)に結婚し、同年12月には長男である香川照之が誕生した。しかし、実質的な夫婦生活は1年数カ月で別居に至り、1968年(昭和43年)に正式に離婚した。長男・照之は浜に引き取られた。
この破局の原因は、女優の藤間紫との不倫であった。藤間紫は猿翁が12歳の時の初恋の相手であったが、彼女は猿翁よりも16歳年上で既婚者であり、子持ちであった。しかもその夫は、猿翁自身の踊りの師匠である六世藤間勘十郎(二世藤間勘祖)であった。一度は諦めて浜木綿子と結婚した猿翁であったが、結局、藤間紫への思いを断ち切ることができず、長男が1歳を迎える頃には家庭を捨て、藤間紫と駆け落ち同然の同棲生活を始めた。この同棲は35年にも及び、1985年(昭和60年)に藤間紫の離婚が成立すると、2000年(平成12年)2月28日に二人は正式に結婚した。その後、藤間紫が創始した紫派藤間流の二代目家元として、自身も「二代目藤間紫」を名乗った。しかし、その後は不遇が続き、2003年には猿翁が脳梗塞を発症、2009年には藤間紫が肝不全のため死去した。
藤間紫の死後、2010年(平成22年)3月頃から元博多座の女性スタッフと同棲を開始し、彼女は猿翁の身の回りの世話から一門の人事まで多岐にわたるサポートを行ったとされる。
4.2. 息子・香川照之との関係
長男である香川照之(のちの九代目市川中車)との関係は、長年にわたり複雑で緊張を伴うものであった。猿翁と浜木綿子の離婚後、照之は母に引き取られ、猿翁との間にはほとんど交流がない時期が続いた。
照之は大学卒業後、1989年(平成元年)に俳優としてデビューした。この年、25歳の冬に、照之は思い立って猿翁の公演先へ会いに行った。しかし、猿翁は照之を「大事な公演の前にいきなり訪ねてくるとは、役者としての配慮が足りません」と叱責し、さらに「即ち、私は家庭と訣別した瞬間から蘇生したのです。だから今の僕とあなたとは何の関わりもない。あなたは息子ではありません。したがって僕はあなたの父でもない」「あなたとは今後、二度と会う事はありません」と完全に拒絶し、突き放したという。この厳しい言葉の真意について、猿翁は隠居名「猿翁」襲名後に放送されたNHKスペシャルの中で、「生きるも死ぬも身一つで、僕はあえて一人でやってきました。だから、照之も役者の道を貫きたいと思うなら私の事を父と思うな、何ものにも耐えうる独立自尊の精神でいきなさいと。僕としてはごく当然のことを言ったつもりなのですよ」と述懐している。これは、息子に自立の精神を促すための厳しさであったと説明された。
その後、藤間紫の尽力によって、猿翁と照之の和解が進められた。2009年(平成21年)の藤間紫の葬儀には、照之も親族として参列した。さらに、2011年(平成23年)9月27日に行われた、甥である二代目市川亀治郎の四代目市川猿之助襲名、自身の二代目市川猿翁襲名、そして照之とその息子である政明の歌舞伎界入りを発表する記者会見の場では、猿翁は涙ながらに「浜さん、ありがとう。恩讐の彼方に、ありがとう」と、前妻である浜木綿子に感謝の言葉を述べた。その後、香川照之の歌舞伎初舞台のリハーサル中に、浜木綿子と猿翁が離婚以来約45年ぶりに言葉を交わす様子が報じられている。この会見後、香川は猿翁宅近くのマンションに居を移し、稽古は香川が猿翁宅に通って行われた。
5. 晩年、引退、そして逝去
二代目市川猿翁の晩年は、健康問題との闘いと、長年の舞台活動からの引退、そして名跡継承という重要な節目によって特徴づけられた。
5.1. 健康問題と活動減少
2003年(平成15年)11月17日、福岡市博多座での自身の演出・出演による『西太后』の公演中に体調不良を訴え、降板した。この際、公には「初期の脳梗塞」と診断されたと発表されたが、実際にはパーキンソン症候群を発症していたことが後に明らかになった。この病気により、彼は俳優として舞台に立つ機会が著しく減少した。しかし、スーパー歌舞伎や自身が復活させた演目の演出面では引き続き活動を続けた。
5.2. 引退と名跡継承
病状が進行する中で、猿翁は2011年(平成23年)9月、甥である二代目市川亀治郎の猿之助襲名会見時に、長男の香川照之と共に8年ぶりに公の場に姿を現した。そして、2012年(平成24年)6月5日に新橋演舞場で開幕した六月大歌舞伎において、祖父である初代猿翁も名乗った隠居名である「二代目市川猿翁」を襲名し、正式に舞台から引退した。これにより、甥の二代目市川亀治郎が「四代目市川猿之助」を襲名し、猿翁の革新的な歌舞伎の精神は次世代へと継承された。
5.3. 最後の活動と逝去
二代目市川猿翁としての最後の舞台出演は、2013年(平成25年)12月に京都南座で行われた「二代目市川猿翁・四代目市川猿之助・九代目市川中車 襲名披露口上」であった。
その後も、2014年(平成26年)2月1日から2月28日まで日本経済新聞朝刊の「私の履歴書」に自身の半生を綴った連載が掲載された。2018年(平成30年)2月27日には、中日劇場における三代目市川右團次、二代目市川笑也、市川弘太郎らの夜の公演のカーテンコールに姿を見せ、「澤瀉屋っ!」という掛け声と拍手喝采に包まれた。
2023年(令和5年)9月13日午前6時55分、不整脈のため東京都内で死去した。83歳没。死没日付をもって従四位に叙され、旭日中綬章が贈られた。
6. 遺産と評価
二代目市川猿翁は、歌舞伎界において多岐にわたる功績を残し、その芸術性や革新性に対して様々な評価がなされている。
6.1. 業績と肯定的評価
猿翁の最大の業績は、歌舞伎という伝統芸能に新たな息吹を吹き込み、現代の観客にも広く受け入れられるエンターテインメント性を確立したことにある。彼が提唱し、実践した「スーパー歌舞伎」は、従来の古典歌舞伎の枠を超えた壮大なスケールと物語性で、新しい歌舞伎ファンを多く獲得した。特に「宙乗り」や「早替り」などのケレン技法を積極的に取り入れ、これを芸術として昇華させたことは、歌舞伎の可能性を大きく広げた。
初期には保守層からの批判に晒されたものの、彼の先駆的な精神と、見応えのある舞台は最終的に広範な認知と支持を獲得し、多くの歌舞伎俳優がその演出を取り入れるようになった。これにより、歌舞伎はより親しみやすい芸術となり、その魅力を現代に伝え続ける上で極めて重要な役割を果たした。彼の功績は高く評価され、2010年(平成22年)には文化功労者に顕彰されている。
6.2. 批判と論争
猿翁の革新的な試みは、初期には伝統主義者たちから強い批判を受けた。特に、彼が積極的に取り入れた「ケレン」は、一部の歌舞伎愛好家からは「客受けを狙った邪道」と見なされ、「喜熨斗サーカス」と揶揄された。この批判は、歌舞伎の本質的な芸術性よりも視覚的な派手さを優先しているという見方から生じたものである。しかし、猿翁はこうした批判にも屈することなく、自身の芸術を追求し続けた結果、これらの技法を歌舞伎の主流に定着させることに成功した。
6.3. 受賞と栄典
猿翁は、その長いキャリアを通じて、数々の賞と栄典を受け、彼の芸術的貢献が国内外で広く認められた。
- 1965年:第11回テアトロン賞
- 1969年:名古屋ペンクラブ賞
- 1976年:芸術選奨新人賞
- 1980年:松尾芸能賞優秀賞
- 1981年:ボローニャ市文化功労章
- 1984年:毎日芸術賞
- 1985年:日本文化デザイン賞
- 1987年:フランス芸術文化勲章オフィシエ(2等)
- 1988年:都民文化栄誉章
- 1990年:芸術選奨文部大臣賞
- 1996年:読売演劇大賞優秀男優賞、菊池寛賞
- 2000年:紫綬褒章
- 2010年:文化功労者
- 2013年:第22回モンブラン国際文化賞
- 2023年:従四位、旭日中綬章(死没日付)
7. 作品
二代目市川猿翁は、歌舞伎の舞台に加えて、映画やテレビドラマにも出演し、また歌舞伎に関する著作も多数発表している。
7.1. 主な舞台出演
歌舞伎における彼の代表的な役柄、いわゆる「当たり役」は以下の通りである。
- 『義経千本櫻』の狐忠信
- 『慙紅葉汗顔見勢』(伊達の十役)の十役早替り
- 『ヤマトタケル』のヤマトタケル
- 『オグリ』の小栗判官
7.2. その他の媒体出演
- 映画
- 『大忠臣蔵』(松竹、1957年) - 大石主税 役
- 『楢山節考』(松竹大船、1958年) - けさ吉 役
- 『大坂城物語』(東宝、1961年) - 霧隠才蔵 役
- 『忠臣蔵 花の巻・雪の巻』(東宝、1962年) - 大石主税 役
- テレビドラマ
- シオノギテレビ劇場『若き日の信長』(フジテレビ、1964年)
- その他
- 『ゆく年くる年』1984-85年版(テレビ東京制作) - 総合司会
7.3. 著書と出版物
歌舞伎に対する彼の思想や芸術哲学は、彼自身が執筆した著書や評伝を通じて深く洞察することができる。
- 『演者の目』(朝日新聞社、1976年)
- 『猿之助修羅舞台 - 未来は今日にあり』(大和山出版社、1984年、PHP文庫、1994年)
- 『猿之助の歌舞伎講座』(新潮社「とんぼの本」、1984年)
- 『市川猿之助 歌舞伎の時空』(PARCO出版局、1986年) - 写真:稲越功一
- 新版『市川猿之助』(講談社、1993年)
- 横内謙介と共著『夢みるちから スーパー歌舞伎という未来』(春秋社、2001年)
- 『スーパー歌舞伎 ものづくりノート』(集英社新書、2003年)
評伝
- 『市川猿之助の仕事』(演劇出版社、1995年)
- 光森忠勝『市川猿之助 傾き一代』(新潮社、2010年)
8. 外部リンク
- [https://meikandb.kabuki.ne.jp/actor/30/ 歌舞伎俳優名鑑 現在の俳優篇 / 市川猿翁(二代目) - (歌舞伎 on the web)]
- [https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/p/index.html?id=D0009072068_00000 NHK人物録 市川猿翁(二代目)]