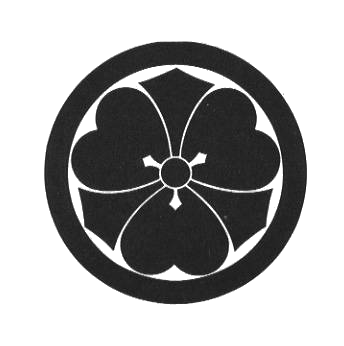1. 生涯
酒井忠利の生涯は、徳川家康とその子徳川秀忠に仕え、数々の戦役で功績を挙げ、やがて大名として領地を広げ、江戸幕府の要職である老中まで昇り詰めた軌跡である。
1.1. 出生と背景
酒井忠利は永禄2年(1559年)、酒井正親の三男として生まれた。母は石川清兼の娘である妙玄尼。彼は徳川家康の遠縁にあたる家柄であり、酒井氏の庶流である雅楽頭酒井家忠利系の初代当主を務めた。
1.2. 徳川家での活動
忠利は兄の酒井重忠と共に徳川家康に仕えた。天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは、その武功が大いに評価された。天正18年(1590年)、家康が関東に移封された際、忠利は武蔵国川越に3000石の所領を与えられた。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠に供奉し、その行動を共にした。慶長19年(1614年)から始まった大坂の陣(大坂冬の陣・大坂夏の陣)では、江戸城の留守居役という重要な役割を担った。
1.3. 大名としての統治と昇進
関ヶ原の戦い後、忠利は徳川家康から7000石を加増され、合計1万石の大名として駿河田中藩に移された。これは慶長6年(1601年)のことである。慶長14年(1609年)には、さらに1万石が加増され、合計2万石となり、所領は武蔵川越藩に移され、初代藩主となった。その後も忠利は幕府の要職を歴任し、石高はしばしば加増され、最終的には3万7000石を領する大名へと昇進した。彼はまた、江戸幕府の老中も務めた。川越藩主としては、その後酒井忠勝が後を継いだ。
2. 系譜
- 父:酒井正親
- 母:妙玄尼(石川清兼の娘)
- 正室:宝鏡院(鈴木重直の娘)
- 子女:
- 長男:酒井忠勝(1587年 - 1662年)
- 次男:酒井忠吉(1589年 - 1663年)
- 男子(生母不詳):酒井忠重、酒井忠久、酒井忠末、酒井忠次
- 女子:高木正綱室
- 女子:河合宗利室
- 女子:三浦好正室
3. 死去
酒井忠利は寛永4年11月14日(1627年12月21日)に死去した。享年69であった。
4. 評価と遺産
酒井忠利は、徳川家康の幼少期からの家臣として、またその子徳川秀忠を支える重臣として、徳川氏の天下統一とその後の江戸幕府の基盤確立に大きく貢献した。小牧・長久手の戦いや関ヶ原の戦いといった主要な戦役での功績は、彼が武将として優れた能力を持っていたことを示している。また、大坂の陣における江戸城の留守居役は、単なる軍事力だけでなく、幕府の中枢を担う者としての信頼と重要性を示している。駿河田中藩から武蔵川越藩へと転封し、石高を着実に増やしていった過程は、彼が大名としての統治能力と、幕府内での政治的影響力を確立していったことを物語る。最終的に老中の地位に就いたことは、彼が江戸幕府の初期において、最も信頼され、重要な役割を担った人物の一人であったことを裏付けている。彼の死後も、その家系は雅楽頭酒井家として存続し、子孫は幕府の重職を代々務め、酒井氏の発展に貢献した。彼の功績は、徳川幕府の安定と発展に不可欠なものであったと言える。