1. 概要
アルベルト・ヒナステラは、20世紀のアルゼンチンを代表するクラシック音楽の作曲家であり、アメリカ大陸における最も重要な作曲家の一人とされています。彼の音楽は、アルゼンチンの豊かな民俗音楽やガウチョの伝統、さらには先コロンブス期の文化から深くインスピレーションを得ており、それらを独自の現代的な音楽言語と融合させることで、アルゼンチンの文化的アイデンティティを音楽的に表現しました。生涯にわたる彼の創作活動は「客観的ナショナリズム」「主観的ナショナリズム」「新表現主義」という三つの時期に分類され、それぞれ異なる様式的な進化を遂げながらも、常に力強いリズムと色彩豊かな響きを特徴としています。オペラ、バレエ、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、ピアノ曲、声楽曲、合唱曲、オルガン曲、付随音楽、映画音楽など多岐にわたるジャンルで作品を残し、アストル・ピアソラをはじめとする多くの後進の音楽家たちに影響を与えました。特に、彼の作品が時の政府によって演奏禁止とされた事例は、芸術が社会や政治とどのように関わるかを示す重要な側面であり、彼の音楽が単なる芸術作品に留まらず、社会的な言説の一部であったことを示しています。
2. 略歴
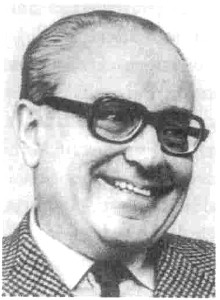
2.1. 出生と幼少期
アルベルト・エバリスト・ヒナステラ(Alberto Evaristo Ginasteraカタルーニャ語)は、1916年4月11日にブエノスアイレスで生まれました。彼の父親はスペイン人、母親はイタリア人でした。晩年、彼は自身の姓をスペイン語の「ヒナステラ」(xinaˈsteɾaスペイン語)ではなく、カタルーニャ語やイタリア語の「ジナステラ」(dʒinaˈsteːraカタルーニャ語)のように、英語の「George」の「G」のような柔らかい発音で呼ぶことを好んでいました。
2.2. 教育と初期のキャリア
ヒナステラはブエノスアイレスのウィリアムズ音楽院で学び、1938年に卒業しました。若い教授として、彼はサン・マルティン将軍士官学校で教鞭を執りました。1945年から1947年にかけてアメリカ合衆国を訪れ、タングルウッド音楽センターでアーロン・コープランドに師事しました。その後、ブエノスアイレスに戻り、そこで作曲家協会を共同で設立しました。彼は数々の教職を務め、1949年には現在ヒラルド・ヒラルディ音楽院として知られる音楽・舞台芸術院を設立しました。

2.3. 弟子たち
ヒナステラの著名な弟子には、アストル・ピアソラ(1941年に師事)、アルシデス・ランサ、ホルヘ・アントゥネス、ワルド・デ・ロス・リオス、ジャクリーン・ノヴァ、ブラス・アテオルチュア、ラファエル・アポンテ=レデなどがいます。
2.4. 後期と死
1968年にヒナステラは再びアメリカ合衆国へ移住し、1970年にはヨーロッパへと居を移しました。彼は1983年6月25日にスイスのジュネーヴで67歳で亡くなり、同地の王の墓地に埋葬されました。
3. 音楽様式と時代区分
3.1. 影響とインスピレーション
ヒナステラの作品の多くは、「ガウチョ」の伝統からインスピレーションを得ています。この伝統では、平原の土地を持たない馬乗りであるガウチョがアルゼンチンの象徴とされています。彼の音楽は、アルゼンチンの民俗音楽、ガウチョの伝統、そして先コロンブス期の文化など、多様な要素に深く根ざしています。彼はこれらの要素を、単に引用するだけでなく、自身の音楽言語の中に有機的に統合しました。例えば、1960年に作曲されたドラマティック・ソプラノと53の打楽器のための「魔法のアメリカ大陸に寄せるカンタータ」は、古代の先コロンブス期の伝説に基づいています。この作品の米国西海岸初演は、1963年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校でアンリ・テミアンカとウィリアム・クラフトの指揮のもと、ロサンゼルス・パーカッション・アンサンブルによって行われました。
3.2. 音楽的時期
ヒナステラ自身は、自身の音楽を3つの時期に分類しています。これらの時期は、アルゼンチンの伝統的な音楽要素の利用方法において特徴的な違いが見られます。
- 客観的ナショナリズム(1934年 - 1948年)
- この時期の作品は、アルゼンチンの民俗主題を直接的かつ明確な形で統合していることが多いです。
- 主観的ナショナリズム(1948年 - 1958年)
- この時期には、民俗要素をより抽象的な形で取り入れるようになりますが、作品には依然として明確なアルゼンチンの個性が残されています。
- 新表現主義(1958年 - 1983年)
- 後期には、民俗要素は連続的な技法を用いてより近代的な作風へと進化し、十二音技法や微分音といった現代音楽の技法も用いられるようになります。
3.3. 様式的な進化
ヒナステラは、初期の明快なオスティナート語法を用いた作風から、次第に原始主義的・無調的な傾向へと移行しました。最終的には、十二音技法や微分音といった先進的な作曲技法も取り入れ、その音楽言語は生涯を通じて大きく発展しました。
4. 主要作品
4.1. オペラ
- 『ドン・ロドリーゴ』 Op. 31 (1963年 - 1964年)
- 『ボマルツォ』 Op. 34 (1966年 - 1967年)
- 1972年までアルゼンチンでの上演が禁止されていました。
- 『ベアトリクス・チェンチ』 Op. 38 (1971年)
- パーシー・ビッシュ・シェリーの戯曲『チェンチ家』を基にしています。
4.2. バレエ
- 『パナンビ』 Op. 1 (1935年)
- 『エスタンシア』 Op. 8 (1941年)
4.3. 管弦楽曲
- バレエ『パナンビ』組曲 Op. 1a (1937年)
- バレエ『エスタンシア』からの舞曲集 Op. 8a (1943年)
- 『クリオーリョのファウスト』序曲 Op. 9 (1943年)
- 『オジャンタイ』:3つの交響的楽章 Op. 17 (1947年)
- 『協奏的変奏曲』 Op. 23 (1953年)
- 『パンペアーナ第3番』 Op. 24 (1954年)
- 『弦楽のための協奏曲』 Op. 33 (1965年)
- 『交響的練習曲』 Op. 35 (1967年)
- 『ポポル・ヴフ』 Op. 44 (1975年 - 1983年)
- 作曲家の死により未完に終わりました。
- 『パウ・カザルスによる主題のグロス』弦楽オーケストラ版 Op. 46 (1976年)
- 『パウ・カザルスによる主題のグロス』フルオーケストラ版 Op. 48 (1976年 - 1977年)
- 『ユービラム』 Op. 51 (1979年 - 1980年)
4.4. 協奏曲
- ピアノ
- ピアノ協奏曲第1番 Op. 28 (1961年)
- ピアノ協奏曲第2番 Op. 39 (1972年)
- ヴァイオリン
- ヴァイオリン協奏曲 Op. 30 (1963年)
- チェロ
- チェロ協奏曲第1番 Op. 36 (1968年)
- チェロ協奏曲第2番 Op. 50 (1980年 - 1981年)
- ハープ
- ハープ協奏曲 Op. 25 (1956年 - 1965年)
- 数少ないハープのための協奏曲として知られています。
- ハープ協奏曲 Op. 25 (1956年 - 1965年)
4.5. 室内楽および器楽曲
- 二重奏曲(フルートとオーボエのための) Op. 13 (1945年)
- 『パンペアーナ第1番』(ヴァイオリンとピアノのための) Op. 16 (1947年)
- 弦楽四重奏曲第1番 Op. 20 (1948年)
- 『パンペアーナ第2番』(チェロとピアノのための) Op. 21 (1950年)
- 弦楽四重奏曲第2番 Op. 26 (1958年、1968年改訂)
- ピアノ五重奏曲 Op. 29 (1963年)
- 弦楽四重奏曲第3番(ソプラノと弦楽四重奏のための) Op. 40 (1973年)
- 『プニェーニャ第1番』(フルートのための) Op. 41 (1973年)
- 作曲家の死により未完に終わりました。
- 『プニェーニャ第2番』(チェロのための) Op. 45 (1976年)
- パウル・ザッハーへのオマージュ。
- ギター・ソナタ Op. 47 (1976年、1981年改訂)
- チェロ・ソナタ(チェロとピアノのための) Op. 49 (1979年)
- 4本のトランペットのためのファンファーレ Op. 51a (1980年)
4.6. ピアノ作品
- 『アルゼンチン舞曲集』 Op. 2 (1937年)
- 『3つの小品』 Op. 6 (1940年)
- 『マランボ』 Op. 7 (1940年)
- 「小さな舞曲」(バレエ『エスタンシア』 Op. 8より) (1941年)
- 『12のアメリカ前奏曲』 Op. 12 (1944年)
- 『クレオール舞曲組曲』 Op. 15 (1946年、1956年改訂)
- 『アルゼンチン童謡の主題によるロンド』 Op. 19 (1947年)
- 「我が子アレックスとヘオルヒーナに捧げる」と記されています。
- ピアノ・ソナタ第1番 Op. 22 (1952年)
- ドメニコ・ツィポーリのオルガン・トッカータの編曲 (1970年)
- ピアノ・ソナタ第2番 Op. 53 (1981年)
- ピアノ・ソナタ第3番 Op. 54 (1982年)
- ヒナステラの最後の作品で、単一楽章からなります。
- 『子供たちのためのアルゼンチン舞曲集』 (未完)
- 「モデラート:アレックスのために」
- 「風景:ヘオルヒーナのために」
4.7. 声楽および合唱作品
- 2つの歌曲(声とピアノのための) Op. 3 (1938年)
- 第1曲目の「忘却の木の歌」は、ヒナステラの歌曲の中でも特に知られています。ピアノ曲「ミロンガ」は、作曲家自身がこの歌曲をピアノ独奏用に編曲したものです。
- 『トゥクマンの歌』(声、フルート、ハープ、打楽器、ヴァイオリンのための) Op. 4 (1938年)
- 『詩篇150』 (混声合唱、児童合唱、オーケストラのための) Op. 5 (1938年)
- 『アルゼンチン民謡による5つの歌曲集』(声とピアノのための) Op. 10 (1943年)
- 『ある農園での一日』(声とピアノのための) Op. 11 (1943年)
- 『エレミア預言者の哀歌』 (合唱のための) Op. 14 (1946年)
- 『魔法のアメリカ大陸に寄せるカンタータ』(ドラマティック・ソプラノと打楽器オーケストラのための) Op. 27 (1960年)
- 『ボマルツォ・カンタータ』(独唱、ナレーター、室内オーケストラのための) Op. 32 (1964年)
- オペラ『ボマルツォ』とは全く別の作品です。
- 『ミレナ』(ソプラノとオーケストラのための) Op. 37 (1971年)
- 『セレナータ』(バリトン、チェロ、木管五重奏、打楽器、ハープ、コントラバスのための) Op. 42 (1973年)
- 『グレゴリオ受難曲の群衆』 (独唱、合唱、少年合唱、オーケストラのための) Op. 43 (1975年)
- 『奪われたキスの歌』(声とピアノのための) (作曲年代不明)
4.8. オルガン作品
- 『トッカータ、ヴィラシコとフーガ』 Op. 18 (1947年)
- 『「輝く曙の光」による変奏曲とトッカータ』 Op. 52 (1980年)
- ブージー・アンド・ホークスの社長W.スチュアート・ポープに献呈され、1980年にミネアポリスで開催されたアメリカオルガン奏者協会の全国大会でマリリン・メイソンによって初演されました。
4.9. 付随音楽および映画音楽
- 『ドン・バシリオの不幸せな結婚』 (1940年)
- 『不満なドニャ・クロリンダ』 (1941年)
- 『マランボ』 (1942年)
- 『アメリカのバラ』 (1945年)
- 『古き種子』 (1947年)
- 『自由の誕生』 (1949年)
- 『橋』 (1950年)
- 『ファクンド、平原の虎』 (1952年)
- 『クリオーリョの馬』 (1953年)
- 『あなたの忠実な僕』 (1954年)
- 『ママの夫たち』 (1956年)
- 『女性の謎』 (1956年)
- 『生命の泉』 (1957年)
- 『赤ちゃんをお風呂に入れなければ』 (1958年)
- 『限界』 (1958年)
- 『心の聖母マリアへ』 (1960年)
- 『驚異の乙女』 (1961年)
4.10. 作曲家によって撤回された作品
- 『子供のための小品集』(ピアノのための) (1934年)
- 『プーナの印象』(フルートと弦楽四重奏のための) (1934年)
- 『アルゼンチン協奏曲』(ピアノと管弦楽のための) (1936年)
- 『荷馬車引きが歌う』(合唱のための) (1937年)
- ソナチネ(ハープのための) (1938年)
- 交響曲第1番「ポルテーニャ」 (1942年)
- 交響曲第2番「エレジー」 (1944年)
5. 影響と評価
5.1. 後続の音楽家やジャンルへの影響
ヒナステラは、多くの著名な音楽家を指導し、彼らのキャリアに大きな影響を与えました。その中でも最も初期の弟子の一人であるアストル・ピアソラは、後にタンゴ音楽に革新をもたらしました。
また、ヒナステラの作品はクラシック音楽の枠を超え、他のジャンルにも影響を与えました。プログレッシブ・ロックバンドのEL&Pは、1973年のアルバム『恐怖の頭脳改革』に、ヒナステラのピアノ協奏曲第1番の第4楽章を元にした「トッカータ」を収録しています。EL&Pのメンバーであるキース・エマーソンが編曲の許可を得るためにヒナステラを訪れた際、ヒナステラはその出来栄えを絶賛したと伝えられています。
5.2. 文化的意義と批評的受容
ヒナステラの音楽は、アルゼンチンの文化的アイデンティティの形成と表現に大きく貢献しました。彼の作品は、アルゼンチンの民俗要素を洗練された現代音楽の語彙と融合させることで、国際的な舞台でアルゼンチン音楽の存在感を示しました。
彼の作品に対する社会的・批評的な受容は多岐にわたります。特に、オペラ『ボマルツォ』が1967年にアルゼンチンで上演禁止となったことは、芸術表現の自由と政治的権力との間の緊張関係を示す象徴的な出来事でした。この禁止は1972年に解除されましたが、彼の作品が単なる芸術作品としてだけでなく、社会的な言説の一部として認識されていたことを示しています。
日本の指揮者堤俊作は、1978年のジュネーブ国際音楽コンクール指揮部門で最高位を受賞した際に、ヒナステラが審査員を務めていました。堤は後にヒナステラのバレエ『エスタンシア』の日本初演を手がけ、日本におけるヒナステラの作品の普及にも貢献しました。
6. ディスコグラフィー
- 『ボマルツォ』:ワシントン・オペラ協会、ジュリアス・ルーデル指揮。1967年録音、ソニー・クラシカルより2016年に再リリース。
- 『魔法のアメリカ大陸に寄せるカンタータ』:ラケル・アドナイロ(ソプラノ)、ロサンゼルス・パーカッション・アンサンブル、ウィリアム・クラフト指揮。カルロス・チャベスの『打楽器のためのトッカータ』と共に収録。LPレコード、コロンビア・マスターワークス MS 6447、1963年。
- 『魔法のアメリカ大陸に寄せるカンタータ』:マギル・パーカッション・アンサンブル、P.ベルーゼ(指揮)、エリーズ・ベダール(ソプラノ)、マギル・レコードCD、1997年。
- 『ピアノ作品全集』:アンジェイ・ピクル(ピアノ)、ドゥクス・レコーディング・プロデューサーズ、2007年。
- 弦楽四重奏曲第1番:パガニーニ弦楽四重奏団、デッカ・ゴールド・レーベル。
- 『ラテンアメリカの芸術歌曲』:パトリシア・カイセド(ソプラノ)、パウ・カサン(ピアノ)、アルベルト・モラレーダ・レコーズ、バルセロナ、2001年。ヒナステラの『アルゼンチン民謡による5つの歌曲集』と「忘却の木の歌」を収録。
- 『アルゼンチン・フローレス:ヒナステラとグアスタビーノの歌曲』:インカ・ローズ・デュオ(アンネリーゼ・スコヴマンド(声)、パブロ・ゴンサレス・ハセイ(ギター))、クレオ・プロダクションズ、クレオ・プロド1002、2007年。ゴンサレス・ハセイによる声とギターのための編曲で、『アルゼンチン民謡による5つの歌曲集』 Op. 10と『2つの歌曲』 Op. 3を収録。
- ピアノ協奏曲第1番第4楽章の編曲「トッカータ」:エマーソン・レイク・アンド・パーマー、『恐怖の頭脳改革』、1973年。
- 『ニスマンがヒナステラを演奏:3つのピアノ協奏曲』:バーバラ・ニスマン(ピアノ)、ケネス・キースラー(指揮)、ミシガン大学交響楽団。(CD)ピエリアン0048、2012年。
- 『ピアノ独奏およびピアノ/室内楽作品全集』:バーバラ・ニスマン(ピアノ)、アウロラ・ナトーラ=ヒナステラ(チェロ)、ルーベン・ゴンサレス(ヴァイオリン)、ローレンシアン弦楽四重奏団。スリー・オレンジズ・レコーディングス(3OR-01)。
- 『アルベルト・ヒナステラ、「ラテンアメリカの男」、バーバラ・ニスマンによるマスタークラス』:スリー・オレンジズ・レコーディングス(3OR-30)、2022年。
- 『ポポル・ヴフ - マヤの創造』、『エスタンシア』、『パナンビ』、『クレオール舞曲組曲』(オーケストラ版世界初演)、『オジャンタイ』:ジゼル・ベン=ドール(指揮)、ロンドン交響楽団、エルサレム交響楽団、BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団。ナクソス、2010年。
- 『パナンビ、エスタンシア(全バレエ)』:ジゼル・ベン=ドール(指揮)、ルイス・ガエタ(ナレーター/バスバリトン)、ロンドン交響楽団。ナクソス、1998年および2006年。
- 『パブロ・カザルスによる主題のグロス』、『協奏的変奏曲』:ジゼル・ベン=ドール(指揮)、ロンドン交響楽団、イスラエル室内管弦楽団。ナクソス、1995年および2010年。
- ジョン・アンティル:バレエ組曲『コロボリー』、ヒナステラ:バレエ組曲『パナンビ』:ロンドン交響楽団、サー・ユージン・グーセンス(指揮)、エベレスト・ステレオLP、SDBR 3003。
- 弦楽四重奏曲集:「ヒナステラ:弦楽四重奏曲」:クアルテート・ラテンアメリカーノ、クラウディア・モンティエル(ソプラノ)[Elan 82270]。
- ピアノ協奏曲第1番、ピアノ・ソナタ第1番:ヒルデ・ソマー(ピアノ)、エルンスト・メルツェンドルファー(指揮)、ウィーン・フィルハーモニア管弦楽団。デスト(D-402/DS-6402)。
- 『エクリプス』:ドイツ・グラモフォン、4862383、2022年。ヒラリー・ハーン(ヴァイオリン)、アンドレス・オロスコ=エストラーダ(指揮)、フランクフルト放送交響楽団、様々な作曲家の作品を収録。