1. 概要
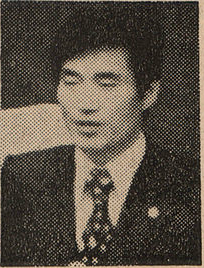
李基澤は1967年に新民党の青年政治家として政界に入り、その後約30年間にわたり国会議員を務めた。彼の政治活動は、朴正煕や全斗煥といった独裁政権に対する民主化運動と密接に結びついており、幾度も政治弾圧を受けながらも、野党の主要な役職を歴任し続けた。特に民主党(通称「ちび民主党」)の総裁、民主党の共同代表、そして統合民主党の総裁を務めた。彼の政治キャリアは、韓国の激動の現代政治史において、一貫して民主主義と反独裁を追求した野党指導者としての道を象徴している。
2. 初期生い立ちと教育
李基澤は1937年7月25日、日本統治下の慶尚北道迎日郡青葉面(現在の浦項市北区)で漢学者の次男として生まれた。朝鮮戦争が勃発した1950年、一家は釜山に転居した。彼は釜山商業高等学校(現開成高等学校)を卒業後、高麗大学校商科大学に進学した。高麗大学校総学生会(学生自治会)の会長を務めていた際、1960年の大統領選挙における李承晩大統領と自由党による大規模な不正選挙に抗議する学生デモを主導した。この運動は四月革命の導火線となり、李承晩政権の崩壊に繋がった。この経験が彼の政治家としての道を決定づけることとなった。大学卒業後、彼は義兄の李壬龍(이임용イ・イムヨン韓国語)と実姉の李善愛が経営していた泰光産業(現泰光グループ)に入社し、その創立メンバーの一人となった。1961年には、慶尚南道民主青年委員会の課長を務めている。彼の本貫は永川李氏である。
3. 政治経歴
李基澤の政治キャリアは、韓国の激動の現代史と共に歩んだ。彼は若くして国会に足を踏み入れ、一貫して野党の主要人物として、民主化と政治改革のために尽力した。
3.1. 第3共和国から維新時代にかけての初期政治活動
1967年の第7代総選挙に先立ち、李基澤は自身の大学時代の恩師である兪鎮午(유진오ユ・ジノ韓国語)総裁が率いる新民党に入党した。彼は全国区(比例代表)14位で立候補し、30歳という韓国史上最年少の国会議員として初当選を果たした。党内では「汎青年闘争委員会」を組織し、朴正煕大統領と民主共和党が提案した大統領の3選を可能にする憲法改正案に強く反対する運動を主導した。
1971年の第8代総選挙では、選挙区を釜山直轄市東萊区乙選挙区(通称釜山第3選挙区)に移して当選した。その後も1973年と1978年の総選挙で東萊区から連続して当選を果たし、党内での地位を確立していった。1976年には新民党の事務総長に就任した。
李基澤は党総裁の金泳三に対して批判的な立場を取ることもあった。1976年の党大会で行われた総裁選挙では、彼は対政府強硬派の金泳三に対抗する穏健派の李哲承を支持し、李哲承の総裁就任に貢献した。その後、李哲承によって事務総長に任命されたが、間もなく両者の関係は疎遠になった。1979年5月の総裁選挙にも出馬したが、1次投票で李哲承と金泳三に次ぐ3位(得票率17.8%)に終わり、決選投票には進めなかった。しかし、彼は決選投票で金泳三を支持し、金泳三の総裁就任に貢献した。これにより、李基澤は最年少で党の副総裁に就任した。
3.2. 政治活動禁止と亡命 (1980年代)
1979年10月26日の朴正煕大統領暗殺事件後、全斗煥を中心とする新軍部が粛軍クーデターや光州事件の鎮圧を通じて政権を掌握した。1980年、新軍部が制定した「政治風土刷新のための特別措置法」(政治風土刷新法)により、李基澤は政治活動の禁止措置の対象となり、国会議員を辞職し、政界からの引退を余儀なくされた。このため、1981年の総選挙には出馬できなかった。彼の選挙区は、元秘書である朴冠用や金晋宰が引き継いだ。その後、彼は米国へ渡り、ペンシルベニア大学の客員教授として活動した。1983年には、金泳三が政治活動の自由を求めて行った15日間のハンガー・ストライキに入った翌日の5月19日に帰国し、民主化運動への関心を失っていないことを示した。
3.3. 政界復帰と野党指導力 (1980年代)
1984年に政治活動の禁止が解除されると、李基澤は金泳三や金大中と共に新韓民主党(新民党)に合流した。当初、彼は以前の地盤であった東萊区からの出馬を予定していたが、その選挙区はすでに朴冠用が占めていたため、1985年2月の第12代総選挙では釜山南区・海雲台区選挙区から出馬し、見事国会議員に返り咲いた。
李基澤は李敏雨総裁の下で党の副総裁を務めた。しかし、1987年には李敏雨総裁が議院内閣制を支持する「李敏雨構想」を発表したことで、党内で激しい内紛が生じた。これに対し、大統領直選制を主張する金泳三と金大中は強く反発し、両者とその支持派は新韓民主党を離脱し、1987年4月21日に統一民主党を結成した。李基澤もこれに同調し、新韓民主党を離党したものの、「6月民主抗争」中の6月29日宣言が発表されるまでは統一民主党には参加しなかった。
1987年6月、与党が大統領直選制への改憲を受け入れた後、李基澤は統一民主党に入党し、再び副総裁に就任した。彼は1988年4月の第13代総選挙で海雲台区から再選された。1987年から1989年まで統一民主党副総裁を務め、1989年には徐錫宰の後任として院内総務(国会対策委員長)も兼任した。また、全斗煥政権下の不正(5共非理)を調査するために設置された「5共非理特別委員会」の委員長を務め、不正の糾明に貢献した。
3.4. 政党指導部と統合 (1990年代)
1990年1月22日、統一民主党総裁の金泳三は、盧泰愚大統領の与党である民主正義党と、金鍾泌総裁の新民主共和党との「三党合同」を宣言し、民主自由党を結成した。これに対し、李基澤は盧武鉉などの党内改革派とともに三党合同への参加を拒否し、民主党を結成して初代総裁に就任した。この党は「ちび民主党」と通称された。彼は野党統合を目指し、金大中が率いる新民主連合党(平和民主党が改編した政党)と交渉を進めた。この時期、李基澤は国軍保安司令部の査察対象の一人であり、盧泰愚政府から監視されていたことが、1990年10月4日に脱走兵尹錫陽の暴露によって明らかになった。
1991年の地方選挙での苦戦を受け、李基澤は金大中の新民主連合党との統合を決断した。1991年9月16日、両党は合流し、新たな「民主党」を創設し、金大中と李基澤は共同代表に就任した。1992年3月の第14代総選挙では、彼は比例代表(全国区)2位で当選した。
1992年5月26日に行われた大統領候補予備選挙では、李基澤は金大中に大差で敗れた。この大統領選挙で金大中が金泳三に敗北し、政界引退を宣言すると、李基澤は1993年3月11日に単独で民主党総裁に就任し、最大野党のリーダーとして活動した。この時期(1993年から1994年)は、彼にとって全盛期と言えるが、党内最大勢力であった「東橋洞系」(金大中派)との間で頻繁に主導権争いを繰り広げた。
1995年初めには、李鍾賛の新韓国党(새한국당セハングクタン韓国語)を民主党に吸収統合したが、地方選挙における公認問題を巡り、再び金大中派との間で衝突が激化した。同年7月、金大中が政界復帰を宣言すると、彼の主導で新政治国民会議(새정치국민회의セジョンチクンミンフェイ韓国語)が創設され、東橋洞系の議員全員が民主党を離党した。これにより李基澤は総裁職を辞任せざるを得なくなった。民主党に残った勢力は、1995年12月21日に「統合民主党」として再編された。
1996年の第15代総選挙では、彼は海雲台区・機張郡甲選挙区から出馬したが、与党新韓国党の金雲煥に敗れ、約30年にわたる国会議員としてのキャリアが一旦途絶えた。落選後、彼は統合民主党の総裁に選出された。国会議員への復帰を目指し、1997年7月の再補欠選挙では自身の出身地である浦項市北区から立候補したが、朴泰俊に敗れた。同年9月11日、彼は総裁職を辞任し、後任には元ソウル市長の趙淳が就任した。
趙淳のリーダーシップの下、統合民主党は少数野党としての限界を克服するため、与党である新韓国党との統合を決定した。両党は合併してハンナラ党を結成し、李基澤を含む多くの党員が新党に合流した。これにより、李基澤は初めて「与党政治家」の立場を経験することになった。しかし、1997年12月の大統領選挙でハンナラ党の李会昌候補が金大中に敗れたため、彼は再び野党の立場に戻った。1998年6月の地方選挙でハンナラ党が敗北すると趙淳が総裁を辞任し、李基澤は李会昌が新総裁に選出されるまで総裁権限代行を務めた。
3.5. 後期の政治活動 (2000年代以降)
2000年4月の第16代総選挙を前に、ハンナラ党内で公認候補選定を巡る対立が生じた。李基澤は党の決定に反発し、金潤煥や金光一といった党の重鎮、そして在野の張基杓らとともにハンナラ党を離党し、新たな政党「民主国民党」を創設した。彼は釜山蓮堤区から出馬したが、ハンナラ党の権泰望に敗れ、この党は2議席に留まった。その後、民主国民党の最高委員に選出された。
2002年12月の大統領選挙では、李基澤は同じ釜山商業高校の後輩であり、かつての民主党の同僚でもあった新千年民主党の盧武鉉候補を支持し、遊説にも積極的に参加した。盧武鉉が大統領に当選した後、李基澤は新千年民主党中央選挙対策委員会の常任顧問を務めた。しかし、盧武鉉政権(「参与政府」)の政策路線とは次第に思想的対立が生じ、李基澤は盧武鉉への支持を撤回し、積極的な政治参加を拒否した。2004年の総選挙には出馬しなかった。
2007年12月の大統領選挙では、李基澤はハンナラ党の李明博候補を支持することを表明し、ハンナラ党選挙対策委員会の常任顧問を務めた。李明博が大統領に当選すると、李基澤はハンナラ党に復党した。2008年9月1日には、大統領の諮問機関である民主平和統一諮問会議の首席副議長に任命された。この人事は、李明博支持に対する「報恩性人事」との議論を呼んだが、彼は2011年までその職務を全うした。その後も、様々な団体で活動を行った。
4. 思想と政治的立場
李基澤の政治的生涯は、一貫して韓国の民主化と社会正義の実現に捧げられた。彼の思想と政治的立場は、以下の特徴によって示される。
- 反独裁と民主主義の擁護**: 彼は若くして李承晩政権の不正選挙に抗議する四月革命を主導し、その後も朴正煕や全斗煥といった軍事独裁政権に対して、一貫して野党の立場で抵抗した。特に朴正煕の3選改憲反対運動や、全斗煥の新軍部による政治弾圧への抵抗(15日間のハンガー・ストライキを含む)は、彼の反独裁主義の強い意志を示している。
- 「生涯野党人」としてのアイデンティティ**: 彼は政治キャリアのほとんどを野党で過ごし、与党との連携を常に慎重に評価した。特に1990年の三党合同への不参加は、政治的利益よりも信念を優先する彼の姿勢を象徴している。彼にとって、野党は単なる政権批判の立場ではなく、民主主義を守る最後の砦であった。
- 社会正義と人権への関心**: 全斗煥政権下の不正を調査する「5共非理特別委員会」の委員長を務めたことは、過去の不義を清算し、社会正義を確立しようとする彼の姿勢を示している。
- 野党統合への尽力**: 彼は「ちび民主党」の総裁として、また金大中との共同代表として、野党勢力の統合に積極的に取り組んだ。これは、分立しがちな野党勢力を結集させ、独裁に対抗する強力な民主勢力を構築しようとする彼の努力であった。
- 現実主義と変化**: 生涯にわたり野党のリーダーとして活動した李基澤だが、彼の政治的スタンスは常に一定ではなかった。2002年の盧武鉉支持から、後に「思想的対立」を理由に支持を撤回し、2007年には李明博を支持したことは、彼が現実の政治情勢や自身の信念の変化に応じて、柔軟な選択をしたことを示している。これは、政権奪取という現実的な目標と、民主主義という普遍的な価値の間で、彼なりのバランスを模索した結果と解釈できる。
5. 私生活
李基澤は李京義と結婚し、李成虎という一人の息子と、李禹仁、李芝仁、李世仁という三人の娘を儲けた。
彼の親族は、泰光グループの主要メンバーであった。泰光グループの創業者で初代会長の李壬龍は李基澤の義兄(姉の夫)にあたり、李基澤の姉である李善愛が李壬龍と結婚していた。李基澤自身も泰光産業の創立メンバーとして入社している。また、第2代会長の李基和は李基澤の実兄であり、第3代会長の李豪鎮は甥にあたる。
6. 死去と遺産
李基澤は2016年2月20日、持病のためソウル市内のカトリック大学校ソウル聖母病院で死去した。享年78歳であった。
彼が死去する前日、自らの回顧録『牛行』(우행ウヘン韓国語)を完成させた。この回顧録は2017年9月15日に出版された。彼の死後、多くの政治家が彼に対する追悼のコメントを発表し、その功績を称えた。
元国会議長の丁世均は、「彼は常に信念と情熱をもって行動した」と述べた。元国会議長の文喜相は、「彼のリーダーシップは『優しさ』で表現された。頑固さの中に意欲を満たした『傾聴のリーダーシップ』は本当に印象的だった」と評した。元ソウル市長の朴元淳は、「彼は四月革命のきっかけとなった学生運動を主導した。私は彼の後輩として、彼の回顧録を読むことで韓国政治史をより深く学ぶことができる」と語った。
李基澤は、軍事独裁政権下の激動期に、一貫して民主化と反独裁を追求した「生涯野党人」として、韓国政治史に大きな足跡を残した。彼の生涯と活動は、韓国の民主主義の発展において重要な遺産となっている。
7. 選挙結果
李基澤が参加した主要な選挙における結果は以下の通りである。
| 年 | 選挙区 | 所属政党 | 得票率 (%) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 比例代表(14位) | 新民党 | 32.70% | 当選 |
| 1971 | 東萊区乙 | 新民党 | 65.89% | 当選 |
| 1973 | 東萊区 | 新民党 | 39.23% | 当選 |
| 1978 | 東萊区 | 新民党 | 40.14% | 当選 |
| 1985 | 南区・海雲台区 | 新韓民主党 | 43.00% | 当選 |
| 1988 | 海雲台区 | 統一民主党 | 58.30% | 当選 |
| 1992 | 比例代表(2位) | 民主党 | 29.20% | 当選 |
| 1996 | 海雲台区・機張郡甲 | 統合民主党 | 47.65% | 落選 |
| 1997 | 浦項市北区 | 統合民主党 | 28.33% | 落選 |
| 2000 | 蓮堤区 | 民主国民党 | 26.53% | 落選 |