1. 生い立ちと背景
アッバス・キアロスタミは1940年6月22日にテヘランで生まれた。彼の最初の芸術的な経験は絵画であり、10代後半まで描き続け、18歳の時に絵画コンテストで優勝した。その後、テヘラン大学美術学部に進学し、絵画とグラフィックデザインを専攻した。学費を稼ぐため、彼は交通巡査としても働いた。
1.1. 初期芸術活動
画家、デザイナー、イラストレーターとして、キアロスタミは1960年代に広告業界で働き、ポスターのデザインやコマーシャルの制作を手掛けた。1962年から1966年の間に、彼はイランのテレビ向けに約150本の広告を撮影した。1960年代後半には、映画のクレジットタイトル(マスウード・キミアイ監督の『カイザー』など)の制作や、児童書のイラストも手掛けるようになった。
2. 映画監督としてのキャリア
キアロスタミは監督として、イラン国内外で数々の主要作品を生み出し、その独自の手法で国際的な評価を確立した。
2.1. 1970年代
1970年、ダリウシュ・メルジュイ監督の映画『牛』によってイラン・ニューウェーブが始まった頃、キアロスタミはテヘランの児童・青少年知育開発協会(カヌン)に映画制作部門を設立するのを手伝った。その部門の処女作であり、キアロスタミの初の映画となったのは、12分の短編『パンと裏通り』(1970年)であった。この作品は、一人の学童が攻撃的な犬と対峙する姿を描いたネオリアリズム風の短編映画である。この後、『休み時間』(1972年)が続いた。カヌンに設立されたこの映画制作部門は、その後イランで最も注目される映画スタジオの一つとなり、キアロスタミの作品だけでなく、『ランナー』や『バシュー、小さな異邦人』といった高く評価されたペルシャ映画も制作した。
1970年代、キアロスタミは個人主義的な映画制作スタイルを追求した。最初の映画について、彼は次のように述べている。
「『パンと裏通り』は私の映画における初めての経験であり、非常に困難なものでした。とても幼い子供と犬、そして撮影監督を除いては素人ばかりのクルーと仕事をしなければならず、撮影監督はずっと文句を言い続けていました。まあ、撮影監督はある意味で正しかったのでしょう。なぜなら、私は彼が慣れ親しんでいた映画制作の慣習に従わなかったからです。」
『経験』(1973年)に続き、キアロスタミは1974年に『トラベラー』(Mossafer)を公開した。『トラベラー』は、小さなイランの都市出身のトラブルを抱えた少年カッセム・ジュライが、遠く離れたテヘランでのサッカー試合を観戦するために、友人や隣人を騙して資金を集め、試合に間に合うようにスタジアムへ向かうが、皮肉な運命のいたずらに遭うという物語である。この映画は、目標達成への少年の決意と、彼の非道徳的な行動がもたらす影響への無関心さを描くことで、人間の行動と善悪の均衡を考察した。これにより、キアロスタミのリアリズム、ダイエジェティックな単純さ、そして様式的な複雑さ、さらには身体的および精神的な旅への彼の魅了といった評価をさらに高めた。
1975年、キアロスタミは短編映画『私にもできる』と『一つの問題に対する二つの解決策』を監督した。1976年初頭には『色彩』を公開し、その後、結婚式のスーツを巡って3人のティーンエイジャーが対立する物語を描いた54分の映画『ウェディング・スーツ』を制作した。
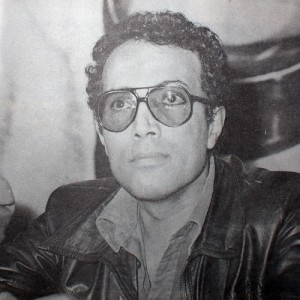
キアロスタミは次に『レポート』(1977年)を監督した。上映時間112分と、これまでの作品よりも大幅に長尺であった。この映画は、賄賂を受け取ったとして告発された徴税人の人生を中心に展開し、自殺をテーマの一つとしていた。1979年には、『ファースト・ケース、セカンド・ケース』をプロデュースし監督した。
2.2. 1980年代
1980年代初頭、キアロスタミは『歯痛』(1980年)、『秩序ある、あるいは無秩序な』(1981年)、『コーラス』(1982年)など、いくつかの短編映画を監督した。1983年には『フェロー・シチズン』を監督したが、イラン国外でその名が知られるようになったのは、『友だちのうちはどこ?』(1987年)の公開以降である。これらの映画は、彼の後の作品の基礎を築いた。
『友だちのうちはどこ?』は、8歳の学童が、友人が学校を退学させられないよう、隣村に住む友人宅にノートを返しに行こうとするという単純な物語である。イランの地方の人々の伝統的な信仰が描かれている。この映画は、イランの田園風景の詩的な描写と、キアロスタミ作品の重要な要素であるリアリズムで注目された。キアロスタミはこの映画を子供の視点から制作した。
『友だちのうちはどこ?』、『そして人生はつづく』(1992年、別名『ライフ・アンド・ナッシング・モア』)、そして『オリーブの林をぬけて』(1994年)は、批評家によって「コケル三部作」と称されている。これら3作品はすべてイラン北部のコケル村を舞台としており、1990年に4万人もの死者を出した1990年マンジル・ルドバール地震に関連している。キアロスタミは、生、死、変化、継続性といったテーマを用いてこれらの映画を結びつけている。この三部作は、1990年代にフランスや、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フィンランドといった西ヨーロッパ諸国で成功を収めた。しかし、キアロスタミ自身はこれら3作品を三部作とは考えていなかった。彼は、後の2作品に『桜桃の味』(1997年)を加えた3本を、命の尊さという共通のテーマを持つ三部作であると示唆した。1987年には、キアロスタミは『鍵』の脚本にも関わり、この作品の編集も手掛けたが、監督は務めなかった。1989年には『ホームワーク』を公開した。
2.3. 1990年代

1990年代のキアロスタミの最初の映画は『クローズ・アップ』(1990年)であった。この作品は、映画監督モフセン・マフマルバフになりすまし、ある家族を騙して自身の新作映画に出演させると信じ込ませた男の実際の裁判の物語である。家族は詐欺の動機を窃盗だと疑うが、なりすまし犯のホセイン・サブジアンは、自身の動機はもっと複雑だと主張する。ドキュメンタリーと演出された部分が混在するこの作品は、マフマルバフのアイデンティティを乗っ取ったサブジアンの道徳的正当性を検証し、彼の文化的・芸術的才能を感知する能力に疑問を投げかけている。英国映画協会(BFI)の「史上最高の映画50選」で42位にランクインした『クローズ・アップ』は、クエンティン・タランティーノ、マーティン・スコセッシ、ヴェルナー・ヘルツォーク、ジャン=リュック・ゴダール、ナンニ・モレッティなどの監督から称賛を受け、ヨーロッパ中で公開された。
1992年、キアロスタミは『そして人生はつづく』を監督した。これは、批評家によって「コケル三部作」の第2作目と見なされている。この映画は、1990年の地震で死亡したかもしれない2人の少年を探すため、テヘランからコケルへ車で向かう父と幼い息子の旅を描いている。父と息子は荒廃した風景の中を旅しながら、災害の中で生きることを強いられた地震の生存者たちに出会う。同年、キアロスタミはこの作品の監督で、彼にとってキャリア初のプロフェッショナルな映画賞であるロベルト・ロッセリーニ賞を受賞した。いわゆる「コケル三部作」の最終作は『オリーブの林をぬけて』(1994年)で、これは『そして人生はつづく』の周辺的なシーンを中心的なドラマに拡大したものである。
エイドリアン・マーティンなどの批評家は、「コケル三部作」の映画制作スタイルを「図式的」(diagrammatical)と呼び、風景の中のジグザグのパターンと、生命および世界の力の幾何学とを結びつけている。『そして人生はつづく』(1992年)におけるジグザグの道のフラッシュバックは、観客に地震前に撮影された1987年の前作『友だちのうちはどこ?』の記憶を呼び起こさせる。これは、1994年の『オリーブの林をぬけて』における地震後の復興と象徴的に結びついている。1995年、ミラマックスは『オリーブの林をぬけて』を米国で劇場公開した。
キアロスタミは次に、元アシスタントのジャファール・パナヒ監督の『旅』(1994年)と『白い風船』(1995年)の脚本を手がけた。1995年から1996年にかけて、彼は他の40人の映画監督とのコラボレーション作品である『リュミエールと仲間たち』の制作にも参加した。
キアロスタミは1997年のカンヌ国際映画祭で『桜桃の味』によりパルム・ドール(金棕櫚賞)を受賞した。これは、自殺を決意した男性、バディ氏のドラマである。この映画は、道徳、自殺行為の正当性、そして思いやりの意味といったテーマを探求した。
キアロスタミは1999年に『風が吹くまま』を監督し、ヴェネツィア国際映画祭で審査員特別大賞(銀獅子賞)を受賞した。この映画は、遠隔地のクルディスタンの村での見知らぬ男の滞在を通して、労働の尊厳に関する農村と都市の見方を対比させ、男女平等や進歩の恩恵といったテーマに取り組んだ。この映画の珍しい特徴は、多くの登場人物の声は聞こえるものの、姿は映らないことである。少なくとも13人から14人のセリフのある登場人物が画面に登場しない。
2.4. 2000年代
2000年、サンフランシスコ国際映画祭の授賞式で、キアロスタミは監督としての生涯功労を称える黒澤明賞を授与されたが、これをイラン映画への貢献を称え、ベテランのイラン人俳優ベフルズ・ヴォスギに贈呈し、皆を驚かせた。
2001年、キアロスタミはアシスタントのセイフォラ・サマディアンとともに、国連国際農業開発基金の要請でウガンダのカンパラを訪れ、ウガンダの孤児を支援するプログラムに関するドキュメンタリーを撮影した。彼は10日間滞在し、『ABCアフリカ』を制作した。当初の目的は撮影準備のための調査であったが、キアロスタミはそこで撮影されたビデオ映像だけで映画全体を編集することになった。ウガンダの孤児の多さは、HIV/AIDSの流行で両親を失った結果である。
「タイムアウト」誌の編集者で国立映画劇場の主任プログラマーであるジェフ・アンドリューは、この映画に言及して次のように述べた。「彼のこれまでの4つの長編映画と同様に、この映画は死についてではなく、生と死についてである。それらがいかに関連しているか、そしてその共生的な必然性に対して我々がどのような態度をとるべきか、である。」
翌年、キアロスタミは『10話』(2002年)を監督した。これは、珍しい映画制作手法を明らかにし、多くの脚本の慣習を放棄した作品である。キアロスタミはイランの社会政治的状況に焦点を当てた。映像は、数日間にわたってテヘランの街を運転する一人の女性の目を通して見られる。彼女の旅は、姉、ヒッチハイクする売春婦、婚約者に裏切られた花嫁とその要求の多い幼い息子など、様々な乗客との10の会話で構成されている。この映画制作スタイルは、多くの批評家から称賛された。
ニューヨーク・タイムズのA・O・スコットは、キアロスタミについて、「過去10年間で最も国際的に評価されたイラン人映画監督であるだけでなく、世界の自動車映画の巨匠の一人でもある...彼は自動車を、内省、観察、そして何よりも会話の場として理解している」と書いた。
2003年、キアロスタミは『ファイブ・デディケイテッド・トゥ・オズ』(別名『ファイブ』)を監督した。これは対話や人物描写のない詩的な長編映画である。カスピ海のほとりで、手持ちのDVカメラで撮影された5つの長尺な自然のワンカットで構成されている。映画には明確なストーリーラインはないが、ジェフ・アンドリューは「単なる美しい映像以上のものである」と主張している。彼はさらに、「順序立てて構成されており、一種の抽象的または感情的な物語の弧を形成している。それは、分離と孤独から共同体へ、動きから静止へ、ほとんど無音から音と歌へ、光から闇へ、そして再び光へと感動的に移行し、再生と新生の音色で終わる」と述べた。彼は、映像の明らかな単純さの裏に隠された人工の度合いにも言及している。
2005年、キアロスタミは、イタリアを旅する列車を舞台としたアンソロジー映画『明日へのチケット』の中央部分を監督した。他の部分はケン・ローチとエルマンノ・オルミが監督した。
2008年、キアロスタミは長編映画『シーリーン』を監督した。この作品は、多くの著名なイラン人女優とフランス人女優ジュリエット・ビノシュが、部分的に神話に基づくペルシャ文学の恋愛物語『ホスローとシーリーン』を基にした映画を鑑賞する様子をクローズアップで捉え、女性の自己犠牲をテーマとしている。この映画は、「映像、音、女性観客の間の関係性を説得力をもって探求している」と評されている。
同年夏、彼はウィリアム・シメル主演でクリストフ・ルセ指揮のモーツァルトのオペラ『コジ・ファン・トゥッテ』をエクス=アン=プロヴァンス音楽祭で演出した。しかし、翌年のイングリッシュ・ナショナル・オペラでの公演は、国外渡航許可が下りなかったため、監督することができなかった。
2.5. 2010年代
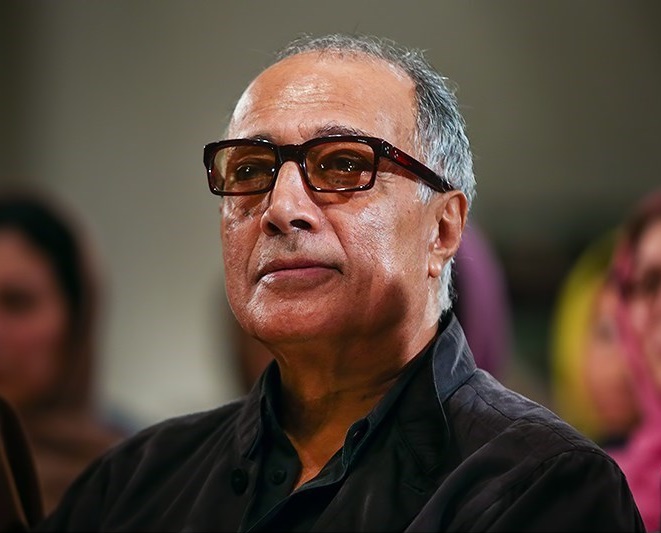
再びジュリエット・ビノシュが主演した『トスカーナの贋作』(2010年)はトスカーナで制作され、キアロスタミにとって初めてイラン国外で撮影・制作された映画となった。この作品は、英国人男性とフランス人女性の出会いの物語で、2010年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを競った。ガーディアン紙のピーター・ブラッドショーは、この映画を「興味深い奇妙さ」と評し、「『トスカーナの贋作』は、ジュリエット・ビノシュが善意の熱情をもって演じる結婚生活の脱構築された描写だが、一貫して不可解で、作為的で、しばしば単に奇妙な、最も特殊な高尚な失敗作である」と述べた。彼はこの映画が「間違いなくキアロスタミの構成技法の一例ではあるが、成功した例ではない」と結論付けた。しかし、ロジャー・イーバートは、「キアロスタミがオフスクリーン空間を作り出す手腕は実に素晴らしい」と評価した。ビノシュはこの映画での演技により、カンヌ映画祭で女優賞を受賞した。
キアロスタミの最後の作品から2番目にあたる『ライク・サムワン・イン・ラブ』は、日本を舞台に日本で撮影され、批評家から概ね肯定的な評価を受けた。
キアロスタミの最終作品『24フレーム』は2017年に遺作として公開された。この実験映画は、キアロスタミの24枚のスチル写真に基づいており、批評家から非常に肯定的な評価を受け、Rotten Tomatoesでは92%のスコアを獲得した。彼の死の1週間前、キアロスタミはアカデミー賞の審査員の多様性を高める取り組みの一環として、ハリウッドのアカデミー賞に招待されていた。
2.6. 映画祭での活動
キアロスタミは数多くの映画祭で審査員を務めた。特に1993年、2002年、2005年のカンヌ国際映画祭では審査員を務め、2005年にはカメラ・ドールの審査委員長も務めた。また、2014年のカンヌ国際映画祭ではシネフォンダシオンおよび短編部門の審査委員長に任命された。
その他、1985年のヴェネツィア国際映画祭、1990年のロカルノ国際映画祭、1996年のサンセバスチャン国際映画祭、2004年のサンパウロ国際映画祭、2007年のカパルビオ・シネマ映画祭(審査委員長)、2011年のキュステンフェストでも審査員を務めている。また、ポルトガルのエストリル映画祭を含むヨーロッパ各地の多くの映画祭にも定期的に姿を見せていた。
3. 映画的スタイルとテーマ
キアロスタミの映画は、彼独自の制作方法、哲学的探求、そして作品全体にわたる主要なテーマによって特徴づけられる。
3.1. 独自の映画技法
キアロスタミは、サタジット・レイ、ヴィットリオ・デ・シーカ、エリック・ロメール、ジャック・タチと比較されることもあるが、彼の映画は独自のスタイルと、彼自身の発明による技法をしばしば用いている点で異彩を放っている。
1970年の『パンと裏通り』の撮影中、キアロスタミは、少年と襲いかかる犬の撮影方法について、経験豊富な撮影監督と大きな意見の相違があった。撮影監督が、少年が近づく別々のショット、少年が家に入ってドアを閉める手のクローズアップ、その後に犬のショットと分けようとしたのに対し、キアロスタミは、これら3つのシーンを全体として捉えることで、状況にさらなる緊張感を生み出すことができると信じていた。この1ショットを完成させるのに約40日かかり、キアロスタミが完全に満足するまで続けられた。キアロスタミは後に、シーンを分割すると映画の構造のリズムと内容が乱れてしまうため、シーン全体を流れるように撮影することを好むとコメントしている。
他の監督とは異なり、キアロスタミは大規模な作品における派手な戦闘シーンや複雑な追跡シーンの演出には関心を示さず、代わりに映画という媒体を自身の要求に合わせて形成しようと試みた。キアロスタミは、「コケル三部作」で自身のスタイルを確立したようで、この三部作には自身の映画素材への無数の言及が含まれており、各映画間で共通のテーマと主題を結びつけている。スティーブン・ブランズフォードは、キアロスタミの映画は他の監督の作品への言及を含まず、むしろ自己言及的な方法で構築されていると主張している。ブランズフォードは、彼の映画はしばしば、ある映画が以前の映画を振り返り、部分的にその神秘性を解き明かすという、進行中の弁証法的な関係にあると考えている。
彼は新しい撮影方法を実験し続け、異なる監督手法や技術を用いた。その一例が『10話』である。この映画は走行中の自動車内で撮影され、キアロスタミ自身はその場にいなかった。彼は俳優たちに何をするべきかを指示し、ダッシュボードに設置されたカメラが彼らがテヘランを走り回る様子を撮影した。カメラは回り続け、彼らの日常の様子を極端なクローズアップショットで捉えた。『10話』は、デジタルカメラを使って監督を事実上排除するという実験であった。この「デジタル・マイクロシネマ」と呼ばれる新たな方向性は、マイクロ予算での映画制作であり、デジタル制作基盤と結びついている。
キアロスタミの映画は、映画の異なる定義を提示している。ウィリアム・パターソン大学のジャムシード・アクラミ教授のような映画学の専門家によれば、キアロスタミは観客の関与を増やすことで、一貫して映画を再定義しようと努めた。晩年には、彼は自身の映画のタイムスパンを次第に短くしていった。アクラミは、これにより映画制作が集合的な努力から、より純粋で基本的な芸術表現の形式へと還元されたと考えている。
3.2. フィクションとノンフィクションの融合
キアロスタミの映画には、著しい曖昧さ、単純さと複雑さの珍しい混合、そしてしばしばフィクションとドキュメンタリーの要素の混合(ドキュフィクション)が含まれている。キアロスタミは「私たちは嘘を通してでしか真実に近づくことはできない」と述べている。
キアロスタミの映画では、フィクションとノンフィクションの境界が著しく曖昧になっている。フランスの哲学者ジャン=リュック・ナンシーは、キアロスタミ、特に『そして人生はつづく』について論じる中で、彼の映画は完全にフィクションでもなければ、完全にドキュメンタリーでもないと主張している。『そして人生はつづく』は、描写でも報告でもなく、むしろ「証拠」(evidence)であると彼は主張する。
「全ては報告のように見えるが、全てが強調している(indique à l'évidence)のは、それがドキュメンタリーのフィクションであること(実際、キアロスタミは地震の数ヶ月後に映画を撮影している)、そしてむしろ『フィクション』についてのドキュメントであることだ。それは非現実を想像するという意味ではなく、イメージを構築する技術、つまり『芸術』という非常に特殊で精密な意味においてである。なぜなら、そのイメージによって、毎回、それぞれが世界を開き、その中で自分自身に先行する(s'y précède)ものは、あらかじめ与えられたもの(donnée toute faite)(夢や幻想、悪い映画のように)ではないからだ。それは発明され、切り取られ、編集されるべきものなのだ。したがって、それは『証拠』なのだ。もしある日、私が一日に10回も往復する自分の道を『見る』ことになったなら、私はその瞬間に自分の道の新しい『証拠』を構築するだろう。」
ナンシーにとって、ドキュメンタリーや想像力としてではなく、「証拠」としての映画というこの概念は、キアロスタミが生と死を扱う方法(上記、『ABCアフリカ』に関するジェフ・アンドリューのコメント、すなわちキアロスタミの映画は死についてではなく生と死についてであるという趣旨)と結びついている。
「存在は生と死の無関心に抵抗し、機械的な『生命』を超えて生きる。それは常に自身の喪でもあり、自身の喜びでもある。それは形となり、イメージとなる。それはイメージの中で疎外されるのではなく、そこに提示される。イメージは存在の証拠であり、その主張の客観性である。この思考 - 私にとって、それはこの映画[『そして人生はつづく』]そのものの思考である - は困難な思考であり、おそらく最も困難なものだ。それは遅い思考であり、常に進行中であり、道そのものが思考になるように道を切り開く。それは、イメージがこの思考になるように、イメージがこの思考の証拠になるようにイメージをほつれさせるものであり、それを『表現』するためではない。」
言い換えれば、生と死を対立する力として単に表現するだけでなく、自然の各要素がいかに不可分に結びついているかを示すことを望み、キアロスタミは、観客に文書化可能な「事実」を提示するだけではない、しかし単なる巧妙な芸術でもない映画を考案した。なぜなら、「存在」は単に生命以上のものを意味し、投影的であり、還元不可能な虚構の要素を含んでいるが、この生命を「超える」存在であることで、死と汚染されているからである。ナンシーは、キアロスタミの「嘘だけが真実への道である」という言葉の解釈への手がかりを与えているのである。
3.3. 詩とイメージ
メリーランド大学カレッジパーク校のアハマド・カリミ=ハッカクは、キアロスタミの映画的スタイルの一面として、ペルシャ詩の本質を捉え、彼の映画の風景の中に詩的なイメージを創造する能力を挙げている。『友だちのうちはどこ?』や『風が吹くまま』など、彼のいくつかの映画では、古典ペルシャ詩が直接引用されており、それらの芸術的なつながり、そして過去と現在、継続性と変化の間の密接な関係を強調している。
登場人物たちは主に古典ペルシャ詩人ウマル・ハイヤーム、あるいはソフラブ・セペリやフォルグ・ファッロフザードといった現代ペルシャ詩人の詩を暗唱する。『風が吹くまま』のあるシーンでは、広大な麦畑が波打つ黄金の作物とともに映し出され、その中を医者が映画製作者を伴ってねじれた道をスクーターで走っていく。別の世界がこの世界よりも良い場所だというコメントに対し、医者はハイヤームのこの詩を暗唱する。
彼らは天国でのホーリーたちを約束するが
私はワインの方が良いと言うだろう
約束よりも今を大切にせよ
太鼓の音は遠くからの方が心地よい
キアロスタミによるソフラブ・セペリとフォルグ・ファッロフザードの詩の創作的な翻案は、テキスト変換の領域を広げるものであると主張されている。翻案は、先行するテキストを新しいテキストへと変換することと定義される。ワシントン大学のシマ・ダードは、キアロスタミの翻案は、その限界をテクスト間の潜在性からジャンルを超えた潜在性へと拡大することで、翻案の理論的領域に到達していると主張している。
3.4. 生と死のテーマ
変化と継続性という概念は、生と死のテーマに加えて、キアロスタミの作品において主要な役割を果たしている。特に「コケル三部作」では、これらのテーマが中心的な役割を担っている。1990年のマンジル・ルドバール地震の災害後で描かれているように、これらは破壊を乗り越え、それに抗う人間のレジリエンス(回復力)の力を表している。
生き残るための本能的な渇望を描くコケル映画とは異なり、『桜桃の味』は生命の脆さを探求し、そのいかに尊いものであるかに焦点を当てている。
一部の映画批評家は、『桜桃の味』や『風が吹くまま』のように、キアロスタミの映画言語における光と闇のシーンの組み合わせが、無限の可能性を秘めた生と、誰の人生にも訪れる事実としての死という、両者の相互的な存在を示唆していると見ている。
3.5. 精神性
キアロスタミの「複雑な」音と映像、そして哲学的なアプローチは、しばしばアンドレイ・タルコフスキーやロベール・ブレッソンといった「神秘的な」映画監督と比較される原因となっている。文化的な大きな違いを認めつつも、キアロスタミに関する欧米の批評の多くは、同様に厳格で「精神的」な詩学と道徳的献身を理由に、彼をイラン版のこれらの監督と同等と位置づけている。彼の映画における特定のイメージは、スーフィズムの概念と類似していると指摘する者もいる。
デヴィッド・ステリットやスペインの映画教授アルベルト・エレナといった多くの英語圏の作家は、キアロスタミの映画を精神的と解釈する一方で、デヴィッド・ウォルシュやハミッシュ・フォードなどの他の批評家は、彼の映画における精神性の影響をより低いものと評価している。
4. 多彩な芸術的才能

キアロスタミは、ジャン・コクトー、サタジット・レイ、ピエル・パオロ・パゾリーニ、デレク・ジャーマン、アレハンドロ・ホドロフスキーらと同様に、詩、舞台美術、絵画、写真など、他の芸術分野でも自己表現を行った映画監督であった。彼らは、世界に対する自身の解釈や、我々の関心事やアイデンティティへの理解を、それらの媒体を通して表現した。
キアロスタミは著名な写真家であり詩人でもあった。彼の200編以上の詩を収録したバイリンガル版詩集『風と歩く』(Walking with the Wind)は、ハーバード大学出版局から出版された。彼の写真作品には、1978年から2003年の間に故郷テヘランで撮影された、主に雪景色をテーマとした30枚以上の写真を収めた『無題の写真』(Untitled Photographs)がある。1999年には自身の詩集も出版している。キアロスタミはまた、モーツァルトのオペラ『コジ・ファン・トゥッテ』のプロデュースも行い、この作品は2003年にエクス=アン=プロヴァンスで初演された後、2004年にはロンドンのイングリッシュ・ナショナル・オペラで上演された。
カ・フォスカリ大学のリカルド・ツィポリは、キアロスタミの詩と映画の間の関係性や相互接続性を研究した。その分析結果は、キアロスタミの「不確かな現実」の扱いが、彼の詩と映画でいかに似通っているかを明らかにしている。
キアロスタミの詩は、ペルシャの画家で詩人であるソフラブ・セペリの晩年の自然詩を彷彿とさせる。一方で、熟考を要せずして哲学的真理を簡潔に示唆する点、詩的声の無批判的なトーン、そして一人称代名詞、副詞、形容詞への過度な依存を排除した詩の構造、さらには季語を含む行など、この詩の多くは俳句的な特徴を備えている。
キアロスタミの3巻のオリジナル詩集、さらにニーマ・ユーシジ、ハーフェズ、ルーミー、サアディーといった古典および現代ペルシャ詩人からの彼の選集は、2015年に英語に翻訳され、ニューヨークのSticking Place Booksからバイリンガル(ペルシャ語/英語)版として出版された。
5. 私生活
1969年、キアロスタミはパルヴィン・アミル=ゴリと結婚し、アフマドとバフマンの2人の息子をもうけたが、1982年に離婚した。
1979年のイラン革命後、多くの同業者が国外へ逃れた中で、キアロスタミは数少ないイラン国内に留まった監督の一人である。彼はそれが自身のキャリアにおいて最も重要な決断の一つであったと信じている。イランに恒久的に拠点を置き、その国民的アイデンティティを保つことが、映画製作者としての彼の能力を確固たるものにしたと述べている。
「地面に根を張った木を、ある場所から別の場所に移植すると、その木はもう実を結ばなくなります。たとえ結んだとしても、元の場所にいた時ほど良い実にはなりません。これは自然の法則です。もし私が自分の国を離れていたら、その木と同じようになっていたでしょう。」
キアロスタミは、光過敏症のため、しばしば黒い眼鏡やサングラスを着用していた。
6. 病気と死
6.1. 死に至る経緯
2016年3月、キアロスタミは腸管出血のため入院し、2度の手術後に昏睡状態に陥ったと報じられた。イラン保健医療教育省の報道官を含む情報源は、キアロスタミが胃腸がんを患っていたと報じた。しかし、2016年4月3日、キアロスタミの医療チームの責任者であるレザ・パイダールは、映画監督が癌を患っているという報道を否定する声明を発表した。しかし、6月下旬には治療のためパリの病院へ出発し、2016年7月4日にその地で逝去した。彼の死の1週間前、キアロスタミはアカデミー賞の審査員の多様性を高める取り組みの一環として、ハリウッドのアカデミー賞に招待されていた。イランの駐仏大使アリ・アハニは、キアロスタミの遺体がイランへ送還され、ベヘシュテ・ザフラー墓地に埋葬される予定だと述べた。しかしその後、彼の遺体はパリからテヘランへ空輸された後、自身の遺志に基づき、テヘランの北東約40 kmにあるリゾート地ラヴァサンに埋葬されることが発表された。彼の遺体は2016年7月8日にテヘランのエマーム・ホメイニー国際空港に帰還し、イランの映画監督、俳優、女優、その他の芸術家たちが大勢空港に集まり、哀悼の意を表した。
映画監督であり親しい友人であったモハンマド・シルヴァニは、2016年6月8日にキアロスタミの言葉を自身のFacebookのウォールに引用した。「もうこれ以上映画を撮って立つことはできないだろうと信じている。彼ら(医療チーム)はそれを(彼の消化器系を)破壊してしまった。」このコメントの後、イラン人の間でキアロスタミの治療中の医療過誤の可能性を調査するためのキャンペーンがTwitterとFacebookで立ち上げられた。しかし、長男のアフマド・キアロスタミは、シルヴァニのコメントの後、父親の治療における医療過誤を否定し、父親の健康状態に懸念はないと述べた。キアロスタミの死後、イラン医療評議会(Iranian Medical Council)の長であるアリレザ・ザリ医師は、フランスの対応機関であるパトリック・ブエに対し、キアロスタミの医療記録をイランに送付し、さらなる調査を行うよう求める書簡を送った。キアロスタミの死から9日後の2016年7月13日、彼の家族は、キアロスタミの主治医を通じて、医療過誤に対する正式な苦情を申し立てた。著名なイラン人映画監督のダリウシュ・メルジュイも、キアロスタミを治療した医療チームを批判し、法的措置を要求した。
6.2. 葬儀と追悼

芸術家、文化関係者、政府関係者、そしてイラン国民は、キアロスタミの死から6日後の7月10日、感情的な葬儀で彼に別れを告げるために集まった。式典は、彼が約40年前に映画制作のキャリアを始めた児童・青少年知育開発協会で行われた。参列者たちは、彼の映画のタイトルや最も有名なポスターの写真を掲げ、キアロスタミが文化、特にイランの映画制作に貢献した支援を称えた。式典は著名なイラン人俳優パルヴィズ・パラストゥイが司会を務め、画家アイディン・アグダシュルーや受賞歴のある映画監督アスガル・ファルハーディーが彼の専門的な能力を強調するスピーチを行った。彼はその後、テヘラン北部のラヴァサンの私的な式典で埋葬された。
マーティン・スコセッシは、この訃報に「深く衝撃を受け、悲しんでいる」と述べた。アカデミー賞受賞監督のアスガル・ファルハーディーは、友人を訪ねるためにパリへ飛ぶ予定であったが、「とても悲しく、完全にショックを受けている」と語った。モフセン・マフマルバフも同様の感情を示し、イラン映画が国際的な評価を得たのはキアロスタミのおかげだが、その認知度は彼の故国での作品の公開には繋がらなかったと述べた。「キアロスタミは今日のイラン映画に国際的な信頼性をもたらした」と彼はガーディアン紙に語った。「しかし、彼の映画は残念ながらイランではあまり見られなかった。彼は世界の映画を変え、ハリウッドの粗野なバージョンとは対照的に、それを新鮮で人間的なものにした。」ペルシャの神秘主義者で詩人のジャラール・ウッディーン・ルーミーの22代目の姪であるエシン・チェレビも、別途メッセージでキアロスタミの逝去に哀悼の意を表した。国連教育科学文化機関(UNESCO)のイラン代表部も、キアロスタミを称えるための追悼記帳簿を開設した。
イランのハサン・ロウハーニー大統領はTwitterで、監督の「生に対する異質で深遠な態度と、平和と友情への彼の招待」が「永続的な功績」となるだろうと述べた。モハンマド・ジャヴァード・ザリーフ外務大臣もまた、キアロスタミの死は国際映画にとっての損失であると述べた。フランスのフランソワ・オランド大統領は声明で、監督がフランスと「密接な芸術的絆と深い友情」を築いたことを称賛した。
ニューヨーク・タイムズ、CNN、ガーディアン、ハフポスト、インデペンデント、AP通信、ユーロニュース、ル・モンドなどのメディアもキアロスタミの死に反応した。『ニューヨーク・タイムズ』は「アッバス・キアロスタミ、高く評価されたイラン人映画監督、76歳で死去」と報じ、ピーター・ブラッドショーはキアロスタミを「洗練された、自信に満ちた映画詩の巨匠」と称賛した。
パリでの追悼式に集まった群衆は、セーヌ川のほとりで追悼集会を開いた。その後、群衆が川に流したキアロスタミの写真を波が運び去るのを許した。それは、多くのイラン人が熱烈に評価する映画監督との別れを告げる象徴的な瞬間であった。
7. 受容と批評
キアロスタミは、世界中の観客と批評家の両方から高い評価を受けており、1999年には2つの国際批評家投票によって1990年代で最も重要なイラン人映画監督に選ばれた。彼の4作品は、シネマテーク・オンタリオの「90年代ベスト映画」投票でトップ6に入った。彼は映画理論家、批評家、そしてジャン=リュック・ゴダール、ナンニ・モレッティ、クリス・マルケルといった同業者からも認められた。黒澤明はキアロスタミの映画について、「言葉では言い表せない感情を抱く...サタジット・レイが亡くなった時、私は非常に落ち込んだ。しかし、キアロスタミの映画を観た後、神が彼に代わるにふさわしい人物を与えてくださったことに感謝した」と語っている。
マーティン・スコセッシのような高く評価される監督は、「キアロスタミは映画芸術の最高レベルを体現している」とコメントしている。オーストリアの監督ミヒャエル・ハネケは、アッバス・キアロスタミの作品を存命の監督の中で最高の部類に入ると称賛した。2006年、ガーディアン紙の批評家委員会は、キアロスタミを非アメリカ人監督の中で最高の現代映画監督と評価した。
ジョナサン・ローゼンバウムなどの批評家は、「アッバス・キアロスタミの映画が観客を分断することは避けられない事実だ。これはこの国でも、彼の母国イランでも、そしてどこで上映されても同じだ」と主張している。ローゼンバウムは、キアロスタミの映画を巡る意見の相違や論争は、彼の映画制作スタイルに起因すると論じている。ハリウッドであれば本質的な物語情報と見なされるものが、キアロスタミの映画では頻繁に欠落しているためである。同様に、カメラの配置も標準的な観客の期待を裏切ることが多く、『そして人生はつづく』や『オリーブの林をぬけて』の終盤のシーンでは、観客は重要なシーンの対話や状況を想像することを強いられる。『ホームワーク』や『クローズ・アップ』では、サウンドトラックの一部が覆い隠されたり、沈黙させられたりしている。批評家は、キアロスタミの映画表現の繊細さは、批評的分析に抵抗する部分が大きいと主張している。
キアロスタミはいくつかの作品でヨーロッパで高い評価を得ている一方で、イラン政府は彼の映画の上映を許可することを拒否している。これに対し彼は、「政府は過去10年間、私の映画のいかなる上映も許可しないと決定した。彼らは私の映画を理解しておらず、そのため、彼らが望まないメッセージが伝わることを恐れて上映を阻止しているのだと思う」と述べた。
アメリカ同時多発テロ事件の後、キアロスタミはニューヨーク映画祭に出席するためのビザを拒否された。彼を招待した映画祭ディレクターのリチャード・ペーニャは、「今日の我が国で起こっていることのひどい兆候であり、これがイスラム世界全体にどのような否定的なメッセージを送るか、誰も理解していないし気にかけようともしないようだ」と述べた。これに抗議して、フィンランドの映画監督アキ・カウリスマキは映画祭をボイコットした。キアロスタミはニューヨーク映画祭だけでなく、オハイオ大学やハーバード大学からも招待されていた。
2005年、ロンドン・フィルム・スクールは、キアロスタミの作品のワークショップと映画祭を「アッバス・キアロスタミ:芸術家のビジョン」と題して開催した。ロンドン・フィルム・スクールのディレクターであるベン・ギブソンは、「ごく少数の人々しか、最も基本的な要素から、ゼロから映画を創造するような創造的かつ知的な明晰さを持っていない。キアロスタミのような巨匠が即興で思考するのを見られる機会を得たことは、私たちにとって非常に幸運なことだ」と述べた。彼はその後、名誉准教授に任命された。
2007年には、ニューヨーク近代美術館とMoMA PS1が共同で、キアロスタミの作品展「アッバス・キアロスタミ:イメージメーカー」を開催した。
キアロスタミとその映画スタイルは、複数の書籍や、『クローズ・アップの公開日』(1996年、ナンニ・モレッティ監督)、『アッバス・キアロスタミ:生の芸術』(2003年、パット・コリンズ&ファーガス・デイリー監督)、『アッバス・キアロスタミ:ある報告』(2014年、バフマン・マクスードルー監督)という3本の映画の題材となっている。
キアロスタミは、監督マーティン・スコセッシが設立したワールド・シネマ財団の諮問委員会のメンバーであった。この財団の目標は、長らく忘れ去られていた世界の映画を発掘し、修復することである。
7.1. 受賞歴
キアロスタミは世界中の観客と批評家から賞賛を浴び、2000年までに少なくとも70の賞を受賞した。主な受賞歴は以下の通りである。
- ロベルト・ロッセリーニ賞(1992年)
- シネ・デクヴェルト賞(1992年)
- フランソワ・トリュフォー賞(1993年)
- ピエル・パオロ・パゾリーニ賞(1995年)
- ユネスコフェデリコ・フェリーニ金メダル(1997年)
- カンヌ国際映画祭パルム・ドール(1997年)
- ユース賞(2010年、『トスカーナの贋作』)
- 外国語作品賞(1998年、『桜桃の味』)
- テッサロニキ国際映画祭名誉ゴールデンアレクサンダー賞(1999年)
- ヴェネツィア国際映画祭審査員特別大賞(1999年)
- 国際映画批評家連盟賞(1999年、『風が吹くまま』)
- 黒澤明賞(2000年)
- エコール・ノルマル・シュペリウール名誉博士号(2003年)
- コンラート・ヴォルフ賞(2003年)
- 高松宮殿下記念世界文化賞(2004年)
- カンヌ映画祭カメラ・ドール審査委員長(2005年)
- 英国映画協会フェローシップ(2005年)
- ロカルノ国際映画祭名誉豹賞(2005年)
- アンリ・ラングロワ賞(2006年)
- トゥールーズ大学名誉博士号(2007年)
- コルカタ国際映画祭ワールド・グレート・マスターズ(2007年)
- ヴェネツィア映画祭「グローリー・トゥ・ザ・フィルムメーカー・アワード」(2008年)
- 監督・ばんざい!賞(2008年、『シーリーン』)
- パリ大学名誉博士号(2010年)
- バトゥミ国際アートハウス映画祭生涯功労賞(2010年)
- 旭日小綬章(2013年)
- オーストリア科学芸術勲章(2014年)
- アンタルヤ国際映画祭名誉ゴールデンオレンジ賞(2014年)
7.2. 批判と論争
2010年の映画『トスカーナの贋作』では、監督がカンヌ映画祭の会場に来られなかったことに対して主演のジュリエット・ビノシュが批判的なコメントをしたため、イラン国内での上映禁止及びビノシュの入国禁止令が出るという事件が起きた。
2020年8月、映画『10話』に主演したマニア・アクバリは、キアロスタミがアクバリが撮影した私的な映像を無許可で映画に編集したとして、剽窃の疑いでキアロスタミを告発した。アクバリの娘で『10話』にも出演したアミナ・マヘルは、2019年の短編映画『母への手紙』の中で、自身の出演シーンが知らされないまま撮影されたと述べた。2022年には、アクバリとマヘルは配給会社MK2に対し、映画の流通を停止するよう求めているが、MK2はまだ対応していないと明らかにした。その結果、英国映画協会(BFI)は『10話』をキアロスタミの回顧展から削除した。
2022年、アクバリはキアロスタミが彼女を2度レイプしたと告発した。一度目はテヘランでアクバリが25歳、キアロスタミが約60歳の時、二度目は『10話』が公開された後のロンドンであったという。
8. 影響力
キアロスタミは、イラン・ニューウェーブ映画の基礎を築く上で中心的な役割を果たし、その特徴的なスタイルは世界中の映画製作に大きな影響を与えた。彼の作品は、後に続く映画製作者たちにインスピレーションを与え、映画芸術の可能性を広げた。彼は、マーティン・スコセッシが設立したワールド・シネマ財団の諮問委員会のメンバーでもあり、世界中の忘れられた映画の発見と修復に貢献することで、国際的な映画遺産の保護にも力を尽くした。このように、キアロスタミはイラン映画界のみならず、世界映画史全体に深い足跡を残した巨匠として認識されている。
9. 作品リスト
キアロスタミが監督または脚本として参加した主要な長編および短編映画のリストを年代順に提示する。
9.1. 長編
| 年 | 邦題 | 原題 | 監督 | 脚本 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | The Experience | 〇 | 〇 | アミール・ナーデリーと共同脚本 | |
| 1974 | トラベラー | Mossafer | 〇 | 〇 | |
| 1976 | A Wedding Suit | 〇 | 〇 | パルヴィズ・ダヴァイーと共同脚本 | |
| 1977 | レポート | The Report | 〇 | 〇 | |
| 1979 | First Case, Second Case | 〇 | 〇 | ||
| 1983 | Fellow Citizen | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー映画 | |
| 1984 | First Graders | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー映画 | |
| 1987 | 友だちのうちはどこ? | Where Is the Friend's Home? | 〇 | 〇 | コケル三部作の第1作 |
| 1987 | 鍵 | The Key | ✕ | 〇 | |
| 1989 | ホームワーク | Homework | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー映画 |
| 1990 | クローズ・アップ | Close-Up | 〇 | 〇 | ドキュフィクション |
| 1992 | そして人生はつづく | Life, and Nothing More... | 〇 | 〇 | コケル三部作の第2作。英語タイトルはAnd Life Goes On |
| 1994 | オリーブの林をぬけて | Through the Olive Trees | 〇 | 〇 | コケル三部作の最終作 |
| 1994 | The Journey | ✕ | 〇 | 別名Safar | |
| 1995 | 白い風船 | The White Balloon | ✕ | 〇 | |
| 1997 | 桜桃の味 | Taste of Cherry | 〇 | 〇 | |
| 1999 | 柳と風 | Willow and Wind | ✕ | 〇 | |
| 1999 | 風が吹くまま | The Wind Will Carry Us | 〇 | 〇 | |
| 2001 | ABCアフリカ | ABC Africa | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー映画 |
| 2002 | The Deserted Station | ✕ | 〇 | ストーリーコンセプト | |
| 2002 | 10話 | Ten | 〇 | 〇 | ドキュフィクション |
| 2003 | クリムゾン・ゴールド | Crimson Gold | ✕ | 〇 | |
| 2003 | ファイブ・デディケイテッド・トゥ・オズ | Five Dedicated to Ozu | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー映画、別名Five |
| 2004 | 10 on Ten | 〇 | 〇 | キアロスタミ自身の映画、特に『10話』に関するドキュメンタリー映画 | |
| 2005 | 明日へのチケット | Tickets | 〇 | 〇 | エルマンノ・オルミ、ケン・ローチと共同監督。ポール・ラヴァーティ、エルマンノ・オルミと共同脚本 |
| 2006 | Men at Work | ✕ | ✕ | ストーリーコンセプト | |
| 2006 | Víctor Erice-Abbas Kiarostami: Correspondences | 〇 | 〇 | 著名な監督ビクトル・エリセとの共同制作。エリセも脚本・監督 | |
| 2007 | Persian Carpet | 〇 | 〇 | 『ペルシャ絨毯』の15セグメントのうち「Is There a Place to Approach?」のみ監督 | |
| 2008 | シーリーン | Shirin | 〇 | 〇 | |
| 2010 | トスカーナの贋作 | Certified Copy | 〇 | 〇 | |
| 2012 | ライク・サムワン・イン・ラブ | Like Someone in Love | 〇 | 〇 | |
| 2012 | Meeting Leila | ✕ | 〇 | ||
| 2016 | Final Exam | ✕ | ✕ | 遺作、死前にストーリーコンセプト提供。監督はアデル・ヤラギ、脚本も担当 | |
| 2017 | 24フレーム | 24 Frames | 〇 | 〇 |
9.2. 短編
| 年 | 邦題 | 原題 | 監督 | 脚本 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | パンと裏通り | The Bread and Alley | 〇 | 〇 | |
| 1972 | Recess | 〇 | 〇 | ||
| 1975 | Two Solutions for One Problem | 〇 | 〇 | ||
| 1975 | So Can I | 〇 | 〇 | ||
| 1976 | The Colours | 〇 | 〇 | ||
| 1977 | Tribute to the Teachers | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー | |
| 1977 | Jahan-nama Palace | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー | |
| 1977 | How to Make Use of Leisure Time | 〇 | 〇 | ||
| 1978 | Solution | 〇 | 〇 | 英語タイトルはSolution No.1 | |
| 1980 | Driver | 〇 | 〇 | ||
| 1980 | Orderly or Disorderly | 〇 | 〇 | ||
| 1982 | The Chorus | 〇 | 〇 | ||
| 1995 | Solution | 〇 | 〇 | ||
| 1995 | キング・オブ・フィルム/巨匠たちの60秒 | Lumière and Company | 〇 | 〇 | オムニバス作品の一篇 |
| 1997 | The Birth of Light | 〇 | 〇 | ||
| 1999 | Volte sempre, Abbas! | 〇 | 〇 | ||
| 2005 | Roads of Kiarostami | 〇 | 〇 | ||
| 2007 | ロミオはどこ? | Where is my Romeo? | 〇 | 〇 | オムニバス『それぞれのシネマ』の一篇 |
| 2007 | Is There a Place to Approach? | 〇 | 〇 | 『ペルシャ絨毯』の15セグメントのうちの1つ | |
| 2013 | The Girl in the Lemon Factory | ✕ | 〇 | キアラ・マラノンも脚本・監督 | |
| 2014 | Seagull Eggs | 〇 | 〇 | ドキュメンタリー |