1. 概要

クレメンス5世(Clemens Quintusクレメンス・クィントゥスラテン語、1264年頃 - 1314年4月20日)は、カトリック教会の第195代ローマ教皇(在位:1305年6月5日 - 1314年4月20日)。本名はベルトラン・ド・ゴ(Bertrand de Gothベルトラン・ド・ゴフランス語)という。彼はフランス王国出身の教皇であり、その治世はフランス王フィリップ4世(端麗王)の強い影響下に置かれた。
クレメンス5世は、テンプル騎士団の解散を決定し、その多くの団員の処刑を承認したことで歴史に名を残している。また、教皇庁をローマからフランスのアヴィニョンへ移転させ、後に「アヴィニョン捕囚」として知られる時代を招いた。この決定は、教皇権の地位とヨーロッパ史に長期的な影響を与え、教皇権の世俗権力への従属を象徴する出来事となった。彼の治世中にはヴィエンヌ公会議が召集され、教会改革や異端問題が議論されたが、その成果は限定的であった。
2. 初期生涯と背景
クレメンス5世の初期の生涯は、フランスのアキテーヌ地方で形成され、その後の教皇としてのキャリアに影響を与える法学と神学の深い教育を受けた。
2.1. 幼少期と教育
ベルトラン・ド・ゴは、1264年頃にアキテーヌ地方のヴィランドロ(Villandrautヴィランドロフランス語)で、ヴィランドロ領主ベラール(Bérardベラールフランス語)の息子として生まれた。彼はトゥールーズ(Toulouseトゥールーズフランス語)で芸術を学び、その後オルレアン(Orléansオルレアンフランス語)とボローニャ(Bolognaボローニャイタリア語)で教会法と民法を修めた。
2.2. 初期キャリア
学業を終えたベルトランは、ボルドーのサン=タンドレ大聖堂(Saint-Andréサン=タンドレフランス語)の参事会員および祭服保管官となった。その後、リヨン大司教であった兄ベラール・ド・ゴ(Bérard de Gotベラール・ド・ゴフランス語)の総代理を務めた。兄ベラールは1294年にアルバーノの枢機卿に任命され、フランスへの教皇特使となった。ベルトラン自身もサン=ベルトラン=ド=コマンジュ(Saint-Bertrand-de-Commingesサン=ベルトラン=ド=コマンジュフランス語)の司教に任命され、その司教座聖堂を大幅に拡張し、装飾する責任を負った。1297年には教皇ボニファティウス8世(Bonifacius VIIIボニファティウス8世ラテン語)の司祭となり、ボルドー大司教に任命された。
ボルドー大司教として、ベルトラン・ド・ゴは名目上はイングランド王の臣下であったが、幼少の頃からフランス王フィリップ4世(端麗王)の個人的な友人であった。
3. 教皇選出

1304年7月に教皇ベネディクトゥス11世が崩御した後、フランス派とイタリア派の枢機卿間の対立により、教皇空位期間が生じた。ペルージャ(Perugiaペルージャイタリア語)で開かれたコンクラーヴェでは両派の勢力が拮抗し、膠着状態が約1年間続いた。この状況下で、ベルトラン・ド・ゴは1305年6月にクレメンス5世として教皇に選出された。彼はイタリア人でも枢機卿でもなかったため、その選出は中立性を示すジェスチャーと見なされた可能性がある。
当時の年代記作家ジョヴァンニ・ヴィッラーニ(Giovanni Villaniジョヴァンニ・ヴィッラーニイタリア語)は、ベルトランが教皇に就任する前に、サントンジュのサン=ジャン=ダンジェリ(Saint-Jean-d'Angélyサン=ジャン=ダンジェリフランス語)でフィリップ4世と正式な合意を結んでいたという噂を記している。この噂が真実であったかどうかは不明だが、将来の教皇が枢機卿団のコンクラーヴェによって条件を課されていた可能性は高い。
選出の2週間後、ベルトランはヴィエンヌ(Vienneヴィエンヌフランス語)で非公式に選出の通知を受け、ボルドーに戻った。ボルドーで彼は正式に教皇として承認され、イングランド王エドワード1世からの贈り物がジョン・オブ・ヘイヴァリングによって贈呈された。当初、ベルトランはヴィエンヌを教皇戴冠式の地として選んだが、フィリップ4世の反対によりリヨン(Lyonリヨンフランス語)に変更された。1305年11月14日、ベルトランはフィリップ4世が臨席する中で盛大に教皇として戴冠した。彼の最初の行動の一つは、9人のフランス人枢機卿を任命することであった。
クレメンス5世の戴冠式では、ブルターニュ公ジャン2世が祝賀行事中に教皇の馬を群衆の中を先導していた。あまりにも多くの観衆が壁の上に押し寄せたため、壁の一つが崩壊し、公爵の上に倒れかかり、彼は4日後に死亡した。
4. 教皇としての治世
クレメンス5世の教皇としての治世は、フランス王フィリップ4世の強力な影響下で、教会とヨーロッパ史に大きな転換点をもたらす主要な出来事が相次いだ。
4.1. フランス王フィリップ4世との関係
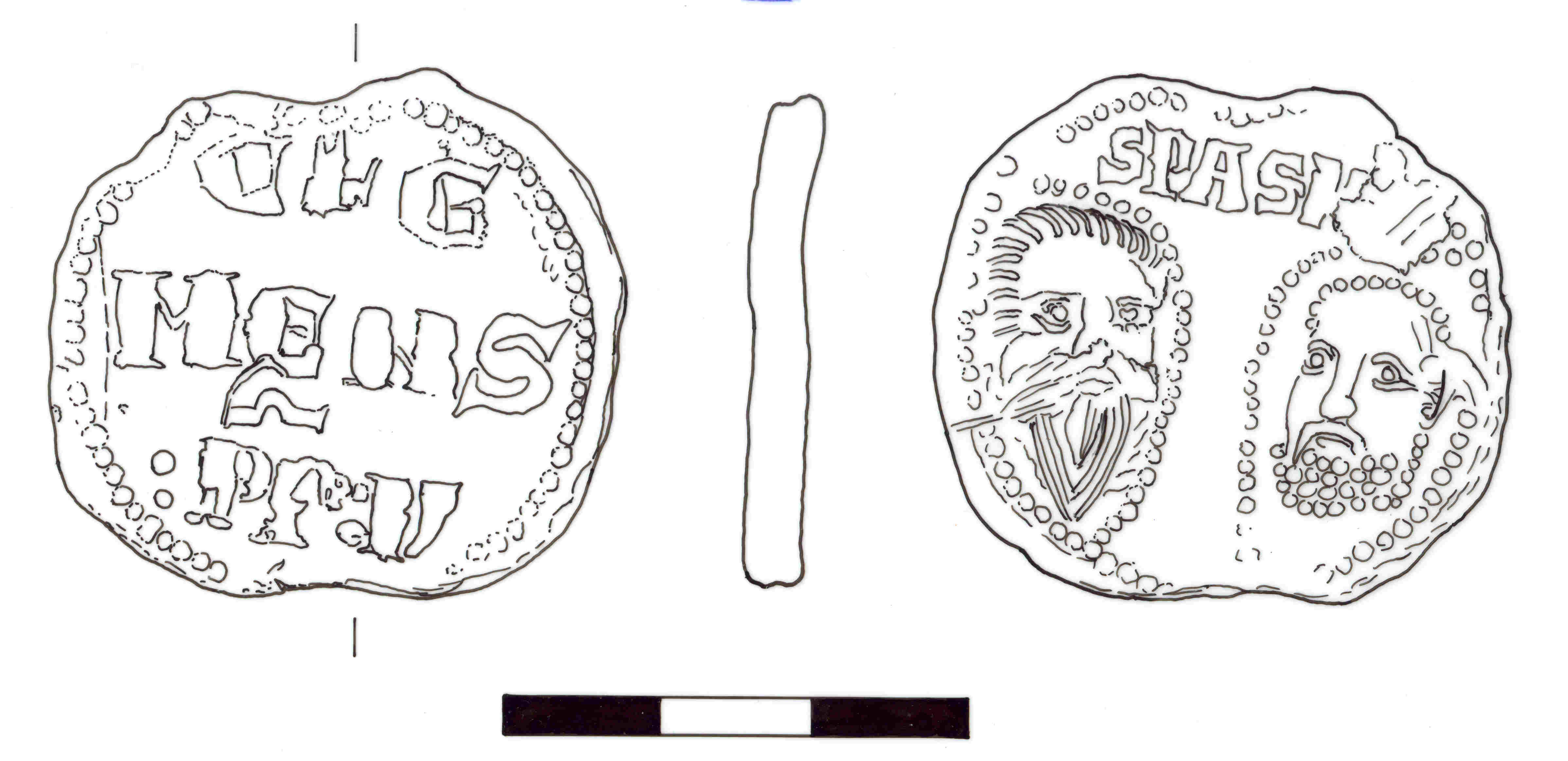
クレメンス5世の教皇職は、当初からフランス王フィリップ4世の強力な政治的・財政的影響下に置かれた。1306年初頭、クレメンス5世は、フランス王に適用される可能性のある教皇勅書『クレリシス・ライコス』(Clericis Laicosクレリシス・ライコスラテン語)の内容を釈明し、さらにボニファティウス8世が世俗君主に対する教皇の優位性を主張し、フィリップの政治計画を脅かした勅書『ウナム・サンクタム』(Unam Sanctamウナム・サンクタムラテン語)を事実上撤回した。これは教皇政策の根本的な変更を意味した。クレメンス5世は病気のため1306年の大半をボルドーで過ごし、その後はポワティエなどで暮らした。
フィリップ4世の弁護士たちは、故ボニファティウス8世に対するギヨーム・ド・ノガレ(Guillaume de Nogaretギヨーム・ド・ノガレフランス語)の異端容疑を再審理するよう圧力をかけた。この容疑は『ウナム・サンクタム』を巡るパンフレット論争で広まっていた。クレメンス5世は、1309年2月2日にアヴィニョンで始まったこの異例の裁判の圧力に屈し、裁判は2年間続いた。証人を召喚する文書の中で、クレメンス5世はボニファティウス8世の無罪に対する個人的な確信と、王の要求を満たす決意の両方を表明した。最終的に、1311年2月、フィリップ4世はクレメンス5世に書簡を送り、この手続きを将来のヴィエンヌ公会議に委ねることを放棄した。クレメンス5世は、アナーニ事件でボニファティウスを拉致したすべての関係者を赦免した。
4.2. テンプル騎士団の弾圧

1307年10月13日の金曜日、フランスで数百人のテンプル騎士団員が逮捕された。この行動は、財政的な動機と、王権の威信を高めるための効率的な王室官僚機構によって行われたと見られる。フィリップ4世がこの動きの原動力であったが、これはクレメンス5世の歴史的評価にも影響を与えた。クレメンス5世の戴冠式のその日から、王はテンプル騎士団を高利貸し、信用膨張、詐欺、異端、ソドミー、不道徳、虐待などの罪で告発した。教皇の良心の呵責は、急成長するフランス国家が教会を待たずに独立して行動するかもしれないという感覚が高まることで増幅された。
フィリップ4世の意向に従い、クレメンス5世は1311年にヴィエンヌ公会議を召集したが、公会議はテンプル騎士団を異端として有罪とすることを拒否した。しかし、教皇は騎士団の評判が悪く、教皇の銀行家として、東方への巡礼者の保護者としての有用性を失っていたと判断し、結局騎士団を解散させた。フランス国内の騎士団の資産はフィリップ4世によって没収され、一部は聖ヨハネ騎士団に譲渡されたが、フィリップ4世は死ぬまでテンプル騎士団の資産を無断で使用し続けた。
異端やソドミーといった虚偽の告発を除けば、テンプル騎士団の有罪か無罪かは、歴史上最も難しい問題の一つである。これは、先行する世代で築き上げられたヒステリックな雰囲気(世俗の支配者と聖職者の間で交わされた過度に激しい言葉や誇張された非難が特徴)と、陰謀論者や疑似歴史家によってこの主題が取り上げられてきたことによる。フィリップ4世は騎士団に多額の借金を抱えていたため、経済的理由が最大の動機であった可能性がある。同様の理由で、フィリップ4世は数年前にユダヤ人やイタリアの金融業者をフランスから追放し、その財産を没収していた。また、フィリップ4世はエルサレムの聖地奪還の使命を自らの手で達成したいと願っており、そのために自らが統制できる新たな騎士団を組織しようとしていた。彼の統制外にあり、強力な名声と富を得ていたテンプル騎士団は、最優先で排除すべき対象であった。さらに、当時のフランスが抱えていた慢性的な財政難、物価上昇、過度な税金に対する不満を鎮めるために、テンプル騎士団は最適な犠牲者であった。
1314年、ジャック・ド・モレー(Jacques de Molayジャック・ド・モレーフランス語)ら騎士団の最高幹部は異端として火刑に処せられたが、ド・モレーは死の際にフィリップ4世とクレメンス5世を呪ったと伝えられている。奇しくも、この二人も同じ年に相次いでこの世を去っている。
4.3. アヴィニョン遷都(アヴィニョン教皇庁)
q=Avignon|position=right
1309年3月、教皇庁は4年間滞在したポワティエから、アヴィニョン近郊のコンタ・ヴァネサン(Comtat Venaissinコンタ・ヴァネサンフランス語)へ移転した。当時、コンタ・ヴァネサンはフランス領ではなく、シチリア国王が神聖ローマ帝国皇帝から与えられた封土であった。
フランス側は、ローマがローマ貴族間の対立と武装民兵の活動により治安が極度に悪化し、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂が火災で焼失するなど危険な状態であったため、安全保障上の理由から、事実上の首都であるカルパントラ(Carpentrasカルパントラフランス語)への移転を正当化した。
しかし、この教皇庁の移転は、イタリアの詩人ペトラルカ(Petrarcaペトラルカイタリア語)が古代ユダヤ人のバビロン捕囚に例えて「アヴィニョン捕囚」(1309年 - 1377年)と呼んだ時代の前触れとなり、「王たちの父」と称されるほど強力であった教皇権が衰退の道を辿る兆候となった。このアヴィニョン捕囚は、世俗権力が教権を掌握した中世の一現象と見なされている。
4.4. ヴィエンヌ公会議

クレメンス5世は、フィリップ4世からの圧力により、1311年にヴィエンヌ公会議を召集した。この公会議の目的は、主にテンプル騎士団問題の処理と教会改革であった。公会議はテンプル騎士団を異端として有罪とすることを拒否したが、教皇は騎士団がその有用性を失い、評判も悪かったと判断し、解散を決定した。
公会議では、オリヴィ(Oliviオリヴィフランス語)の魂に関する誤った主張や、ランベール・ド・ベグ(Lambert de Bègueランベール・ド・ベグフランス語)とベギン(Béguinベギンフランス語)が提唱した異端(地上で人間が完全な状態に達し、罪を犯さなくなるという主張)も非難された。また、聖職者の生活を含む教会改革に関する多くの法令が発布された。
4.5. 十字軍とモンゴルとの関係

クレメンス5世は、中国の福音化のため、フランシスコ会の宣教師ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノ(Giovanni da Montecorvinoジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノイタリア語)を元の首都カンバリク(現在の北京)に派遣した。ジョヴァンニは1294年に北京に到着し、多くの同修道士の協力を得て、死去するまで宣教活動を行い、多くの成果を上げた。北京をはじめとする各地に多くの教会が建設された。1307年、クレメンス5世はジョヴァンニを大司教に任命し、その後さらに多くのフランシスコ会士を補佐司教としたが、目的地に到達できたのは4名のみであった。
クレメンス5世は、イスラム教徒に対するフランク・モンゴル同盟の可能性を探るため、モンゴル帝国と断続的に連絡を取った。1305年4月、モンゴルイルハン朝の支配者オルジェイトゥ(Өлзийтオルジェイトゥモンゴル語)は、ブスカレロ・デ・ギゾルフィ(Buscarello de Ghizolfiブスカレロ・デ・ギゾルフィイタリア語)を団長とする使節団をクレメンス5世、フィリップ4世、そしてイングランド王エドワード1世に派遣した。1307年には、トンマーゾ・ウージ・ディ・シエーナ(Tommaso Ugi di Sienaトンマーゾ・ウージ・ディ・シエーナイタリア語)が率いる別のモンゴル使節団がヨーロッパの君主たちのもとに到着した。しかし、協調した軍事行動は実現せず、同盟の希望は数年で消滅した。
1308年、クレメンス5世は聖地のマムルーク朝に対する十字軍の説教を命じた。その結果、1309年7月にはアヴィニョンの城門前に「貧者の十字軍」が集結し、クレメンス5世は彼らに大赦を与えた。十字軍は1310年初頭に出発したが、聖ヨハネ騎士団は聖地へ向かう代わりに、東ローマ帝国からロドス島を征服した。貧者の十字軍は聖地に到達できず、最終的に遠征は失敗に終わった。
1312年4月4日、ヴィエンヌ公会議でクレメンス5世によって新たな十字軍が公布された。1313年にはオルジェイトゥから西方、特にイングランド王エドワード2世へ別の使節が送られた。同年、フィリップ4世は「十字架を背負い」、レバントへの十字軍に参加する誓いを立てた。
4.6. ローマおよびイタリアとの関係

クレメンス5世の教皇在位期間は、イタリアにとっても壊滅的な時期であった。教皇領は3人の枢機卿に統治が委ねられたが、ローマはコロンナ家(Colonnaコロンナイタリア語)とオルシーニ家(Orsiniオルシーニイタリア語)の派閥争いの戦場と化し、統治不能な状態であった。1310年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ7世(Henricus VIIハインリヒ7世ラテン語)がイタリアに入り、ミラノにヴィスコンティ家(Viscontiヴィスコンティイタリア語)を皇帝代理として確立した。彼は1312年にローマでクレメンス5世の特使によって戴冠したが、1313年にシエーナ(Sienaシエーナイタリア語)近郊で死去した。
フェラーラ(Ferraraフェラーライタリア語)はエステ家(Esteエステイタリア語)を排除して教皇領に編入されたが、教皇軍はヴェネツィア共和国とその住民と衝突した。破門と聖務停止が意図した効果をもたらさなかったため、クレメンス5世は1309年5月にヴェネツィアに対する十字軍を説き、海外で捕らえられたヴェネツィア人は非キリスト教徒と同様に奴隷として売買される可能性があると宣言した。
クレメンス5世は神聖ローマ帝国との関係においては日和見主義者であった。フランスが強大になりすぎることを恐れ、フィリップ4世の弟であるヴァロワ伯シャルル(Charles de Valoisシャルル・ド・ヴァロワフランス語)の立候補を全力で支持することを拒否し、ルクセンブルクのハインリヒ(ハインリヒ7世)を承認した。ハインリヒは1312年にラテラノ大聖堂で教皇代理によって皇帝として戴冠された。しかし、ハインリヒがナポリ王ロベール(Robert d'Anjouロベールフランス語)と対立すると、クレメンスはロベールを支持し、皇帝を破門と聖務停止で脅かした。しかし、ハインリヒの予期せぬ死によって危機は回避された。
4.7. その他の政策と活動
クレメンス5世の治世におけるその他の注目すべき出来事には、ロンバルディア(Lombardyロンバルディアイタリア語)におけるドルチーノ派(Dulciniansドルチーノ派ラテン語)の暴力的弾圧(彼が異端と見なしたもの)と、1313年のクレメンス教令集(Constitutiones Clementinaeクレメンス教令集ラテン語)の公布が含まれる。この教令集は、後にヨハネス22世によって1317年10月25日に勅書『クオニアム・ヌッラ』で再発行された。
また、彼はペルージャ大学、オックスフォード大学、オルレアン大学の設立にも関与した。
5. 死
クレメンス5世は1314年4月20日に崩御した。ある記録によると、彼の遺体が安置されていた教会で夜間に雷雨が発生し、雷が教会を直撃して火災が発生したという。火勢は非常に激しく、消し止められた時には教皇の遺体はほとんど焼失していた。彼は生前の遺言に従い、故郷ヴィランドロに近いユゼスト(Uzesteユゼストフランス語)の参事会教会に埋葬された。
ジャック・ド・モレーが火刑に処される際にフィリップ4世とクレメンス5世を呪ったと伝えられているが、奇しくもこの二人も同じ年に相次いでこの世を去っている。
6. 評価と遺産
クレメンス5世の治世は、教皇庁と中世ヨーロッパ史に大きな影響を与え、その歴史的評価は批判と論争に満ちている。
6.1. 批判と論争
クレメンス5世は、フランス王権への過度な従属、特にフィリップ4世の強力な影響下で行動したことで批判されている。彼の治世は、教皇庁のアヴィニョンへの移転(「アヴィニョン捕囚」)によって象徴され、これは教皇権が世俗権力、特にフランス王権の支配下に置かれたことを示すものと見なされている。
テンプル騎士団の解散過程における彼の役割も、歴史的な論争の的となっている。公会議が騎士団を異端として有罪とすることを拒否したにもかかわらず、教皇が騎士団を解散させたことは、フィリップ4世の政治的・経済的圧力に屈した結果であると広く認識されている。騎士団の財産を没収し、その負債を帳消しにしようとするフィリップ4世の動機が、この弾圧の背後にあったことが指摘されている。この一連の出来事は、教皇権の弱体化と、世俗権力による教会への介入の増大を示すものとして、批判的に扱われることが多い。
6.2. ポップカルチャーにおける描写
クレメンス5世は、テレビドラマ『ナイトフォール』(Knightfallナイトフォール英語)のシーズン2でスティーヴン・フェウェル(Stephen Fewellスティーヴン・フェウェル英語)によって演じられている。