1. 生涯と活動
ジェレミー・リフキンは、その幼少期から教育を経て、多岐にわたる社会活動や著作活動を通じて、環境問題、経済変革、科学技術の倫理、そして持続可能な社会の構築に対する深い洞察と提言を世界に発信し続けている。
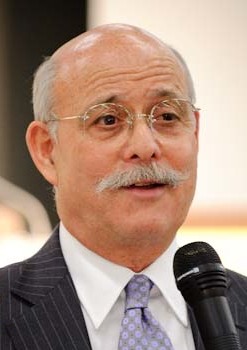
1.1. 幼少期と教育
リフキンは1945年1月26日、コロラド州デンバーで、プラスチックバッグ製造業者である父ミルトン・リフキンと母ヴィヴェット・ラヴェルの間に生まれた。彼はシカゴ南西側で育った。
1967年にペンシルベニア大学を卒業し、ウォートン・スクールで経済学の理学士号を取得した。彼は同大学の卒業生総代を務め、またペンシルベニア大学同窓会からのメリット賞も受賞している。
学生時代からベトナム戦争反対運動に積極的に参加し、平和運動の一員として活動した。その後、タフツ大学フレッチャー法律外交大学院に進学し、国際関係学の修士号(1968年)を取得したが、そこでも反戦活動を継続した。大学院卒業後は、アメリカの貧困地域で奉仕活動を行うVISTA(Volunteers in Service to America)に参加した。
1.2. 1970年代の活動と経済動向財団の設立
1970年代に入り、リフキンは活発な社会運動を展開した。1970年には、建国200周年を「革命的代替案」として提供するために人民建国200周年委員会(People's Bicentennial Commission)を設立した。1973年には、ボストン茶会事件200周年を記念してボストン港で石油会社に対する大規模な抗議行動を組織し、活動家たちが空の石油樽を港に投棄した。これは1973年のOPECによる石油禁輸に続くガソリン価格高騰の直後に行われたもので、後にメディアによって「ボストン石油党事件」と呼ばれた。1975年4月17日から18日には、アメリカ独立戦争の始まりを記念するコンコードの戦いの200周年を祝うためにコンコード橋に陣取り、当時のジェラルド・フォード大統領の記念碑献花を妨害しようと試みた。さらに、1976年7月4日には、人民建国200周年委員会が他の祝典とは異なる代替案として、ワシントンのナショナル・モールで集会を開催した。
1977年にはテッド・ハワードと共に経済動向財団(Foundation on Economic Trends, FOET)を設立した。この財団は、環境、経済、気候変動に関する国内外の公共政策問題に積極的に取り組んでいる。FOETは、新たな動向とその環境、経済、文化、社会への影響を調査し、訴訟活動、公開教育、連合形成、草の根運動を通じて目標達成を目指している。同年、彼は『誰が神を演じるべきか?』を出版し、勃興期のバイオテクノロジー産業に対する主要な批判者の一人となった。
1978年にはランディ・バーバーと共著で『北は再び立ち上がる:1980年代の年金、政治、権力』を出版した。この本とそれに続く著者らのアメリカの労働組合運動、金融界、市民社会組織との連携は、アメリカにおける公的年金基金や労働組合の年金基金の社会的責任投資(SRI)の時代を切り開く助けとなった。ニューヨーク大学の法と社会変革レビュー誌は、「社会的責任投資の概念は、以前は特定の利益団体にのみ関心を持たれていたが、1978年のジェレミー・リフキンとランディ・バーバーによる『北は再び立ち上がる』の出版により、広く注目を集めるようになった」と指摘している。この本は、後にESG(環境、社会、ガバナンス)投資基準へと発展する初期の基礎を築いた。
1.3. 1980年代の活動と思想の展開
1980年代は、リフキンの環境思想と科学技術への批判が具体化し、広範な影響力を持つようになった時期である。
1980年に出版された彼の著書『エントロピー』は、熱力学の概念であるエントロピーが、原子力や太陽エネルギー、都市の衰退、軍事活動、教育、農業、健康、経済、政治にどのように適用されるかを論じた。これは『沈黙の春』、『閉鎖された輪』、『成長の限界』、『スモール・イズ・ビューティフル』の後継として「包括的な世界観」であると『ミネアポリス・トリビューン』は評した。リフキンの著作は、ニコラス・ジョルジェスク=レーゲンが1971年に著した『エントロピー法則と経済過程』で表明された思想に強く影響を受けている。1989年の改訂版『エントロピー:温室効果の世界へ』には、ジョルジェスク=レーゲンが「後書き」を寄稿している。
同年、アメリカ最高裁判所は、遺伝子操作された最初の生命体の特許を認める判決を下した(賛成5名、反対4名)。ジェレミー・リフキンの事務所である人民事業委員会は、遺伝子操作された生物への特許付与はアメリカの特許法でカバーされていないと主張し、米国特許商標庁を支持するアミカス・ブリーフ(法廷助言書)を提出した。多数意見を代表してウォーレン・バーガー最高裁長官は、嘆願者側のブリーフを「恐ろしい悲惨なパレード」と呼び、「関連する区別は、生きたものと無生物の間ではなく、生きているか否かにかかわらず自然の産物と、人間が作った発明との間にある」と主張した。一方、少数意見を代表してウィリアム・ブレナン最高裁判事は、「特許法の適用範囲を拡大または縮小するのは、この裁判所ではなく議会の役割である」と主張し、「特許を求められている組成物(遺伝子操作された微生物)は、公共の関心事項に特有の形で関与する」とさらに示唆した。
1984年5月16日、ジョン・J・シリカ連邦地方裁判所判事は、「遺伝子組み換え生物の環境への意図的な初放出」を伴うはずだった実験を中止させる判決を下した。この訴訟は、ワシントンD.C.に拠点を置く経済動向財団の代表であるジェレミー・リフキンによって提起された。原告は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が「試験にゴーサインを出す」前に、遺伝子組み換え生物を環境に放出することの潜在的なリスクと結果の評価を怠ったことで、国家環境政策法(NEPA)に違反したと主張した。雑誌『サイエンス』は、この判決が「ほとんどの観察者を愕然とさせた」と記録した。シリカ判事は判決の中で、リフキンと彼の弁護団が訴訟で「成功する可能性が高いことを十分に示している」と述べた。また、『サイエンス』は、シリカ判事がNIHに対し、「学術研究者による改変生物の放出を伴うこれ以上の実験を承認しないよう」指示したと報じた。この裁判所の判決は、アメリカおよび世界中で遺伝子組み換え生物の環境放出を規制するプロセスの始まりと評価されている。
1989年には、リフキンはワシントンD.C.に35カ国からの気候科学者と環境活動家を集め、初のグローバル・グリーンハウス・ネットワーク会議を開催した。同年、彼は気候変動と関連する環境問題についてハリウッドで一連の講演を行い、映画、テレビ、音楽業界の多様なリーダーたちを対象に、キャンペーンのための組織化を目的とした。その直後、二つのハリウッドの環境団体、アース・コミュニケーションズ・オフィス(ECO)と環境メディア協会が設立された。
また1989年、リフキンは環境保護主義者のグループと共に、NASAのガリレオ探査機を搭載するロケットの打ち上げを阻止しようと試みた。彼らは、ロケットが爆発する「非常に高いリスク」と、アメリカ領土に「致死的なプルトニウムを飛散させる」危険性があると主張した。この訴訟は最終的に却下され、ガリレオ計画は成功した。
1.4. 1990年代の活動と労働・遺伝子工学への視点
1990年代、リフキンは食肉産業、労働市場、遺伝子工学、環境問題に関する重要な著作を発表し、社会に大きな影響を与えた。
1992年、リフキンは著書『牛肉の終焉』を出版した。この本は、『ワシントン・ポスト』から「新鮮な思考と論理的な議論...信頼できる研究と論理的な結論を組み合わせたもの」として、「あらゆる偏見のない人々を食肉売り場を素通りさせるに十分な経済的、医学的、環境的、倫理的な議論を提供している」と評価された。
同年、リフキンと経済動向財団は、すべての遺伝子組み換え食品に政府による表示を義務付ける「ピュア・フード・キャンペーン」を開始した。このキャンペーンは、国内を代表する1,500人以上のシェフによって主導された。
1993年、リフキンはグリーンピース、レインフォレスト・アクション・ネットワーク、パブリック・シチズンなど6つの環境団体による連合体である「ビヨンド・ビーフ・キャンペーン」を開始した。この運動の目標は、牛肉の消費量を50%削減することであり、家畜からのメタン排出量が二酸化炭素の23倍もの温暖化効果を持つと主張した。
1995年に出版された彼の著書『労働の終焉』は、オートメーション、技術による代替、企業の人員削減、および雇用の未来に関する今日のグローバルな議論を形成するのに貢献したと評価されている。2011年にオートメーションと技術による雇用の代替を巡る論争の激化について報じた『エコノミスト』誌は、リフキンが1996年の『労働の終焉』の出版でこの傾向に注目したことを指摘した。同誌はさらに、「機械が労働者になるほど賢くなったとき、つまり資本が労働になったとき、何が起こるのか?」と問いかけた。そして、『エコノミスト』は、「これは、社会評論家であるジェレミー・リフキンが1996年に出版した著書『労働の終焉』で主張しようとしていたことだ...リフキンは予言的に、社会は新たな段階に入りつつあり、そこで消費されるすべての財とサービスを生産するために必要な労働者の数はますます少なくなるだろうと論じた。『今後数年間で、より洗練されたソフトウェア技術が文明をほぼ無労働者の世界へと近づけるだろう。そのプロセスはすでに始まっている』と彼は書いた」と述べた。
1998年に出版された彼の著書『バイオテック・センチュリー』は、遺伝子ビジネスの新時代に付随する問題に取り組んでいる。『ネイチャー』誌はこの本のレビューで、「リフキンは、遺伝子技術が提起する現実的および潜在的な危険性と倫理的難題に注目を促すという点で、最善の仕事をしている...科学機関が科学の一般理解に苦慮している今、科学技術のトレンドを一般に伝えるリフキンの成功から学ぶべきことは多い」と評している。
『バイオテック・センチュリー』の中で、リフキンは「遺伝子工学は究極のツールである」と主張している。「遺伝子技術によって、我々は生命の遺伝的設計図そのものに対する制御を獲得する。このような前例のない力が実質的なリスクを伴わないと考える合理的な人間がいるだろうか?」また、彼は、複製が生殖を部分的に置き換えることや、「遺伝的にカスタマイズされ大量生産された動物のクローンが、その血液や乳中に大量の安価な化学物質や薬物を分泌する化学工場として人間用に利用される可能性がある」といった変化を強調している。
リフキンの生物科学における活動には、動物の権利と世界中の動物保護の擁護も含まれる。
1.5. 2000年代以降の活動とグローバルな提言
2000年代以降、リフキンは持続可能な経済と社会の構築に向けた新たなパラダイムを提唱し、世界各国の政府や国際機関に影響を与え続けている。
2000年に出版されたリフキンの著書『アクセス経済』は、社会が市場における財産の所有から、ネットワークにおけるサービスへのアクセスへと移行しつつあり、それによって共有経済が生まれるという概念を初めて導入した。Journal of Consumer Researchによると、「アクセス現象は、リフキン(2000年)によって一般向けのビジネス誌で初めて記録された。彼は主に企業間セクターを調査し、我々がアクセスの時代に生きていると主張する。この時代では、所有権体制がアクセス体制へと変化しており、それはサプライヤーのネットワークによって管理される資産の短期的な限定使用を特徴とする」と述べている。
リフキンは2002年に『水素革命:世界的なエネルギーウェブの創造と地球上の権力の再分配』を出版した。同年、当時の欧州委員会委員長であったロマーノ・プローディの顧問を務めていたリフキンは、欧州連合(EU)をグリーン水素経済パラダイムへと変革するための数十億ユーロ規模の研究開発計画を約束する戦略的ホワイトペーパーを作成した。リフキンは2002年10月にプローディと共にEU会議に参加し、「化石燃料への依存から脱却し、21世紀の最初の『水素経済』超大国となるためのヨーロッパの協調的な長期計画」を発表した。プローディ委員長は、EUの水素R&Dイニシアティブが、1960年代から1970年代の米国の宇宙計画が米国にとって重要であったのと同様に、ヨーロッパの未来にとって重要であると述べた。
『水素革命』の出版後(2002年)、リフキンは米国とヨーロッパの両方で、再生可能エネルギー源によって生成される水素の政治的推進に取り組んだ。米国では、リフキンはグリーン水素連合の設立に尽力した。この連合は13の環境・政治団体(グリーンピースやMoveOn.orgを含む)で構成され、再生可能な水素ベースの経済構築にコミットしている。
彼の2004年の著書『ヨーロピアン・ドリーム』は国際的なベストセラーとなり、2005年にはドイツでその年の最優秀経済書に贈られるコリネ国際文学賞を受賞した。『ビジネスウィーク』誌はこの本のレビューで、「リフキンは、(ヨーロッパの)ビジョンのために説得力のある議論を展開しており、それがグローバルな理想としてアメリカン・ドリームを凌駕していると述べている...アメリカとヨーロッパの精神の違いに関する魅力的な研究である」と指摘した。
2009年、リフキンは『共感の時代:危機の時代における地球規模の意識への競争』を出版した。『ハフィントン・ポスト』誌の書評で、アリアナ・ハフィントンは次のように書いている。「リフキンは珍しい種族であり、その不在がしばしば正当に嘆かれている公共知識人である。リフキンは...人間が本質的に攻撃的で、貪欲で、自己中心的であるという結論につながるのではなく、『根本的に共感的な種』、リフキンが『共感的人間(Homo empathicus)』と呼ぶ存在であるという新たな科学的発見を検証している...『共感の時代』は、人間の本性に関する従来の見方に大胆に挑戦し、人類が共有され相互につながった世界に生きる大家族であると見なす対抗物語に置き換えようとする魅力的な本である」。
2011年、リフキンは『第三次産業革命:横断的な力がエネルギー、経済、そして世界をいかに変革するか』を出版した。この本はニューヨーク・タイムズのベストセラーとなり、19カ国語に翻訳された。2014年までに、中国だけでも約50万部が印刷された。
2012年5月10日、リフキンはグローバル・グリーン・サミット2012で基調講演を行った。この会議は韓国政府とグローバル・グリーン成長機構(GGGI)が主催し、経済協力開発機構(OECD)と国際連合環境計画(UNEP)が共催した。当時の韓国の李明博大統領も会議で演説し、グリーン経済を推進するために第三次産業革命の概念を受け入れた。
2012年12月、『ブルームバーグ ビジネスウィーク』は、新たに選出された中国の李克強国務院総理がリフキンのファンであり、『第三次産業革命:横断的な力がエネルギー、経済、そして世界をいかに変革するか』に「細心の注意を払うよう国の学者たちに伝えた」と報じた。
リフキンは2012年にイタリア=アメリカ財団から「アメリカ賞」を受賞した。彼は現在、ワシントンD.C.の郊外、メリーランド州ベセスダのオフィスで活動している。
2014年4月、リフキンは『限界費用ゼロ社会:モノのインターネット、協働的コモンズ、資本主義の終焉』を出版した。『フォーチュン』誌はこの本を「その範囲において称賛に値する...我々の経済の未来が次の世代にとって何をもたらすかについての心温まる物語」と評した。この本は15カ国語に翻訳された。
2015年春、リフキンはベルギーのハッセルト大学から名誉博士号を授与された。また、2015年秋にはベルギーのリエージュ大学からも名誉博士号を授与された。
2015年11月、『ハフィントン・ポスト』は北京から、「中国の李克強首相はジェレミー・リフキンの著書『第三次産業革命』を読んだだけでなく、それを真剣に受け止めている。彼と彼の同僚たちは、10月29日に北京で発表された中国の第13次五カ年計画の核とした」と報じた。『ハフィントン・ポスト』はさらに、「中国の未来に向けたこの青写真は、毛沢東の死と1978年の鄧小平による改革開放以来の、最も重大な方向転換を示している」と述べた。
2016年には、TIRコンサルティング・グループLLCと、その社長であるリフキンが、ロッテルダム-ハーグ都市圏とルクセンブルク大公国の両方から委託を受け、それぞれの管轄区域をゼロエミッションの第三次産業革命インフラと経済に変革するための地域マスタープランの策定を監督した。両地域では、TIRコンサルティング・グループのチームと協力して、気候変動に対処し、それぞれの経済と社会を「グリーン化」するための広範なイニシアティブを構想し実行するため、市民会議が設立された。
2017年1月31日、欧州中央銀行は「未来へ:ヨーロッパのデジタル統合市場」をテーマとする会議を主催し、リフキンは欧州連合をスマートな第三次産業革命パラダイムに変革することに関する基調講演を行った。2017年2月7日、欧州委員会と欧州地域委員会はブリュッセルで、「ヨーロッパへの投資:第三次産業革命に向けたスマートシティおよび地域連合の構築」をテーマとする会議を共催した。ジェレミー・リフキンは、欧州委員会のマロシュ・シェフチョビッチ副委員長および欧州地域委員会のマルック・マルックラ委員長と共に、欧州連合全体でのスマートシティとスマート地域のアジェンダを発表した。
ジェレミー・リフキンは、VICEメディアが製作した長編ドキュメンタリー映画『第三次産業革命:過激な新しい共有経済』のエグゼクティブ・共同プロデューサー兼主演を務めている。19カ国語に字幕が付されたこの映画は、2017年にトライベッカ映画祭でプレミア上映され、2018年からはYouTubeで公開されている。2023年5月現在、この映画は800万回視聴されている。
2019年9月、リフキンは『グリーン・ニューディール:なぜ化石燃料文明は2028年までに崩壊し、地球上の生命を救う大胆な経済計画』を出版した。『フォーブス』誌はこの本のレビューで、「ジェレミー・リフキンは、欧州連合の長期経済ビジョンであるスマート・ヨーロッパの主要な設計者であり、中国の第三次産業革命ビジョンの主要な顧問である...彼の新しい著書『グリーン・ニューディール』は、崩壊しつつある20世紀の化石燃料時代の中で、米国をそのまどろみから目覚めさせようとする本質的な試みである」と指摘した。
同年、欧州委員会とその委員長であるウルズラ・フォン・デア・ライエンは、2050年までにヨーロッパを「世界初の気候中立大陸」にする計画である欧州グリーンディールを発表した。欧州委員会は、「第三次産業革命を牽引する」という名目で、欧州経済と社会の根本的な変革を示す一連の提案、プロジェクト、イニシアティブを提示した。
2020年12月、リフキンは気候変動への取り組みに関する功績を称えられ、第13回ドイツ持続可能性賞を受賞した。この賞は、ドイツの元外務大臣、副首相、経済大臣、環境大臣であったジグマール・ガブリエルによる称賛の辞と共にリフキンに贈られた。
2021年、ジェレミー・リフキンとTIRコンサルティング・グループLLCおよびパートナーは、上院多数党院内総務チャック・シューマーのために用意された16兆ドル規模、20年間の「アメリカ3.0レジリエント・インフラ計画」を発表した。この計画は、7月29日にブルームバーグの記事で「エネルギーの第一人者は、縮小する米国のインフラ計画に期待外れ」という見出しで最初に報じられた。
アメリカ3.0インフラ変革計画(2022年~2042年)は、21世紀経済のためのスマート・デジタル・ゼロエミッション型第三次産業革命インフラを拡大、展開、管理するための大規模な投資を詳細に記している。この計画は、2022年から2042年の期間に平均1500万から2200万人の新規雇用を創出すると予測されている。投資された1ドルごとに、2022年から2042年の間に2.9 USDのGDPが返還されると予測されている。ブルームバーグの記事は、「約20年間、米国の作家で気候活動家であるジェレミー・リフキンは、彼が第三次産業革命と呼ぶものに向けて、ヨーロッパや中国の政府に経済を再構築する方法について助言してきた」と指摘した。
リフキンはまた、デイビッド・アッテンボローが出演するBBCのドキュメンタリーシリーズ『ア・パーフェクト・プラネット』の第5話(最終話)で、経済・環境に関する解説を提供した。
2022年11月、リフキンは『レジリエンスの時代:再野生化する地球上での存在の再考』を出版した。『フィナンシャル・タイムズ』紙はこの本のレビューで、「...この影響力のある米国の思想家は...人類がレジリエンスの時代へと移行しており、それは自然界や互いとの関係を変革する可能性があると主張している...リフキンは、生産性が再生性へと、国内総生産が生活の質の指標へと変わる、広範な経済的・社会的変化の未来を見ている。消費主義、多国籍企業、グローバリゼーションは衰退し、『エコ・スチュワードシップ』、ハイテク協同組合、そして『グローカライゼーション』が栄える。この本は、多くの読者にとって魅力的である一方で、他の人々を激怒させること間違いなしである。人間が引き起こし、いまだに解決に苦しんでいる環境問題に対処する必要性について何十年も警告してきた作家にとって、それは決して珍しいことではない」と記した。
1.6. 2024年の活動
2024年、リフキンは『プラネット・アクア:宇宙における私たちの家を再考する』を出版した。この本は、地球上の水資源の重要性と、それを取り巻く課題について論じている。
2. 主要な著作と思想
ジェレミー・リフキンの思想は、熱力学の概念から出発し、現代の資本主義社会が抱える問題点を深く批判し、持続可能で共感に満ちた未来社会の青写真を描いている。彼の著作は、エネルギー、労働、環境、技術といった多岐にわたる分野にわたる。
2.1. エントロピーと環境思想
リフキンの核となる思想の一つは、1980年に出版された著書『エントロピー』に集約されている。この著作は、熱力学第2法則、すなわちエントロピー増大の法則を社会、経済、環境問題に応用し、世界を再解釈しようとする試みである。彼は、地球のエネルギーや資源が有限であり、利用可能なエネルギーが徐々に減少し、無秩序が増大していくというエントロピーの法則を、人類社会の発展モデルに当てはめて批判した。
この考え方の根底には、ニコラス・ジョルジェスク=レーゲンの1971年の著書『エントロピー法則と経済過程』が強く影響している。リフキンは、無限の成長を前提とする現代経済システムが、このエントロピーの法則に逆行するものであり、最終的には資源の枯渇と環境の劣化をもたらすと主張した。彼は、初期から環境保全と資源枯渇問題に対する強い批判的視点を持ち、有限な地球資源の効率的な利用と持続可能な社会への転換の必要性を訴えた。
2.2. 現代社会批判と新たな経済パラダイムの提案
リフキンは、一連の著作を通じて、現代社会が抱える根深い問題点を鋭く批判し、それに対する新たな経済的・社会的パラダイムを提案してきた。
『牛肉の終焉』(1992年)では、大規模な食肉産業が環境に与える負荷(メタン排出、森林破壊など)と、それに伴う健康問題、倫理的問題を指摘し、持続可能な食糧システムへの移行を促した。
『労働の終焉』(1995年)では、情報技術とオートメーションの進化が、過去の産業革命とは異なり、肉体労働だけでなく知的労働の分野でも恒久的な雇用減少をもたらし、労働の概念そのものが変容すると論じた。彼は、この「無労働者の世界」において、政府と市民社会が連携し、新たな社会部門(例えば、社会サービスや環境再生など)での雇用創出や、ボランティア活動の活発化を通じて、市場経済の外部に位置する「社会経済」を構築する必要性を提唱した。
『バイオテック・センチュリー』(1998年)では、遺伝子工学や生命工学技術が、人間のゲノム操作、クローン技術、遺伝子組み換え作物の商業化といった倫理的に問題のある領域に踏み込んでいることを指摘し、生命の商業化や生命体の「発明」に対する規制の必要性を訴えた。彼は、科学技術の進歩がもたらす「前例のない力」が「実質的なリスク」を伴うことを強調し、人類が生命の「遺伝的設計図」を制御する際に直面する倫理的難題を提起した。
『アクセス経済』(2000年)では、現代社会がモノの「所有」から「アクセス」へと移行していることを描いた。つまり、製品そのものを購入するのではなく、サービスとしての利用権や一時的なアクセス権を重視する経済へと変化していると主張した。これは、企業が所有権を手放さず、顧客に短期的な使用権をネットワークを通じて提供する「共有経済」や「サブスクリプション型経済」の概念を先駆的に提示したものであり、現代のデジタルプラットフォーム経済の台頭を予見していた。
これらの著作を通じて、リフキンは資本主義の限界、技術進歩がもたらす負の側面、そして生命の倫理的な問題に対し、批判的な視点を提供するとともに、市場経済の外にある「協働的コモンズ」や「アクセス経済」といった新たな社会経済モデルを提案し、持続可能な発展のための代替案を模索した。
2.3. 持続可能な未来と第三次産業革命
リフキンは、数々の著作を通じて、持続可能な未来社会の実現に向けた具体的な青写真と、そのための核となる概念を提示してきた。
『水素革命』(2002年)では、再生可能エネルギー源によって生成される水素を基盤とした新たなエネルギーインフラ「水素経済」の可能性を提唱した。彼は、水素が従来の化石燃料に代わるクリーンなエネルギーキャリアとなり、世界的なエネルギーネットワークの構築を可能にすると考えた。
『共感の時代』(2009年)では、人間の共感能力こそが、地球規模の危機に直面する現代社会を救う鍵であると論じた。彼は、歴史を通じて人間の意識が部族的なものから国家、そしてグローバルな意識へと拡大してきたことを示し、情報通信技術の発展がこの共感の範囲をさらに広げ、「共感的人間(Homo empathicus)」としての新たな人類の可能性を開くと主張した。
これらの思想を集大成し、最も広範な影響を与えたのが『第三次産業革命』(2011年)である。リフキンは、再生可能エネルギー、エネルギーインターネット、3Dプリンターによる分散型製造、IoTによるデータ共有、そして共有経済という5つの柱を組み合わせることで、持続可能で分散型の経済システムが構築されると提唱した。これは、数百万の建物が小さな「発電所」となり、エネルギーを共有ネットワーク上で取引し、情報共有によって効率的な生産と消費が実現される世界像である。
続く『限界費用ゼロ社会』(2014年)では、IoTとデータ共有の進展により、多くの財やサービスの「限界費用」がゼロに近づき、従来の資本主義経済の枠組みが崩壊し、市場経済と並行して「協働的コモンズ」が台頭すると予見した。協働的コモンズでは、人々が情報を共有し、モノを共同で生産・利用することで、富が分散され、新たな形の社会価値が生まれるとした。
『グリーン・ニューディール』(2019年)では、気候変動対策と経済活性化を同時に実現する政策パッケージとしての「グリーン・ニューディール」を提案し、化石燃料文明から再生可能エネルギー主導の社会への緊急な移行を訴えた。彼は、この移行が2028年までに完了しなければ、地球の生態系が取り返しのつかない打撃を受けると警鐘を鳴らした。
そして、『レジリエンスの時代』(2022年)では、気候変動や生態系の崩壊に直面する中で、人類が「効率性」を追求する産業時代の思考から、「レジリエンス」(回復力、適応力)を重視する時代へと移行する必要性を論じた。彼は、地域に根ざしたエコ・スチュワードシップ、ハイテク協同組合、グローカライゼーションといった概念を通じて、自然との共生と相互依存に基づく新たな社会関係を構築することが、地球と人類の未来を再構築する鍵であると主張している。
3. 国際的な影響力と諮問活動
ジェレミー・リフキンは、その革新的な経済・社会理論を通じて、世界各国の政府や国際機関に対し、重要な政策立案に関する諮問役割を果たし、具体的な影響力を行使してきた。
特に、彼は「第三次産業革命」の長期的な経済持続可能性計画の主要な提唱者であり、この計画は2007年に欧州議会によって正式に承認された。2002年には、当時の欧州委員会委員長であったロマーノ・プローディの顧問として、欧州連合を数十億ユーロ規模のグリーン水素経済パラダイムへと変革する戦略的なホワイトペーパーを策定した。プローディ委員長は、このEUの水素R&Dイニシアティブを、1960年代から1970年代の米国の宇宙計画に匹敵する、ヨーロッパの未来にとって極めて重要なものと位置づけた。2017年には、欧州中央銀行の会議で基調講演を行い、EUをスマートな第三次産業革命パラダイムへと変革する構想について語った。また、欧州委員会副委員長のマロシュ・シェフチョビッチや欧州地域委員会委員長のマルック・マルックラと共に、EU全体でのスマートシティおよびスマート地域のアジェンダを発表した。2019年には、欧州委員会とその委員長であるウルズラ・フォン・デア・ライエンが、「第三次産業革命を牽引する」というスローガンの下、ヨーロッパを2050年までに「世界初の気候中立大陸」にする「欧州グリーンディール」を発表しており、これはリフキンの思想が政策に大きな影響を与えていることを示している。
アジア地域においても、リフキンは重要な役割を担っている。2012年には、韓国政府とグローバル・グリーン成長機構(GGGI)が主催するグローバル・グリーン・サミットで基調講演を行い、当時の韓国の李明博大統領は、グリーン経済を推進するために第三次産業革命の概念を受け入れた。また、2012年12月には、中国の李克強国務院総理がリフキンの著書『第三次産業革命』を熟読し、その思想が2015年10月に発表された中国の第13次五カ年計画の核に取り入れられたと報じられた。このことは、中国の経済と社会の方向性を大きく転換させるものとして注目された。
国際的な影響力は、数々の受賞歴や名誉博士号にも表れている。彼は2012年にイタリア=アメリカ財団から「アメリカ賞」を受賞した。2005年には、彼の著書『ヨーロピアン・ドリーム』がドイツでその年の最優秀経済書としてコリネ国際文学賞を受賞している。さらに、2015年にはベルギーのハッセルト大学とリエージュ大学から名誉博士号を授与された。2020年12月には、気候変動への取り組みに関する功績を称えられ、第13回ドイツ持続可能性賞を受賞し、元外務大臣のジグマール・ガブリエルから授与された。
4. 評価と批判
ジェレミー・リフキンは、その広範な著作と活動を通じて、世界中で多大な影響力を持ち、肯定的な評価と同時に、厳しい批判にも晒されてきた。
4.1. 肯定的評価
リフキンは、その思想と活動を通じて、環境問題、経済変革、科学技術の倫理といった分野で重要な貢献を果たし、高く評価されている。
『ヨーロピアン・エナジー・レビュー』は、「おそらく、欧州連合の野心的な気候変動とエネルギー政策に、ジェレミー・リフキンほど大きな影響を与えた著者や思想家はいないだろう」と評している。実際に、彼はEUの長期経済ビジョンである「スマート・ヨーロッパ」の主要な設計者であり、欧州グリーンディールの発表など、EUの政策決定にその思想が色濃く反映されている。
米国では、彼は数多くの議会委員会で証言を行い、環境、科学、技術に関連する様々な問題について責任ある政府政策を確保するための訴訟活動で成功を収めてきた。『バージニア法と技術ジャーナル』は彼の活動を「対立者の目を通したバイオテクノロジー」と題して取り上げ、彼が環境保護と技術規制の分野で重要な役割を果たしたことを示唆している。
憂慮する科学者同盟は、リフキンのいくつかの出版物を消費者にとって有用な参考資料として引用している。『ニューヨーク・タイムズ』はかつて、「学術界、宗教界、政界の他の人々は、ジェレミー・リフキンを、大胆に考え、物議を醸す問題を提起し、社会的および倫理的な予言者として貢献する意欲を称賛している」と述べた。
また、『ネイチャー』誌は、彼の著書『バイオテック・センチュリー』の書評で、「リフキンは、遺伝子技術によって引き起こされる現実的および潜在的な危険性と倫理的難題に注意を促すという点で、最も優れた仕事をしている...科学機関が科学の一般理解に苦慮している現在、彼らは科学技術のトレンドを一般に伝えるリフキンの成功から多くを学ぶことができる」と指摘しており、彼の複雑な科学技術の概念を一般大衆に分かりやすく伝える能力が高く評価されている。
4.2. 批判と論争
一方で、リフキンの著作は、その科学的厳密性の欠如や、自身の見解を宣伝するために用いた戦術のため、物議を醸すことが多い。彼は経済学と国際関係学を専攻しており、正統な科学教育を受けた経験がないことが批判の対象となる。
その批判の例として、『エンロピー』という著書について、熱力学第2法則を十分に理解せずに、自意的に解釈したという指摘がある。韓国の科学ジャーナリストであるイ・ドクファンは、「エントロピー」の概念が熱力学の範囲を逸脱していると批判した。
また、タイム誌は1989年のプロフィール記事で、ジェレミー・リフキンを「科学界で最も憎まれた男」(The Most Hated Man In Science)と表現し、「『忌まわしい否定の男』とも呼ばれる彼は、新しい技術に対する制御されていない実験の危険性を警告する」と報じた。記事は、「リフキンが遺伝子研究の正確な規制を求めるのは確かに正当である。個人の健康と環境を保護するためだ。しかし、科学者たちを狂った魔法使いや倫理に反するストレンジラブ博士の弟子と呼ぶリフキンの激しい攻撃の公平性については、十分に疑問視する理由がある。リフキンが最も成功するとき、彼は基礎研究を遅らせ、医療の進歩を阻害し、おそらく経済にさえ損害を与える可能性がある」と述べている。遺伝学者であるノートン・ジンダーは、リフキンを「愚か者」「扇動者」と呼んだと報じられている。これに対し、リフキン本人は「そのような批判は、彼が正しい道を進んでいることの証拠に過ぎない」と応じた。
さらに、彼の1984年の著書『アルジェニー』については、進化生物学者であるスティーヴン・ジェイ・グールドが厳しい批判を展開している。グールドは、1985年の『ディスカバー』誌の記事(後にエッセイ集『嵐の中のウニ』(1987年、ペンギンブックス)に再録)で次のように述べている。
:「私は『アルジェニー』を、学術書を装った反知性主義的なプロパガンダの巧みに構築された小冊子と見なす。重要な思想家による真剣な知的著作として宣伝された書籍の中で、これほど粗悪な著作を読んだことはない。実に残念なことだ、なぜならその根深い問題は悩ましく、リフキンが進化系統の整合性を尊重する基本的な訴えには同意するからだ。しかし、欺瞞的な手段は良い目的を損なうものであり、私たちはリフキンの人間的な結論を、彼自身の嘆かわしい戦術から救い出さなければならない。」
グールドは、リフキンの主張が科学的厳密性を欠き、藁人形論法などの論理的誤謬を用いていると批判した。
5. 著作リスト
ジェレミー・リフキンが著述した書籍を年代順に以下に記す。
- 1973年: 『革命をアメリカ流に実行する方法:建国200周年宣言』(How to Commit Revolution American Style: Bicentennial Declaration) - ジョン・ロセンとの共著
- 1975年: 『コモン・センスII:企業暴政に反対する理由』(Common Sense II: The Case Against Corporate Tyranny)
- 1977年: 『自分の仕事を所有せよ:働くアメリカ人のための経済民主主義』(Own Your Own Job: Economic Democracy for Working Americans)
- 1977年: 『誰が神を演じるべきか?:生命の人工創造とそれが人類の未来に意味すること』(Who Should Play God? The Artificial Creation of Life and What it Means for the Future of the Human Race) - テッド・ハワードとの共著
- 1978年: 『北は再び立ち上がる:1980年代の年金、政治、権力』(The North Will Rise Again: Pensions, Politics and Power in the 1980s) - ランディ・バーバーとの共著
- 1979年: 『出現する秩序:不足の時代の神』(The Emerging Order: God in the Age of Scarcity) - テッド・ハワードとの共著
- 1980年: 『エントロピー:新しい世界観』(Entropy: A New World View) - テッド・ハワードとの共著、ニコラス・ジョルジェスク=レーゲンによる後書き
- 1983年: 『アルジェニー:新しい言葉-新しい世界』(Algeny: A New Word-A New World) - ニカノル・ペルラスとの共著
- 1985年: 『異端者の宣言』(Declaration of a Heretic)
- 1987年: 『タイム・ウォーズ:人類史における主要な対立』(Time Wars: The Primary Conflict In Human History)
- 1990年: 『グリーン・ライフスタイル・ハンドブック:地球を癒す1001の方法』(The Green Lifestyle Handbook: 1001 Ways to Heal the Earth) - リフキン編集
- 1991年: 『バイオスフィア政治学:新しい世紀のための新しい意識』(Biosphere Politics: A New Consciousness for a New Century)
- 1992年: 『牛肉の終焉:牛文化の興隆と衰退』(Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture)
- 1992年: 『投票をグリーンに:90年代における政治的選択をするための完全な環境ガイド』(Voting Green: Your Complete Environmental Guide to Making Political Choices In The 90s) - キャロル・グリューネワルド・リフキンとの共著
- 1995年: 『労働の終焉:地球規模の労働力減少とポスト市場時代の夜明け』(The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era)
- 1998年: 『バイオテック・センチュリー:遺伝子を駆使し、世界を作り変える』(The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World)
- 2000年: 『アクセス経済:人生のすべてが有償体験となるハイパー資本主義の新文化』(The Age Of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-For Experience)
- 2002年: 『水素革命:世界的なエネルギーウェブの創造と地球上の権力の再分配』(The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth)
- 2004年: 『ヨーロピアン・ドリーム:ヨーロッパの未来像がいかに静かにアメリカン・ドリームを凌駕しているか』(The European Dream: How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream)
- 2010年: 『共感の時代:危機の時代における地球規模の意識への競争』(The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness In a World In Crisis)
- 2011年: 『第三次産業革命:横断的な力がエネルギー、経済、そして世界をいかに変革するか』(The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World)
- 2014年: 『限界費用ゼロ社会:モノのインターネット、協働的コモンズ、資本主義の終焉』(The Zero Marginal Cost Society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism)
- 2019年: 『グリーン・ニューディール:なぜ化石燃料文明は2028年までに崩壊し、地球上の生命を救う大胆な経済計画』(The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028, and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth)
- 2022年: 『レジリエンスの時代:再野生化する地球上での存在の再考』(The Age of Resilience: Reimagining Existence on a Rewilding Earth)
- 2024年: 『プラネット・アクア:宇宙における私たちの家を再考する』(Planet Aqua: Rethinking Our Home in the Universe)