1. 生い立ちと背景
若松孝二は、1936年4月1日に宮城県遠田郡涌谷町の貧しい米農家の家庭に生まれた。彼の父親は家畜商で獣医師でもあったが、大酒飲みであり、若松は幼い頃からこの父親に反抗しながら育った。
1.1. 成長過程と形成期における経験
若松は農業高校を2年生の時に中退し、家出して東京へ上京した。上京後は様々な職を転々とし、職人見習いや新聞配達などの肉体労働を経験した。その後、新宿の安田組の大幹部であったヤクザの荒木恷あらきいく日本語の下で、ヤクザの下働きとして活動した時期もある。1957年には、チンピラ同士の諍いから逮捕され、半年間拘置所に拘禁され、執行猶予付きの判決を受けた。この時の経験は、彼の人生観や後の映画制作に大きな影響を与えたとされ、監督デビュー作である『甘い罠』については、「警官を殺すために映画監督になった」と豪語するほど、警察官殺しをテーマにした内容となっている。
2. 経歴
若松孝二は、映画監督としてのキャリアをテレビ映画の助監督としてスタートさせた。俳優の大瀬康一は、若松が『月光仮面』で擬音助手を務めていたと証言している。また、弟子の井上淳一は、若松が新宿の安田組にいた頃、撮影現場の交通整理をしていたことがきっかけで助監督になったと語っている。ある時、シナリオの改変に腹を立ててプロデューサーを殴り、その場でクビになったことが、彼のキャリアの転機となった。
2.1. 映画界への進出と初期の活動
プロデューサーを殴って解雇された後、ピンク映画の企画が巡ってきたことが若松孝二の映画監督としての道を拓いた。1963年、彼はピンク映画『甘い罠』で映画監督としてデビューした。本作の制作にあたっては、若松自らが制作費の150.00 万 JPYを投じて撮影を行った。低予算ながらも、その圧倒的な迫力ある映像はピンク映画としては異例の集客力を示し、若松は「ピンク映画の黒澤明」と形容されるほどのヒット作を量産するようになった。
日活では、1963年から1965年にかけて、当時の扇情的な話題に基づいた20本のエクスプロイテーション映画を監督した。武智鉄二の1964年の作品『白日夢』の成功後、ピンク映画というジャンルに興味を持つようになった。1965年の彼の作品『壁の中の秘事』は、日本映画製作者連盟推薦の大映作品などを差し置いて、第15回ベルリン国際映画祭の正式上映作品に選ばれた。この作品が日本の映画倫理委員会(映倫)の審査を通過する前に映画祭に提出されたことは、当時の政府にとって二重の恥辱と受け止められた。なぜなら、ピンク映画はすでに国内の主要な映画ジャンルとして台頭していたものの、批評的な注目や国際的な輸出に値するものとは見なされていなかったからである。しかし、この映画は映画祭で熱狂的な歓迎を受け、一方で国内では「国辱」発言などもあってセンセーショナルな騒動となった。当時のある討論番組では本作を巡って、「あんなのは映画じゃない」、「いや、今の日本の閉塞状況がリアルに描かれている」と激論が交わされた。これにより若松の名前はピンク映画業界を超えて広く一般に知れ渡ることとなった。政府からの報復措置を恐れた日活は、国内での公開を低調にしたため、失望した若松は日活を辞め、自身のプロダクション「若松プロダクション」を1965年に設立した。このプロダクションには、足立正生や大和屋竺といった才能が集まった。若松はその後も亡くなるまで、スキャンダラスな作品をエネルギッシュに次々と発表し続けた。
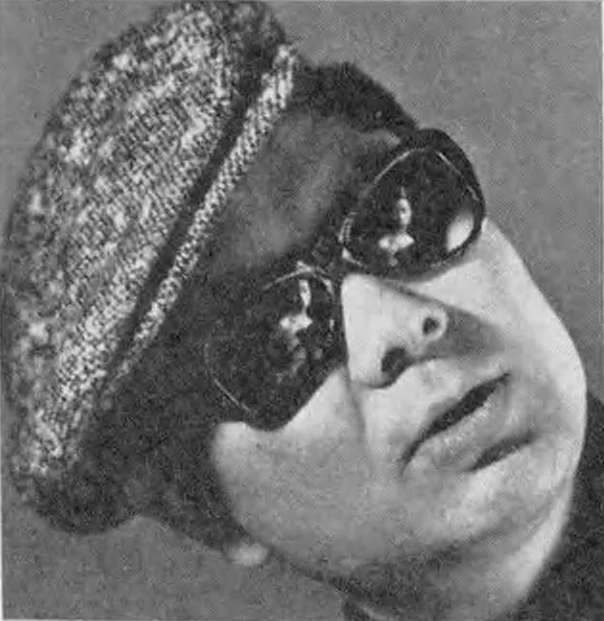
2.2. 作品世界とスタイル
若松孝二の映画作りの原点は「怒り」であり、反体制の視点から社会を描く手法は、当時の若者たちから圧倒的に支持された。彼は「学生運動を支持するために映画を作ったことはなかった」と語り、自分自身が面白いと思った映画を撮っていると述べている。
1960年代後半に若松が独立して制作した映画は、非常に低予算であったが、しばしば芸術的な作品であり、通常は性と極度の暴力を政治的メッセージと混ぜ合わせた内容であった。一部の批評家は、これらの映画が検閲論争から無料の宣伝を生み出すことを意図した、政府への意図的な挑発であったと示唆している。彼の映画は通常、100.00 万 JPY(約5000 USD)未満で制作され、ロケーション撮影、ワンテイク、自然光の使用など、極端なコスト削減策が必要とされた。彼の初期の映画は通常、モノクロで、演劇的な効果のために時折カラーが挿入された。
2.3. 代表的な演出作品
若松孝二の最初の自主制作映画は、1966年の『胎児が密猟する時』である。これは、男が女性を誘拐し、拷問し、性的虐待を加えるが、最終的に彼女が逃げ出して彼を刺殺するという物語である。フリーズフレーム、フラッシュバック、手持ちカメラ、そして2つの部屋と廊下に限定されたロケーションが、この映画の不穏で閉所恐怖症的な雰囲気を高めている。
1967年の『性の放浪』は、今村昌平の『人間蒸発』(1967年)のパロディである。若松の映画では、男が東京の家族を捨てて旅に出て、様々な性的冒険に興じる。彼が家に帰ると、妻が失踪した夫を探す今村昌平のドキュメンタリーに出演していることを知る。
1967年の『犯された白衣』は、アメリカ合衆国でリチャード・スペックによって8人の看護学生が殺害された事件に基づいている。1969年の『日本暴行暗黒史』は、第二次世界大戦後の日本で発生した連続強姦事件に基づいている。1969年の『ゆけゆけ二度目の処女』は、同年にマンソン・ファミリーによって行われたテート・ラビアンカ殺人事件に大まかに基づいている。
1970年の『性賊 セックスジャック』では、「革命運動がいかに常に政府のために働くスパイによって潜入されているかを示す」ことを試みた。彼の最も批評的に評価された映画の一つは、1977年の『聖母観音大菩薩』であり、これは「現代映画における比喩と象徴主義の使用の『教科書的な例』」と呼ばれている。
2008年の『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』は、「あさま山荘事件」に基づいている。長く厳しいこの映画には、この悲劇と日本の急進左翼の自滅につながった政治的背景に関する長いドキュメンタリー部分が含まれている。この作品は、2007年8月の湯布院映画祭で「特別試写作品」として上映され、同年10月には第20回東京国際映画祭で「日本映画・ある視点 作品賞」を受賞した。同年12月に若松が設立した映画館シネマスコーレで公開され、2008年3月から全国で公開された。2008年2月に開催された第58回ベルリン国際映画祭では、最優秀アジア映画賞(NETPAC賞)と国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)を受賞した。また、第63回毎日映画コンクールで監督賞、第18回日本映画批評家大賞で作品賞を受賞し、2007年度宮城県芸術選奨(メディア芸術部門)を受賞した。
2010年の彼の映画『キャタピラー』は、第60回ベルリン国際映画祭で金熊賞を競った。撮影期間は12日間、スタッフは11人という低予算で制作された。日本での公開を前に、2010年2月20日、主演の寺島しのぶがベルリン国際映画祭で主演女優賞を受賞した。観客は「戦争がただの殺し合いでしかない現実」と、「生の根源であるセックス」に引き込まれたという。
2011年には、高名な小説家で政治活動家である三島由紀夫の晩年、特に1970年11月25日のいわゆる三島事件に至る一連の出来事に焦点を当てた新作映画『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』が完成段階にあると発表された。この映画では、日本の俳優井浦新が三島由紀夫を演じている。この映画は、2012年カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で競合した。
2012年には、船戸与一原作の『海燕ホテル・ブルー』、そして中上健次原作、寺島しのぶ主演の『千年の愉楽』を制作し、後者は2013年春の公開を控えていた。
2.4. プロデュース・その他の活動
若松孝二は、監督業の傍ら、映画プロデューサーとしても多岐にわたる活動を行った。特に、大島渚監督の『愛のコリーダ』(1976年)のプロデュースは、彼のキャリアにおける重要な業績の一つである。他にも、大和屋竺監督『荒野のダッチワイフ』(1967年)、足立正生監督『女学生ゲリラ』(1969年)、神代辰巳監督『赤い帽子の女』(1982年)、木俣堯喬監督『鍵』(1983年、兼演出)など、数多くの作品を手がけた。
1986年には、東映と共同で6000.00 万 JPYを投じて『松居一代の衝撃』を製作した。しかし、その内容が風俗法に抵触するとされ、岡田茂東映社長が警視庁から呼び出しを受ける事態となった。岡田社長は「日本の普通の劇場では上映しない」と約束せざるを得ず、このため同作は成人映画扱いとなり、配給を変更してピンク映画の劇場で小規模上映された。結果として大赤字を出し、若松プロダクションがあった原宿セントラルアパートのマンションを売却して借金返済に充てなければならなかった。この一件以降、若松は自ら借金をして映画を制作することができなくなった。
若松は、テレビドラマの演出やミュージック・ビデオの制作も手がけた。唯一の音楽ビデオクリップとして、ソウル・フラワー・ユニオンの「イーチ・リトル・シング」と「風の市」を1998年にアイルランドで撮影している。また、時に役者として映画に出演することもあった。
彼は、名古屋のミニシアター「シネマスコーレ」を自ら経営し、若手映画監督の育成にも尽力した。彼の初期のキャリアを助けられた監督の中には、高橋伴明、中村幻児なかむらげんじ日本語、向井寛などがいる。若松作品は海外での評価も高く、元ソニック・ユースのジム・オルークは、若松の映画音楽を作りたいがために日本語を習得したほどである。
3. 思想とイデオロギー
若松孝二の映画制作の根底には、常に社会に対する「怒り」と反権力の思想があった。彼は自身の作品を通じて、既存の体制や権威を批判し、社会の暗部やタブーを暴き出すことを追求した。性や暴力といった過激な表現は、単なる扇情主義ではなく、社会の抑圧や人間の深層心理を抉り出すための手段として用いられた。
彼は、自身の映画が学生運動を行う若者たちから支持された一方で、「学生運動を支持するために映画を作ったことはなかった」と語っている。これは、特定の政治運動に与するのではなく、あくまで自身の内なる「怒り」と「面白い」と感じる映画表現を追求した結果として、反体制的なメッセージが作品に宿ったことを示唆している。彼の作品は、革命運動におけるスパイの存在を描いた『性賊 セックスジャック』や、日本の急進左翼の悲劇的な自滅を描いた『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』など、社会の矛盾や権力の欺瞞を鋭くえぐるものであった。特に『キャタピラー』では、「戦争がただの殺し合いでしかない現実」を描き、強い反戦のメッセージを込めた。若松の映画は、常に社会の周縁に目を向け、抑圧された人々の声なき声を代弁しようとする、徹底した社会批判の視点に貫かれていた。
4. 死去
2012年10月12日午後10時15分ごろ、若松孝二は東京都新宿区内藤町の横断歩道がない都道を横断中、左から来たタクシーにはねられた。腰などを強く打ち、病院に搬送された。当初の報道では命に別状はないとされていたが、実際には病院搬送時から意識不明の状態が続いていた。そして、事故から5日後の2012年10月17日午後11時5分、入院先の病院で死去した。76歳没。
彼の死は、次回作の予算会議からの帰宅途中に起こった。その企画は、日本の原子力ロビーと東電に関する映画であったと報じられている。
5. 評価と遺産
若松孝二は、日本の映画界において、その革新的な作品と反骨精神によって独自の地位を確立した。彼の作品は、国内外の批評家から高く評価され、後世の映画監督や映画文化に大きな影響を与え続けている。
5.1. 批評的評価
若松孝二は、「ピンク映画の革新者」として、また「1960年代の日本を代表する監督の一人」として高く評価されている。彼の作品『壁の中の秘事』(1965年)がベルリン国際映画祭で正式上映されたことは、当時の日本の映画界に大きな衝撃を与え、ピンク映画が単なる低俗な娯楽ではなく、芸術的な表現たり得ることを示した。この出来事は、国内で「国辱」と批判される一方で、日本の閉塞状況をリアルに描いていると擁護する声もあり、激しい議論を巻き起こした。
彼の映画は、性や暴力といったテーマを扱いながらも、その根底には社会批判や政治的メッセージが深く込められており、これが国内外の批評家から注目される要因となった。特に『聖母観音大菩薩』(1977年)は、「現代映画における比喩と象徴主義の使用の『教科書的な例』」と評されるなど、その芸術性が高く評価されている。また、晩年の作品である『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』(2008年)や『キャタピラー』(2010年)は、社会派作品として再び国際的な注目を集め、ベルリン国際映画祭での受賞やノミネート、カンヌ国際映画祭での選出など、その批評的評価を不動のものとした。
5.2. 映画界への影響
若松孝二は、その独自の制作スタイルと反骨精神によって、後進の映画監督や映画文化に多大な影響を与えた。彼は低予算での映画制作を実践し、ロケーション撮影、ワンテイク、自然光の活用といった手法を積極的に取り入れることで、独立系映画制作の可能性を広げた。
また、彼は自身のプロダクション「若松プロダクション」を通じて、多くの若手映画監督に業界での最初の経験を積む機会を提供した。高橋伴明、中村幻児なかむらげんじ日本語、向井寛といった監督たちは、若松の指導のもとでキャリアをスタートさせている。彼の存在は、商業主義に囚われず、自らの信念に基づいて映画を撮り続ける独立映画制作者たちの精神的支柱となった。
若松作品の国際的な評価の高さも、日本映画界に大きな影響を与えた。ジム・オルークが若松の映画音楽を手がけるために日本語を習得したというエピソードは、彼の作品が国境を越えてアーティストにインスピレーションを与えたことを示している。名古屋のミニシアター「シネマスコーレ」の経営に携わるなど、映画の製作だけでなく、上映環境の維持・発展にも貢献した。
2012年には第17回釜山国際映画祭で「今年のアジア映画人賞」を受賞し、マスタークラスを開催するなど、アジアの映画界にもその影響力を示した。彼の死後も、彼の作品は再評価され続け、その先駆的な精神は現代の映画制作者たちに受け継がれている。2018年には、井浦新が若松孝二を演じた映画『止められるか、俺たちを』が公開され、2024年には続編『青春ジャック 止められるか、俺たちを2』も公開されるなど、その遺産は今なお語り継がれている。
6. 作品リスト
若松孝二が関わった主な映画、テレビドラマ、ミュージックビデオなどの作品を以下にリストアップする。
6.1. 監督作品
若松孝二が監督を務めた映画作品を公開年順に並べる。
- 『甘い罠』(1963年)
- 『激しい女たち』(1963年)
- 『おいろけ作戦』(1963年)
- 『恐るべき遺産 裸の影』(1964年)
- 『鉛の墓標』(1964年)
- 『逆情』(1964年)
- 『壁の中の秘事』(1965年)
- 『情事の履歴書』(1965年)
- 『胎児が密猟する時』(1966年)
- 『性の放浪』(1967年)
- 『日本暴行暗黒史 異常者の血』(1967年)
- 『乱行』(1967年)
- 『続日本暴行暗黒史 暴虐魔』(1967年)
- 『犯された白衣』(1967年)
- 『腹貸し女』(1968年)
- 『新日本暴行暗黒史 復讐鬼』(1968年)
- 『金瓶梅』(1968年)
- 『狂走情死考』(1969年)
- 『処女ゲバゲバ』(1969年)
- 『ゆけゆけ二度目の処女』(1969年)
- 『現代好色伝 テロルの季節』(1969年)
- 『やわ肌無宿 男殺し女殺し・裸の銃弾』(1969年)
- 『通り魔の告白 現代性犯罪暗黒篇』(1969年)
- 『理由なき暴行 現代性犯罪絶叫篇』(1969年)
- 『日本暴行暗黒史 怨獣』(1970年)
- 『性賊 セックスジャック』(1970年)
- 『新宿マッド』(1970年)
- 『秘花』(1971年)
- 『赤軍-PFLP・世界戦争宣言』(1971年)
- 『私は濡れている』(1971年)
- 『天使の恍惚』(1972年)
- 『(秘)女子高生 恍惚のアルバイト』(1972年)
- 『㊙女子高校生課外サークル』(1973年)
- 『濡れた賽ノ目』(1974年)
- 『略称・連続射殺魔』(1975年)
- 『拷問百年史』(1975年)
- 『女刑御禁制百年』(1977年)
- 『聖母観音大菩薩』(1977年)
- 『日本御禁制 女人売買』(1977年)
- 『暴虐女拷問』(1978年)
- 『13人連続暴行魔』(1978年)
- 『残忍連続強漢魔』(1978年)
- 『現代性犯罪 暴行監獄』(1979年)
- 『餌食』(1979年)
- 『現代性犯罪 全員殺害』(1979年)
- 『聖少女拷問』(1980年)
- 『密室連続暴行』(1981年)
- 『水のないプール』(1982年)
- 『スクラップ ストーリー ある愛の物語』(1984年)
- 『松居一代の衝撃』(1986年)
- 『キスより簡単』(1989年)
- 『われに撃つ用意あり READY TO SHOOT』(1990年)
- 『キスより簡単2 漂流篇』(1991年)
- 『エロティックな関係』(1992年)
- 『寝盗られ宗介』(1992年)
- 『シンガポール・スリング』(1993年)
- 『Endless Waltz エンドレス・ワルツ』(1995年)
- 『標的 羊たちの悲しみ』(1996年)
- 『明日なき街角』(1997年)
- 『飛ぶは天国、もぐるが地獄』(1999年)
- 『首相官邸の女』(2001年)
- 『完全なる飼育 赤い殺意』(2004年)
- 『17歳の風景 少年は何を見たのか』(2005年)
- 『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』(2008年)
- 『キャタピラー』(2010年)
- 『海燕ホテル・ブルー』(2012年)
- 『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』(2012年)
- 『千年の愉楽』(2012年)
6.2. 製作作品
若松孝二がプロデュースまたは製作に関わった映画作品をリストアップする。
- 『乾いた処女』(監督:梅沢薫・1965年)
- 『堕胎』(監督:足立正生・1966年)
- 『荒野のダッチワイフ』(監督:大和屋竺・1967年)
- 『避妊革命』(監督:足立正生・1967年)
- 『女学生ゲリラ』(監督:足立正生・1969年)
- 『性遊戯』(監督:足立正生・1969年)
- 『ニュー・ジャック・アンド・ベティ』(監督:沖島勲・1970年)
- 『夜にほほよせ』(監督:林静一、1973年)
- 『愛のコリーダ』(監督:大島渚・1976年)
- 『赤い性 暴行傷害』(監督:高橋伴明・1977年)
- 『日本の拷問』(監督:高橋伴明・1978年)
- 『戒厳令の夜』(監督:山下耕作・1980年)
- 『赤い帽子の女』(監督:神代辰巳・1982年)
- 『鍵』(監督:木俣堯喬・1983年)
- 『びんばりハイスクール』(監督:鈴木則文・1990年)
6.3. 出演作品
若松孝二が俳優として出演した映画作品をリストアップする。
- 『青春☆金属バット』(監督:熊切和嘉・2006年) - 自称ベーブ・ルースの息子
- 『無間地獄 凶悪金融道』(2003年、原作:新堂冬樹、東映ビデオ) - 富樫組組長
6.4. テレビドラマ
若松孝二が演出やプロデュースを手がけたテレビドラマ作品をリストアップする。
- 『極道落ちこぼれ カタギになりたい!』(1993年、TBS)
- 『極道落ちこぼれII 駆けおちしました!?』(1994年、TBS)
- 『恋する日曜日「ウェディングベル 前後編」』(2003年、BS-i)
- 『文學の唄 恋する日曜日「蒲団 前後編」』(2005年、BS-i)
- 『文學の唄 恋する日曜日「老妓抄」』(2005年、BS-i)
- 『東京少女 岡本杏理「家出のススメ。」』(2008年、BS-i)
- 『東京少女 福永マリカ「井の中のマリカ」』(2008年、BS-i)
- 『東京少女 岡本あずさ「絆 前後編」』(2008年、BS-i)
- 『ケータイ刑事 銭形命「恋愛泥棒マリン再び現る!~謎の怪盗予告事件~」』(2009年、BS-TBS)
6.5. ミュージック・ビデオ
若松孝二が制作したミュージックビデオ作品をリストアップする。
- ソウル・フラワー・ユニオン「イーチ・リトル・シング」
- ソウル・フラワー・ユニオン「風の市」
7. 受賞歴
若松孝二が映画監督として、またプロデューサーとして受賞した主な賞を以下にまとめる。
- 第58回ベルリン国際映画祭(2008年)
- 最優秀アジア映画賞(NETPAC賞) - 『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』
- 国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞) - 『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』
- 第20回東京国際映画祭(2007年)
- 「日本映画・ある視点」部門 作品賞 - 『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』
- 第63回毎日映画コンクール(2008年)
- 監督賞 - 『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』
- 第18回日本映画批評家大賞(2008年)
- 作品賞 - 『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』
- 宮城県芸術選奨(2007年度)
- メディア芸術部門
- 第2回TAMA映画賞(2010年)
- 特別賞 - 『キャタピラー』
- 新藤兼人賞(2010年)
- プロデューサー賞(SARVH賞) - 『キャタピラー』
- 第17回釜山国際映画祭(2012年)
- 今年のアジア映画人賞
8. 関連書籍
若松孝二自身による著作や、彼に関する伝記、評論などの二次的資料を紹介する。
- 若松孝二・俺は手を汚す(ダゲレオ出版、1982年6月 → のち河出書房新社、2012年12月)
- 若松孝二(著)小出忍・掛川正幸(編)『時効なし。』(ワイズ出版、2004年12月)
- 若松孝二反権力の肖像(作品社、四方田犬彦・平沢剛=編、2007年11月)
- 若松孝二 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(游学社、2008年2月)
- 若松孝二全発言(河出書房新社、平沢剛=編、2010年7月)
- 若松孝二 キャタピラー(游学社、2010年8月)
- 若松孝二 海燕ホテル・ブルー(游学社、2012年3月)
- 若松孝二 11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち(游学社、2012年6月)
- KAWADE夢ムック 文藝別冊 総特集 若松孝二 闘いつづけた鬼才(河出書房新社、2013年1月)
- 若松孝二 千年の愉楽(游学社、2013年1月)
- 対談集 若松孝二の時代を撃て!(游学社、2013年4月)
- 原渕勝仁著『若松孝二と赤軍レッド・アーミー』(世界書院、2016年7月)