1. 概要
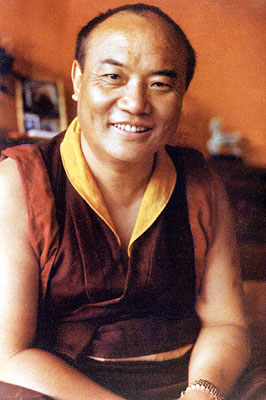
カルマパ(ཀརྨ་པ་チベット語)は、チベット仏教の四大教派の一つであるカギュ派の最大支派、カルマ・カギュ派の最高指導者である化身ラマの名跡である。この血統は、チベット仏教の主要な転生者 lineage の中でも最も古く、初代カルマパであるトゥースム・キェンパによって1110年に確立された。「カルマパ」という名称は、「仏陀の活動を遂行する者」、あるいは「すべての仏陀の活動の具現者」を意味する。歴代のカルマパは、詳細な予言書を通じて自身の転生を予言し、これまでに17の化身が確認されている。
カルマパは、「聖下ギャルワ・カルマパ」(རྒྱལ་བ་チベット語、勝利者)や、より正式には「ギャルワン」(རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་チベット語、勝利者の王)といった敬称で呼ばれる。また、正装時に着用する黒帽から「カルマ黒帽ラマ」の異名を持つ。観音菩薩の化身と信じられている。一般的にはダライ・ラマ、パンチェン・ラマに次ぐチベット仏教の序列第三位とされることがあるが、ダライ・ラマとパンチェン・ラマはゲルク派に属するため、厳密には宗派が異なるためこの表現は正確ではない。しかし、カルマ・カギュ派の広範な影響力や、17世カルマパの亡命に関するニュースが世界的に報じられたことから、彼らが高い知名度を持つことは事実である。
歴代カルマパの主要な座所はチベット中央部のウー・ツァンにあるツルプ僧院であった。チベット亡命後には、インドのシッキム州にあるルムテク僧院(ダーマ・チャクラ・センター)が主要な拠点となった。国際的な活動拠点としては、米国ニューヨーク州のカルマ・トリヤーナ・ダルマチャクラや、フランスドルドーニュ県のダグポ・カギュ・リンなどが挙げられる。
第16世カルマパの死後、その転生者である第17世カルマパの認定をめぐってカルマ・カギュ派内部で激しい論争が発生し、複数の候補者が現れて宗派が分裂するという事態に至った。しかし、2023年12月4日には、二人の主要な候補者であるウゲン・ティンレー・ドルジェとティンレー・タイェ・ドルジェが共同声明を発表し、この論争の解決に向けた大きな進展が見られた。
2. 歴史と起源
2.1. 血統の確立
カルマパの血統は、ガムポパの高弟であったトゥースム・キェンパ(དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་チベット語、1110年 - 1193年)によって確立された。トゥースム・キェンパは、ソナム・リンチェンの弟子でもあり、1147年にチベット東部リオチェ近郊のカルマにカルマ・デンサ僧院を創建したことが、カルマ・カギュ派とカルマパの血統の始まりとされている。幼い頃から仏教を学び、20代から30代にかけて高名な師を求めて修行を積んだ彼は、50歳で夢ヨガの修行中に悟りを開いたと伝えられている。この成就により、彼は当時の高僧であるシャキャ・シュリーやラマ・シャンによって、『三昧王経』や『楞伽経』で出現が予言されていた観音菩薩の化身であるカルマパとして認識された。
この血統の口伝は、伝統的に金剛総持にまで遡り、インドのマハームドラーとタントラの師であるティローパ(989年 - 1069年)からナーローパ(1016年 - 1100年)を経て、マルパ・ロツァワ、そしてミラレパへと受け継がれた。これらのカルマ・カギュ(བཀའ་བརྒྱུདチベット語)派の祖師たちは、総じて「黄金の数珠」と呼ばれている。
2.2. 化身ラマの認定システム
カルマパは、自らの意思で転生するラマの系譜であり、カルマ・パクシ(ཀརྨ་པཀྵི་チベット語、1204年 - 1283年)は、自身の転生状況を予言したチベット仏教で最初の公認されたトゥルク(སྤྲུལ་སྐུ་チベット語、化身ラマ)である。この伝統は、カルマパの血統がチベット仏教において最初に転生制度を確立したことを意味する。
カルマパの転生者の身元は、複数の方法を組み合わせて確認される。その中には、悟りを開いた血統の師による神通力的な洞察、先代カルマパが遺した詳細な予言書、そして若い子供自身による自己宣言や、前世の知る人や物を識別する能力が含まれる。特に予言書は、転生者の誕生の時期や場所、両親の名前、そして特定の自然現象の兆候を記している。この予言書は、カルマパの転生が血筋によるものではなく、精神的な血統に基づくものであることの揺るぎない証拠とされている。第3世カルマパのランジュン・ドルジェは、この化身ラマ制度のさらなる発展や体系化に貢献したとされている。
3. 特徴と象徴
3.1. 黒帽
カルマパは「黒帽」(ཞྭ་ནགシャナクチベット語)の保持者であり、「黒帽ラマ」としても知られている。この黒帽(རང་འབྱུང་ཅོད་པན།ランジュン・チェプンチベット語、「自生冠」の意)は、伝統的にダキニたちが自らの髪で織り上げ、カルマパの精神的覚醒を認識して授けたものだと伝えられている。
歴代のカルマパによって着用されてきた物理的な黒帽は、この精神的な冠を物質的に表現したものであり、明王朝の永楽帝が第5世カルマパのテシン・シェクパに贈ったものである。永楽帝はまた、カルマパに「大宝法王」の称号を授けた。
この黒帽は、第16世カルマパの最後の拠点であったインドのシッキム州にあるルムテク僧院に最後に所在が確認されたが、1993年以降、同僧院は混乱に見舞われており、黒帽が現在もそこにあるかどうかについて懸念が持たれている。インド政府が近い将来、同僧院に残された物品の棚卸しを行う予定とされている。
4. 歴代カルマパの一覧
| 代数 | 名前 | 生没年 | チベット語(ワイリー方式) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1世 | トゥースム・キェンパ | 1110年 - 1193年 | དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་チベット語 | ガムポパの高弟、カルマ派の派祖 |
| 2世 | カルマ・パクシ | 1204/06年 - 1283年 | ཀརྨ་པཀྵི་チベット語 | チベット仏教で最初の転生を予言した化身ラマ |
| 3世 | ランジュン・ドルジェ | 1284年 - 1339年 | རང་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་チベット語 | 化身ラマ制度の発展に貢献 |
| 4世 | ルルペー・ドルジェ | 1340年 - 1383年 | རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 5世 | テシン・シェクパ | 1384年 - 1415年 | དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་チベット語 | 永楽帝より黒帽を授かる |
| 6世 | トンワ・トゥンデン | 1416年 - 1453年 | མཐོང་བ་དོན་ལྡན་チベット語 | |
| 7世 | チュータク・ギャムツォ | 1454年 - 1506年 | ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་チベット語 | |
| 8世 | ミキュー・ドルジェ | 1507年 - 1554年 | མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 9世 | ワンチュク・ドルジェ | 1555/56年 - 1603年 | དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 10世 | チューイン・ドルジェ | 1604年 - 1674年 | ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 11世 | イェシェー・ドルジェ | 1676年 - 1702年 | ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 12世 | チャンチュプ・ドルジェ | 1703年 - 1732年 | བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 13世 | ドゥートゥル・ドルジェ | 1733年 - 1797年 | བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 14世 | テクチョク・ドルジェ | 1798年 - 1868年 | ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 15世 | カキャプ・ドルジェ | 1871年 - 1922年 | མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 16世 | ランジュン・リクペー・ドルジェ | 1923/24年 - 1981年 | རང་འབྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་チベット語 | |
| 17世 | ウゲン・ティンレー・ドルジェ | 1985年 - 現在 | ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།チベット語 | 多数派の推戴。ダライ・ラマ14世と中華人民共和国政府に認定される |
| 対立17世 | ティンレー・タイェ・ドルジェ | 1983年 - 2017年 | ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ།チベット語 | 少数派(シャマル派)の推戴。2017年3月、結婚により僧位を放棄 |
5. 第17世カルマパと後継者論争
第16世カルマパ、ランジュン・リクペー・ドルジェが1981年に逝去した後、カルマパの血統の継承を巡る複雑な論争がカルマ・カギュ派内部で勃発した。この論争は、複数の候補者が17世カルマパの座を主張し、結果的に宗派が大きく分裂するという事態に発展した。過去にも8世、10世、12世、そして16世カルマパの認定において紛争があったが、それらは最終的に解決された。しかし、17世カルマパの論争は特に長く続き、カルマ・カギュ派の血統に根本的な影響を及ぼした。
5.1. 論争の背景
第17世カルマパの継承をめぐる論争は、カルマ・カギュ派内部の異なる派閥間の権力闘争と、特定のラマの予言書の解釈の違いが複雑に絡み合って発生した。先代カルマパの予言書が公表された際、その真偽や解釈を巡って主要な摂政たちの間で意見の相違が生じ、これが論争の直接的な引き金となった。さらに、宗派の政治的、経済的な影響力もこの対立の背景にあったとされる。
5.2. 主要な関係者と主張
この論争における主要な候補者は、ウゲン・ティンレー・ドルジェとティンレー・タイェ・ドルジェの二人である。
- ウゲン・ティンレー・ドルジェ**:1985年に誕生。カルマ・カギュ派の多数派によって1992年に17世カルマパとして認定された。この認定は、ダライ・ラマ14世と中華人民共和国政府双方から公的に承認され、ウゲン・ティンレー・ドルジェに大きな宗教的、政治的正統性を与えることとなった。彼は現在、インドに居住している。
- ティンレー・タイェ・ドルジェ**:1983年に誕生。彼は、カルマ・カギュ派の筆頭摂政(副教主)であったシャマル・リンポチェ(カルマ赤帽ラマ)によって17世カルマパとして認定された。シャマル・リンポチェはウゲン・ティンレー・ドルジェの認定を認めず、独自の路線を歩んだ。ティンレー・タイェ・ドルジェは、主に欧米諸国で精力的に布教活動を展開し、少数派の支持者を得た。
- その他の候補者**:2001年には、シッキム州出身のダワ・サングポ・ドルジェ(1977年生)も17世カルマパを自称したが、彼の主張は広く支持されることはなかった。
5.3. 論争の推移と近年の進展
17世カルマパの論争は長年にわたり続き、カルマ・カギュ派内部の分裂を深めた。しかし、この論争は新たな局面を迎えることとなった。2016年3月25日、ティンレー・タイェ・ドルジェはインドのニューデリーで幼なじみの女性と結婚し、2017年4月には僧位を放棄することを宣言した。これにより、彼を推戴していたシャマル派は、教主としての僧位を持つ者を失う形となった。
その後、この論争は和解の方向へと動き出した。2023年12月4日、ウゲン・ティンレー・ドルジェとティンレー・タイェ・ドルジェの両名が共同声明を発表した。この声明は、クンツィク・シャマル・リンポチェの転生に関するものであり、長年にわたる両者間の対立関係において、重要な和解の兆しと見なされた。この共同声明は、血統の統一と将来の協力に向けた画期的な進展として、両派によって広く受け止められた。この進展が、カルマ・カギュ派の血統と組織の今後に対し、どのような長期的な影響をもたらすか、引き続き注目されている。
6. 役割と影響

カルマパの血統は、チベット仏教、特にカルマ・カギュ派において中心的な役割を担っている。カルマパは、金剛総持の化身ラマとして、カルマ・カギュ派の教義と伝統を継承・維持し、仏教哲学と実践の重要な源泉であり続けている。彼らは、教えの保存、僧侶の育成、そしてチベット文化と精神性の維持に貢献してきた。また、カルマパの存在は、チベット仏教全体における化身ラマ制度の最も初期の確立者として、他の主要な転生者(ダライ・ラマやパンチェン・ラマなど)にも影響を与えた。
近年では、17世カルマパの亡命と国際的な活動を通じて、チベット仏教の教えを世界中に広め、文化交流を促進する上で重要な役割を果たしている。特に、長年にわたる転生者論争を経て和解の方向性が見られることで、カルマ・カギュ派の結束を再構築し、より広範なチベット仏教コミュニティにおけるその影響力を高めることが期待されている。
7. 主要な僧院と拠点
カルマパ血統は、その長い歴史の中で多くの重要な僧院や活動拠点を築いてきた。これらの場所は、カルマ・カギュ派の教えの中心地であり、世界中の信徒にとって精神的な支えとなっている。
- チベットの歴史的拠点**:ツルプ僧院(མཚུར་ཕུ་དགོན་པチベット語、Tsurphu Monastery)は、チベットのウー・ツァン(中央チベット)のトルン渓谷に位置し、歴代カルマパの主要な座所として歴史的に機能してきた。ここはカルマ・カギュ派の創始以来の中心地であり、その教えが発展し、広められた場所である。
- 亡命後の主要拠点**:第16世カルマパの亡命後、インドのシッキム州にあるルムテク僧院(ダーマ・チャクラ・センター、Rumtek Monastery)が、カルマパの主要な亡命後の拠点となった。この僧院は、チベット仏教の教えと文化を維持し、世界中に広めるための重要な中心地である。
- 国際的な活動拠点**:カルマパ血統は、世界各地に広範な活動拠点を有している。これには、米国ニューヨーク州にあるカルマ・トリヤーナ・ダルマチャクラ(Karma Triyana Dharmachakra)、フランスドルドーニュ県のダグポ・カギュ・リン(Dhagpo Kagyu Ling)、そしてドミニカなどが含まれる。また、ブータンのタシ・チョリンも国際的な拠点の一つとして機能している。これらの僧院やセンターは、世界中の仏教徒に教えを提供し、文化交流を促進するための重要な役割を担っている。