1. 幼少期と背景
1.1. 出生と初期の人生
クマールはインドのラージャスターン州シュリー・ドゥンガルガルで生まれた。9歳の時、彼は家族のもとを離れ、ジャイナ教の僧侶となった。
1.2. 還俗とガンディーの影響
18歳の時、マハトマ・ガンディーの著書を読んだことをきっかけに、彼は修行僧の道を捨てた。その後、ガンディーの著名な弟子であり、非暴力と土地改革の思想を提唱したヴィノバ・バーヴェの弟子となった。
2. 平和巡礼
2.1. 巡礼の動機と計画
1962年6月、バートランド・ラッセルが原子爆弾に反対する市民的不服従運動を展開し投獄されたというニュースに触発され、クマールと友人E・P・メノンは、核保有国である4つの首都、すなわちモスクワ、パリ、ロンドン、ワシントンD.C.への平和巡礼を決意した。彼らはこの旅に一切の金銭を持たずに行くことを決め、「平和のための巡礼」と名付けた。
2.2. 行程と経験
この巡礼は2年半を要し、8,000マイル(約1.40 万 km)以上を歩いた。バーヴェは若い二人に二つの「贈り物」を与えた。一つは、どこを歩いても無一文であること。もう一つは、菜食主義者であることだった。
彼らはまずパキスタンを通過した。インドとの歴史的な対立と反感があるにもかかわらず、パキスタンの人々からは大きな親切を受けた。カイバル峠を越えてパキスタンを出た後、彼らはアフガニスタン、イラン、アルメニア、ジョージア、そしてコーカサス山脈を越えて、モスクワに到達した。その後、パリ、ロンドン、ワシントンD.C.へと旅を続けた。
徒歩で移動し、金銭を持たなかったため、クマールと彼の同行者は、食事や宿泊を提供してくれる人々と共に過ごした。モスクワへ向かう途中、彼らはある紅茶工場で二人の女性に出会った。彼らが旅の目的を説明すると、女性の一人が紅茶の包みを4つ渡し、核保有国4カ国の指導者それぞれに届けるよう依頼した。その際、「ボタンを押す必要があると思ったら、一分間立ち止まって、淹れたての紅茶を一杯飲んでください」というメッセージも伝えてほしいと頼んだ。この出来事は彼らの旅をさらに鼓舞し、巡礼の理由の一部となった。彼らは最終的に、核保有国4カ国の指導者に「平和の紅茶」を届けた。また、韓国の資料によると、彼らはインドに戻る前に日本を訪れたという。
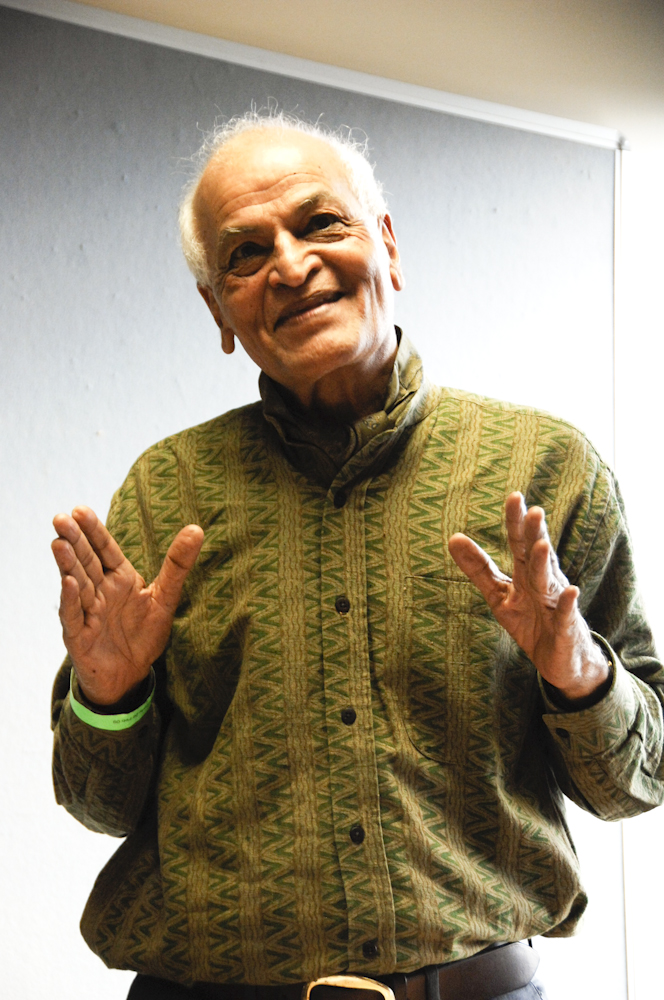
2.3. 巡礼の記録
この平和巡礼の旅は、クマールの著書『No Destination: Autobiography of a Pilgrim英語』に詳細に記録されている。
3. イギリスでの活動と貢献
3.1. シューマッハー・カレッジ
シューマッハー・カレッジは、真に持続可能で豊かな社会を創造するための国際的な教育機関として、1991年に設立された。最大50人程度の小規模な共同体で、生徒、講師、スタッフが共に掃除や料理といった生活の基盤となる活動に参加する。これにより、机上で得た知識や理論を超えて、共同生活を通じた実際の行動や経験から学ぶことを重視している。
カレッジでは、1年間の修士課程(ホリスティックサイエンス修士課程)の他、年間10~20のショートコース(1週間から3週間)を運営している。これらのコースでは、開発・発展、食、経済、組織運営、精神的成長、持続可能性、平和、平等など、多岐にわたるテーマを統合的に学ぶことができる。カレッジ専従講師の他、フリチョフ・カプラ、ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ、ヴァンダナ・シヴァなど、さまざまな分野の世界的な第一人者が数日から2週間の講義を行っている。2006年までに、延べ88カ国から約3,000人(18歳から80歳)がこのカレッジで学んだ。
3.2. スモール・スクール
「スモール・スクール」は、知的、実践的、霊的なバランスを取りながら全人的発達を促すことを目的とした、地域の小規模な学校(中学・高校)である。1982年に地域コミュニティの9世帯の保護者と共に設立された。在学者数は約40人で、対象年齢は11歳から16歳。8人の生徒に対して1人の常勤教師がつくという手厚い指導体制が特徴である。この学校を元祖として、イギリスでは「人間的なサイズ」のスモール・スクール運動が広がり、オルタナティブ教育の一翼を担っている。
3.3. 『リサージェンス&エコロジスト』編集長
1973年から2016年まで、クマールは『Resurgence & Ecologist英語』誌の編集長を務めた。この雑誌は、かつて『Resurgence英語』誌として、グリーン運動の芸術的・精神的な旗艦と評されていた。彼は同誌を通じて、環境保護運動に多大な貢献をした。
3.4. その他のメディアと活動
クマールは、BBCの『Today programme英語』内の「Thought for the Day英語」コーナーに寄稿したほか、『Desert Island Discs英語』にも出演した。また、リチャード・ドーキンスのドキュメンタリー『The Enemies of Reason英語』の「迷信の奴隷たち」というエピソードで、現代社会における非科学的信念の蔓延を調査する中で、ドーキンスからインタビューを受けた。さらに、BBC2の自然史シリーズのために、映画『Earth Pilgrim英語』を制作している。
2009年10月に発売された書籍『We Are One: A Celebration of Tribal Peoples英語』にも寄稿者の一人として参加した。この書籍は、世界中の民族の文化を探求し、その多様性と直面する脅威を描いている。部族の人々の声明、写真、そして国際的な著者、活動家、政治家、哲学者、詩人、芸術家、ジャーナリスト、人類学者、環境保護主義者、写真ジャーナリストによるエッセイが収められている。この書籍の販売による印税は、先住民の権利を擁護する組織であるサバイバル・インターナショナルに寄付される。
4. 哲学と思想
4.1. 環境主義と自然への畏敬
サティシュ・クマールは、政治や社会の議論の中心に、自然への深い敬意を置くべきだと強く信じている。彼の環境主義的視点は、人間が自然の一部であり、その生態系と調和して生きることの重要性を強調している。彼は、現代社会が自然から乖離し、その結果として環境問題や社会問題が生じていると指摘し、自然との再接続こそが持続可能な未来への鍵であると説く。
4.2. 非暴力と平和主義
マハトマ・ガンディーやヴィノバ・バーヴェらの思想に深く影響を受け、クマールは生涯を通じて非暴力と平和主義を擁護してきた。彼は特に核兵器の廃絶を強く訴え、その信念を行動で示すために、核保有国の首都を巡る平和巡礼を行った。彼の平和主義は、単なる戦争の否定にとどまらず、すべての生命に対する敬意と、対話を通じた紛争解決の追求に基づいている。
4.3. 質素な生活と精神性
クマールは、個人の生き方として質素な生活を送ることを実践し、その重要性を説いている。彼は物質的な豊かさの追求が精神的な貧困をもたらすと批判し、消費主義社会からの脱却を提唱する。質素な生活は、自己の内面と向き合い、精神的な成長を促すための基盤であると彼は考えている。彼の生活様式は、持続可能性と精神的な充足が密接に結びついているという彼の哲学を体現している。
4.4. リアリズムへの批判
クマールは、現代社会の多くの問題が、いわゆる「現実主義的」な政治アプローチによって引き起こされたと批判している。彼は、現実主義が戦争、気候変動、大規模な貧困、そして生態系の破壊をもたらしたと主張し、その「現実」が多くの人々を飢えさせていると指摘する。これに対し、彼は自身の理想主義的な視点こそが、真の解決策をもたらすと提唱している。彼にとって、現実主義は「時代遅れで、過剰に評価され、完全に誇張された概念」なのである。
5. 主要著作
サティシュ・クマールの主要な著作は、彼の環境主義、精神性、平和主義といった思想的テーマを深く掘り下げている。
- 『No Destination: Autobiography of a Pilgrim英語』(2014年、初版1978年) - 彼の平和巡礼の旅を記録した自伝。
- 『You Are, Therefore I Am: A Declaration of Dependence英語』(2002年) - 相互依存の哲学を探求する。
- 邦訳:『君あり、故に我あり-依存の宣言』(尾関 修, 尾関 沢人 訳、講談社、2005年)
- 『Images of Earth and Spirit: A Resurgence anthology英語』(ジョン・レーンとサティシュ・クマール編、2003年) - 『Resurgence』誌に掲載された芸術と精神性に関するアンソロジー。
- 『The Intimate and the Ultimate英語』(ヴィノバ・バーヴェ著、サティシュ・クマール編、2004年) - 師であるヴィノバ・バーヴェの思想をまとめたもの。
- 『The Buddha and the Terrorist: The Story of Angulimala英語』(2006年) - 仏教の物語を通して、非暴力と許しの力を説く。
- 『Spiritual Compass: The Three Qualities of Life英語』(2008年) - 人生の三つの質(土、心、社会)に関する精神的な指針。
- 『Earth Pilgrim英語』(エチャン・デラヴィ、マヤ・クマール・ミッチェルとの対談、2009年) - 地球を巡る巡礼者の視点から、自然とのつながりを語る。
- 『Soul, Soil, Society: a New Trinity for our Time英語』(2013年) - 魂、土壌、社会という現代のための新たな三位一体を提唱。
- 『Elegant Simplicity: the Art of Living Well英語』(2019年) - 質素でありながら豊かな生き方について。
- 『Pilgrimage for Peace: the Long Walk from India to Washington英語』(2021年) - 平和巡礼に関する新たな視点を提供する。
- 『土(Soil)と心(Soul)と社会(Society)』(サティシュ・クマール東京講演2007 懐かしい未来編集ブックレット)[http://afutures.shop-pro.jp/?pid=38628950 購入ページ]
- 『つながりを取りもどすために 「土」と「心」が創る「持続可能な社会」』(サティシュ・クマール講演会2009 懐かしい未来編集ブックレット)[http://afutures.shop-pro.jp/?pid=38628994 購入ページ]
6. 私生活
サティシュ・クマールは、インドにいた妻との間に二人の子供(娘と息子)をもうけている。1973年にイギリスに定住し、現在はパートナーのジューン・ミッチェルと二人の子供と共に、デヴォン州ハートランドで質素な生活を送っている。
7. 政治活動
2015年のイギリス総選挙に先立ち、クマールはイングランド・ウェールズ緑の党のキャロライン・ルーカス議員の立候補を支持した数少ない著名人の一人である。
8. 評価と遺産
サティシュ・クマールは、ジャムナラル・バジャジ国際賞を受賞するなど、その活動が高く評価されている。彼の思想と実践は、環境運動、平和運動、そしてオルタナティブ教育の分野に多大な影響を与え、その遺産は今日まで多くの人々にインスピレーションを与え続けている。彼は、自然への敬意、非暴力、質素な生活、そして現実主義への批判を通じて、より持続可能で調和のとれた社会の実現に向けた道を提示し続けている。
9. 関連項目
- マハトマ・ガンディー
- ヴィノバ・バーヴェ
- バートランド・ラッセル
- ジャイナ教
- シューマッハー・カレッジ
- 緑の党
- 質素な生活
- 非暴力
- 核兵器廃絶
- 環境主義