1. 概要

フランシスコ・スアレス(Francisco Suárezスペイン語、1548年1月5日 - 1617年9月25日)は、スペイン出身のイエズス会士で、哲学者、神学者、法学者である。彼はサラマンカ学派の主要な人物の一人として知られ、第二スコラ学の歴史において、ルネサンス期からバロック期への移行を示す転換点と見なされている。
スアレスは、形而上学、神学、法学といった多岐にわたる分野で膨大な著作を残した。特に、彼の主著である『形而上学論考』(Disputationes Metaphysicae)は、17世紀を通じてヨーロッパで広く読まれ、トマス主義を基盤としつつ、スコラ学の体系化に大きく貢献した。法学の分野では、自然法と国際法に関する彼の独創的な思想が、後のフーゴー・グロティウスやザムエル・フォン・プーフェンドルフといった思想家に影響を与え、国際法の基礎を築いた「国際法のゴッドファーザー」とも称される。
また、王権神授説を批判し、君主が暴政を行った場合の人民による抵抗権を主張したことでも知られる。この主張は、当時のイングランド国王ジェームズ1世やロバート・フィルマー、トマス・ホッブズなどから激しい批判を浴び、彼の著作が焼却される事態も招いたが、社会契約論や人民主権論の萌芽として、その後の政治哲学に間接的な影響を与えた。
2. 生涯と経歴
フランシスコ・スアレスは、16世紀半ばのスペインに生まれ、幼少期から厳格な教育を受け、やがてイエズス会に入会し、生涯を学問と教育に捧げた。
2.1. 幼少期と教育
スアレスは1548年1月5日にスペインアンダルシア州グラナダで生まれた。

法学者ガスパル・スアレス・デ・トレドとその妻アントニア・バスケス・デ・ウティエルの間の末息子であり、貴族の家系に育った。10歳から3年間の予備教育を受けた後、1561年にサラマンカ大学に入学し、法学を学んだ。
2.2. イエズス会入会と初期活動
1564年、16歳でサラマンカのイエズス会に入会した。彼はアロンソ・ロドリゲス神父の指導のもと、2年間の集中的な精神的修練を積んだ。1566年8月にはイエズス会士として最初の誓願を立て、同年10月からサラマンカで神学の学習を開始した。初期の学業では決して優秀な学生ではなく、入学試験に2度失敗した後、学問を諦めかけるほどであった。しかし、3度目の挑戦で合格してからは状況が好転した。
1570年に神学課程を修了すると、スアレスはまずサラマンカでスコラ哲学の家庭教師として、その後セゴビアのイエズス会学院で哲学教授として教鞭を執り始めた。1572年3月にはセゴビアで司祭に叙階された。彼は1574年9月にバリャドリッドのイエズス会学院で神学を教えるために移籍するまで、セゴビアで哲学の教鞭を取り続けた。これ以降、彼は生涯にわたって神学を教えることになった。
2.3. 主要な教育活動
スアレスはその後、さまざまな場所で教鞭を執った。具体的には、アビラ(1575年)、セゴビア(1575年)、バリャドリッド(1576年)、ローマ(1580年 - 1585年)、アルカラ・デ・エナーレス(1585年 - 1592年)、サラマンカ(1592年 - 1597年)である。1597年にはポルトガルのコインブラ大学の神学教授の主要な職に就くためコインブラに移住し、短い期間ローマで教えたことを除き、1617年に死去するまでこの地にとどまった。
スアレスは生涯を通じて膨大な量の著作(彼の完全なラテン語の著作は26巻に及ぶ)を著し、当時の最大の哲学者・神学者とみなされた。ローマ教皇グレゴリウス13世は彼のローマでの最初の講義に出席し、ローマ教皇パウルス5世はイングランド国王ジェームズ1世の議論に反駁するよう彼を招き、その知識を活かすために側近に留めておきたいと望んだ。また、スペイン国王フェリペ2世はコインブラ大学の名声を高めるために彼を派遣し、スアレスがバルセロナ大学を訪れた際には、大学の博士たちがそれぞれの学部の記章を身に着けて彼を出迎えた。こうしたことから、彼は「俊秀博士(Doctor Eximius et Piusラテン語、傑出し敬虔なる博士)」という尊称で呼ばれた。
2.4. 死去
1617年9月25日、スアレスはポルトガルのリスボンまたはコインブラで死去した。彼の遺体はリスボンのサン・ロケ教会(旧イエズス会教会)に埋葬された。彼の死後、17世紀半ばには彼の蔵書がエチオピアに送られたが、その多くは失われ、一部はポルトガル領インドのゴアにたどり着いた。彼の名声はさらに高まり、フーゴー・グロティウス、ルネ・デカルト、ジョン・ノリス、ゴットフリート・ライプニッツといった後の著名な哲学者に直接的な影響を与えた。
3. 主要な思想と業績
スアレスの思想は、その体系的な探求と独創性において、中世スコラ学の集大成であるとともに、近代哲学および国際法の先駆と評価されている。
3.1. 形而上学
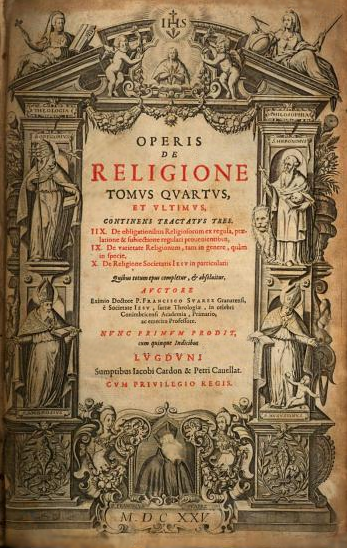
スアレスにとって形而上学は「実在の質」に関する学問であり、概念的実在よりも現実的実在、物質的実在よりも非物質的実在を主に扱った。彼は(以前のスコラ学者たちと同様に)神の場合には本質と実存は同一であると主張したが(存在論的証明を参照)、トマス・アクィナスらとは異なり、有限な存在者の本質と実存は「現実には」区別されないとした。スアレスは、両者は単に「概念的に」区別されるにすぎず、実際には分離不可能であるが、論理的には別々に構想できると論じた。
普遍者の問題については、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥスの実在論とウィリアム・オブ・オッカムの唯名論の間の中間路線を追求しようと努めた。彼の立場はトマス・アクィナスよりもわずかに唯名論に近い。彼は「穏健な唯名論者」に分類されることもあるが、客観的精度(praecisio obiectiva)を認めている点で、穏健な実在論者とも見なされる。存在の世界における唯一の真の実在的統一は個物であり、普遍者が「事物の側で」(ex parte rei)個別に存在すると主張することは、個物を単一の不可分な形態の単なる偶有性に還元することになる。スアレスは、ソクラテスの人間性はプラトンの人間性と異ならないが、それでもそれらが「現実的に」(realiter)同じ人間性を構成するわけではないと主張する。個物の数だけ「形式的統一」(この場合は人間性)が存在し、これらの個物は事実上の統一ではなく、本質的または理念的な統一を構成するにすぎない(「このように、同じ本性であると言われる多くの個物は、事物の実在的な実体や本質によってそれらを結合するのではなく、理性の働きを通じてのみそうである」)。しかし、形式的統一は心の恣意的な創造物ではなく、「理性のいかなる働きよりも先行して(存在論的に)事物の本性のうち」に存在する。
彼の形而上学の業績、特に『形而上学論考』(1597年)は、トマス主義、スコトゥス主義、唯名論という当時の三つの主要な学派を統合し、中世の思想史における体系化の顕著な試みであり、アラビアや中世後期の著作に対する深い注釈も含まれる。彼は当時最高の形而上学者としての名声を得た。これにより、彼は「スアレス主義(Suarism)」と呼ばれる自身の学派を設立した。その主要な特徴は以下の通りである。
- 存在者の固有の具体的実体による個体化原理。
- 質の純粋な可能性の否定。
- 直接的な知覚の対象としての単一性。
- 被創造物の本質と存在の間の「推論された理性の区別」(distinctio rationis ratiocinatae)。
- 相互に数的にのみ区別される精神的実体の可能性。
- 堕天使の罪としての位格的結合への野心。
- アダムが罪を犯さなかったとしても受肉が起こり得たという主張。
- 教会の法における誓約の厳粛性。
- モリーナ主義を修正し、有効恩寵の作用に適した主観的状況、場所、時間の導入によって、恩寵の効力を調和させようとする「合致主義(congruism)」の体系、そして「功績が予見される以前の」(ante praevisa merita)予定説。
- 科学と信仰の両方によって同じ真理を保持する可能性。
- 信仰行為に含まれる神の権威への信頼。
- 聖変化によってキリストの体と血が生産されることが聖餐の犠牲を構成するという見解。
- 聖母マリアの最終的な恩寵が、天使と聖人の恩寵を合わせたものよりも優れているという信仰。
スアレスは『形而上学論考』の第二部(第28章から第53章)で、無限者(神)と有限者(被創造物)の区別を確立している。存在の最初の区分は、無限なる存在と有限なる存在である。存在を無限と有限に分ける代わりに、「それ自体からなる存在」(ens a se)と「他からなる存在」(ens ab alio)、すなわち自己起因的実在と他者起因的実在に分けることもできる。これに対応する第二の区別は、「必然的存在」(ens necessarium)と「偶然的存在」(ens contingens)である。さらに別の区別として、「本質による存在」(ens per essentiam)と「参与による存在」(ens per participationem)、すなわちその本質によって存在する存在と、それ自体で存在する存在への参与によってのみ存在する存在との区別がある。この区別は、トマス・アクィナスが『神学大全』ですでに採用していた。
さらに、「非創造的存在」(ens increatum)と「創造的存在」(ens creatum)、すなわち非被造物と被造物との区別がある。最後の区別は、「純粋活動としての存在」(actus purus)と「潜在的存在」(ens potentiale)、すなわち純粋な現実としての存在と潜在的な存在である。スアレスは、存在の最初の分類、すなわち無限者と有限者への分類を最も根本的なものとして支持し、他の分類もそれに合わせて適切に位置づけた。最後の第54章では、「理性の存在者」(entia rationis)について扱っており、これらは不可能な意図的対象、すなわち私たちの心によって創造されるが、実際の現実には存在できない対象である。
3.2. 神学
神学において、スアレスはエボラの著名なイエズス会教授ルイス・デ・モリーナの教義を支持した。モリーナは、予定説と人間の自由意志の教義、そしてドミニコ会の予定説の教えを調和させようと試みた。その際、予定説は神が人間の意志の自由な決定を予知した結果として生じるものであり、そのため予定説によって意志が何ら影響を受けることはないと主張した。スアレスは、この見解を恩寵の効力と特別な選びに関するより正統的な教義と調和させようと努め、たとえ誰もが絶対的に十分な恩寵を共有するとしても、選ばれた者にはその特有の気質や状況に適合した恩寵が与えられ、それによって彼らは不可避的に、しかし同時に完全に自由にその影響に身を委ねると主張した。この中道的な体系は「合致主義」として知られるようになった。
3.3. 法哲学

法哲学において、スアレスの主要な貢献は、おそらく彼の自然法に関する著作、そして実定法と君主の地位に関する議論に由来する。彼の膨大な著作『法律についての、そして立法者たる神についての論究』(Tractatus de legibus ac deo legislatore、1612年)において、彼はフーゴー・グロティウスやザムエル・フォン・プーフェンドルフの先駆者として、自然法と国際法の重要な区別を行った。彼は国際法を慣習に基づくと見なした。彼の方法は全体としてスコラ学に基づいているが、グロティウスも彼に大いに敬意を払っている。
この著作の根本的な立場は、すべての立法権と父権は神に由来し、すべての法の権威は究極的には神の永遠の法から派生するというものである。スアレスは、当時イングランドおよび大陸の一部で普及していた家父長制的統治論や王権神授説を否定した。彼はトマス・ホッブズやジョン・ロックのような近世の政治哲学者たちの間で支配的となった社会契約論の類型に反論したが、グロティウスによって伝えられた彼の思想の一部は、後の自由主義的な政治理論に影響を与えた。
彼は、人間は神から与えられた社会的本性を持っており、これには法を制定する潜在的な能力が含まれると論じた。しかし、政治社会が形成されると、国家の権威は神からではなく人間から生じるため、その本質は関係する人々によって選択され、彼らの自然な立法権が統治者に与えられる。人々はこの権力を与えたからこそ、統治者が彼らに対して悪く振る舞った場合に限り、その権力を取り戻し、統治者に反抗する権利を持つ。しかし、彼らは節度と正義をもって行動しなければならない。特に、人民は統治者がいかに暴君となろうとも、彼を殺すことから控えなければならない。これに対し、もし政府が人民に強制されたものであるならば、彼らは反抗によって自らを防衛する権利を持ち、さらには暴君を殺害する権利すら持つ。
スアレスは法哲学においてアクィナスから大きな影響を受けたが、いくつかの顕著な相違点がある。アクィナスは「法」を「人間を行為に導き、あるいは行為から遠ざける、行為の規範であり尺度である」(『神学大全』I-II, 90, 1)と広く定義した。スアレスは、この定義は厳密な意味での法ではないもの、例えば不正な命令や完全の勧告にも当てはまるため、広すぎる議論した。
また、スアレスは「法」のアクィナスによるより形式的な定義、すなわち「理性による共同の善のための制定であり、共同体を管理する者によって作られ、公布されたもの」(『神学大全』I-II, 90, 4)にも異議を唱えている。彼はこの定義は、法が主に理性行為ではなく意志行為であることを認識していないと主張し、特定の個人に対する命令を誤って法と数えることになると述べている。
最後に、スアレスは、神が自然法の二次的な戒律の一部、例えば殺人、窃盗、姦通の禁止を変更または停止できるというアクィナスの主張(『神学大全』I-II, 94, 5)に異議を唱えた。スアレスは、人間性が不変である限り自然法は不変であり、神によってなされたように見える自然法の変更は、実際には対象の変更に過ぎないと主張した。例えば、神がホセアに「淫行の妻」(すなわち売春婦と性交すること)を娶るように命じた場合、これは姦通の禁止からの免除ではない。「なぜなら神は、女性の同意なしに男性にその女性に対する「支配権」を移し、両者の間にそのような絆を成立させる力を持っており、その絆によって結合はもはや淫行ではなくなるからである。」
1613年、ローマ教皇パウルス5世の扇動により、スアレスはヨーロッパのキリスト教君主たちに捧げられた『イングランド教会の誤謬に対する普遍的カトリック信仰の擁護』(Defensio catholicae fidei contra anglicanae sectae errores)という論文を執筆した。これはイングランド国王ジェームズ1世が臣民に要求した忠誠の誓いに対抗するものであった。
ジェームズ1世(彼自身も才能ある学者であった)は、この著作を死刑執行人によって焼却させ、最も厳重な罰則の下でその閲覧を禁じ、スペイン国王フェリペ3世に対して、王位と王権の公然たる敵をその領内に匿っていることについて激しく苦情を述べた。
4. 主要な著作
スアレスは多岐にわたるテーマで膨大な数の著作を残し、その多くが当時の学術界に大きな影響を与えた。彼の主要な著作を以下に示す。
- 『受肉について』(De Incarnatione、1590年 - 1592年):キリストの受肉に関する神学的論考。
- 『秘跡について』(De sacramentis、1593年 - 1603年):キリスト教の秘跡に関する詳細な解説。
- 『形而上学論考』(Disputationes metaphysicae、1597年):スアレスの哲学思想の集大成であり、最も影響力のある著作。当時のヨーロッパの大学で広く読まれ、スコラ学の体系化に貢献した。
- 『神の本質と属性について』(De divina substantia eiusque attributis、1606年):神の存在と属性に関する神学的探求。
- 『神の予定と排斥について』(De divina praedestinatione et reprobatione、1606年):予定説と人間の運命に関する神学的議論。
- 『聖三位一体の神秘について』(De sanctissimo Trinitatis mysterio、1606年):三位一体の教義に関する論考。
- 『宗教について』(De religione、1608年 - 1625年):宗教の原理とその実践に関する著作。
- 『法律についての、そして立法者たる神についての論究』(De legibus、1612年):自然法、国際法、そして統治権の起源に関する彼の重要な法哲学著作。グロティウスに影響を与えた。
- 『イングランド教会の誤謬に対する普遍的カトリック信仰の擁護』(Defensio fidei、1613年):イングランド国王ジェームズ1世の忠誠の誓いを批判し、教皇の権威と抵抗権を擁護した政治神学的著作。
- 『恩寵について』(De gratia、1619年):神の恩寵とその人間への作用に関する神学的考察。
- 『天使について』(De angelis、1620年):天使の性質と役割に関する論考。
- 『六日間の創造の業について』(De opere sex dierum、1621年):天地創造に関する神学的解説。
- 『魂について』(De anima、1621年):人間の魂の性質と機能に関する哲学的探求。
- 『信仰、希望、愛徳について』(De fide, spe et caritate、1622年):キリスト教の三つの神学的徳に関する論考。
- 『人間の究極目的について』(De ultimo fine hominis、1628年):人間の究極的な幸福と目的に関する神学的・哲学的議論。
18世紀には、ヴェネツィア版の『全集』(Opera Omnia、23巻、1740年 - 1751年)が出版され、その後パリのヴィヴェス版(26巻+索引2巻、1856年 - 1861年)が刊行された。1965年には、ヴィヴェス版の『形而上学論考』(第25巻 - 第26巻)がゲオルク・オルムス社から再版された。1597年から1636年の間に『形而上学論考』は17版を重ねている。
5. 評価と影響
スアレスの思想は、その革新性と体系性により、後世の哲学者、神学者、法学者に広範かつ多大な影響を与えた。一方で、彼の政治哲学における急進的な主張は、激しい論争と批判を招くことにもなった。
5.1. 肯定的評価と影響
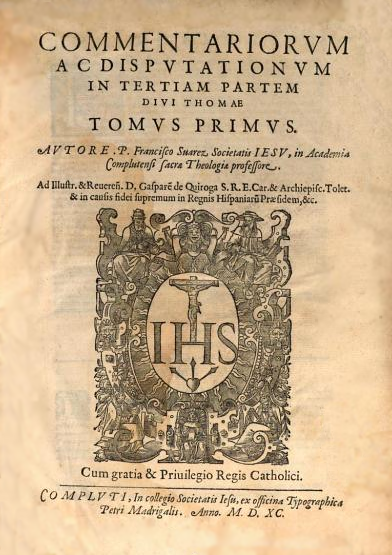
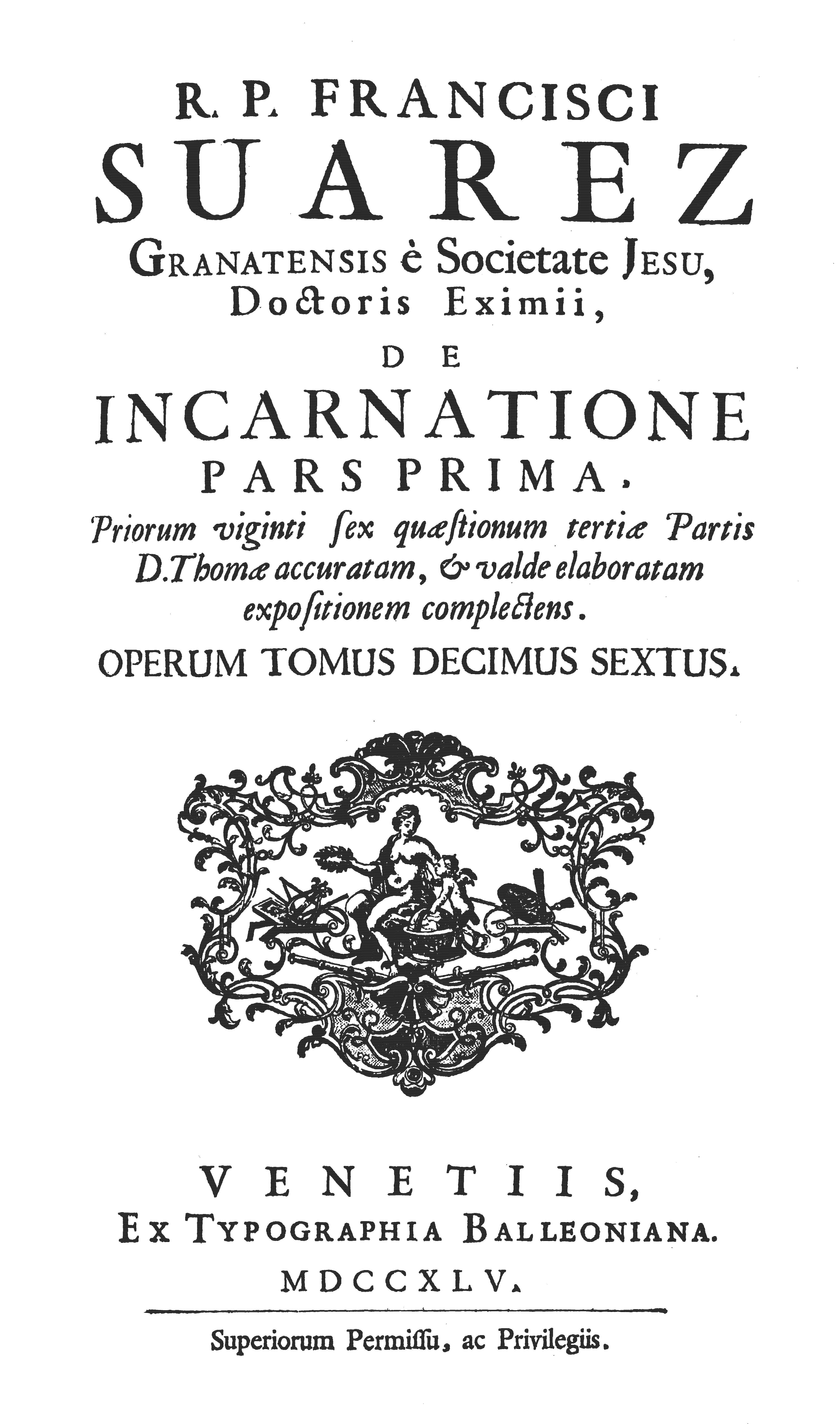
スアレスの形而上学と神学への貢献は、17世紀および18世紀のスコラ学に、カトリックとプロテスタントの両陣営で大きな影響を与えた。特に、彼の『形而上学論考』は、イエズス会の強力な学術ネットワークのおかげもあり、スペイン、ポルトガル、イタリアのカトリック系学校で広く教えられた。
この著作はこれらの学校からドイツの多くのルター派大学にも広まり、特にマルティン・ルターの哲学に対する姿勢よりもフィリップ・メランヒトンを支持する者たちによって研究された。17世紀の多くのルター派大学では、『形而上学論考』が哲学の教科書として用いられた。同様に、スアレスはドイツやオランダの改革派の学校においても、形而上学と法、特に国際法の両分野で大きな影響力を持った。彼の著作は、例えばフーゴー・グロティウス(1583年 - 1645年)によって高く評価された。また、アルトゥル・ショーペンハウアーやマルティン・ハイデッガーといった後世の思想家も彼の著作を引用し、インスピレーションの源としていた。
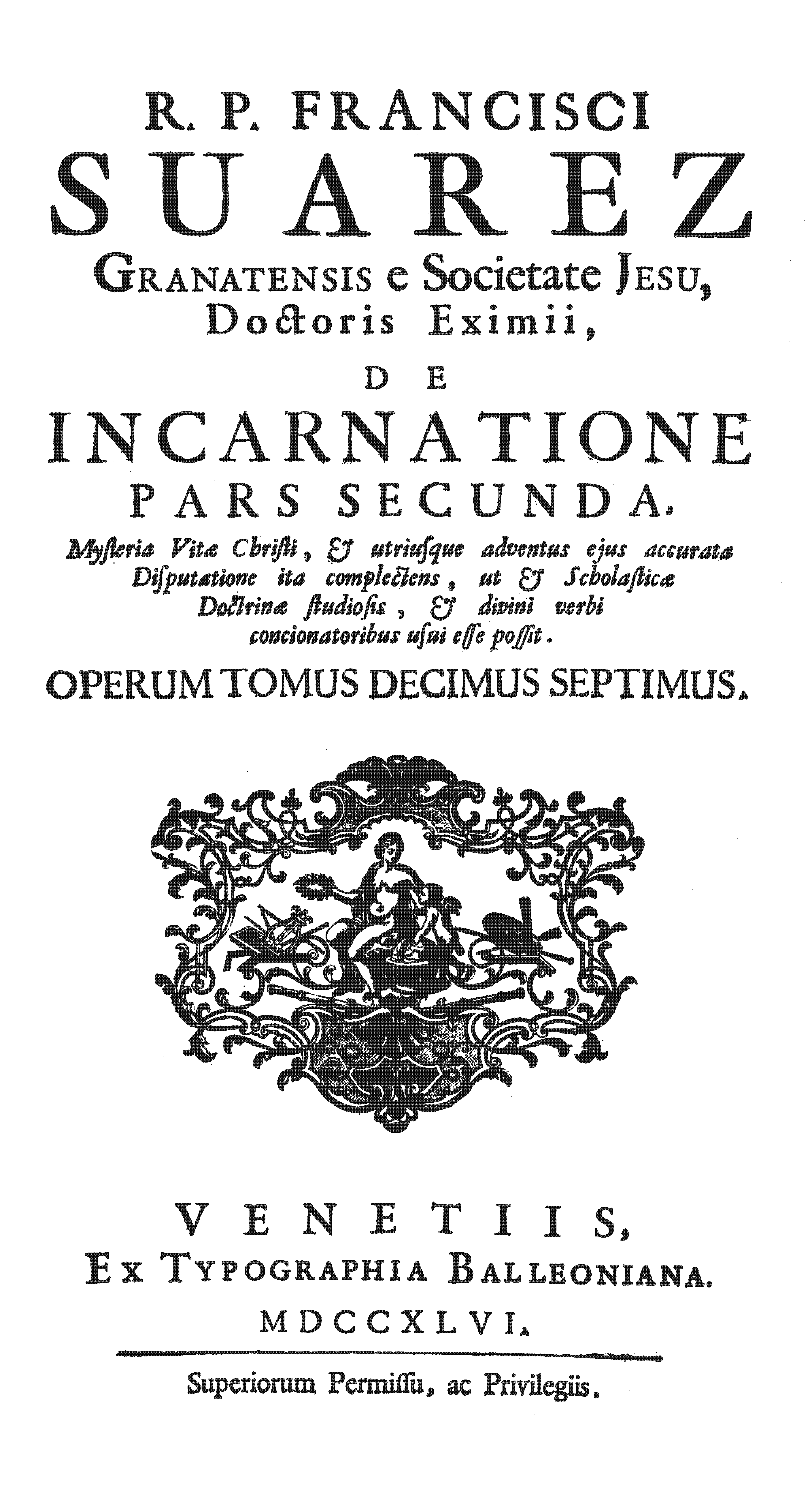
彼の思想は、バルトロメウス・ケッケルマン(1571年 - 1609年)、クレメンス・ティンプラー(1563年 - 1624年)、ギルバート・ジャック(1578年 - 1628年)、ヨハン・ハインリヒ・アルステッド(1588年 - 1638年)、アントニウス・ワラエウス(1573年 - 1639年)、ヨハネス・マッコーヴィウス(ヤン・マコフスキ;1588年 - 1644年)などの著作に顕著に表れている。この影響は非常に広範であったため、1643年にはオランダの改革派神学者ヤコブス・レヴィウスが、彼の著作『Suarez repurgatus』(「浄化されたスアレス」の意)を出版するきっかけとなった。スアレスの『法律についての、そして立法者たる神についての論究』は、ピューリタンのリチャード・バクスターによって法に関する最良の著作の一つとして引用され、バクスターの友人であるマシュー・ヘイルも彼の自然法理論においてこの著作を参考にした。
5.2. 批判と論争
スアレスの政治秩序の人類起源論と、民衆の反対に由来する暴君殺しの擁護論は、イングランドの哲学者ロバート・フィルマーの著作『総家長論』(Patriarcha, Or the Natural Power of Kings)において厳しく批判された。フィルマーは、カルヴァン主義者やスアレスのようなカトリック教徒が、王権神授説の危険な敵であると信じていた。王権神授説は、親が子に持つ優位性によって正当化されるものであり、フィルマーはこれをアダムまで遡れると主張した。
また、スアレスが『イングランド教会の誤謬に対する普遍的カトリック信仰の擁護』で主張した、教皇権の優位性や、人民に由来する国王権力が暴政を行った場合に臣民が君主を廃位または殺害する権利を持つという急進的な思想は、当時のイギリスやフランスにおいて大きな論争を巻き起こした。特にイングランド国王ジェームズ1世は、彼の著作を公共の場で焼却させ、厳しい罰則をもってその閲覧を禁止した。このイエズス会の過激な思想は、宗教改革後のローマ・カトリック教会によるプロテスタントに対する苛烈な弾圧や、カトリックとプロテスタント間の宗教戦争の口実の一つとも見なされた。トマス・ホッブズもまた、彼の主著『リヴァイアサン』の中で、イエズス会のこのような政治思想を批判している。しかし、スアレスの思想は、国際法学においてグロティウスの先駆となるものであり、その影響はプロテスタントの大学にも広く及んだ。