1. 生涯
ユーディ・メニューインは、その生涯を通じて音楽界に大きな足跡を残し、幼少期からの神童としての活躍、戦時中の献身的な活動、そして晩年の教育者・指揮者としての貢献で知られている。
1.1. 幼少期と教育

ユーディ・メニューインは1916年4月22日にニューヨークで生まれた。父モシェはベラルーシのホメリ出身のリトアニア系ユダヤ人であり、母マルタはクリミア・カライム人であった。父モシェを通じて、彼はラビの家系に連なる。モシェとマルタ(旧姓シェア)は、オスマン帝国時代のエルサレム県で出会い、1914年にニューヨークで結婚した。1919年末にはアメリカ市民権を取得し、家族の姓をムヌヒンからメニューインに変更した。メニューインには、ピアニストで人権活動家でもあった姉のヘプシバ・メニューインと、ピアニスト、画家、詩人であった妹のヤルタ・メニューインがいる。
メニューインが初めてヴァイオリンの指導を受けたのは4歳の時で、シグムント・アンカー(1891年-1958年)から教えを受けた。両親は彼をルイス・パーシンガーに師事させたいと望み、パーシンガーもこれに応じた。メニューインはしばらくの間、ハイド・ストリートにあるパーシンガーのスタジオでレッスンを受けた。1921年11月には、生徒の発表会で初の公開ソロ演奏を行った。

1923年、7歳でサンフランシスコ交響楽団と共演し、ソロヴァイオリニストとしてデビューした。この後、パーシンガーは正式に彼の指導を引き受け、1928年から1929年にかけての初期のソロ録音ではピアノ伴奏を務めた。1924年2月29日にはオークランド公会堂で正式にデビューし、その後アルフレッド・ハーツ指揮のサンフランシスコ交響楽団とのソロ共演、スコティッシュ・ライト・ホールでのリサイタルを行った。彼の名声は先行してニューヨークに伝わり、1926年3月17日にはマンハッタン・オペラハウスでニューヨークデビューを果たした。
メニューイン一家がパリに移住した際、パーシンガーはメニューインに自身の恩師であるベルギーの巨匠で教育者のウジェーヌ・イザイに師事することを勧めた。メニューインはイザイから一度レッスンを受けたものの、イザイの指導法や高齢を理由に好まなかった。代わりに、ルーマニアの作曲家でヴァイオリニストのジョルジュ・エネスクに師事し、彼の指導の下、姉のヘプシバを含む複数のピアニストと録音を行った。彼はまた、バーゼルでアドルフ・ブッシュの生徒でもあった。彼はスイスのこの都市に1年以上滞在し、そこでドイツ語とイタリア語のレッスンも受け始めた。
1.2. 初期経歴
1929年4月12日、ゼンパー・オーパーは予定されていたプログラムをキャンセルし、12歳のユーディ・メニューインの演奏会を開催した。その夜、彼はバッハ、ベートーヴェン、ブラームスのヴァイオリン協奏曲を演奏し、観客を熱狂させた。その1週間前には、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とブルーノ・ワルターの指揮の下、ベルリンで演奏し、同様に熱狂的な反応を得ていた。ある新聞評論家は、彼のベルリンでの演奏について次のように評した。「太った小さな金髪の少年が指揮台に上がり、ペンギンのように交互に片足を踏み出す、たまらなく滑稽な姿でたちまち皆の心を掴む。しかし待て、彼がヴァイオリンに弓を当ててバッハのヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調を演奏し始めれば、笑いは止まるだろう。」
彼の最初の協奏曲録音は1931年にロンドンで行われたブルッフのト短調協奏曲で、サー・ランドン・ロナルドの指揮によるものであった。レーベルには「マスター・ユーディ・メニューイン」と記されている。1932年には、エドワード・エルガー自身の指揮でエルガーのヴァイオリン協奏曲ロ短調をロンドンでHMVのために録音した。1934年には、ピエール・モントゥーの指揮の下、パリでエミール・ソレのカデンツァによるパガニーニのニ長調協奏曲をノーカットで録音した。1934年から1936年にかけて、彼はヨハン・ゼバスティアン・バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータの最初の全曲録音を行ったが、ソナタ第2番イ短調は全6曲がCD化されるまでリリースされなかった。
バルトーク・ベーラの音楽への関心から、彼はバルトークに作品の委嘱を行った。その結果生まれたのが無伴奏ヴァイオリンソナタで、1943年に完成し、1944年にニューヨークでメニューインによって初演された。これは作曲家にとって最後から2番目の作品となった。
2. 主要活動および業績
ユーディ・メニューインは、ヴァイオリニスト、指揮者、教育者、そして社会活動家として、多岐にわたる分野で顕著な功績を残した。
2.1. バイオリン演奏者としての活動

メニューインは20世紀を代表するヴァイオリニストの一人として、そのキャリアを通じて数々の重要な演奏と録音を行った。彼は、バルトーク・ベーラやエドワード・エルガーといった作曲家たちと直接交流し、彼らの作品の初演や録音に貢献した。特にエルガーのヴァイオリン協奏曲は、作曲家自身の指揮で録音された彼の代表的な録音の一つである。
彼はまた、ラヴィ・シャンカルやステファン・グラッペリといった異なるジャンルの音楽家とも共演し、音楽の境界を越えた活動を展開した。1966年にはバース国際音楽祭でシャンカルと共演し、その成功を基に1967年に共作アルバム『West Meets East英語』を発表、グラミー賞最優秀室内楽パフォーマンス賞を受賞した。この共同作業は『West Meets East, Volume 2英語』(1968年)、『West Meets East, Volume 3英語』(1976年)と続き、後者にはジャン=ピエール・ランパルも参加した。1970年代にはジャズ・ヴァイオリニストのステファン・グラッペリと共演し、1930年代のクラシック曲を集めたアルバム『Jalousie英語』を制作した。
メニューインは数々の名器を演奏したことでも知られている。最も著名なのは、1742年製のグァルネリ・デル・ジェス(愛称「ロード・ウィルトン」)である。その他にも、1680年製のジョヴァンニ・ブッセート、1695年製のジョヴァンニ・グランチーノ、1703年製のグァルネリ・フィリウス・アンドレア、ストラディバリウスの「ソイル」、1733年製の「プリンス・ケフェンヒューラー・ストラディバリ」、そして1739年製のジュゼッペ・グァルネリ・デル・ジェスなどを演奏した。彼は自伝『Unfinished Journey英語』の中で、「偉大なヴァイオリンは生きている。その形そのものが製作者の意図を体現し、その木材には歴代の所有者の歴史、あるいは魂が宿っている。私は、魂を解き放つ、あるいは、残念ながら侵害する感覚なしに演奏することはない」と記している。
2.2. 指揮者としての活動
メニューインは後半生において、ヴァイオリニストとしての活動に加え、指揮者としても精力的に活動した。1984年から1999年に亡くなるまで、シンフォニア・ヴァルソヴィアの初代客演指揮者を務め、300回以上の公演を行った(その約半分は1996年から1998年の間に行われた)。彼は「他のどのオーケストラとの仕事も、シンフォニア・ヴァルソヴィアとのソリストとして、また指揮者としての仕事ほど満足感を与えてくれなかった」と語っている。また、著書『Unfinished Journey: Twenty Years Later英語』では、「彼ら(シンフォニア・ヴァルソヴィア)とできるだけ多くの時間を過ごし、共に音楽を創り出すことから得られる深い満足感を享受することは、真のインスピレーションであった」と付け加えている。1991年にはイングリッシュ・シンフォニー・オーケストラの首席客演指揮者に就任し、この職も亡くなるまで務めた。
1990年には、アジアン・ユース・オーケストラの初代指揮者を務め、ジュリアン・ロイド・ウェバーやアジア各地の若い才能ある音楽家たちと共に、日本、台湾、シンガポール、香港を含むアジア各地をツアーした。
2.3. 第二次世界大戦中の活動

第二次世界大戦中、メニューインは連合軍兵士のために慰問演奏を行った。そして、1945年4月に解放された後、同年6月と7月には、ベンジャミン・ブリテンのピアノ伴奏で、ベルゲン・ベルゼン強制収容所をはじめとするいくつかの強制収容所の生存者のために演奏を行った。
戦後間もない1947年には、和解の行為としてドイツを再訪し、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と協奏曲を演奏した。彼はホロコースト後、ドイツの音楽と精神を回復させたいと述べ、ユダヤ人批評家に対して、ドイツを再訪した初のユダヤ人音楽家となった。
2.4. 国際活動と文化交流
メニューインは、ドイツとの和解を試みたことで、ユダヤ人社会から反発を受けたが、「ヒトラーのドイツは滅びたのです」と述べ、ドイツの音楽と精神の回復を訴えた。彼は、ナチス時代にドイツで指揮を執ったことで批判されていたヴィルヘルム・フルトヴェングラーを擁護し、フルトヴェングラーが多くのユダヤ人音楽家のナチス・ドイツからの脱出を助けたことを指摘した。
戦後間もない1951年、彼はアメリカの親善大使として日本を訪れた。この初来日の際、当初はアメリカ人として日本に悪感情を抱いており、日本の新聞記者に対して「ジャーナリストなら、真珠湾攻撃を知っていただろう?」と詰問したこともあった。しかし、この来日中に日本に対する感情が大きく変化し、大の親日家となった。後年、彼は武満徹がアンドレイ・タルコフスキーの死を悼んで作曲した弦楽合奏曲『ノスタルジア』を絶賛し、自らこの曲を演奏した。また、皇室とも親交を持ち、皇后のピアノ伴奏でヴァイオリンを弾くなどしている。この来日中に出会った靴磨きの少年にヴァイオリンを贈ったという美談が『朝日新聞』に掲載され、後にこの美談を基にした創作童話『少年とバイオリン~音楽の神様からの贈り物~』(滝一平作、宇野亜喜良画、國分紘子解説、ヤマハミュージックメディア)も出版された。
彼はソ連のユダヤ系演奏家と親しい関係を結び、ダヴィッド・オイストラフの初訪米を実現するために国務省の友人に協力を依頼したり、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチがその反体制的な姿勢からソ連当局から嫌がらせを受け、出国を妨害された際には、自らソ連当局に圧力をかけるなど、共産主義体制下のソ連音楽家を支援した。
1950年から1951年にかけて、スイスのジュネーヴで開催された「人民の世界大会」(Peoples' World Convention英語、またはPeoples' World Constituent Assembly英語)のスポンサーの一人でもあった。1975年には、国際音楽評議会の会長として、10月1日を国際音楽の日と宣言した。この国際音楽の日は、1973年にローザンヌで開催された第15回国際音楽評議会総会で採択された決議に基づき、同年から実施された。1992年にはユネスコの親善大使に任命された。
2.5. 教育および慈善活動
メニューインは音楽教育の振興と社会貢献にも尽力した。1957年にはスイスのグシュタードでメニューイン・フェスティバル・グシュタードを創設した。1962年にはサリー州ストーク・ダバーノンにユーディ・メニューイン音楽学校を設立した。また、同時期にカリフォルニア州ヒルズボロのヌエヴァ・スクールでも音楽プログラムを確立した。
1955年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで審査員を務めた後、メニューインは財政難に陥っていたグランプリ受賞者であるアルゼンチンのヴァイオリニスト、アルベルト・リジーのためにロックフェラー財団の助成金を取り付けた。メニューインはリジーを唯一の個人指導生徒とし、二人はヨーロッパ各地のコンサートホールで広範なツアーを行った。この若き弟子は後に、師を称えてグシュタードに国際メニューイン音楽アカデミー(IMMA)を設立した。
1977年には、イアン・スタウトツカーと共に慈善団体「Live Music Now英語」を設立した。これは英国最大の音楽アウトリーチプロジェクトであり、プロの音楽家を雇用・訓練し、地域社会で活動させ、生演奏を聴く機会が少ない人々にその体験を届けている。
1983年には、ロバート・マスターズと共にユーディ・メニューイン国際青少年ヴァイオリンコンクールを設立した。これは今日、若い才能のための世界有数のフォーラムの一つとなっており、その受賞者の中にはタスミン・リトル、ニコライ・ズナイダー、イリヤ・グリンゴルツ、ユリア・フィッシャー、樫本大進、レイ・チェンなど、著名なヴァイオリニストが多数含まれている。
1980年代には、「音楽ガイド」シリーズの書籍を執筆・監修した。このシリーズは各楽器と声楽を扱っており、メニューイン自身が執筆したものもあれば、他の著者が編集したものもあった。彼はまた、プリアウ・レイニエにヴァイオリン協奏曲『Due Canti e Finale英語』の作曲を委嘱し、エディンバラ国際フェスティバルで初演した。さらに、レイニエの最後の作品である『Wildlife Celebration英語』も委嘱し、ジェラルド・ダレルのダレル野生動物保護基金のために演奏した。
3. 思想および関心事
メニューインは、音楽以外の分野にも深い関心を持ち、哲学、精神世界、そして個人の生活様式に至るまで、多様な探求を行った。
3.1. ヨガと精神世界
メニューインは精神世界に強い興味を持ち、坐禅やヨーガの実践を通じて、心身のバランスを保とうと努めた。1953年には『Life英語』誌に、彼が様々な神秘的なヨガのポーズをとる写真が掲載された。1952年、インドを訪れたメニューインは、新国家初代首相のジャワハルラール・ネルーによって、当時国内ではほとんど知られていなかった影響力のあるヨガ行者B.K.S.アイアンガーに紹介された。メニューインはアイアンガーがロンドン、スイス、パリなど海外で教える手配をし、アイアンガーは西洋で教える最初の著名なヨガマスターの一人となった。
メニューインはまた、1948年にロサンゼルスで米国初のヨガスタジオを開設したインドラ・デヴィからもレッスンを受けた。デヴィとアイアンガーは共に、インドの有名なヨガマスターであるクリシュナマチャリアの生徒であった。
3.2. 哲学および政治的観点
彼はユダヤ系ドイツ人哲学者コンスタンティン・ブルンナーの思想に深く傾倒し、ブルンナーが彼に「人生の出来事や経験を当てはめることができる理論的枠組み」を提供してくれたと語っている。ブルンナーがシオニズムに反対し、キリスト教に近い立場を貫いたことから、メニューインもヨーロッパ人の同化主義者の姿勢を選び、アイザック・スターンなどに比べて、イスラエルの利害に対する関心が著しく低かった。
1991年、イスラエル政府からウルフ賞を授与された際、クネセトでの受賞スピーチで、イスラエルによるヨルダン川西岸地区の継続的な占領を批判した。彼は、この無駄な恐怖による統治、命の基本的な尊厳に対する軽蔑、従属する人々への絶え間ない窒息は、そのような存在の恐ろしい意味、忘れがたい苦しみを自ら知りすぎている人々が採用すべき最後の手段であるべきだと述べた。また、約5000年間、道徳的公正の規範を守ろうと努力し、私たちが見るような社会を自ら創造し達成できるにもかかわらず、その偉大な資質と恩恵を彼らの中に住む人々と分かち合うことを拒否する、彼の偉大な民であるユダヤ人にはふさわしくないと付け加えた。
また、晩年には、ホロコーストに疑問を投げかけたフランスの左翼系哲学者ロジェ・ガロディを支持したことなど、物議を醸す言動も見られた。
3.3. 生活方式
彼はペスカタリアン(魚は食べるが肉は食べない菜食主義者)であった。
4. 個人史
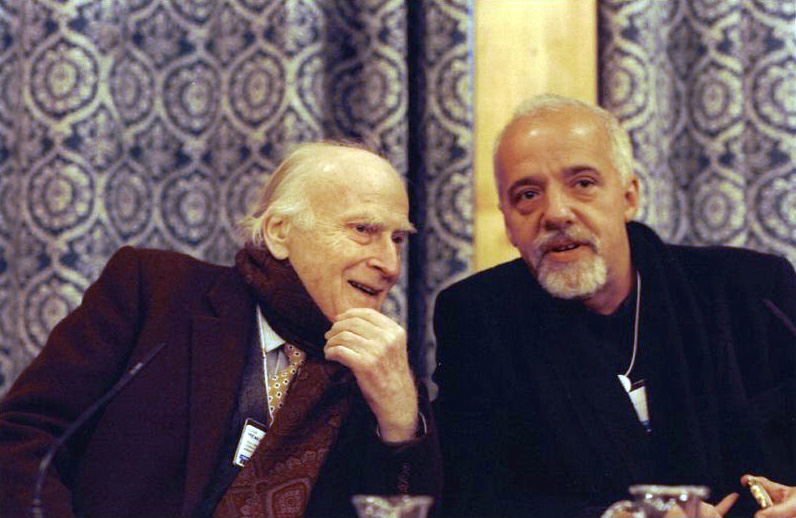
メニューインは生涯で2度結婚している。最初の妻はオーストラリアの実業家の娘で、姉ヘプシバの最初の夫リンゼイ・ニコラスの妹であったノーラ・ニコラスである。彼らにはクローヴとザミラ(ピアニストのフー・ツォンと結婚)という2人の子供がいた。1947年に離婚した後、彼はイギリスのバレリーナで女優のダイアナ・グールドと結婚した。ダイアナの母はピアニストのエヴリン・スチュアート、継父はセシル・ハーコート提督であった。夫妻には、ホロコースト否認者で極右活動家として知られるジェラード・メニューインと、ピアニストのジェレミー・メニューインという2人の息子がいた。3人目の子供は出生後まもなく亡くなっている。1960年代から1970年代にかけて、彼らはハイゲートのザ・グローヴ2番地に住んでいた。この家は後にスティングが所有した。
「Yehudiヘブライ語」という名前は、ヘブライ語で「ユダヤ人」を意味する普通名詞の男性単数形である。2004年10月に再掲載された『New Internationalist英語』誌のインタビューで、彼は自身の名前の由来について次のように語っている。
自分たちのアパートを見つけなければならなくなった両親は、近所を探し、公園から徒歩圏内の物件を選んだ。大家が部屋を見せた後、彼らを送り出す際に言った。「そして、喜んでいただきたいのですが、私はユダヤ人はお断りしています。」大家の誤解が彼女に明らかになると、その反ユダヤ主義の大家は断られ、別のアパートが見つかった。しかし、彼女の失態は跡を残した。通りに戻った母は誓いを立てた。生まれてくる赤ちゃんには、彼の民族を世界に宣言するラベルを付けるだろう。彼は「ユダヤ人」と呼ばれるだろう、と。
メニューインは1970年にスイスの名誉市民となり、その後1985年にはイギリスの市民権も取得した。
5. 死去および遺産
メニューインは1999年3月12日、ドイツベルリンのマルティン・ルーサー病院で気管支炎の合併症により82歳で死去した。彼の死後まもなく、王立音楽アカデミーは「ユーディ・メニューイン・アーカイブ」を取得した。これには、演奏のために書き込まれた楽譜、メニューインに関する書簡、ニュース記事、写真、自筆の音楽原稿、そしてニコロ・パガニーニの肖像画数点が収められている。このアーカイブは、一人の音楽家によって収集された最も貴重で包括的なコレクションの一つとされている。
6. 評価および批判
ユーディ・メニューインは、その音楽的才能と人道主義的活動により広く尊敬を集めたが、彼の特定の政治的見解や行動は論争の的となることもあった。
6.1. 肯定的評価
メニューインは、20世紀を代表するヴァイオリニストとして、その卓越した技術と深い音楽性で世界中の聴衆を魅了した。彼は幼少期から「神童」と称され、その演奏は常に高い評価を受けてきた。
音楽家としての業績に加え、彼は人道主義者としても多大な貢献をした。第二次世界大戦中の連合軍兵士への慰問演奏や、解放後の強制収容所での演奏は、彼の深い共感と平和への願いを示している。また、戦後のドイツとの和解への尽力は、困難な状況下での彼の勇気と寛容さを象徴するものである。
教育者としても、ユーディ・メニューイン音楽学校や国際メニューイン音楽アカデミーの設立を通じて、多くの若い音楽家を育成し、その才能を開花させるための機会を提供した。彼はまた、国際音楽の日を提唱するなど、音楽の普及と文化交流の促進にも貢献した。彼の活動は、音楽が持つ癒しと統合の力を信じる彼の信念に基づいていた。
6.2. 批判と論争
メニューインは、その政治的見解、特にイスラエルに対する批判的な姿勢や、特定の哲学者への支持を巡って批判や論争に直面することもあった。
彼はシオニズムに対して批判的な見解を持ち、イスラエルによるヨルダン川西岸地区の占領を公然と非難した。1991年にイスラエル政府からウルフ賞を授与された際の受賞スピーチでは、この占領を「恐怖による無駄な統治」「従属する人々への絶え間ない窒息」と表現し、「私の偉大な民であるユダヤ人にはふさわしくない」と述べた。この発言は、ユダヤ人社会から強い反発を招いた。
また、晩年にホロコースト否認者として知られるフランスの哲学者ロジェ・ガロディを支持したことは、大きな物議を醸した。この行動は、彼の過去の人道主義的活動とは矛盾すると見なされ、彼の評価に影を落とすこととなった。
7. 受賞および栄誉
ユーディ・メニューインは、その卓越した音楽的才能と多岐にわたる活動に対し、世界各国から数多くの賞と栄誉を授与された。
| 年 | 賞・栄誉 | 備考 |
|---|---|---|
| 1965 | 大英帝国勲章ナイト・コマンダー(KBE) | 当時はアメリカ市民であったため名誉勲章。後にイギリス市民権取得により実質的な勲章となる。 |
| 1965 | エディンバラ市名誉市民 | |
| 1968 | ジャワハルラール・ネルー国際理解賞 | |
| 1969-1975 | 国際音楽評議会会長 | |
| 1970 | トリニティ音楽大学学長 | |
| 1972 | レオニー・ソニング音楽賞 | デンマーク |
| 1983 | エルガー協会会長 | |
| 1984 | エルンスト・フォン・ジーメンス音楽賞 | |
| 1986 | ケネディ・センター名誉賞 | |
| 1987 | メリット勲章(OM) | |
| 1987 | ブリット・アワード最優秀英国クラシック録音賞 | ジュリアン・ロイド・ウェバーとのエルガーのチェロ協奏曲の録音に対して。 |
| 1990 | グレン・グールド賞 | 長年の貢献を称えて。 |
| 1991 | ウルフ賞芸術部門 | |
| 1991 | フィッツウィリアム・カレッジ名誉フェロー | |
| 1992 | ユネスコ親善大使 | |
| 1993 | 一代貴族(ストーク・ダバーノンのメニューイン男爵) | サリー州ストーク・ダバーノンにちなむ。 |
| 1994 | サンギート・ナタク・アカデミーフェローシップ | インドの音楽、舞踊、演劇の国立アカデミーによる最高栄誉。 |
| 1994 | コネック財団コネック勲章 | アルゼンチン |
| 1997 | オットー・ハーン平和メダル(金メダル) | ドイツ国連協会(DGVN)より。 |
| 1997 | アストゥリアス皇太子賞(平和部門) | ムスティスラフ・ロストロポーヴィチと共同受賞。 |
| 1997 | ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章 | |
| 1998 | 聖ヤコブの剣軍事勲章大十字章 | ポルトガル |
| 多数 | 名誉博士号 | オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、セント・アンドルーズ大学、ブリュッセル自由大学、バース大学など20大学から。 |
| 多数 | 名誉市民 | エディンバラ、バース、ランス、ワルシャワ。 |
| 多数 | 金メダル | パリ、ニューヨーク、エルサレム。 |
| 不明 | カラマズー大学名誉学位 |
また、ブリュッセルの欧州議会にあるコンサート・パフォーマンスホールは「ユーディ・メニューイン・スペース」と名付けられている。
8. 文化的な影響
ユーディ・メニューインは、クラシック音楽界のみならず、大衆文化にもその影響を及ぼした。
- 1930年代から1940年代にかけて流行した流行語「Who's Yehoodi?英語」は、メニューインがラジオ番組にゲスト出演した際に、ジェリー・コロンナが「イェフーディ」を謎の不在人物を表すスラングとして広めたことに由来する。この言葉は最終的にメニューインとの元の関連性を失った。
- 彼は、モアカム・アンド・ワイズ・ショーの1971年のクリスマス特番に出演する予定であったが、「バーケンヘッドのアーガイル劇場で『オールド・キング・コール』の公演がある」ため出演できなかった。彼はアンドレ・プレヴィン指揮の有名な「グリーグのピアノ協奏曲」のスケッチでエリック・モアカムに置き換えられた。また、1973年のクリスマス特番では、「ヴァイオリンではだめだ」と言われ、「バンジョー」を演奏するために招待されたが、彼は「お役に立てない」と残念そうに答えた。
- 子供時代のメニューインの写真は、時に主題統覚検査の一部として使用されることがある。