1. 概要
第48代横綱である大鵬幸喜は、1940年(昭和15年)5月29日に樺太敷香郡敷香町(現在のロシアサハリン州ポロナイスク市)で生まれ、2013年(平成25年)1月19日に72歳で亡くなった日本の大相撲力士である。出生名は納谷 幸喜なや こうき日本語、またІван Маркіянович Боришкоイヴァーン・マルキャノヴィチ・ボリシコウクライナ語というウクライナ語名も持っていた。彼は第二次世界大戦後の相撲界において、最も偉大な力士の一人と広く評価されている。
大鵬は1961年(昭和36年)に当時史上最年少の21歳3ヶ月で横綱に昇進し、1960年(昭和35年)から1971年(昭和46年)にかけて32回の幕内最高優勝を果たした。この優勝回数は2014年(平成26年)まで破られることのない記録であり、白鵬翔が2015年(平成27年)1月場所に33回目の優勝を果たすまで最多記録として君臨した。彼の支配力は絶大で、6場所連続優勝を2回達成し、1968年(昭和43年)から1969年(昭和44年)にかけては双葉山定次以来となる45連勝を記録した。また、幕内での現役生活中、毎年少なくとも1回は優勝を果たした唯一の力士である。
彼は特に女性や子供たちに人気の高い大横綱であり、当時の流行語となった「巨人・大鵬・卵焼き」は彼の社会的な存在感を象徴している。現役引退後は相撲の親方として相撲部屋を経営したが、健康問題に悩まされ、その活動は限定的であった。しかし、その功績は広く認められ、2004年(平成16年)に紫綬褒章、2009年(平成21年)には文化功労者に選出され、相撲界から初の栄誉となった。死去後、2013年(平成25年)2月には国民栄誉賞が追贈され、「国民的英雄」と称された。
2. 来歴と背景
大鵬幸喜の生涯は、彼の出生地である樺太での過酷な幼少期から始まり、北海道での貧しい少年時代を経て、相撲の道に進むまでの波乱に満ちた背景を持つ。
2.1. 誕生と幼少期
大鵬幸喜は1940年(昭和15年)5月29日、日本の領有下にあった南樺太の敷香町(現在のロシアサハリン州ポロナイスク)で、ウクライナ人の父マルキャン・ボリシコと日本人の母納谷キヨの三男として生まれた。彼の出生名はІван Маркіянович Боришкоイヴァーン・マルキャノヴィチ・ボリシコウクライナ語、また日本名では納谷幸喜であった。父マルキャンはロシア革命後に日本に亡命した元コサック騎兵将校であり、いわゆる白系ロシア人の一人であった。南樺太は当時日本領であったため、大鵬は外国出身横綱とは見なされない。
太平洋戦争末期、1945年(昭和20年)にソ連軍が南樺太に侵攻した際、大鵬は母と共に最後の引き揚げ船である小笠原丸で北海道への引き揚げを余儀なくされた。当初は小樽市へ向かう予定であったが、母子の体調不良(大鵬本人の証言では、幼かった大鵬が下船を駄々をこねたため)により、途中の稚内市で下船した。その後、小笠原丸は留萌市沖でソ連潜水艦L-12の魚雷攻撃を受け沈没する(三船殉難事件)が、大鵬親子は難を逃れた。この経験は、戦火とは無縁の環境で育った同時代のライバル柏戸剛とは対照的なものであった。
北海道での生活は母子家庭であったため非常に貧しかった。母の再婚により一時的に住吉姓を名乗った時期もあったが、その再婚相手が教師であったため毎年転勤を繰り返し、一家は北海道各地を転々とした。大鵬自身も家計を助けるため納豆を売り歩くなど、貧しい少年時代を送った。10歳で母が再婚相手と離婚したため、再び納谷姓に戻った。
2.2. 相撲への入門
中学校卒業後、大鵬は金の卵として北海道弟子屈高等学校の定時制に通いながら林野庁関連の仕事に従事していた。1956年(昭和31年)、二所ノ関(後の二所ノ関親方)一行が訓子府町に巡業に来た際、大鵬は紹介を受けて高校を中途退学し、二所ノ関部屋へ入門した。入門当初、母からは反対されたが、相撲部屋を見学した際に力士たちの礼儀正しさに感銘を受けた叔父が母を説得し、入門が実現した。また、巡業で振る舞われたちゃんこの美味しさも入門の動機の一つであったという。
1956年9月場所で初土俵を踏んだ。同期には、後の大関清國勝雄や小結沢光幸夫、前頭大心昇、玉嵐孝平らがいる。入門当初から大鵬は柏戸と共に横綱確実の大器と評され、「二所ノ関部屋のプリンス」「ゴールデンボーイ」といった愛称で呼ばれた。序ノ口時代から大幅な勝ち越しで順調に番付を上げ、1958年3月場所では三段目で優勝した。幕下時代には腰椎を損傷するなど厳しい稽古による負担があったものの、公式発表されるほどの怪我でなければ相手に気づかれないよう工夫して稽古に励んだ。
1959年(昭和34年)に十両昇進が決まると、それまで本名の納谷幸喜で土俵に上がっていた彼に四股名が与えられることになった。故郷の北海道に因んだ四股名を期待していた大鵬に、二所ノ関は「もっといい名前がある。『タイホウ』だ」と告げた。その四股名「大鵬」は、中国の古典『荘子 逍遥遊』に登場する伝説上の巨大な鳥「鵬(peng、しばしば鳳凰と訳される)」に由来しており、「翼を広げると三千里、ひと飛びで九万里の天空へ飛翔する」という意味が込められていた。漢詩を好む二所ノ関が最も有望な弟子に与えるべく温存していた名前であり、大鵬の成長は師の期待以上であった。
3. プロ相撲経歴
大鵬幸喜のプロ相撲選手としてのキャリアは、彼が相撲史にその名を刻むことになる比類なき記録と支配の時代によって特徴づけられる。
3.1. 初期昇進
1960年(昭和35年)1月場所で新入幕を果たすと、大鵬は初日から11連勝という鮮烈なデビューを飾った。これは千代の山雅信の13連勝に次ぐ昭和以降2位の記録であり、一場所での連勝としては昭和以降最多である。12日目には、将来のライバルとなる小結柏戸剛と早くも対戦し、これが彼の幕内での初黒星となった。最終的に12勝3敗の好成績を収め、敢闘賞を受賞した。この場所では計3人の三役と対戦したが、当時の観客からは「小結、関脇では相手不足で、大関・横綱と組ませても五分に戦えるのではないか」とまで言われるほどの評価を得ていた。
同年3月場所では東前頭4枚目まで番付を上げたが、横綱朝潮との初挑戦で敗れるなど、序盤から横綱・三役陣に連敗を喫した。特に4日目には前場所優勝の栃錦清隆に敗れたが、これは栃錦との唯一の対戦となった(栃錦は翌場所引退)。この場所は、大鵬が生涯で唯一となる皆勤負け越し(7勝8敗)を記録した場所であり、柏戸と大鵬が共に幕内で皆勤して取組が組まれなかった唯一の場所でもある。
しかし、続く5月場所では東前頭6枚目に下がって出直しとなったが、初日に朝潮を破り、生涯唯一の金星を獲得するなど11勝4敗で二度目の敢闘賞を受賞した。7月場所で新小結に昇進すると、この場所でも11勝4敗の好成績を残し、9月場所では当時史上最年少となる20歳3ヶ月で新関脇となった。さらに11月場所では13勝2敗の成績で、これも当時の史上最年少となる20歳5ヶ月で幕内最高優勝を達成し、場所後には史上最年少で大関へ昇進した。入幕した年に大関昇進を果たした力士は2019年現在でも大鵬のみであり(入幕から6場所での大関昇進も、年6場所制後最短)、同じく入幕した1960年に年間最多勝を獲得するという、この賞が発足して以来唯一の記録を樹立した。小結・関脇の番付をわずか3場所で通過し、合計36勝9敗という圧倒的な強さを見せつけた。この11月場所をきっかけに、TBSアナウンサーの小坂秀二が発した「柏鵬時代」という言葉が一気に定着した。
3.2. 横綱への昇進
1961年(昭和36年)1月場所で新大関として臨んだ場所では10勝5敗に終わり、13勝2敗で初優勝を飾った柏戸に主役を譲る形となり、綱取りの面でも一歩先んじられた。しかし、翌3月場所からはほぼ毎場所優勝争いに絡む活躍を見せ、7月場所では柏戸と朝潮(元朝汐)を連破して13勝2敗を記録し、大関として初の優勝を果たした。朝潮とはこの取組で対戦成績を4勝4敗の五分とし、これが最後の対戦となった。9月場所では14日目に柏戸に敗れて3敗目を喫したが、柏戸と平幕明武谷力伸との優勝決定戦に臨み、巴戦を制して2場所連続優勝を達成した。
この活躍を受け、場所後日本相撲協会は横綱審議委員会に大鵬・柏戸両名の横綱昇進を諮問し、両名とも満場一致で横綱に推薦された。大鵬は21歳3ヶ月、柏戸は22歳9ヶ月での横綱昇進となり、ともに当時の最年少記録だった照國萬藏の23歳3ヶ月を更新した(大鵬の記録は後に北の湖敏満の21歳2ヶ月に更新される)。横綱審議委員会が内規を定めてから、大関で2場所連続優勝を果たして横綱に昇進したのは大鵬が初めてであった。昇進時の口上は「横綱の地位をけがさぬよう今後も精進します」であった。彼の出生地である樺太は日本領であったため、大鵬は日本国籍を有しており、初めての非日本人横綱とは見なされなかった。
3.3. 横綱としての支配
柏戸と同時昇進し、1961年(昭和36年)には両者が揃って横綱に推挙されたことで、「柏鵬時代」と呼ばれる相撲の黄金時代を築き上げた。後に第69代横綱となった白鵬翔の四股名は、この両横綱に由来している。新横綱として臨んだ1961年(昭和36年)11月場所と1962年(昭和37年)1月場所を連続優勝し、新横綱としては異例の好成績でその地位を確立した。さらに同年7月場所から1963年(昭和38年)5月場所まで、最初の6連覇を達成した。
しかし、この時期は「型のある相撲」と評された柏戸が休場を繰り返す一方で、「型のない相撲」の大鵬が一人勝ちする状況が続き、相撲人気の低迷期と重なった。NET(現在のテレビ朝日)は1964年(昭和39年)5月限りで、日本テレビとTBSは1965年(昭和40年)1月限りで大相撲中継から撤退しており、これは大鵬の常勝による土俵のマンネリ化が一因とされている。神風正一などからは「型がない」と批判されたが、師匠の二所ノ関は「型がないのが大鵬の型」と反論した。大鵬自身も当時の時津風理事長が「『これは大鵬しかできるものがいなかった』という相撲の内容を示せばいい。後世に至ってもどの力士も真似のできないもの、それが大鵬の型である」と語ったことで、自身の相撲に確信を持てるようになったと述べている。
大鵬は柏戸を圧倒する強さを見せ、横綱在位中特にキャリアの初期においては比類なき支配力を誇った。2005年(平成17年)に第68代横綱朝青龍明徳が記録を更新するまで、彼は戦後唯一の6場所連続優勝を2度達成した横綱であった。また、全勝優勝(15勝0敗)を8回記録しており、これは2013年(平成25年)に白鵬によって破られるまで最多数であった。
1964年(昭和39年)には本態性高血圧により幕内初の途中休場となり、入院を余儀なくされた。退院後すぐに二所ノ関から龍沢寺での座禅を命じられた。さらに1965年(昭和40年)には柏戸や北の富士勝昭と共にアメリカから拳銃を密輸入していたことが発覚し、書類送検され、罰金3.00 万 JPYの略式起訴処分を受けた。警視庁の調べに対し、大鵬は「若羽黒の件がバレ、怖くなって隅田川に捨てた」と供述した。しかし日本相撲協会からは譴責処分に留まった。この直後の1965年5月場所では左足首関節内骨折で9勝6敗となり、千秋楽は休場して不戦敗となった。
再起をかけた1966年(昭和41年)3月場所からは再び6連覇を達成した。しかし1967年(昭和42年)には左肘を負傷し、その怪我を取り戻そうと稽古で無理をした結果、左膝靭帯断裂の重傷を負った。これにより、1968年(昭和43年)3月場所から3場所連続で全休することになった。復帰した同年9月場所では、初日に栃東知頼に敗れ周囲から限界説が囁かれたが、その後は慎重に勝ちを重ね、叩き込みを多用する相撲に変化した。結果として、横綱として内容は冴えないとされながらも、同場所2日目から1969年(昭和44年)3月場所初日までの間に、双葉山定次(69連勝)に次ぐ45連勝を記録した。この連勝は、同場所2日目に羽黒岩智一(戸田智次郎)に押し出しで敗れたことで途切れたが、ビデオ画像や写真では戸田の足が先に土俵から出ていたため、「世紀の大誤審」として問題となり、この出来事をきっかけに翌場所からビデオ画像の導入が始まった。大鵬自身は、この誤審の判定について不満を述べることなく、「ああいう相撲をとった自分が悪いんです」と語り、その高潔な相撲哲学が話題となり、横綱としての評価を一層高めた。しかし、相撲記者の若林哲治によると、大鵬は内心激怒しており、当時の新聞には「俺は残っていたと思った」との談話や、顔がこわばっていたとの記述があるという。
大鵬は同場所5日目から肺炎で途中休場し、肺機能が低下したことで激しい稽古ができなくなった。それでも1969年(昭和44年)5月場所では30回目の優勝を飾り、この功績を讃えて同年9月場所初日には日本相撲協会から一代年寄「大鵬」が授与された。現役晩年に至っても、北の富士勝昭と玉の海正洋の両横綱に対しては最後まで壁として君臨し続けた(北の富士・玉の海が横綱に昇進して以降の対戦成績は共に大鵬の4勝2敗で勝ち越している)。1971年(昭和46年)1月場所には32回目の優勝を果たしたが、千秋楽の玉の海戦では寄り切って1敗で並び、優勝決定戦ではその玉の海と水入りとなる大相撲の末、勝利を収めた。
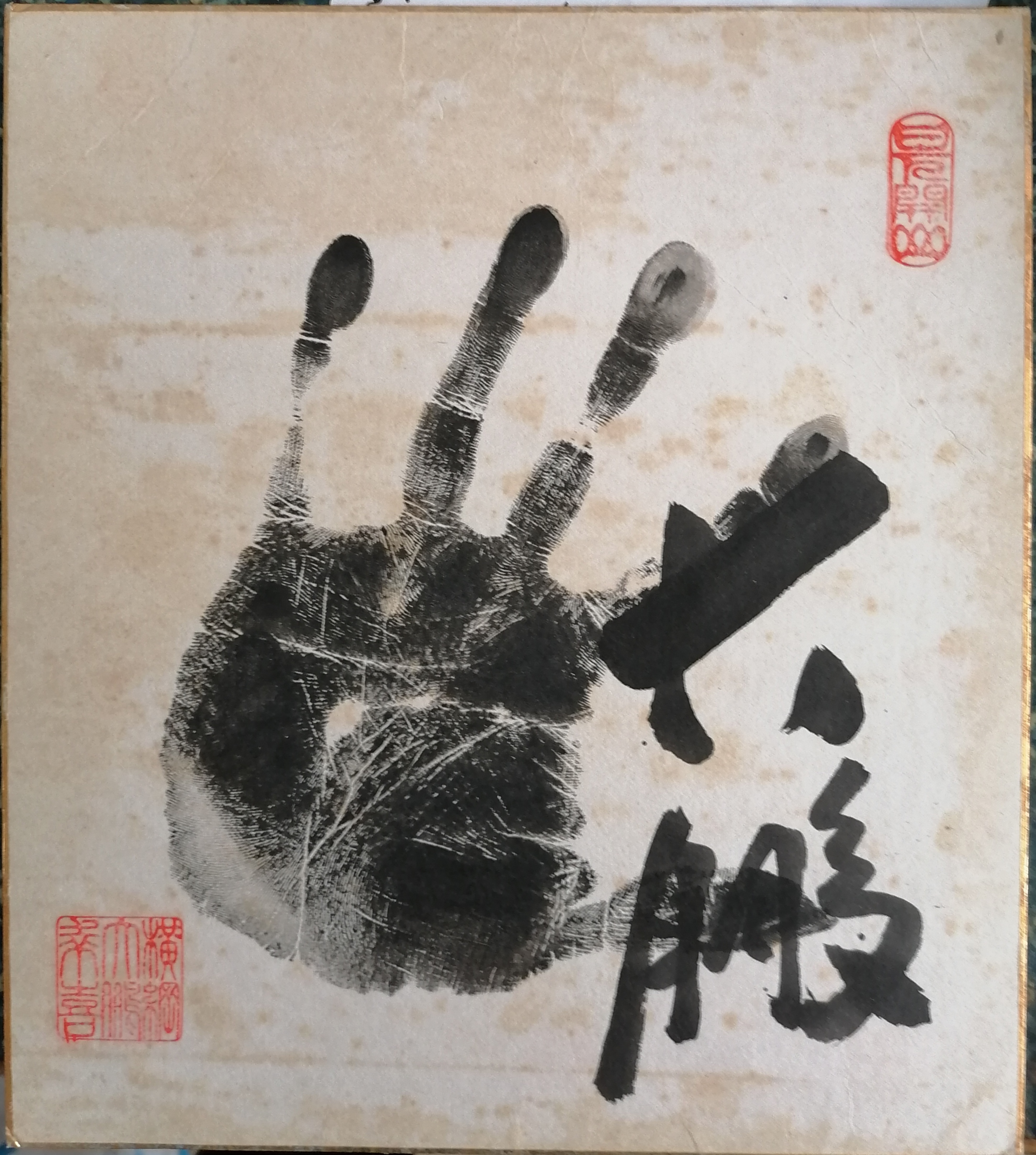
3.3.1. 柏戸とのライバル関係
大鵬と柏戸剛は1961年(昭和36年)9月場所に同時に横綱に昇進し、彼らの激しいライバル関係は相撲史における黄金時代を形成した。この時代は「柏鵬時代」と呼ばれ、後世の力士たちにも大きな影響を与えた。第69代横綱白鵬翔の四股名もこの両横綱に由来している。柏戸が優勝回数5回に対し、大鵬は32回と圧倒的な差をつけたものの、大鵬は「柏戸さんがいたからこそ大鵬がいた。大鵬がいたからこそ柏戸さんがいた」と語り、二人の間には競技を超えた真の友情が存在し、柏戸の1996年(平成8年)の死去まで続いた。
柏戸と大鵬の対戦は、1960年(昭和35年)1月場所から1969年(昭和44年)5月場所までの58場所で37回実現した。千秋楽結びの一番での対戦は史上3位の21回に上り、そのうち5回は両者が優勝圏内にいる相星決戦(同じ成績で優勝を争う直接対決)であった。特に記憶に残る千秋楽の対戦を以下に示す。
| 場所 | 柏戸成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1962年11月場所 | 12勝3敗(9勝) | 13勝2敗(8敗) | 大鵬 | 柏戸3敗、大鵬1敗で対戦し柏戸が勝利。 |
| 1963年9月場所 | 15勝0敗(10勝) | 14勝1敗(8敗) | 柏戸 | 千秋楽全勝同士相星決戦で柏戸が勝利。 |
| 1964年3月場所 | 14勝1敗(10勝) | 15勝0敗(11敗) | 大鵬 | 2回目の千秋楽全勝同士相星決戦で大鵬が勝利。 |
| 1966年5月場所 | 12勝3敗(13勝) | 14勝1敗(13敗) | 大鵬 | 千秋楽、柏戸2敗、大鵬1敗で対戦し大鵬が勝利。 |
| 1966年7月場所 | 12勝3敗(13勝) | 14勝1敗(14敗) | 大鵬 | 千秋楽、柏戸2敗、大鵬1敗で対戦し大鵬が勝利。 |
| 1966年9月場所 | 13勝2敗(14勝) | 13勝2敗(14敗) | 大鵬 | 千秋楽、柏戸2敗、大鵬1敗で対戦し柏戸が勝利。優勝決定戦では大鵬が勝利。 |
| 1967年5月場所 | 13勝2敗(16勝) | 14勝1敗(16敗) | 大鵬 | 千秋楽、柏戸2敗、大鵬全勝で対戦し柏戸が勝利。 |
両者が横綱に昇進する以前(1961年9月場所まで)の対戦成績は柏戸の7勝3敗であったが、両者が横綱同士となって以降(1961年11月場所以降)の対戦成績は、大鵬の18勝9敗と大きく勝ち越している。優勝回数も、この期間では柏戸の4回に対し、大鵬は29回を記録している。
3.4. 現役からの引退
1971年(昭和46年)3月場所で12勝3敗と健在ぶりを示したものの、同年5月場所で栃富士勝健に尻から落ちる形で敗れた際に体力の限界を感じた。さらに5日目には新鋭の貴ノ花利彰に同じく尻から落ちる敗戦を喫したことで、引退を決意した。貴ノ花との一番は、大鵬が左かち上げから左ハズ、右おっつけで攻め込んだが、貴ノ花が右おっつけから右上手を取り、大鵬の左腰に食いつく絶好の体勢になり、大鵬は掬い投げや突き押しで応戦するも貴ノ花に体を預けられて尻から落ちていった、という内容であった。
大鵬自身は翌6日目の福の花孝一戦を自身最後の相撲とすることを希望したが、日本相撲協会から「死に体で土俵に上がることはできない」と却下されたため、福の花戦は不戦敗となり、貴ノ花との取組が現役最後の一番となった。横綱在位は約10年に及んだ。彼の現役時代の勝率は80%を超え、これも戦後最高記録である。彼はその偉大な功績を讃えられ、一代年寄「大鵬」として、株式を購入することなく日本相撲協会の年寄となることを許された初の元力士となった。引退の決断についてはなかなか踏ん切りがつかなかったが、当時2歳だった長女の言葉が後押しとなり決意が固まったという。
引退を発表した翌朝、NHKの朝のニュース番組に出演した大鵬は、「最も誇れる自身の記録は何か?」と問われ、「6場所連続優勝2回」と答えている。
引退相撲は1971年(昭和46年)10月2日に蔵前国技館で盛大に行われた。太刀持ちに玉の海正洋、露払いに北の富士勝昭と、両横綱を従えて最後の横綱土俵入りを披露した。しかし、それからわずか9日後の10月11日に玉の海が急死するという悲劇に見舞われた。玉の海は虫垂炎を患っていたが、責任感の強さから大鵬の引退相撲が終わるまで入院を拒否したため症状が悪化し、手遅れの状態になったと言われている。
4. 引退後の活動
大鵬幸喜の引退後の人生は、相撲界への貢献と私生活における困難が交錯するものであった。
4.1. 相撲部屋の経営
現役引退後、大鵬は所属していた二所ノ関部屋から独立し、1971年(昭和46年)12月に大鵬部屋を創立した。彼は親方として、関脇巨砲丈士や幕内嗣子鵬慶昌といった力士たちを育成した。しかし、自身の現役時代の成功を指導者として再現することは難しかったとされている。
2002年(平成14年)5月には、ロシア出身の露鵬幸生を自部屋に招き入門させた。露鵬は2006年(平成18年)3月場所で小結まで昇進する期待に応えたが、2008年(平成20年)に大麻問題により弟の白露山佑太と共に日本相撲協会を解雇された。
2003年(平成15年)2月には、自身の娘婿である元関脇貴闘力忠茂に部屋の運営を譲り渡した。この際、大鵬が一代年寄であったため「大鵬」の年寄名が継承できず、部屋は貴闘力がもともと所有していた名跡「大嶽」を冠して大嶽部屋と改称された。しかし、貴闘力は2010年(平成22年)7月4日に野球賭博問題で相撲協会を解雇された。その後、大鵬の直弟子であった元十両大竜忠博が部屋を継承することになった。
大鵬は娘たちに力士と結婚して部屋を継がせるという考えは持っていなかったが、娘と貴闘力の結婚を喜んだ。一方で、貴闘力にギャンブル癖があることを交際中から心配しており、彼が賭博で作った借金を何度も肩代わりしていたという。貴闘力は大鵬に誓ってギャンブルをやめたにもかかわらず、隠れて借金を重ね、野球賭博にまで手を出したことで解雇に至った。この出来事は、大鵬が4人の孫を力士にするという夢を抱き、大嶽部屋の改装に着手していた矢先のことであった。
4.2. 公的な役割と健康問題
大鵬は1976年(昭和51年)に35歳という若さで役員待遇・審判部副部長に就任したが、1977年(昭和52年)に脳梗塞で倒れ、左半身麻痺の後遺症が残った。これにより、理事長などの重要な職に就任する見込みがなくなった。引退後に「大鵬 翔己」としていた年寄名を、この病気を患って以降は現役時代の「大鵬 幸喜」に戻している。
脳梗塞からの回復に向けて、彼は廊下を這うことから始めるなど献身的なリハビリを重ね、歩ける程度には回復した。1980年(昭和55年)には理事に就任し、地方場所(名古屋場所)担当部長や相撲教習所所長などを歴任し、8期務めた後、1996年(平成8年)に役員待遇に退いた。
2005年(平成17年)5月に65歳で定年退職すると、約9年間空席であった相撲博物館館長に就任した。協会在籍中に理事長や執行部での経験がなかったにもかかわらず、館長職に就任したのは異例の抜擢とされている。2008年(平成20年)11月には体調不良を理由に相撲博物館館長を辞任し、同年12月26日に職を退いた。
2000年(平成12年)には、自身同様「昭和の大横綱」と評される北の湖敏満(太刀持ち)と九重貢(元千代の富士貢、露払い)の2人を従えて、還暦土俵入りを披露した。脳梗塞の後遺症で四股が踏めないため、土俵入りそのものは行わず、赤い綱を締めて雲龍型のせり上がりの構えを取り、土俵中央で柏手を打つという一部の所作を披露するに留まった。

父親がウクライナ人であった縁から、大鵬はサハリン州における日本研究家の働きかけで、ウクライナのハルキウ市に大鵬記念館が建設されるなど、日本とウクライナの国際交流の主役として脚光を浴びた。彼はハルキウで相撲大会を企画するなど、交流を深めた。ロシア連邦との交流にも及び、2002年(平成14年)には北オセチア共和国出身のボラーゾフ兄弟を日本に招き、兄の露鵬幸生を自身の部屋に入門させた(弟の白露山佑太は別の部屋へ入門)。しかし、露鵬は2008年(平成20年)にドーピング検査で大麻の陽性反応が出たことで、弟と共に日本相撲協会を解雇された。
4.3. 栄誉と受賞
大鵬幸喜は、その相撲界への多大な貢献と国民的英雄としての存在感から、生前と死後に数々の権威ある表彰や賞を授与された。
- 2004年(平成16年)に日本政府から紫綬褒章を授与された。
- 2009年(平成21年)10月27日には、相撲界から初となる文化功労者に選出された。
- 2011年(平成23年)1月18日には、ウクライナ大統領令により、ウクライナ三等功労勲章を授与された。
- 2013年(平成25年)1月19日、死去同日付で正四位並びに旭日重光章が追贈された。
- 2013年(平成25年)2月15日には、国民栄誉賞が授与されることが決定し、同年2月25日に未亡人や白鵬らが出席して授与式が行われた。当時の首相安倍晋三は彼を「国民的英雄」と称した。
5. 人物と人柄
大鵬幸喜の私生活は、その相撲人生と同様に国民の関心を集めるものであった。家族との絆、友人との交流、そして彼独自の性格的特徴が、彼を単なる力士以上の存在として記憶させている。
5.1. 家族と交友関係
大鵬幸喜は1966年(昭和41年)に結婚した。この年は彼が26歳の誕生日を迎える年であり、かつ5月場所で優勝を果たした最終日と重なる、彼の人気絶頂期であった。妻は旅館経営者の娘であり、帝国ホテルで行われた盛大な結婚披露宴には、1000人の来賓と200人以上の記者が集まった。彼は相撲界で初めて結婚後に記者会見を開いた力士であり、これは現在では一般的な慣例となっている。
大鵬の三女は元関脇貴闘力忠茂と結婚し、貴闘力は引退後に大鵬部屋を引き継ぎ(大嶽部屋と改称)親方となった。しかし、貴闘力が賭博スキャンダルで日本相撲協会を解雇された後、彼は大鵬の娘と離婚した。大鵬は娘たちに力士と結婚して部屋を継いでほしいという意向は持っていなかったが、三女と貴闘力の結婚を喜んでいた。一方で、貴闘力にギャンブル癖があることを交際中から心配しており、彼が賭博で作った借金を何度も肩代わりしていたという。貴闘力は大鵬に誓ってギャンブルをやめたにもかかわらず、隠れて借金を重ね、野球賭博にまで手を出したことで解雇に至った。この出来事は、大鵬が4人の孫を力士にするという夢を抱き、大嶽部屋の改装に着手していた矢先のことであった。大鵬は貴闘力に離縁を申し渡し、三女と貴闘力は離婚した。大鵬は三女に対し「お前は何も悪くない。堂々としてなさい」と繰り返し語り、最期まで娘たちを心配し、「いつでも帰っておいで」と声をかけ続けたという。貴闘力は2013年の大鵬の最期に立ち会うことはできたが、葬儀への参列は許されなかった。
大鵬の孫たちは、相撲界に足跡を残している。彼の最年少の孫である王鵬幸之介(納谷幸之介、2000年(平成12年)生まれ)は、2018年(平成30年)1月に大嶽部屋からプロの力士として入門し、「王鵬」の四股名で活躍している。彼の兄弟である納谷幸林(2019年11月入門)と夢道鵬幸成(2020年3月入門)も相撲界に進んだ。大鵬の長男の息子である納谷幸男(1994年(平成6年)生まれ)はプロレスラーとして活動している。大鵬は自身の息子たちに相撲を強制することはなく、「好きなことをさせればいい」と常に語っていたという。
大鵬は、ライバルであった柏戸剛と共に「柏鵬時代」と呼ばれる相撲の黄金時代を築き上げた。彼らは競技上では激しく競い合ったものの、土俵の外では真の友情を育んでいた。また、巨人の王貞治とは、同じ1940年(昭和15年)5月生まれであり、共に並外れた努力家であったことから、非常に親しい友人関係を築いていた。王貞治は、大鵬の死に際し「同じ時代に世の中に出て、光栄だった」と追悼のコメントを寄せた。
大鵬は、当時の子供たちの好きなものを並べた「巨人・大鵬・卵焼き」という流行語でその人気と知名度を象徴された。しかし、大鵬自身は「巨人と一緒にされては困る」と語ったことがある。その理由は、彼自身がアンチ巨人であったこと、団体競技である野球と個人競技である相撲を一緒にされたくない気持ちがあったこと、そして何よりも「大鵬の相撲には型がない」と批判されていた時期に「大人のファンは柏戸と大洋ホエールズ」などと評論家から揶揄されたことがあったためであるという。ただし、後年に出版した自伝には『巨人 大鵬 卵焼き - 私の履歴書』という題名を付けた。このフレーズは、1960年代前半の高度経済成長期に、通産官僚の堺屋太一が「日本の高度成長が国民に支持されるのは、子供が巨人、大鵬、卵焼きを好きなのと一緒だ」と発言したことがきっかけで広まったとされている。
5.2. 趣味と関心事
大鵬幸喜は、相撲以外にも様々な趣味や関心事を持っていた。現役時代は野球と麻雀を趣味としていた。新入幕の頃はあまり野球に興味がなかったものの、1966年(昭和41年)頃には稽古の合間にキャッチボールをするほどになり、腕前も上々であったという。麻雀は「下手の横好き」であり、4人麻雀で一人負けすることもあった。
彼は大の酒豪としても知られ、一日の酒量が18 L(一斗)に達し、ビールを一升瓶で20本(36 L)飲んだこともあったという。塩辛い物も好み、酒のつまみに大ぶりの明太子を2腹も3腹も食べながら飲んだと伝えられている。若き頃は親友の王貞治と夜通し酒を酌み交わすこともあり、王が酔いつぶれて一眠りして起きると、大鵬は変わらぬペースで飲み続けていたという逸話が残っている。場所の終盤、明け方まで飲んでいて付け人が「横綱、きょうは大関戦ですが」と心配すると「どうしておれが大関とやるのに寝なきゃいけないんだ」と豪語したという。しかし、この多量の飲酒が後に脳卒中などの健康問題を引き起こす大きな原因の一つとなったと言われている。
彼は故郷北海道出身であることからスズランの花を好み、贈られてきたスズランは花の命が尽きるまで大切に可愛がったという。彼の化粧廻しにもスズランの花がデザインされていた。また、飯倉の「レストラン竜」で提供されるサーロインステーキを好んで食した。パリやスペインの肉は日本のものと比べて質が劣ると感じていたという。
横綱時代の彼の歌のレパートリーには、サンタ・ルチア、オー・ソレ・ミオ、エルビス・プレスリー、ボビー・ダーリンなどの曲があった。
5.3. 評価とエピソード
大鵬は、その強さだけでなく、人間的な魅力と高潔な相撲哲学によっても多くのエピソードを残し、国民から特別な評価を受けてきた。
若い頃は色白の美男子と評判で、その人気は非常に高かった。男性相撲ファンに絶大な支持を誇った柏戸に対し、大鵬は女性や子供からの絶大な支持を得ていた。大鵬の取組の時間帯には、銭湯の女湯ががら空きになったという逸話も残っている。彼の人気を受けて、全盛期には「幸喜」と名付けられた男児が多く誕生し、俳優・劇作家の三谷幸喜もその一人である。
彼は「相撲の天才」と呼ばれることが多かったが、本人は「人より努力をしたから強くなった」と語り、この呼称を嫌った。大鵬の素質に惚れ込んだ師匠の二所ノ関は、四股500回、鉄砲2000回、瀧見山延雄による激しいぶつかり稽古といったスパルタ教育で彼を徹底的に鍛え上げた。全盛期には1時間ものぶつかり稽古をこなすほどの持久力を持ち、二所ノ関は彼に雑用やちゃんこ番をさせず、稽古に専念させた。彼はむしろ弟弟子である大麒麟將能こそ天才と呼ぶにふさわしいと発言している。玉ノ海梅吉など、彼の取り口を批判する者でさえも、大鵬の体が稽古によって作られたものであることは高く評価していた。1966年(昭和41年)頃の取材では、バーベルやエキスパンダーを用いた科学的トレーニングを取り入れていることも明かされており、相撲の稽古のみに固執しない一面も持っていた。
新入幕の翌年に横綱に昇進した力士は、大鵬以前にはなく、2018年(平成30年)現在でも大鵬が唯一の存在である。彼の三賞受賞数が3回と少ないのは、あまりにも早く大関・横綱へ昇進したためである。しかし、横綱は降格を許されない地位であり、体力が衰えて好成績が出せなくなれば早期引退しか道はないことを大鵬自身はよく理解しており、横綱昇進が決定した際にも喜びよりも、むしろ引退時のことを意識せずにはいられなかったという。かつて栃錦清隆が横綱昇進時に師匠から「今日からは毎日、辞める時のことを考えて過ごせ」と言い渡されたという話を聞き、深く感じ入る所があったと述べている。
彼の横綱土俵入りは、肘を少し曲げ伸ばししながら掌を返すことが特徴であった。非常にテンポが遅い土俵入りで知られ、大抵2分余り、現役最終盤の1970年(昭和45年)から1971年(昭和46年)にかけては3分を超えるほどになった。しかし、横綱初期には二子山親方から「せり上がりに区切りが無く、中段が早すぎる。柏手を打つときに首を振る癖がある。内側に向けて四股を踏むのも良くない」と厳しく指導されるなど、土俵入りは未熟であるとの評判であった。新横綱時の静岡県島田市での巡業では、東から土俵に上がったにもかかわらず、左足で四股を踏んだ後、帰る際に足を間違えて逆の西方を向いてしまう失態を演じ、その後しばらくは土俵入りに相当神経を使い、終えた後は毎回汗びっしょりになっていたという。また、当初の土俵入りは1分10秒程度で終わり、新聞記者から「早すぎて締まりがない」と指摘されたことで、以後間合いを持たせるよう留意したという。
大鵬は現役時代から慈善活動にも熱心であった。「大鵬慈善ゆかた」などを販売し、その収益を1967年(昭和42年)から1968年(昭和43年)までは老人ホーム・養護施設へテレビを寄贈した。翌1969年(昭和44年)からは日本赤十字社に「大鵬号」と命名した血液運搬車を贈呈し、2009年(平成21年)9月に70台目(自身の年齢と同数)の贈呈を終えるまで活動を継続した。
親方としては、1982年(昭和57年)に「世界人道者賞」を受賞している。これは日本ではあまり知られていないが、ローマ法王などが受賞した世界的に重要な賞である。大鵬部屋創設当初、大鵬自身がベンツを運転してちゃんこの材料を仕入れていたという逸話もある。露鵬幸生の大麻問題では北の湖敏満理事長と対応を協議する事態となり、最終的には娘婿の貴闘力(大嶽親方)が責任を問われ日本相撲協会を解雇され、自身も相撲博物館館長を辞任した。
かつては第68代横綱・朝青龍明徳のよき相談役として知られ、相手次第で取り口を変える自身のような万能型の大横綱の道を歩みつつある朝青龍を厳しく、かつ温かく見守っていた。しかし、朝青龍は2005年(平成17年)に7場所連続優勝などの新記録を達成した頃から、大鵬の元へ相談に来ることがなくなり、最終的に度重なるトラブルにより2010年(平成22年)1月場所後に現役引退せざるを得なくなった。大鵬は引退会見を見て「会見で謝罪なく腹立たしい」と憤慨し、朝青龍が力士の所作やマナーについて「現役を辞めるころになったらうまくなりますよ」と返答したことで、大鵬は朝青龍を見捨てたという。
2004年(平成16年)、大鵬部屋は三女の夫である貴闘力(16代大嶽)が継承し大嶽部屋と改称したが、大鵬は部屋の運営を貴闘力と共に行っていたため、よくぶつかっていたという。大鵬は「頼られると全部受け入れてしまう人」であり、貴闘力が賭博で作った借金を何度も肩代わりしていた。
貴乃花光司が二所ノ関一門の反対を押し切って理事選に出馬した際、大鵬は「二所ノ関一門が(貴乃花親方を)破門にすると言ってきた。私に言わせれば『何を言ってるんだ』と。自分のことだけを考えてやるのはダメなんだ。協会の将来とか全体を、いろんなことを考えていかないといけない」と述べ、出馬に「GOサイン」を出して大きな役割を果たした。理事選の夜、貴乃花は自らのグループの親方を率いて大鵬宅を訪れ、当選を報告した。
亡くなるまで日刊スポーツの相撲担当評論家を務め、本場所開催中(奇数日目)は同誌に解説「土評」を連載していた。
二所ノ関部屋が消滅問題に直面した際、大鵬は「時代の流れでは致し方無いだろうが、今一度部屋再興を望みたい」と談話を発表した。その後、二所ノ関部屋は2014年12月1日付で再興された。
彼の墓所は東京都江東区の妙久寺(納谷家の菩提寺)にある。戒名は「大道院殿忍受錬成日鵬大居士」である。
6. 取り口
大鵬幸喜の相撲は、その卓越した技術と戦略的アプローチによって特徴づけられる。彼は特に廻しを取ってからの巧みな技と力で知られ、それゆえ「四つ相撲」の力士として評価されていた。
大鵬の得意とする形は「左四つ」(右を差し、左で相手の廻しを外から取る)であり、その体勢からの「寄り切り」が最も得意な決まり手で、全勝星の約30%を占めた。掬い投げ(廻しを取らずに相手の脇の下から手を入れて投げる技)と上手投げ(相手の廻しを上から取って投げる技)も頻繁に用いた。
若い頃は、もろ差し(両腕を交差して相手の片腕を挟むように差す比較的珍しい型)を駆使し、柏戸のような突進力のある相手に対する守りを固める相撲を得意とした。新入幕の頃は立合いの当たりや突っ張りがそれほど強くなかったが、これは彼が差し身(相手の懐に差し込む動き)を活かす相撲に繋がった。自分より差し身の巧い相手には突っ張ってから差し、差し身の劣る相手にはいきなり差しに行くなど、状況に応じて取り口を変化させた。
非常に手堅い相撲を取り、胸を合わせずに前屈みになって腰を引く「逆・くの字」の体勢で相手の攻めを防ぎ、横へ回りながら自分有利の体勢に持ち込んだ。一度差すと必ず差し手を返し、掬って相手の出足を止め、その後は腰を落として寄っていく。左四つの場合は、前に出てからの右上手投げで決めることが多かった。体勢の巧みさ、特に懐の深さに加え、真綿やスポンジに例えられるほど体が柔らかく、どんな当たりも受け止めても崩れない相撲を可能にした。全盛期の琴櫻傑將が放ったぶちかましを稽古場で受け止められたのは大鵬ただ一人だったと言われ、彼の特異な体質を表す逸話である。
大兵にもかかわらず、前捌き(相手の攻めをかわして前に出る動き)や回り込み(相手の横や後ろに回り込む動き)が巧みで、冷静かつ緻密な相撲を取った。また、突っ張りも強く、突っ張ってからの叩き込みも懐の深さゆえによく決まった。相手が突っ張りの威力に耐えられず足元が崩れて倒れるような相撲も多く、結果的に「叩き込み」で決まった場合でも、その背景には突き押しの威力が存在した。
一方で、大鵬には反り腰がなく、上体が反ると体勢を残すことができなかった。この腰の脆さが弱点であり、普段は「逆くの字」の体勢、体の柔らかさ、懐の深さで補っていた。しかし、胸を合わせてがっぷり四つになると勝負に出にくくなり、立合いから上体を起こされて押されると一方的に攻められることも少なくなかった。このような弱点は、対戦経験の少ない平幕や押し相撲を得意とする相手との序盤戦で露呈することが多く、「序盤・平幕・押し相撲」が大鵬の鬼門とされた。彼自身も押し相撲に苦戦したことを認め、「『押されてはいけない』という先入観にとらわれ、差し身にこだわりすぎて、狙っていくところをいなされ、アワを食っているうちに、押し出されるというケースが多かった」と語っている。彼なりの押し相撲対策が確立したのは、横綱になって2年目あたりであったという。
基本的には左四つに組みとめての寄りと投げが主体のスタイルだが、押し相撲や右四つでも相撲が取れるなど、オールラウンダーであった。しかし、この点が「絶対的な型がない」と批判されることもあった。これは右四つの完成された型を持った双葉山定次とは対照的であり、大鵬以前はこうした相撲は小兵のやることとされ、横綱・大関には相応しくないと見なされていた。また、「逆・くの字」の体勢は「へっぴり腰」と揶揄されることもあり、腰の力で相手の攻めを受け止める相撲を本格的とする評論家(小坂秀二など)からは「小さな相撲」と批判されたこともある。しかし、相手次第で取り口を変える柔軟性は高く評価されており、二所ノ関は「型のないのが大鵬の型」「名人に型なし」と反論した。大鵬が勝ち続けることで、その「型のない」相撲は、状況に応じて相撲を変える「自然体」と評価されるようになった。大鵬は自覚していた攻めの遅さを補うため、稽古場では口に水を含みながら相撲を取ることで、短い相撲を取らざるを得ないように工夫したという。
彼はその強さと出世の早さから「相撲の天才」と呼ばれることが多かったが、本人は「人より努力をしたから強くなった」と語り、この言葉を嫌った。大鵬の素質に惚れ込んだ二所ノ関の徹底的な指導によって鍛え上げられたが、その指導内容は四股500回、鉄砲2000回、瀧見山延雄による激しいぶつかり稽古といったスパルタ教育であった。全盛期は1時間ものぶつかり稽古をこなすほどの持久力があり、二所ノ関は大鵬に雑用やちゃんこ番をさせず、稽古に専念させた。彼はむしろ弟弟子である大麒麟將能の方が天才と呼ぶにふさわしいと発言している。
7. 主な記録と功績
大鵬幸喜は、その相撲人生において数々の歴史的な記録と比類なき功績を打ち立てた。
7.1. 通算成績
大鵬幸喜の通算成績は以下の通りである。
- 通算成績**:872勝182敗136休(勝率.827)
幕内最高優勝32回は、白鵬翔に次ぐ歴代2位の記録であるが、彼が引退した当時は最多優勝記録であった。彼は数々の金字塔を打ち立てたが、特に入幕した1960年から引退した1971年までの12年間、毎年必ず最低1回は優勝した記録は「一番破られにくい記録」と言われた(現在は白鵬の16年連続に次いで歴代2位であるが、白鵬は「入幕年の優勝」は達成していない)。
7.2. 注目すべき連勝記録
大鵬の最多連勝記録は、45連勝である(1968年9月場所2日目から1969年3月場所初日まで。1926年の東西相撲合併以降、歴代4位)。
その他、大鵬の主な20連勝以上の記録は以下の通りである。
| 回数 | 連勝数 | 期間 | 止めた力士 | 止めた力士の決まり手 | 連勝が止まった場所の | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1962年7月場所3日目 - 1962年9月場所12日目 | 北葉山英俊 | うっちゃり | 西大関2枚目張出 | |
| 2 | 30 | 1963年3月場所5日目 - 1963年7月場所4日目 | 青ノ里盛 | 寄り切り | 東前頭3枚目 | 1963年5月場所全勝優勝を含む。 |
| 3 | 34 | 1963年11月場所千秋楽 - 1964年5月場所3日目 | 前田川克 | 引き落とし | 西前頭2枚目 | 1964年1月場所・3月場所の2場所連続全勝優勝を含む。 |
| 4 | 20 | 1964年9月場所5日目 - 1964年11月場所9日目 | 明武谷保彦 | 突き出し | 東関脇 | |
| 5 | 26 | 1966年5月場所2日目 - 1966年7月場所12日目 | 豊山勝夫 | 下手投げ | 東大関 | |
| 6 | 34 | 1966年11月場所初日 - 1967年3月場所4日目 | 浅瀬川剛也 | 寄り切り | 東前頭3枚目 | 1966年11月場所・1967年1月場所の2場所連続全勝優勝を含む。 |
| 7 | 25 | 1967年9月場所初日 - 1967年11月場所10日目 | 海乃山勇 | けたぐり | 西関脇 | 1967年9月場所全勝優勝を含む。 |
| 8 | 45 | 1968年9月場所2日目 - 1969年3月場所初日 | 羽黒岩智一 | 押し出し | 東前頭筆頭 | 1968年11月場所・1969年1月場所の2場所連続全勝優勝を含む。 |
| 9 | 20 | 1970年11月場所6日目 - 1971年1月場所10日目 | 琴櫻傑將 | 押し出し | 東大関2枚目張出 |
上記の通り、大鵬は20連勝以上を9回、30連勝以上を4回記録している。
7.3. 各段優勝
大鵬幸喜の各段優勝は以下の通りである。
- 幕内最高優勝**:32回
- 1960年11月場所
- 1961年7月場所、9月場所、11月場所
- 1962年1月場所、7月場所、9月場所、11月場所
- 1963年1月場所、3月場所、5月場所
- 1964年1月場所、3月場所、9月場所、11月場所
- 1965年3月場所、7月場所、11月場所
- 1966年3月場所、5月場所、7月場所、9月場所、11月場所
- 1967年1月場所、5月場所、9月場所
- 1968年9月場所、11月場所
- 1969年1月場所、5月場所
- 1970年3月場所
- 1971年1月場所
- 全勝優勝**:8回(引退当時歴代1位タイ、現在歴代2位タイ)
- 連覇**:6連覇(1962年7月場所-1963年5月場所、1966年3月場所-1967年1月場所の2度達成)
- 同点優勝**:2回
- 十両優勝**:1回(1959年11月場所)
- 三段目優勝**:1回(1958年3月場所)
7.4. 三賞と金星
大鵬幸喜が受賞した特別賞(三賞)と獲得した金星は以下の通りである。
- 三賞**:3回
7.5. 場所別成績
| 年 | 月場所 | 番付 | 成績 | 優勝 | 三賞 | 金星 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956年 | 9月場所 | 前相撲 | - | - | - | - |
| 1957年 | 1月場所 | 序ノ口23西 | 7勝1敗 | - | - | - |
| 3月場所 | 序二段83東 | 6勝2敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 序二段29西 | 7勝1敗 | - | - | - | |
| 9月場所 | 三段目71西 | 7勝1敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 三段目37東 | 6勝2敗 | - | - | - | |
| 1958年 | 1月場所 | 三段目20西 | 6勝2敗 | - | - | - |
| 3月場所 | 三段目1東 | 8勝0敗 | 優勝 | - | - | |
| 5月場所 | 幕下31西 | 7勝1敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 幕下9東 | 7勝1敗 | - | - | - | |
| 9月場所 | 幕下2西 | 3勝5敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 幕下7東 | 6勝2敗 | - | - | - | |
| 1959年 | 1月場所 | 幕下4東 | 6勝2敗 | - | - | - |
| 3月場所 | 幕下1東 | 6勝2敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 十両20西 | 9勝6敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 十両16東 | 9勝6敗 | - | - | - | |
| 9月場所 | 十両10東 | 13勝2敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 十両3東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 1960年 | 1月場所 | 幕内13西 | 12勝3敗 | - | 敢闘賞 | - |
| 3月場所 | 幕内4東 | 7勝8敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 幕内6東 | 11勝4敗 | - | 敢闘賞 | 金星 | |
| 7月場所 | 小結西 | 11勝4敗 | - | - | - | |
| 9月場所 | 関脇西 | 12勝3敗 | - | 技能賞 | - | |
| 11月場所 | 関脇東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 1961年 | 1月場所 | 大関東 | 10勝5敗 | - | - | - |
| 3月場所 | 大関西 | 12勝3敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 大関東 | 11勝4敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 大関東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 9月場所 | 大関東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 1962年 | 1月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 11勝4敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 9月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 1963年 | 1月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - | |
| 7月場所 | 横綱東 | 12勝3敗 | - | - | - | |
| 9月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 横綱西 | 12勝3敗 | - | - | - | |
| 1964年 | 1月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 10勝5敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 横綱東 | 1勝4敗10休 | - | - | - | |
| 9月場所 | 横綱西 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 1965年 | 1月場所 | 横綱東 | 11勝4敗 | - | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 9勝6敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 横綱西 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 9月場所 | 横綱東 | 11勝4敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 横綱西 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 1966年 | 1月場所 | 横綱東 | 全休 | - | - | - |
| 3月場所 | 横綱西 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 7月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 9月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - | |
| 1967年 | 1月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 7月場所 | 横綱東 | 2勝1敗12休 | - | - | - | |
| 9月場所 | 横綱西 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 11勝2敗2休 | - | - | - | |
| 1968年 | 1月場所 | 横綱東 | 1勝3敗11休 | - | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 全休 | - | - | - | |
| 5月場所 | 横綱西 | 全休 | - | - | - | |
| 7月場所 | 横綱西 | 全休 | - | - | - | |
| 9月場所 | 横綱西 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - | |
| 1969年 | 1月場所 | 横綱東 | 15勝0敗 | 優勝 | - | - |
| 3月場所 | 横綱東 | 3勝2敗10休 | - | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 13勝2敗 | 優勝 | - | - | |
| 7月場所 | 横綱東 | 11勝4敗 | - | - | - | |
| 9月場所 | 横綱東 | 11勝4敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 横綱東 | 6勝4敗5休 | - | - | - | |
| 1970年 | 1月場所 | 横綱東 | 全休 | - | - | - |
| 3月場所 | 横綱西 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - | |
| 5月場所 | 横綱東 | 12勝3敗 | - | - | - | |
| 7月場所 | 横綱西 | 2勝2敗11休 | - | - | - | |
| 9月場所 | 横綱西 | 12勝3敗 | - | - | - | |
| 11月場所 | 横綱西 | 14勝1敗 | - | - | - | |
| 1971年 | 1月場所 | 横綱西 | 14勝1敗 | 優勝 | - | - |
| 3月場所 | 横綱西 | 12勝3敗 | - | - | - | |
| 5月場所 | 横綱西 | 3勝3敗引退 | - | - | - |
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。
三賞は敢闘賞、殊勲賞、技能賞。その他に金星。
番付階級は幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口。
幕内序列は横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列)。
7.6. 幕内対戦成績
幕内対戦成績を以下に示す。なお、括弧内の数字は、勝数または負数の中に占める不戦勝、不戦敗の数を示す。
| 力士名 | 勝数 | 負数 | 力士名 | 勝数 | 負数 | 力士名 | 勝数 | 負数 | 力士名 | 勝数 | 負数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青ノ里 | 14 | 2 | 朝潮(米川) | 4 | 4 | 浅瀬川 | 7 | 1 | 朝登 | 2 | 0 |
| 天津風 | 4 | 0 | 泉洋 | 1 | 0 | 一乃矢 | 1 | 0 | 岩風 | 17 | 2 |
| 宇多川 | 3 | 0 | 追手山 | 1 | 0 | 大晃 | 7 | 1 | 小城ノ花 | 19 | 1 |
| 海乃山 | 21 | 4 | 開隆山 | 16 | 4 | 柏戸 | 21 | 16 | 和晃 | 1 | 0 |
| 金乃花 | 7 | 1 | 北の洋 | 7 | 1 | 北の富士 | 26 | 5 | 北葉山 | 24 | 11 |
| 君錦 | 1 | 0 | 清國 | 29 | 4(1) | 黒姫山 | 2 | 1 | 高鉄山 | 7 | 1 |
| 琴櫻 | 22 | 4 | 佐田の山 | 27 | 5 | 沢光 | 1 | 0 | 潮錦 | 4 | 0 |
| 信夫山 | 2 | 0 | 大豪 | 9 | 0 | 大受 | 3 | 1 | 大雪 | 1 | 0 |
| 大雄 | 5 | 0 | 大竜川 | 2 | 0 | 貴ノ花 | 3 | 2 | 高見山 | 11 | 0 |
| 玉の海 | 21 | 7 | 常錦 | 2 | 0 | 鶴ヶ嶺 | 19 | 1 | 出羽錦 | 17 | 3 |
| 時津山 | 3 | 0 | 時葉山 | 3 | 0 | 栃東 | 6 | 2 | 栃王山 | 5 | 0 |
| 栃錦 | 0 | 1 | 栃ノ海 | 17 | 6 | 栃光 | 24 | 6 | 栃富士 | 0 | 1 |
| 豊國 | 10 | 3 | 鳴門海 | 1 | 0 | 成山 | 2 | 1 | 錦洋 | 0 | 1 |
| 羽黒岩 | 6 | 1 | 羽黒川 | 14 | 1 | 羽黒山 | 21 | 0 | 長谷川 | 21 | 2 |
| 花光 | 1 | 0 | 廣川 | 7 | 0 | 福田山 | 0 | 2 | 福の花 | 10 | 1 |
| 房錦 | 6 | 5 | 富士錦 | 27 | 3 | 藤ノ川 | 16 | 1 | 二子岳 | 7 | 1 |
| 前田川 | 8 | 3 | 前の山 | 13 | 3 | 三重ノ海 | 3 | 1 | 禊鳳 | 1 | 0 |
| 三根山 | 1 | 0 | 明武谷 | 20 | 5 | 陸奥嵐 | 10 | 3 | 豊山 | 28 | 4 |
| 義ノ花 | 4 | 1 | 龍虎 | 9 | 1 | 若杉山 | 1 | 0 | 若秩父 | 4 | 0 |
| 若天龍 | 2 | 0 | 若浪 | 8 | 1 | 若羽黒 | 13 | 2 | 若二瀬 | 8 | 0 |
| 若前田 | 4 | 0 | 若見山 | 11 | 0 |
- 上記に加えて、優勝決定戦で柏戸に2勝、明武谷に1勝、佐田の山・玉の海にそれぞれ1勝1敗の記録がある。
8. 死去
大鵬幸喜は2013年(平成25年)1月19日、心室頻拍のため、東京都新宿区の慶應義塾大学病院において72歳で死去した(享年73歳)。彼が亡くなるわずか16日前の同年1月3日には、故郷の弟子屈町に暮らす実兄が急性心筋梗塞のため79歳で死去しており、大鵬は体調不良のためその葬儀に参列できなかったことも後に明らかになった。70歳に入ってからは酸素ボンベを頻繁に使用するようになっていたという。また、入院中には、頸髄損傷で同じ病院に入院中だった尾車親方(元大関琴風豪規)を見舞い、「おーい、何やってんだ。お前、早く弟子のところに帰ってやらんか。俺も昔、この病院でリハビリやったんだ」と励ましたという。
大鵬の訃報を受けて、日本相撲協会の北の湖敏満理事長や九重貢事業部長などが哀悼の意を表す談話を発表した。また、同世代の日本スポーツ界のヒーローであった長嶋茂雄、ファイティング原田、そして大鵬と親友関係であった王貞治はそれぞれ「同じ時代に世の中に出て、光栄だった」と故人との思い出を語る談話を発表した。通夜は1月30日、葬儀・告別式は1月31日に、いずれも青山葬儀所で営まれ、王貞治、黒柳徹子、白鵬翔らが弔辞を読んだ。
彼の死後、1月19日付で正四位並びに旭日重光章が追贈された。また、2013年(平成25年)2月15日付で国民栄誉賞が授与され、同年2月25日には未亡人と白鵬らが出席して授与式が行われた。菅義偉官房長官(当時)は、大鵬を「国民的英雄」と称した。
2013年(平成25年)3月24日、3月場所千秋楽の優勝力士インタビューにおいて、白鵬の呼びかけで観客全員による1分間の黙祷が行われた。白鵬は、大鵬が彼に定期的に助言を与え、「記録は破られるためにある」と語っていたことを明かしている。白鵬は、大鵬の死去から2年後の2015年(平成27年)1月場所に33回目の優勝を果たし、大鵬の持つ史上最多優勝記録を更新した。
9. 評価と遺産
大鵬幸喜は、その卓越した相撲の技と人間性によって、相撲史に不朽の遺産を残した。彼が日本社会に与えた影響は計り知れず、後世の力士たちにも多大な影響を与え続けている。
9.1. 歴史的評価と影響
大鵬幸喜は「昭和の大横綱」と称され、戦後最強の横綱と評されることが多い。ある評論では、「恐らく近代以降の(そして戦後に限れば間違いなく)最も偉大な力士」と評されている。彼は終戦直後の復興期から高度経済成長期にかけての日本の相撲黄金時代を支え、国民的英雄として日本社会に多大な影響を与えた。
彼の功績は、白鵬翔が数々の記録を更新するまで、長きにわたり最高峰の座を占めた。白鵬自身も大鵬から助言を受けており、彼の記録を破ることは、大鵬への最大の恩返しであると語っている。大鵬は、後続の力士たちにとって、目標とすべき偉大な存在であり続けた。
9.2. 批判と論争
大鵬幸喜の輝かしいキャリアの中にも、いくつかの批判や論争のあった出来事が存在する。
1965年(昭和40年)には、拳銃密輸事件に巻き込まれ、書類送検された。この件では、日本相撲協会からの処分は譴責に留まった。
1969年(昭和44年)3月場所での羽黒岩智一との一戦で、彼の45連勝が「世紀の大誤審」によって途切れたとされる出来事があった。この判定を巡っては大きな議論を呼び、結果として翌場所からビデオ判定が導入されるきっかけとなった。大鵬自身は、この誤審に対して不満を述べることなく、「ああいう相撲をとった自分が悪いんです」と語り、その高潔な姿勢が評価された。しかし、一部の相撲記者は彼が内心激怒していたと伝えている。
引退後、彼が創立した大鵬部屋は、自身の現役時代の成功を指導者として再現することは難しかったとされている。2008年(平成20年)には、自身の部屋のロシア人弟子である露鵬幸生が大麻問題で日本相撲協会を解雇される事態が発生し、当時の北の湖敏満理事長と共に対応を協議する立場に置かれた。さらに、部屋を継承させた娘婿の貴闘力忠茂が野球賭博問題で2010年(平成22年)に協会を解雇されたことは、大鵬にとって大きな衝撃であった。娘の証言によれば、大鵬は貴闘力のギャンブルによる借金を何度も肩代わりし、彼が再びギャンブルに手を出したことに深く失望していたという。貴闘力の解雇後、大鵬は娘に貴闘力との離婚を促し、娘に対し「お前は何も悪くない。堂々としてなさい」と繰り返し語った。
現役時代の取り口についても批判は存在した。特に1968年(昭和43年)に左膝を痛めて以降、叩き込みなどの引き技に頼る相撲が目立つようになり、一部の評論家からは「型がない」「へっぴり腰」「小さな相撲」などと揶揄された。
9.3. 追悼と記念
大鵬幸喜の生涯と功績は、様々な形で追悼され、記念されている。
- 彼が少年時代を過ごした北海道弟子屈町の川湯温泉には、1984年(昭和59年)に開館した大鵬相撲記念館がある。この記念館には、大鵬が実際に使用した化粧廻しや優勝トロフィーなどゆかりの資料が展示されており、彼の栄光の記録と生涯を綴ったドキュメンタリー映像も上映されている。記念館の前には、大鵬の銅像も建てられている。
- 2014年(平成26年)8月15日には、彼の生誕地であるサハリンに大鵬の銅像が建立された。これは、大鵬の母と妻の出身地である秋田県の関係者を中心に募金活動が行われ、同県在住の彫刻家によって制作されたものである。
- 彼の父親の出身地であるウクライナのハルキウ市には、大鵬記念館が建設されている。
- 死去後、彼には正四位並びに旭日重光章、そして国民栄誉賞が追贈され、国家としての最高級の栄誉が与えられた。