1. 生涯と背景
アブー・ヌワースは、アラブ人の父とペルシャ人の母を持つ混合的な出自を持つ。彼の生涯は、初期の教育からバグダッドでの宮廷生活、そして晩年の投獄と死に至るまで、その文学活動と密接に結びついている。
1.1. 出生と家族
アブー・ヌワースは、西暦756年から758年の間に、アッバース朝のアフヴァーズ州(現在のイラン、フーゼスターン州)のアフヴァーズ市、またはその近隣地区で生まれた。彼のフルネームはアブー・アリー・アル=ハサン・イブン・ハーニー・アブド・アル=アワル・アル=サバーフである。父のハーニーはウマイヤ朝最後のカリフ、マルワーン2世の軍に仕えたアラブ人(おそらくダマスカス出身)であった。母のグルバン(またはグルナーズ)はアフヴァーズ出身のペルシャ人織工(または裁縫師)であった。ハーニーはアフヴァーズの警察に勤務中にグルバンと出会った。アブー・ヌワースが10歳の時、父ハーニーが亡くなった。その後、幼いアブー・ヌワースは母と共にイラク南部のバスラへ移住した。
1.2. 教育と初期の師事
バスラに移住後、アブー・ヌワースはクルアーン学校に通い、幼くしてハフィズ(クルアーンの暗唱者)となった。彼の若々しい容姿と生まれ持ったカリスマ性は、クーファの詩人ワーリバ・イブン・アル=フバーブ(アブー・ウサーマ・ワーリバ・ブン・フバーブ)の注目を引き、ワーリバはアブー・ヌワースを若い弟子としてクーファへ連れて行った。ワーリバはアブー・ヌワースの詩人としての才能を見抜き、この道に進むよう励ましただけでなく、若い彼に性的な魅力を感じ、エロティックな関係を持っていた可能性もある。アブー・ヌワースが成人してからの少年との関係は、ワーリバとの自身の経験を反映しているようである。
ワーリバの死後、アブー・ヌワースは詩人で翻訳家のハラフ・アフマルの弟子となった。彼はイスラーム教の聖典を学ぶとともに、当時の高名な文法学者であるアブー・ウバイダ(ムアンマル・ブン・ムサンナー)やアブー・ザイド(サイード・ブン・アウス・アンサーリー)のもとでアラビア語の文法を学んだ。また、言い伝えによると、彼は語彙に関する知識を深めるために砂漠のベドウィンの元へも赴いたという。ハラフ・アフマルはアブー・ヌワースに、何千行にも及ぶ古典詩を暗記し終えるまでは一行も詩を詠んではならぬと命じ、彼がすっかり暗記してしまうと今度は覚えた詩をすべて忘れることを命じたという逸話が残っている。過去の詩をすべて忘れて初めて、アブー・ヌワースは詩を作れるようになったとされ、このエピソードは詩人としての彼の形成期を象徴している。
2. バグダッドでのキャリア
アブー・ヌワースは、バグダッドに移住後、その文学的才能と革新的なスタイルで急速に名声を得た。彼の詩は、当時の宮廷生活と都市の享楽主義を反映していた。
2.1. バグダッドへの移住と宮廷生活
詩人として頭角を現すと、アブー・ヌワースはすぐにアッバース朝の首都バグダッドへ移住した。これはカリフに頌詩を献上し、その寵を得るためであった。当時、バグダッドは広大なアッバース朝の版図を統べる中枢として建都されたばかりであった。彼はカリフハールーン・アッ=ラシードにその徳を讃える頌詩(マディーフ)を献上したところ、気に入られてお目通りが許された。この時期に、バルマク家出身の宮廷詩人アバーン・ブン・アブドゥルハミード・ラーヒキーと親交を結び、バルマク家にも出入りするようになった。もっとも、このバルマク家とのつながりは、ラーヒキーが自身のパトロンであるハールーン・アッ=ラシードから、潜在的なライバルであるアブー・ヌワースを引き離そうとする打算の産物であったとも言われる。
ハールーン・アッ=ラシードによるバルマク家の粛清に際して、アブー・ヌワースはエジプトに身を隠した。エジプトの歳入庁長官ハティーブ・ブン・アブドゥルハミードが彼を匿い、詩人は長官を讃える頌詩を作った。エジプトでの亡命生活は長くなく、比較的すぐにバグダッドへ戻ることができた。そこで彼は新しいカリフ、ハールーン・アッ=ラシードの息子であるアル=アミーンのナディーム(酒飲み友だち、御伽衆)となった。彼の詩作の大部分はアル=アミーンの在位年代(809年から813年)になされたと考えられている。アル=アミーンとは相性が良く、数々の冒険を共にしたと伝えられるが、それでもアル=アミーンは飲酒を理由にアブー・ヌワースを牢屋に入れたことがあるようである。
2.2. 文学的スタイルとテーマ
アブー・ヌワースは、エスプリとユーモアにあふれる詩情により、すぐにバグダッドで有名になった。彼は砂漠の伝統を受け継いだ古典的な主題を扱わず、都会生活を語り、葡萄酒の悦楽(ハムリヤートkhamriyyatアラビア語)や少年愛(ムジュニーヤートmujuniyyatアラビア語)を卑近なユーモアを交えて謳った。彼はアラビア語詩に新しい様式や内容の多様性をもたらした「ムフダスーン(muhdathūn)」と呼ばれる「モダン派」詩人の代表格とみなされている。ムフダスーンは、8世紀初頭にバシャール・ブン・ブルドが登場し、カスィーダ(定型長詩)に代表される古典的様式から離れて、近代的な詩を作ろうとした文学的流行に連なる。
アブー・ヌワースの詩は、当時の社会情勢を反映し、ペルシャ文化要素を称賛し、アラブの古典主義を風刺する文化的な批評の側面も持っていた。彼は飲酒を主題とした詩で、酒がもたらす肉体的・形而上学的な喜びを称賛し、イスラーム世界の詩の規範に反するものであった。また、彼の詩には、キリスト教徒の少年が酒を給仕する様子や、キリスト教への改宗を仄めかす内容など、宗教的なタブーに挑戦する表現も見られた。これらの詩は、異性愛の規範、同性愛の非難、飲酒の禁止、そしてイスラームそのものを嘲笑するものであった。
3. 主要作品とジャンル
アブー・ヌワースは多岐にわたるジャンルで詩を創作したが、特に飲酒詩と狩猟詩においてその才能が際立っていた。彼の詩集『ディーワーン』は、頌詩、挽歌、諷刺詩、男女間の宮廷愛詩、悔悛詩、狩猟詩、飲酒詩といったジャンルに分類されている。
3.1. 飲酒の詩(ハムリヤート, Khamriyyat)
アッバース朝への王朝交代後、飲酒詩には新しい時代の精神が反映された。アブー・ヌワースは飲酒詩の発展に大きな影響を与えた人物であり、彼の詩はバグダッドのエリート層を楽しませるために書かれたと考えられている。飲酒詩の中心は、ワインの味、外観、香り、そして身体と精神への影響を鮮やかに描写することにある。アブー・ヌワースは、詩の中でペルシャ人を賛美し、アラブの古典主義を嘲笑する多くの哲学的思想やイメージを取り入れた。彼は飲酒詩を、イスラーム世界におけるアッバース朝時代のテーマを反映させる媒体として利用した。
例えば、彼の『ハムリヤート』には次のような一節がある。
「ワインはペルシャの職人が様々な模様で飾った銀の壺で我々の間に回される。その底にはホスロー(ペルシャの王)が、側面には騎馬の弓兵が狩るオリックスが描かれている。ワインの場所はチュニックのボタンが留まる場所、水の場所はペルシャ帽(カランスワqalansuwahアラビア語)が被られる場所だ。」
この一節は、当時のペルシャ語の使用に対応するペルシャのイメージが強く現れている。アブー・ヌワースは詩の中で詩的かつ政治的な調子を持つことで知られていた。他のアッバース朝の詩人たちと同様に、アブー・ヌワースはワインを飲むことへの開放性や宗教の軽視を償うかのような表現を用いた。彼はワインを言い訳と解放者として用いながら、イスラームに対する風刺的な攻撃を行った。彼の『ハムリヤート』のある特定の詩句は、宗教との彼の皮肉な関係を例証しており、ワインの宗教的禁止を神の許しと比較している。アブー・ヌワースは、あたかも彼の罪が宗教的枠組みの中で正当化されるかのように文学を書き、ワインとセクシュアリティへの愛を反映していた。彼の詩は、イスラーム世界の詩の規範に適合しないワインを飲む肉体的・形而上学的な経験を称賛するために書かれた。
アッバース朝の飲酒詩における継続的なテーマは、ワイン店が通常少年を給仕として雇っていたという事実から、少年愛との関連であった。これらの詩はしばしば好色で反抗的であった。彼の『ディーワーン』のエロティックな部分では、若い給仕の少女が少年のような服装をしてワインを飲んでいる様子が描写されている。アブー・ヌワースの少年への愛情は、彼の詩や社交生活を通して示された。彼は興味深い偏見を探求した。それは、同性愛が革命が始まった州からアッバース朝のイラクに輸入されたというものである。彼は、ウマイヤ朝時代には詩人は女性の愛人しか持たなかったと記している。ヌワースの誘惑的な詩は、ワインを非難とスケープゴートの中心テーマとして用いている。彼の『アル=ムハッラマ』からの抜粋にそれが示されている。
「ガラスの中で広がる時、無数の色を誇り、全ての舌を黙らせる。
しなやかな若者の手の中で、金色の、仕立て屋の糸巻きのような体を誇示し、恋人の要求に美しく応える。
こめかみには一本の巻き毛があり、その目つきは災いを告げる。
彼はキリスト教徒で、ホラーサーンの服をまとい、チュニックは胸元と首を露わにしている。
この優雅な美しさに話しかければ、高山からイスラームを投げ捨てるだろう。
もし全ての罪人を罪に導くお方(神)の略奪を恐れなければ、
私は彼の宗教に改宗し、愛をもって知的にそれに入るだろう、
なぜなら、主がこの若者をこれほどまでに際立たせたのは、彼の宗教が真実でなければありえないと知っているからだ。」
この詩は、アブー・ヌワースの様々な罪、すなわちキリスト教徒に給仕されること、少年の美しさを賛美すること、キリスト教に証拠を見出すことを示している。アブー・ヌワースの著作は、異性愛の規範、同性愛の非難、飲酒の禁止、そしてイスラームそのものを嘲笑している。彼は文学を用いて、アッバース朝時代の宗教的・文化的規範に反証した。彼の詩の多くは少年への愛情を描写しているが、ワインの味と喜びを女性に関連付けるのはアブー・ヌワースの特徴的な技法である。アブー・ヌワースの好みは、彼の時代の男性の間では珍しいことではなく、ホモエロティックな歌詞や詩はムスリム神秘主義者の間で人気があった。
3.2. 愛の詩(同性愛を含む)
アブー・ヌワースの詩のいくつかは、多くのセクシュアリティ、エロティシズム、力、そして自己抑制を含んでいる。彼の詩を読むと、蜂蜜で満たされた飲み物、美味しい食べ物、ワインでいっぱいのグラスを囲んで、砂漠のバーでの性的な宴会に参加しているような印象を受ける。彼の詩を読むと、弱々しい奴隷や従順な愛する者たちの影が、他の客に囲まれ、奔放な人々を招いている様子を想像することができる。彼の詩は、男性愛を含む多様な愛と欲望のテーマを扱い、その内容は社会規範に対する挑戦的な側面も持っていた。
3.3. 狩猟の詩(タルディーヤ, Tardiyya)と風刺
アブー・ヌワースは、タルディーヤtardiyyaアラビア語と呼ばれる狩猟詩を発明し、詩の一ジャンルになるまで狩猟詩の世界を高めた詩人とされる。狩猟の主題自体は、先イスラーム時代の詩人イムルル・カイスのカスィーダやムアッラカートにも見られる。彼はまた、社会や人物を風刺する詩(ヒジャーhijaアラビア語)も多く残しており、自分に風刺の才能があることを自覚していた。彼は詩人同士の激しい詩的な罵り合いや侮辱を含む風刺詩の伝統にも参加した。
3.4. 文学的革新(ムアンマーなど)
アブー・ヌワースは、ムアンマーmu'ammāアラビア語(文字通り「目隠しされた」または「不明瞭な」)と呼ばれる文学形式の発明者の一人として評価されている。これは、単語や名前を構成する文字を組み合わせることで解かれるなぞなぞである。彼はまた、アラビア語の二つのジャンル、ハムリヤ(飲酒詩)とタルディーヤ(狩猟詩)を完成させた。彼は古い時代の詩から多くを汲み取り、なおかつそれからの流れを断ち切ることで、アラビア語詩におけるその卓越性を示した。彼は先イスラーム時代の詩を再認識し、散文と韻文を切り分けた文法学派の研究に学んでおり、その点を考慮すると、彼が師匠のハラフ・アフマルに強いられたという、有名な「忘却のアネクドート」が、また異なった様相を持つ。
アブー・ヌワースの詩は、恋愛、特に少年愛を扱ったもの(ムジューニーヤ)だけでなく、権力者を讃えたり、風刺したりするものもある。讃える詩はカスィーダ、風刺する詩はヒジャーといい、自分に風刺の才能があることも自覚していた。特に好んだテーマは飲酒と恋愛である。ムジューニヤート或いはハムリヤートと呼ばれる飲酒詩はバシャール・ブン・ブルドが導入したムフダスーンの流れに連なるものである一方、恋愛詩は古典形式にのっとったもの(保護や禄を与える者を讃える詩)である。これはアブー・ヌワースという詩人が登場した時代を反映している。当時、文学的創作は二つの対照的な要因により決定付けられていた。一つ目は文法学者が確立した古典詩の規範的価値であり、知識人もこれにのっとって詩を鑑賞した。二つ目は詩人の地位と社会的機能である。詩人の社会的地位の確保や上昇は、詩人に禄を与える者に委ねられていた。これら二つの要因により頌詩カスィーダが芸術の規範になり、カスィーダ古典詩の語彙、形式、主題を利用して詩作せざるをえない状況になった。
4. 思想と哲学
アブー・ヌワースの詩には、彼の個人的な思想や当時の社会に対する批評が色濃く反映されている。
4.1. 詩に見られる主題と哲学
アブー・ヌワースは、その詩において享楽主義、愛、宗教的批判、そして回心といった多様な個人的思想や価値観を探求した。彼は若き日に享楽的な生活を送り、飲酒や愛(特に少年愛)を公然と謳い上げた。彼の詩は、ワインの物理的・形而上学的な喜びを称賛し、当時のイスラーム世界の詩の規範に挑戦するものであった。彼はまた、宗教的な禁忌を風刺し、飲酒を罪の言い訳や解放の手段として描いた。しかし、投獄を経験した後、彼の詩は宗教的なテーマへと変化し、悔悛の念や神への帰依を表現するようになった。これは、彼の人生における重要な転換点であり、彼の思想の複雑さを示している。
4.2. 文化的な批評
アブー・ヌワースの作品は、アッバース朝時代の社会情勢を色濃く反映していた。彼は、砂漠の伝統に根ざした古典的なアラビア語詩の主題から意図的に離れ、都市生活の現実と享楽主義を詩の主要なテーマとした。彼は、詩の中でペルシャ文化の要素を称賛し、アラブの古典主義を風刺する姿勢を見せた。例えば、ワインの詩ではペルシャの職人による銀の壺やペルシャの王ホスローのイメージを用いることで、当時のバグダッドにおけるペルシャ文化の影響力を示唆した。
彼はまた、イスラームの規範や社会の偽善に対する批判を詩に込めた。飲酒の禁止や同性愛への非難といったテーマを嘲笑し、自身の罪を宗教的枠組みの中で正当化するような皮肉な表現を用いた。彼の詩は、異性愛の規範や宗教そのものへの挑戦であり、当時の宗教的・文化的規範に対する彼の批判的な思想を明確に示している。
5. 投獄と死
アブー・ヌワースの晩年は、彼の放蕩な生活と詩の内容が原因で、投獄と病に苦しめられた。
5.1. 投獄経験
アブー・ヌワースは、カリフを侮辱したり、イスラーム教を冒涜するような禁じられた主題(飲酒や同性愛)を扱ったりした詩のために、何度か投獄や拘禁を経験した。特にカリフアル=アミーンの治世下では、飲酒を理由に牢屋に入れられたことがあると伝えられている。インドネシア語の資料によると、彼は「カフィラ・バニ・ムダール」という詩でカリフの怒りを買い、投獄されたことがきっかけで、それまでの享楽的な詩から宗教的なテーマへと作風を変化させたとされている。
5.2. 死と埋葬
アブー・ヌワースの死因や時期については、様々な説があり、情報が錯綜している。
- 一説には、彼がナウバフト家を風刺する詩を作ったために、彼らによって毒殺されたという説がある。
- 別の説では、彼は死の直前まで酒を飲み続け、居酒屋で亡くなったとされる。
- 第三の説は、ナウバフト家によって殴打され、その際にワインが彼の感情を煽った結果、死に至ったというもので、毒殺説と飲酒説を組み合わせたような内容である。
- さらに、彼が投獄中に亡くなったという説もあるが、これは彼が病に苦しみ、友人が見舞いに訪れたという多くの逸話と矛盾する。
最も可能性が高いのは、彼が病気で亡くなったという説であり、ナウバフト家の屋敷で亡くなったとすれば、毒殺の神話が生まれた背景となる。彼は西暦814年から816年の間に、アッバース朝の大内戦中、アル=マアムーンがホラーサーン州から進軍する直前に亡くなった。彼はバグダッドのシュニジ墓地に埋葬された。
q=Shunizi cemetery, Baghdad|position=right
6. 遺産と影響
アブー・ヌワースは、アラビア語詩の歴史において革新的な存在であり、その影響は後世の文学や文化に深く刻まれている。
6.1. 文学史上の影響
アブー・ヌワースは、アラビア語詩の「ムフダスーン(モダン派)」の最重要人物の一人として、古典的な詩の形式や主題から離れ、新しい様式と内容の多様性をもたらした。彼は、飲酒詩(ハムリヤートKhamriyyatアラビア語)と狩猟詩(タルディーヤTardiyyaアラビア語)という二つのアラビア語ジャンルを完成させ、詩の一ジャンルとして確立した功績を持つ。また、「ムアンマーmu'ammāアラビア語」(文字通り「目隠しされた」または「不明瞭な」)と呼ばれる文学形式の発明者の一人としても評価されている。
彼の作品は、後世の多くの詩人に影響を与えた。12世紀にアル=アンダルスで活動したイブン・クズマーンは彼を深く尊敬しており、アブー・ヌワースと比較されることもある。彼の詩は、オマル・ハイヤームやハーフェズといったペルシャの詩人にも影響を与えたとされる。
アブー・ヌワース自身は詩集(ディーワーン)を編まなかったため、多くの作品、特にエジプト亡命中の作品が失われた。他方で、飲酒や男色を扱った詩を中心に、多くの偽作が誤ってヌワースのものとされたこともあった。アブー・バクル・スーリー、アリー・ブン・ハムザ、トゥーズーンをはじめとして、ヌワースのディーワーンの編集に心血を注いだ者は数多い。数あるディーワーンの中でも重要なのが、10世紀のスーリーの編集したものと、ハムザ・イスファハーニー(d. 970)の編集したものである。前者は真作の可能性が高い詩だけを集めている点に特徴があり、後者は真作・偽作を問わず集められた詩のすべてを収録している点に特徴がある。後者の校定本は前者の3倍の分量になり、1500作品13000行を有する。また、ハムザによるディーワーンは、ヌワースに関する噂話(アフバール)を多数収録しており、これもスーリーには見られないものである。
彼の作品を編纂した主な人物は以下の通りである。
| 詩集の編纂者 | 特徴 |
|---|---|
| ヤヒヤー・イブン・アル=ファドルとヤクブ・イブン・アル=シッキート | 詩を10の主題カテゴリに分類し、アルファベット順ではない。アル=シッキートは800ページの解説を執筆。 |
| アブー・サイード・アル=スッカリー | 詩を編集し、解説と言語学的注釈を提供。1000フォリオの詩集の約3分の2を完成。 |
| アブー・バクル・イブン・ヤヒヤー・アル=スーリー | 詩をアルファベット順に整理し、誤った帰属を修正。 |
| アリー・イブン・ハムザ・アル=イスバハーニー | 詩をアルファベット順に編集。 |
| ユースフ・イブン・アル=ダーヤ | 詩集を編纂。 |
| アブー・ヒッファーン | 詩集を編纂。 |
| イブン・アル=ワッシャー・アブー・タイイブ | 詩集を編纂。 |
| イブン・アンマール | ヌワースの作品を批判し、盗作の事例を引用。 |
| アル=ムナッジム家(アブー・マンスール、ヤヒヤー・イブン・アビー・マンスールなど複数の人物) | 詩集を編纂。 |
| アブー・アル=ハサン・アル=スマイサーティー | ヌワースを称賛する作品を執筆。 |
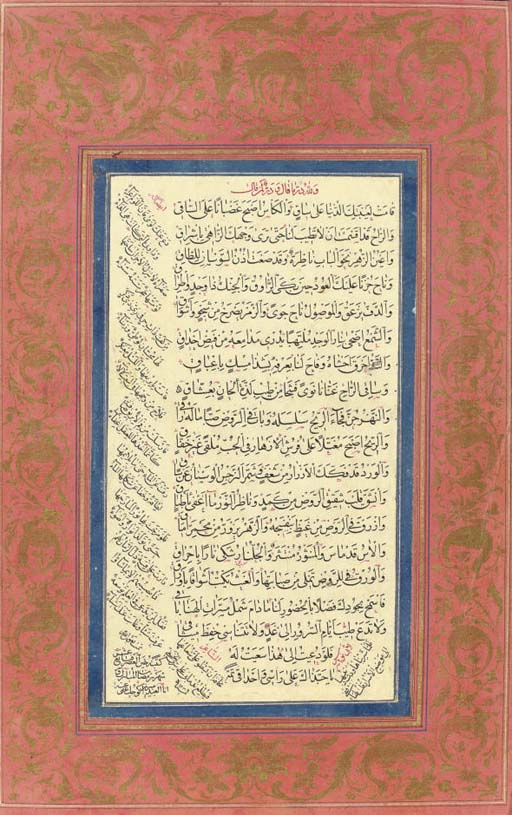

6.2. 文化的なプレゼンス
アブー・ヌワースは、文学作品だけでなく、民衆の物語の中にも登場し、その文化的なプレゼンスを確立した。彼は『千夜一夜物語』に、カリフハールーン・アッ=ラシードの取り巻きの一人として、しばしば道化的な役割や愉快な仲間として登場する。作中では「やくざな無頼漢」という性格が与えられているが、実在のヌワースにはハールーン・アッ=ラシードの寵を得たという確かな記録はない。民衆の想像の世界では、時にはお忍びで冒険に繰り出す同カリフの宮廷の道化師、あるいは愉快な仲間という役どころが与えられている。
彼の人物像や伝説は、誇張や想像を交えながら語り継がれ、交易を通じてアラブ世界と文化的に接続していた東アフリカ沿岸世界やインドネシアにも伝播した。東アフリカのスワヒリ文化圏では、「アブヌワシ(Abunuwasiスワヒリ語)」や「キブヌワシ(Kibunuwasiスワヒリ語)」という現地音化された名前で知られ、ナスレッディン・ホジャばなしのように、数多くの民話に登場する。ここでは、歴史上の人物としての存在から遊離し、時には擬人化された野ウサギとなって、王や商人といった権威者を頓智や屁理屈で翻弄するトリックスターとして活躍する。アフリカの角地域、特に1940年代にエリトリアで収集された民話にも「アブナワス(Abunawas英語)」の名が見られ、「とてもかしこい男」として描かれている。コモロ諸島でも、「アブヌワの物語群」が最もよく語られる民話の一つとして報告されている。
インドネシアでは、アブー・ヌワースは「アブナワス(Abunawasインドネシア語)」と呼ばれ、しばしばナスレッディン・ホジャと混同されるが、両者は異なる人物である。アブー・ヌワースは8世紀にバグダッドで活躍した詩人であり、ナスレッディン・ホジャは13世紀にトルコで活躍したユーモラスなスーフィーであった。インドネシアの物語では、彼が庶民と上流階級の関係を浮き彫りにすることが多い。
6.3. 記念と現代的評価
アブー・ヌワースの功績を記念して、いくつかの地名が名付けられている。バグダッドには、詩人にちなんで名付けられた場所がいくつか存在する。アブー・ヌワース通りはティグリス川の東岸に沿って走り、かつては街の目玉となっていた地区である。アブー・ヌワース公園は、ジュムフリヤ橋からカラダ地区の7月14日橋付近の間の2.5 kmにわたって伸びている。
さらに、宇宙においても彼の名が刻まれている。1976年には、水星のクレーターの一つが「アブー・ヌワース・クレーター」と命名された。
一方で、彼の作品は現代において検閲の対象となることもある。彼の作品は20世紀初頭まで自由に流通していたが、1932年にカイロで最初の検閲版が刊行された。2001年1月には、エジプト文化省がアブー・ヌワースのホモエロティックな詩を含む約6,000冊の書籍の焼却を命じた。また、サウジアラビアの『グローバル・アラビア百科事典』のアブー・ヌワースの項目では、少年愛に関する全ての言及が省略された。
しかし、現代における再評価の動きも見られる。2007年にアルジェリアで設立された「アブー・ナワス協会」は、詩人の名にちなんで名付けられ、アルジェリアにおける同性愛の非犯罪化、特にアルジェリア刑法第333条および第338条の廃止を目指している。これは、彼がかつて詩で表現した社会規範への挑戦が、現代の人権運動にインスピレーションを与えていることを示している。
彼の生涯は、アンドリュー・キリーンによる小説『The Father of Locks』(2009年)や『The Khalifah's Mirror』(2012年)で、ジャアファル・アル=バルマキーのために働くスパイとして描かれるなど、フィクションの題材にもなっている。タイイブ・サーリフのスーダンの小説『北への移住の季節』(1966年)では、主人公の一人ムスタファ・サイードが、ロンドンの若いイギリス人女性を誘惑する手段としてアブー・ヌワースの恋愛詩を引用している。タンザニアの芸術家ゴッドフリー・ムワンペンブワ(ガド)は、1996年にスワヒリ語のコミックブック『Abunuwasi』を制作し、東アフリカの民間伝承と『千夜一夜物語』の架空のアブー・ヌワシからインスピレーションを得たトリックスターの主人公を描いている。ピエル・パオロ・パゾリーニの映画『アラビアンナイト』(1974年)では、「シウム」の物語がアブー・ヌワースのエロティックな詩に基づいており、シーン全体でオリジナルの詩が使用されている。