1. 初期生誕および教育
エーリヒ・ラインスドルフは、オーストリアの首都ウィーンでユダヤ人の家庭に生まれた。彼の父はアマチュアのピアニストであり、幼い頃から音楽に触れる環境で育った。
1.1. 幼少期および音楽教育
ラインスドルフは5歳で地元の学校で音楽の学習を始め、幼い頃から音楽への才能を示した。彼はチェロと作曲を学び、10代の頃には歌手のピアノ伴奏者としても活動した。その後、ザルツブルクのモーツァルテウムで指揮法を学び、さらにウィーン大学とウィーン国立音楽大学でチェロとピアノの専門的な訓練を受けた。この体系的な音楽教育が、彼の後の幅広い音楽活動の基盤となった。
1.2. ヨーロッパでの初期キャリア
1934年から1937年にかけて、ラインスドルフはザルツブルク音楽祭で著名な指揮者であるブルーノ・ワルターとアルトゥーロ・トスカニーニの助手を務め、巨匠たちの下で貴重な経験を積んだ。この期間中、彼は1936年にはイタリアのボローニャでオペラを指揮し、プロの指揮者としてのキャリアをスタートさせた。1937年にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場で『ワルキューレ』を指揮してデビューを飾り、その後もフランスやイタリアなどで活動を続けた。
2. アメリカ移住および市民権取得
1937年のザルツブルク音楽祭で、ラインスドルフはアメリカ人の新聞社オーナーで投資家のチャールズ・エドワード・マーシュと出会った。マーシュはユダヤ系音楽家のアメリカへの脱出を支援しており、その尽力により、ラインスドルフは同年11月にアメリカへ渡り、メトロポリタン歌劇場の副指揮者の地位を得ることができた。
オーストリアがナチス・ドイツに併合されたのは、彼が祖国を発ってわずか数か月後の1938年3月のことであった。マーシュの知人であり、当時テキサス州選出の新人下院議員であった、後の大統領リンドン・ジョンソンの支援も受け、ラインスドルフはアメリカに留まることが可能となり、1942年にはアメリカ市民権を取得して帰化した。この移住は、彼がナチスの脅威から逃れる上で極めて重要な転機となった。
2.1. メトロポリタン歌劇場デビューおよび初期アメリカ活動
ニューヨークに到着後、ラインスドルフはメトロポリタン歌劇場で副指揮者としての職務を開始した。彼は特にワーグナー作品の解釈で名声を博し、1939年にアルトゥル・ボダンツキーが急逝すると、メトロポリタン歌劇場の「ドイツ物レパートリー責任者」に任命された。この時期、彼の指揮するワーグナーは特に注目を集め、彼のキャリアにおける重要な節目となった。
3. 主要指揮キャリア
エーリヒ・ラインスドルフは、クリーヴランド管弦楽団、ロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団、ボストン交響楽団など、アメリカの主要なオーケストラで音楽監督や首席指揮者を歴任し、その辣腕を振るった。
3.1. クリーヴランド管弦楽団
1943年、ラインスドルフはクリーヴランド管弦楽団の音楽監督に3年契約で就任した。当時31歳という若さ、そしてオペラ以外の指揮経験が限られていたことから、その能力について疑問の声も上がったが、オーケストラの理事会による投票で選出された。彼は就任後、オーケストラのコンサートを事前に宣伝し、より幅広い聴衆に届けるためにシーズン全体を前もって計画する意向を示した。また、第二次世界大戦の影響で実現は困難であったものの、年間を通して演奏活動を行うことを望んだ。さらに、毎週日曜夜のラジオ放送の交渉を成功させ、クリーヴランド管弦楽団の演奏がアメリカ全土、メキシコの一部、そして短波放送を通じてヨーロッパ、南アメリカ、南太平洋にまで届くようになった。特に、戦争へのアメリカの関与を考慮し、コンサートが録音され、海外のアメリカ軍事地域に放送されることになった点は重要であった。
しかし、ラインスドルフの音楽監督としての在任期間は短命に終わった。1943年10月、彼は徴兵対象となる可能性を告げる手紙を受け取った。健康上の問題を抱えていたため、召集されることはないだろうと彼は考えていたが、同月中に徴兵通知を受け取り、「政府の命令に従うつもりだ」と報道陣に語った。ラインスドルフの突然の徴兵は、クリーヴランド管弦楽団を運営する音楽芸術協会に新たな音楽監督を見つけるという大きな問題をもたらした。
ラインスドルフの兵役は1944年9月に名誉除隊となり短期間で終わったが、オーケストラは既に後任の人選を進めていた。1944年11月には、ラインスドルフと共にメトロポリタン歌劇場にいたジョージ・セルがセヴェランス・ホールでデビューし、絶賛を博した。ラインスドルフはまだ契約下にあったものの、音楽監督としての権限の多くを失っており、演奏内容から録音権限に至るまで、多くの問題で妥協を強いられた。彼はシーズン最後のプログラムでセヴェランス・ホールの指揮台に戻ったが、世論がセルに傾く中で辞任を表明した。しかし、1970年にセルが亡くなった後、ラインスドルフは1980年代を通じて定期的にクリーヴランド管弦楽団を客演指揮し、ロリン・マゼールからクリストフ・フォン・ドホナーニへの音楽監督移行期(1982年から1984年)には「政権交代の橋渡し」役を務めた。
3.2. ロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団
1947年から1955年の間、ラインスドルフはロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務めた。しかし、彼はそこで出会ったロチェスター市民の偏狭な音楽理解に絶望することになる。ラインスドルフの「ロチェスターは世界一小奇麗な行き止まりだ!」(Rochester is the best disguised dead end in the world!英語)という言葉は広く知られるようになった。
3.3. ボストン交響楽団
1962年にはボストン交響楽団の音楽監督に就任した。ボストンでの在任期間中、彼はRCAレコードとの間で数多くの録音を行ったが、同時に演奏家や管理者との間で衝突を繰り返すなど、論争も絶えなかった。
1963年11月22日、ボストン交響楽団のコンサート中に、ラインスドルフは演奏を中断し、テキサス州ダラスでのケネディ大統領暗殺という衝撃的なニュースを聴衆に知らせるという歴史的な役割を果たした。彼はテロリストへの憤りと大統領への哀悼の意を述べ、その後、ベートーヴェンの交響曲第3番から「葬送行進曲」を演奏した。また、ケネディ追悼ミサではモーツァルトの『レクイエム』を演奏し、その録音は現在もCD化され発売されている。
ボストン交響楽団との契約開始時には、プロコフィエフの主要な全作品を録音すると発表されたが、彼の在任期間の終わりまでに録音・リリースされたのは、交響曲第2番、第3番、第5番、第6番、ヴァイオリン協奏曲、5つのピアノ協奏曲、『ロメオとジュリエット』からの音楽、『スキタイ組曲』、そしてチェロのための交響的協奏曲のみであった。彼のRCAビクターでの録音の多くは、同社の物議を醸したダイナグルーヴ処理によって音質が損なわれたと見なされた。
1969年にラインスドルフはボストン交響楽団のポストを離れた。
3.4. その他主要指揮活動
ラインスドルフは短い期間ではあるがニューヨーク・シティ・オペラの音楽監督を務めた後、再びメトロポリタン歌劇場と提携を結んだ。1978年から1980年の間はベルリン放送交響楽団(現:ベルリン・ドイツ交響楽団)の首席指揮者を務めている。
1967年にはイスラエル・フィルハーモニー管弦楽団を客演指揮する予定であったが、第三次中東戦争の勃発により急遽帰国することになった。彼はタキシードを脱ぐのも忘れるほど慌てて帰国したと伝えられている。演奏会自体は戦争中であったにもかかわらず、ズービン・メータが代役を務めて開催された。
1974年、ラインスドルフはメトロポリタン歌劇場で『トリスタンとイゾルデ』を客演指揮することになったが、経営悪化による歌手のキャンセルが相次いだ。これに対し、当時の音楽監督ラファエル・クーベリックや首席指揮者ジェームズ・レヴァインが無力であったとして、『ニューヨーク・タイムズ』紙に苦言を呈した。この発言がクーベリックの音楽監督辞任に影響を与えたという説もある。その後もラインスドルフはメトロポリタン歌劇場で客演指揮を務めたが、彼の要求は厳しく、たびたびトラブルを引き起こした。
4. 客演指揮および後期キャリア
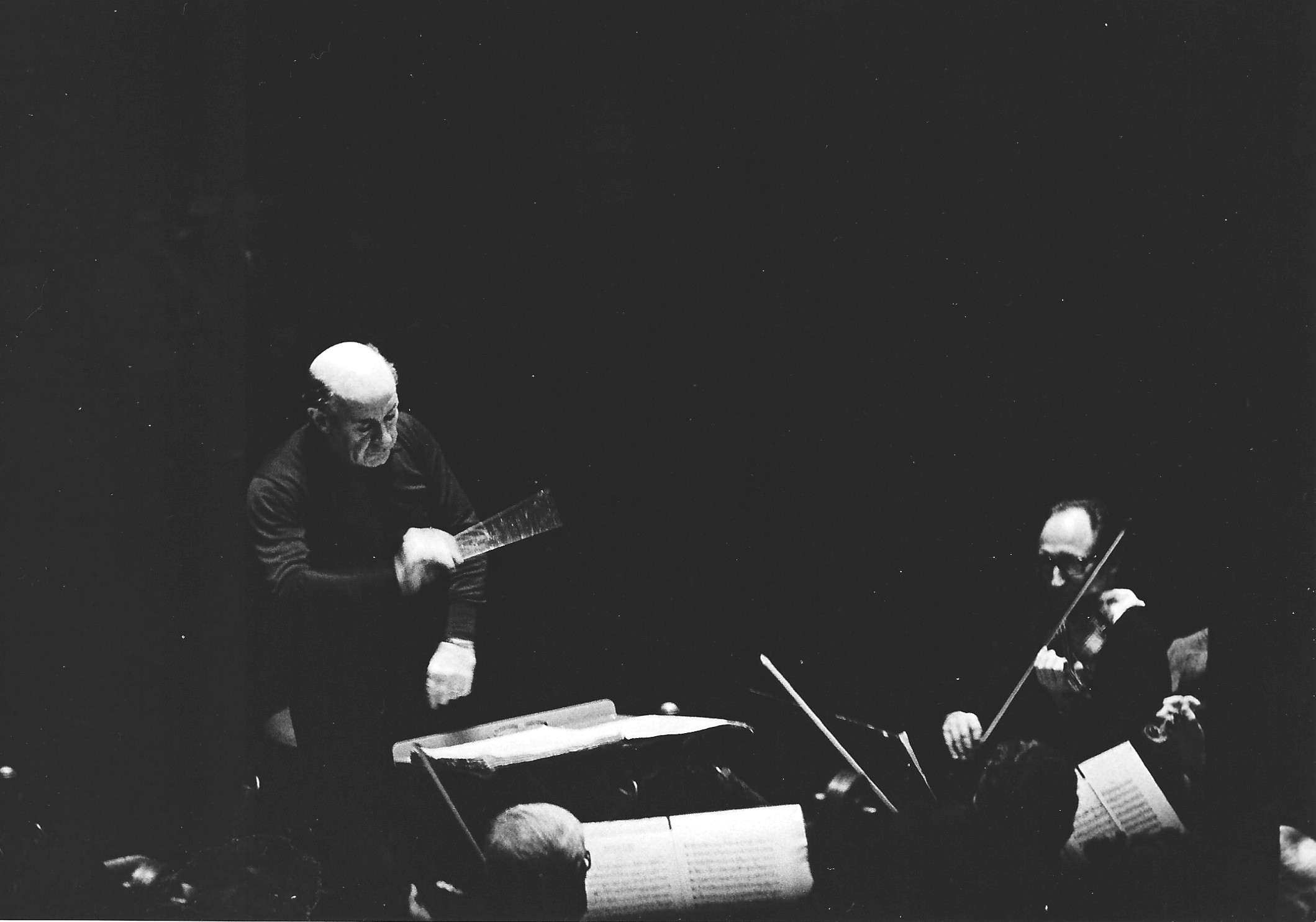
1969年にボストン交響楽団を辞任し、全ての常任指揮者の職を離れた後も、ラインスドルフはその後20年間にわたり、世界中の歌劇場やオーケストラで広範な客演指揮活動を続けた。特にメトロポリタン歌劇場とニューヨーク・フィルハーモニックとは密接な関係を維持し、数多くの公演を指揮した。彼の音楽的影響力は、定職を離れた後も衰えることなく、国際的な舞台で発揮され続けた。
5. 音楽的スタイルおよび評判
ラインスドルフは、その厳格な基準と辛辣な人柄で知られる指揮者であった。彼は演奏に極めて高い水準を求め、その要求は時に演奏家や管理者との衝突を招くこともあった。しかし、その厳しさの裏には、作品に対する深い理解と、最高の演奏を追求する揺るぎない信念があった。
彼は歌劇とシンフォニーの両方に幅広い適応性を持つことで評価された。特にワーグナー作品の解釈で名声を博し、メトロポリタン歌劇場のドイツ物レパートリーの責任者を務めた経験は、彼のオペラ指揮者としての地位を確立した。また、彼の指揮には「アメリカ的な要素」が相当部分加味されていたと評されており、その明快で力強い演奏スタイルは、多くの聴衆を魅了した。彼の個性的なアプローチと妥協を許さない姿勢は、クラシック音楽界において独特の存在感を放っていた。
6. 音盤およびメディア活動
エーリヒ・ラインスドルフは、そのキャリアを通じて膨大な数の録音を残し、数々の賞を受賞した。また、テレビ番組やDVDなど、視覚メディアを通じてもその芸術を広く伝えた。
6.1. 音盤主要内容
ラインスドルフはキャリアを通じて精力的に録音活動を行った。初期にはRCAビクターやコロンビア・レコードでクリーヴランド管弦楽団との78回転盤を制作した。1950年代初頭には、ウェストミンスター・レコードでロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団とモーツァルトの全交響曲を録音し、コロンビア・レコードではロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団とベートーヴェンの『英雄』交響曲の録音を開始した。この『英雄』はアルトゥーロ・トスカニーニの演奏に匹敵するほどの熱量を持つと高く評価された。
1960年代には、ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、そしてロサンゼルスの臨時編成オーケストラであるザ・コンサート・アーツ・オーケストラとキャピトル・レコードのために多数のステレオ録音を行った。また、RCAビクターではアニア・ドーフマンとフィラデルフィア管弦楽団(ディスク上ではロビン・フッド・デル管弦楽団と表記)と共に、ブラームスの交響曲第1番、フランクの交響曲ニ短調、メンデルスゾーンとグリーグのピアノ協奏曲を録音した。
1957年からはRCAビクターのためにローマで一連のステレオによるオペラ全曲録音を開始し、ジンカ・ミラノフ、ユッシ・ビョルリング、レナード・ウォーレンを擁するプッチーニの『トスカ』から始まった。ボストン交響楽団の音楽監督としては、RCAビクターとの録音を続け、マーラー、バルトークの作品、ベートーヴェンとブラームスの交響曲全集、そしてジョン・F・ケネディ大統領追悼のためのライブ録音『モーツァルトのレクイエム』などの注目すべきリリースがある。
その後も追加のオペラ録音を行い、コルンゴルトの『死の都』の初の完全ステレオ録音(キャロル・ネブレット、ルネ・コロと共演)をRCAで行った。ラインスドルフはボストン交響楽団とピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインと共に、ルービンシュタインにとって2度目となるベートーヴェンのピアノ協奏曲全集、ブラームスのピアノ協奏曲第1番、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を録音した。また、ボストン交響楽団とワーグナーの『ローエングリン』全曲を録音した。これは当時、アメリカの主要オーケストラによるワーグナー・オペラの初の録音であり、大規模かつ費用のかかるプロジェクトであった。
デッカ/ロンドンでは、『ドン・ジョヴァンニ』、『コジ・ファン・トゥッテ』、『フィガロの結婚』といった数多くのモーツァルトのオペラ、そして高く評価されたワーグナーの『ワルキューレ』の録音を行った。1970年代にボストンを離れた後、ラインスドルフはデッカ/ロンドンに戻り、彼らの著名なフェイズ4ステレオ・プロジェクトでいくつかのリリースを録音し、特にストラヴィンスキーの『春の祭典』と『ペトルーシュカ』が挙げられる。1980年代には、シェフィールド・ラボのためにロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団と3枚のダイレクト・トゥ・ディスク録音を行った。
ラインスドルフは主要なオペラの音楽からオーケストラ組曲を編曲したことでも知られている。これにはドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』、ワーグナーの『パルジファル』、リヒャルト・シュトラウスの『影の無い女』が含まれる。
6.2. 受賞および栄誉
ラインスドルフは、その輝かしいキャリアの中で、合計7つのグラミー賞を受賞した。また、生涯で12回のグラミー賞ノミネートも果たしている。
| 年 | 賞のカテゴリー | 受賞作品 |
|---|---|---|
| 1961 | 最優秀オペラ録音 | 『トゥーランドット』 |
| 1964 | 最優秀オペラ録音 | 『蝶々夫人』 |
| 1964 | 最優秀オーケストラ演奏 | バルトーク: 『管弦楽のための協奏曲』 |
| 1965 | 最優秀オーケストラ演奏 | マーラー: 交響曲第5番 / ベルク: 『ヴォツェック』からの抜粋 |
| 1967 | 最優秀オーケストラ演奏 | マーラー: 交響曲第6番 |
| 1969 | 最優秀オペラ録音 | 『コジ・ファン・トゥッテ』 |
| 1972 | 最優秀オペラ録音 | 『アイーダ』 |
6.3. 視覚媒体
ラインスドルフの演奏は、DVDやテレビ放送を通じても広く公開された。DVDでは、ウィーン交響楽団を指揮した『ヨハン・シュトラウス:有名作品集』が2003年にドルビーデジタル形式でリリースされている。また、ボストン交響楽団とのテレビ放送された公演の多くがVAIやICA ClassicsからDVD化されており、特に1969年4月にカラーで収録されたチャイコフスキーの交響曲第5番の演奏は、批評家から高い評価を受けている。
ラインスドルフとボストン交響楽団は、地元放送局WGBH-TVや全国放送のPBSの「イブニング・アット・シンフォニー」番組に定期的に出演した。1967年8月17日には、NBCで2時間のプライムタイム特別番組『タングルウッドの夕べ』がカラーで放送され、イツァーク・パールマンがゲストソリストとして出演した。これは、商業ネットワークが定期的に長編のクラシックコンサートを放送していた時代の象徴的な出来事であった。
7. 著述活動
ラインスドルフは、自身の音楽的経験と深い洞察に基づいた複数の著書やエッセーを執筆した。彼の著作は、音楽理論、作曲家との関係、そして自身の音楽キャリアに対する彼の見解を提示している。
彼の回想録である『Cadenza: A Musical Careerカデンツァ:音楽のキャリア英語』は1976年に出版された。また、1981年には『The Composer's Advocate: A Radical Orthodoxy for Musicians作曲家の擁護者:音楽家のための過激な正統性英語』を著し、音楽家が作曲家の意図をいかに忠実に再現すべきかという彼の哲学を詳述した。さらに、死後の1997年には『Erich Leinsdorf on Musicエーリヒ・ラインスドルフ、音楽を語る英語』が出版された。
8. 個人史
ラインスドルフの私生活に関する公開された情報は限られているが、彼はニューヨーク州ホーソーンのマウント・プレザント墓地に埋葬されている。
9. 死亡

エーリヒ・ラインスドルフは1993年9月11日、スイスのチューリッヒにて癌のため81歳で死去した。
10. 遺産および評価
エーリヒ・ラインスドルフは、その厳格な指揮と幅広いレパートリーを通じて、クラシック音楽界に多大な影響を与え、その遺産は今日まで受け継がれている。
10.1. クラシック音楽に与えた影響
ラインスドルフは、オーケストラの演奏水準の向上に大きく貢献した。彼の妥協を許さない厳格な姿勢は、所属するオーケストラの技術的・芸術的レベルを引き上げ、その名声を高めることに寄与した。また、彼は幅広いレパートリーを積極的に取り上げ、特にワーグナー作品の解釈においては、その明晰さと力強さで高い評価を得た。
彼の膨大な音盤制作は、クラシック音楽の普及に重要な役割を果たした。ラジオ放送や録音を通じて、彼の演奏はより多くの聴衆に届けられ、クラシック音楽の大衆化に貢献した。彼はまた、主要なオペラ作品からオーケストラ組曲を編曲するなど、レパートリーの拡大にも尽力した。
10.2. 批判的評価および論争
ラインスドルフの音楽的解釈とリーダーシップは、同時代および後世の批評家から様々な評価を受けた。彼の厳格な基準は、時に演奏家や管理者との衝突を引き起こし、「辛辣な人柄」と評されることもあった。
特に、ロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団在任中には、ロチェスターの音楽文化に対する彼の批判的な見解が知られている。「ロチェスターは世界一小奇麗な行き止まりだ!」という彼の発言は、その率直で妥協を許さない性格を象徴している。また、メトロポリタン歌劇場での客演指揮の際には、当時の経営陣や他の指揮者の対応を厳しく批判し、それが音楽監督の交代に影響を与えた可能性も指摘されている。彼の要求の厳しさは、しばしばトラブルの原因となったが、それは彼が音楽の質に対して決して妥協しなかった証でもあった。
彼の指揮は、その明晰さ、正確さ、そして構造的な整合性において高く評価された一方で、感情表現の面では抑制されていると見る向きもあった。しかし、彼の芸術的誠実さと、作曲家の意図を忠実に再現しようとする姿勢は、多くの音楽家や聴衆から尊敬を集めた。