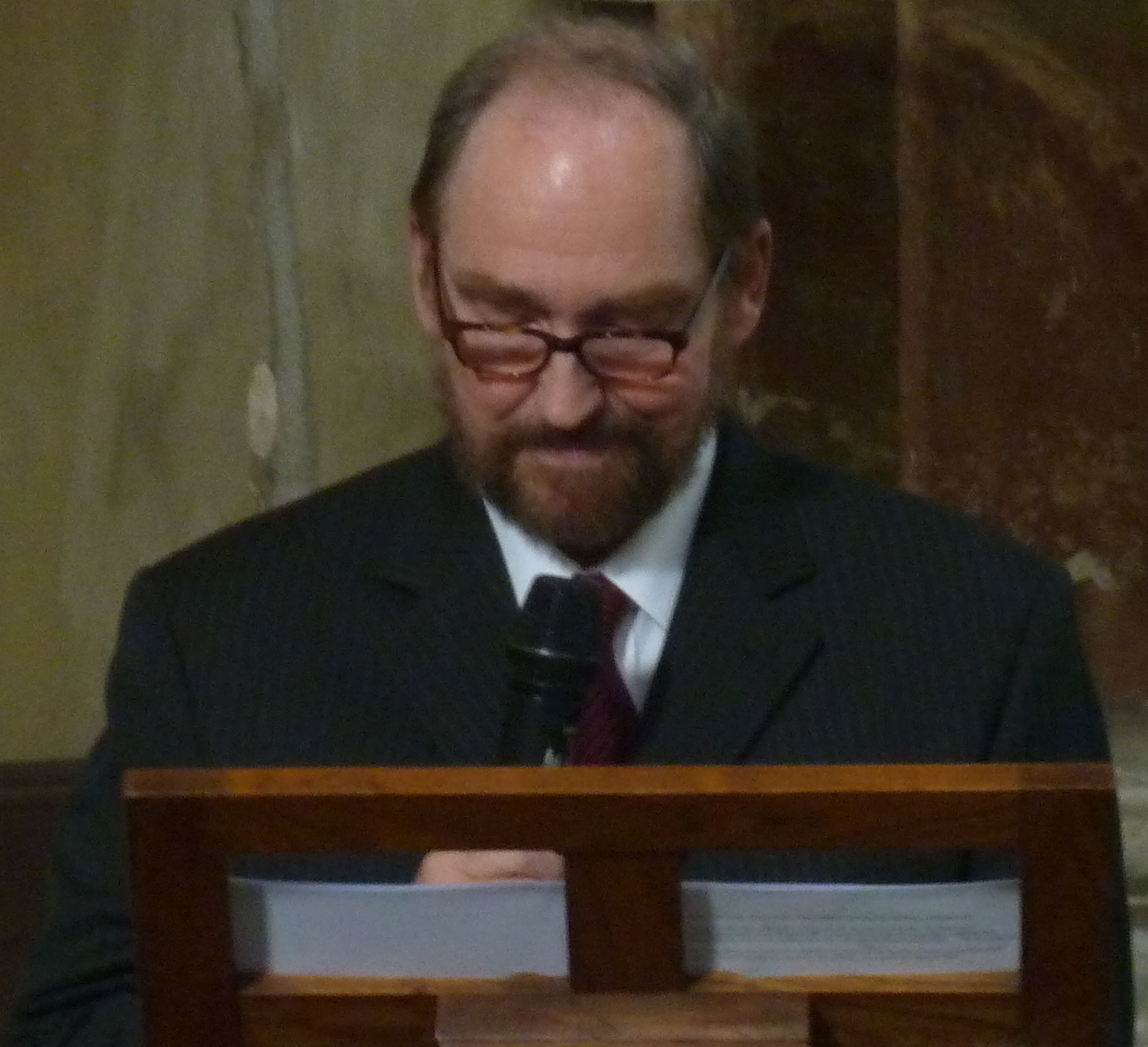1. 概要
オーストリア大公カール・ルートヴィヒ・ハプスブルク=ロートリンゲン(Carl Ludwig Habsburg-Lothringenドイツ語、1918年3月10日 - 2007年12月11日)は、オーストリア=ハンガリー帝国最後の皇帝カール1世とツィタ皇后の間の四男として生まれ、激動の20世紀を生き抜いた実業家、そして社会貢献者です。オーストリアの帝政が崩壊する直前に生まれ、幼少期を亡命先で過ごし、第二次世界大戦ではアメリカ軍に参加するなど、その生涯は多岐にわたります。戦後はベルギーやカナダで実業家として成功を収め、特にジェンスターの設立と発展に尽力し、その事業手腕を発揮しました。同時に、貧困層や失業者への支援、ユダヤ人難民の救済活動にも積極的に関与し、人道的な貢献を果たしました。彼の生涯は、旧王室の一員としての歴史的背景を持ちながらも、新しい時代において経済と社会福祉の分野で具体的な成果を残した点で、特筆すべき意義があります。この記事では、彼の個人的な背景から、企業家としてのキャリア、社会活動、そして祖国オーストリアとの複雑な関係に至るまで、その広範な影響と社会的重要性を詳しく探ります。
2. 生涯
オーストリア大公カール・ルートヴィヒは、激動の時代に生まれ、その生涯は亡命、戦争、そして実業家としての成功と社会貢献に彩られました。
2.1. 幼少期と教育
カール・ルートヴィヒは、1918年3月10日、バーデン・バイ・ウィーンで、オーストリア=ハンガリー帝国最後の皇帝カール1世とパルマ公ロベルト1世の娘であるツィタ皇后の間の第5子、四男として誕生しました。帝政崩壊のわずか半年前に生まれた彼の誕生時には、101発の祝砲が鳴らされたと伝えられています。
幼少期は、両親の最初の亡命先であるポルトガルのマデイラ島で過ごしました。その後、家族はベルギーへ移り、1930年代には長兄で家長であるオットーの援助のもと、ルーヴェン・カトリック大学で学びました。第二次世界大戦中の1940年、ナチス・ドイツ軍の侵攻に伴い、家族とともに北米へ避難し、母や未成年の弟妹たちと一緒にカナダのケベックに落ち着きました。この北米移住の際、彼は「Karl」の綴りを「Carlドイツ語」に変更しています。ケベックでは、ラヴァル大学で法学、政治学、社会学を学びました。
2.2. 第二次世界大戦への参加
カール・ルートヴィヒは、第二次世界大戦中に積極的に軍務に就き、その人道的な側面も示しました。彼は1943年にアメリカ軍に入隊しました。フランクリン・D・ルーズベルト大統領の命令により、中立国ポルトガルにおいてハンガリーとの秘密裏の和平交渉を試みましたが、これは最終的に失敗に終わりました。
また、彼は兄のフェリックスとともに、アメリカ陸軍の「自由オーストリア大隊」(101st歩兵大隊)に志願しました。しかし、この大隊は、部隊の大部分を占めていた亡命ユダヤ人志願兵が最終的に入隊を拒否したため、解散されることになりました。彼はこの間、アドルフ・ヒトラー率いるドイツから逃れてきたユダヤ人難民を支援する活動にも尽力しました。1944年にはノルマンディー上陸作戦にも参加し、1947年には陸軍少佐に昇進しました。
2.3. 事業と社会活動
戦後、カール・ルートヴィヒは実業家としてのキャリアを築き、同時に社会貢献活動にも力を入れました。アメリカ軍での勤務を終えた後、彼はベルギー企業の米国支社に入社し、ニューヨークやワシントンで働きました。
1958年に妻子とともにヨーロッパへ戻り、ブリュッセルでソシエテ・ジェネラル・ド・ベルジック社に勤務しました。その後、同社のカナダにおける子会社であるジェンスターを創設し、1986年に引退するまで同社の取締役を務めました。彼はジェンスターに様々な部門を創設することで会社規模を大きくし、引退するまでに同社の社員を2000人以上に増やしました。この業績は、彼の優れた事業手腕を示すものです。
また、彼は社会活動にも熱心でした。ベルギーでは、特に貧困層や失業者を支援する活動に尽力し、社会福祉の向上に貢献しました。これは、彼のハプスブルク家としての社会的責任感と、困窮する人々への深い共感を示すものでした。
2.4. オーストリアとの関係と帰国
カール・ルートヴィヒと祖国オーストリアとの関係は、ハプスブルク法によって複雑なものとなりました。1919年に制定されたこの法律は、オーストリア=ハンガリー帝国の旧統治者家門ハプスブルク家の資産を没収し、その成員がオーストリア市民権を得るためには皇位請求権とハプスブルク家の成員たる身分の放棄を宣言することを求めていました。
カール・ルートヴィヒはすぐ上の兄フェリックスとともに、オーストリア共和国政府に没収されたハプスブルク家の資産の一部返還を求めました。これらの資産の一部は、1935年から1936年にかけてハプスブルク家と共和国政府が一時的に和解した際に弁済されましたが、1938年のアンシュルス(ドイツによるオーストリア併合)の際にナチス・ドイツ政府に没収され、それ以来ハプスブルク側には返還されていませんでした。
長兄のオットーとは異なり、カール・ルートヴィヒはオーストリア市民権の取得と引き換えに皇位請求権放棄とハプスブルク家の成員たる身分の放棄を宣言することを拒否したため、長らくオーストリア政府から入国を禁じられていました。しかし、1996年3月26日に、オーストリア政府の譲歩により、彼は兄フェリックスとともに、皇位請求権放棄に明示的に言及しない形で共和国政府への忠誠を誓う宣言を行いました。これにより、同年4月16日にはオーストリア議会も彼ら兄弟に対するパスポートと入国許可証の付与を承認し、カール・ルートヴィヒは祖国への帰還を果たすことができました。
3. 結婚と子女
カール・ルートヴィヒは1950年1月17日にベルギーのエノー州ベルイユで、リーニュ公ウジェーヌ2世とノアイユ公女フィリピンヌ・ド・ノアイユの娘であるリーニュ公女ヨランド・ド・リーニュ(Yolande de Ligneフランス語、1923年5月6日 - 2023年9月13日)と結婚しました。彼らの間には4人の子女が生まれ、その血統はベルギー貴族とも結びついています。
- ルドルフ・マリア・カール・オイゲン・アンナ・アントニウス・マルクス・ダヴィアノ大公(Rudolf Maria Carl Eugen Anna Antonius Marcus d'Avianoドイツ語、1950年11月17日生)
- 1976年7月3日、ブリュッセルにて、ヴィランファーニュ・ド・ヴォジェルサンク女男爵エレーヌ(Hélène de Villenfagne de Vogelsanckフランス語、1954年4月24日生)と結婚。夫妻はその後ベルギーに居住しました。
- 1978年5月29日、彼と彼の子女および男系子孫は、王室特許状により、世襲の称号「ハプスブルク=ロートリンゲン公(女公)」および「敬称殿下」のベルギー貴族に編入されました。
- ルドルフはスイスのヴィラール=シュル=グランに拠点を置く投資会社「AAA gestion」で働き、ディーシュバッハ城に居住しています。
- 夫妻には8人の子女がいます。彼らは後にオーストリア帝室家長の承認により「オーストリア大公・大公女」の称号を認められました。
- カール・クリスティアン大公(Carl Christianドイツ語、1977年5月9日生) - 2007年6月2日、エステル・ド・サン=ロマン(1979年生)と結婚。
- プリシラ大公女(Priscillaドイツ語、1980年6月5日生) - 2022年、ガブリエル・コントレラス・ミジャンと婚約。
- ヨハネス大公(Johannesドイツ語、1981年6月1日生) - スイスのカトリック共同体「Eucharistein」の司祭。
- トマス大公(Thomasドイツ語、1983年10月13日生) - スイスのカトリック共同体「Eucharistein」のメンバー。
- マリー=デ=ネイジュ大公女(Marie-des-Neigesドイツ語、1986年6月17日生) - スイスのカトリック共同体「Eucharistein」のメンバー。
- フランツ=ルートヴィヒ大公(Franz-Ludwigドイツ語、1988年10月5日生) - 2018年、マティルド・ヴィニョン(1992年生)と結婚。
- ミヒャエル大公(Michaelドイツ語、1990年9月15日生)
- ヨーゼフ大公(Josephドイツ語、1991年11月14日生) - スイスのカトリック共同体「Eucharistein」のメンバー。
ルドルフ・マリア大公(左、カール・ルートヴィヒの長男)とツィタ皇后に関するプレゼンテーションを行うツィタ大公女(2014年) - アレクサンドラ・マリア・アンナ・フィリッパ・オットーニア大公女(Alexandra Maria Anna Philippa Othoniaドイツ語、1952年7月10日生)
- 1984年、チリのローマ教皇庁大使ヘクトル・リエスレ・コントレラス(Héctor Riesle Contrerasスペイン語、1943年2月16日生)と結婚。
- 夫妻には3人の子女がいます。
- フェリペ・リエスレ・デ・ハプスブルク=ロレーナ(Felipe Riesle de Habsburgo-Lorenaスペイン語、1986年2月27日生) - ピラール・ガルシア=ウイドブロ・エチェベリアと結婚。
- マリア・ソフィア・リエスレ・デ・ハプスブルク=ロレーナ(María Sofía Riesle de Habsburgo-Lorenaスペイン語、1987年7月18日生) - ロドリゴ・リソパトロン・モンテロと結婚。
- コンスタンサ・リエスレ・デ・ハプスブルク=ロレーナ(Constanza Riesle de Habsburgo-Lorenaスペイン語、1989年9月1日生) - セバスティアン・プリエト・ドノソと結婚。
- カール・クリスティアン・マリア・アンナ・ルドルフ・アントン・マルクス・ダヴィアノ大公(Carl Christian Maria Anna Rudolph Anton Marcus d'Avianoドイツ語、1954年8月26日生)
- 1982年、ルクセンブルク大公女マリー=アストリッド・ド・リュクサンブール(Marie Astrid of Luxembourgフランス語、1954年2月17日生)と結婚。
- 彼も兄ルドルフと同様に、スイスのヴィラール=シュル=グランに拠点を置く投資会社「AAA gestion」で働いています。
- 夫妻には5人の子女がいます。
- マリー=クリスティーヌ大公女(Marie-Christineドイツ語、1983年7月31日、ブリュッセル生) - 2008年12月6日、リンブルフ=スティルム伯ルドルフ(1979年3月20日、ユクル生)とメヘレンで民事婚、後に聖ロンボウツ大聖堂で宗教婚を挙げました。夫妻には3人の息子がいます。
- レオポルド・ド・リンブルフ=スティルム伯(Léopoldフランス語、2011年4月19日、ブエノスアイレス生)
- コンスタンタン・ド・リンブルフ=スティルム伯(Constantinフランス語、2013年10月25日、ブエノスアイレス生)
- ガブリエル・ド・リンブルフ=スティルム伯(Gabrielフランス語、2016年生)
- イムレ大公(Imreドイツ語、1985年12月8日、ジュネーヴ生) - 2012年12月8日、アメリカ合衆国ワシントンD.C.の聖母マリア・神の母カトリック教会にてキャスリーン・エリザベス・ウォーカー(Kathleen Elizabeth Walker英語、1986年4月17日、シンシナティ生)と結婚。夫妻には5人の子女がいます。
- マリア=ステラ大公女(Maria-Stellaドイツ語、2013年11月11日、キルヒベルク生)
- マグダレナ大公女(Magdalenaドイツ語、2016年2月24日、キルヒベルク生)
- ユリアーナ大公女(Julianaドイツ語、2018年10月14日、ジュネーヴ生)
- チェチリア大公女(Ceciliaドイツ語、2021年1月15日、ジュネーヴ生)
- カール大公(Karlドイツ語、2023年6月4日、ジュネーヴ生)
- クリストフ大公(Christophドイツ語、1988年2月2日、ジュネーヴ生) - 2012年12月29日、フランスのナンシーにあるサン=エヴル・ナンシー大聖堂にてアデライード・マリー・ベアトリス・ドラペ=フリッシュ(Adélaïde Marie Béatrice Drapé-Frischフランス語、1989年9月4日、レ・リラ生)と結婚。夫妻には4人の子女がいます。
- カタリナ大公女(Katarinaドイツ語、2014年12月22日、ジュネーヴ生)
- ソフィア大公女(Sophiaドイツ語、2017年8月31日、ジュネーヴ生)
- ヨーゼフ大公(Josefドイツ語、2020年10月、ジュネーヴ生)
- フラヴィア大公女(Flaviaドイツ語、2023年生)
- アレクサンダー大公(Alexanderドイツ語、1990年9月26日、メイラン生) - 2023年9月30日、ベルギーのブロイユにてナターシャ・ルミアンツェフ=パシュケヴィッチと結婚。
- ガブリエラ大公女(Gabriellaドイツ語、1994年3月26日、ジュネーヴ生) - 2020年9月12日、オーストリアのイェンバッハにあるトラツベルク城にてブルボン=パルマ家のアンリ公(Henriフランス語、1991年10月14日、ロスキレ生)と結婚。夫妻には3人の娘がいます。
- ヴィクトリア・アントニア・マリー=アストリッド・リディア・ド・ブルボン=パルマ公女(Victoria Antonia Marie-Astrid Lydiaフランス語、2017年10月30日、ジュネーヴ生)
- アナスタシア・エリカ・アレクサンドラ・マリー・ヨランド・ド・ブルボン=パルマ公女(Anastasia Erika Alexandra Marie Yolandeフランス語、2021年7月3日、ジュネーヴ生)
- フィリッピナ・ド・ブルボン=パルマ公女(Philippinaフランス語、2023年生)
- マリア・コンスタンツァ・アンナ・ロザリオ・ローベルタ大公女(Maria Constanza Anna Rosario Robertaドイツ語、1957年10月19日生)
- 1994年6月18日、ベルギーのブロイユにて、アウエルスペルク=トラウトゾーン侯家家長フランツ・ヨーゼフ(Franz Josef, Fürst von Auersperg-Trautsonドイツ語、1954年12月11日生)と結婚。
- 夫妻には3人の実子(1人は生後まもなく死去)と1人の養女がいます。いずれも「アウエルスペルク=トラウトゾーン公女」の称号を持ちます。
- アンナ・マリア・フォン・アウエルスペルク=トラウトゾーン公女(Anna Mariaドイツ語、1997年9月24日生)
- アレクサンドラ・マリア・フォン・アウエルスペルク=トラウトゾーン公女(Alexandra Mariaドイツ語、1998年2月9日生、同日死去)
- ラディスラヤ・フォン・アウエルスペルク=トラウトゾーン公女(Ladislayaドイツ語、1999年2月26日生)
- エレオノラ・フォン・アウエルスペルク=トラウトゾーン公女(Eleonoraドイツ語、2002年5月28日生)
- マリー=クリスティーヌ大公女(Marie-Christineドイツ語、1983年7月31日、ブリュッセル生) - 2008年12月6日、リンブルフ=スティルム伯ルドルフ(1979年3月20日、ユクル生)とメヘレンで民事婚、後に聖ロンボウツ大聖堂で宗教婚を挙げました。夫妻には3人の息子がいます。
4. 死去
カール・ルートヴィヒ大公は、2007年12月11日にベルギーのブリュッセルで89歳で逝去しました。彼の葬儀は翌2008年1月12日にオーストリアのウィーンで執り行われました。彼の遺体は、ハプスブルク家の歴代皇帝や皇族が眠るカプツィーナー納骨堂に、母であるツィタ皇后の棺の隣に埋葬されました。
葬儀にはオーストリア=ハンガリー帝国の旧皇室、ルクセンブルク大公家、ベルギー王室など、多数の王族が参列しました。また、オーストリア共和国政府もこの葬儀に協力し、オーストリア警察が動員されるなど、国家レベルでの関与が見られました。これは、かつて皇室と対立した政府が、旧皇室の一員であるカール・ルートヴィヒの死去に際して一定の敬意を示したことを意味します。


5. 家族関係
カール・ルートヴィヒ大公の祖先を以下に示します。
- 1. カール・ルートヴィヒ・ハプスブルク=ロートリンゲン大公
- 2. 父: オーストリア皇帝カール1世
- 4. 父方の祖父: オーストリア大公オットー・フランツ
- 8. 父方の曾祖父: オーストリア大公カール・ルートヴィヒ
- 9. 父方の曾祖母: 両シチリア公女マリア・アンヌンツィアータ
- 5. 父方の祖母: ザクセン王女マリア・ヨーゼファ
- 10. 父方の曾祖父: ザクセン国王ゲオルク
- 11. 父方の曾祖母: ポルトガル王女マリア・アナ
- 4. 父方の祖父: オーストリア大公オットー・フランツ
- 3. 母: パルマ公女ツィタ
- 6. 母方の祖父: パルマ公ロベルト1世
- 12. 母方の曾祖父: パルマ公カルロ3世
- 13. 母方の曾祖母: アルトワ公女ルイーズ・マリー・テレーズ
- 7. 母方の祖母: ポルトガル王女マリア・アントニア
- 14. 母方の曾祖父: ポルトガル国王ミゲル1世
- 15. 母方の曾祖母: レーヴェンシュタイン=ヴェルトハイム=ローゼンベルク侯女アデライデ
- 6. 母方の祖父: パルマ公ロベルト1世
- 2. 父: オーストリア皇帝カール1世
6. 評価と遺産
オーストリア大公カール・ルートヴィヒの生涯は、単なる旧王室の一員という枠を超え、多角的な貢献と影響力を持つものでした。彼は、帝政が崩壊し、ハプスブルク家がかつての権力を失った時代に生まれながらも、その状況を乗り越え、実社会で顕著な成功を収めました。
彼の事業家としての才能は、カナダにおけるジェンスターの設立と発展に最もよく表れています。同社を大きく成長させ、数千人規模の雇用を創出したことは、彼の経済界におけるリーダーシップと先見の明を証明するものです。これは、貴族としての出自に甘んじることなく、自らの力で社会に価値を生み出した好例と言えます。
また、第二次世界大戦中のアメリカ軍への参加や、ユダヤ人難民への支援、戦後のベルギーにおける貧困層や失業者への援助活動は、彼の人間性と社会貢献への強い意志を示しています。特に、難民支援は、普遍的な人道主義の観点から高く評価されるべき活動です。これらの行動は、彼の高潔な精神と、苦しむ人々に寄り添う姿勢を明確に物語っています。
祖国オーストリアとの関係においては、ハプスブルク法による皇位請求権放棄問題は複雑な課題でした。しかし、彼は最終的に、皇位請求権を明示的に放棄することなく、共和国政府への忠誠を誓うという形でこの問題に決着をつけ、祖国への帰還を果たしました。これは、旧王室の歴史と新しい共和国の間の架け橋となる、象徴的な和解のジェスチャーでした。
カール・ルートヴィヒ大公の生涯は、激動の時代に高貴な血統を持ちながらも、ビジネスと社会貢献の両面で実りある足跡を残した人物の模範として、歴史に刻まれるでしょう。彼の遺産は、単なる家系の継承にとどまらず、変化する世界に適応し、積極的に社会に関与することの重要性を示唆しています。