1. 初期生と教育
マーガレット・アリス・マレーの初期の人生は、インドでの幼少期からイギリス、ドイツでの成長過程、家族関係、そして看護師や社会福祉士としての初期の経験が特徴的である。これらの経験は、彼女の後の学術的な道とフェミニストとしての視点に大きな影響を与えた。
1.1. 幼少期と成長過程
マーガレット・マレーは1863年7月13日、当時イギリス領インド帝国の主要な軍事都市であり首都であったベンガル管区のコルカタで生まれた。彼女は両親のジェームズとマーガレット・マレー、姉のメアリー、父方の祖母と曾祖母とともに市内で暮らした。父のジェームズ・マレーはアングロ・アイリッシュ系でインド生まれのビジネスマンであり、セランポール製紙工場の支配人を務め、コルカタ商工会議所の会頭に3度選出された。母のマーガレット(旧姓カー)は1857年にイギリスからインドに移住し、キリスト教の宣教師として働き、インド人女性の教育に尽力した。彼女はジェームズと結婚し、2人の娘を産んだ後もこの活動を続けた。
マレー一家の生活のほとんどは、インド人居住区から隔てられたコルカタのヨーロッパ人居住区で営まれていたが、マレーは10人のインド人使用人との交流や、ムスーリーでの幼少期の休暇を通じてインド社会のメンバーと接した。歴史家のアマラ・ソーントンは、マレーのインドでの幼少期が彼女の生涯にわたって影響を与え続け、彼女がイギリスとインドの両方の要素を持つ「ハイブリッドな多国籍的アイデンティティ」を持っていたと示唆している。幼少期、マレーは正式な教育を受けることはなく、後に大学入学まで試験を受けたことがなかったことを誇りに思っていたと述べている。
1870年、マーガレットと姉のメアリーはイギリスに送られ、バークシャー州ランボーンに住む叔父のジョン(牧師)とその妻ハリエットのもとに身を寄せた。叔父のジョンは彼女たちに厳格なキリスト教教育と女性の劣等性に関する信念を教え込んだが、マレーはこれらを後に拒絶した。しかし、叔父が彼女を地元の記念碑に連れて行ったことで、マレーの考古学への関心が目覚めた。1873年、姉妹の母親がヨーロッパに到着し、彼女たちを連れてドイツのボンに移り住み、そこで2人ともドイツ語を流暢に話せるようになった。1875年にはコルカタに戻り、1877年まで滞在した。その後、両親とともにイギリスに戻り、サウスロンドンのシデナムに定住した。ここでは、父親がロンドンの事務所で働く間、クリスタル・パレスを頻繁に訪れた。
1880年、彼女たちはコルカタに戻り、マーガレットはその後7年間をそこで過ごした。彼女は聖公会修道女会が運営するコルカタ総合病院で看護師となり、コレラの流行に対処する病院の取り組みに関与した。1881年、18歳の時、マーガレットはジェームズ・マレー(血縁関係はない)がオックスフォード英語辞典(OED)に掲載する単語や引用を世界中の英語話者に呼びかけていることを知った。彼女は涼しい早朝に屋根で本を読む習慣があり、ウィリアム・L'アイル版のアルフリックの『サクソン旧約聖書および新約聖書に関する論文』から300項目をマレーに提出した。彼女は1888年までボランティアを続け、マレーの要求通り、4インチ×6インチの紙片に合計5,000項目を提出した。
1887年、彼女はイギリスに戻り、ウォリックシャー州ラグビーに移り住んだ。そこには、すでに寡婦となっていた叔父のジョンが引っ越してきていた。ここで彼女は、地元の貧困層を支援する社会福祉士として働き始めた。父親が引退してイギリスに移住すると、彼女はハートフォードシャー州ブッシーの彼の家に引っ越し、1891年に父親が亡くなるまで一緒に暮らした。1893年、彼女は姉が新しい夫とともに移り住んでいたタミル・ナードゥ州チェンナイ(旧マドラス)を訪れた。
1893年後半、マレーは姉のメアリーがザ・タイムズ紙でフリンダーズ・ペトリー(後の彼女の師となる)が教えるエジプト・ヒエログリフのクラスの広告を見つけたことで、初めてエジプト学に触れることになった。後の自伝で、マレーは姉が結婚して子育てで忙しく、自身がそのクラスに通うことができなかったため、マレーに強く勧めたことが、彼女のエジプト学キャリアの道を開いたと述べている。
1.2. 教育と学問への道

母と姉の勧めで、マレーはロンドン中心部ブルームズベリーにあるユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)に新設されたエジプト学部に登録することを決めた。1894年1月、30歳でUCLでの研究を開始した。当時のエジプト学は、オックスフォード大学が中期エジプト語を東洋言語の一つとして提供していた以外は、正式な学位課程ではなかった。この学部は、エジプト探査基金(EEF)の共同創設者の一人であるアメリア・エドワーズの寄付によって設立され、先駆的な初期の考古学者であるウィリアム・フリンダーズ・ペトリー卿が運営し、UCLの南回廊にあるエドワーズ図書館を拠点としていた。マレーがUCLに入学した際のクラスは、主に他の女性と年配の男性で構成されていた。そこで彼女は、フランシス・ルウェリン・グリフィスが教える古代エジプト語と、ウォルター・ユーイング・クラムが教えるコプト語のコースを受講した。
マレーはすぐにペトリーと知り合い、彼の写字生兼挿絵画家となり、コプトスでの発掘報告書『コプトス』のための図面を制作した。その見返りに、ペトリーは彼女が最初の研究論文「エジプト史初期における財産継承」を執筆するのを支援し、この論文は1895年に『聖書考古学協会議事録』に掲載された。ペトリーの事実上非公式な助手となったマレーは、グリフィスが不在の際に言語学の授業の一部を担当するようになった。1898年、彼女は助講師の職に任命され、エジプト学部の言語学コースの指導を担当することになった。これにより、彼女はイギリスで最初の女性考古学講師となった。この職務において、彼女は週に2日をUCLで過ごし、残りの日は病気の母親の介護に充てた。時が経つにつれて、彼女は古代エジプトの歴史、宗教、言語に関するコースを教えるようになった。
マレーの学生たち(彼女は彼らを「ギャング」と呼んだ)の中には、後にエジプト学に顕著な貢献をした者もおり、レジナルド・エンゲルバッハ、ジョージナ・エイトケン、ガイ・ブラントン、マートル・ブルームなどがいた。彼女はUCLの給与を補うため、大英博物館でエジプト学の夜間クラスを教えていた。
2. エジプト学・考古学キャリア
マーガレット・アリス・マレーの学術的キャリアは、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)での教職、主要な考古学発掘調査、学術著作、そしてエジプト学の普及活動にわたる幅広い活動によって特徴づけられる。彼女の活動は、エジプト学の発展に貢献しただけでなく、学術界における女性の役割を拡大する上でも重要な意味を持った。
2.1. ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)での活動
UCLにおいて、マレーは1921年に講師に、1922年には上級講師に、そして1924年には助教授に昇進した。彼女は1910年にエジプト考古学の正式な証明書制度の導入に尽力し、その責任を負った。エジプト学部の非公式な管理職も務め、学生に栄養価が高く手頃な価格の昼食を提供すべきだと考え、長年にわたりUCL食堂委員会に所属した。1927年には、エジプト学におけるキャリアに対して名誉博士号を授与された。同年、彼女はUCL訪問中のメアリー・オブ・テック王妃をエジプト学部に案内する任務を負った。この頃には、教育の負担が軽減され、マレーは国際的な旅行に多くの時間を費やすことができた。1920年にはエジプトに再訪し、1929年には南アフリカを訪れ、南アフリカの先史時代をテーマとした英国科学振興協会の会議に出席した。1930年代初頭にはソビエト連邦を旅し、レニングラード、モスクワ、ハルキウ、キーウの博物館を訪れた。その後、1935年後半にはノルウェー、スウェーデン、フィンランド、エストニアで講演ツアーを行った。
マレーは1927年に法的な定年を迎えていたが、その後も毎年契約を更新され、1935年までUCLに在籍した。この年、彼女はUCLを退職したが、その理由は明確にしなかった。1933年にペトリーがUCLを退職し、妻とともにイギリス委任統治領パレスチナのエルサレムに移住したため、マレーは『エンシェント・エジプト』誌の編集を引き継ぎ、エジプト周辺およびエジプトと交流した古代社会の研究関心の高まりを反映して誌名を『エンシェント・エジプト・アンド・ジ・イースト』に変更した。この雑誌はマレーの退職も一因となり、1935年に廃刊となった。
2.2. 主要な発掘調査とフィールドワーク

この時点まで、マレーはフィールドワークの経験がなかったため、1902年から1903年の発掘シーズンにエジプトアビドスでのペトリーの発掘調査に参加するためにエジプトに渡った。ペトリーと彼の妻ヒルダ・ペトリーは1899年からこの地で発掘を行っており、フランスのコプト語学者エミール・アメリノーから考古学的調査を引き継いでいた。マレーは当初、現場の看護師として参加したが、その後ペトリーから発掘方法を教えられ、上級職に任命された。
このことは、女性からの指示を受けることを嫌う一部の男性発掘者との間に問題を引き起こした。この経験は、他の女性発掘者(中にはフェミニスト運動に積極的に参加している者もいた)との議論と相まって、マレーが公然とフェミニズムの視点を取り入れるきっかけとなった。アビドスでの発掘中に、マレーはオシレイオンを発見した。これは新王国時代のセティ1世の命により建設されたオシリス神に捧げられた神殿である。彼女は1904年に発掘報告書『アビドスにおけるオシレイオン』を出版し、その中で発見された碑文を調査し、建物の目的と用途を明らかにした。
1903年から1904年の発掘シーズン中、マレーはエジプトに戻り、ペトリーの指示によりカイロ近郊の古王国時代のサッカラ墓地での調査を開始した。マレーは発掘の法的許可を持っていなかったため、代わりに1860年代にオーギュスト・マリエットによって発掘された10の墓からの碑文の転写に時間を費やした。彼女は1905年にその成果を『サッカラ・マスタバスI』として出版したが、碑文の翻訳は1937年まで『サッカラ・マスタバスII』として出版されなかった。『アビドスにおけるオシレイオン』と『サッカラ・マスタバスI』の両方は、エジプト学界で非常に大きな影響力を持つこととなり、ペトリーはマレーの自身のキャリアへの貢献を認めた。

1921年から1927年にかけて、彼女はエディス・ゲストとガートルード・ケイトン・トンプソンの助けを借りて、マルタでの考古学発掘調査を主導した。彼女は、新しい飛行場の建設によって脅かされていた青銅器時代の巨石記念物であるサンタ・ソフィア、サンタ・マリア・タル=バッカリ、グハール・ダラム、ボルグ・イン=ナドゥールを発掘した。この活動はパーシー・スレーデン記念基金から資金援助を受けた。その結果として発表された3巻の発掘報告書は、マルタ考古学の分野で重要な出版物と見なされるようになった。発掘中、彼女は島の民間伝承に興味を持ち、1932年に著書『マルタの民話』を出版した。この本の多くは、マヌエル・マグリと友人のリザ・ガレアが以前に収集した物語の翻訳であった。1932年、マレーはマルタに戻り、マルタ国立考古学博物館に収蔵されている青銅器時代の陶器コレクションの目録作成を支援し、別の出版物『マルタの青銅器時代陶器のコーパス』につながった。
マルタでの業績に基づき、ケンブリッジ大学考古学人類学博物館のキュレーターであるルイ・クラークは、1930年から1931年にかけてメノルカ島での発掘調査を主導するよう彼女を招いた。ゲストの助けを借りて、彼女はタライオティック文化の遺跡であるトレプコとサ・トレタ・デ・トラムンタナを発掘し、『メノルカにおけるケンブリッジ発掘調査』の出版につながった。
1935年にパレスチナを訪れた際、マレーは隣接するヨルダンのペトラを訪れる機会を得た。この遺跡に興味を抱いた彼女は、1937年3月と4月に再訪し、遺跡内のいくつかの洞窟住居で小規模な発掘調査を行った。その後、ペトラに関する発掘報告書とガイドブックの両方を執筆した。
2.3. 学術的貢献と普及活動

ロンドンに戻ったマレーは、ダブリン国立博物館、エディンバラのスコットランド国立古物博物館、スコットランド古物協会が所有するエジプトの遺物について助言を求められ、これらの目録作成を行った。その功績により、スコットランド古物協会のフェローに選出された。
ペトリーはマンチェスターのマンチェスター博物館のエジプト学部門とつながりがあり、彼の発見物の多くがそこに収蔵されていた。そのため、マレーはしばしばこの博物館を訪れてこれらの遺物の目録を作成し、1906年から1907年の学年度には定期的にそこで講義を行った。
1907年、ペトリーは二人の兄弟の墓を発掘した。これは古代エジプト中王国時代の2人の司祭、ナハト=アンクとクヌム=ナハトの墓である。マレーは後者のミイラ化された遺体の公開解体を行うことになった。1908年5月に博物館で行われたこの解体は、女性が公開でミイラの解体を主導した初めての事例であり、500人以上の観衆が詰めかけ、報道機関の注目を集めた。マレーは、この解体が中王国時代とその埋葬習慣の学術的理解にとって重要であることを特に強調し、これを不道徳と見なす一般の人々を激しく非難した。彼女は「古代の遺物のあらゆる痕跡は、感傷的にならず、無知な人々の叫びを恐れることなく、慎重に研究され記録されなければならない」と宣言した。その後、彼女は2体の遺体の分析に関する著書『二人の兄弟の墓』を出版し、これは21世紀まで中王国時代のミイラ化の習慣に関する重要な出版物であり続けた。
マレーは一般教育に献身し、西洋世界における古代エジプトのイメージに古代エジプトに関する確かな学問を注入することを望み、この目的のために一般読者向けの書籍を多数執筆した。1905年には『初級エジプト語文法』を出版し、1911年には『初級コプト語(サヒド語)文法』が続いた。1913年には、ジョン・マレーの「東洋の知恵」シリーズのために『古代エジプトの伝説』を出版した。彼女は、ハワード・カーターによるツタンカーメンの墓の発見(1922年)に続くエジプト学への一般の関心の高まりを特に喜んだ。少なくとも1911年から1940年に彼が亡くなるまで、マレーはロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの人類学者チャールズ・ガブリエル・セリグマンの親しい友人であり、彼らは共同で人類学の読者層を対象としたエジプト学に関する様々な論文を執筆した。これらの多くは、エジプト学の雑誌では掲載されないような主題、例えば子宮の「サ」記号などを扱っており、そのため王立人類学研究所の雑誌『マン』に掲載された。1916年、セリグマンの推薦により、彼女は同研究所の会員に招待された。
1914年、ペトリーはUCLに拠点を置く自身の英国エジプト考古学学校(BSAE)を通じて学術雑誌『エンシェント・エジプト』を創刊した。彼がエジプトでの発掘のためにロンドンを離れていることが多かったため、マレーはほとんどの場合、事実上の編集者として活動した。彼女はまた、この雑誌に多くの研究論文を発表し、特にペトリーが読めなかったドイツ語の出版物の書評を多数執筆した。
3. フェミニズムと社会活動

ロンドンに戻ったマレーは、フェミニズム運動に積極的に参加し、その活動にボランティアとして貢献し、財政的にも寄付を行い、フェミニストのデモ、抗議活動、行進に参加した。女性社会政治連合に加盟し、1907年の泥の行進や1911年6月の女性戴冠式行列のような大規模な行進にも参加した。彼女は学術界での尊敬されるイメージを維持するため、自身の活動の過激な側面を隠していた。
マレーはまた、自身のキャリアを通じて女性の専門的境界を押し広げ、考古学や学術界全体で他の女性を指導した。女性は男性の談話室を使用できなかったため、彼女はUCLに女性用談話室を開設するよう働きかけ、後に、より大きく設備の整った部屋がその目的に転用されるよう尽力した。この部屋は後に「マーガレット・マレー・ルーム」と改名された。UCLでは、同僚の女性講師であるウィニフレッド・スミスと友人になり、共に大学における女性の地位と認知度向上を目指して活動した。マレーは、男性の大学組織を怒らせることを恐れて要求を出さない女性職員に特に不満を抱いていた。学生には栄養価が高く手頃な価格の昼食が提供されるべきだと考え、長年にわたりUCL食堂委員会に所属した。
第一次世界大戦が1914年に勃発し、イギリスがドイツ帝国やオスマン帝国と戦争状態に入ったため、ペトリーや他の職員は発掘のためにエジプトに戻ることができなくなった。代わりに、ペトリーとマレーは過去数十年間に収集した遺物コレクションの再編成に多くの時間を費やした。イギリスの戦争努力を支援するため、マレーはカレッジ女性組合協会の志願航空分遣隊の志願看護師として登録し、数週間にわたりフランスのサン=マロに派遣された。
彼女自身が病に倒れた後、サマセット州グラストンベリーで療養することになり、そこでグラストンベリー修道院と、伝説上のアーサー王やアリマタヤのヨセフが聖杯をもたらしたという民間伝承に興味を持つようになった。この関心を追求し、彼女は論文「聖杯伝説におけるエジプト的要素」を『エンシェント・エジプト』誌に発表したが、その結論に同意する者は少なく、ジェシー・ウェストンなどからは、証拠に基づく飛躍が多すぎると批判された。
4. 民俗学と魔女カルト仮説
マレーが提唱した「魔女カルト仮説」は、彼女の学術的キャリアにおける最も論争を呼んだ側面の一つである。この仮説は、魔女裁判の犠牲者が、キリスト教以前の異教信仰の信者であったと主張し、学界で大きな議論を巻き起こした。
4.1. 魔女カルト仮説の形成と内容

マレーの民俗学への関心は、近世ヨーロッパの魔女裁判への興味へとつながった。1917年、彼女は英国フォークロア学会の機関誌『フォークロア』に論文を発表し、そこで初めて魔女カルト理論の彼女のバージョンを明確に述べた。彼女は、ヨーロッパ史で迫害された魔女たちは、実際には「信仰、儀式、組織が、当時のいかなるカルトとも同じくらい高度に発達した明確な宗教」の信者であったと主張した。彼女はその後、『マン』誌や『スコティッシュ・ヒストリカル・レビュー』誌にこの主題に関する論文を発表した。彼女はこれらの見解を、1921年の著書『西ヨーロッパの魔女カルト』でより詳細に述べた。この本はヘンリー・バルフォアによる肯定的な査読を経てオックスフォード大学出版局から出版され、出版時には批判と支持の両方を受けた。学術雑誌の多くの書評は批判的で、歴史家たちは彼女が使用した同時代の記録を歪曲し、誤解していると主張したが、この本はそれでも影響力を持った。
この分野での彼女の業績の結果として、彼女は1929年の『ブリタニカ百科事典』第14版の「魔術」の項目を執筆するよう招待された。彼女はこの機会を利用して自身の魔女カルト理論を広め、他の学者によって提案された代替理論については言及しなかった。彼女の項目は1969年まで百科事典に掲載され、一般の人々が容易にアクセスできるようになり、このため彼女のこの主題に関する考えは非常に大きな影響力を持つことになった。ディオン・フォーチュン、ルイス・スペンス、ラルフ・シャーリー、J. W. ブロディー・インネスなどのオカルティストから特に熱狂的な支持を受けた。これはおそらく、彼女の古代の秘密結社に関する主張が、様々なオカルトグループの間で共通する同様の主張と共鳴したためであろう。マレーは1927年2月に英国フォークロア学会に入会し、その1か月後には学会の評議会に選出されたが、1929年には辞任した。マレーは1933年の著書『魔女の神』で魔女カルト理論を再提示したが、これはより広範な非学術的な読者層を対象としていた。この本では、彼女は魔女カルトのより不快な側面、例えば動物犠牲や幼児犠牲などを削除または緩和し、その宗教を「古き宗教」としてより肯定的な言葉で描写し始めた。
『西ヨーロッパの魔女カルト』において、マレーは自身の研究をグレートブリテン島に限定したと述べているが、フランス、フランドル地方、ニューイングランドの資料にも言及している。彼女は「実践的魔術」(あらゆる目的のための呪文や魔法の実行を指す)と「儀式的魔術」(「西ヨーロッパの古代宗教」、彼女が「ディアナ崇拝」とも呼んだ豊穣信仰)を区別した。彼女は、このカルトはかつて「非常に高い確率で」男性神と「母なる女神」の両方の崇拝に捧げられていたが、「カルトが記録された時点では、男性神の崇拝が女性神の崇拝に取って代わっていた」と主張した。彼女の主張では、裁判記録に「悪魔」として言及された人物は、魔女たちの神であり、「顕現し、受肉した」存在であり、魔女たちは彼に祈りを捧げた。彼女は、魔女たちの集会では、神は通常男性によって、時には女性や動物によって擬人化されたと主張した。人間がこの存在を擬人化する際には、通常は質素な服装をしていたが、魔女のサバトでは完全な衣装を身につけて現れたという。
会員は「入会儀式」を通じて子供または大人としてカルトに参加したとマレーは述べた。マレーは、申請者は自身の自由意志で参加することに同意し、彼らの神への奉仕に献身することに同意しなければならなかったと主張した。彼女はまた、場合によっては、これらの個人が誓約書に署名したり、信仰に洗礼を受けたりする必要があったと主張した。同時に、彼女は宗教が主に世襲制で受け継がれたと主張した。マレーはこの宗教を、13人のメンバーからなるコヴンに分かれていると描写し、コヴンは裁判記録でしばしば「悪魔」と呼ばれたコヴンの役員によって率いられていたが、その役員は「グランドマスター」に責任を負っていた。マレーによれば、コヴンの記録は秘密の書物に保管されており、コヴンはメンバーを規律し、裏切り者と見なされた者を処刑することさえあった。
この魔女カルトを「喜びに満ちた宗教」と描写し、彼女はそれが祝う主要な2つの祭りが5月前夜と11月前夜であったと主張した。しかし、他の宗教的祝日は2月1日と8月1日、冬至と夏至、そしてイースターであった。彼女は「宗教の全メンバーの総会」がサバトとして知られていたのに対し、より私的な儀式的な集会はエスバットとして知られていたと主張した。マレーは、エスバットは真夜中に始まる夜間の儀式であり、「主にビジネスのためであり、一方サバトは純粋に宗教的であった」と主張した。前者では、悪意ある目的と善意ある目的の両方のために魔法の儀式が行われた。彼女はサバトの儀式には、魔女たちが神に敬意を払い、彼への「忠誠と服従の誓い」を更新し、前回のサバト以来行われたすべての魔法の行為の報告を彼に提供することが含まれていたと主張した。この事業が完了すると、カルトへの入会や結婚が行われ、儀式や豊穣の儀式が行われ、その後サバトは祝宴と踊りで終わった。

儀式的魔術を「豊穣崇拝」と見なし、彼女は多くの儀式が豊穣と雨乞いを確実にするために考案されたと主張した。彼女は、魔女によって行われる4種類の犠牲があったと主張した。新参者が血で自分の名前を書く血の犠牲。動物の犠牲。魔法の力を得るために非キリスト教の子供を犠牲にすること。そして豊穣を確実にするために魔女の神を火で犠牲にすることである。
彼女は、魔女が様々な動物に変身するという記述を、魔女が神聖とみなした特定の動物の衣装を身につける儀式を表していると解釈した。彼女は、使い魔に関する記述は、魔女が動物を使用することに基づいていると主張した。彼女はこれを占いに使用される「占いの使い魔」と、他の魔法の儀式に使用される「家庭の使い魔」に分類した。
マレーは、キリスト教化の過程を生き延びたキリスト教以前の豊穣信仰がイギリスに存在し、それが「特定の場所と特定のコミュニティの階級の間でのみ実践された」と主張した。彼女は、イギリスの妖精の民話は、近世まで島に住み続けた生き残りのドワーフの一種に基づいていると信じていた。彼女は、この種族が魔女と同じ異教の宗教を信仰していたと主張し、それが両者の民話的なつながりを説明しているとした。本の付録では、彼女はジャンヌ・ダルクとジル・ド・レが魔女カルトのメンバーであり、そのために処刑されたと主張したが、ジャンヌ・ダルクの場合については歴史家によって反駁されている。
『西ヨーロッパの魔女カルト』は「少量の史料調査と、19世紀版の印刷された裁判記録、さらに近世のパンフレットや悪魔学の著作の広範な使用に基づいていた」と、後の歴史家ロナルド・ハットンは述べている。彼はまた、この本のトーンは概して「堅苦しく臨床的で、すべての主張は綿密に資料に脚注が付けられ、豊富な引用がなされていた」とも指摘している。ベストセラーにはならず、最初の30年間でわずか2,020部しか売れなかった。しかし、多くの人々がマレーをこの主題の権威として扱うようになり、1929年には『ブリタニカ百科事典』の「魔術」の項目を執筆するよう招待され、そこで彼女は自身の解釈を学術界で普遍的に受け入れられているかのように提示した。この項目は1969年に置き換えられるまで百科事典に掲載され続けた。
マレーは『西ヨーロッパの魔女カルト』に続き、1931年に大衆出版社サンプソン・ロウから『魔女の神』を出版した。内容は前作と似ているが、大衆市場を対象としていた点が異なっていた。この本のトーンも前作とは大きく異なり、「感情的に誇張された[言葉]と宗教的な表現で彩られ」、魔女カルトを繰り返し「古き宗教」と呼んだ。この本では、彼女は前作で主張した、性や動物や子供の犠牲など、カルトを悪く見せるような主張の多くを「削除または緩和」した。
この本で彼女は、魔女たちの神を「角のある神」と呼び始め、それが旧石器時代以来ヨーロッパで崇拝されてきた存在であると主張した。彼女はさらに、青銅器時代にはこの神の崇拝がヨーロッパ、アジア、アフリカの一部に広まっており、これらの社会から発見された様々な角のある人物の描写がそれを証明していると主張した。引用された証拠の中には、モヘンジョ・ダーロで発見された角のある人物像(しばしばパシュパティの描写と解釈される)や、エジプトのオシリス神とアメン神、ミノア文明のミノタウロスなどが含まれていた。ヨーロッパ大陸では、彼女は角のある神がギリシア神話のパン、ガリアのケルヌンノス、そして様々なスカンジナビアの岩絵で表現されていると主張した。この神がキリスト教当局によって悪魔と宣言されたと主張しながらも、彼女は彼の崇拝が近世まで公式にキリスト教化された社会で証言されていると断言し、ドーセット・ウーザーやパック・フェアなどの民間伝承の慣習を彼の崇拝の証拠として挙げた。
1954年、彼女は『イングランドの神聖王』を出版し、ジェームズ・フレイザーの『金枝篇』に影響を受け、その理論を大幅に拡張した。この人類学の書は、世界中の社会が自然の神々に王を犠牲に捧げていたと主張していた。彼女の著書では、この慣習が中世イングランドまで続いており、例えばウィリアム2世の死は実際には儀式的な犠牲であったと主張した。この本は学術界では真剣に受け止められず、多くの支持者からも無視された。
4.2. 学界における受容と批判

初期の出版時、マレーの論文は多くの読者、中には著名な学者(ただし魔女裁判の専門家はいなかった)から好意的に受け入れられた。近世イギリスの歴史家であるジョージ・ノーマン・クラークやクリストファー・ヒルは彼女の理論を自身の著作に取り入れたが、後者は後にその理論から距離を置いた。1961年の『西ヨーロッパの魔女カルト』の再版では、中世の歴史家スティーヴン・ランシマンが序文を寄せ、マレーの「些細な詳細には批判の余地があるかもしれない」と認めつつも、全体的には彼女の論文を支持した。彼女の理論は、アルノ・ルネバーグが1947年の著書『魔女、悪魔、そして豊穣魔術』で、またペネソーン・ヒューズが1952年の著書『魔女』で要約された。その結果、カナダの歴史家エリオット・ローズは1962年の著書で、マレーの魔女裁判に関する解釈は「執筆時点では、より高い知的レベルでほとんど議論の余地のない支配力を持っている」と主張し、「教育を受けた人々」の間で広く受け入れられていると述べた。
ローズは、マレーの理論がこれほど支持された理由の一つは、UCLの教員という「威厳ある経歴」であり、それが多くの読者の目に彼女の理論に大きな正当性を与えたためだと示唆した。彼はさらに、マレーの視点が多くの人々にとって魅力的であったのは、「ジェームズ・フレイザーやロバート・グレーヴスの読者がよく知っているキリスト教以前のヨーロッパの全体像」を裏付けるものであったためだと示唆した。同様に、ハットンは、マレーの理論が人気を博した原因は、「時代の多くの感情的衝動に訴えかけた」ためだと示唆した。これには、「古代の秘密に満ちた時代を超越したイングランドの田園地帯という概念」、パンの文学的人気、キリスト教化の過程後も大多数のイギリス人が長く異教徒のままであったという広範な信念、そして民間伝承の習慣が異教の生き残りであるという考えが含まれる。同時に、ハットンは、マレーの理論が、魔女裁判が大規模な妄想の結果であるという、それまで支配的であった合理主義的な考えよりも、多くの人々にとってより説得力があるように見えたと示唆した。
これに関連して、民俗学者ジャクリーン・シンプソンは、マレーの理論の魅力の一部は、魔女が存在したことを否定する合理主義者と、近世にキリスト教に対する実際のサタン的陰謀が存在し、超自然的な力を持つ魔女がいたと主張するモンタギュー・サマーズのような人々との間の「長年の不毛な議論に対する、賢明で、神秘を解き明かし、解放的なアプローチ」を提供したように見えたことだと示唆した。歴史家ヒルダ・エリス・デヴィッドソンは、「当時、彼女の最初の本がどれほど新鮮で、刺激的であったか」と述べ、「新しいアプローチであり、非常に驚くべきものであった」と指摘した。
マレーの理論は、近世の魔女裁判の専門家からは支持を得ることはなく、初期の出版以来、多くの彼女のアイデアは「事実の誤りと方法論の欠陥」を指摘する人々によって異議を唱えられた。実際、1920年代から1930年代にかけて発表された彼女の著作に関する学術的な書評のほとんどは批判的であった。ジョージ・L・バーは、『アメリカン・ヒストリカル・レビュー』で彼女の魔女カルトに関する最初の2冊の著書を批評した。彼は、彼女が「現代の学者による綿密な一般史」に精通しておらず、拷問や強制によって得られた告白であるかどうかにかかわらず、裁判記録が告発された魔女の真の魔術経験を正確に反映していると仮定していることを批判した。彼はまた、彼女が自身の解釈を裏付けるために証拠を選択的に使用していること、例えば裁判記録に現れる超自然的な出来事や奇跡的な出来事を省略していることを非難した。W. R. ハリデーは『フォークロア』誌の書評で、またE. M. ローブは『アメリカン・アンソロポロジスト』誌の書評で、非常に批判的であった。
その後すぐに、裁判記録の第一人者の一人であるL'エトランジュ・ユーウェンが、マレーの解釈を否定する一連の著書を発表した。ローズは、マレーの魔女カルトに関する著書には「信じられないほどの数の些細な事実の誤りや計算の誤り、そしていくつかの推論の矛盾」が含まれていると示唆した。彼は、彼女の主張は「おそらく、他の誰かによってまだ証明されるかもしれないが、私は非常に疑わしい」と認めた。イギリスのキリスト教化と魔女裁判の開始との間に約1000年のギャップがあることを強調し、彼はその間の期間に魔女カルトが存在した証拠がないと主張する。彼はさらに、マレーがキリスト教以前のイギリスを社会的・文化的に一枚岩の存在として扱っていることを批判するが、実際には多様な社会と宗教的信念が存在していた。彼はまた、中世のイギリス人の大多数が異教徒のままであったというマレーの主張を「無知に基づく見解」として異議を唱える。
マレーは自身の著作に対する批判に直接反応することはなかったが、批判者に対しては敵対的な態度を取った。晩年、彼女は自身の著作の書評を読むのをやめ、批判者たちは単に非キリスト教の宗教に対する彼ら自身のキリスト教的偏見から行動しているのだと信じていた。シンプソンは、これらの批判的な書評にもかかわらず、イギリスの民俗学の分野では、マレーの理論が「承認されずに、しかし異議を唱えられることなく通過することを許された。それは礼儀正しさからか、あるいは誰もその主題を研究するほど真剣に興味を持っていなかったためか」と指摘した。その証拠として、彼女はマレーの1917年の論文からロセル・ホープ・ロビンズの1963年の論文までの間、『フォークロア』誌に魔術に関する実質的な研究論文が掲載されなかったことを指摘した。彼女は、この期間にセオ・ブラウン、ルース・タング、エニッド・ポーターなどの民俗学者によってイギリスの民俗学の地域研究が発表された際、いずれも魔術信仰を解釈するためにマレーの枠組みを採用しなかったことを強調し、マレーの理論が民俗学の学者によって広く無視されていたという彼女の主張を裏付けた。
マレーの著作は1963年の彼女の死後、ますます批判されるようになり、マレーの魔女カルト理論に対する決定的な学術的否定は1970年代に起こった。これらの数十年間、ヨーロッパと北米の様々な学者、例えばアラン・マクファーレン、エリック・ミデルフォート、ウィリアム・モンター、ロバート・ミュシャンブレッド、ゲルハルト・ショルマン、ベンテ・アルバー、ベンクト・アンカルローなどが、魔女裁判のアーカイブ記録に関する詳細な研究を発表し、魔術で裁かれた人々が生き残ったキリスト教以前の宗教の実践者ではなかったことを疑いの余地なく明らかにした。
1971年、イギリスの歴史家キース・トーマスは、この研究に基づいて、「告発された魔女たちが悪魔崇拝者であったり、異教の豊穣崇拝のメンバーであったりしたことを示唆する証拠はほとんどない」と述べた。彼は、マレーの結論は「ほとんど完全に根拠がない」と述べた。なぜなら、彼女はユーウェンが提供した裁判記録の体系的な研究を無視し、自身の主張を裏付けるために非常に選択的に資料を使用したからである。
1975年、歴史家ノーマン・コーンは、マレーの「ヨーロッパ史、さらにはイギリス史に関する知識は表面的であり、歴史的方法の理解は皆無であった」と述べ、彼女の考えは「フレーザー流の誇張され歪曲された型にしっかりと嵌め込まれていた」と付け加えた。同年、宗教史家ミルチャ・エリアーデは、マレーの著作を「絶望的に不適切」であり、「数えきれないほどの恐ろしい誤り」を含んでいると評した。1996年、フェミニストの歴史家ダイアン・パーキスは、マレーの論文は「本質的にありそうもない」ものであり、「現代の学術界ではほとんど支持されていない」と述べたが、トーマス、コーン、マクファーレンのような男性学者が、自分たちの男性中心で方法論的に健全な解釈を、マレーの魔女カルトに関する「女性化された信念」と対比させるという不公平な男性中心主義的アプローチを採用したと感じた。
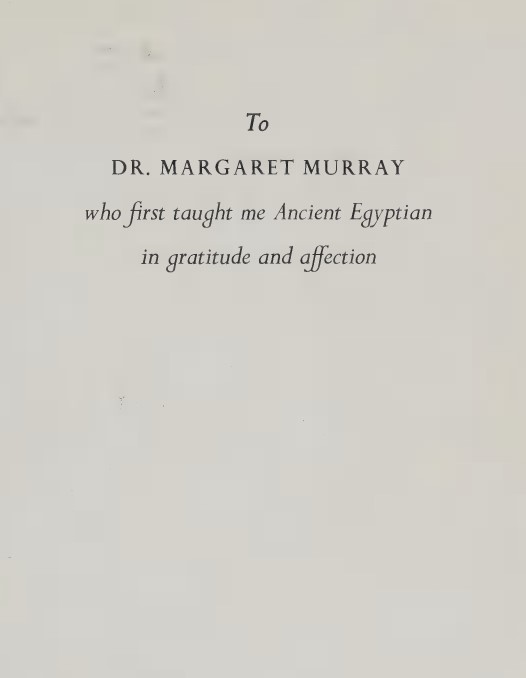
ハットンは、マレーが自身の資料を「無謀なまでに」扱ったと述べた。彼女は「広大な空間と時間に散らばる資料」から「魔女の慣行とされる鮮やかな詳細」を取り上げ、それをカルト全体の規範であると宣言したのである。シンプソンは、マレーが証拠の選択を非常に限定的に行い、特に裁判記録中の超自然的な出来事や奇跡的な出来事に関する記述を無視したり合理化したりすることで、彼女が描写している出来事を歪曲した方法を概説した。例えば、シンプソンが指摘したように、マレーは、悪魔が魔女のサバトに割れた蹄で現れたという主張を、彼が特殊な靴を履いた男であったと合理化し、同様に、魔女がほうきに乗って空中を飛んだという主張は、実際にはほうきの上で跳ねたり、幻覚作用のある軟膏を体に塗ったりする慣行に基づいていると断言した。この評価に同意し、歴史家のジェフリー・バートン・ラッセルは、独立作家ブルックス・アレクサンダーとともに、「一般的に、マレーの資料の使い方は恐ろしい」と述べた。両者はさらに、「今日、学者たちは、マレーが間違っていただけでなく、彼女の基本的な前提のほとんどすべてにおいて、完全に恥ずかしいほど間違っていたことで意見が一致している」と主張した。
イタリアの歴史家カルロ・ジンズブルグは、マレーの理論に「わずかな支持」を与えようとしたとされている。ジンズブルグは、彼女の論文は「完全に非批判的な方法で定式化されており」、「深刻な欠陥」を含んでいるものの、「真実の核」を含んでいると述べた。彼は、ヨーロッパの魔術が「古代の豊穣崇拝に根ざしている」という彼女の主張は正しいという意見を述べ、彼がフリウーリ地方で記録された16世紀から17世紀のベナンダンティという農耕的な幻視の伝統を研究したことで、それが裏付けられたと主張した。しかし、何人かの歴史家や民俗学者は、ジンズブルグの主張はマレーのそれとは大きく異なると指摘している。マレーが、魔女のサバト中に物理的に会合するキリスト教以前の魔女カルトの存在を主張したのに対し、ジンズブルグは、近世に魔術と混同されたヨーロッパの幻視の伝統の一部が、キリスト教以前の豊穣宗教に起源を持つと主張した。さらに、他の歴史家はジンズブルグのベナンダンティの解釈に批判を表明している。コーンは、資料にはベナンダンティが「古くからの豊穣崇拝の生き残り」であるという考えを正当化する「いかなるものも全くない」と述べた。これらの見解に呼応し、ハットンは、ジンズブルグのベナンダンティの幻視の伝統がキリスト教以前の慣習の生き残りであるという主張は、「不完全な資料的および概念的基盤」に基づいているとコメントした。彼は、ジンズブルグの「仮定」である「16世紀に夢見られていたことが、実際には異教時代に宗教儀式として行われていた」という考えは、完全に「彼自身の推論」であり、文書証拠によって裏付けられていないと付け加えた。
4.3. ウィッカおよび現代文化への影響

マレーの魔女カルト理論は、現代の異教の宗教であるウィッカの青写真を提供し、マレーは「ウィッカの祖母」と呼ばれている。異教研究の学者イーサン・ドイル・ホワイトは、この理論が「ウィッカが自らを構築した歴史的物語を形成した」と述べている。なぜなら、1940年代から1950年代にかけてイギリスで出現したウィッカは、この魔女カルトの生き残りであると主張したからである。ウィッカの神学的構造は、角のある神と母なる女神を中心に展開し、マレーの古代魔女カルトに関する思想から採用された。ウィッカのグループは「コヴン」と名付けられ、その集会は「エスバット」と呼ばれたが、これらはいずれもマレーが広めた言葉である。マレーの魔女カルトと同様に、ウィッカの実践者は入会儀式を通じて参加した。魔女が呪文を本に書き留めていたというマレーの主張は、ウィッカの影の書に影響を与えた可能性がある。ウィッカの初期の年の車輪(季節の祭り)の体系も、マレーの枠組みに基づいていた。
マレーの著書が出版される以前にウィッカが存在した証拠がないことを指摘し、メリフィールドは、20世紀のイギリスで独自の魔女のコヴンを形成しようとした人々にとって、「マレーは理想的な妖精のゴッドマザーのように見えたかもしれず、彼女の理論は彼らが切望するファンタジーの領域へと彼らを運ぶカボチャの馬車となった」とコメントした。歴史家のフィリップ・ヘセルトンは、最古とされるウィッカのグループであるニューフォレスト・コヴンが、マレーの理論を知る秘教主義者によって1935年頃に設立され、彼ら自身が魔女カルトのメンバーの転生であると信じていた可能性があると示唆した。ジェラルド・ガードナーは、ニューフォレスト・コヴンのイニシエートであると主張し、ガードナー派ウィッカの伝統を確立し、この宗教を普及させた。シンプソンによれば、ガードナーは英国フォークロア学会のメンバーの中で、マレーの魔女カルト仮説を「心から」受け入れた唯一の人物であった。両者は知り合いであり、マレーはガードナーの1954年の著書『今日の魔術』に序文を寄せたが、その序文で彼女は、ガードナーが自身の魔女カルトの生き残りであるという主張を信じているかどうかを明示的に述べなかった。2005年、ノーブルは「ジェラルド・ガードナーがいなければ、マレーの名前は今日ではほとんど忘れ去られていたかもしれない」と示唆した。
マレーの魔女カルト理論は、1930年から1970年の間にボブ・クレイ=エガートン、ロバート・コクラン、チャールズ・カーデル、ロザリーン・ノートンなどによってイギリスとオーストラリアで確立された非ガードナー派ウィッカの伝統にも中核的な影響を与えた可能性が高い。
著名なウィッカの信者であるドリーン・ヴァリアンテは、イギリス中に残るマレー派魔女カルトの痕跡であると信じるものを熱心に探した。ヴァリアンテは、学術的に否定された後もマレーの魔女カルトを信じ続け、マレーを「注目すべき女性」と評した。
1960年代後半のサンフランシスコでは、エイダン・A・ケリーが自身のウィッカの伝統であるニュー・リフォームド・オーソドックス・オーダー・オブ・ザ・ゴールデン・ドーンを創設する際に、マレーの著作を資料の一つとして使用した。1970年代初頭のロサンゼルスでは、ズザンナ・ブダペストが自身のフェミニスト志向の伝統であるダイアニック・ウィッカを確立する際に、マレーの著作を使用した。マレーの魔女カルト理論は、アメリカのゲイ解放活動家アーサー・エヴァンスが1978年に執筆した著書『魔術とゲイ・カウンターカルチャー』の思想の基礎ともなった。
ウィッカのコミュニティは、魔女カルト理論の学術的否定を徐々に認識するようになった。それに伴い、1980年代から1990年代にかけて、その文字通りの真実性への信仰は低下し、多くのウィッカ信者はそれを比喩的または象徴的な真実を伝える神話と見なすようになった。他の人々は、宗教の歴史的起源は重要ではなく、ウィッカは参加者に与える精神的経験によって正当化されると主張した。これに対し、ハットンはウィッカの初期の発展を探求する歴史的研究である『月の勝利』を執筆した。1999年の出版後、この本はイギリスの異教徒コミュニティに強い影響を与え、ウィッカ信者の間でマレー派理論への信仰をさらに侵食した。逆に、他の実践者はこの理論に固執し、それを重要な信仰箇条として扱い、ヨーロッパ魔術に関するポスト・マレー派の学説を拒絶した。何人かの著名な実践者は、ウィッカが旧石器時代にまで遡る起源を持つ宗教であると主張し続けたが、他の人々は歴史学の妥当性を否定し、真実の判断基準として直感と感情を強調した。「反修正主義者」のウィッカ信者(ドナルド・H・フリュー、ジャニ・ファレル=ロバーツ、ベン・ウィットモアなど)は、細部の問題でポスト・マレー派の学説を攻撃する批判を発表したが、マレーの元の仮説を完全に擁護した者はいなかった。
5. 後期の生活と継続的な活動
マレーは1935年にUCLを退職した後も、研究活動を続け、英国フォークロア学会の会長を歴任し、講演や著作活動を通じて晩年も学術界に貢献し続けた。
1935年のパレスチナ旅行中、彼女は隣接するヨルダンのペトラを訪れる機会を得た。この遺跡に興味を抱いた彼女は、1937年3月と4月に再訪し、遺跡内のいくつかの洞窟住居で小規模な発掘調査を行った。その後、ペトラに関する発掘報告書とガイドブックの両方を執筆した。イギリスに戻ってからは、1934年から1940年にかけてケンブリッジ大学ガートン・カレッジのエジプト古美術品の目録作成を支援し、1942年まで同大学でエジプト学の講義を行った。彼女の民俗学への関心は広範にわたり、エセル・ラドキンの『リンカンシャーの民間伝承』の序文を執筆し、その中で女性が男性よりも優れた民俗学者であると論じた。
第二次世界大戦中、マレーはロンドン大空襲を避けるためケンブリッジに移り住み、戦後の生活に備えて軍人を教育するグループ(おそらく陸軍時事局または王立陸軍教育隊の「ブリティッシュ・ウェイ・アンド・パーパス」)でボランティア活動を行った。ケンブリッジを拠点に、彼女は街の近世史の研究に着手し、地元の教区教会、ダウニング・カレッジ、イーリー大聖堂に保管されている文書を調査したが、その成果を出版することはなかった。1945年には、「ウィッチ・エルムのベラは誰?」殺人事件に一時的に関与した。
戦後、彼女はロンドンに戻り、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)とUCL考古学研究所(当時は独立機関、現在はUCLの一部)に近いエンズレイ・ストリートの下宿に落ち着いた。彼女はUCLとの関わりを続け、考古学研究所の図書館を利用した。ほとんど毎日、大英博物館を訪れて図書館を利用し、週に2回はシティ・リテラリー・インスティテュートで古代エジプト史と宗教に関する成人教育クラスを教えた。この職を退職する際、彼女はかつての教え子であるヴェロニカ・セトン=ウィリアムズを後任に指名した。
マレーは一般大衆へのエジプト学普及への関心を継続した。1949年には、ジョン・マレーの「東洋の知恵」シリーズの2作目となる『古代エジプトの宗教詩』を出版した。同年、彼女はまた、UCLでの多くの講義をまとめた『エジプトの栄光』を出版した。この本は、エジプトがギリシャ・ローマ社会、ひいては現代西洋社会に影響を与えたと主張する文化伝播主義的な視点を取り入れた。これは、ペトリーの他の社会がエジプト文明の出現に影響を与えたという信念と、グラフトン・エリオット・スミスの非常に異端で厳しく批判された過度な文化伝播説(エジプトがすべての世界文明の源であるという見解)との間の妥協点と見なされた。この本は、考古学界から賛否両論の評価を受けた。
1953年、マレーは前会長アラン・ゴムの辞任後、英国フォークロア学会の会長に任命された。学会は当初ジョン・マヴロゴルダートにこの職を打診したが、彼は辞退し、マレーは数か月後に指名を受諾した。マレーは1955年まで2期にわたり会長を務めた。1954年の会長演説「民俗学研究の場としてのイングランド」では、彼女は自国の民俗学に対するイギリス人の無関心を嘆き、他国の民俗学に偏っていると述べた。1961年秋号の『フォークロア』誌では、彼女の98歳の誕生日を記念してマレーへのフェストシュリフトが掲載された。この号には、考古学、妖精、近東の宗教シンボル、ギリシャ民謡などを扱う様々な学者からの寄稿が収められていたが、魔術に関するものは含まれていなかった。これは、他の民俗学者が彼女の魔女カルト理論を擁護しようとしなかったためである可能性がある。
1957年5月、マレーは考古学者T・C・レズブリッジの物議を醸す主張を擁護した。レズブリッジはケンブリッジシャー州ゴーグ・マゴーグ・ヒルズのワンデルベリー・ヒルで3つのキリスト教以前のヒル・フィギュアを発見したと主張した。マレーは個人的にはその図形の真実性について懸念を表明していた。レズブリッジはその後、彼女の魔女カルト理論を擁護する本を執筆し、そのカルトの起源をキリスト教以前の文化に求めた。1960年、彼女は自身の論文コレクション(全国の幅広い個人との書簡を含む)を英国フォークロア学会アーカイブに寄贈し、現在は「マレー・コレクション」として知られている。
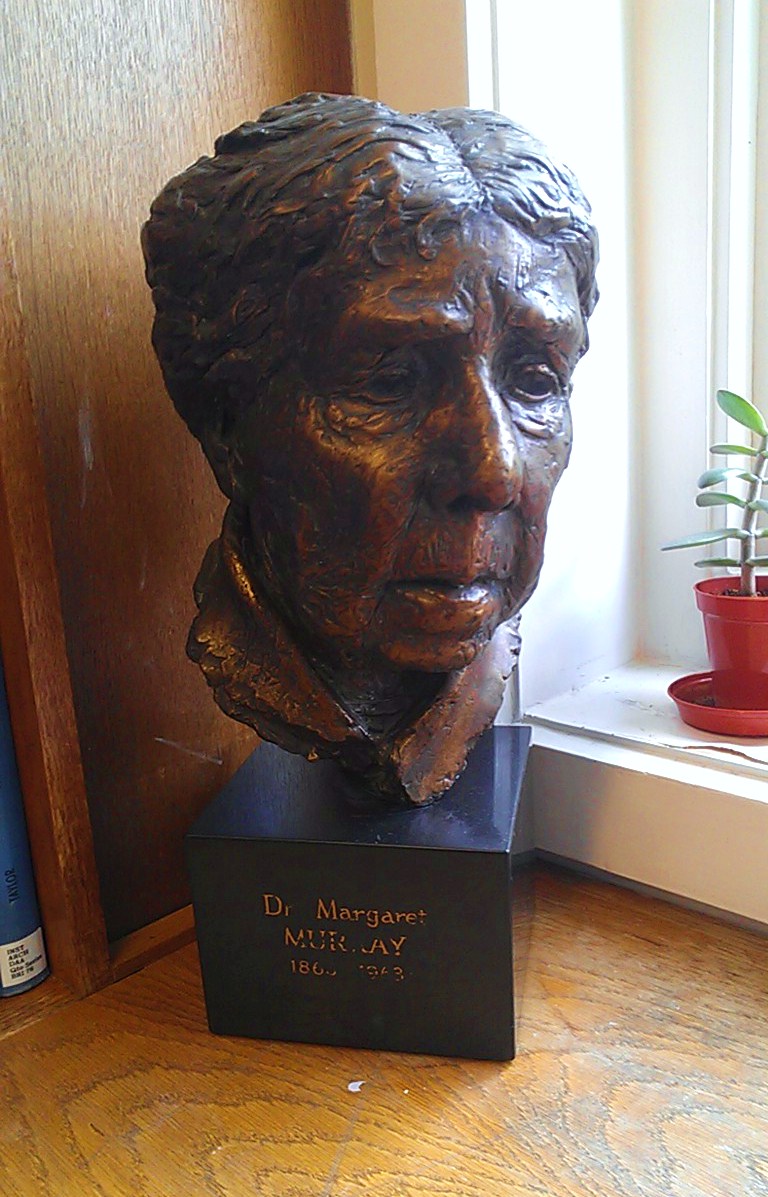
関節炎で体が不自由になったマレーは、北ロンドンのノース・フィンチリーにある自宅に引っ越し、そこで引退した看護師夫婦の介護を受けた。ここから彼女は時折タクシーでロンドン中心部へ向かい、UCL図書館を訪れた。
健康状態が悪化する中、マレーは1962年にハートフォードシャー州ウェルウィンのクイーン・ヴィクトリア記念病院に移り、24時間体制の介護を受けることになった。彼女はここで人生の最後の18か月を過ごした。1963年7月13日、彼女の100歳の誕生日を記念して、友人、元学生、医師のグループが近くのエイオット・セント・ローレンスでパーティーを開いた。2日後、彼女の主治医が彼女をUCLに連れて行き、2度目の誕生日パーティーが開催された。これも多くの友人、同僚、元学生が出席した。これが彼女が大学を訪れた最後の機会となった。王立人類学研究所の雑誌『マン』では、マレーが「生きた記憶の中で、もしその全歴史においてでなければ、研究所のフェローとして唯一[100歳に達した]人物」であると記された。同年、彼女は2冊の著書を出版した。1冊は『宗教の起源』で、人類最初の神々は男性神ではなく女神であったと主張した。もう1冊は自伝『私の最初の100年』で、これは主に肯定的な書評を受けた。彼女は1963年11月13日に死去し、遺体は火葬された。
6. 人生
マレーは生涯独身を貫き、自身の人生を学問に捧げた。この点で、ハットンは彼女を同時代の他の著名なイギリス人女性学者、ジェーン・エレン・ハリソンやジェシー・ウェストンと比較している。マレーの伝記作家キャスリーン・L・シェパードは、彼女が特にエジプト学において一般市民への普及活動に深くコミットしており、「一般市民がエジプトの歴史に関する知識を得る手段を変えたいと願っていた。科学的な研究室の扉を開放し、一般市民を招き入れたいと望んでいた」と述べている。彼女は旅行を最も好きな活動の一つと考えていたが、時間と財政的な制約のため、定期的に行うことはできなかった。彼女の給与は低く、著書からの収入もわずかであった。
母親によって敬虔なキリスト教徒として育てられたマレーは、当初は信仰を説くために日曜学校の教師を務めていた。しかし、学術界に入った後、彼女は宗教を拒絶し、英国フォークロア学会の他のメンバーの間では著名な懐疑主義者であり合理主義者としての評判を得た。彼女は組織化された宗教に対して公然と批判的であったが、何らかの形の神に対する個人的な信念は持ち続けていた。自伝では、「科学が自然と呼び、宗教が神と呼ぶ」ような「目に見えない支配的な力」を信じていると述べている。
彼女はまた、魔術を信じ、実践していた。彼女は、ふさわしいと感じた人物に対して呪いをかけた。あるケースでは、友人のウォルター・ブライアン・エメリーを差し置いてヤロスラフ・チェルニーがエジプト学教授に昇進したことが不当だと感じた際、彼に呪いをかけた。この呪いはフライパンで材料を混ぜるというもので、2人の同僚の立ち会いのもとで行われた。別の例では、第一次世界大戦中にヴィルヘルム2世の蝋人形を作り、それを溶かしたと言われている。ルース・ホワイトハウスは、マレーが自伝でそのような出来事に言及していないことや、彼女の全体的に合理的なアプローチを考慮すると、「呪文の効果に対する真の信念」というよりも「いたずら心」が彼女の魔術の実践の動機であった可能性があると主張している。
7. 遺産と評価
マーガレット・アリス・マレーの遺産は、エジプト学、考古学、民俗学の分野における彼女の業績、女性学者としての地位の変化、そして彼女の理論が社会に与えた複合的な影響を総合的に考察することで、多角的に評価される。
7.1. 学術分野における遺産
ハットンは、マレーが「専門的学術界に深刻な影響を与えた」初期の女性の一人であると述べ、考古学者のネイル・フィネランは彼女を「戦後イギリス考古学界の最も偉大な人物の一人」と評した。彼女の死後、ダニエルは彼女を「エジプト学の偉大な老婦人」と呼び、ハットンはエジプト学が「彼女の学術キャリアの中核」であったと指摘した。2014年、ソーントンは彼女を「イギリスで最も有名なエジプト学者の一人」と称した。
しかし、考古学者のルース・ホワイトハウスによれば、マレーの考古学とエジプト学への貢献は、ペトリーの業績に影を潜め、彼女がしばしば自身の研究者としてではなく、ペトリーの助手の一人として認識されることが多かったため、見過ごされがちであった。彼女が引退する頃には、この分野で高く評価されるようになっていたが、ホワイトハウスによれば、彼女の死後、マレーの評価は低下した。ホワイトハウスはこれを、彼女の魔女カルト理論の否定と、この分野の男性優位の歴史から女性考古学者が一般的に抹消されたことに起因すると考えている。
『フォークロア』誌に掲載されたマレーの死亡記事で、ジェームズは彼女の死が「特に英国フォークロア学会の年譜において、また彼女の影響が多くの方向と分野で感じられたより広い領域において、異例の興味と重要性を持つ出来事であった」と記した。しかし、後の学術的な民俗学者、例えばシンプソンやウッドは、マレーと彼女の魔女カルト理論を彼らの分野、特に英国フォークロア学会にとっての恥辱として挙げている。シンプソンは、マレーの学会会長としての地位が、多くの歴史家が民俗学という学術分野に対して抱く不信感の原因となったと示唆した。彼らは、すべての民俗学者がマレーの考えを支持していると誤解するようになったからである。同様に、キャサリン・ノーブルは「マレーは魔術の研究にかなりの損害を与えた」と述べた。
1935年、UCLはエジプト学の最優秀論文を提出した学生に授与される「マーガレット・マレー賞」を設立し、これは21世紀まで毎年授与され続けている。1969年、UCLは彼女を称えて談話室の一つに彼女の名前を冠したが、1989年にはオフィスに転用された。1983年6月、エリザベス王太后がこの部屋を訪れ、そこでマレーの『私の最初の100年』の複製が贈られた。UCLはまた、マレーの胸像を2つ所蔵しており、1つはペトリー博物館に、もう1つはUCL考古学研究所の図書館に置かれている。この彫刻は彼女の学生の一人であるヴィオレット・マクダーモットの依頼により、芸術家スティーブン・リカードによって制作された。UCLはまた、ウィニフレッド・ブラントンによるマレーの水彩画も所蔵している。これは以前はペトリー・ギャラリーに展示されていたが、後にアートコレクションの収蔵庫に保管された。
2013年、マレーの生誕150周年と没後50周年を記念して、UCL考古学研究所のルース・ホワイトハウスはマレーを「注目すべき女性」であり、その生涯は「考古学界全体、特にUCLにおいて、祝う価値がある」と評した。考古学史家ロザリンド・M・ヤンセンは、彼女のUCLエジプト学部の研究を「マレーへの賛辞として」『最初の100年』と題した。マレーの友人マーガレット・ステファナ・ドロワーは、2004年に出版された編集書『ブレイク・グラウンド:先駆的な女性考古学者たち』の一章として、彼女の短い伝記を執筆した。2013年、レキシントン・ブックスは、当時ミズーリ科学技術大学の助教授であったキャスリーン・L・シェパードが執筆したマレーの伝記『マーガレット・アリス・マレーの生涯:考古学における女性の仕事』を出版した。この本はシェパードのオクラホマ大学での博士論文に基づいている。ある書評家は、この本が「明確で魅力的な方法で書かれている」と特徴づけながらも、シェパードの本がマレーを「科学者」として焦点を当てているため、マレーの魔術の実践やウィッカとの関係については言及が少ないと指摘した。
7.2. 文学および大衆文化における影響
シンプソンは、『ブリタニカ百科事典』にマレーの論文が掲載されたことで、それが「ジャーナリスト、映画制作者、大衆小説家、スリラー作家」にアクセス可能となり、彼らがそれを「熱狂的に」採用したと指摘した。それはオルダス・ハクスリーやロバート・グレーヴスの作品に影響を与えた。マレーの思想は、歴史小説家ローズマリー・サトクリフの作品における異教の描写を形作った。マレーの宗教に関する思想は、もう一人のイギリスの歴史小説家ヘンリー・ツリースのフィクションにも見出すことができる。また、アメリカのホラー作家H・P・ラヴクラフトにも影響を与え、彼は架空のクトゥルフ神話のクトゥルフ崇拝に関する著作で『西ヨーロッパの魔女カルト』を引用した。別のホラー作家デニス・ウィートリーは、マレーの魔術に関する思想を自身の小説『悪魔のいけにえ』に取り入れ、オカルトに関するノンフィクション『悪魔とそのすべての業』でマレーの著作を引用した。
作家シルヴィア・タウンゼント・ワーナーは、1926年の小説『ロリー・ウィローズ』にマレーの魔女カルトに関する著作が影響を与えたと述べ、感謝の意を込めてマレーに自身の本のコピーを送り、その後すぐに2人は昼食を共にした。しかし、魔女カルトの描写にはいくつかの違いがあった。マレーが組織化されたキリスト教以前のカルトを描写したのに対し、ワーナーは漠然とした家族の伝統を描写し、それは明確に悪魔崇拝的であった。
1927年、ワーナーは魔術に関する講演を行い、マレーの著作からの強い影響を示した。マレーとワーナーの関係を分析したイギリス文学の学者ミミ・ウィニックは、両者が「近代における女性の新たな可能性を想像することに携わっていた」と特徴づけた。ファンタジー小説『ランマス・ナイト』は、王室の役割という同じアイデアに基づいている。
8. 著作目録
マーガレット・アリス・マレーが出版した主要な著作と論文のリストを出版年順に整理し、彼女の学術的生産性を示す。彼女の著作目録は、1961年にウィルフレッド・ボンザーによって『フォークロア』誌に掲載され、友人のドロワーも2004年に限定的な死後著作目録を作成した。また、キャスリーン・L・シェパードによる2013年の伝記にも限定的な著作目録が掲載されている。
| 出版年 | 題名 | 共著者 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 1903 | 『エジプト古美術品コレクションガイド』 | - | エディンバラ科学芸術博物館(エディンバラ) |
| 1904 | 『アビドスにおけるオシレイオン』 | - | エジプト調査記録(ロンドン) |
| 1905 | 『サッカラ・マスタバス』パートI; パートII | クルト・セテによる章を含む | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1905 | 『サッカラ・マスタバス パートIとグロブ』 | 『グロブ』はL. ロアト著 | エジプト調査記録(ロンドン) |
| 1905 | 『初級エジプト語文法』 | - | ユニヴァーシティ・カレッジ・プレス(ロンドン) |
| 1908 | 『古王国時代の名前と称号の索引』 | - | 英国エジプト考古学学校(ロンドン) |
| 1910 | 『二人の兄弟の墓』 | - | シェラット&ヒューズ(マンチェスター) |
| 1911 | 『初級コプト語(サヒド語)文法』(第2版1927年) | - | ユニヴァーシティ・カレッジ・プレス(ロンドン) |
| 1913 | 『古代エジプトの伝説』 | - | ジョン・マレー(ロンドン);東洋の知恵シリーズ |
| 1921 | 『西ヨーロッパの魔女カルト:人類学の研究』 | - | オックスフォード大学出版局(オックスフォード) |
| 1923 | 『マルタの発掘調査、パートI』 | - | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1925 | 『マルタの発掘調査、パートII』 | - | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1929 | 『マルタの発掘調査、パートIII』 | - | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1930 | 『エジプト彫刻』 | - | ダックワース(ロンドン) |
| 1931 | 『エジプト神殿』 | - | サンプソン・ロウ、マーストン&カンパニー(ロンドン) |
| 1931 | 『魔女の神』(1960年版) | - | フェイバー&フェイバー(ロンドン) |
| 1932 | 『マルタの民話』 | L. ガレア | エンパイア・プレス(マルタ) |
| 1933 | 『コプト語読本、初心者向け用語集付き』 | ドロシー・ピルチャー | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1934 | 『メノルカにおけるケンブリッジ発掘調査、サ・トレタ』 | - | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1934 | 『マルタの青銅器時代陶器のコーパス』 | ホレス・ベックとテモスティクレス・ザミット | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1937 | 『サッカラ・マスタバス パートII』 | - | エジプト調査記録(ロンドン) |
| 1938 | 『メノルカにおけるケンブリッジ発掘調査、トラプコ』 | - | バーナード・クアリッチ(ロンドン) |
| 1939 | 『ペトラ、エドムの岩の都市』 | - | ブラッキー |
| 1940 | 『ペトラの通り』 | J. C. エリス | 英国エジプト考古学学校とバーナード・クアリッチ |
| 1949 | 『古代エジプトの宗教詩』 | - | ジョン・マレー(ロンドン) |
| 1949 | 『エジプトの栄光:エジプト文化と文明の概観』 | - | フィロソフィカル・ライブラリー(ロンドン) |
| 1954 | 『イングランドの神聖王。人類学の研究』 | - | フェイバー&フェイバー(ロンドン) |
| 1963 | 『私の最初の100年』 | - | ウィリアム・キンバー&カンパニー(ロンドン) |
| 1963 | 『宗教の起源』 | - | キーガン・ポール(ロンドン) |