1. 概要

ユルゲン・ハーバーマス(Jürgen Habermasドイツ語)は、批判理論とプラグマティズムの伝統を受け継ぐドイツの哲学者、社会学者、心理学者、そしてジャーナリストとしても知られる人物です。彼はフランクフルト学派の第二世代に位置し、マックス・ホルクハイマーやテオドール・アドルノ、ヘルベルト・マルクーゼら先達の批判理論が到達した悲観的な状況を克服し、新たなパラダイムを導入することでこの理論を再活性化させました。
ハーバーマスの主要な功績は、「コミュニケーション的合理性」(または「コミュニケーション的理性」)の概念とその理論を確立したことにあります。これは、合理性を宇宙の構造ではなく、対人関係における言語的コミュニケーションの構造の中に位置づける点で、従来の合理主義の伝統とは一線を画します。彼の社会理論は、人間の解放という目標を推進しつつ、包括的な普遍主義的道徳的枠組みを維持しています。この枠組みは、すべての言語行為には相互理解という固有の「τέλος目的古代ギリシア語」が内在しており、人間はそのような理解を達成するコミュニケーション能力を持っているという「普遍的語用論」の主張に基づいています。
彼は公共圏理論、討議民主主義、そして近代性に関する議論で特に知られています。彼の理論体系は、現代の制度や、人間が熟慮し合理的な利益を追求する能力の中に潜在する、理性、解放、そして合理的・批判的なコミュニケーションの可能性を明らかにすることに捧げられています。また、マックス・ウェーバーが提唱した合理化に関する議論、特にその再解釈を通じて、近代という現象を深く探求しました。
ハーバーマスは、ドイツの政治や国際社会の主要な問題に積極的に関与し、公共的知識人としての重要な役割を果たしてきました。彼はナチス時代の歴史解釈を巡る「歴史家論争」において「憲法パトリオティズム」を提唱し、コソボ紛争やイラク戦争、イスラエル・ハマス戦争などに対する見解を表明しました。彼の思想は、民主主義、人権、社会進歩の尊重を重視する中道左派的な視点に深く根ざしており、権威主義体制に対する批判的な姿勢も明確に示しています。
2. 生涯
2.1. 幼少期と教育
ユルゲン・ハーバーマスは1929年6月18日、ドイツノルトライン=ヴェストファーレン州デュッセルドルフに生まれました。父はエルンスト、母はグレーテです。彼は先天性の口唇口蓋裂を持って生まれ、幼少期に2度の矯正手術を受けました。ハーバーマス自身は、この言語障害が彼に相互依存とコミュニケーションの重要性について深く考えさせるきっかけとなったと語っています。
彼はケルン近郊のグマースバッハで育ちました。父エルンストはケルン商工会議所の専務理事を務めており、ハーバーマスは父をナチス党の同調者であり、1933年以降は国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の党員であったと述べています。ユルゲン自身もドイツ少年団(ヒトラーユーゲントの一部門)の少年指導者(Jungvolkführerドイツ語)を務めました。彼が青年期に差し掛かる第二次世界大戦末期に、アドルフ・ヒトラー率いるナチス体制の犯罪性が明らかになるにつれて、彼とドイツ国民は深く影響を受けました。この経験が、ハーバーマスの民主主義の重要性についての思考を形成する一因となった可能性が指摘されています。彼は敬虔なプロテスタントの家庭で育ち、祖父はグマースバッハの神学校の校長を務めていました。
1945年のドイツ敗戦後、彼はギムナジウムでの学業を再開しました。アメリカ占領下で受けた民主主義教育は、彼の思想形成に大きな影響を与えました。彼はゲッティンゲン大学(1949年-1950年)、チューリッヒ大学(1950年-1951年)、ボン大学(1951年-1954年)で学び、哲学、歴史学、心理学、ドイツ文学、経済学などを専攻しました。特に新カント派、現象学、哲学的人間学の影響を受けました。1952年からはフランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング紙などに書評や批評を寄稿し始め、1953年には同紙に「ハイデッガーと共にハイデッガーに反対して考える」という論文を寄稿し、ハイデッガーを批判しました。1954年にはフリードリヒ・シェリングの思想における「絶対と歴史」の対立に関する論文「Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denkenドイツ語」(「絶対と歴史:シェリングの思想における二重性について」)でボン大学から哲学の博士号を取得しました。彼の博士論文の指導委員にはエーリッヒ・ロータッカーとオスカー・ベッカーが含まれていました。
2.2. 学術的経歴
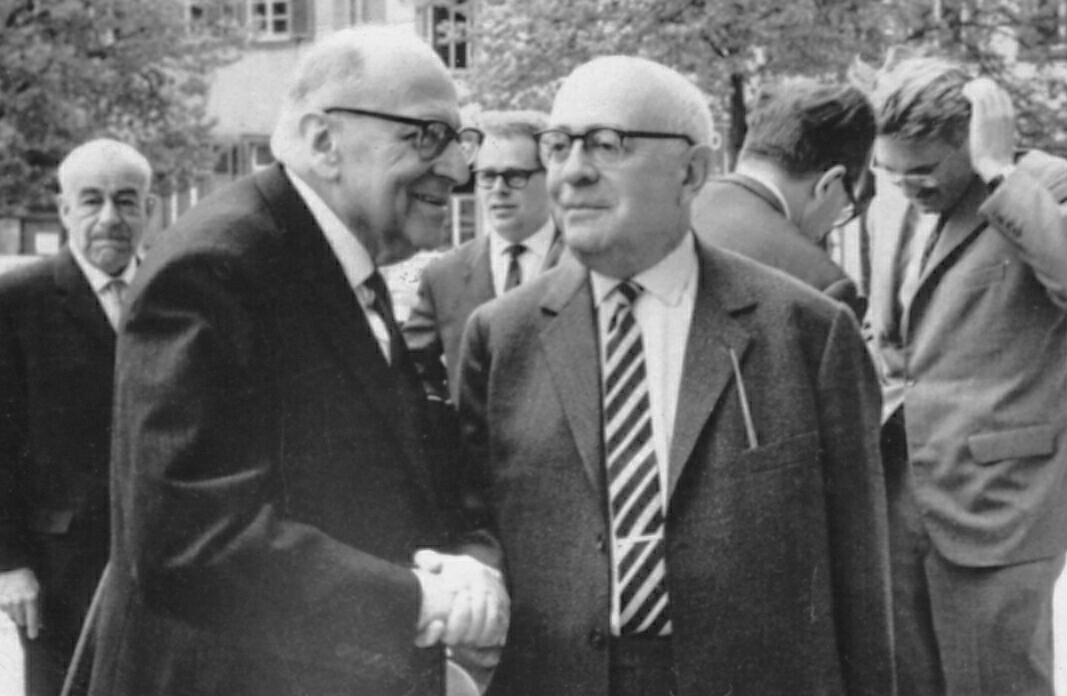
1956年から、彼はフランクフルト大学の社会研究所で、マックス・ホルクハイマーとテオドール・アドルノという批判理論家の下で哲学と社会学を学びました。しかし、ハーバーマスは、ホルクハイマーが論文改訂に受け入れがたい要求を出したこと、またフランクフルト学派が政治的懐疑主義と近代文化への軽蔑により麻痺しているという自身の信念から、両者間に溝が生じました。その結果、彼はマルクス主義者のヴォルフガング・アーベンドロートの指導の下、マールブルク大学で政治学の教授資格を取得しました。
彼の教授資格取得論文は「Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaftドイツ語」(『公共性の構造転換:ブルジョワ社会の一カテゴリーに関する探求』)と題され、18世紀のサロンから資本主義的マスメディアの影響による変容まで、ブルジョワ公共圏の発展に関する詳細な社会史が描かれています。1961年にはマールブルク大学の私講師(Privatdozentドイツ語)となり、1962年にはハンス・ゲオルク・ガダマーとカール・レーヴィットの働きかけにより、当時のドイツの学術界では異例のことながら、ハイデルベルク大学の哲学「員外教授」(無給教授)の職を打診され、これを受諾しました。同年、彼の教授資格取得論文の出版により、ドイツ国内で初めて本格的な注目を集めました。1964年には、アドルノの強力な支持を受けて、ホルクハイマーがフランクフルト大学を退任した哲学部・社会学部の講座を引き継ぐため、フランクフルト大学に戻りました。哲学者アルブレヒト・ヴェルマーは1966年から1970年までフランクフルトで彼の助手を務めました。
1971年に彼はミュンヘン近郊のシュタルンベルクにあるマックス・プランク研究所の「科学技術世界生活条件研究のためのマックス・プランク研究所」所長に就任し、1983年までその職を務めました。これは彼の最高傑作とされる『コミュニケーション的行為の理論』の出版から2年後のことでした。1984年にはアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選出されました。
1983年に彼はフランクフルト大学の教授職と社会研究所の所長職に復帰しました。1993年にフランクフルト大学を退職して以降も、ハーバーマスは活発な執筆活動を続けています。1986年には、ドイツの研究における最高の栄誉であるドイツ研究振興協会のゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ賞を受賞しました。彼はまた、イリノイ州エバンストンのノースウェスタン大学で「常任客員教授」の職を、ニューヨーク市のニュースクール大学で「テオドール・ホイス教授」の職を務めました。
ハーバーマスは2003年にアストゥリアス皇太子賞社会科学部門を、2004年には京都賞思想・芸術部門を受賞しました(5000.00 万 JPY)。2005年3月5日には、サンディエゴ大学の京都シンポジウムの一環として、「世俗的文脈における宗教の公共的役割」と題する講演を行い、政教分離が中立主義から徹底した世俗主義へと進化する過程について論じました。2005年にはホルベア国際記念賞(約52.00 万 EUR)を受賞しました。2007年には『タイムズ・ハイアー・エデュケーション』誌の人文科学分野(社会科学を含む)で、マックス・ウェーバーを上回り、アーヴィング・ゴッフマンに次いで7番目に引用された著者にリストされました。計量書誌学的研究は、彼の継続的な影響力と重要性の増大を示しています。
ユルゲン・ハーバーマスは、ドイツの社会文化史の研究者であり、ゲッティンゲン大学の近代史教授であったレベッカ・ハーバーマス(1959年-2023年)の父でもあります。
2.3. 思想的継承と教育者としての役割
ハーバーマスは、その学術的な生涯において、数多くの知的伝統から影響を受け、独自の包括的な哲学的・社会理論的枠組みを構築しました。彼に影響を与えた主な思想家や学派は以下の通りです。
- ドイツ哲学**: イマヌエル・カント、フリードリヒ・シェリング、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、ヴィルヘルム・ディルタイ、エドムント・フッサール、ハンス・ゲオルク・ガダマーらから、認識論、現象学、解釈学的洞察を得ました。
- マルクス主義**: カール・マルクス自身の理論に加え、マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノ、ヘルベルト・マルクーゼらフランクフルト学派の批判的な新マルクス主義理論から、社会批判の伝統を継承しました。
- 社会学**: マックス・ウェーバー、エミール・デュルケーム、ジョージ・ハーバート・ミードの社会学理論は、彼の社会システムと相互作用に関する理解の基礎となりました。
- 言語哲学と言語行為論**: ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン、J. L. オースティン、P. F. ストローソン、スティーヴン・トゥールミン、ジョン・サールらの思想は、彼のコミュニケーション理論の根幹をなす「普遍的語用論」の発展に不可欠でした。
- 発達心理学**: ジャン・ピアジェとローレンス・コールバーグの発達心理学は、彼の道徳的発展と理性の概念に影響を与えました。
- アメリカプラグマティズム**: チャールズ・サンダース・パースやジョン・デューイらのプラグマティズムは、彼の実践的思考と社会的行動理論に深く影響を与えました。
- 社会システム理論**: タルコット・パーソンズとニクラス・ルーマンの社会システム理論は、彼が近代社会の合理化と生活世界の「システムによる植民地化」を分析する上で重要な参照点となりました。
- 新カント主義**: 認識論的基礎付けと普遍主義的規範論の探求において、新カント主義の伝統も彼に影響を与えています。
ハーバーマスは著名な教師であり、指導者でもありました。彼の最も著名な教え子には、談話の区別と合理性の理論家であるプラグマティズム哲学者ヘルベルト・シュネーデルバッハ、ベルリンのヘルティー・スクール・オブ・ガバナンス教授である政治社会学者クラウス・オッフェ、ラ・トローブ大学教授でジャーナル『テーゼ・イレブン』の主編集者である社会哲学者ヨハン・アーナソン、北フロリダ大学哲学講座教授の社会哲学者ハンス=ヘルベルト・ケーグラー、エアフルト大学およびシカゴ大学教授の社会学者ハンス・ヨアス、社会進化論理論家クラウス・エーダー、社会哲学者アクセル・ホネット、ボストンカレッジ教授でジャーナル『哲学と社会批評』の主編集者である政治理論家デビッド・ラスムッセン、環境倫理学者コンラート・オット、ハーバーマス思想の多くを後に拒否したアナキズム・資本主義哲学者ハンス=ヘルマン・ホッペ、アメリカの哲学者トーマス・A・マッカーシー、社会研究におけるマインドフルネスな探求の共同創始者ジェレミー・J・シャピロ、ノースウェスタン大学哲学教授の政治哲学者クリスティーナ・ラフォン、そして暗殺されたセルビア首相ゾラン・ジンジッチなどがいます。
3. 哲学と社会理論
3.1. 思想的背景と影響
ハーバーマスは、イマヌエル・カント、カール・マルクス、マックス・ウェーバー、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインといった多岐にわたる思想家や学派から影響を受け、独自の哲学的な発展を遂げました。彼はカントから理性の自律性と普遍主義の概念を、マルクスからは社会批判と解放の思想を継承しました。しかし、彼はマルクスの経済主義的決定論を批判し、経済システムの自律性への過度な依存を疑問視しました。
マックス・ウェーバーの合理化論は、ハーバーマスの思想に大きな影響を与えましたが、彼はウェーバーが強調した目的合理性が、本来人間の自由と幸福に貢献するはずの理性が、逆に「鉄の檻」のように人間を拘束する逆説的な状況を生み出したと指摘しました。これに対し、ハーバーマスはウェーバーの悲観主義を克服し、近代的な理性の潜在力を「未完の近代」として再評価しようと試みました。
また、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインらの言語哲学と言語行為論は、彼の「コミュニケーション的行為論」の基礎を築きました。彼は、言語を通じて人々が相互理解を追求する過程こそが、理性の真の姿であり、社会の民主化と人間化を可能にすると考えました。
彼はフランクフルト学派の批判理論を継承しつつも、彼らの悲観主義や全体主義的傾向を克服しようと努めました。彼らは近代社会における理性の道具化と文化産業による支配を強く批判しましたが、ハーバーマスは彼らの分析が目的合理性に偏りすぎ、生活世界におけるコミュニケーション的な合理化の潜在力を十分に認識していなかったと指摘しました。彼はアメリカのプラグマティズム、行為論、そしてポスト構造主義からも影響を受けつつ、独自の視点から近代社会の認識論的、社会理論的基礎付けを追求しました。
3.2. コミュニケーション的行為論
コミュニケーション的行為論は、ハーバーマス思想の核心をなす概念であり、「コミュニケーション的理性」または「コミュニケーション的合理性」と呼ばれます。これは、理性を人間の言語的コミュニケーションの構造の中に位置づけることで、従来の合理主義の伝統と一線を画しています。この理論は、人間の解放という目的を推進しつつ、包括的な普遍主義的道徳的枠組みを維持しています。
この枠組みは「普遍的語用論」という主張に基づいており、すべての言語行為には「τέλος目的古代ギリシア語」(ギリシア語で「目的」の意)である相互理解という内在する目標があり、人間はそのような理解をもたらすコミュニケーション能力を持っているとします。ハーバーマスは、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン、J. L. オースティン、ジョン・サールの言語行為哲学、ジョージ・ハーバート・ミードの精神と自己の相互作用的構成に関する社会学的理論、ジャン・ピアジェとローレンス・コールバーグの道徳発達理論、そしてフランクフルト学派の同僚であるカール=オットー・アーペルの討議倫理学からこの枠組みを構築しました。
ハーバーマスの著作は、カントと啓蒙主義、そして民主社会主義の伝統と共鳴しています。彼は、理性の人間的潜在力、特に討議倫理学を通じて、世界を変革し、より人道的で公正かつ平等な社会を実現する可能性を強調します。ハーバーマスは、啓蒙主義が「未完のプロジェクト」であると述べていますが、それは破棄されるべきではなく、修正され補完されるべきだと主張しています。この点において、彼はフランクフルト学派の過度な悲観主義や政治的過激主義、誇張を批判し、ポストモダニズムの多くの思想からも距離を置いています。
社会学において、ハーバーマスの主要な貢献は、コミュニケーション的合理性と合理化、そして戦略的・道具的合理性と合理化の違いに焦点を当てた包括的な社会進化と近代化の理論を構築したことです。これには、タルコット・パーソンズの教え子であるニクラス・ルーマンが展開した差異化に基づく社会システム理論に対するコミュニケーション的視点からの批判も含まれます。
彼の近代と市民社会の擁護は、他の思想家たちに影響を与え、ポスト構造主義の多様な形態に対する主要な哲学的代替案と見なされています。彼はまた、後期資本主義に関する影響力のある分析も提供しました。
ハーバーマスは、社会の合理化、人間化、民主化を、人類に固有のコミュニケーション能力に内在する合理性の潜在力の制度化という観点から捉えています。ハーバーマスは、コミュニケーション能力は進化の過程で発展してきたものの、現代社会においては、市場、国家、組織といった社会生活の主要な領域が戦略的・道具的合理性に支配され、システムの論理が生活世界の論理に取って代わることで、しばしば抑制されたり弱められたりしていると主張します。
3.3. 公共圏理論
ハーバーマスは、主著『公共性の構造転換』において、18世紀以前のヨーロッパ文化は「表象的」文化によって支配されていたと論じています。この文化では、ある勢力が聴衆に圧倒的な力を見せつけることで自己を「表象」しようとしました。例えば、フランス国王ルイ14世のヴェルサイユ宮殿は、来訪者の感覚を圧倒することで、フランス国家と国王の偉大さを示すことを意図していたとハーバーマスは主張しました。
ハーバーマスは「表象的」文化をマルクス主義的理論における封建制の発展段階に対応するものと見なし、資本主義の発展段階の到来が「Öffentlichkeitドイツ語」(公共圏)の出現を特徴づけたと論じました。「Öffentlichkeitドイツ語」に特徴づけられる文化においては、国家の管理外に公共空間が出現し、個人が意見や知識を交換しました。
ハーバーマスの見解では、18世紀ヨーロッパにおける新聞、文芸雑誌、読書会、フリーメイソンのロッジ、コーヒーハウスの増加は、それぞれ異なる形で「表象的」文化が「Öffentlichkeitドイツ語」文化に徐々に取って代わられていくことを示しました。ハーバーマスは、「Öffentlichkeitドイツ語」文化の本質的な特徴はその「批判的」性質にあると主張しました。一方的な勢力が活動し、他方が受動的であった「表象的」文化とは異なり、「Öffentlichkeitドイツ語」文化は、個人が会話で会うか、印刷媒体を通じて意見を交換するかによって、対話によって特徴づけられました。ハーバーマスは、イギリスがヨーロッパで最も自由主義的な国であったため、公共圏の文化は1700年頃に最初にそこで出現し、「Öffentlichkeitドイツ語」文化の成長は18世紀のほとんどの期間にわたって大陸ヨーロッパで起こったと主張しています。彼の見解では、フランス革命は「表象的」文化の崩壊と、それに代わる「Öffentlichkeitドイツ語」文化の出現が大きな原因でした。
しかし、ハーバーマスによれば、様々な要因が最終的に公共圏の衰退をもたらしました。その要因には、商業的なマスメディアの成長があり、それが批判的な公共を受動的な消費者の公共へと変えました。また、福祉国家は国家と社会を徹底的に統合し、公共圏を締め出しました。公共圏はまた、公共精神に基づく合理的合意の形成の場ではなく、国家の資源をめぐって自己利益が対立する場へと変質しました。
彼は、代表制民主主義に依存する国民国家が、市民の平等な権利と義務に基づく討議民主主義に依存する政治的有機体へと置き換わる未来に、公共圏の復活の可能性を見出しています。このような直接民主主義主導のシステムにおいては、公共的論点の議論のために活動的な公共圏が必要とされ、その議論が意思決定プロセスに影響を与えるメカニズムも必要とされます。
インドネシア語の資料では、公共圏は「民主的空間」または「社会の談話の場」として、市民が意見、利害、欲求を談話的に表明できる場と説明されています。これは民主主義において不可欠な要素であり、市民が政治的な不安をコミュニケーションする場、そして国家や政府に対して自由に態度や主張を表明できる場であるとされます。公共圏は単なる物理的な制度や組織ではなく、市民同士のコミュニケーションそのものであり、自由で開かれた、透明性があり、政府の介入がなく、誰でもアクセスできる必要があります。このような公共圏から、市民社会の連帯の力が結集され、市場や資本主義のメカニズム、政治のメカニズムに対抗できるとハーバーマスは考えます。
ハーバーマスは公共圏をいくつかの領域に区分しています。これには、多元性(家族、非公式な集団、任意団体など)、公共性(マスメディア、文化的機関など)、私的領域(個人の発達と道徳の領域)、そして合法性(一般的な法構造と基本的人権)が含まれます。したがって、公共圏は一つだけでなく、市民社会の中に多数存在すると考えられます。公共圏は市場や政治の利害に縛られず、どこにでも存在し、制限されないものです。
3.4. 批判理論と近代性
ハーバーマスはフランクフルト学派の批判理論を継承しつつも、彼らの悲観主義を克服しようと試みました。彼は、近代が「未完のプロジェクト」であるという概念を通じて、近代理性の潜在力を強調します。ハーバーマスは、啓蒙主義が「未完のプロジェクト」であると述べていますが、それは破棄されるべきではなく、修正され補完されるべきだと主張しています。この点において、彼はフランクフルト学派、そして多くのポストモダニズム思想の過度な悲観主義、政治的過激主義、誇張を批判し、距離を置いています。
社会学において、ハーバーマスの主要な貢献は、コミュニケーション的合理性と合理化、そして戦略的・道具的合理性と合理化の違いに焦点を当てた包括的な社会進化と近代化の理論を構築したことです。彼は、タルコット・パーソンズの教え子であるニクラス・ルーマンが展開した差異化に基づく社会システム理論を、コミュニケーション的視点から批判しました。
彼の近代と市民社会の擁護は、他の思想家たちに影響を与え、ポスト構造主義の多様な形態に対する主要な哲学的代替案と見なされています。彼はまた、後期資本主義に関する影響力のある分析も提供しました。
ハーバーマスは、社会の合理化、人間化、民主化を、人類に固有のコミュニケーション能力に内在する合理性の潜在力の制度化という観点から捉えています。ハーバーマスは、コミュニケーション能力は進化の過程で発展してきたものの、現代社会においては、市場、国家、組織といった社会生活の主要な領域が戦略的・道具的合理性に支配され、システムの論理が生活世界の論理に取って代わることで、しばしば抑制されたり弱められたりしていると主張します。
ハーバーマスは、現代社会では科学技術が個人の思想とは関係なく客観的に体系化されており、目的合理性において科学技術の体系は絶対的な根拠を持っているとしました。ゆえにあらゆる政治行為の価値はまず目的合理性において科学的あるいは技術的に正当なものであるかどうかの判断抜きには成立せず、イデオロギーが何らかの制度を社会に確立するときに目的合理性に合致しているかどうかということは大きな影響を持つとされました。ときにはこのような目的合理性がそれ自体で支配的な観念となり、人間疎外をもたらすと指摘しました。すなわちこのような目的合理性が支配的な社会では、文化的人間性は否定され、人間行動は目的合理性に適合的なように物象化されていくと警告したのです。
3.5. 再構成的科学
ハーバーマスは「再構成的科学」という概念を、哲学と社会科学の間に「一般社会理論」を位置づけ、さらに「大理論」と「経験的研究」の間の断絶を再構築するという二重の目的を持って導入しました。
「合理的再構成」のモデルは、「生活世界」(文化、社会、人格)の「構造」とそのそれぞれの「機能」(文化的再生産、社会的統合、社会化)に関する調査の主軸をなします。この目的のために、「すべての生活世界に下位する構造」(「内的関係」)の「象徴的表象」と、その複合体における社会システムの「物質的再生産」(社会システムと環境間の「外的関係」)との間の弁証法を考慮する必要があります。
このモデルは、とりわけ「社会進化論」に応用されています。これは、社会文化的生命形態の系統発生(「人間化」)に必要な条件の再構成から始まり、ハーバーマスが原始的、伝統的、近代的、現代的な形態に細分化した「社会形成」の発展の分析に至るものです。
ハーバーマスは、「生活世界と社会システム(そしてその内部では、「生活世界の合理化」と「社会システムの複雑性の増大」)の分化を通じてハーバーマスがまとめた「社会形成」の「発展の論理の再構築」のモデルを形式化しようと試みています。さらに、彼は「歴史的プロセス」の「ダイナミクスの解釈」と、とりわけ進化論の命題の「理論的意味」に関する方法論的な明確化を提供しようとしています。ドイツの社会学者は、「事後的な合理的再構成」と「システム/環境モデル」が完全な「歴史学的応用」を持つことはできないと考えていますが、これらは確かに「歴史的説明」の議論構造における一般的な前提として機能します。
3.6. 討議民主主義
ハーバーマスが展開した討議民主主義の概念は、彼のコミュニケーション理論の応用として位置づけられます。この概念は、ラテン語の「deliberatioラテン語」(熟慮、検討、討議)に由来し、政治における「合議」を意味します。討議民主主義という用語は、民主主義の概念に特有の意味を与え、実践的な談話、政治的意見と願望の形成、そして人民主権を手続きとして含意します。
討議民主主義理論は、市民を規制する特定の規則に焦点を当てるのではなく、それらの規則を生み出す手続きに焦点を当てます。この理論は、政治的決定がどのように下されるべきか、そして市民がそれらの規則に従うような方法で規則がどのような条件の下で生み出されるべきかを理解するのに役立ちます。言い換えれば、討議民主主義は、それらの集団的決定の妥当性に関心を抱きます。間接的に、この文脈における世論は、市民が従うことになる決定を主張することができます。
討議民主主義においては、人民主権が多数決の決定を抑制する役割を果たすことができます。市民は、権限を持つ人々によって下された決定を批判することができます。政府によって出された政策を批判する勇気を持つならば、間接的に、私たちはもはや非合理的な社会ではなく、合理的な社会の一員となっているのです。世論や願望は、形式的な政治や政治的決定をコントロールする機能を持ちます。合法的な政策を批判する勇気を持つならば、間接的に、私たちはすでにシステムに従っていることになります。
また、討議民主主義における「理想的な発話状況」(ideal speech situation英語)という概念は、参加者が談話において同等の能力を持ち、社会的平等が保証され、彼らの発言がイデオロギーやその他の誤りによって歪められないことを要求します。この真理の合意説のバージョンにおいて、ハーバーマスは、真理とは理想的な発話状況において合意されるであろうものであると主張します。
4. 主要な論争と社会への関与
ハーバーマスは著名な公共的知識人としても知られ、その学術活動だけでなく、当時の政治や社会問題に対する積極的な介入でも注目されました。
4.1. 主要な哲学者との論争
ハーバーマスは、数多くの主要な哲学者との論争に参加し、自身の思想を深化させ、発展させてきました。
4.1.1. 実証主義論争
実証主義論争は、1961年に批判的合理主義者(カール・ポパー、ハンス・アルバート)とフランクフルト学派(テオドール・アドルノ、ユルゲン・ハーバーマス)の間で繰り広げられた、社会科学の方法論を巡る政治的・哲学的な論争です。これは1961年から1969年にかけてドイツ社会学界全体における幅広い議論へと発展しました。ハーバーマスはこの論争において、実証主義が事実の客観的記述に終始し、社会の構造的な問題やイデオロギーを批判的に分析する能力に欠けていると指摘し、批判理論の立場を擁護しました。
4.1.2. ハーバーマスとガダマー
ハンス・ゲオルク・ガダマーとの間には、解釈学の限界を巡る論争が存在します。ガダマーは1960年に主著『真理と方法』を完成させ、社会を批判するための真に客観的な立場を見出すために、歴史と文化を超越することの可能性についてハーバーマスと議論を交わしました。
1960年代、ガダマーはハーバーマスを支持し、ホルクハイマーの反対にもかかわらず、彼が教授資格を取得する前にハイデルベルクでの職を提供されるよう働きかけました。両者はともに実証主義を批判しましたが、1970年代に哲学的対立が生じました。この対立はガダマーの哲学的影響力の範囲を広げました。両者の間には、解釈学的伝統から出発し、ギリシアの実践哲学に回帰するといった根本的な合意があるにもかかわらず、ハーバーマスはガダマーの伝統と偏見への強調が、権力のイデオロギー的作動を見えなくしていると主張しました。ハーバーマスは、ガダマーのアプローチが社会におけるイデオロギーの源泉に対する批判的反省を可能にしないと信じました。彼はガダマーが伝統に対して教条的な態度を支持していると非難し、それが理解の歪みを特定することを困難にしていると指摘しました。これに対し、ガダマーは、解釈学の普遍的な性質を拒否することこそが、主体が過去から自由になれるという欺瞞を肯定するため、より教条的な態度であると反論しました。
4.1.3. ハーバーマスとフーコー
ミシェル・フーコーの「権力分析」と「系譜学」の思想、またはユルゲン・ハーバーマスの「コミュニケーション的合理性」と「談話倫理学」の思想のどちらが、社会における権力の性質に対するより良い批判を提供するのかを巡る論争が存在します。この論争は、権力、理性、倫理、近代、民主主義、市民社会、そして社会行為に関する問いに関連する、ハーバーマスとフーコーの中心的な思想を比較し、評価するものです。ハーバーマスは、権力がコミュニケーションを歪め、支配をもたらすものと捉えるのに対し、フーコーは権力が遍在的であり、知識と絡み合って主体を形成すると考えます。
4.1.4. ハーバーマスとアーペル
ハーバーマスとカール=オットー・アーペルはともに、ポスト形而上学的な普遍的道徳理論を支持していますが、この原理の性質と正当化について意見が異なります。ハーバーマスは、原理が人間活動の超越論的条件であるというアーペルの見解に反対していますが、アーペルはそれを主張します。彼らは互いの立場を批判し合います。ハーバーマスは、アーペルが超越論的条件に過度に関心を抱いていると主張し、アーペルは、ハーバーマスが批判的談話を十分に評価していないと主張します。
4.1.5. ハーバーマスとロールズ
ジョン・ロールズとの間にも論争が存在します。この論争は、政治哲学の目標が現代の自由民主主義の規範的な基盤を明らかにすることであるとすれば、文化的多元主義の条件下でどのように政治哲学を行うべきかという問いに焦点を当てています。ハーバーマスは、ロールズの視点が人民主権の思想と矛盾していると信じる一方で、ロールズは政治的正当性は健全な道徳的推論の問題である、あるいはハーバーマスの理論では民主的意志形成が不当に格下げされていると主張します。ロールズが『政治的リベラリズム』(1993年)を出版すると、ハーバーマスは『ジャーナル・オブ・フィロソフィー』誌に「理性の公共的使用による宥和」と題する論文を寄稿し、ロールズが「原初状態」という実体的な概念を用いて近代的理性の普遍性を導き出す方法論には難点があると批判し、むしろ理性の公共的使用という手続き的な概念による代替案を提示しました。
4.1.6. ハーバーマスとデリダ
ハーバーマスとジャック・デリダは、1980年代に始まった一連の論争に関与し、1990年代後半には相互理解と友情が深まり、2004年のデリダの死まで続きました。彼らは元々、ハーバーマスが1984年にデリダをフランクフルト大学での講演に招いた際に接触しました。翌年、ハーバーマスは『近代の哲学的ディスクルス』で「起源の時間化された哲学を超えて:デリダ」というエッセイを発表し、そこでデリダの方法論が社会批判のための基礎を提供できないと描写しました。デリダは、ハーバーマスを例に挙げつつ、「哲学を文学に、論理を修辞学に還元していると私を非難する者たちは...明らかに、そして注意深く私を読んでいない」と述べました。1989年のデリダの最後の反論の後、両哲学者間の議論は継続しませんでしたが、デリダが述べたように、学術界のグループは「一種の『戦争』を遂行したが、私たち自身は個人的にも直接的にも参加しなかった」のです。
1990年代末、ハーバーマスは講演中のアメリカの大学で行われたパーティーでデリダに声をかけました。その後、彼らはパリで夕食を共にしてから、多くの共同プロジェクトに参加しました。2000年には、フランクフルト大学で哲学、法、倫理学、政治学の問題に関する共同ゼミを開催しました。2000年12月、パリでジョゼフ・コーエンとラファエル・ザギュリー=オルリが主催した「ユダヤ性:ジャック・デリダへの問い」と題する会議で、ハーバーマスは「倫理的な問いにどう答えるか?」と題する講演を行いました。ハーバーマスの講演後、両思想家はハイデッガーと倫理の可能性について非常に白熱した議論を交わしました。会議録は2002年にエディション・ガリレ(パリ)から、その後フォードハム大学出版局(2007年)から英語で出版されました。
アメリカ同時多発テロ事件の後、デリダとハーバーマスは、ジョバンナ・ボッラドリの『テロルの時代と哲学の使命』の中で、9月11日攻撃と対テロ戦争に対するそれぞれの意見を述べました。2003年初頭、ハーバーマスとデリダはともに、来るイラク戦争に反対する活動を活発に行いました。後に『古きヨーロッパ、新しきヨーロッパ、核となるヨーロッパ』という本になったマニフェストの中で、両者は欧州連合諸国のより緊密な統一を呼びかけ、アメリカの外交政策に対抗できる勢力を構築すべきだと主張しました。デリダはこの本の中で、ジョージ・W・ブッシュ政権によるイラク戦争への支持要求への反応として、ハーバーマスが2003年2月に発表した宣言(「2月15日、あるいはヨーロッパ人を結びつけるもの:核となるヨーロッパから始まる共通外交政策への訴え」)に無条件で同意することを表明する序文を執筆しました。
4.2. 歴史家論争
ハーバーマスは学者であると同時に公共的知識人としても有名ですが、特に1980年代には、大衆紙を用いてドイツの歴史家エルンスト・ノルテ、ミヒャエル・シュテュルマー、クラウス・ヒルデブラント、アンドレアス・ヒルグルーバーを攻撃したことで知られています。ハーバーマスがこれらの歴史家に対する見解を最初に表明したのは、1986年7月11日の『ディー・ツァイト』紙に掲載された「一種の損害清算」と題された文化・芸術に関する意見エッセイ(feuilletonドイツ語)でした。
ハーバーマスは、ノルテ、シュテュルマー、ヒルデブラント、ヒルグルーバーがナチス時代に関する「弁明的」な歴史記述を行っていると批判し、1945年以降存在していたハーバーマスが考える「ドイツの西欧への開放」を「閉じようとしている」と主張しました。ハーバーマスは、ノルテ、シュテュルマー、ヒルデブラント、ヒルグルーバーがナチス支配とホロコーストをドイツ史の主流から切り離し、ナチズムをボリシェヴィズムへの反応として説明し、第二次世界大戦中のドイツ国防軍(ドイツ陸軍)の評判を部分的に回復させようとしていると主張しました。
ハーバーマスは、シュテュルマーがドイツ史の中に「代理宗教」を創り出そうとしており、それがヒルグルーバーのドイツ陸軍の東部戦線における最期の日の栄光化と相まって、「ドイツナショナリズムで彩られた一種のNATO哲学」として機能しようとしていると書きました。ヒルグルーバーがアドルフ・ヒトラーがユダヤ人を絶滅させようとしたのは「その『人種革命』だけが彼の『帝国』の世界大国としての地位に永続性を与えることができたからだ」と述べたことについて、ハーバーマスは「ヒルグルーバーが接続法を使わないため、歴史家が今回もその個別の視点を採用したのかどうかわからない」と書いています。
ハーバーマスは次のように述べました。「ドイツ連邦共和国の西欧政治文化への無条件の開放は、私たちの戦後期における最大の知的功績であり、私の世代は特にこれを誇りに思うべきだ。この出来事は、私たちの修正主義者たちが『ヨーロッパにおけるドイツ人の古くからの地理的中心的位置』(シュテュルマー)や『破壊されたヨーロッパ中心部の再構築』(ヒルグルーバー)といった地政学的な鼓動で私たちを温めようとしている中央ヨーロッパのイデオロギーを克服することによってこそ、まさに達成されたのだ。西欧から私たちを遠ざけない唯一の愛国心は、憲法パトリオティズムである。」
「歴史家論争」(Historikerstreitドイツ語)として知られるこの論争は、全く一方的なものではありませんでした。ハーバーマス自身も、ヨアヒム・フェスト、ハーゲン・シュルツェ、ホルスト・メラー、イマヌエル・ガイス、クラウス・ヒルデブラントといった学者たちから攻撃を受けました。一方で、マルティン・ブロシャート、エーバーハルト・イエッケル、ハンス・モムゼン、ハンス=ウルリヒ・ヴェーラーといった歴史家たちからは支持を受けました。
4.3. 政治・社会問題に関する見解
ハーバーマスは現代社会の多様な政治的および社会的問題に対して批判的な見解を表明し、積極的に関与してきました。
4.3.1. 宗教に対する視点
ハーバーマスの宗教に対する姿勢は長年にわたって変化してきました。分析者のフィリップ・ポルティエは、ハーバーマスのこの社会領域に対する姿勢に3つの段階を特定しています。第一段階は1980年代で、若きユルゲンはマルクスの精神に則り、宗教を「疎外をもたらす現実」および「支配の道具」と見なし、宗教に反対していました。第二段階は1980年代半ばから21世紀初頭にかけてで、この時期は宗教について議論することをやめ、世俗的評論家として宗教を私生活の問題に限定していました。そして第三段階はそれ以降で、ハーバーマスは宗教の肯定的な社会的役割を認めるようになりました。
1999年のインタビューで、ハーバーマスは次のように述べています。
「近代の規範的自己理解にとって、キリスト教は単なる先駆者や触媒以上の役割を果たしてきた。普遍主義的平等主義、そこから自由と連帯における共同生活、自律的な生活行動と解放、個人的良心の道徳、人権と民主主義の理想が生まれたが、これらはユダヤの正義の倫理とキリスト教の愛の倫理の直接の遺産である。この遺産は、実質的に変わることなく、継続的な批判的再appropriationと再解釈の対象となってきた。今日に至るまで、これに代わるものはない。そして、ポスト国民国家的状況という現在の課題に直面する中で、私たちは過去と同様に、この実体から栄養を摂取しなければならない。その他のすべては、ポストモダニズムの空虚な言葉に過ぎない。」
この発言は多くの記事や書籍で誤引用されることがあり、ハーバーマスが「キリスト教こそが、自由、良心、人権、民主主義といった西洋文明の基準の究極的な基礎である。今日に至るまで、私たちに他の選択肢はない。私たちはこの源泉から栄養を摂取し続けている。その他のすべては、ポストモダニズムの空虚な雑談である」と述べたとして引用されることがあります。
彼の著書『Zwischen Naturalismus und Religionドイツ語』(『自然主義と宗教の間』、2005年)の中で、ハーバーマスは、多文化主義と移民の結果として、宗教の力が増大しており、したがって、世俗的な人々は公共の場における宗教者の役割を寛容に受け入れる必要があり、逆もまた同様であるという双方向的な寛容性の必要性を主張しています。
2007年初頭、イグナチウス・プレスは、ハーバーマスと当時の聖座教理省長官であるヨゼフ・ラッツィンガー(2005年に教皇ベネディクト16世として選出)との対談『世俗化の弁証法』を出版しました。この対談は2004年1月14日に、ミュンヘンのバイエルンカトリックアカデミーが両思想家を招いた後に開催されました。この対談は、次のような現代の問いを取り上げています。
- 私たちのポスト形而上学的時代において、理性と秩序ある自由の公共文化は可能か?
- 哲学は存在と人類学におけるその基礎から永久に切り離されているのか?
- この合理性の衰退は、宗教そのものにとって機会なのか、それとも深い危機なのか?
この対談において、ハーバーマスの変化が明らかになりました。特に、宗教の公共的役割についての彼の再考です。ハーバーマスは自らを「方法論的無神論者」と述べ、これは哲学や社会科学を行う際に特定の宗教的信条について何も前提しないことを意味します。しかし、この視点から書きながらも、社会における宗教の役割に対する彼の発展的な立場は、いくつかの困難な問いへと彼を導き、その結果、彼は将来の教皇との対話の中でいくつかの譲歩をしました。これらは、近代の問題に対するコミュニケーション的合理性による解決策について彼が持つ立場をさらに複雑にする結果をもたらしました。ハーバーマスは、自己を自由主義者と認める思想家にとっても、「宗教的声を公共の場から排除することは、きわめて非自由主義的である」と信じています。
さらに、ハーバーマスは「ポスト世俗社会」という概念を普及させました。これは、近代という考えが不成功であり、時には道徳的に失敗したと認識されている現代を指すもので、階層化や分離ではなく、信仰と理性の間に新たな平和的な対話と共存が求められ、互いに学び合うべきであるとしています。
4.3.2. 社会主義に対する視点
ハーバーマスは、マルクスが生産力の解放的潜在力を過大評価していることに懸念を示したハンナ・アーレントのような20世紀のマルクス主義評論家に賛同しています。アーレントは自著『全体主義の起源』でこの点を提示し、ハーバーマスは『コミュニケーション的行為の理論』所収の「生活世界とシステム:機能主義的理性の批判」においてこの批判を広げています。ハーバーマスは次のように述べています。
「...伝統的なマルクス主義の分析は...今日、政治経済の批判の手段を用いるとき...もはや明確な予測はできない。そのためには、自己再生産的な経済システムの自律性を依然として前提しなければならないだろう。私はそのような自律性を信じていない。まさにこの理由から、経済システムを支配する法則は、マルクスが分析したものと同一ではない。もちろん、これは経済システムを動かすメカニズムを分析することが誤っているという意味ではない。しかし、そのような分析の正統派のバージョンが有効であるためには、政治システムの影響を無視しなければならないだろう。」
ハーバーマスは、マルクスとその階級闘争理論を否定したのは、「1945年以降」西側諸国で発展した「福祉国家」による「階級対立の鎮静化」であり、それは「ケインズ経済学の手段に依拠した改革主義者」のおかげであるという立場を再確認しました。イタリアの哲学者・歴史家ドメニコ・ロスルドは、これらの主張の主要な点について、「明らかであるべき問いの欠如によって特徴づけられている」と批判しました。「福祉国家の出現は、資本主義に内在する傾向の必然的な結果だったのか?それとも、従属階級による政治的・社会的動員、最終的には階級闘争の結果だったのか?ドイツの哲学者がこの問いを提起していれば、おそらく彼は福祉国家の永続性を前提とすることを避けていただろう。その不安定さと漸進的な解体は今や誰の目にも明らかであるにもかかわらず。」
4.3.3. 戦争に対する立場
1999年、ハーバーマスはコソボ紛争について言及しました。彼は『ディー・ツァイト』紙の記事でNATOによるユーゴスラビア空爆を擁護し、論争を巻き起こしました。
2002年には、米国がイラク戦争に突入すべきではないと主張しました。
2023年11月13日、ハーバーマスはイスラエルのハマース主導の攻撃に対する軍事対応を支持する声明を発表し、ガザ地区におけるイスラエルの行動を指す「ジェノサイド」という用語を否定しました。
4.3.4. 欧州連合に対する見解
欧州債務危機中、ハーバーマスは欧州におけるアンゲラ・メルケルの指導力を批判しました。2013年にはヴォルフガング・シュトレークと衝突しました。シュトレークは、ハーバーマスが擁護するようなヨーロッパの連邦主義こそが、この大陸の危機の根源であると主張しました。ハーバーマスとジャック・デリダは、アメリカ同時多発テロ事件後、欧州連合諸国のより緊密な統合を求めるマニフェストを共同で発表し、アメリカの外交政策に対抗できる勢力を作ることを主張しました。
4.3.5. 学生運動批判と「左派ファシズム」論争
1960年代後半から激化した西ドイツ国内の学生運動勢力との対立を背景に、ハーバーマスは1971年に突然教授職を辞し、シュタルンベルクのマックス・プランク科学技術世界生活条件研究所に研究者として移籍しました。彼は学生たちの暴力的なデモを「マゾヒズム」であると非難し、学生運動を「左派ファシズム」と激しく攻撃しました。この発言は大きな論争を巻き起こし、彼は瞬く間に急進的な学生運動家たちの敵となり、「ブルジョワ反動的知識人」として中傷されることになります。ハーバーマスは、このような対立が続く大学に留まり、議論を続けることを望まなかったとされています。この時期から約10年間、彼は研究所にこもり、研究と執筆に専念しました。彼の代表作である「コミュニケーション的行為の理論」は、この長期間の思索と探求の末に誕生しました。ハーバーマスに対する極右陣営からの攻撃とは別に、左翼や学生運動陣営からの批判は、彼らが自身の過ちに対する批判を受け入れないという偏狭さを露呈するきっかけとなりました。
4.3.6. 韓国社会との関係
ハーバーマスは韓国社会の問題にも関心を示しました。特に、2003年に韓国に帰国した宋斗律(ソン・ドゥユル)教授が国家保安法違反で懲役刑を宣告され収監されていた際、「安重根平和賞」を受賞することになった時、ハーバーマスは宋斗律教授が刑務所から直接出てきて賞を受け取ると誤解し、彼にドイツ大使館に避難するよう直接忠告したと言われています。
ハーバーマスは宋斗律教授の博士論文の指導教授でもありました。韓国では1986年まで彼の著作の入手が困難であり、同年には翻訳の試みもなされたものの実現しませんでした。1987年2月以降、単行本として出版されるようになりましたが、当初はあまり注目されませんでした。しかし、1994年以降、彼の著作が活発に翻訳・出版されるようになり、韓国の学界や知識人社会に大きな影響を与えました。特に、金芝河や宋斗律といった批判的な人物の処遇が問題になった際には、韓国政府の暴力性と表現の自由、思想の自由を尊重しない態度を批判し、非難しました。
5. 受賞歴と栄誉
ユルゲン・ハーバーマスは、その生涯にわたって数多くの学術的および文化的な賞を受賞し、顕著な功績が認められてきました。
- 1974年: ヘーゲル賞
- 1976年: ジークムント・フロイト賞
- 1980年: テオドール・アドルノ賞
- 1985年: 『Die neue Unübersichtlichkeitドイツ語』に対しショル兄弟賞
- 1986年: ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ賞
- 1987年: ソニング賞(ヨーロッパ文化への優れた貢献に対し2年ごとに授与)
- 1995年: カール・ヤスパース賞
- 1999年: テオドール・ホイス賞
- 2000年: ヘルムホルツ・メダル
- 2001年: ドイツ書籍協会平和賞
- 2003年: アストゥリアス皇太子賞社会科学部門
- 2004年: 京都賞思想・芸術部門 (5000.00 万 JPY)
- 2005年: ホルベア国際記念賞 (約52.00 万 EUR)
- 2006年: ブルーノ・クライスキー賞
- 2008年: ロカルノ国際映画祭でハンス・リンギアー財団よりヨーロッパ政治文化賞 (5.00 万 EUR)
- 2010年: ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンよりユリシーズ・メダル
- 2011年: Viktor-Frankl-Preisドイツ語
- 2012年: Georg-August-Zinn-Preisドイツ語
- 2012年: ハインリヒ・ハイネ賞
- 2012年: ミュンヘン市文化栄誉賞
- 2013年: エラスムス賞
- 2015年: クルーゲ賞
- 2021年: シェイク・ザーイド・ブック・アワード(アラブ首長国連邦の政治体制を抑圧的な非民主主義と見なし辞退)
- 2022年: 弁証法メダル
- 2022年: プール・ル・メリット勲章
- 2024年: ヨハン・スクデ政治学賞
6. 主要著作
ユルゲン・ハーバーマスが執筆した主要な学術書籍および論文を年代順に列挙し、各著作の核心内容を簡潔に紹介します。
- Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denkenドイツ語 (1954年): フリードリヒ・シェリングの思想における「絶対」と「歴史」の対立を扱った博士論文。
- Student und Politikドイツ語 (1961年): 学生の政治的意識に関する社会学的調査。
- 『公共性の構造転換』 (Strukturwandel der Öffentlichkeitドイツ語) (1962年): ブルジョワ公共圏の歴史的発展とその変容を分析した初期の代表作。
- 『理論と実践』 (Theorie und Praxisドイツ語) (1963年): 社会哲学に関する研究。
- 『社会科学の論理によせて』 (Zur Logik der Sozialwissenschaftenドイツ語) (1967年): 社会科学の方法論に関する考察。
- 『イデオロギーとしての技術と科学』 (Technik und Wissenschaft als "Ideologie"ドイツ語) (1968年): 科学技術とイデオロギーの関係を論じた著作。
- 『認識と関心』 (Erkenntnis und Interesseドイツ語) (1968年): 人間の認識と関心の不可分な関係を考察した主要な認識論的著作。
- Protestbewegung und Hochschulreformドイツ語 (1969年): 学生運動と大学改革に関する批判的分析。
- Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?ドイツ語 (1971年): ニクラス・ルーマンとの共著で、社会システム理論の可能性と限界を議論。
- 『哲学的・政治的プロフィール』 (Philosophisch-politische Profileドイツ語) (1971年): 現代ヨーロッパの哲学者たちに関するエッセイ集。
- Kultur und Kritikドイツ語 (1973年): 文化と批判に関するエッセイをまとめたもの。
- 『後期資本主義における正統化の問題』 (Legitimationsprobleme im Spätkapitalismusドイツ語) (1973年): 後期資本主義社会における正統化の危機を分析。
- 『史的唯物論の再構成』 (Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismusドイツ語) (1976年): 歴史的唯物論の再解釈を試みた著作。
- Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische Philosophen.ドイツ語 (1978年): 政治、芸術、宗教に関するエッセイ集。
- 『コミュニケーション的行為の理論』 (Theorie des kommunikativen Handelnsドイツ語) (1981年): 彼の主著であり、コミュニケーション的合理性、生活世界とシステムの理論を体系的に展開。
- Kleine politische Schriften I-IVドイツ語 (1981年): 政治に関する短編論文集。
- 『道徳意識とコミュニケーション行為』 (Moralbewusstsein und kommunikatives Handelnドイツ語) (1983年): 道徳とコミュニケーション行為の関係を探求。
- Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelnsドイツ語 (1984年): 『コミュニケーション的行為の理論』の予備研究と補足。
- 『新たなる不透明性』 (Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften Vドイツ語) (1985年): 福祉国家の危機などを論じた政治論文集。
- 『近代の哲学的ディスクルス』 (Der philosophische Diskurs der Moderneドイツ語) (1985年): ポストモダニズムとの対決を通じて近代哲学の概念を再構築。
- Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VIドイツ語 (1987年): 歴史家論争に関する論文を含む政治論文集。
- 『ポスト形而上学の思想』 (Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätzeドイツ語) (1988年): 形而上学後の哲学の可能性を論じた論文集。
- Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VIIドイツ語 (1990年): ドイツ統一に関する政治論文集。
- 『近代--未完のプロジェクト』 (Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätzeドイツ語) (1990年): 近代の理性とプロジェクトの未完性を論じたエッセイ集。
- 『討議倫理』 (Erläuterungen zur Diskursethikドイツ語) (1991年): 討議倫理の概念を解説。
- Texte und Kontexteドイツ語 (1991年): テクストとコンテクストに関する論文集。
- 『未来としての過去--ハーバーマスは語る』 (Vergangenheit als Zukunft? Das alte Deutschland im neue Europa?ドイツ語) (1991年): マイケル・ハラーとの対談。
- 『事実性と妥当性:法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究』 (Faktizität und Geltungドイツ語) (1992年): 法と民主主義に関する討議理論を展開した主要作。
- Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine Politische Schriften VIIIドイツ語 (1995年): ベルリン共和国の常識に関する政治論文集。
- 『他者の受容:多文化社会の政治理論に関する研究』 (Die Einbeziehung des Anderenドイツ語) (1996年): 他者の受容と多文化社会の政治理論に関する研究。
- Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essaysドイツ語 (1997年): 感覚的印象から象徴的表現への哲学論文集。
- Die postnationale Konstellation. Politische Essaysドイツ語 (1998年): ポスト国民国家の状況に関する政治論文集。
- 『真理と正当化:哲学論文集』 (Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätzeドイツ語) (1999年): 真理と正当化に関する哲学論文集。
- 『法と正義のディスクルス--ハーバーマス京都講演集』 (1999年): 京都での講演をまとめたもの。
- Zeit der Übergänge. Kleine Politische Schriften IXドイツ語 (2001年): 移行期に関する政治論文集。
- 『人間の将来とバイオエシックス』 (Die Zukunft der menschlichen Naturドイツ語) (2001年): 遺伝子工学と人間倫理に関する考察。
- Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunftドイツ語 (2001年): コミュニケーション的行為と脱超越論的理性に関する著作。
- 『引き裂かれた西洋』 (Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften Xドイツ語) (2004年): 世界政治における西洋の分裂と、新たな国際秩序の模索を論じた政治論文集。
- 『ポスト世俗化時代の哲学と宗教』 (Dialektik der Säkularisierungドイツ語) (2005年): ヨーゼフ・ラッツィンガーとの対談で、世俗化と宗教の弁証法を議論。
- 『自然主義と宗教の間--哲学論集』 (Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätzeドイツ語) (2005年): 自然主義と宗教の間の哲学的な問題を考察。
- 『ああ、ヨーロッパ』 (Ach, Europa. Kleine politische Schriften XI.ドイツ語) (2008年): ヨーロッパの将来と統合に関する政治論文集。
- Philosophische Texteドイツ語 (2009年): 5巻からなる哲学論文集。
- 『ヨーロッパ憲法論』 (Zur Verfassung Europas. Ein Essayドイツ語) (2011年): ヨーロッパの憲法に関するエッセイ。
- Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Replikenドイツ語 (2012年): ポスト形而上学の思想に関する続編。
- Im Sog der Technokratie. Kleine politische Schriften XIIドイツ語 (2013年): テクノクラシーの渦中にある政治に関する論文集。
- Auch eine Geschichte der Philosophieドイツ語 (2019年): 2巻からなる哲学史。
7. 評価と影響
7.1. 学術的影響と評価
ハーバーマスの思想は、現代哲学、社会学、政治理論など多岐にわたる分野に甚大な影響を与え、その継続的な影響力と重要性の増大は計量書誌学的研究によっても示されています。彼はフランクフルト学派に連なりながらも、その悲観主義を乗り越え、コミュニケーション的合理性という独自の概念を提示することで、批判理論を新たな段階へと引き上げました。
彼のコミュニケーション的行為論は、知識論や社会理論の基礎を再構築し、後期資本主義と民主主義の分析、社会進化論的文脈における法の支配、そして現代政治への深い洞察を提供しました。特に、マックス・ウェーバーによって示された近代社会の合理化に関する議論を深化させ、「生活世界」が「システム」によって「植民地化」されるという現象を分析しました。しかし、彼は理性の道具化という負の側面だけでなく、コミュニケーション能力に内在する理性の潜在力を信じ、社会の人間化と民主化の可能性を追求しました。
ハーバーマスによる近代と市民社会の擁護は、多くの思想家に影響を与え、ポスト構造主義の様々な潮流に対する主要な哲学的代替案として位置づけられています。彼の理論は、真理と正当性の基礎を主体間の対話と相互理解に見出すことで、普遍主義的な規範と価値観を再構築しようとする試みであり、現代の多元的社会における合意形成の可能性を探る上で重要な枠組みを提供しています。
7.2. 批判と論争
ハーバーマスは、その思想と社会への積極的な関与ゆえに、生涯を通じて様々な批判と論争に直面してきました。
例えば、彼の「近代対ポストモダニズム」という1981年のエッセイでは、20世紀の失敗を踏まえ、啓蒙主義の意図を維持すべきか、それとも近代というプロジェクト全体を失われたものと見なすべきかという問いを提起しました。ハーバーマスは、生活世界の合理的で「科学的」な理解の可能性を放棄することを拒否しました。彼はポストモダニズムに対していくつかの主要な批判を投げかけました。それは、彼らが真剣な理論を生産しているのか、それとも単なる文学を生み出しているのかが曖昧であること、規範的な感情に動かされているにもかかわらず、その感情の性質が読者から隠蔽されていること、近代社会内で生じる現象や実践を区別できない全体主義的な視点を持っていること、そしてハーバーマスが絶対的に中心的と考える日常生活とその実践を無視していることなどです。
また、1960年代の西ドイツ学生運動に対する彼の批判、特に「左派ファシズム」という発言は、彼を学生運動家たちの敵に回し、「ブルジョワ反動的知識人」と見なされる一因となりました。この論争は、左翼・運動陣営が自身の過ちに対する批判を受け入れない偏狭さを露呈するきっかけを作ったとも指摘されています。
マルクス主義との関係においては、彼の福祉国家論に対する批判も存在します。彼は、マルクスの階級闘争理論が福祉国家によって「階級対立の鎮静化」がなされたことで「論破された」と主張しましたが、ドメニコ・ロスルドのような思想家は、福祉国家の出現が資本主義の内在的傾向によるものか、それとも下層階級の政治的・社会的動員(階級闘争)の結果であるかという問いをハーバーマスが避けていると批判しました。また、福祉国家の永続性を前提とすることの不安定さも指摘されています。
7.3. 公共的知識人としての役割
ハーバーマスは、その学術的な貢献だけでなく、ドイツ国内および国際社会における主要な社会的・政治的議論に積極的に参加し、公共的知識人として重要な役割を果たしてきました。
彼は1980年代の「歴史家論争」において、大衆紙を通じてナチス時代の歴史解釈を巡る歴史家たちへの批判を表明し、ドイツの過去との向き合い方、特にホロコーストの唯一性とドイツの民主主義的自己理解の基礎である「憲法パトリオティズム」を巡る重要な議論を主導しました。この論争は、彼が公共的知識人としての役割を積極的に果たすことを示しました。
また、コソボ紛争におけるNATOの介入の擁護、イラク戦争への反対、イスラエル・ハマス戦争に関する見解表明など、様々な国際紛争に対して自身の倫理的・政治的立場を表明し、議論に介入しました。欧州連合の統合問題においても、欧州債務危機におけるアンゲラ・メルケルの指導力への批判や、ジャック・デリダとの共同声明でより緊密なEU統合を呼びかけるなど、積極的な発言を行いました。
彼のアラブ首長国連邦のシェイク・ザーイド・ブック・アワードを辞退したことは、人権と民主主義の価値に対する彼の断固たる姿勢を示すものであり、彼が単なる象牙の塔の学者ではなく、社会の規範的問題に深く関与する倫理的な主体であることを明確にしました。このように、ハーバーマスは学術と政治の間の架け橋となり、民主主義的政治文化を促進する上で大きな貢献を果たしてきました。
8. 受賞歴と栄誉
ユルゲン・ハーバーマスは、その生涯にわたって数多くの学術的および文化的な賞を受賞し、顕著な功績が認められてきました。
- 1974年: ヘーゲル賞
- 1976年: ジークムント・フロイト賞
- 1980年: テオドール・アドルノ賞
- 1985年: 『Die neue Unübersichtlichkeitドイツ語』に対しショル兄弟賞
- 1986年: ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ賞
- 1987年: ソニング賞(ヨーロッパ文化への優れた貢献に対し2年ごとに授与)
- 1995年: カール・ヤスパース賞
- 1999年: テオドール・ホイス賞
- 2000年: ヘルムホルツ・メダル
- 2001年: ドイツ書籍協会平和賞
- 2003年: アストゥリアス皇太子賞社会科学部門
- 2004年: 京都賞思想・芸術部門 (5000.00 万 JPY)
- 2005年: ホルベア国際記念賞 (約52.00 万 EUR)
- 2006年: ブルーノ・クライスキー賞
- 2008年: ロカルノ国際映画祭でハンス・リンギアー財団よりヨーロッパ政治文化賞 (5.00 万 EUR)
- 2010年: ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンよりユリシーズ・メダル
- 2011年: Viktor-Frankl-Preisドイツ語
- 2012年: Georg-August-Zinn-Preisドイツ語
- 2012年: ハインリヒ・ハイネ賞
- 2012年: ミュンヘン市文化栄誉賞
- 2013年: エラスムス賞
- 2015年: クルーゲ賞
- 2021年: シェイク・ザーイド・ブック・アワード(アラブ首長国連邦の政治体制を抑圧的な非民主主義と見なし辞退)
- 2022年: 弁証法メダル
- 2022年: プール・ル・メリット勲章
- 2024年: ヨハン・スクデ政治学賞
9. 主要著作
ユルゲン・ハーバーマスが執筆した主要な学術書籍および論文を年代順に列挙し、各著作の核心内容を簡潔に紹介します。
- Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denkenドイツ語 (1954年): フリードリヒ・シェリングの思想における「絶対」と「歴史」の対立を扱った博士論文。
- Student und Politikドイツ語 (1961年): 学生の政治的意識に関する社会学的調査。
- 『公共性の構造転換』 (Strukturwandel der Öffentlichkeitドイツ語) (1962年): ブルジョワ公共圏の歴史的発展とその変容を分析した初期の代表作。
- 『理論と実践』 (Theorie und Praxisドイツ語) (1963年): 社会哲学に関する研究。
- 『社会科学の論理によせて』 (Zur Logik der Sozialwissenschaftenドイツ語) (1967年): 社会科学の方法論に関する考察。
- 『イデオロギーとしての技術と科学』 (Technik und Wissenschaft als "Ideologie"ドイツ語) (1968年): 科学技術とイデオロギーの関係を論じた著作。
- 『認識と関心』 (Erkenntnis und Interesseドイツ語) (1968年): 人間の認識と関心の不可分な関係を考察した主要な認識論的著作。
- Protestbewegung und Hochschulreformドイツ語 (1969年): 学生運動と大学改革に関する批判的分析。
- Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?ドイツ語 (1971年): ニクラス・ルーマンとの共著で、社会システム理論の可能性と限界を議論。
- 『哲学的・政治的プロフィール』 (Philosophisch-politische Profileドイツ語) (1971年): 現代ヨーロッパの哲学者たちに関するエッセイ集。
- Kultur und Kritikドイツ語 (1973年): 文化と批判に関するエッセイをまとめたもの。
- 『後期資本主義における正統化の問題』 (Legitimationsprobleme im Spätkapitalismusドイツ語) (1973年): 後期資本主義社会における正統化の危機を分析。
- 『史的唯物論の再構成』 (Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismusドイツ語) (1976年): 歴史的唯物論の再解釈を試みた著作。
- Politik, Kunst, Religion. Essays über zeitgenössische Philosophen.ドイツ語 (1978年): 政治、芸術、宗教に関するエッセイ集。
- 『コミュニケーション的行為の理論』 (Theorie des kommunikativen Handelnsドイツ語) (1981年): 彼の主著であり、コミュニケーション的合理性、生活世界とシステムの理論を体系的に展開。
- Kleine politische Schriften I-IVドイツ語 (1981年): 政治に関する短編論文集。
- 『道徳意識とコミュニケーション行為』 (Moralbewusstsein und kommunikatives Handelnドイツ語) (1983年): 道徳とコミュニケーション行為の関係を探求。
- Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelnsドイツ語 (1984年): 『コミュニケーション的行為の理論』の予備研究と補足。
- 『新たなる不透明性』 (Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften Vドイツ語) (1985年): 福祉国家の危機などを論じた政治論文集。
- 『近代の哲学的ディスクルス』 (Der philosophische Diskurs der Moderneドイツ語) (1985年): ポストモダニズムとの対決を通じて近代哲学の概念を再構築。
- Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VIドイツ語 (1987年): 歴史家論争に関する論文を含む政治論文集。
- 『ポスト形而上学の思想』 (Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätzeドイツ語) (1988年): 形而上学後の哲学の可能性を論じた論文集。
- Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VIIドイツ語 (1990年): ドイツ統一に関する政治論文集。
- 『近代--未完のプロジェクト』 (Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätzeドイツ語) (1990年): 近代の理性とプロジェクトの未完性を論じたエッセイ集。
- 『討議倫理』 (Erläuterungen zur Diskursethikドイツ語) (1991年): 討議倫理の概念を解説。
- Texte und Kontexteドイツ語 (1991年): テクストとコンテクストに関する論文集。
- 『未来としての過去--ハーバーマスは語る』 (Vergangenheit als Zukunft? Das alte Deutschland im neue Europa?ドイツ語) (1991年): マイケル・ハラーとの対談。
- 『事実性と妥当性:法と民主的法治国家の討議理論にかんする研究』 (Faktizität und Geltungドイツ語) (1992年): 法と民主主義に関する討議理論を展開した主要作。
- Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine Politische Schriften VIIIドイツ語 (1995年): ベルリン共和国の常識に関する政治論文集。
- 『他者の受容:多文化社会の政治理論に関する研究』 (Die Einbeziehung des Anderenドイツ語) (1996年): 他者の受容と多文化社会の政治理論に関する研究。
- Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essaysドイツ語 (1997年): 感覚的印象から象徴的表現への哲学論文集。
- Die postnationale Konstellation. Politische Essaysドイツ語 (1998年): ポスト国民国家の状況に関する政治論文集。
- 『真理と正当化:哲学論文集』 (Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätzeドイツ語) (1999年): 真理と正当化に関する哲学論文集。
- 『法と正義のディスクルス--ハーバーマス京都講演集』 (1999年): 京都での講演をまとめたもの。
- Zeit der Übergänge. Kleine Politische Schriften IXドイツ語 (2001年): 移行期に関する政治論文集。
- 『人間の将来とバイオエシックス』 (Die Zukunft der menschlichen Naturドイツ語) (2001年): 遺伝子工学と人間倫理に関する考察。
- Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunftドイツ語 (2001年): コミュニケーション的行為と脱超越論的理性に関する著作。
- 『引き裂かれた西洋』 (Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften Xドイツ語) (2004年): 世界政治における西洋の分裂と、新たな国際秩序の模索を論じた政治論文集。
- 『ポスト世俗化時代の哲学と宗教』 (Dialektik der Säkularisierungドイツ語) (2005年): ヨーゼフ・ラッツィンガーとの対談で、世俗化と宗教の弁証法を議論。
- 『自然主義と宗教の間--哲学論集』 (Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätzeドイツ語) (2005年): 自然主義と宗教の間の哲学的な問題を考察。
- 『ああ、ヨーロッパ』 (Ach, Europa. Kleine politische Schriften XI.ドイツ語) (2008年): ヨーロッパの将来と統合に関する政治論文集。
- Philosophische Texteドイツ語 (2009年): 5巻からなる哲学論文集。
- 『ヨーロッパ憲法論』 (Zur Verfassung Europas. Ein Essayドイツ語) (2011年): ヨーロッパの憲法に関するエッセイ。
- Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Replikenドイツ語 (2012年): ポスト形而上学の思想に関する続編。
- Im Sog der Technokratie. Kleine politische Schriften XIIドイツ語 (2013年): テクノクラシーの渦中にある政治に関する論文集。
- Auch eine Geschichte der Philosophieドイツ語 (2019年): 2巻からなる哲学史。
10. 評価と影響
10.1. 学術的影響と評価
ハーバーマスの思想は、現代哲学、社会学、政治理論など多岐にわたる分野に甚大な影響を与え、その継続的な影響力と重要性の増大は計量書誌学的研究によっても示されています。彼はフランクフルト学派に連なりながらも、その悲観主義を乗り越え、コミュニケーション的合理性という独自の概念を提示することで、批判理論を新たな段階へと引き上げました。
彼のコミュニケーション的行為論は、知識論や社会理論の基礎を再構築し、後期資本主義と民主主義の分析、社会進化論的文脈における法の支配、そして現代政治への深い洞察を提供しました。特に、マックス・ウェーバーによって示された近代社会の合理化に関する議論を深化させ、「生活世界」が「システム」によって「植民地化」されるという現象を分析しました。しかし、彼は理性の道具化という負の側面だけでなく、コミュニケーション能力に内在する理性の潜在力を信じ、社会の人間化と民主化の可能性を追求しました。
ハーバーマスによる近代と市民社会の擁護は、多くの思想家に影響を与え、ポスト構造主義の様々な潮流に対する主要な哲学的代替案として位置づけられています。彼の理論は、真理と正当性の基礎を主体間の対話と相互理解に見出すことで、普遍主義的な規範と価値観を再構築しようとする試みであり、現代の多元的社会における合意形成の可能性を探る上で重要な枠組みを提供しています。
10.2. 批判と論争
ハーバーマスは、その思想と社会への積極的な関与ゆえに、生涯を通じて様々な批判と論争に直面してきました。
例えば、彼の「近代対ポストモダニズム」という1981年のエッセイでは、20世紀の失敗を踏まえ、啓蒙主義の意図を維持すべきか、それとも近代というプロジェクト全体を失われたものと見なすべきかという問いを提起しました。ハーバーマスは、生活世界の合理的で「科学的」な理解の可能性を放棄することを拒否しました。彼はポストモダニズムに対していくつかの主要な批判を投げかけました。それは、彼らが真剣な理論を生産しているのか、それとも単なる文学を生み出しているのかが曖昧であること、規範的な感情に動かされているにもかかわらず、その感情の性質が読者から隠蔽されていること、近代社会内で生じる現象や実践を区別できない全体主義的な視点を持っていること、そしてハーバーマスが絶対的に中心的と考える日常生活とその実践を無視していることなどです。
また、1960年代の西ドイツ学生運動に対する彼の批判、特に「左派ファシズム」という発言は、彼を学生運動家たちの敵に回し、「ブルジョワ反動的知識人」と見なされる一因となりました。この論争は、左翼・運動陣営が自身の過ちに対する批判を受け入れない偏狭さを露呈するきっかけを作ったとも指摘されています。
マルクス主義との関係においては、彼の福祉国家論に対する批判も存在します。彼は、マルクスの階級闘争理論が福祉国家によって「階級対立の鎮静化」がなされたことで「論破された」と主張しましたが、ドメニコ・ロスルドのような思想家は、福祉国家の出現が資本主義の内在的傾向によるものか、それとも下層階級の政治的・社会的動員(階級闘争)の結果であるかという問いをハーバーマスが避けていると批判しました。また、福祉国家の永続性を前提とすることの不安定さも指摘されています。
10.3. 公共的知識人としての役割
ハーバーマスは、その学術的な貢献だけでなく、ドイツ国内および国際社会における主要な社会的・政治的議論に積極的に参加し、公共的知識人として重要な役割を果たしてきました。
彼は1980年代の「歴史家論争」において、大衆紙を通じてナチス時代の歴史解釈を巡る歴史家たちへの批判を表明し、ドイツの過去との向き合い方、特にホロコーストの唯一性とドイツの民主主義的自己理解の基礎である「憲法パトリオティズム」を巡る重要な議論を主導しました。この論争は、彼が公共的知識人としての役割を積極的に果たすことを示しました。
また、コソボ紛争におけるNATOの介入の擁護、イラク戦争への反対、イスラエル・ハマス戦争に関する見解表明など、様々な国際紛争に対して自身の倫理的・政治的立場を表明し、議論に介入しました。欧州連合の統合問題においても、欧州債務危機におけるアンゲラ・メルケルの指導力への批判や、ジャック・デリダとの共同声明でより緊密なEU統合を呼びかけるなど、積極的な発言を行いました。
彼のアラブ首長国連邦のシェイク・ザーイド・ブック・アワードを辞退したことは、人権と民主主義の価値に対する彼の断固たる姿勢を示すものであり、彼が単なる象牙の塔の学者ではなく、社会の規範的問題に深く関与する倫理的な主体であることを明確にしました。このように、ハーバーマスは学術と政治の間の架け橋となり、民主主義的政治文化を促進する上で大きな貢献を果たしてきました。
11. 参考文献
- Gregg Daniel Miller, 『Mimesis and Reason: Habermas's Political Philosophy』, SUNY Press, 2011年。
- Marvin Rintala, 『Jürgen Habermas: a philosophical-political profile』, Perspectives on Political Science, 2002年。
- Martin Matuštík, 『Jürgen Habermas』, 2001年。
- Martin Matuštík, 『Postnational identity: critical theory and existential philosophy in Habermas, Kierkegaard, and Havel』, 1993年。
- Thomas McCarthy, 『The Critical Theory of Jürgen Habermas』, MIT Press, 1978年。
- Raymond Geuss, 『The Idea of a Critical Theory』, Cambridge University Press, 1981年。
- J.G. Finlayson, 『Habermas: A Very Short Introduction』, Oxford University Press, 2004年。
- Jane Braaten, 『Habermas's Critical Theory of Society』, State University of New York Press, 1991年。
- Thomas Kupka, 「Jürgen Habermas' diskurstheoretische Reformulierung des klassischen Vernunftrechts」, 『Kritische Justiz』 27巻 (1994年), pp. 461-469。
- Andreas Dorschel, 「Handlungstypen und Kriterien. Zu Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns」, 『Zeitschrift für philosophische Forschung』 44巻 (1990年), 第2号, pp. 220-252。
- Erik Oddvar Eriksen and Jarle Weigard, 『Understanding Habermas: Communicative Action and Deliberative Democracy』, Continuum International Publishing, 2004年。
- Detlef Horster, 『Habermas: An Introduction』, Pennbridge, 1992年。
- Martin Jay, 『Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukacs to Habermas』 (Chapter 9), University of California Press, 1986年。
- Ernst Piper (ed.), 『Historikerstreit: Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistschen Judenvernichtung』, Piper, 1987年 (英訳版: James Knowlton and Truett Cates訳, 『Forever In The Shadow Of Hitler?: Original Documents Of the Historikerstreit, The Controversy Concerning The Singularity Of The Holocaust』, Humanities Press, 1993年)。
- Andrew Edgar, 『The Philosophy of Habermas』, McGill-Queen's UP, 2005年。
- Nicholas Adams, 『Habermas & Theology』, Cambridge University Press, 2006年。
- Mike Sandbothe, 『Habermas, Pragmatism, and the Media』, sandbothe.net, 2008年 (ドイツ語原著: Michael Funken編, 『Über Habermas. Gespräche mit Zeitgenossen』, Primus, 2008年)。
- Stefan Müller-Doohm, 『Jürgen Habermas』, Suhrkamp, 2008年。
- Knut Wenzel and Thomas M. Schmidt (Hrsg.), 『Moderne Religion? Theologische und religionsphilosophische Reaktionen auf Jürgen Habermas』, Herder, 2009年。
- Luca Corchia, 『Jürgen Habermas. A bibliography: works and studies (1952-2013)』, Arnus Edizioni - Il Campano, 2013年。
- Luca Corchia, 『Jürgen Habermas. A Bibliography. 1. Works of Jürgen Habermas (1952-2018)』, Department of Political Science, University of Pisa (Italy), 2018年。
- Luca Corchia, 『Jürgen Habermas. A bibliography. 2. Studies on Jürgen Habermas (1962-2015)』, Department of Political Science, University of Pisa (Italy), 2016年。
- Peter Koller, Christian Hiebaum, 『Jürgen Habermas: FaktizitätとGeltung』, Walter de Gruyter, 2016年。
- Bertens, 『Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman』, Gramedia, 2002年。
- Listiyono (dkk), 『Epistemologi Kiri』, AR-Ruzzmedia, 2007年。
- Budi Hardiman, 『Kritik Ideologi』, Penerbit Kanisius, 2009年。
- F.Budi Hardiman, 『Menuju Masyarakat Komunikatif』, Penerbit Kanisius, 2009年。
- Franz Magnis Suseno, 『Pijar-Pijar Filsafat』, Penerbit Kanisius, 2005年。
- Fresco Budi Hardiman, 『Demokrasi Deliberatif』, Penerbit Kanisius, 2009年。
- Budi Hardiman, 『Ruang Publik』, Penerbit Kansius, 2010年。
- 中岡成文, 『ハーバーマス: コミュニケーション行為 現代思想の冒険者たち27』, 講談社, 1996年。
- 山口節郎, 「批判理論と社会システム理論:ハーバーマス/ルーマン論争」, 『社会・経済システム』 2巻 (1984年), pp. 7-12。
- 徐道植, 「ハバーマス『認識と関心』」, (オンライン資料)。
- 河相福, 『フーコー&ハーバーマス- 狂気の時代 コミュニケーションの理性』, 金英社, 2009年。
- Walter Reese-Schäfer, 『ハーバーマス』 (善于賢訳), 葛廩, 1998年。
- 文聖勳, 『ハーバーマスが語るコミュニケーション物語』, 子音と母音, 2008年。
- ユルゲン・ハーバーマス, 『政治文化の現実とコミュニケーション的社会批判理論:ハーバーマス政治時事評論選集』 (洪基洙訳), 文藝マダン, 1996年。
- 尹平重, 『フーコーとハーバーマスを越えて』, 教保文庫, 1997年。
12. 外部リンク
- [http://www.habermasforum.dk/ Habermas Forum] by Thomas Gregersen; updated bibliography, news and literature on Habermas
- [http://www.signandsight.com/features/676.html 『Towards a United States of Europe』], by Jürgen Habermas, at signandsight.com, published 27 March 2006
- [http://www.signandsight.com/features/1349.html 『How to save the quality press?』] Habermas argues for state support for quality newspapers, at signandsight.com, published 21 May 2007
- [https://web.archive.org/web/20110618001410/http://www.helsinki.fi/~amkauppi/hablinks.html Habermas links collected by Antti Kauppinen (writings; interviews; bibliography; Habermas explained, discussed, reviewed; and other Habermas sites; 『updated 2004』)]
- [https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention by Douglas Kellner]
- [https://web.archive.org/web/20070216033930/http://filer.case.edu/~ngb2/Authors/Habermas.html Jurgen Habermas, On Society and Politics]
- [https://web.archive.org/web/20080203161418/http://www.stanford.edu/dept/complit/cgi-bin/?q=node%2F222 Juergen Habermas gives Memorial Lecture] in honor of American Philosopher, Richard Rorty on 2 November 2007 5pm Cubberley Auditorium, at Stanford University. Transcript available [https://web.archive.org/web/20071104173604/http://www.telospress.com/main/index.php?main_page=news_article&article_id=204 here].
- [http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/066649.html Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida]
- 徳永恂 [http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%83%8F%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9/ 「ハバーマス」(Yahoo!百科事典)]