1. オーストリアでの生い立ちと教育
マリア・レオポルディナは、オーストリア・ハプスブルク家の一員として生まれ育ち、幅広い教育を受けた。
1.1. 出生と両親

マリア・レオポルディナは1797年1月22日、オーストリア大公国のウィーンにあるホーフブルク宮殿で生まれた。彼女は神聖ローマ皇帝フランツ2世(1804年からはナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝に即位した際、神聖ローマ皇帝の称号放棄を求めたため、オーストリア皇帝フランツ1世となった)と、その二番目の妻であるナポリ・シチリア王女マリア・テレジアの六番目の子(生存した子としては三番目)であり、彼女の両親の二度目の結婚から生まれた子としては五番目(生存した子としては三番目)、女子としては四番目(生存した女子としては二番目)である。
彼女の父方の祖父母は神聖ローマ皇帝レオポルト2世とスペイン王女マリア・ルイーサで、母方の祖父母はナポリ・シチリア王フェルディナンド4世・3世(後の両シチリア王フェルディナンド1世)とオーストリア大公女マリア・カロリーナである。両親(重従兄妹同士である)を通じて、マリア・レオポルディナはハプスブルク・ロートリンゲン家(1282年から1918年までオーストリアなどを統治し、マリア・レオポルディナの誕生時にはヨーロッパで最も古い現存する統治家系であった)と、ブルボン家(彼女の誕生時にスペイン、ナポリ、シチリア、パルマを統治していた王家で、フランスを1589年から統治していた主要な家系はフランス革命後の1792年に廃位されたが、1814年から1830年の間に短期間復興した)の双方の血を引いている。
彼女はカルロス・H・オベラッカー・ジュニアの著書『女帝レオポルディナ:彼女の生涯と時代』によれば「カロリーネ・ヨーゼファ・レオポルディーネ・フランツィスカ・フェルディナンデ」と名付けられた。これはベッティーナ・カンンの著書『ある女帝の手紙』などによっても確認されている。オベラッカー・ジュニアは、1797年1月25日のオーストリアの新聞『ウィーナー・ツァイトゥング』の抜粋を提示しており、それには大公女のフルネームで出生が報じられている。彼はまた、保存されている洗礼記録には「マリア」という名前が含まれていないことにも言及しており、これは事実である。オベラッカー・ジュニアによれば、大公女はブラジルへの航海中に個人的な取引を行う際にすでにこの名前を使い始めていたという。ブラジルでは、彼女はレオポルディナ、あるいは1822年のブラジル憲法への宣誓に見られるように、マリアというファーストネームのみで署名するようになった。オベラッカー・ジュニアが提示した別の説によると、大公女は聖母マリアへの深い信仰から、そしてその庇護を願うために「マリア」という名前を使い始めた可能性があり、また義理の姉妹たちが皆この名前を使っていたためでもあるという。
マリア・レオポルディナはヨーロッパ史の激動期に生まれた。1799年、ナポレオン・ボナパルトが第一統領となり、後に皇帝に即位した。彼はその後、ナポレオン戦争と呼ばれる一連の紛争を開始し、ヨーロッパ大陸の国境を頻繁に再定義する「同盟」システムを構築した。オーストリアは、歴史的な敵であるフランスとの全てのナポレオン戦争に積極的に参加した。ナポレオンはヨーロッパの旧王室制度を揺るがし、神聖ローマ帝国では激しい戦いが始まった。彼女の姉である大公女マリア・ルドヴィカは1810年にナポレオンと結婚し、フランスとオーストリアの関係強化を図った。この同盟は疑いなくハプスブルク家にとって最も深刻な敗北の一つであった。彼女たちの母方の祖母であるナポリ・シチリア王妃マリア・カロリーナ(1793年に最愛の妹マリー・アントワネットが処刑された後、フランスに関する全てを深く憎んでいた)は、義理の息子の態度に不満を漏らした:「まさしく私が欠けていたこと、悪魔の祖母になることだ」。
1.2. 教育


1807年4月13日、10歳のマリア・レオポルディナ大公女は出産合併症で母を亡くした。一年後の1808年1月6日、父はマリア・レオポルディナが後に人生で最も重要な人物と語るマリア・ルドヴィカ・フォン・エスターライヒ=エステと再婚した。
夫の従姉妹であり、マリア・テレジア女帝の孫娘である新しい皇后は、教養豊かで、文化と知的な輝きにおいて前任者を凌駕していた。詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテのミューズであり個人的な友人でもあった彼女は、マリア・レオポルディナの知的な形成に責任を持ち、ヨーゼフ・ハイドンやルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの文学、自然、音楽への興味を育んだ。彼女自身には子供がいなかったため、前任者の子供たちを喜んで養子とした。マリア・レオポルディナは義母を常に実母のように慕い、マリア・ルドヴィカ皇后を「精神的な母」として育った。彼女のおかげで、大公女は1810年と1812年に義母とカールスバートに行った際にゲーテと会う機会を得た。
マリア・レオポルディナは、ハプスブルク家の3つの原則である「規律」「信仰」「義務感」に従って育てられた。彼女の幼少期は、厳格な教育、多様な文化的刺激、そして父の領土を脅かす相次ぐ戦争によって特徴づけられた。彼女と兄弟たちは、祖父のレオポルト2世が定めた教育原則に従って育てられた。レオポルト2世は、人々の間の平等を説き、全ての人を丁寧に扱い、慈善の実践の必要性、そして何よりも国家の必要性のために自己の欲望を犠牲にすることを説いた。これらの原則の中には、以下の文章を書写して筆記を練習する習慣があった。
「貧しい人々を抑圧するな。慈善を施せ。神が与えたものに不平を言うな、しかし己の習慣を改善せよ。我々は善人となるために真剣に努力しなければならない。」
マリア・レオポルディナと兄弟たちの学習プログラムには、読み書き、ダンス、絵画、ピアノ、乗馬、狩猟、歴史、地理、音楽などの科目が含まれていた。さらに上級のモジュールでは、数学(算術と幾何学)、文学、物理学、歌唱、工芸が含まれた。幼少期からマリア・レオポルディナは、自然科学の分野、特に植物学と鉱物学に強い関心を示した。この事実は彼女の教師たちや父であるオーストリア皇帝フランツ1世の目にも留まり(彼らはこのような傾向が彼女の兄弟のいずれかに現れるのがより自然だと考えていたため、若い大公女の興味に驚いたが)、彼女の学習を妨げることはなかった。
大公女は父から収集の習慣も受け継いだ。彼女は硬貨、植物、花、鉱物、貝殻のコレクションを始めた。1816年10月から12月の間に、彼女はポルトガル語を急速に習得した。12月には、大公女はすでにポルトガル外交官と流暢に話しており、「ブラジルの地図とこの王国の歴史またはそれに関連する記録を含む本に囲まれて」暮らしていた。言語学習は家族の形成の一部であり、レオポルディナは著名な多言語話者となり、母国語のドイツ語のほか、ポルトガル語、フランス語、イタリア語、英語、ギリシア語、ラテン語の7か国語を話した。
レオポルディナと彼女の兄弟たちは、博物館、植物園、工場、農場へ頻繁に連れて行かれた。また、子供たちに儀式や公衆の場に慣れさせる目的で、ダンスに参加したり、演劇で演じたり、観客のために楽器を演奏したりすることも珍しくなかった。ハプスブルク家の皇帝や皇女たちは、人前で話す能力、より優れた発音、弁論術を養うために劇場を訪れることを奨励された。
2. 結婚交渉とブラジルへの到着
マリア・レオポルディナとペドロの結婚が戦略的同盟として交渉され、彼女のブラジルへの困難な航海と、それに伴う科学探査隊の活動が描かれる。
2.1. 結婚交渉と挙式
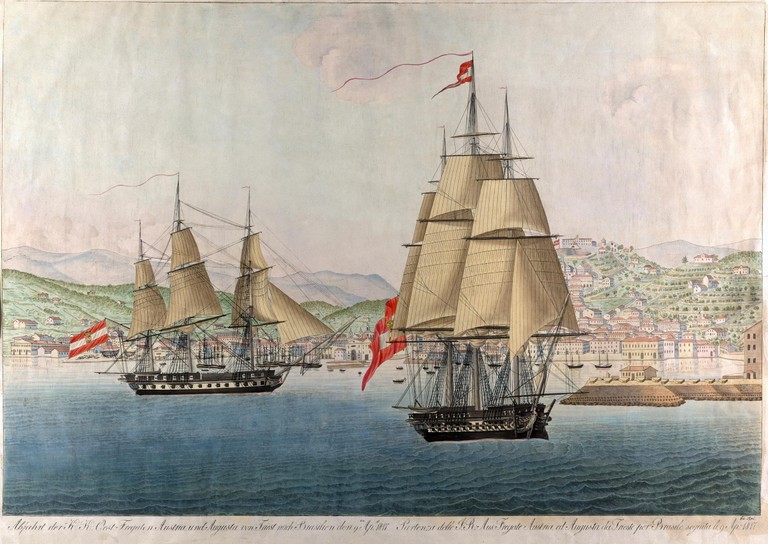
何世紀にもわたり、ヨーロッパの王室結婚は主に政治的同盟として機能した。結婚を通じて、ヨーロッパ大陸の地政学的地図は、王家間の共通の利益と連帯の複雑な網によって形作られた。マリア・レオポルディナとポルトガル、ブラジル及びアルガルヴェス連合王国の王太子ペドロ・デ・アルカンタラとの結婚は、ポルトガルとオーストリアの君主制間の戦略的同盟であった。この同盟により、ハプスブルク・ロートリンゲン家は有名な格言「Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube」(他者に戦争をさせよ、汝、幸いなるオーストリアよ、結婚せよ)を成就させた。
1816年9月24日、フランツ1世皇帝により、ペドロ・デ・アルカンタラがハプスブルク家の大公女を妻に迎えることを望んでいると発表された。クレメンス・フォン・メッテルニヒ公は、マリア・レオポルディナが「妻になる番」であるため、彼女が結婚すべきだと提案した。マリアルヴァ侯爵は、結婚交渉において大きな役割を果たした。彼はかつてアレクサンダー・フォン・フンボルトの助言を受けてフランス美術使節団のブラジル来訪を交渉した人物である。ポルトガル国王ジョアン6世は、交渉にインファンタ・ドナ・イザベル・マリア(1826年から1828年までポルトガル王国の摂政を務め、未婚のまま亡くなる)を含めるためにあらゆる努力をした。マリアルヴァ侯爵は、ブラジルが「スペイン植民地で進行していた独立戦争の炎から確実に逃れた」ことを証明すれば、ポルトガル王家は大陸に帰還する決意をしていると保証し、これによりオーストリアの結婚の同意を得た。これが確約されると、1816年11月29日にウィーンで契約が署名された。
2隻の船が準備され、1817年4月には科学者、画家、庭師、剥製師、そしてその助手たちがマリア・レオポルディナに先立ってリオデジャネイロへと旅立った。その間、マリア・レオポルディナは未来の居住地の歴史と地理を学び、ポルトガル語を習得した。これらの数週間で、大公女は『ヴァデメクム』という、他のハプスブルク家の王女からはこれまでに作成されたことのないユニークな文書を編纂し、執筆した。
マリア・レオポルディナとペドロの代理結婚式は、1817年5月13日にウィーンのアウグスティナー教会で行われた。花婿は花嫁の叔父であるテシェン公カールが代理を務めた。
「結婚式の頂点はウィーンのアウガルテンで、6月1日にマリアルヴァは、彼の国の輝き、富、もてなしを披露する機会がほとんどなかったにもかかわらず、冬の間ずっと準備を進めていた豪華なレセプションを催した。結婚式の少し前、2隻のオーストリアフリゲート艦『アウストリア』と『アウグスタ』はリオデジャネイロへ向かい、新しく設立されたオーストリア大使館の家具や装飾品、ブラジル内陸への科学探検のための装備、そして多数のオーストリア商業製品の展示品を運んだ。」
この結婚を通じて、ジョアン6世は伝統的な王朝との新たな同盟を築くことで、領土におけるイギリスの過度な影響力を打ち消す機会を見た。一方、オーストリアは、新しいポルトガル・ブラジル帝国を、神聖同盟の反動的、絶対主義的な理想に完璧に合致する重要な大西洋同盟国と見なした。このようにして、この結婚は純粋に政治的な行為であり、感情的なものではなかった。
2.2. 大西洋横断と科学探査隊

マリア・レオポルディナのブラジルへの旅は困難で時間がかかった。大公女は1817年6月2日にウィーンを発ち、フィレンツェへ向かった。そこで、ポルトガル宮廷からのさらなる指示を待った。当時のブラジルでは、ペルナンブーコ反乱以来、君主制の権威が不安定であったためである。
1817年8月13日、マリア・レオポルディナはついにリヴォルノ(イタリア)から、ポルトガル艦隊の「D. João VI」号と「São Sebastião」号に乗船することが許可された。彼女は荷物と大勢の随行員とともに、86日間におよぶ大西洋横断に臨んだ。人間の背丈ほどの大きさの箱が40個あり、そこには彼女の衣装、書物、コレクション、そして将来の家族への贈り物が詰められていた。彼女はまた、印象的な規模の従者を引き連れていた。女官、女中頭、執事、6人の女官、4人の小姓、6人のハンガリー貴族、6人のオーストリア衛兵、6人の侍従、総施し長、司祭、秘書官、医師、演奏家、鉱物学者、そして彼女の絵画教師である。大公女は2日後の8月15日にブラジルへ向け出発した。乗船時からすでに気づかれていた習慣や風俗の違いは、彼女がリオデジャネイロで直面するであろう困難を予兆させるものであった。しかし、彼女が初めてポルトガル領に足を踏み入れたのは、ブラジルではなく、9月11日のマデイラ島であった。

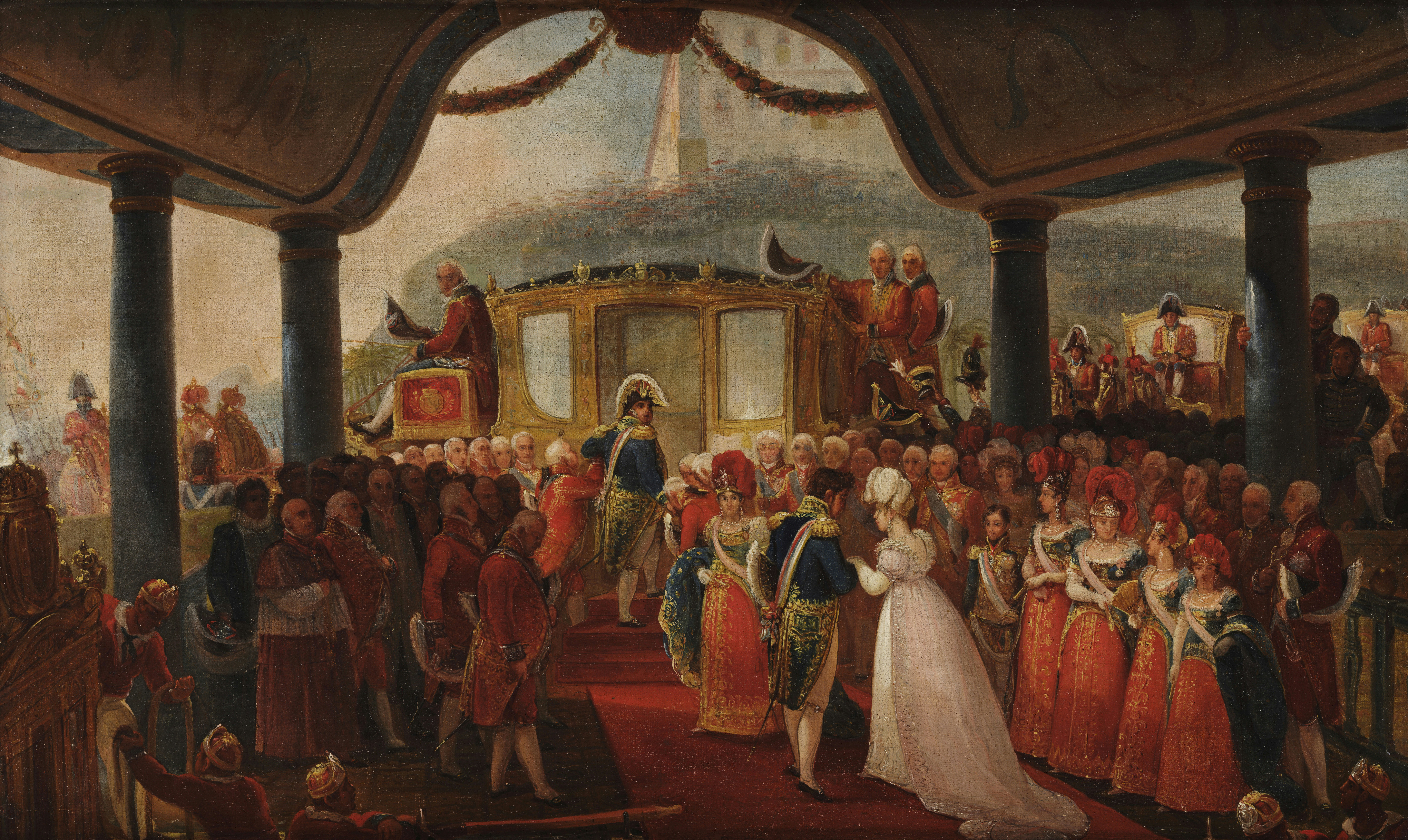
1817年11月5日、マリア・レオポルディナはリオデジャネイロに到着し、ついに夫とその家族に会った。翌日、リオデジャネイロ大聖堂のカペラ・レアルで正式な結婚式が市を挙げての祝賀ムードの中で執り行われた。
彼女の到着時、マリア・レオポルディナの容姿は、美しい大公女を期待していたポルトガル王室を驚かせた。彼女は太っていたが、美しい顔立ちをしていた。しかし、彼女は当時の女性としては並外れて教養があり、植物学に強い関心を持っていた。彼女の到着はジャン=バティスト・デブレに最初の依頼を与え、彼は12日間で市を装飾する任務を負った。彼はカトゥンビ地区にスタジオを構え、後に自然主義者として、マリア・レオポルディナのために植物や花の絵を描いた。彼は「私は、かつてのフランス女帝である彼女の妹の名において、彼女が敢えて依頼したいくつかの絵を優雅に描くことを担当した」と語っている。彼の工房で、デブレは緑と金色の宮廷の豪華な制服、新しい国家の装飾品をデザインし、以前には1806年にイタリア王国のためにナポレオンが作成した王冠もデザインした。デブレはまた、南十字星勲章の記章(レジオンドヌール勲章に匹敵する)もデザインし、数年後にはペドロの2番目の妻であるロイヒテンベルク公女アメリーを称えるために制定された薔薇勲章もデザインした。
遠くから見ると、ポルトガル王太子は当初、彼の新しい妻には完璧で教養のある紳士に見えたが、現実は大きく異なっていた。ペドロはマリア・レオポルディナより1歳年下で、仲人から聞かされた描写にはめったに合致しなかった。彼の気質は衝動的で短気であり、教育も控えめであった。若い夫婦間の口頭でのコミュニケーションさえ困難であった。なぜなら、ペドロはフランス語をほとんど話さず、彼のポルトガル語は粗野としか言いようがなかったからである。さらに、ポルトガルの伝統に従い、18歳のペドロは、過去に多くの恋愛遍歴を持ち、主に競馬と色恋沙汰に関心があるだけでなく、結婚時にはフランス人ダンサーのノエミ・ティエリーとまるで結婚しているかのように暮らしており、マリア・レオポルディナがリオデジャネイロに到着してから1ヶ月後に、彼の父によってついに宮廷から追放された。
若い夫婦はサン・クリストヴァン宮殿の比較的狭い6つの部屋に住み始めた。中庭や馬小屋への道は舗装されておらず、熱帯の雨が全てをすぐに泥に変えた。どこにでも虫がおり、衣服の中にもいた。ベルベットやプラッシュ製の制服や宮廷の儀礼服は熱と湿気で腐り、カビが生えた。メッテルニヒ公爵は、エシュヴェーゲ男爵からウィーンの彼のパートナーへの手紙を傍受し、その中で彼は次のように述べている:「王太子について言えば、彼は生まれつきの知性がないわけではないが、正式な教育が不足している。彼は馬に囲まれて育ち、プリンセスは遅かれ早かれ、彼が調和して共存できないことに気づくだろう。さらに、リオの宮廷はヨーロッパの宮廷と比べて非常に退屈で取るに足らない。」
マリア・レオポルディナの到着を機に、移民の第一波がブラジルに到着した。スイス人入植者は宮廷の近くに定住し、ノヴァ・フリブルゴを建設し、後に皇帝の夏の離宮となるペトロポリスに定住した。1824年からは、ゲオルク・アントン・シェッファー少佐が組織したヨーロッパでのブラジルキャンペーンにより、ドイツ人がより多く到着し、再びノヴァ・フリブルゴやサンタカタリーナ州およびリオグランデ・ド・スル州の温帯地域に定住し、新しい王女を称えてサン・レオポルド植民地が設立された。ポメラニアからの入植者の中にはエスピリトサント州へ行った者もおり、1880年代まで完全な孤立状態で暮らしていたため、ポルトガル語さえ話さなかった。
ブラジルは、他のアメリカ大陸の国々よりもはるかに早く、ヨーロッパの著名な芸術家や科学者によって描写され、研究されるという特権を得た。17世紀、ブラジル北東部のオランダ占領の文脈で、ナッサウ=ジーゲン公ヨハン・マウリッツは、熱帯病の研究に来た医師ヴィレム・ピーソ、当時20代前半の有名な画家フランス・ポスト、同じく画家であるアルベルト・エックハウト、地図製作者コルネリウス・ゴリアート、そしてピーソと共にブラジル自然に関する最初の科学書『ブラジル自然史』(アムステルダム、1648年)の著者となる天文学者ゲオルク・マルクグラフなど、かなりの数の協力者をブラジルに連れてきた。ナッサウ=ジーゲン公はまた、カスパー・バルラエウスにブラジルでの統治の歴史を委ねて、自身の行政の政治的出来事を永続させることにも関心を持っていた。
オランダが追放されると、ポルトガルは、領土の回復が一連の幸運な状況の結果であり、ポルトガル領アメリカへの新たな侵攻の場合には繰り返すことができないことに気づいた。この状況を鑑み、ポルトガルは、17世紀半ばから王室がブラジルに到着し、プリンス・リージェント・ジョンがサルバドール滞在中の1808年に署名した最初の法令である友好的諸国への港開放令によって象徴されるブラジルの世界への開放まで、その海外領土への外国人のアクセスを禁止し、アメリカ大陸に関するいかなるニュースや言及の出版も禁止するという国家政策をとった。
港の開放とそれに伴うブラジル領への外国人上陸禁止の撤廃は、ヨーロッパの博物学者にとって困難な時期と重なった。彼らのヨーロッパ内での移動はナポレオン戦争によって著しく妨げられていたからである。さらに、この広大な地球の領土に関する知識の不足も相まって、ヨーロッパで多大な科学的関心を引き起こした。この世界的背景と並行して、マリア・レオポルディナは幼少期(約14歳)から自然科学、特に地質学と植物学に特別な関心を示し始めた。この事実は彼女の教師たちや父であるオーストリア皇帝フランツ1世の目にも留まらなかったわけではない(彼らはそのような傾向が彼女の兄弟のいずれかに現れるのがより自然だと考えていたため、若い大公女の興味に驚いたが)、しかし若いマリア・レオポルディナの学習を妨げることはなかった。

そのため、1817年にマリア・レオポルディナとペドロの結婚が間近に発表されると、すぐにオーストリア宮廷の支援のもと(ただしバイエルン出身の科学者も含まれていた)、それまで科学にとって未知のブラジル領への主要な科学探検隊が組織された。
1815年、バイエルン王マクシミリアン1世はすでに南アメリカを横断する大規模な科学探検隊を計画していたが、いくつかの問題が発生し、探検は実行されなかった。そこで1817年、マリア・レオポルディナがペドロとの結婚のためにブラジルへ出発する際、バイエルン王はこれを機に、彼の臣民である医師・植物学者カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスと動物学者ヨハン・バプティスト・フォン・シュピックスを大公女の随行員として派遣した。
これらに加え、ウィーン自然史博物館の館長カール・フォン・シュライバースは、メッテルニヒ公爵の命令を受けて、大公女の随行員となる著名な科学者たちを招集した。その中には、植物学者・昆虫学者ヨハン・クリスティアン・ミカン、医師・鉱物学者・植物学者ヨハン・バプティスト・エマヌエル・ポール、植物画家ヨハン・ブフベルガー、動物学者ヨハン・ナッテラー、画家トマス・エンダー、庭師ハインリヒ・ヴィルヘルム・ショット、そしてイタリアの博物学者ジュゼッペ・ラッディがいた。このグループは、ウィーンに設立される博物館のために、標本を収集し、人々や風景のイラストを作成することを目的としていた。
最も関心が高かったのは、植物、動物、インディアンの研究を通じて新世界を描写することだった。この大きな魅力は、ドイツの地理学者アレクサンダー・フォン・フンボルトとエメ・ボンプランの著書『新大陸の赤道地域への旅、1799年-1804年』(Le voyage aux régions equinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799-1804)の最初の巻の出版によるものであった。フンボルトはヨハン・モーリッツ・ルゲンダスなど多くの芸術家に影響を与え、彼の研究やフンボルト派の芸術家の際立った特徴は、見たもの全てを百科事典的に、すなわち詳細に説明することであった。
マリア・レオポルディナの科学に対する関心は、1818年に義父を説得して王立博物館(現在のブラジル国立博物館)を設立させたことで注目された。ブラジルに到着してわずか数ヶ月後には、最初のブラジル自然史博物館も設立され、科学者たちがブラジルを探検することを奨励した。1824年9月、多くの旅を経験し出版実績もあるイギリスの作家マリア・グラハムがボア・ヴィスタに到着し、ペドロとマリア・レオポルディナから友好的な歓迎を受け、当時教育がほとんど顧みられていなかった長女マリア・ダ・グロリアの養育に関して全面的な権限を与えられた。すぐにマリア・レオポルディナと娘の家庭教師の関係は温かい友情へと発展した。さらに、二人は科学に対する共通の興味を持っていた。わずか6週間後、マリア・グラハムはペドロによってその職を解雇され、マリア・レオポルディナを落胆させたが、二人の女性の共通の興味は、マリア・レオポルディナが亡くなるまで彼女たちが親密な関係を保つことを可能にした。彼女たちは、男性優位の世界で生活しているため、得られなかった情報を手に入れたいと望んでいたのである。
3. ブラジル独立運動への関与
ブラジル独立を巡る政治的背景から、摂政としての彼女の政治的影響力、独立宣言への貢献、そしてバイア州での独立過程への関与に至るまでを詳述する。
3.1. 独立を巡る背景

1821年はマリア・レオポルディナの人生において決定的な年となった。ヨーロッパで最も保守的で長く続く家系であるハプスブルク・ロートリンゲン家の一員として、彼女は当時の絶対主義君主制の型に沿った慎重な教育を受けて育った。1821年6月、恐れを抱いたマリア・レオポルディナは父に「夫は、神よ助けたまえ、新しい思想を愛している」と書き送った。彼女は新しい立憲的で自由主義的な政治的価値観に不審を抱いていた。数年前にヨーロッパで起こった出来事を個人的に目撃しており、その中でナポレオン・ボナパルトが組織的に大陸の政治権力を変革し、これらの新しい政治的概念に対する彼女の見方に一定の影響を与えていた。大公女が規律を受けてきた保守的で伝統的な教育もこの側面に加わっている。
愛情と承認に欠けていたマリア・レオポルディナは、すぐに幻想のない人生に立ち向かう成熟した女性へと変化した。ポルトガルとブラジルの間の摩擦が展開するにつれて、彼女はブラジル独立に先立つ政治的混乱にますます深く関与するようになった。ブラジルの政治への彼女の関与は、後にジョゼ・ボニファシオ・デ・アンドラダと共に独立において極めて重要な役割を果たすことになる。この段階で、彼女はウィーン宮廷の保守的(絶対主義的)な考え方から距離を置き、ブラジルの大義のために、より自由主義的(立憲主義的)な言説を採用する。
1820年にポルトガルで起こった自由主義革命の結果、1821年4月25日、宮廷はポルトガルへの帰還を余儀なくされた。11隻の艦隊がジョアン6世国王、宮廷、王室、王室の財宝を大陸へと連れ戻し、ペドロ王子のみが摂政としてブラジルに残り、摂政評議会によって広範な権力が与えられた。当初、新しい摂政は混乱を支配することができなかった。状況はポルトガル軍によって支配され、無政府状態であった。ポルトガル人とブラジル人の間の対立はますます明らかになった。マリア・レオポルディナの書簡からは、彼女がブラジル国民の大義を熱心に支持し、国の独立を願うようになったことが明確に見て取れる。
3.2. 政治的影響力と摂政

マリア・レオポルディナは、フランス革命中にギロチンにかけられた大叔母、最後のフランス王妃であるマリー・アントワネットの例から、民衆革命を恐れて育った。しかし、1789年のフランスや最近の1820年のポルトガルで起こったような、民衆蜂起によって君主の権力が減少する革命への恐れは、ブラジルでは見られなかった。「自治運動、そしてその後の独立運動がペドロとドナ・レオポルディナを主役として獲得すると、ブラジル人は初めて彼らを味方と見なし、権力を放棄するために打ち破るべき暴君とは見なさなかった」。
絶対君主制への忠誠を保つよう教育されたマリア・レオポルディナは、ポルトガルとの決裂に先立つ困難な時期に摂政となることも、受けた教育に明確に反する態度で、ペドロ王子よりも早くブラジル独立を擁護することも想像していなかった。オーストリア大公女は常にブラジル側の大義を支持し、ヨーロッパの友人たちに宛てた数通の手紙で、ポルトガル人とブラジル人を区別し始め、植民地に対するポルトガルの支配について自身の考えを明確にした。宮廷のポルトガルへの帰還とペドロのブラジル摂政への任命(1821年4月25日)により、マリア・レオポルディナは、ハプスブルク家とブラガンサ家のブラジルにおける権力を脅かす自由主義の過剰に対する王朝の正当性を守るには、アメリカに留まることが解決策であると確信した。一方、ペドロは、政治経験がなく、当時の不安定な状況に圧倒され、父に摂政の職を解かれ、家族と共にポルトガルへの帰還を許してくれるよう絶えず懇願していた。1821年9月、ジョアン6世が出発してから6ヶ月後、彼は書いた:「陛下にこの重い任務から解放していただくよう、切に懇願いたします」。
マリア・レオポルディナの滞在への決意は、ジョゼ・ボニファシオ・デ・アンドラダというサンパウロ出身の教養ある男性の支持を得てさらに強固になった。彼の助けを借りて、彼女はブラジルの領土保全は彼ら二人がそこに留まることによってのみ可能であると夫を決定的に説得した。ついに1822年1月9日、ペドロは厳粛に宣言した:「フィコ!」(「私は残る」)。24歳にして、マリア・レオポルディナは、残りの人生で父、兄弟、その他の家族の近くで暮らすことを奪われることになる政治的決断を下した。彼女の姉マリー・ルイーズがナポレオン・ボナパルトと結婚したのが、この結婚を通じてオーストリア帝国とフランス帝国の政治的関係を密接にする意図であったのと同様に、マリア・レオポルディナには姉よりもはるかに重要な歴史的役割が待っていた。
2日後、摂政王子のブラジル残留決定は、コルテス(ブラジル国民の選出された議会代表で、王室全体が国を去り、その後ブラジルが分離した地域に分割されることを望んでいた)の間で憤慨を引き起こした。政府機関や建物が焼かれ、革命が勃発した。ペドロとマリア・レオポルディナはその時劇場にいた。彼が軍を率いてコルテスに対抗する間、マリア・レオポルディナは舞台に上がり、「落ち着いてください、夫がすべてを掌握しています!」と発表した。この発表(歓喜で迎えられた)により、彼女はブラジル国民の側にしっかりと身を置いた。
しかし、マリア・レオポルディナは自身の命が危険に晒されていることを知っていた。彼女は慌ててボア・ヴィスタに戻った。当時妊娠7ヶ月だった彼女は、3歳の娘マリア・ダ・グロリアと11ヶ月の息子ジョアン・カルロスを連れて馬車に乗り込み、危険な12時間の旅を経てサンタ・クルスへ逃げた。政治情勢はすぐに落ち着き、彼女は子供たちとボア・ヴィスタに戻ることができた。しかし、幼いジョアン・カルロス王子は負担から回復することなく、1822年2月4日に亡くなった。
1821年末、マリア・レオポルディナが秘書シェッファーに宛てた手紙は、彼女がその時からペドロよりもブラジルとブラジル人に対して決意を固めていたことを明確に示している。ポルトガル宮廷の要求に逆らってブラジルに留まる必要があったのである。彼女の「フィコの日」は夫よりも早かった。
1822年8月6日にペドロによって署名された友好的諸国への宣言書では、リスボンのコルテスがブラジル問題に関して行った専制政治が非難され、ブラジルの友好的諸国に対し、もはやポルトガル政府ではなくリオデジャネイロと直接問題に対処するよう求め、ブラジル人の視点からその大義と出来事を説明した。しかし、同じ文書では、独立宣言前夜であっても、摂政王子がポルトガルとブラジルの間の関係を解消しようとはしておらず、両国の間の結びつきを守ることも約束していないことが見て取れる。これは非効果的な中立措置であった。なぜなら、1ヶ月後には国は独立するからである。女性は政治環境ではあまり評価されていなかったため、マリア・レオポルディナは「具体的な助言と夫への影響を通じて、自身の征服を達成していた」。ペドロは当初、中立を保ち、コルテスに逆らえばポルトガル王位継承権を失うという懲罰を避けるために、ブラジルの自由という考えとの接触を避けていた。マリア・レオポルディナは、コルテスに支配されたポルトガルはすでに失われたものであり、ブラジルはまだ白紙の状態であり、旧宗主国よりもはるかに重要な将来の大国になる可能性があると認識していた。コルテスの命令が実行されれば、南アメリカのスペイン植民地で起こったように、ブラジルは最終的に何十もの共和国に分裂してしまうだろう。エゼキエル・ラミレスによれば、南部諸州では独立国家としてのブラジル統一の兆候が見られたが、北部はリスボンのコルテスを支持し、地域独立を求めていた。もし摂政王子がその時国を去っていたら、ポルトガルにとってブラジルは失われていただろう。なぜならリスボンのコルテスは、各州と個別に直接連絡を取ろうとすることで、スペインのコルテスが植民地を失う原因となったのと同じ過ちを繰り返していたからである。
ブラジルの利益を擁護するマリア・レオポルディナの態度は、ブラジル独立の際にペドロに宛てた手紙に雄弁に刻まれている。
「できるだけ早く戻ってくる必要があります。私がこれほどまでにあなたの即時帰還を望むのは、愛だけではなく、愛するブラジルが置かれている状況のためです。あなたの存在、多大なエネルギーと厳しさだけが、破滅から救うことができます。」
リオデジャネイロでは、何千もの署名が集められ、摂政がブラジルに留まることを要求した。「ジョゼ・ボニファシオ・デ・アンドラダのポルトガルの傲慢に対する勇敢な態度は、特にサンパウロの南部諸州に存在していた統一への願望を大いに勇気づけた。高度な教育を受けた人々がこの運動を主導した。」「フィコの日」の後、ジョゼ・ボニファシオの指導のもと、新しい内閣が組織され、彼は「厳格な君主主義者」であり、摂政王子はすぐに国民の信頼を得た。1822年2月15日、ポルトガル軍はリオデジャネイロを去り、その出発はブラジルと宗主国との関係解消を意味した。ペドロはミナスジェライスで勝利を収め、歓迎された。
3.3. 独立宣言への貢献
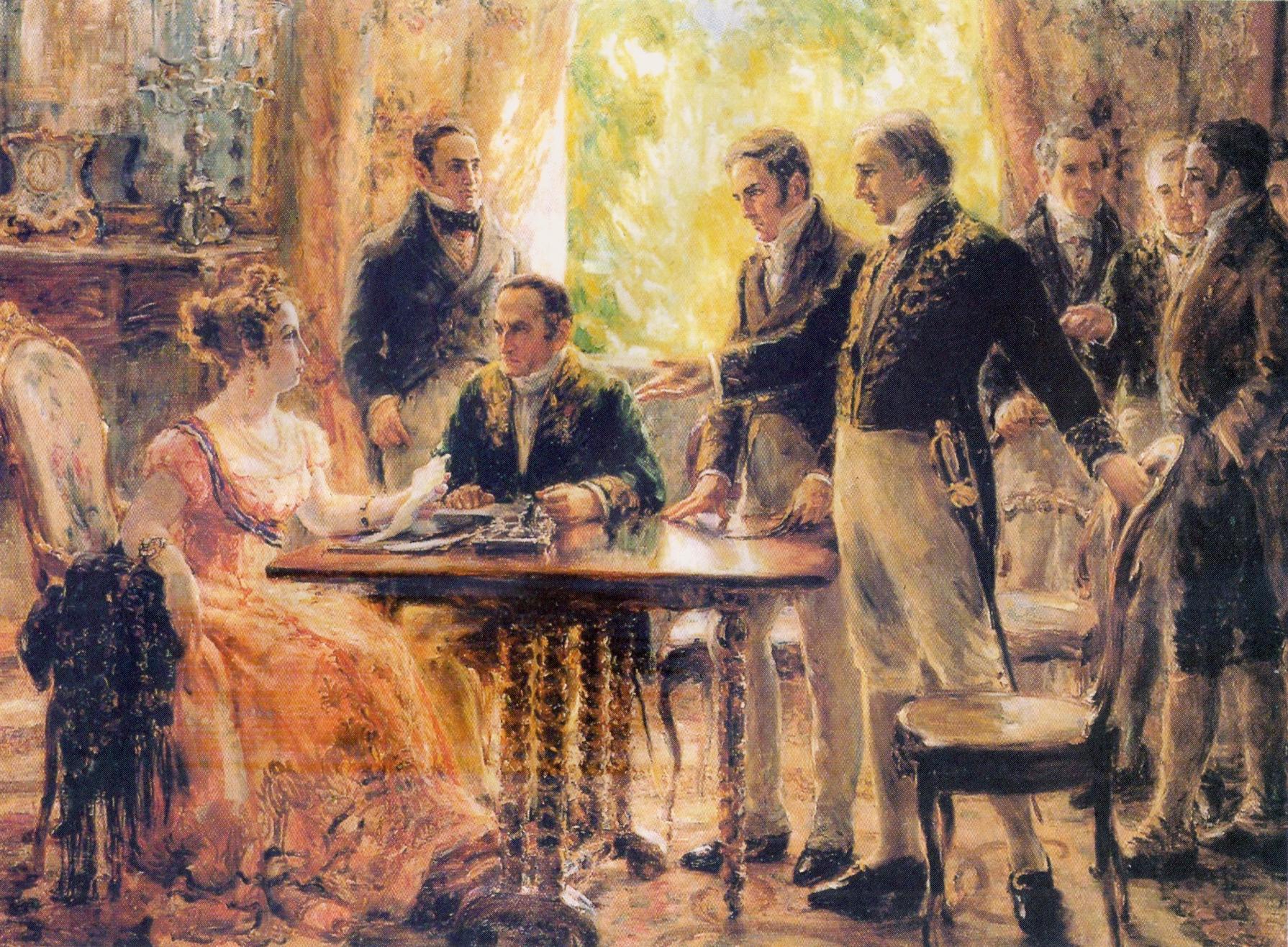
1822年8月に夫がサンパウロへ政治情勢の沈静化のために旅立った際(これは9月のブラジル独立宣言へと繋がった)、マリア・レオポルディナは彼の公式代表、すなわち不在中の摂政に任命された。彼女の地位は1822年8月13日付の受任文書によって確認され、そこにはペドロが彼女を国務会議の長およびブラジル王国の摂政代理に任命し、彼の不在中に必要なあらゆる政治的決定を下す全権を与えると明記されていた。独立の過程における彼女の影響力は大きかった。ブラジル国民はすでに、ポルトガルがペドロを呼び戻し、ブラジルを再びポルトガルと連合した「王国」ではなく、単なる植民地の地位に格下げする意図があることを認識していた。サンパウロ州がブラジルの他の地域から分離される内戦が勃発する恐れがあった。
摂政はリスボンからの新しい要求を含む勅令を受け取った。ペドロの帰還を待つ時間もなく、マリア・レオポルディナはジョゼ・ボニファシオ・デ・アンドラダの助言を受け、暫定的な政府首長としての権限を行使し、1822年9月2日の朝、国務会議を開催し、独立宣言に署名してブラジルをポルトガルから分離すると宣言した。マリア・レオポルディナはペドロに手紙を送り、ジョゼ・ボニファシオからの別の手紙や、夫であるペドロやジョアン6世国王の行動を批判するポルトガルからのコメントも添えた。夫への手紙の中で、摂政は夫にブラジル独立を宣言するよう促し、「果実は熟している、今すぐ摘み取らなければ腐ってしまう」と警告した。
ペドロは1822年9月7日、サンパウロで妻の手紙を受け取り、ブラジル独立宣言を発した。マリア・レオポルディナはリスボンから受け取った書類や、コルテス代理のアントニオ・カルロス・リベイロ・デ・アンドラダのコメントも送っており、ペドロは首都での自身への批判を知った。ジョアン6世とコルテスに支配された全閣僚の立場は困難であった。
夫の帰還を待つ間、すでに独立した国の暫定統治者であったマリア・レオポルディナは、ブラジルの国旗を考案し、そこにはブラガンサ家の緑とハプスブルク家の金色を組み合わせた。他の著者によれば、1820年代にブラジルで見たものをデザインしたフランス人芸術家ジャン=バティスト・デブレが、旧ポルトガル宮廷の象徴である旧体制の抑圧に取って代わる国旗の作者であるという。デブレはジョゼ・ボニファシオ・デ・アンドラダと協力して美しい帝国旗をデザインした。その旗ではブラガンサ家の緑色の長方形が森を、ハプスブルク・ロートリンゲン家の色である黄色の菱形が金を象徴していた。その後、マリア・レオポルディナは、オーストリア皇帝である父やポルトガル王である義父に手紙を書き、新しい国の自治をヨーロッパ諸国に承認させることに深く尽力した。
マリア・レオポルディナはブラジル初の皇后となり、1822年12月1日、夫であるペドロ1世の憲法帝およびブラジル永遠の擁護者としての戴冠式と聖別式でその称号を奉戴された。当時のブラジルは南アメリカで唯一の君主国であったため、マリア・レオポルディナは新世界初の皇后であった。
3.3.1. バイアの独立過程への参加
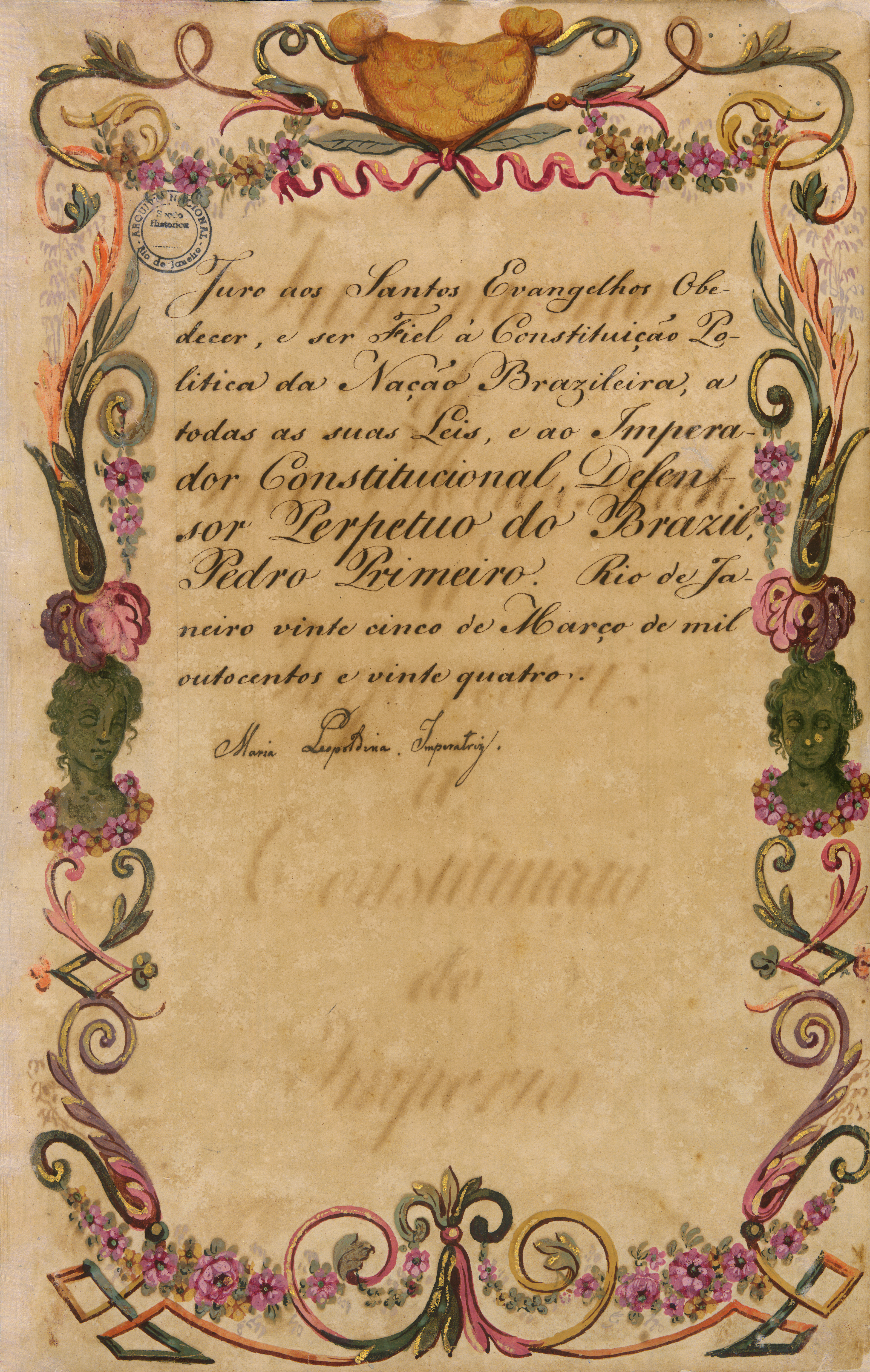
政府の最初の本拠地であり、宗主国の政策の放射中心地であり、戦略的な港であったバイア州は、エスピリトサント州の相続人たる領地で金が発見されるまで、ブラジルにおける特権的な地位を失うことはなかった。そして、バンデイランテスによって鉱床が発見された地域は、この領地から分割され、ミナスジェライス州となった(新たな鉱床が発見されるたびにこの分割は繰り返され、エスピリトサント州は金の密輸に対する不運な防壁としてミナスジェライス州を狭めた)。その後、1776年に首都がリオデジャネイロに移された。サルバドールは、1808年に一時的に滞在した宮廷を、恒久的に歓迎しようとはしなかった。ポルトガルからの分離の過程で、バイア州は対立する潮流を抱えていた。独立派の内陸部と、リスボン宮廷に忠実な州都である。1822年9月7日以降、武装闘争が起こり、1823年7月2日には帝国軍が勝利を収めた。
バイアの女性たちは愛国的な戦いに積極的に参加した。ブラジルの大義に忠実な兵士として秘密裏に入隊したマリア・キテーリアは、マリア・グラハムによって記述され、ペドロ1世皇帝によって南十字星勲章を授与された。イタパリキ島の口頭伝承には、40人以上の黒人女性を率いて島を守ったとされるマリア・フェリパ・デ・オリベイラの役割も記録されている。すでにラパ修道院の修道院長であったジョアナ・アンジェリカ修道女は、自らの命をかけてポルトガル軍の回廊への侵入を防いだ。
女性の政治的意識は、「バイアの婦人たちからレオポルディナ殿下へ」という書簡でも強調されており、これは夫と国を代表して愛国的な決議に貢献した摂政を祝うものである。1822年8月に手渡しで届けられた186人のバイアの婦人からの手紙には、マリア・レオポルディナのブラジル滞在への感謝が表明されていた。摂政は夫に宛てて、政治における女性の存在についての見解を述べ、これらの婦人たちの態度が「女性はより陽気で、良い大義により忠実であることを証明している」と伝えている。政府を再び受け入れることはなかったものの、バイア州はブラジル帝国の地域政治バランスにおいて重要な役割を果たした。独立過程で得られた支援を認識し、皇帝と皇后は1826年2月から3月の間にサルバドールを訪れた。
4. ブラジル皇后とポルトガル王妃
ブラジル初の皇后としての戴冠と、短期間ではあったがポルトガル王妃を兼ねた経緯、そしてそれぞれの役割について解説する。
4.1. ブラジル皇后として
マリア・レオポルディナはブラジル初の皇后となり、1822年12月1日、夫であるペドロ1世の憲法帝およびブラジル永遠の擁護者としての戴冠式と聖別式でその称号を奉戴された。当時のブラジルは南アメリカで唯一の君主国であったため、マリア・レオポルディナは新世界初の皇后であった。
4.2. ポルトガル王妃として


ポルトガル国王ジョアン6世は1826年3月10日に崩御した。その結果、ペドロはポルトガル王位をペドロ4世として継承しつつ、ブラジル皇帝ペドロ1世としての地位も維持した。これにより、マリア・レオポルディナはブラジル皇后とポルトガル王妃を兼ねることとなった。しかし、ブラジルとポルトガルの再統合が両国民にとって受け入れがたいものであることを認識していたペドロは、わずか2ヶ月後の5月2日には、長女マリア・ダ・グロリアにポルトガル王位を急遽譲位し、彼女はマリア2世女王となった。
5. 私生活と家族
夫ペドロ1世との複雑な関係と、彼女がもうけた子供たちについて詳述する。
5.1. ペドロ1世との関係
皇帝のサントス侯爵夫人ドミティラ・デ・カストロ・カント・エ・メロとのスキャンダラスな関係、私生児の公的な認知、愛人を皇后の女官長に任命したこと、そして1826年初頭に皇帝夫妻がサントス侯爵夫人と共にバイアへ旅行したことなどは、マリア・レオポルディナを完全に辱め、精神的・心理的に打ち砕く出来事であった。皇帝が1824年5月に愛人との間に儲けた娘(皇后も3ヶ月後に子を産んだばかりであった)は、彼によって公式に嫡出子とされ、イザベル・マリア・デ・アルカンタラ・ブラジレイラと名付けられ、公女の称号と「殿下」の敬称が与えられた。姉のマリー・ルイーズへの手紙で、皇后は「誘惑的な怪物こそが私のすべての不幸の原因です」と述べている。孤独で孤立し、ただ王位継承者(後のペドロ2世は1825年に誕生する)を産むことに専念していたマリア・レオポルディナは、ますます鬱病に陥っていった。1826年11月の初めから、皇后の健康は急速に衰え、痙攣、嘔吐、出血、錯乱が頻繁に見られるようになり、新たな妊娠によってさらに悪化した。
マリア・レオポルディナはブラジル国民全体から愛され、彼女の人気はペドロよりもさらに大きく、表現力豊かなものであった。リオデジャネイロの人々は皇后の病状の深刻さを注視し始めた。プロイセン王国の大使テュレミムは、皇后への公衆の愛情表現についてベルリンの宮廷に敬意を込めて報告した。
「民衆の間の困惑は言葉では言い表せないほどだった。これほど一致した感情はこれまで見られたことがない。人々は文字通りひざまずいて、皇后の無事を全能の神に懇願していた。教会は空になることはなく、家庭の礼拝堂では皆ひざまずいていた。男性たちは行列を組んだが、それは普段はほとんど笑いを誘うような習慣的なものではなく、真の信仰心によるものだった。要するに、これほど予期せぬ愛情が、偽りなく現れたことは、病気の皇后にとって真の満足であったに違いない。」
1826年12月7日、『ディアリオ・フルミネンセ』紙は、リオデジャネイロの人々が「苦悩の様子で、常に皇后の『痛ましい状態』を知ろうとし続けている」と報じた。
「速報に関して言えば、すでに直接宮廷に赴き、身分を問わず、老若男女、国民、外国人、富者も貧者も入り混じり、目に涙を浮かべ、顔をうつむかせ、心が苦しさと不安で満たされながら、皆が同じ質問をしている--皇后様はいかがでございますか?」
前日の午後(12月6日)、同じ新聞が報じたところによると(後にサンパイオ神父の説教でも確認された)、それぞれの教会から「聖なる像」を伴う数多くの行列が帝国礼拝堂を目指していた。サンパイオ神父によると、
「サン・クリストヴァン宮殿の入り口で、これほど多くの人が集まるのはかつてなかった。馬車は押しつぶされ、誰もが涙を流しながら走っていた。しかし、市中心部では、祈りの行列が、それぞれの像を伴い、聖職者全員(正規、非正規問わず)の付き添いのもと、巡行していた。人々は、普段は決して聖堂を離れない、そして今回初めて、大雨の中、皇后を訪問するかのようにやって来たノッサ・セニョーラ・ダ・グロリアの像を、公に信仰心を示すことなく見ることはできない。皇后は毎週土曜日にその祭壇の足元に現れたのだから......要するに、最も深く信仰されている聖人像を帝国礼拝堂に持っていかなかった修道会は一つもなかった。」
6. 子供たち

1818年6月までにマリア・レオポルディナは妊娠し、1819年4月4日に難産の末に長女マリア・ダ・グロリアが生まれた。次の妊娠は1819年11月に流産に終わり、1820年4月26日には二度目の流産を経験した。この時の子は息子で、ミゲルにちなんでミゲルと名付けられたが、すぐに亡くなった。これらの妊娠失敗はマリア・レオポルディナに深い影響を与え、彼女はブラガンサ家の世継ぎを産むという自身の第一の義務を認識し、鬱病に陥り一時的に社交界から身を引いた。最初の生存する息子、ベイラ公ジョアン・カルロスは1821年3月6日に生まれ、宮廷と人々の喜びとなったが、1822年2月4日に生後11ヶ月で亡くなった。その後の3度の妊娠では、ジャヌアリア(1822年3月11日生)、パウラ(1823年2月17日生)、フランシスカ(1824年8月2日生)の3人の娘が生まれた。そして、待ち望んだ息子で世継ぎである、後のペドロ2世が1825年12月2日に生まれた。彼女の9回目となる最後の妊娠が彼女にとって命取りとなり、流産による合併症で亡くなった。
| 名前 | 肖像 | 生没年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マリア2世 |  | 1819年4月4日 - | 1826年から1853年までポルトガル女王。マリア2世の最初の夫、ロイヒテンベルク公アウグストは結婚数ヶ月後に亡くなった。二度目の夫はザクセン=コーブルク=ゴータ公フェルディナントで、彼らの最初の子が生まれた後、ポルトガル王フェルナンド2世となった。この結婚から11人の子供をもうけた。マリア2世は弟ペドロ2世の皇女として推定相続人であったが、1835年10月30日の法律第91号によりブラジル継承順位から除外された。 |
| ミゲル、ベイラ公 | 1820年4月26日 | 生まれた時から亡くなるまでベイラ公であった。 | |
| ベイラ公ジョアン・カルロス | 1821年3月6日 - | 生まれた時から亡くなるまでベイラ公であった。 | |
| ジャヌアリア |  | 1822年3月11日 - | 両シチリア王フランチェスコ1世の息子、アクイラ伯ルイジ王子と結婚。この結婚から4人の子供をもうけた。1822年6月4日にポルトガルのインファンタとして公式に承認されたが、後にブラジル独立後、ポルトガル継承順位から除外されたと見なされた。 |
| パウラ |  | 1823年2月17日 - | 9歳で死亡、おそらく髄膜炎が原因。ブラジル独立後にブラジルで生まれたため、パウラはポルトガル継承順位から除外された。 |
| フランシスカ |  | 1824年8月2日 - | フランス王ルイ・フィリップ1世の息子、ジョアンヴィル公フランソワ王子と結婚。この結婚から3人の子供をもうけた。ブラジル独立後にブラジルで生まれたため、フランシスカはポルトガル継承順位から除外された。 |
| ペドロ2世 |  | 1825年12月2日 - | 1831年から1889年までブラジル皇帝。両シチリア王フランチェスコ1世の娘、テレーザ・クリスティーナと結婚。この結婚から4人の子供をもうけた。ブラジル独立後にブラジルで生まれたため、ペドロ2世はポルトガル継承順位から除外され、父の退位時にポルトガル王ペドロ5世とはならなかった。 |
7. 健康悪化と死
マリア・レオポルディナの晩年の健康状態、その死因を巡る論争、そして死に対する人々の反応と追悼について詳述する。
7.1. 死因と状況
ブラジル初代皇后の実際の死因については意見の相違がある。一部の著者によると、マリア・レオポルディナは産褥敗血症で死亡したとされている。当時、皇帝はシスプラチナ戦争中に軍を視察するためリオグランデ・ド・スル州に滞在していた。
マリア・レオポルディナが夫の癇癪中の暴行の結果として死亡したという説は、ガブリアク、カール・ザイドラー、ジョン・アーミテージ、イザベル・ルストサなどの歴史家によって裏付けられた広く流布した説である。死因となった実際の暴力という認識は、最近行われた皇后の遺体の発掘調査で骨折がなかったことから、ある程度の後退を見せた(ただし、致命的な暴行が必ずしも骨折を引き起こすわけではない)。これは1826年11月20日に起こったとされており、マリア・レオポルディナがウルグアイとの戦争に対処するために皇帝が南部へ旅立つ間、摂政を引き継ぐことになっていた。ペドロ1世は、自身の不倫関係や夫婦間の険悪な雰囲気に関する噂が嘘であることを証明しようと、盛大な送別会を催し、皇后と愛人のサントス侯爵夫人の両方に、聖職者や外交使節の前で儀礼的な口づけに出席するよう要求した。この要求に応じれば、マリア・レオポルディナは夫の愛人を公に認めることになり、このため彼女はペドロ1世の命令に逆らい、レセプションへの出席を拒否した。気性が荒いことで知られる皇帝は、妻と激しい口論になり、宮殿中を引きずり回そうとさえし、言葉と蹴りで攻撃した。結局、彼はサントス侯爵夫人だけを伴って口づけの儀式に出席し、事態を解決することなく戦争へ出発した。この暴行の目撃者は他に3人しかおらず、暴行を受けたという疑惑は、その後マリア・レオポルディナを支えた女官や医師たちによって提起された。事実の現実は異なっていたかもしれない。
「ペドロが彼女を蹴り、それが彼女の病気の原因になったというのは誇張された話である。オーストリアの代理人(オーストリア大使フィリップ・レオポルト・ヴェンツェル・フォン・マレシャル男爵を指す)によって目撃された場面は、荒々しい言葉によるものであった。マリア・レオポルディナは妊娠中の不調の理由に欠けていたわけではなく、そのために彼女は屈したのである。」
数ヶ月間重度の鬱状態にあり、妊娠12週目であった皇后の健康状態は著しく悪化していた。伝えられるところによると、彼女は最後の書簡を姉のマリー・ルイーズに送り、それはアギアール侯爵夫人に口述筆記させたもので、その中で夫に愛人がいる前で受けたひどい暴行について言及している。しかし、最近の研究では、マリア・レオポルディナからのこの最後の手紙が偽造である可能性が示されている。フランス語の原本はブラジルでも国外でも発見されていない。帝国博物館(ペトロポリス)の歴史文書にある写しはポルトガル語で書かれており、1826年12月12日付の原本に従って転写されたというフランス語の文が一つだけある。これまで全ての研究者が使用してきたこの写しは、1834年8月5日(皇后の死から約8年後)にリオデジャネイロで公証人ジョアキン・ジョゼ・デ・カストロに登録されるために初めて現れた。セザール・カドリーノ、J・M・フラッハ、J・ブベロット、カルロス・ハインドリックスが手紙の出所を証明する証人として務めた。このうち、カドリーノとフラッハの2人は、マリア・レオポルディナに多大な恩義があり、彼らにとって皇后自身による「告白」ほど良いものはなかった。
7.2. 周囲の反応と追悼
マリア・レオポルディナの苦悶のさなか、皇后がキンタ・ダ・ボア・ヴィスタに監禁されているとか、サントス侯爵夫人の指示で医師に毒殺されているなど、様々な噂が飛び交った。サントス侯爵夫人の人気はすでに芳しくなかったが、さらに悪化し、彼女のサン・クリストヴァンにある家は投石され、皇后の執事であった彼女の義弟は2発の銃弾を受けた。侯爵夫人が皇后の女官として医療の場に立ち会う権利は否定され、大臣や宮殿の役人たちは彼女が宮廷に出席し続けるべきではないと示唆した。
1826年12月11日に皇帝に提出された妻の死に関する声明は、発作、高熱、錯乱を報告している。国民からの高い評価を受け、夫よりもはるかに慕われていた彼女の死は、国家の大部分によって悼まれた。
この事件の経緯はヨーロッパに広まり、ペドロ1世の名声はひどく傷つけられたため、彼の再婚は非常に困難になった。伝えられるところによると、ペドロ1世帝国勲章の最初の受章者であるオーストリア皇帝フランツ1世は、義理の息子であるブラジル皇帝からの謝罪としてこの栄誉を受け取ったという。
2012年3月から8月にかけて行われた皇室の法医学分析に立ち会った検視官ルイス・ロベルト・フォンテスは、マリア・レオポルディナの流産と死は、リオデジャネイロのキンタ・ダ・ボア・ヴィスタにおける皇帝夫妻の喧嘩ではなく、重い病気が原因であると述べた。彼はミュシアル(アドルフォ・ルッツ研究所博物館)での講演で公衆に語った。
「今日私たちが言えるのは、皇后が何で亡くならなかったか、ということです。ペドロ1世の裏切りによる喧嘩があったとしても、それはドナ・レオポルディナの死とは関係ありません。彼女は重度の感染症にかかっていましたが、どのような病気かはまだ分かっていません。死因を特定するためには、さらなる分析が必要です。CTスキャンでは大腿骨や他の骨に骨折は見られず、はしごから落ちたという伝説や(ペドロによる)事故を否定しています。検査から、彼女が3週間患っていた重度の感染症が死因である可能性が見られました。」
最初の流産の兆候は11月19日に起こり、皇后は少量の出血があった。週が進むにつれて病状が悪化し、発熱や重度の下痢も患った。これは妊娠中の女性にとって危険な腸内出血を示唆するものである。
11月30日には錯乱も加わり、医療記録によると、皇后は死亡する数日前の12月2日に、妊娠約3ヶ月の男児を流産した。赤ちゃんを失った後もマリア・レオポルディナの健康は改善せず、ますます錯乱、発熱、出血が増加した。検視官は「つまり、彼女は明確な敗血症の症状、死の症状にあった」と述べた。
マリア・レオポルディナは1826年12月11日、30歳の誕生日を5週間前にして、リオデジャネイロ市北部のサン・クリストヴァン地区にあるキンタ・ダ・ボア・ヴィスタのサン・クリストヴァン宮殿で亡くなった。葬儀はブラジル帝国の公式説教師であったフランシスコ・ド・モンテ・アルヴェルネが司式した。
彼女の遺体は、帝国マントルに包まれ、3つの棺に納められた。最初の棺はポルトガル松製、2番目の棺は鉛製(ラテン語の碑文があり、その上には2本の交差した脛骨と、その上に帝国の銀色の紋章があった)、3番目の棺は杉製であった。

彼女は1826年12月14日にアジューダ修道院(現在のシネランディア)の教会に埋葬された。1911年に修道院が取り壊された際、彼女の遺体は同じくリオデジャネイロにあるサント・アントニオ修道院に移され、彼女と一部の皇室メンバーのために霊廟が建設された。1954年には、彼女の遺体は最終的にサンパウロ市にあるイピランガの碑の下の帝国地下墓所と礼拝堂にある、金で装飾された緑色の花崗岩製の石棺に改葬された。
8. 遺産と影響力
ブラジル独立における彼女の政治的・社会的影響、そして科学や文化への貢献について多角的に評価する。
8.1. 政治的・社会的影響
マリア・レオポルディナは、ペドロ1世のスキャンダルや不倫関係によって傷つけられ、憂鬱な女性として描かれることが多い(彼女を三角関係の脆弱な環として表現する)。しかし、最近の歴史研究では、彼女の国家史におけるより受動的でないイメージが主張されている。
マリア・レオポルディナはブラジルの政治において大きな存在感を示した。ポルトガル宮廷がポルトガルへ帰還した時も、1822年の独立までのブラジルとポルトガルの間の摩擦の裏舞台でも同様であった。ペドロ1世がまだポルトガルとの連合王国を維持する可能性を残していたのに対し、マリア・レオポルディナは宗主国からの完全な解放が最も賢明な道であるとすでに判断していた。マリア・レオポルディナの知的・政治的教育は、国家に対する強い義務感と犠牲の精神と相まって、特にジョアン6世国王がポルトガルの圧力の下でリスボンへの帰還を余儀なくされた後、ブラジルにとって極めて重要であった。彼女はオーストリア大公女でありハプスブルク・ロートリンゲン家の一員であり、貴族的・絶対主義的な体制の下で教育を受けていたにもかかわらず、自由主義や立憲主義に影響を受け、ブラジルにとってより代表的な理想や統治形態を擁護することを躊躇しなかった。
ブラジル国民は、マリア・レオポルディナがブラジルに足を踏み入れた最初の瞬間から、彼女に多大な尊敬と賞賛を抱いていた。非常に人気があり(特に貧しい人々や奴隷の間でこの見方はさらに強かった)、彼女の死以来、「ブラジル人の母」と呼ばれるようになった。「この新興帝国の守護天使」の称号を皇后に与える請願も行われた。彼女が病に臥せっていた最晩年の期間中、リオデジャネイロの街では行列が行われ、教会や礼拝堂は深い悲しみに包まれた人々で満ちた。彼女の死の報は市内全体に衝撃を与えた。人々は涙ながらに街頭に繰り出し、「我々の母が死んだ。私たちはどうなるのか?誰が黒人の味方をしてくれるのか?」と奴隷たちが叫びながら嘆き悲しんだという報告もある。彼女の死により、ペドロ1世の人気は、第一次統治の諸問題と相まって、著しく低下した。彼女の人生の作家であり伝記作家であるカルロス・H・オベラッカー・ジュニアは、「彼女ほど国民に愛され、認められた外国人は滅多にいない」と述べている。
生涯を通じて、マリア・レオポルディナは奴隷制度を終わらせる方法を模索していた。ブラジルにおける労働の形態を変える試みとして、皇后はヨーロッパからの移民を国に奨励した。マリア・レオポルディナのブラジル到着は、ドイツ人移民のブラジルへの流入を促し、最初はスイス人から始まり、リオデジャネイロに定住してノヴァ・フリブルゴ市を創設した。その後、ブラジル南部を開発するために、皇后はドイツ人移民を奨励した。南アメリカにおけるマリア・レオポルディナの存在は、ドイツ語圏の人々の間でブラジルを「宣伝」する方法として注目を集めた。
8.2. 科学・文化への貢献

皇后のブラジルにおける重要性と関連性は、彼女がイタリア半島から同行した科学使節団にも起因する。この使節団はヨーロッパの画家、科学者、植物学者で構成されていた。マリア・レオポルディナは植物学と地質学に興味があったため、2人のドイツ人科学者、植物学者カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスと動物学者ヨハン・バプティスト・フォン・シュピックス(19世紀の自然科学における著名な人物)が彼女と共に来訪した。さらに、旅行画家トマス・エンダーも同行した。この使節団の研究は、『ブラジル周遊記』や『ブラジル植物誌』などの著作に結実した。『ブラジル植物誌』は約2万ページに及ぶ大作で、数千種の自生植物の分類と図解が収められている。科学者たちは、リオデジャネイロからペルーやコロンビアとの国境まで、さらに約1.00 万 kmを旅した。
ポルトガルへの帰還を拒否したマリア・レオポルディナの姿勢は依然として意見が分かれている。一部の作家にとっては革命的な態度であったが、他の者にとっては大公女は単なる戦略家であった。リオデジャネイロ州立大学の教授で貴婦人の教育を専門とするマリア・セリ・シャベス・ヴァスコンセロスは、マリア・レオポルディナのいかなる著作や彼女に関する記述にも反乱の痕跡は一切ないと述べている。「彼女がペドロに独立宣言で影響を与えたからといって、革命的だと言えるのでしょうか?そこに革命的な特徴があるとは思いません。むしろ、彼女は政治史について十分に知識があり、当時の状況と独立にいかに有利であったかについて正確な判断を下したのだと思います」と研究者は擁護している。一方、歴史家のパウロ・レズッティは、「マリア・レオポルディナがブラジルに留まった理由が何であれ、皇后は革命的な女性として解釈されるべきである。なぜなら、彼女はブラジルの意思決定の最高権力で初めて政治を行った人物だからである」と主張している。
9. 大衆文化における描写
マリア・レオポルディナ皇后はこれまで映画やテレビドラマで描かれており、映画『インデペンデンシア・オウ・モルテ』(1972年)ではケイト・ハンセンが、ミニシリーズ『マルケサ・デ・サントス』(1984年)ではマリア・パディーリャが、ミニシリーズ『オ・キント・ドス・インフェルノス』(2002年)ではエリカ・エヴァンティーニが演じている。
マリア・レオポルディナの生涯は、1996年のサンバ学校「インペラトリス・レオポルディネンセ」のテーマとしても取り上げられた。この学校の名前は、レオポルディナ鉄道(皇后にちなんで名付けられた)の地域に拠点を置いていることから、間接的に彼女に由来する。この時、カーニバルデザイナーで教授のローザ・マガリャンエスは、パレードのためにオーストリア政府から支援を受けた。
2007年には、女優エステル・エリアスがミゲル・ファラベラのミュージカル『インペリオ』でマリア・レオポルディナを演じ、ブラジル帝国の歴史の一部が語られた。
2017年には、女優のレティシア・コリンがテレノベラ『ノヴォ・ムンド』でマリア・レオポルディナ皇后を演じた。
2018年には、サンパウロのカーニバルで「トン・マイオール」サンバ学校がマリア・レオポルディナと「インペラトリス・レオポルディネンセ」を称えた。
10. 称号と栄誉
マリア・レオポルディナが受けた称号と栄誉は以下の通りである。
- ポルトガル、ブラジル及びアルガルヴェス連合王国:
- 聖イザベル勲章名誉大師匠
- ヴィラ・ヴィソーザ無原罪受胎騎士団名誉大十字
- ブラジル帝国:
- ペドロ1世勲章名誉大十字
- 南十字星勲章名誉大十字
- オーストリア帝国: 星十字勲章婦人
- スペイン王国: マリア・ルイーサ勲章婦人
- バイエルン王国: 聖エリザベス勲章婦人
11. 家系
マリア・レオポルディナの家系は、ヨーロッパの主要な王家との複雑な血縁関係を示している。彼女は、父方の祖父母である神聖ローマ皇帝レオポルト2世とスペイン王女マリア・ルイーサ、そして母方の祖父母である両シチリア王フェルディナンド1世とオーストリア大公女マリア・カロリーナを通じて、ハプスブルク・ロートリンゲン家とブルボン家の双方に深く繋がっている。彼女の父フランツ2世と母ナポリ・シチリア王女マリア・テレジアは二重の従兄妹同士であり、この血縁関係はフランツ1世とマリア・テレジア、そしてカルロス3世とマリア・アマーリアといった共通の祖父母を通じて形成されている。この系譜は、彼女がヨーロッパの君主制における広範な政治的ネットワークの中心に位置していたことを示している。