1. 伝記
ジュラ・アンドラーシは、その生い立ちから初期の政治活動、そして亡命生活を経てハンガリー政界に復帰するまでの激動の生涯を送った。
1.1. 出生と幼少期
ジュラ・アンドラーシは、カーロイ・アンドラーシ伯爵とエテルカ・サパーリの息子として、1823年3月8日にハンガリー王国領内のオラーフパタク(現在のスロバキア、ロジュニャヴァ郡ヴラホヴォ)で生まれた。ただし、彼の生年月日と出生地については諸説あり、コシツェの記録によれば、彼は1823年3月3日にコシツェ(当時の名称はカッサ)で洗礼を受けている。彼の父は自由主義者で、当時の政府に反対する政治的野党に属しており、政府に反対することが非常に危険な時代であったにもかかわらず、アンドラーシは幼い頃からその日の政治闘争に身を投じ、当初から愛国的な立場をとった。
1.2. 教育
アンドラーシの能力を最初に高く評価したのは、イシュトヴァーン・セーチェニ伯爵であった。1845年、彼はティサ川上流の水利調整協会の会長に任命され、公職でのキャリアを開始した。
亡命生活を送った10年間、彼は当時のヨーロッパ外交の中心地であったパリやロンドンで政治学を深く学んだ。この期間に、彼はフランス第二帝政の華やかな外観の下に隠された弱点を鋭く見抜くことができた。
1.3. 初期キャリア

1846年、アンドラーシはコシュート・ラヨシュの新聞『ペシュティ・ヒールラップ』に政府を厳しく批判する記事を発表し、注目を集めた。彼は1848年の議会に急進派の候補者の一人として選出された。
ヨシプ・イェラチッチ率いるクロアチア人が、当時ハンガリーの一部であったメジムリェをクロアチアに返還させようと試みた際、アンドラーシは軍務に入った。彼は自身の郡のジェントリーを指揮し、パコズドの戦いやシュヴェヒャートの戦いでゲルゲイ・アルトゥールの副官(1848年)として活躍した。
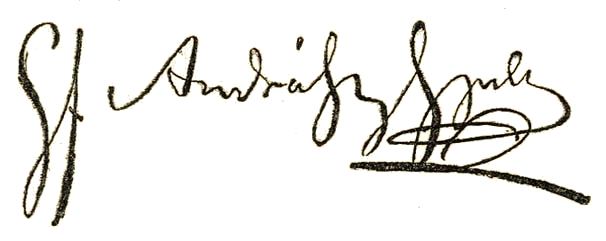
戦争末期、アンドラーシは革命政府によってコンスタンティノープルに派遣され、クロアチアとの戦いにおいて、オスマン帝国の支持は得られなくとも、少なくとも中立を確保しようと努めた。
ヴィラーゴシュの降伏でハンガリー軍が敗北した後、アンドラーシはロンドン、その後パリへと亡命した。1851年9月21日、彼はハンガリーの反乱における役割を理由に、オーストリア政府によって欠席裁判で死刑を宣告され、人形が絞首刑に処された。
10年間の亡命生活を経て、アンドラーシは1858年にハンガリーに帰国したが、その立場は依然として困難であった。彼は一度も恩赦を請願しておらず、オーストリア政府とマジャール保守派(王国の完全な自治権に満たないものを受け入れようとした人々)の双方からの働きかけを一貫して拒否していた。彼はデアーク・フェレンツの党を熱心に支持した。1865年12月21日、彼は議会の副議長に選出された。1866年3月には、オーストリア=ハンガリー妥協(アウスグライヒ)を起草するために議会委員会によって任命された小委員会の委員長に選出された。彼は「委任」という権限の概念を提唱した。当時、彼は委員会の唯一のメンバーであり、国家の主張の正当性を宮廷に納得させることができたと言われた。
2. 主要な活動と業績
ジュラ・アンドラーシは、ハンガリーの政治家として、またオーストリア=ハンガリー帝国の外務大臣として、帝国の形成と外交政策において極めて重要な役割を果たした。
2.1. 1867年オーストリア=ハンガリー大妥協における役割
1866年のケーニヒグレーツの戦い(サドワの戦いとも呼ばれる)でプロイセンがオーストリアを決定的に破った後、ビスマルクは戦後の良好な関係回復を望んだ。フランツ・ヨーゼフ1世皇帝は初めてアンドラーシに助言を求め、アンドラーシは憲法の再確立と責任ある外務・防衛大臣の任命を勧告した。1867年2月17日、皇帝は彼を新しく形成された二重君主国のハンガリー側の初代首相に任命した。当初の明白な第一候補は、妥協の立役者の一人であるデアーク・フェレンツであったが、彼はアンドラーシに道を譲った。デアークはアンドラーシを「神の恩寵によってハンガリーに与えられた天賦の政治家」と評した。
2.2. ハンガリー首相
首相として、アンドラーシは、その断固たる態度、親しみやすさ、そして討論者としての巧みさによって、すぐに主導的な地位を確立した。しかし、デアークの権威が他のすべての党指導者の権威を矮小化していたため、彼の立場は依然として困難であった。アンドラーシは自ら国防と外務の部門を選んだ。彼はホンヴェード制度(国軍)を再編成し、軍事国境地域の規制が彼の人生で最も困難な仕事であったと度々語っていた。
1870年の普仏戦争勃発に際し、アンドラーシはオーストリア君主国の中立を断固として擁護し、1870年7月28日の演説では、オーストリアが1863年以前にドイツで保持していた地位を回復しようとすることが、オーストリアの利益になるとの仮定に強く抗議した。フリードリヒ・フェルディナント・フォン・ボイスト伯爵の失脚(1871年11月6日)に伴い、アンドラーシがその地位を引き継いだ。彼の首相在任期間は画期的なものであった。
2.3. オーストリア=ハンガリー外務大臣
ボイストがドイツに敵対的でロシアに友好的であったのに対し、アンドラーシは逆のアプローチをとった。一つの問題は、ドイツがイタリアと緊密であったが、イタリアとオーストリアは国境地域の支配権をめぐって対立していたことであった。
これまでハプスブルク帝国は、その歴史的な神聖ローマ帝国の伝統から自らを切り離すことができなかった。しかし、イタリアとドイツにおける影響力の喪失と、それに続く二重帝国の形成は、ついに将来の外交の適切な、そして唯一の分野を示唆した。それは、バルカン半島諸民族の国民国家への結晶化がまだ不完全であった近東であった。問題は、これらの民族が独立を許されるのか、それともスルタンの専制政治をツァーリまたはハプスブルク皇帝の専制政治と交換するだけなのかというものであった。
この時点まで、オーストリアはロシアを排除するか、彼らと戦利品を共有することに満足していた。しかし、その不幸の結果として、ヨーロッパの評議会における影響力のほとんどを奪われていた。アンドラーシこそが、オーストリアにヨーロッパ協調における正当な地位を取り戻させた人物であった。まず彼はドイツ皇帝に接近し、その後、ベルリン、ウィーン、サンクトペテルブルク、ヴェネツィアでの会議を通じて、イタリアとロシアの宮廷とのより良好な関係を確立した。
2.4. 外交政策と外交活動
2.4.1. 一般的な外交政策
アンドラーシは保守的な外交路線をとり、東南ヨーロッパへの帝国の拡大を目指した。彼は、イギリスとドイツの支援を得て、オスマン帝国との関係を悪化させることなくこの目標を達成することを好んだ。彼は、スラヴ人および正教会地域への自身の拡張政策から、ロシアを主要な敵対者と見なしていた。また、彼は多民族国家であるオーストリア=ハンガリー帝国に対する脅威として、スラヴ民族主義運動を警戒し、不信感を抱いていた。
彼はロシア帝国とスラヴ系諸国に対抗するため、ドイツ帝国との提携を進めた。これは、ドイツ帝国成立に伴い二重帝国にとっては「ドイツ(統一)問題」よりも「バルカン問題」の比重が高くなり、同時に、帝国内のスラヴ系民族の独立運動を煽る汎スラヴ主義やロシアのバルカン南下政策がハンガリーの領土保全を脅かしかねないという判断によるものであった。それと同時に彼はロシアとの部分的和解にも努め、1872年には独露との三帝同盟を締結し、1877年の露土戦争には中立を維持した。
2.4.2. アンドラーシ文書
オーストリアの影響力の回復は、1875年にボスニアで発生した深刻な騒乱に続く交渉で明らかになった。ウィーン、ベルリン、サンクトペテルブルクの三つの宮廷は、東方問題に対する態度について合意に達し、彼らの見解は、1875年12月30日にアンドラーシがフリードリヒ・フェルディナント・フォン・ボイスト伯爵(セント・ジェームズ宮廷駐在オーストリア大使)に送った「アンドラーシ文書」として知られる公文書にまとめられた。
この文書の中で、アンドラーシは、反乱を局地化しようとする列強の努力が失敗に終わる危険があること、反乱軍が依然として優勢であること、そして様々な勅令に盛り込まれたオスマン帝国の改革の約束が、漠然とした原則表明に過ぎず、これまでも、そしておそらく今後も、地域に適用される意図がなかったことを指摘した。したがって、全面的な紛争の危険を回避するため、彼は、列強が協調してオスマン政府に約束の履行を迫る時が来たことを強く主張した。
その後、より本質的な改革の概要が示された。それは、キリスト教の単なる寛容ではなく承認、徴税請負制度の廃止、そして宗教問題が農業問題と複雑に絡み合っていたボスニア・ヘルツェゴビナにおいては、キリスト教徒の農民を自由な土地所有者に転換させ、イスラム教徒のオスマン地主に対する二重の従属から彼らを解放することであった。
ボスニア・ヘルツェゴビナには、選挙で選ばれた州議会が設置され、終身制の判事が任命され、個人の自由が保障されることになった。最後に、イスラム教徒とキリスト教徒からなる混合委員会が、これらの改革の実施を監視する権限を与えられた。スルタンが約束の実現についてヨーロッパに責任を負うという事実は、反乱軍の当然の疑惑を和らげるのに役立つだろう。この計画に対し、イギリスとフランスは概ね同意し、アンドラーシ文書は交渉の基礎として採用された。
ロシアとオスマン政府の間で戦争が避けられなくなった際、アンドラーシはロシア宮廷と、ロシアが勝利した場合でもオーストリア君主国に不利な形で現状が変更されないよう取り決めた。しかし、サン・ステファノ条約が近東におけるロシアの覇権を脅かしたため、アンドラーシはドイツとイギリスの宮廷と共に、問題の最終的な調整はヨーロッパの会議に提出されるべきであるという意見に同意した。
2.4.3. ベルリン会議

1878年のベルリン会議では、アンドラーシはオーストリアの首席全権代表として、ロシアの獲得利益を減らし、二重君主国の勢力を拡大することに尽力した。会議が6月13日に始まる前、アンドラーシとイギリス外務大臣ソールズベリー侯爵との交渉はすでに6月6日に「イギリスがボスニア=ヘルツェゴヴィナに関するオーストリアのすべての提案に同意し、その見返りにオーストリアがイギリスの要求を支持する」ことで合意に達していた。
アンドラーシは、ボスニア=ヘルツェゴヴィナの占領と行政に加え、オスマン帝国の行政下にとどまったノヴィ・パザル・サンジャクに駐屯軍を置く権利も獲得した。サンジャクはセルビアとモンテネグロの分離を維持し、そこに駐屯するオーストリア=ハンガリー軍は、サロニカへの進撃路を開き、「バルカン西半分を恒久的にオーストリアの影響下に置く」ことになった。「(オーストリア=ハンガリーの)高位軍当局は、サロニカを目標とする即時の大規模遠征を望んでいた」。
この占領は、財政的な理由と、マジャール人の強い親トルコ感情のため、ハンガリーでは非常に不評であった。
1878年9月28日、財務大臣のコロマン・フォン・ツェルは、アルブレヒト大公が指揮する軍隊がサロニカに進軍することを許可するならば辞任すると脅迫した。1878年11月5日のハンガリー議会の会期中、野党は、アンドラーシ外務大臣が近東危機における政策とボスニア=ヘルツェゴヴィナの占領によって憲法を侵害したとして弾劾されるべきだと提案したが、この動議は179対95で否決された。野党の下級議員からは、アンドラーシに対する最も深刻な非難が浴びせられた。
1878年10月10日、フランスの外交官メルヒオール・ド・ヴォギュエは状況を次のように描写している。
「特にハンガリーでは、この『冒険』によって引き起こされた不満が最も深刻な事態に達しており、マジャール民族を活気づけ、その運命の秘密である強力な保守的本能によって促されている。この活発で排他的な本能は、数では少ないながらも、異なる民族と対立する願望を持つ多数の住民が住む国を支配し、その数や知的文化に比べて不釣り合いなほどヨーロッパの事柄で役割を果たす、孤立した集団という歴史的現象を説明する。この本能は今日目覚め、ボスニア=ヘルツェゴヴィナの占領が、ハンガリーの政治組織に新たなスラヴ要素を導入し、クロアチアの反対派により広い分野とさらなる募集の機会を提供することで、マジャール支配が均衡を保っている不安定な均衡を崩す脅威であると感じていると警告している。」
アンドラーシは嵐に屈せざるを得ないと感じ、皇帝に辞表を提出した(1879年10月8日)。引退の前日、彼はドイツとの攻守同盟に署名し、これによってオーストリア=ハンガリーの外交関係は再び安定した基盤の上に置かれた。
2.4.4. 国際関係と提携
アンドラーシは、ロシアおよびスラヴ系諸国に対抗するため、ドイツ帝国との提携を進めた。これは、ドイツ帝国成立に伴い二重帝国にとっては「ドイツ(統一)問題」よりも「バルカン問題」の比重が高くなり、同時に、帝国内のスラヴ系民族の独立運動を煽る汎スラヴ主義やロシアのバルカン南下政策がハンガリーの領土保全を脅かしかねないという判断によるものであった。それと同時に彼はロシアとの部分的和解にも努め、1872年には独露との三帝同盟を締結し、1877年の露土戦争には中立を維持した。
1878年のベルリン会議の結果、要求が通らなかったロシアが三帝同盟から離脱したため同盟は崩壊したが、アンドラーシはドイツとの二帝同盟を締結した(これは1882年にロシアが参加して三帝協商に発展する)。アンドラーシは外務大臣を辞任する前日の1879年10月8日にドイツとの攻守同盟に署名し、これによってオーストリア=ハンガリーの外交関係は再び安定した基盤の上に置かれた。彼の退任後、オーストリア=ハンガリーはグスタフ・ジークムント・カールノキ外相の下でロシアとの提携を重視する外交を進めていった。アンドラーシ外交は、バルカンにおけるオーストリア=ハンガリーの利権を一時的に拡大することには成功したが、長期的に見るとボスニア=ヘルツェゴヴィナ併合に帰着することによってロシアやスラヴ諸国との非和解的対立を招き、(第一次世界大戦による)帝国解体の原因を作り出すことになった。
3. 私生活
ジュラ・アンドラーシの私生活は、公的な活動の陰に隠れがちであったが、家族との関係や、当時の著名な人物との間に囁かれた噂など、興味深い側面も持ち合わせていた。
3.1. 家族関係
アンドラーシは1856年にパリでカティンカ・ケンデッフィ伯爵夫人と結婚した。彼らには2人の息子、ティヴァダール・アンドラーシ(1857年7月10日生まれ)とジュラ(1860年6月30日生まれ)、そして1人の娘、イロナ・アンドラーシ(1858年生まれ)がいた。
両方の息子はハンガリー政治で頭角を現した。ティヴァダールは1890年にハンガリー議会下院の副議長に選出された。ジュラもまた、成功した政治家としてのキャリアを築いた。
ジュラ・アンドラーシ伯爵の孫娘であるクラーラは、ハンガリーの貴族で実業家のカーロイ・オデスカルキ公爵と結婚した。アンドラーシ伯爵には他に3人の孫娘がいた。ボルバーラはパッラヴィチーニ侯爵と結婚し、カタリンはカーロイ・ミハーイ伯爵と結婚し、イロナはパール・エステルハージ公爵の未亡人となった後、ヨージェフ・ツィラーキ伯爵と再婚した。
3.2. エリザベート皇后との噂

アンドラーシ伯爵とオーストリア皇后兼ハンガリー王妃エリザベート(通称シシィ)との間に、長期間にわたる恋愛関係があったという多くの噂が囁かれた。エリザベートはフランツ・ヨーゼフ1世皇帝の妻である。一部では、エリザベートの第四子であるマリー・ヴァレリー大公女がアンドラーシの子供であると噂された。しかし、これには証拠がなく、これらの噂はすべて虚偽であることが証明されている。この噂は、エリザベートとアンドラーシ伯爵の双方がハンガリー、その文化、そして国民的慣習に対して抱いていた献身(エリザベートはハンガリー語に堪能であり、両者ともハンガリーの詩を高く評価していた)と、ハンガリーに対する彼らの夢を追求する中で共に過ごした時間の多さから生まれたのかもしれない。さらに、マリー・ヴァレリーが成長するにつれて、彼女の父フランツ・ヨーゼフとの身体的類似性が非常に顕著になったことも、この噂が虚偽であることを裏付けている。
4. 評価と影響
ジュラ・アンドラーシは、ハンガリー人として数世紀ぶりにヨーロッパの舞台で重要な地位を占めた政治家であり、その業績は多岐にわたる。しかし、彼の政策は多くの批判と論争も引き起こした。
4.1. 肯定的な評価
アンドラーシは、数世紀ぶりにヨーロッパの舞台で地位を確立した最初のマジャール人政治家であった。彼はマジャール人のマグナート(大貴族)と現代の紳士の資質を兼ね備えていたと言われている。彼のモットーは「約束することは難しいが、それを実行することは容易である」であった。もしデアーク・フェレンツが近代ハンガリー国民国家の設計者であるならば、アンドラーシは建築家であると言えるだろう。
引退後も、アンドラーシは代表団や上院で公務に積極的に参加し続けた。1885年には貴族院改革案を熱心に支持したが、一方で1867年の妥協の不可侵性を熱心に擁護し、1889年3月5日には上院で共通軍に対するいかなる分離主義的な干渉にも反対する演説を行った。晩年には人気を取り戻し、1890年2月18日に66歳で死去した際には、国民的な悲劇として悼まれた。彼が亡くなったイストリア地方のヴォロスコ(現在のクロアチア、リエカとオパティヤの間)には、彼を記念する銘板が残されている。
4.2. 批判と論争
アンドラーシの外交は、バルカンにおけるオーストリア=ハンガリーの利権を一時的に拡大することには成功したが、長期的に見るとボスニア=ヘルツェゴヴィナ併合に帰着することによってロシアやスラヴ諸国との非和解的対立を招き、(第一次世界大戦による)帝国解体の原因を作り出すことになった。
ボスニア=ヘルツェゴヴィナの占領は、財政的な理由とマジャール人の強い親トルコ感情のため、ハンガリーでは非常に不評であった。1878年9月28日、財務大臣のコロマン・フォン・ツェルは、アルブレヒト大公が率いる軍隊がサロニカに進軍することを許可するならば辞任すると脅迫した。1878年11月5日のハンガリー議会の会期中、野党は、アンドラーシ外務大臣が近東危機における政策とボスニア=ヘルツェゴヴィナの占領によって憲法を侵害したとして弾劾されるべきだと提案したが、この動議は179対95で否決された。野党の下級議員からは、アンドラーシに対する最も深刻な非難が浴びせられた。
1878年10月10日、フランスの外交官メルヒオール・ド・ヴォギュエは状況を次のように描写している。「特にハンガリーでは、この『冒険』によって引き起こされた不満が最も深刻な事態に達しており、マジャール民族を活気づけ、その運命の秘密である強力な保守的本能によって促されている。この活発で排他的な本能は、数では少ないながらも、異なる民族と対立する願望を持つ多数の住民が住む国を支配し、その数や知的文化に比べて不釣り合いなほどヨーロッパの事柄で役割を果たす、孤立した集団という歴史的現象を説明する。この本能は今日目覚め、ボスニア=ヘルツェゴヴィナの占領が、ハンガリーの政治組織に新たなスラヴ要素を導入し、クロアチアの反対派により広い分野とさらなる募集の機会を提供することで、マジャール支配が均衡を保っている不安定な均衡を崩す脅威であると感じていると警告している。」
5. 栄誉と賞

ジュラ・アンドラーシは、その功績に対し、以下の勲章と栄典を授与された。
- オーストリア=ハンガリー帝国
- 聖イシュトヴァーン王冠勲章大十字章(1867年)
- 金羊毛騎士団騎士(1877年)
- バーデン:忠実勲章騎士(1873年)
- バイエルン:聖フーベルトゥス勲章騎士(1873年)
- ベルギー:レオポルド勲章大綬章
- フランス:レジオンドヌール勲章大十字章
- ギリシャ:救世主勲章大十字章
- イタリア:聖アヌンツィアータ最高勲章騎士(1873年11月28日)
- マルタ主権軍事騎士団:名誉と献身のバイリフ大十字章
- オランダ:オランダ獅子勲章大十字章
- オスマン帝国:メディジディー勲章一等(ダイヤモンド付)
- ペルシア:オーガスト肖像勲章(ダイヤモンド付)
- ポルトガル:塔と剣勲章大十字章
- プロイセン:黒鷲勲章騎士(1872年9月10日)
- ロシア帝国
- 聖アンドレイ勲章騎士(1874年)
- 聖アレクサンドル・ネフスキー勲章騎士
- 白鷲勲章騎士
- 聖アンナ勲章一等騎士
- 聖スタニスラウス勲章一等騎士
- ザクセン:ルー冠勲章騎士(1872年)
- シャム:タイ王冠勲章大十字章
- ヴュルテンベルク:ヴュルテンベルク王冠勲章大十字章(1874年)