1. 概要

東ティモール民主共和国、通称東ティモールは、東南アジアに位置する島国であり、21世紀最初の独立国である。国土はティモール島の東半分、同島北西部の飛び地であるオエクシ=アンベノ、そしてアタウロ島とジャコ島から構成される。南はティモール海を隔ててオーストラリアと、陸上ではインドネシアと国境を接する。
ティモール島には古くからパプア系諸族やオーストロネシア語族が移住し、多様な文化と言語が混在する社会を形成した。16世紀にポルトガルの影響下に入り、1975年までその植民地支配が続いた。独立宣言直後のインドネシアによる侵攻と占領は、大規模な人権侵害や虐殺を引き起こし、国際的な非難を浴びた。住民による粘り強い抵抗運動と国際社会の圧力の結果、1999年の住民投票を経て、2002年5月20日に正式に独立を達成した。
政治体制は半大統領制の共和制で、国民から直接選挙される大統領と、議会が指名する首相が行政権を分担する。独立後の国家建設は困難を伴い、2006年には大規模な国内騒乱も経験したが、民主的な制度の定着と安定に向けた努力が続けられている。経済は石油・天然ガス資源に大きく依存しているが、貧困削減と持続可能な開発が喫緊の課題である。国民の大多数はカトリックを信仰しており、多様な民族と言語が共存する多文化社会を形成している。
2. 国名

この国の公式名称は、ポルトガル語では República Democrática de Timor-Lesteレプーブリカ・デモクラーティカ・ド・ティモール・レステポルトガル語、テトゥン語では Repúblika Demokrátika Timór-Lorosa'eレプブリカ・デモクラティカ・ティモール・ロロサエテトゥン語 である。英語では Democratic Republic of Timor-Lesteデモクラティック・リパブリック・オブ・ティモールレスティ英語 と表記される。略称は、ポルトガル語と英語では Timor-Lesteティモール・レスティ英語、テトゥン語では Timór Lorosa'eティモール・ロロサエテトゥン語 となる。
日本語での公式表記は東ティモール民主共和国、通称は東ティモールである。
「ティモール」の語源は、マレー語およびインドネシア語で「東」を意味する timurティムールマレー語 に由来する。したがって、「東ティモール」は「東の島の東部」という意味合いを持つ、ある種の重言的な地名となっている。「レスティ (Leste)」はポルトガル語で「東」を意味し、「ロロサエ (Lorosa'e)」はテトゥン語で「太陽が昇る場所」、すなわち「東」を意味する。
憲法で定められた公式名称は上記の通りであり、国際連合や欧州連合、ISO (国名コード: TLS, TL) など多くの国際機関や国家が公式名称として Timor-Leste英語 を使用している。インドネシアでは、かつての自国州名であった Timor Timurティモール・ティムールインドネシア語(東ティモール州)と区別するため、国家を指す場合は Timor Lesteティモール・レステインドネシア語 を用いる。
3. 歴史
東ティモールの歴史は、先史時代の人類の到来から始まり、初期の王国形成、ポルトガルによる長期の植民地支配、インドネシアによる残忍な侵攻と占領、そして困難な独立達成と国家建設の道のりを経て現代に至る。
3.1. 先史時代と初期王国
ティモール島への人類の最初の定住は、オーストラロ・メラネシア人の移住の波によるもので、約4万2000年前のジェリマライ遺跡の文化遺物がその証拠とされる。これらの初期の住民は、今日のパプア諸語の祖先となる言語をもたらしたと考えられる。その後、オーストロネシア語族の人々が到来し、新たな言語と文化をもたらし、既存の文化と融合した。これらの移住の波は、島内での農業の発展と関連している可能性がある。
ティモール島の先史時代の政治体制に関する情報は限られているが、島には慣習法によって統治される相互に関連した政体が発展していた。特定の聖なる家(Uma Lulikウマ・ルリックテトゥン語)を中心とする小さな共同体は、より広範な「スッコ」(首長国)の一部であり、それらはさらに「リウライ」と呼ばれる王が率いる大きな王国の一部であった。これらの王国の権力は、世俗的な力を持つリウライと、精神的な力を持つ「ライ・ナイン」(土地の主)の二者によって分担されることが多かった。これらの政体は多数存在し、同盟関係や力関係は変動したが、多くは16世紀のヨーロッパ人による最初の記録からポルトガル支配の終わりまで存続するほど安定していた。
13世紀頃から、ティモール島は白檀を輸出しており、その香木としての価値や工芸品としての用途から重宝された。14世紀までには、白檀、蜂蜜、蝋などを輸出品として、東南アジア、中国、インドの交易ネットワークに組み込まれていた。マジャパヒト王国はティモール島を朝貢国として記録している。この白檀が、16世紀初頭にヨーロッパの探検家たちを島に引き寄せた主要因であった。
3.2. ポルトガル植民地時代

16世紀初頭、ポルトガル人がティモール島に来航し、主に白檀貿易に関与し始めた。当初、ポルトガルのプレゼンスは限定的で、近隣の島々に交易拠点を置いていた。17世紀になって初めて、オランダとの競争の中で他の島々から追われた結果、ティモール島に直接的な拠点を築くようになった。1646年には首都がティモール島西部のクパンに移されたが、1652年にクパンもオランダに奪われたため、ポルトガル人は現在の東ティモールの飛び地であるオエクシのリファウに拠点を移した。島東部におけるヨーロッパ人による実質的な占領は、1769年にディリ市が建設されてから始まったが、実際の支配は依然として極めて限定的だった。オランダ領とポルトガル領の境界線は、1914年に常設仲裁裁判所によって最終的に画定され、これが現在のインドネシアと東ティモールの国境となっている。
ポルトガルにとって、東ティモールは19世紀後半まで、インフラや教育への投資が最小限に抑えられた、顧みられない交易所程度の存在であった。ポルトガルが植民地の内陸部に対する実質的な支配を確立した後も、投資は依然として最小限にとどまった。白檀は主要な輸出品であり続け、19世紀半ばにはコーヒー輸出も重要になった。
20世紀初頭、ポルトガル本国の経済不振により、植民地からより多くの富を搾取しようとする動きが強まり、これは東ティモール人の抵抗を引き起こした。世界恐慌期には植民地は経済的負担と見なされ、ポルトガルからの支援や管理はほとんど受けられなかった。
第二次世界大戦中、ディリは1941年に連合国によって占領され、その後1942年初頭から日本軍によって占領された。植民地の山岳地帯は、ティモールの戦いとして知られるゲリラ戦の舞台となった。東ティモールの義勇兵と連合軍が日本軍に対して戦ったこの戦闘で、4万人から7万人の東ティモール民間人が犠牲になった。日本軍は1943年初頭に最後のオーストラリア軍と連合軍を駆逐したが、第二次世界大戦終結後の日本の降伏により、ポルトガルの支配が再開された。
1950年代にポルトガルは植民地への投資を開始し、教育への資金提供やコーヒー輸出を促進したが、経済は実質的に改善せず、インフラ整備も限定的であった。年間の成長率は2%程度と低迷していた。1974年のカーネーション革命によりポルトガルで独裁体制が崩壊すると、ポルトガルはティモール植民地を事実上放棄し、1975年には東ティモールの政党間で内戦が勃発した。
東ティモール独立革命戦線(フレティリン)は、1975年8月のティモール民主同盟(UDT)によるクーデター未遂に対抗し、同年11月28日に一方的に独立を宣言した。しかし、インドネシア群島内に共産主義国家が誕生することを恐れたインドネシア軍は、12月7日に東ティモールへの侵攻を開始した。インドネシアは1976年7月17日に東ティモールを自国の27番目の州として併合した。国際連合安全保障理事会はこの侵攻に反対し、国連における東ティモールの名目上の地位は「ポルトガル統治下の非自治地域」として残された。
3.3. インドネシアによる侵攻と占領

フレティリンはインドネシアの侵攻に抵抗し、当初は軍隊として領土を保持していたが(1978年11月まで)、その後はゲリラ的な抵抗運動へと移行した。インドネシアによる東ティモール占領は、暴力と残虐行為に特徴づけられる。東ティモールにおける受容・真実・和解委員会のために準備された詳細な統計報告書は、1974年から1999年の間に、紛争に関連する死者が最低でも10万2800人に上り、その内訳は約1万8600人の殺害と、飢餓や病気による8万4200人の過剰死亡であったと指摘している。この期間の紛争関連死者総数を正確に特定することはデータ不足のため困難であるが、ポルトガル、インドネシア、カトリック教会のデータに基づくある推計では、最大で20万人に達した可能性が示唆されている。
抑圧と制限は、保健医療や教育インフラ・サービスの改善を相殺し、生活水準の全体的な改善はほとんど見られなかった。経済成長の恩恵は、主にインドネシアの他地域からの移民にもたらされた。教育の大規模な拡大は、開発のためというよりも、インドネシア語の使用を増やし国内の治安を強化することを意図していた。
1991年のサンタクルス事件(ディリ虐殺事件)では、インドネシア軍による200人以上のデモ参加者の虐殺が発生し、これは独立運動の転換点となり、インドネシアに対する国際的な圧力を高めた。スハルトインドネシア大統領の辞任後、新大統領ユスフ・ハビビは、オーストラリアのジョン・ハワード首相からの書簡に促され、独立に関する住民投票の実施を決定した。インドネシアとポルトガルの間で国連が後援する合意により、1999年8月に国連監視下での住民投票が実施された。独立への明確な賛成票は、インドネシア軍の一部に支援された東ティモールの親インドネシア民兵による報復的な暴力キャンペーンを引き起こした。これに対し、インドネシア政府は、多国籍平和維持軍(INTERFET)が秩序を回復し、東ティモール難民および国内避難民を援助することを許可した。1999年10月25日、東ティモールの行政は国際連合東ティモール暫定統治機構(UNTAET)を通じて国連に引き継がれた。INTERFETの展開は2000年2月に終了し、軍事指揮権は国連に移管された。
このインドネシア占領期における人権侵害は甚だしく、拷問、超法規的処刑、強制失踪、意図的な飢餓作戦などが広範囲に行われた。これらの行為は、国際社会からジェノサイドに等しいと非難されることもある。住民の抵抗運動は、シャナナ・グスマンらが指導するファリンティルを中心に粘り強く続けられ、国際的な注目を集める上で、カルロス・フィリペ・シメネス・ベロ司教やジョゼ・ラモス=ホルタ(後のノーベル平和賞受賞者)のような人物が重要な役割を果たした。
3.4. 独立過程と国連暫定統治

1999年8月30日の住民投票において、東ティモール国民の78.5%がインドネシアからの独立を選択した。この結果を受け、親インドネシア派民兵とインドネシア国軍の一部が組織的な暴力と破壊活動を展開し(1999年東ティモール危機)、多くの市民が殺害され、数十万人が家を追われた。焦土作戦により、インフラの約70%が破壊された。この危機に対し、国際連合安全保障理事会決議1264に基づき、オーストラリアを主体とする東ティモール国際軍(INTERFET)が派遣され、治安回復にあたった。
1999年10月25日、国際連合東ティモール暫定統治機構(UNTAET)が設立され、セルジオ・ヴィエイラ・デ・メロが国連事務総長特別代表として統治を担った。UNTAETは、治安維持、人道支援、行政機構の再建、憲法制定と選挙の準備など、独立に向けた包括的な国家建設プロセスを主導した。この期間、多くの難民が帰還し、司法制度や警察組織の整備が進められた。日本の自衛隊も国際連合平和維持活動の一環として施設部隊などを派遣し、インフラ復旧に貢献した。
2001年8月30日、制憲議会選挙が実施され、フレティリンが第一党となった。制憲議会は2002年3月22日に憲法を承認。同年4月14日には初の大統領選挙が行われ、独立運動の指導者シャナナ・グスマンが初代大統領に選出された。
3.5. 独立以後
2002年5月20日、東ティモールは正式に独立を回復し、国際社会の一員となった。制憲議会は国民議会へと移行し、マリ・アルカティリが初代首相に就任した。同年9月27日には国際連合に加盟した。独立後の国家建設は困難を極め、貧困、失業、インフラの未整備、人材不足など多くの課題に直面した。
3.5.1. 2006年の危機
2006年東ティモール危機は、独立後の東ティモールが直面した最初の深刻な政治的・社会的危機であった。この危機は、国軍兵士約600人(全兵力の約40%)が、主に西部出身者に対する差別的な待遇(昇進や給与など)を理由に抗議し、解雇されたことに端を発する。解雇された兵士たちはアルフレド・レイナド少佐を中心に反乱を起こし、政府軍との間で武力衝突が発生した。
危機はさらに拡大し、警察と国軍の間でも対立が生じ、ディリ市内ではギャング集団による放火や略奪が横行、治安が著しく悪化した。この混乱により、約15万5000人が国内避難民となり、人道危機が発生した。背景には、国軍内部の東西出身者間の対立、独立闘争時代の派閥争い、高い失業率、貧困、そしてアルカティリ首相の指導力に対する不満など、複雑な要因が絡み合っていた。
事態を収拾するため、東ティモール政府はオーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、ポルトガルに国際安定化部隊(ISF)の派遣を要請した。この危機の結果、マリ・アルカティリ首相は辞任に追い込まれ、ジョゼ・ラモス=ホルタが後任の首相に就任した。この危機は、若い国家の脆弱性と、民主主義制度の未熟さ、そして社会的分断の根深さを露呈させ、その後の国家建設に大きな影響を与えた。特に、脆弱な立場の人々(女性、子供、避難民)は大きな困難に直面し、民主主義の発展にも影を落とした。この危機を受けて、国連は国際連合東ティモール統合ミッション(UNMIT)を設立し、再び平和維持と安定化支援に乗り出した。
3.5.2. 近年の情勢
2006年の危機後、東ティモールは政治的安定の回復と国家再建に努めてきた。2007年には大統領選挙と議会選挙が実施され、ジョゼ・ラモス=ホルタが大統領に、シャナナ・グスマンが首相に就任した。しかし、2008年にはラモス=ホルタ大統領暗殺未遂事件が発生するなど、依然として不安定な要素も抱えていた。国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)は2012年末に活動を終了し、治安維持の責任は完全に東ティモール政府に移管された。
その後も複数回の選挙が比較的平和裏に行われ、民主的な政権交代が定着しつつある。2017年にはフランシスコ・グテレス(通称ル・オロ、フレティリン党)が大統領に就任したが、議会選挙後の少数与党政権が機能不全に陥り、2018年に再選挙が行われた。その結果、タウル・マタン・ルアク(元国軍司令官、人民解放党PLP党首)が首相に就任した。2022年の大統領選挙では、ジョゼ・ラモス=ホルタがフランシスコ・グテレスを破り、再び大統領に就任した。
経済面では、依然として石油・天然ガス収入への依存度が高いが、経済多角化や民間セクターの育成が課題となっている。人権状況の改善、司法制度の強化、汚職対策、貧困削減、教育・医療水準の向上など、多くの社会的課題への取り組みが続けられている。特に、過去の人権侵害に対する真相究明と和解、そして社会正義の実現は、国民の悲願であり続けている。東南アジア諸国連合(ASEAN)への加盟申請も行っており、2022年には原則加盟が承認され、正式加盟に向けたロードマップが進められている。
4. 政治

東ティモールは立憲共和制であり、半大統領制を採用している。権力分立の原則に基づき、行政権、立法権、司法権が分立している。民主的発展の過程で多くの課題に直面しながらも、国民の政治参加と人権尊重を重視した国家建設が進められている。
4.1. 政府構造
国家元首は国民の直接選挙で選ばれる大統領であり、任期は5年で、再選は1回まで可能である。大統領は主に象徴的な役割を担うが、法律に対する拒否権、国民投票の発議権、特定の条件下での議会解散権など、一定の権限を有する。
行政の長は首相であり、国会の多数派政党または連立与党の指導者が大統領によって任命される。首相は閣僚を指名し、内閣(閣僚評議会)を率いて行政全般を統括する。
立法府は一院制の国民議会(Parlamento Nacionalポルトガル語)であり、議員は国民の直接選挙(比例代表制)で選ばれ、任期は5年である。議席数は最低52、最大65議席と憲法で定められている。政党は得票率3%の阻止条項をクリアする必要がある。女性議員の比率向上のため、各政党の候補者名簿の3分の1を女性とすることが義務付けられている。
司法府は独立しており、最高裁判所を頂点とする裁判所システムが整備されている。ただし、行政による司法への干渉事例も報告されており、司法の完全な独立性の確保は課題である。
地方行政は中央集権的であるが、オエクシ=アンベノは特別行政地域として一定の自治権を有する。
4.2. 主要政党と選挙
東ティモールの主要政党には、独立闘争を主導した中道左派の東ティモール独立革命戦線(FRETILIN、フレティリン)と、シャナナ・グスマン元大統領・元首相が率いる中道右派のティモール再建国民会議(CNRT)がある。この二大政党に加え、民主党(PD)、人民解放党(PLP)などが国会に議席を有している。
政党政治は、イデオロギーよりも特定の指導者の個人的な影響力に左右される傾向がある。また、独立闘争を経験した「古い世代」の指導者たちが依然として政界で大きな力を持っている。
選挙は独立した選挙管理委員会によって運営され、投票率は概して高い。これまでに複数回の大統領選挙および国会議員選挙が実施されており、政権交代も平和裏に行われている。
市民社会組織は活発で、政府から独立して機能しているが、多くは首都ディリに集中している。労働組合の力は、経済構造上、まだ弱い。カトリック教会は社会的に強い影響力を保持している。
5. 対外関係と軍事
東ティモールの外交政策は、国家の主権と独立の維持、国民の福祉向上、そして国際社会における平和と協力の促進を基本方針としている。独立当初から国際協力は極めて重要であり、国連ミッションや二国間援助が国家建設を支えてきた。
5.1. 対外関係
東ティモールは、国際連合、ポルトガル語諸国共同体(CPLP)の正式な加盟国である。また、東南アジア諸国連合(ASEAN)への加盟を長年の目標としており、2022年11月に原則加盟が承認され、現在は正式加盟に向けたロードマップが進行中である。太平洋諸島フォーラム(PIF)やメラネシア・スピアヘッド・グループ(MSG)にはオブザーバーとして参加している。さらに、脆弱国家のグループであるg7+の主導的役割も担っている。
外交上の主要な懸案事項としては、特に隣国との間の海洋境界線画定問題やティモール海の天然資源(石油・ガス)の分配問題がある。これらの問題解決においては、国際法を遵守し、関係国の立場を尊重しつつ、東ティモールの国益と国民の権利を最大限に確保することを目指している。また、過去の紛争における人権侵害の責任追及や和解プロセスも、一部の国との関係において重要なテーマとなっている。
5.1.1. 主要国との関係
- オーストラリア: 地理的に最も近い先進国であり、独立支援や経済援助において重要な役割を果たしてきた。しかし、ティモール海の石油・ガス資源の権益をめぐり長年対立があった。この問題は2018年に常設仲裁裁判所での調停を経て、海上境界線画定条約が締結され、資源収入の分配についても合意に至った。安全保障、経済、開発協力など幅広い分野で関係を有する。
- インドネシア: 独立に至る経緯から複雑な感情もあるが、最大の隣国として極めて重要な関係にある。国境管理、経済協力、人的交流などが活発化しており、東ティモールはインドネシアのASEAN加盟への支持を重視している。過去の人権侵害問題については、真相究明と和解に向けた両国間の取り組みが進められている。
- ポルトガル: 旧宗主国であり、言語、文化、法制度などの面で深いつながりを持つ。独立支援、教育、司法分野での協力を継続している。CPLPを通じた連携も重要である。
- 韓国: 国連PKO活動(韓国軍の尚緑樹部隊派遣)を通じた独立支援以来、友好関係を維持している。開発協力や人的交流が行われている。
- 中華人民共和国: 近年、インフラ整備や経済支援を通じて影響力を増している。特に「一帯一路」構想のもとで、港湾、道路、政府庁舎などの建設プロジェクトに関与している。東ティモールにとっては重要な開発パートナーの一つであるが、債務問題や地政学的な影響について懸念する声もある。
- 日本: 独立当初からの主要な開発援助国の一つであり、インフラ整備、人材育成、平和構築などの分野で貢献してきた。自衛隊のPKO派遣も行った。東ティモールのASEAN加盟を支持している。
5.1.2. 国際機関における活動
東ティモールは2002年9月27日に国際連合に加盟し、国連の枠組みの中で平和構築、開発、人権擁護などの活動に積極的に参加している。東南アジア諸国連合(ASEAN)へは2011年に正式に加盟申請を行い、2022年11月にASEAN首脳会議で原則加盟が認められ、すべてのASEAN関連会合へのオブザーバー参加が認められた。2023年5月のASEAN首脳会議で正式加盟のためのロードマップが採択され、早期の正式加盟を目指している。ポルトガル語諸国共同体(CPLP)には独立と同時に加盟し、ポルトガル語圏諸国との文化・経済交流を深めている。
5.2. 軍事
東ティモール国防軍(Forças de Defesa de Timor-Lesteポルトガル語, F-FDTL)は、2001年に設立された。その前身は独立闘争を担ったファリンティル(FALINTIL)である。国防軍は、外部からの脅威に対する国土防衛に加え、東ティモール国家警察(PNTL)と協力して国内の重大な暴力犯罪への対処も任務とする。2006年の国内危機以降、組織再編が行われた。
兵力は、常備軍約2,200人、海軍構成部隊約80人からなる。装備は、小型航空機1機、巡視艇7隻を保有しており、海軍力の増強が計画されている。
国防政策は、専守防衛を基本とし、近隣諸国との友好関係と地域協力の枠組みを重視している。オーストラリア、ポルトガル、アメリカ合衆国などと軍事協力関係にある。
軍の民主的統制と人権尊重は、国家建設の重要な課題として位置づけられている。2008年以降、国内における武力の行使は国防軍と国家警察に限定されており、民間人の銃器所持は厳しく制限されている。
6. 行政区画

東ティモールは、最上位の地方行政区画として13の基礎自治体(ムニシピオ) (municípioポルトガル語) と、1つの特別行政区 (Região Administrativa Especialポルトガル語) から構成されている。これらの自治体は、ポルトガル植民地時代に設置された県(distritoポルトガル語)を基盤としており、2009年に「県」から「基礎自治体」へと呼称が変更され、2014年の地方分権法によって一定の自治権が付与された。ただし、行政権能の多くは依然として首都ディリの中央政府に集中している。
各基礎自治体は、さらに複数の行政ポスト (posto administrativoポルトガル語) に分かれ、行政ポストはスッコ (sucoテトゥン語、村落共同体に相当) に、スッコはアルデイア (aldeiaテトゥン語、集落に相当) に細分化される。2022年時点で、全国に64の行政ポスト、442のスッコ、2,225のアルデイアが存在する。
スッコとアルデイアのレベルにおける行政は、伝統的な慣習や共同体の自治に深く根ざしており、地域住民のアイデンティティと密接に結びついている。スッコの指導者は選挙で選ばれるが、国家の正式な行政システムの外に位置づけられつつも、地域社会において大きな影響力を持っている。
以下は、14の自治体の一覧である(人口は2022年国勢調査)。
| 自治体名 | ポルトガル語名 | 首都 | 人口 (2022年) |
|---|---|---|---|
| アイレウ | Aileu | アイレウ | 54,631 |
| アイナロ | Ainaro | アイナロ | 72,989 |
| アタウロ | Atauro | ヴィラ・マウメタ | 10,302 |
| バウカウ | Baucau | バウカウ | 133,881 |
| ボボナロ | Bobonaro | マリアナ | 106,543 |
| コヴァリマ | Cova Lima | スアイ | 73,909 |
| ディリ | Dili | ディリ | 324,269 |
| エルメラ | Ermera | グレノ | 138,080 |
| ラウテン | Lautém | ロスパロス | 69,836 |
| リキシャ | Liquiçá | リキシャ | 83,689 |
| マナツト | Manatuto | マナツト | 50,989 |
| マヌファヒ | Manufahi | サメ | 60,536 |
| オエクシ=アンベノ特別行政区 | Oé-Cusse Ambeno | パンテ・マカッサル | 80,726 |
| ヴィケケ | Viqueque | ヴィケケ | 80,054 |
| 東ティモール合計 | ディリ | 1,340,434 |
オエクシ=アンベノは、インドネシア領西ティモール内に位置する飛び地であり、憲法で特別な行政・経済的地位が規定され、2014年に特別行政区となった。アタウロ島は、かつてディリ県の一部であったが、2022年1月1日に独立した自治体(アタウロ県)となった。
7. 地理
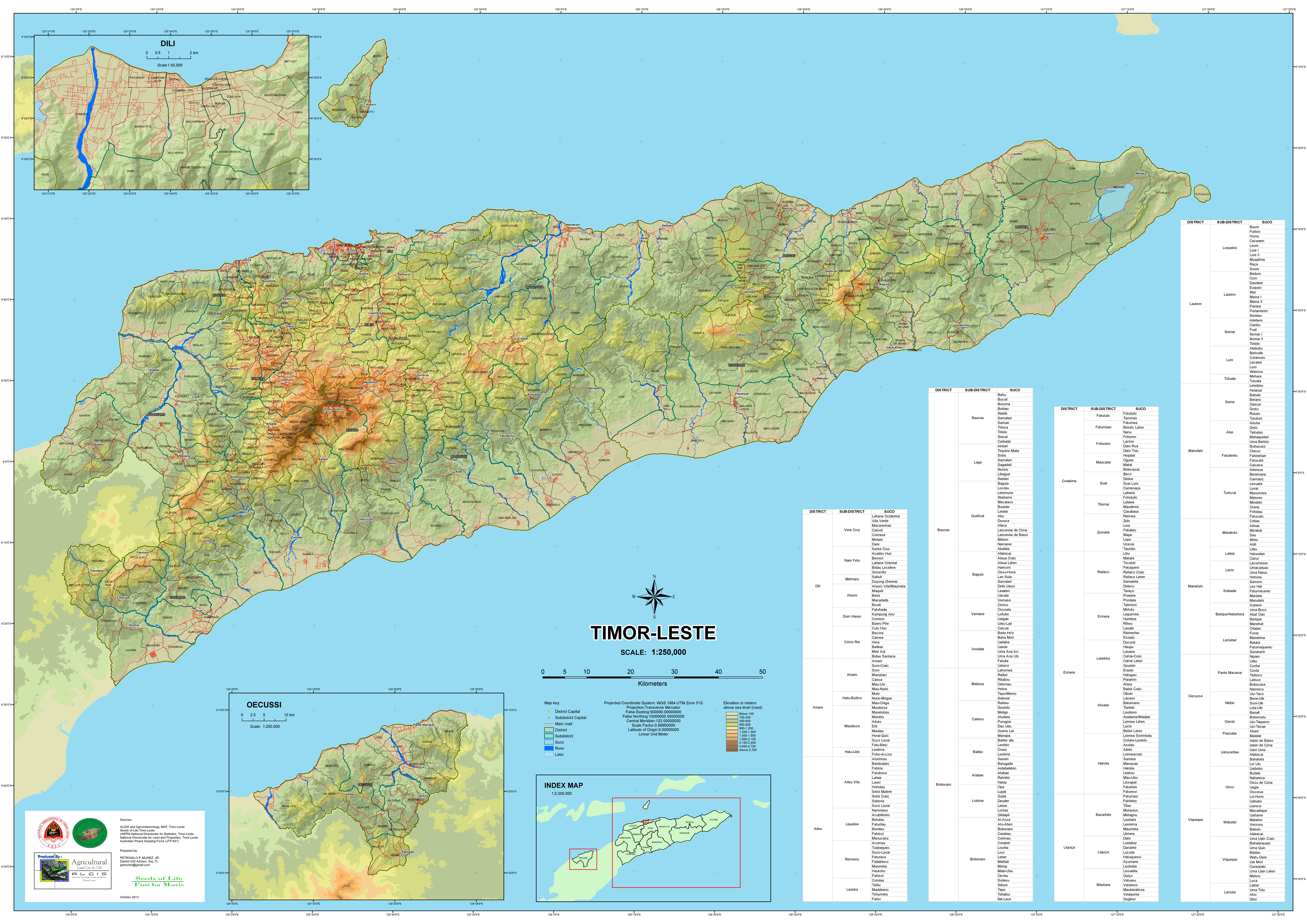
東ティモールは、東南アジアと南太平洋の間に位置し、マレー諸島内の小スンダ列島で最大のティモール島の東半分を占める。ティモール島は、アジアとオセアニアの境界領域であるウォーレシア地域の一部を形成する。北はより荒々しいバンダ海のオンバイ海峡とウェタル海峡、南はより穏やかなティモール海に面している。国土面積は約1.49 万 km2で、東西に約265 km、南北に約97 kmの広がりを持つ。緯度は南緯8度15分から10度30分、経度は東経125度50分から127度30分の間に位置する。海岸線の総延長は約700 km。インドネシアとの主な陸上国境は約125 km、オエクシ飛び地の陸上国境は約100 kmである。南はオーストラリア、その他はインドネシアと排他的経済水域を有する。
7.1. 自然環境
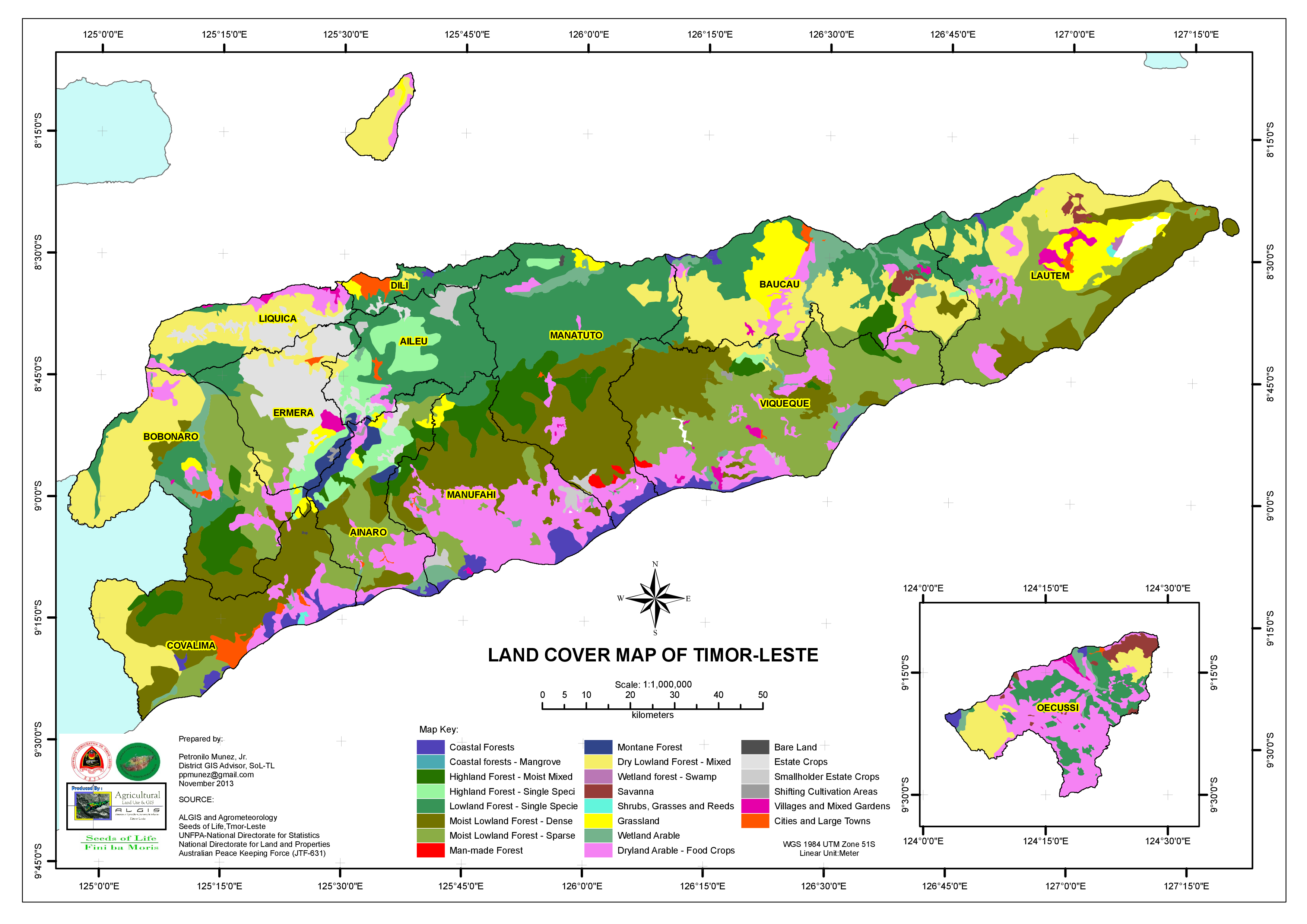
国土の大部分は山がちで、活動を停止した火山性の山脈が島を東西に貫いている。国土のほぼ半分が40%以上の勾配を持つ。南部はやや山が少なく、海岸線近くにいくつかの平野がある。最高峰は標高2963 mのタタマイラウ山(ラメラウ山としても知られる)。ほとんどの河川は乾季には少なくとも部分的に干上がる。一部の沿岸地域と河谷を除き、土壌は浅く浸食されやすく、質も低い。
首都であり最大の都市はディリ。第二の都市は東部の町バウカウである。
7.2. 気候
東ティモールは熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分ではAw)に属し、年間を通じて気温は比較的一定している。雨季は通常12月から5月まで続き、南部と内陸部ではオーストラリアからのモンスーンの影響でやや長くなる。雨季には月間降水量が222 mmから252 mmに達することがある一方、乾季には12 mmから18 mmにまで減少する。
大雨(特にラニーニャ現象によって降雨量が増加した場合)による洪水や地滑りの被害を受けやすい。山岳地帯の内陸部は沿岸部よりも涼しい。沿岸地域は地下水への依存度が高いが、不適切な管理、森林破壊、気候変動による圧力を受けている。気候変動により気温はわずかに上昇したと考えられているが、年間降水量に大きな変化は見られない。
7.3. 生態系と生物多様性
東ティモールの沿岸生態系は多様性に富み、南北の海岸線や東西の地域間で変化が見られる。同国の海域はコーラル・トライアングルと呼ばれる生物多様性のホットスポットの一部であり、豊かなサンゴ礁を有する。特にアタウロ島周辺のサンゴ礁は、調査されたどの場所よりも平均的な魚類の生物多様性が高いと認識されており、平均253種の異なる種が生息している。
最東端地域には、国内初の保護区であるニノ・コニス・サンタナ国立公園があり、イララロ湖地域やパイチャウ山脈が含まれる。ここには国内に残る最後の熱帯乾燥林があり、多くの固有の動植物種が生息し、人口は希薄である。
国内には約41,000種の陸上植物種が存在する。2010年代半ばには、森林が国土の35%を覆っていた。北部沿岸、中央高地、南部沿岸の森林はそれぞれ異なる特徴を持つ。東ティモールはティモールおよびウェタル落葉樹林エコリージョンに属している。
法律による環境保護は存在するものの、政府の優先事項とはなっていない。気候変動に加え、地域の生態系は森林破壊、土地劣化、乱獲、汚染によって脅かされている。
動物相
東ティモールの動物相は多様で、多くの固有種や絶滅危惧種が含まれる。島全体を覆うティモールおよびウェタル落葉樹林地域には、38種の哺乳類が生息する。東ティモール固有の哺乳類はティモールトガリネズミとティモールキクガシラコウモリの2種である。同国および同地域最大の哺乳類であるジャワルサジカと、唯一の在来有袋類であるキタコモンクスクスは、いずれも先史時代に小スンダ列島やニューギニアからの移住者によって島にもたらされたと考えられている。その他の哺乳類としては、カニクイザル、多数のコウモリ種、そして海棲哺乳類のジュゴンなどがいる。東ティモールには在来の馬の品種であるティモールポニーも存在する。
東ティモールの陸上生物多様性は、特に在来の鳥類において顕著である。2022年時点で、289種の鳥類が東ティモールで確認されている。特に絶滅の危機に瀕している鳥類には、絶滅危惧種のティモールアオバトやウェタルチビオバト、そして絶滅寸前のキバタンなどがある。東ティモールには、ゴシキセイガイインコの固有亜種である S. i. rubripileum が生息している。
東ティモールのサンゴ礁は、ソロモン諸島、パプアニューギニア、フィリピン、インドネシア、マレーシア、オーストラリアとともに、世界で最も生物多様性の高いサンゴ礁の場所であるコーラル・トライアングルに位置している。特にアタウロ島のサンゴ礁は、調査されたどの場所よりも平均的な魚類の生物多様性が最も高いと認識されており、アタウロ島沖のサンゴ礁サイトでは平均253種の異なる種が生息している。東ティモールの一つのサイトから記録された種の最高数は642種であり、インドネシアのラジャ・アンパット諸島に次いで2番目に多い。
さらに、これらのサンゴ礁は、コーラル・トライアングルの他の場所と比較して、サンゴの白化や海水温上昇による被害が限定的であるように見える。しかし、比較的手つかずの状態であるにもかかわらず、これらのサンゴ礁は依然として気候変動や生息地の破壊、特に爆破漁業の脅威にさらされている。これにより、サメなどの大型海洋生物が最も影響を受けたとされる。2016年の調査では、サンゴ礁の多様性にもかかわらず、サメの記録が著しく不足していた。
東ティモールの孤立性と観光客の少なさが、観光客が多いバリ島のような場所(観光の過多がサンゴ礁の健康に悪影響を与えている)とは対照的に、サンゴ礁の保全に役立ったと考えられている。東ティモール政府とアタウロ島の地元住民は、地域住民への教育、有害な開発プロジェクトの拒否、そして「タラ・バンドゥ」と呼ばれる自然保護の伝統的な法を重視することを通じて、サンゴ礁の保全に努めている。
8. 経済
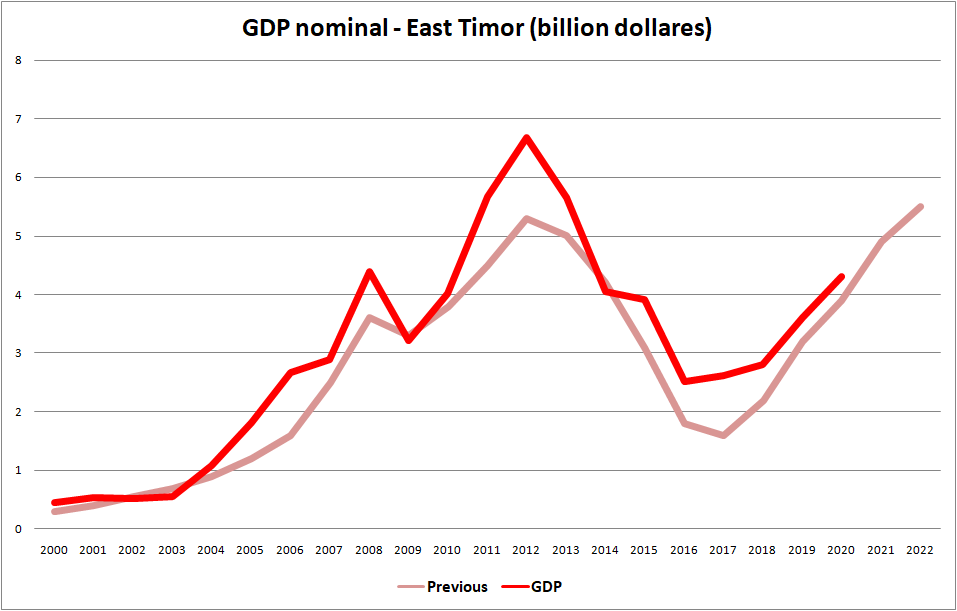
東ティモールの経済は市場経済であるが、少数の一次産品の輸出に大きく依存しており、公的部門の規模が大きい。国内的には、広範な貧困により市場活動は限定的である。通貨はアメリカ合衆国ドルを使用し、小口取引を容易にするために独自のセンターボ硬貨を鋳造している。経済は概して外国投資に対して開かれているが、外国人の土地所有が禁止されているため、多くの外国企業は現地のパートナーを必要とする。競争は、政府の障壁よりも経済規模の小ささによって制限されている。輸出よりも輸入がはるかに多く、物価は近隣諸国よりも高いことが多い。インフレは政府支出に強く影響される。2011年から2021年までの平均成長率は年2.5%と低迷している。
国民の大部分は非常に貧しく、全国民の40%以上が国内の貧困ライン以下で生活している。この貧困は特に農村部で顕著であり、多くが自給自足の農民や漁民である。都市部でさえ、大多数は貧困層に属する。全体的に女性は男性よりも貧しく、低賃金の職業に従事することが多い。栄養失調は一般的で、子供の半数以上が発育阻害を示している。2016年時点で、既婚の労働年齢(15~49歳)男性の91%が就業していたのに対し、既婚の労働年齢女性は43%であった。住宅や土地の所有、銀行口座の保有に関しても、男性に有利な若干の格差がある。人口の約4分の1が居住する東部3自治体は、人口の50%が居住する西部地域よりも貧困度が低い。
家族の66%は自給自足活動によって一部生計を立てているが、国全体としては食料自給を達成しておらず、輸入に依存している。農業労働は貧困のイメージと結びついており、政府からの投資はほとんどない。国内漁獲量の94%は海洋、特に沿岸漁業によるものである。首都ディリの住民は平均して裕福だが、国際基準では依然として貧しい。民間セクターの規模が小さいため、政府が公共事業の顧客となることが多い。国民の4分の1がインフォーマル経済に従事しており、公式の公的および民間セクターの雇用はそれぞれ9%である。労働年齢人口のうち、約23%が正規雇用、21%が学生、27%が自給自足の農家および漁師である。経済は主に現金ベースであり、銀行からの商業信用はほとんど利用できない。海外労働者からの送金は年間約1.00 億 USDに上る。

この貧困は、天然資源の著しい豊かさとは対照的であり、独立時には一人当たりの富は高中所得国に匹敵する価値があった。その半分以上が石油、4分の1以上が天然ガスであった。東ティモール石油基金は、これらの再生不可能な資源を持続可能な富の形態に変えるため、2005年に設立された。2005年から2021年までに、石油販売から得られた230億ドルが基金に入り、投資から80億ドルが生み出された一方、120億ドルが支出された。石油・ガス埋蔵量の減少により、HDIは2010年から低下し始めている。政府支出の80%はこの基金から賄われており、2021年時点で基金残高は190億ドルで、国家予算の10倍に相当する。石油収入が減少するにつれて、基金は枯渇のリスクにさらされており、2009年以降ほぼ毎年、持続可能なレベルを超える引き出しが行われている。バユ・ウンダンガス田の資源は間もなく枯渇すると予想されており、未開発のグレーター・サンライズガス田からの採掘は技術的・政治的に困難であることが判明している。残りの潜在的埋蔵量も、石油・ガスがエネルギー源として好まれなくなるにつれて価値を失いつつある。
国の経済は政府支出と、それより小規模ながら外国からの援助に依存している。政府支出は2012年から減少し始め、これはその後数年間にわたり民間セクターに波及効果をもたらした。政府とその国営石油会社は、しばしば大規模な民間プロジェクトに投資する。政府支出の減少はGDP成長の減少と一致した。石油基金に次いで2番目に大きな政府収入源は税金である。税収はGDPの8%未満であり、地域の他の多くの国や同規模経済の国よりも低い。その他の政府収入は、港湾局、インフラ企業、東ティモール国立大学などを含む23の「自治機関」から得られる。全体として、政府支出は依然として世界で最も高い水準にあるが、教育、保健、水道インフラへの投資はごくわずかである。
民間セクターの発展は、人的資本の不足、インフラの脆弱性、不完全な法制度、非効率的な規制環境のために遅れている。財産権は依然として不明確であり、ポルトガルおよびインドネシア統治時代の矛盾する権利証書に加え、伝統的な慣習権にも対応する必要がある。2010年時点で、都市部(32万1043人)の87.7%、農村部(82万1459人)の18.9%の世帯が電力を利用しており、全体の平均は38.2%である。民間セクターは、労働年齢人口が増加しているにもかかわらず、2014年から2018年にかけて縮小した。農業と製造業は、独立時よりも一人当たりの生産性が低い。非石油経済セクターは発展しておらず、建設業と行政の成長は石油収入に依存している。石油への依存は、いくつかの資源の呪いの側面を示している。コーヒーは2013年から2019年までの全非化石燃料輸出の90%を占め、そのような輸出総額は年間約2000.00 万 USDであった。2017年には、7万5000人の観光客が同国を訪れた。
8.1. 経済構造と現状
東ティモールの経済は、石油と天然ガスの輸出に大きく依存している。これらの資源からの収入は政府歳入の大部分を占め、2005年に設立された東ティモール石油基金を通じて管理されている。この基金は、将来の世代のために資源収入を持続可能な形で活用することを目的としているが、近年は政府支出の増大により、基金の持続可能性が懸念されている。
国内総生産(GDP)は、石油・ガス部門の変動に大きく左右される。通貨はアメリカ合衆国ドルが公式に使用されており、補助通貨として東ティモール・センターボ硬貨が流通している。物価は輸入品への依存度が高いため、比較的高水準で推移している。
雇用は農業部門が依然として最大の受け皿であるが、生産性は低い。失業率は高く、特に若年層の雇用問題は深刻である。貧困率は依然として高く、国民の約4割が貧困ライン以下で生活しており、地域格差や男女格差も存在する。富の分配と社会格差の是正は、経済政策の重要な課題である。
8.2. 主要産業
- 石油・天然ガス: 経済の最大の柱であり、ティモール海のバユ・ウンダンガス田やグレーター・サンライズガス田(オーストラリアとの共同開発区域を含む)からの収入が国家財政を支えている。しかし、既存油田の枯渇が近づいており、新たな開発や経済の多角化が急務となっている。労働者の権利保護や環境への影響評価は、国際的な基準に沿って行われる必要がある。
- 農業: 国民の大多数が従事しているが、主に自給自足的な小規模農業である。主要作物は米、トウモロコシ、キャッサバ、コーヒーなど。特にコーヒー豆は、オーガニックやフェアトレード製品として国際的に評価されており、重要な輸出産品の一つである。土地所有制度の未整備や灌漑施設の不足、技術水準の低さが生産性向上の課題となっている。
- 漁業: 豊富な海洋資源を有するが、小規模な沿岸漁業が中心であり、大規模な商業漁業は未発達である。持続可能な漁業管理と資源保護が求められる。
- 観光業: 手つかずの自然、美しい海岸線、豊かなサンゴ礁、独自の文化など、観光資源は豊富であるが、インフラの未整備やアクセスの悪さから、まだ十分に開発されていない。エコツーリズムなどを中心とした持続可能な観光開発が期待される。
8.3. 開発課題と展望
東ティモール経済は、石油・ガス資源への過度な依存からの脱却と、持続可能で公正な発展の実現という大きな課題に直面している。
- 経済の多角化: 石油以外の産業、特に農業、漁業、観光業、小規模製造業の育成が不可欠である。民間セクターの活性化、外国直接投資の誘致、輸出競争力のある産品の開発が求められる。
- インフラ開発: 道路、港湾、空港、電力、通信、上下水道といった基礎インフラの整備が急務である。これにより、国内経済活動の円滑化、生活水準の向上、投資環境の改善が期待される。
- 人材育成: 教育水準の向上、職業訓練の充実を通じて、産業界が必要とする人材を育成する必要がある。特に、若年層の雇用機会創出が重要である。
- 環境保全: 開発と環境保全の両立が求められる。森林破壊、土地劣化、海洋汚染などの環境問題への対策を強化し、生物多様性の保全に努める必要がある。
- 労働権益の保護: 労働者の権利を保障し、公正な労働条件を確保するための法整備と監督体制の強化が重要である。
- 社会的公正の実現: 貧困削減、地域格差の是正、ジェンダー平等、マイノリティの権利擁護など、包摂的な社会経済開発を目指す必要がある。汚職対策やグッドガバナンスの確立も不可欠である。
これらの課題克服には、政府の強力なリーダーシップ、国際社会との連携、そして国民自身の主体的な取り組みが求められる。石油基金の賢明な活用と、非石油部門への戦略的投資が今後の経済発展の鍵を握る。
9. 交通
東ティモールの交通インフラは、独立後の復興と開発努力にもかかわらず、依然として多くの課題を抱えている。国の地理的条件(山がちな地形)や長年の紛争による破壊が、交通網の整備を困難にしてきた。
主要な交通手段は道路交通であるが、舗装率は低く、特に地方部では雨季に通行が困難になる道路も多い。首都ディリと主要都市を結ぶ幹線道路の改修が進められているが、地方の道路網の整備は遅れている。公共交通機関としては、ミクロレットと呼ばれる小型バスや乗り合いタクシーが主要な都市や町で運行されているが、運行スケジュールや安全面での課題がある。
国内には鉄道は存在しない。
主要な港湾は、首都ディリにあるディリ港である。貨物輸送や国際フェリーが発着するが、施設の老朽化や容量不足が指摘されており、近郊のティバール湾に新港の建設が進められている。
空の玄関口は、ディリにあるプレジデンテ・ニコラウ・ロバト国際空港である。インドネシア(バリ島、ジャカルタ)、オーストラリア(ダーウィン)、シンガポールなどへの国際線が就航している。国内線は、ディリからオエクシやアタウロ島などへの小規模な便が運航されている。
交通インフラの整備は、経済発展、地域間格差の是正、国民生活の向上にとって不可欠であり、政府は国際的な支援を受けながら、道路網の改修、港湾・空港施設の近代化、公共交通システムの改善に取り組んでいる。
10. 社会
東ティモールの社会は、長年の植民地支配と紛争の歴史、そして独立後の国家建設の過程で形成されてきた多様な側面を持つ。人口構成、言語、宗教、教育、保健医療、人権状況、治安、メディアなど、各分野で課題と進展がみられる。
10.1. 人口構成

2022年の国勢調査によると、東ティモールの総人口は約134万人である。人口増加率は比較的高く、年齢構成は若年層が非常に多いピラミッド型を特徴とする。これは高い出生率を反映している。都市化率はまだ低いが、首都ディリへの人口集中が進んでいる。
住民は、オーストロネシア語族系(メラネシア人を含む)とパプア系の諸民族が混住しており、多様な民族集団が存在する。最大の民族集団はテトゥン人である。その他、マンバイ人、マカサエ人、ブナック人、ケマック人、ファタルク人など、多数の小規模な民族集団が独自の言語と文化を保持している。
ポルトガル植民地時代からのメスティーソ(ポルトガル人と現地住民の混血)や、華人(主に客家)のマイノリティも存在する。インドネシア占領期に移住してきたインドネシア人も一部居住している。
民族間の融和とマイノリティの権利擁護、そして特に紛争の影響を受けやすい女性や子供、貧困層などの脆弱な立場の人々の状況改善が社会的な課題となっている。
10.2. 言語
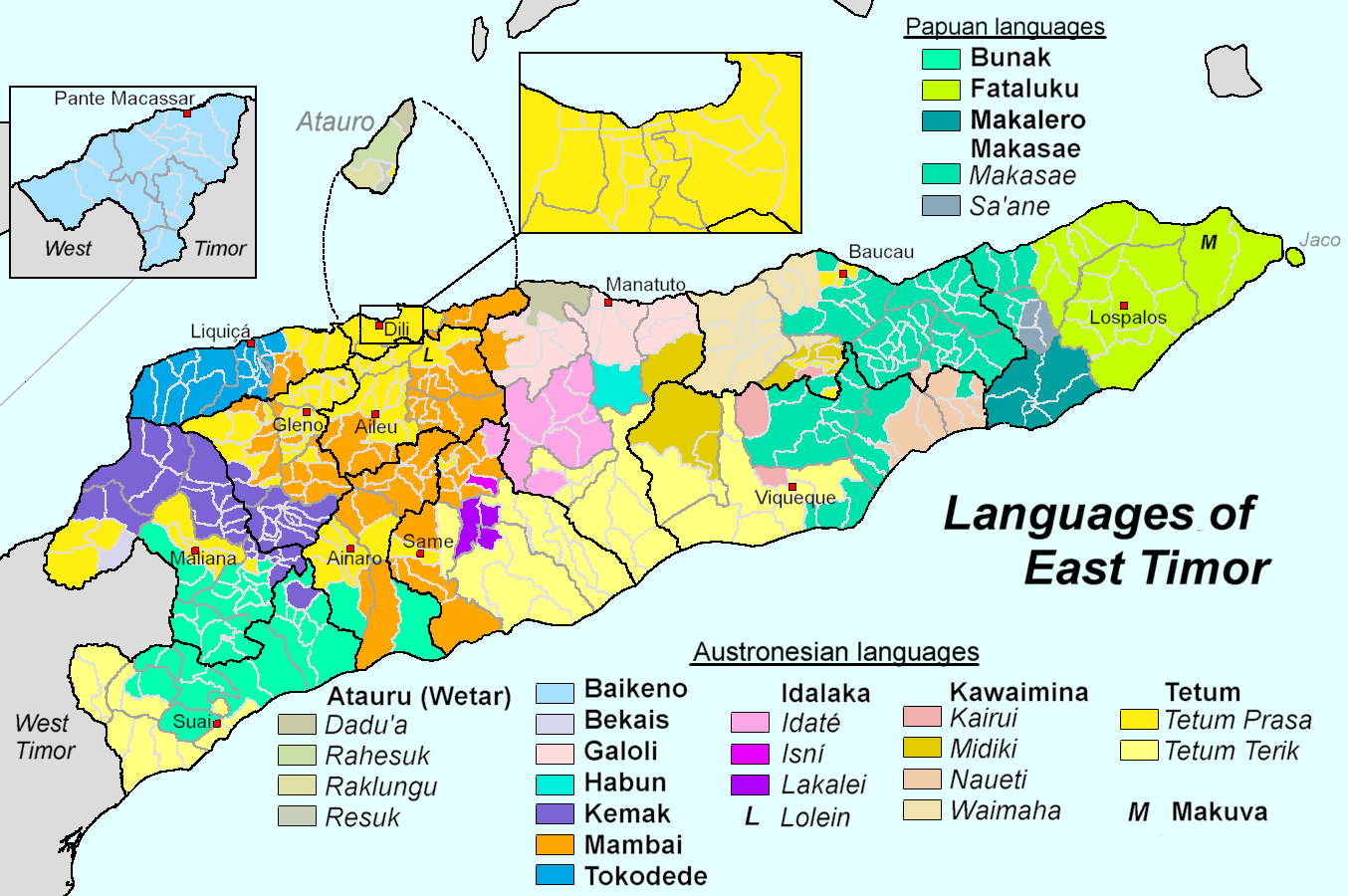
東ティモールは多言語国家であり、公用語はテトゥン語とポルトガル語である。憲法では、インドネシア語と英語が「実用語」として規定されている。
テトゥン語は、オーストロネシア語族に属し、国内で最も広く話されているリンガ・フランカ(共通語)である。ポルトガル語は、旧宗主国の言語であり、法律、行政、高等教育などの分野で使用されているが、国民全体への普及率はテトゥン語ほど高くない。独立後、ポルトガル語教育が推進されている。
インドネシア語は、24年間のインドネシア統治時代の影響で、特に中高年層や教育を受けた層を中心に広く理解され、メディアや商業の分野でも依然として使用されている。英語は、国際機関やNGOとのコミュニケーション、観光業などで重要性を増している。
これらに加え、国内には30以上の地方言語(母語)が存在する。主なものに、マンバイ語、マカサエ語、ファタルク語、ブナック語、ケマック語、トコデデ語などがある。これらの多くはオーストロネシア語族またはパプア諸語に分類される。
言語政策としては、公用語であるテトゥン語とポルトガル語の地位を確立しつつ、地方言語の保護と多様性の尊重が図られている。しかし、教育現場での使用言語や、公的サービスにおける言語アクセスなど、課題も残されている。識字率は徐々に改善しているが、依然として低い水準にある。
10.3. 宗教

東ティモールの国民の大多数はキリスト教を信仰しており、その約97.6%(2022年国勢調査)がローマ・カトリックの信者である。プロテスタントは約1.98%で、その他にイスラム教(0.24%)、伝統信仰(0.08%)、仏教(0.05%)、ヒンドゥー教(0.02%)などが少数存在する。
カトリック教会は、ポルトガル植民地時代に布教が始まり、特にインドネシア占領下で民族的アイデンティティと抵抗運動の精神的支柱として大きな役割を果たした。インドネシアの国家イデオロギーであるパンチャシラは国民に公認宗教への帰属を求めたため、伝統的なアニミズム信仰を持っていた多くの東ティモール人がカトリックに改宗した。その結果、1975年の侵攻時にはカトリック教徒は人口の20%程度だったが、占領初期の10年間で95%に急増した。
憲法は信教の自由と政教分離を保障しつつも、前文で「国家解放の過程におけるカトリック教会の参加」を承認しており、カトリック教会は社会的に強い影響力を保持している。国内にはディリ大司教区、バウカウ教区、マリアナ教区の3つのカトリック教区が存在する。
農村部では、カトリック信仰と伝統的なアニミズム的信仰が習合している様子も見られる。
10.4. 教育

東ティモールの教育制度は、独立後の国家建設における最重要課題の一つとして位置づけられている。長年の紛争とインドネシア統治下での教育機会の制限により、識字率の低さや教育インフラの未整備が深刻な問題であった。
2021年時点での成人識字率は68%、15歳から24歳の若年層では84%であり、徐々に改善している。女子の就学率は男子よりも高い傾向にあるが、思春期に達すると中退する女子もいる。
教育制度は、初等教育(6年間)、前期中等教育(3年間)、後期中等教育(3年間)が基本となっている。公用語であるポルトガル語とテトゥン語が主要な教育言語であるが、教材不足や教員の質の課題も指摘されている。インドネシア語も一部で使用されている。
初等学校は全国に存在するが、教育の質や教材にはばらつきがある。中等学校は主に県都に限定されている。高等教育機関としては、東ティモール国立大学(UNTL)が中心的な役割を担っており、いくつかの私立大学やカレッジも存在する。
政府は教育予算を国家予算の約10%程度配分し、教育機会の拡大、教育の質の向上、教員養成、カリキュラム開発などに取り組んでいる。しかし、依然として地方と都市部の教育格差、中退率の高さ、熟練した教員の不足などが課題として残っている。ポルトガルやオーストラリア、日本などの国々が教育分野での支援を行っている。
10.5. 保健医療
東ティモールの保健医療状況は、独立後に大きく改善したが、依然として多くの課題を抱えている。2021年の国家予算の6%が保健医療に割り当てられた。
1990年から2019年にかけて、平均寿命は48.5歳から69.5歳へと大幅に向上した。乳児死亡率は2003年の1,000人あたり60人から、2016年には30人へと減少した。しかし、依然として妊産婦死亡率や5歳未満児死亡率は高い水準にある。
主な健康問題としては、栄養失調(特に子供の発育阻害が深刻で、5歳未満児の46%が該当)、感染症(結核、マラリア、デング熱など)、下痢症、呼吸器感染症などが挙げられる。また、非感染性疾患も増加傾向にある。
医療サービスへのアクセスは、特に地方部や遠隔地で限られている。医療施設や医療従事者(医師、看護師など)の不足、医薬品の安定供給の課題などが存在する。都市部と地方部の医療格差も大きく、富裕層は国外で高度な医療を受けることもある。
政府は、プライマリ・ヘルスケアの強化、母子保健サービスの改善、感染症対策、医療人材の育成、医療インフラの整備などを重点政策として進めている。国際機関やNGOが保健医療分野で重要な支援活動を行っている。
10.6. 人権状況
東ティモールは独立以来、民主主義と人権の尊重を国家建設の基本理念として掲げている。憲法は基本的な人権と自由を保障しており、表現の自由、集会の自由、信教の自由などが認められている。
しかし、実際の人権状況には依然として課題が存在する。司法制度は脆弱であり、法の支配の確立が途上にある。警察による権力濫用や過剰な武力行使の疑惑も報告されている。刑務所の環境も劣悪であるとの指摘がある。
過去の人権侵害、特にインドネシア占領下(1975年~1999年)に行われた大規模な殺人、拷問、強制失踪などに対する真相究明と正義の回復は、国民にとって極めて重要な課題である。東ティモールにおける受容・真実・和解委員会(CAVR)が設立され、報告書「チェガ!」(もうたくさんだ!)がまとめられたが、加害者の責任追及や被害者への十分な補償は道半ばである。
女性や子供に対する暴力、人身売買、児童労働なども社会問題として存在する。LGBTQの権利は法的に保障されておらず、社会的な差別や偏見も根強い。
表現の自由は概ね保障されているが、政府に批判的なジャーナリストや活動家が圧力を受ける事例も報告されている。
政府は、人権擁護機関の強化、司法改革、警察改革などを通じて人権状況の改善に取り組んでおり、市民社会組織や国際機関も人権擁護活動を活発に行っている。民主主義の定着とともに、人権状況の一層の改善が期待される。
10.7. 治安
東ティモールの治安状況は、2006年の国内騒乱以降、大幅に改善され、現在は比較的安定している。ただし、依然として一般犯罪(窃盗、強盗、暴行など)は発生しており、特に都市部では注意が必要である。
東ティモール国家警察(PNTL)が国内の治安維持を担当しており、国際社会の支援を受けて能力向上が図られてきた。2012年末に国際連合東ティモール統合ミッション(UNMIT)が活動を終了し、治安維持の全責任がPNTLに移管された。
過去には、武術集団(マーシャル・アーツ・グループ)間の抗争や、政治的緊張に起因する散発的な暴力事件が発生したこともある。若年層の失業率の高さや貧困が、犯罪や社会不安の一因となる可能性も指摘されている。
国境地域、特にインドネシアとの陸上国境付近では、不法越境や密輸などの問題も存在する。
全体として、凶悪犯罪の発生率は低いものの、夜間の単独行動を避ける、貴重品を適切に管理するなど、基本的な防犯対策は依然として重要である。
10.8. メディア
東ティモールのメディア環境は、独立後に発展し、表現の自由は憲法で保障されている。しかし、経済的な制約や人材不足、インフラの未整備などがメディアの発展を妨げている側面もある。
主要なメディア媒体は、新聞、ラジオ、テレビ、そして近年急速に普及しつつあるインターネットである。
新聞は主に首都ディリで発行されており、テトゥン語とポルトガル語で書かれているものが多い。発行部数は限られている。
ラジオは、識字率の低さや地方への情報伝達の手段として、最も広範な影響力を持つメディアである。国営ラジオ局に加え、コミュニティラジオ局も各地で活動している。
テレビは、国営放送局ラジオ・テレビジョン・東ティモール(RTTL)が中心であり、ディリ以外での受信可能範囲は限定的である。衛星放送やケーブルテレビも一部で利用可能である。
インターネットの普及率はまだ低いが、都市部を中心に若者層で利用者が増加している。ソーシャルメディアも情報交換の手段として利用されている。
報道の自由は概ね尊重されているが、政府や権力者に対する批判的な報道に対して、間接的な圧力や自己検閲が見られる場合もあるとの指摘もある。ジャーナリストの専門性向上やメディアの経済的自立が課題となっている。
11. 文化

東ティモールの文化は、先住のメラネシア系およびオーストロネシア系諸民族の伝統文化を基盤としつつ、長年のポルトガルによる植民地支配、そして比較的短期ながらも強い影響を残したインドネシア統治時代の文化、さらにはカトリック教会の影響が複雑に混じり合って形成されている。
11.1. 伝統と生活様式

東ティモールの伝統社会では、各集落や氏族のアイデンティティの核となる聖なる家(Uma Lulikウマ・ルリックテトゥン語)が重要な役割を果たす。これらの家屋は、祖先とのつながりや共同体の結束を象徴し、儀礼や集会の中心となる。建築様式は地域によって多様であり、茅葺きの高床式住居などが代表的である。
伝統的な織物であるタイス(Taisテトゥン語)は、女性によって手織りされ、儀礼用の衣装や贈答品として用いられる。タイスの文様や色彩は地域や氏族によって異なり、社会的な地位やアイデンティティを示す役割も持つ。2021年にはユネスコの無形文化遺産に登録された。
口承文学の伝統も豊かで、神話、伝説、叙事詩、民話などが世代を超えて語り継がれてきた。これらの物語は、共同体の歴史や価値観、宇宙観を反映している。
慣習法(アダット)は、土地所有、結婚、紛争解決など、人々の日常生活の様々な側面において依然として影響力を持っている。伝統的なリーダー(リウライやダトなど)が慣習法に基づいて地域社会の調停や意思決定に関与することも多い。
日常生活では、農業や漁業を中心とした自給自足的な生活様式が、特に農村部では今も根強く残っている。共同体内の相互扶助の精神も重視される。
11.2. 芸術
東ティモールの芸術は、伝統的な様式と現代的な表現が共存している。
音楽と舞踊は、儀礼や祝祭において不可欠な要素である。伝統音楽には、竹製の笛、太鼓、ゴングなどが用いられ、独特のリズムと旋律を持つ。舞踊は、戦いや収穫、求愛などをテーマにしたものが多く、色鮮やかな衣装と装飾品を身に着けて踊られる。現代音楽の分野では、ポルトガルやインドネシアのポピュラー音楽の影響を受けたアーティストも活動している。
文学は、口承文学の豊かな伝統に加え、ポルトガル語やテトゥン語による詩作や散文も生まれている。独立運動の指導者であったシャナナ・グスマンは詩人としても知られる。独立後の新しい世代の作家たちによる作品も徐々に現れている。
映画の分野では、2013年に初の長編劇映画『ベアトリスの戦争』(Beatriz's War英語)が公開された。この作品は、インドネシア占領下の東ティモールの女性の視点から描かれ、国際的にも評価された。その後も、ドキュメンタリー映画を中心に製作が続けられている。
その他、木彫り、陶器、絵画などの視覚芸術も存在する。
11.3. スポーツ
東ティモールで最も人気のあるスポーツはサッカーである。ポルトガルとインドネシアの統治下にあった歴史的経緯から、サッカー文化が深く根付いている。国内プロサッカーリーグとしてLFAプリメーラ・ディビジョンが存在する。サッカー東ティモール代表は、国際サッカー連盟(FIFA)およびアジアサッカー連盟(AFC)に加盟しており、FIFAワールドカップ予選やAFCアジアカップ予選、東南アジアサッカー選手権などに参加しているが、国際的な実績はまだ乏しい。
オリンピックには、2000年シドニーオリンピックに個人参加選手団として初参加し、2004年アテネオリンピックから正式に東ティモール選手団として参加している。これまでにメダル獲得はない。陸上競技、ボクシング、自転車競技、テコンドーなどの種目で選手を派遣している。
東南アジア競技大会にも参加しており、アルニス、ボクシング、テコンドーなどの格闘技系種目でメダルを獲得したことがある。
その他、バレーボールやバスケットボールなども人気がある。
11.4. 祝祭日
東ティモールの祝祭日は、国家の重要な出来事を記念する日、宗教的な祝祭日、そして国際的に祝われる日などから構成される。
| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記例(ポルトガル語 / テトゥン語) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | Ano Novo / Tinan Foun | |
| 移動祝日 | 聖金曜日 | Sexta-Feira Santa / Sesta-Feira Santa | 復活祭前の金曜日 |
| 移動祝日 | 復活祭 | Páscoa / Páskua | |
| 5月1日 | メーデー(国際労働者の日) | Dia do Trabalhador / Loron Traballadór nian | |
| 5月20日 | 独立回復記念日 | Dia da Restauração da Independência / Loron Restaurasaun Independénsia nian | 2002年の独立回復を記念 |
| 移動祝日 | 聖体の祝日 | Corpo de Deus / Korpu Kristu nian | |
| 移動祝日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | Eid al-Adha / Idul Adha | イスラム教の祝日 |
| 8月30日 | 国民協議記念日(住民投票記念日) | Dia da Consulta Popular / Loron Konsulta Populár nian | 1999年の独立に関する住民投票を記念 |
| 11月1日 | 諸聖人の日 | Dia de Todos os Santos / Loron Santu Hotu-Hotu nian | |
| 11月2日 | 死者の日 | Dia dos Finados / Loron Matebian nian | |
| 11月12日 | 国民青年デー(サンタクルス事件記念日) | Dia Nacional da Juventude / Loron Nasionál Juventude nian | 1991年のサンタクルス事件を追悼 |
| 11月28日 | 独立宣言記念日 | Dia da Proclamação da Independência / Loron Proklamasaun Independénsia nian | 1975年の一方的な独立宣言を記念 |
| 12月7日 | 国民英雄デー | Dia dos Heróis Nacionais / Loron Erói Nasionál sira-nian | 1975年のインドネシア侵攻の日、追悼 |
| 12月8日 | 無原罪の御宿り | Imaculada Conceição / Imakulada Konseisaun | カトリックの祝日 |
| 12月25日 | クリスマス | Natal / Natál | |
| 移動祝日 | イード・アル=フィトル(断食明けの祭り) | Eid al-Fitr / Idul Fitri | イスラム教の祝日 |