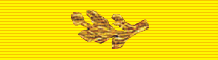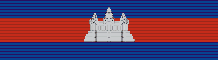1. 概要

笹川陽平(笹川 陽平ささかわ ようへい日本語、1939年1月8日生)は、日本財団の会長であり、世界保健機関(WHO)ハンセン病制圧特別大使、そして日本政府のハンセン病に関する人権啓発大使も務める社会運動家である。彼は、父である笹川良一の影響を受けながら、多岐にわたる国際的および国内的な社会貢献活動を展開してきた。
笹川氏は、社会起業家としての側面を持ち、チェルノブイリ原子力発電所事故の被害児童支援、マラッカ海峡の安全確保、アフリカの食糧増産運動、グローバル奨学金ネットワークの構築、フォーラム2000の運営など、国際社会における幅広い援助活動を主導。国内では、NPO・ボランティア活動の育成、高齢者・障害者福祉の向上、犯罪被害者支援、海賊対策、東京マラソンの開催など、政府の政策が及ばない分野に焦点を当てた活動を行っている。
特に、ハンセン病の制圧と患者・回復者への差別撤廃を生涯の使命と位置づけ、医学的側面だけでなく、人権問題としての解決にも尽力。国連人権理事会での決議採択に貢献し、インドでの支援財団設立など、その活動は国際的に高く評価されている。
一方で、ミャンマー国民和解担当日本政府代表としての活動は、同国の複雑な政治状況、特に2021年ミャンマー軍事クーデター後の国軍との関係性から、その役割や影響について様々な議論を呼んでいる。また、日本財団の主要な財源である競艇事業との関わりや、東日本大震災復興支援におけるフィリップモリスからの寄付受領など、その活動は常に社会的な注目と評価、そして時には批判の対象となってきた。
笹川氏の活動の根底には、現代社会の複雑な問題には協調的アプローチが必要であるという信念があり、政治、政府、学術、民間といった多様なセクターを巻き込んだ広範なネットワークを構築している。彼の取り組みは、民主主義、人権、社会進歩に対する彼の強い信念と、持続可能な解決策を模索する社会起業家精神を反映している。
2. 生涯と背景
笹川陽平は、1939年1月8日に日本で生まれた。彼の人生は、父である笹川良一の影響を強く受けながら形成された。
2.1. 幼少期と教育
笹川陽平は、1939年1月8日に笹川良一の三男として生まれた。1945年、彼が6歳の時、母と共に浅草寿町に住んでいた。3月10日の東京大空襲の際には、隅田川への避難を避け、別の方向へ進んだことが幸いし、町内のほとんどの人々が命を落とす中で、奇跡的に助かったという戦争体験を持つ。
父・良一のもとで、高校、大学と多感な時期を過ごした。当時、東京都文京区小石川にあった良一の家は、食客や来客が絶えず、「笹川旅館」と呼ばれるほど賑わっていた。「学問などしなくていい。社会勉強は俺が教えてやる」というのが良一の教育方針であり、陽平は早朝から掃除、洗濯、靴磨きを終えて登校し、午後4時には帰宅させられ、買い物、料理、風呂掃除など、連日深夜まで手伝いをさせられていた。このような厳しい父親のもとで様々な教育を受けた笹川は、父親に対して「一切反発することはなく、父であると同時に私の人生の師でした」と語っている。
彼は明治大学政治経済学部を卒業した。
2.2. 家族関係
笹川陽平の父は、日本船舶振興会(現・日本財団)の初代会長である笹川良一である。良一は実業家、政治家、そして慈善活動家としても知られている。
陽平には、次兄に元自由民主党衆議院議員の笹川堯がいる。政治家の笹川博義は甥にあたる。
自身の子供としては、長男に貴生(1972年11月23日生)、次男に順平(1975年2月28日生)、三男に光平(1976年8月17日生)、四男に正平(1980年9月2日生)がいる。
3. 経歴とリーダーシップ
笹川陽平は、日本モーターボート競走会会長や海洋政策研究財団理事長を歴任した後、1989年に日本財団理事長に就任した。2005年7月には、前会長の曽野綾子の退任を受けて、会長に選任された。
3.1. 日本財団会長
日本財団会長として、笹川陽平は、その計画性とリーダーシップで国際的に評価されている社会起業家として知られている。彼の指揮のもと、日本財団は多岐にわたる社会貢献事業を展開している。
彼のリーダーシップの下で推進された主要なプロジェクトには、以下のようなものがある。
- チェルノブイリ原子力発電所事故の被害児童に対する20万人規模の検診活動。
- マラッカ海峡の安全な航行を支援するための、利用者負担による支援制度の確立。
- 世界69の大学に広がるグローバル奨学金ネットワークの構築。
- 2,000人の中国人医師を日本に招き、研修を行うプログラムの設立。
- 年間を通じて利用可能な北極海航路の開発。
彼の国際援助活動は、「食料安全保障」「医療」「教育」という、生活に不可欠な3つの分野に焦点を当てている。国内での援助活動は、政府の政策が及ばない分野、特にNPOやボランティア活動の育成、高齢者や障害者へのサービスの拡充、全国の社会福祉団体への2万台の介護車両の寄贈などに重点を置いている。
笹川は、現代の問題には協調的アプローチが不可欠であると信じており、政治、政府、学術、民間の各セクターにまたがる広範なネットワークを築いてきた。その一例が、故ヴァーツラフ・ハヴェル元チェコ共和国大統領と共に11年間運営してきたフォーラム2000である。このイニシアチブは、世界中の専門家や著名な個人を集め、地球規模の問題について議論する場となっている。
また、彼は公益団体の情報公開の重要性を提唱しており、自身の活動や考えを日本語のブログで日々公開している。彼のリーダーシップのもと、日本財団の情報公開への取り組みは、公益分野における政府の改革の中で高い評価を得ている。企業が企業の社会的責任(CSR)を果たす形で社会福祉活動に直接参加するのを支援するウェブサイト「CANPAN CSR Plus」を立ち上げたほか、国や地方自治体、非営利団体、企業のCSR活動が一体となって共通の利益を創出する社会の実現を提唱している。
3.2. その他の主要な役職
日本財団会長の他にも、笹川陽平は国内外で多くの重要な役職を歴任し、その活動を通じて社会に貢献している。
- 世界保健機関(WHO)ハンセン病制圧特別大使**(2001年5月 - 現在):ハンセン病の撲滅と患者・回復者への差別撤廃を目指し、国際的な啓発活動や政策提言を行っている。
- ハンセン病人権啓発大使**(日本国、2007年 - 現在):日本政府の代表として、ハンセン病に関する人権問題の解決に向けた外交活動を展開している。
- ミャンマー少数民族福祉向上大使**(日本国、2012年6月11日 - 現在):ミャンマーにおける少数民族の福祉向上と国民和解の促進に尽力している。
- ミャンマー国民和解担当日本政府代表**(日本国、2013年2月 - 現在):ミャンマー政府と少数民族武装組織間の対話促進を支援し、平和プロセスへの関与を深めている。
4. 主要な活動と業績
笹川陽平が主導し、大きな影響を与えた具体的な活動と業績は多岐にわたる。
4.1. ハンセン病制圧活動
笹川陽平は、ハンセン病の制圧を自身の生涯の使命と位置づけている。この使命は、父である笹川良一から受け継いだものであり、彼の活動の原点となっている。
1965年、笹川は父に連れられて韓国のハンセン病療養所を訪問した。そこでハンセン病患者や回復者が直面する差別を目の当たりにし、その衝撃からハンセン病対策の必要性を痛感し、自ら活動を開始した。彼は「ハンセン病は治る」という正しい知識の普及に努め、蔓延国などで患者・回復者、政府指導者、報道機関などとの対話を推進している。
2001年5月からは世界保健機関(WHO)ハンセン病制圧特別大使を務めている。1990年代には、ハンセン病制圧の主要な方法である多剤併用療法(MDT)の普及に尽力し、世界のハンセン病患者数を劇的に減少させることに貢献した。しかし、病気が治癒しても、社会の偏見により就業や子供の教育において家族までもが差別を受ける現状を問題視し、ハンセン病を単なる医学的問題ではなく、人権問題を含む社会問題として捉えるべきだと提唱した。
この問題意識に基づき、2003年7月には国際連合人権高等弁務官事務所を訪問し、この問題を国際連合人権委員会(現国際連合人権理事会)で取り上げるよう要請した。その結果、2004年3月には国連人権委員会本会議でハンセン病による差別問題を訴え、同年8月には人権促進保護小委員会がハンセン病と差別の問題を正式に人権問題として扱うための調査を開始した。さらに、2005年8月と2006年8月の2度にわたり、同小委員会で各国政府や国連機関に対する現状改善勧告決議が全会一致で採択された。2008年6月には、国連人権理事会で日本政府と58カ国が共同提案した「ハンセン病患者、回復者、家族に対する差別撤廃決議」が全会一致で採択され、その後国連総会でも採択された。
ハンセン病による社会問題の解決のため、2006年にはインドでハンセン病回復者とその家族の自立を支援する「ササカワ・インド・ハンセン病財団」を設立し、インド財界からの寄付金も募っている。また、2016年6月にはローマ教皇庁と国際シンポジウムを共催し、ハンセン病患者への差別撤廃を求める結論と提言が採択された。
国際的なハンセン病制圧活動の実績により、2004年に読売新聞社の読売国際協力賞、2007年にはインドの国際ガンディー賞を受賞した。日本政府からはハンセン病人権啓発大使を委嘱され、ハンセン病の制圧と人権外交に貢献している。
4.2. 海洋政策と活動
笹川陽平は、海洋問題にも積極的に取り組んでいる。彼は、世界で最も船舶の交通量が多いマラッカ海峡の安全確保のための費用負担として、新しい基金の設置を提案した。これは、従来の「海洋利用は無料」という考え方を覆し、現在の国際情勢に鑑みて航行者負担の必要性を説くものである。
また、「海に守られた日本から海を守る日本へ」をコンセプトに、2007年の海洋基本法の制定に奔走し、その中心的な役割を担った。さらに、2004年には国連と日本財団が共同で国連-日本財団フェローシッププログラム([https://www.un.org/Depts/los/nippon/index 国連-日本財団フェローシッププログラム])を立ち上げ、次世代の海洋リーダーや専門家の育成に貢献している。
2016年には、洋上開発における人材育成を目的とした産学官民連携の全国的な取り組みである「日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム」を設立した。2017年には、国連海洋会議の全体会議で、包括的な海洋ガバナンスのための政府間パネルを国連に設置することを提案している。
2018年には、海洋ごみ問題に対処するための大規模な全国的イニシアチブ「CHANGE FOR THE BLUE」プロジェクトの立ち上げを発表し、民間企業、政府、学術機関を含む複数のステークホルダーを巻き込み、具体的なプログラムの実施を目指している。また、2016年には、2030年までに世界の海底地形をマッピングするイニシアチブ「Seabed 2030」を立ち上げた。
4.3. 国際援助と社会起業家活動
笹川陽平は、国際社会において幅広い援助活動と社会起業家としての取り組みを展開している。
- チェルノブイリ事故被害児童支援**: 1999年には、チェルノブイリ原子力発電所事故の被害児童に対する小児医療支援を提供し、10年以上にわたり20万人以上の子供たちの検診活動を支援した。
- アフリカ食糧増産運動**: 1986年には、アフリカ諸国が主要作物の生産で自給自足できるよう支援する「ササカワ・グローバル2000プログラム」を開始した。これは、ジミー・カーター元米国大統領やノーマン・ボーローグ博士(ノーベル平和賞受賞者)と共に20年間にわたって推進された。
- グローバル奨学金ネットワーク構築**: 1987年に、世界中の主要な69大学にまたがる奨学金プログラム「ササカワ・ヤングリーダーズ・フェローシップ基金(SYLFF)」を設立し、次世代のリーダー育成に貢献している。
- 中国医療関係者研修制度**: 1987年に、2,000人の中国人医師を研修するための「ササカワ医学奨学金プログラム」を設立。2016年には、このプログラムを通じて約2,200人の医師が研修を修了し、日中間の医療・保健分野における相互理解と友好を促進した。
- フォーラム2000運営**: 故ヴァーツラフ・ハヴェル元チェコ共和国大統領と共に11年間にわたりフォーラム2000を運営。これは世界各国の知識人や著名人が集まり、地球規模の問題について議論する場となっている。
- アジア公共知識人フェローシップ**: 2000年には、アジアの5カ国で「日本財団アジア公共知識人(API)フェローシップ」を開始した。
- 義肢装具学校の設立**: 2010年には、インドネシアとフィリピンに義肢装具学校を設立した。
4.4. 国内社会貢献活動
笹川陽平は、日本国内においても多岐にわたる社会貢献活動を展開している。
- NGO・ボランティア支援**: 国内のNPOやボランティア活動の育成に力を入れている。東日本大震災の際には、被災地で活動する約700のボランティア団体への支援を行った。
- 高齢者・障害者福祉**: 高齢者や障害者に対する福祉サービスの拡充に重点を置き、全国の社会福祉団体へ2万台の介護車両を寄贈するなど、行政の支援が届きにくい分野を補完している。
- 犯罪被害者支援**: ホスピスナースの育成や、犯罪被害者への支援ネットワークの構築にも取り組んでいる。
- 海賊対策**: 海賊対策の策定や、北朝鮮工作船の一般公開など、海洋安全保障に関する取り組みも行っている。
- 東京マラソンへの貢献**: 2007年の海洋基本法の制定に奔走したほか、東京マラソンの組織化にも中心的な役割を果たした。
- 日本歯科医師会との共同プロジェクト**: 2009年6月1日には、日本歯科医師会と協力して、CSR活動の一環として「トゥースフェアリー(Tooth Fairy)」プロジェクトを開始した。これは、全国の歯科医院で不要になった金歯などの歯科撤去金属を日本財団に提供し、リサイクルして得た資金をミャンマーの小学校建設や小児がん病棟建設に充てるものである。
4.5. ミャンマーへの関与

笹川陽平は、ミャンマーの国民和解担当日本政府代表として、長年にわたり同国の平和プロセスと社会開発に深く関与してきた。
2012年6月11日、日本政府外務省は、ミャンマー国内でハンセン病対策、伝統医療品の普及、小学校建設など様々な活動をしてきた笹川に、ミャンマー少数民族福祉向上大使を委嘱した。軍政時代からミャンマーでの実績が評価されたもので、特に辺境のシャン州で少数民族が対立する中で小学校200校を完成させたことは、専門家からも驚きをもって迎えられた。その後、ラカイン州でも200校の建設を計画している。
2013年2月には、第2次安倍内閣の閣議決定により、ミャンマー国民和解担当日本政府代表に任命された。彼は、軍政時代のトップであったタン・シュエ大統領(当時)や、アウンサンスーチー、テイン・セイン大統領など、ミャンマーの主要な要人との間に信頼関係を築き、政府や外務省に頼らず民間独自で各事業を進めてきた。
2015年と2018年には、ミャンマー政府と少数民族武装組織間の全国停戦合意(NCA)の署名式に、日本政府特使として唯一の非隣接国代表として立ち会い、平和プロセスへの継続的な支援を表明した。また、2002年から開始された学校建設プログラムでは、2018年までにシャン州で300校、ラカイン州で100校、エーヤワディ地方域で60校の計460校が完成した。2016年からは、日本外務省の支援を受け、カレン州やモン州の紛争影響地域で家屋、学校、医療施設、井戸などを建設するリハビリテーションプログラムを開始している。
しかし、2021年2月1日のミャンマー軍事クーデター後も、笹川はミン・アウン・フライン国軍最高司令官との会談を継続しており、その活動については様々な評価と批判が存在する。テレビ朝日の報道ステーションのように、問題が複雑であるとして好意的に報道するメディアがある一方で、笹川のミャンマーへの関与が個人としてなのか、公益財団法人としてなのか、あるいは日本政府代表としてなのかが曖昧であることの危うさや不可解さを指摘する意見もある。クーデター後の武力弾圧に対する国際的な批判が高まる中、国軍と関係のあった日本企業が人権上の理由から撤退を余儀なくされる事例も相次ぎ、笹川の継続的な関与が、クーデター政権に正当性を与えることにつながるのではないかという懸念も示されている。
4.6. 東日本大震災復興支援
2011年3月11日に発生した東日本大震災に際し、笹川陽平は日本財団会長として陣頭指揮を執り、被災地への迅速な支援活動を展開した。
日本財団は、被害が最も甚大だった宮城県石巻市に災害支援センターを設置し、職員を派遣。現場で活動するボランティアたちの受け入れやコーディネートを行った。また、NPOやボランティア団体に対して、活動費として100万円を上限とする支援を実施した。
4月4日には、笹川自ら石巻市や女川町(宮城県)に赴き、死者・行方不明者の家族に対し、弔慰金や見舞金(1人5.00 万 JPY)を直接手渡した。4月中旬からは、大学生を集めて現地でのボランティア隊を組織し派遣。この活動は現在まで継続されており、派遣されたボランティアの数は延べ5,000人を超える。その他、災害FM放送局22局への支援や、4万2,000台のラジオ配布などの支援も実施した。これらの迅速な対応は、1995年の阪神・淡路大震災以来、国内で発生した28回に及ぶ災害ボランティア支援の実績が活かされたものである。
2011年6月には、日本財団とフィリップモリスとの共同で、18歳以上の子どもへの支援プロジェクト「Doorway to Smiles」を立ち上げた。この際、フィリップモリスから初期費用として3000.00 万 JPYが拠出された([http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/press_releases/Pages/20110609.aspx 日本財団とフィリップモリスジャパン株式会社、東日本大震災の被災地で子ども支援共同プロジェクト"Doorway to Smiles"を開始(2011年6月9日)])。笹川は、普段禁煙活動を行っている自身がたばこ会社から寄付金を受け取ることへの批判があることを認識しつつも、これは変節ではなく、被災地への善意は誰からであろうと受け取ると自身のブログで表明した([http://blog.canpan.info/sasakawa/archive/3085 笹川陽平ブログ(2011年6月9日)])。2012年11月には、同プロジェクトの成果として、石巻市役所1階に高校生50名とともに「いしのまきカフェ『 』」(かぎかっこ)をオープンすると発表された([http://www.pmi.com/ja_jp/media_center/press_releases/Pages/20121024.aspx フィリップモリスジャパン株式会社と日本財団が共同で被災地の子ども支援(2012年10月24日)])。
4.7. 文化・社会的な貢献
笹川陽平は、文化振興や社会的な議論にも貢献している。
- 世界的な弦楽器の収集・貸与事業**: 笹川の提案により、日本財団の支援を受けて、姉妹財団である日本音楽財団が1994年からストラディヴァリウスやグァルネリ・デル・ジェスによって製作された世界最高峰の弦楽器を収集し、国内外の一流演奏家や若手有望演奏家に無償で貸与する事業を実施している。現在、ストラディヴァリウス19丁、グァルネリ・デル・ジェス2丁を保有している。2011年6月には、東日本大震災の復興支援のため、保有するストラディヴァリウスの中で最高峰とされる「レディ・ブラント」をロンドンのオークションに出品し、史上最高値の1589.00 万 USD(約12.70 億 JPY)で落札された。その全額は、財団内に設置された「東日本大震災・伝統文化復興支援基金」に充当され、被災地での伝統芸能や祭りで使用する道具(山車、太鼓など)の復興に活用されている。
- 江戸城再建構想**: 2010年2月23日付の産経新聞「正論」欄で、観光立国・日本の目玉として、官民協力による江戸城再建を提唱した。彼は、パリのヴェルサイユ宮殿やロンドンのバッキンガム宮殿、ニューヨークの自由の女神などを例に挙げ、日本を代表する歴史的建造物としての江戸城天守の再建が必要であると主張。これは、日本のトップ技術の結晶であり、家族や地域社会、日本人としての絆を再確認するきっかけにもなると述べた。
- たばこ値上げ論争**: 2008年3月4日の産経新聞「正論」欄で、たばこ1箱1000 JPYへの値上げを提唱し、論争を巻き起こした。彼は、たばこが1箱1000 JPYになれば9割以上の喫煙者が禁煙するという報告を引用し、健康、防火、青少年の健全育成などの観点からたばこの値上げを訴えた。この提唱は、『現代用語の基礎知識2009』に「たばこ1箱1000円論争」として記載された。
4.8. 競艇事業との関わり
笹川陽平は、日本財団の主要な財源の一つである競艇事業の運営に深く関与し、その発展に貢献した。
1981年に全国モーターボート競走会連合会(現・日本モーターボート競走会)副会長に就任した笹川は、売上拡大に向けて様々な施策を打ち出した。1985年には電話投票が開始され、1986年には競艇界の悲願であった専用場外発売場「ボートピア」がオープンした。1994年には同連合会会長に就任。レジャーの多様化やライフスタイルの変化に対応するため、早くからナイターレースに着目し、1984年に浜名湖競艇場で公営競技界初のナイターレースの実験を行った。他の公営競技に先を越されたものの、1997年に桐生競艇場で初開催された。
2000年には連合会会長を退任し、名誉会長に就任。同年10月には、笹川の指揮で動いていた公営競技界初の3連勝式投票法の発売が住之江競艇場で行われ、その後、競馬や競輪も追随した。競艇の売上額は、バブル経済の崩壊と共に1991年の2.20 兆 JPYをピークに減少を続けているが、笹川は副会長に就任した1981年にはすでに、当時の硬直化した競艇界において新たな発想に基づき、将来の厳しい時代に備えた画期的な施策を打ち出していった。
毎年12月に開催される賞金王決定戦競走(SG競走)は、競艇の話題性と選手やレースのステータスを高めるため、1997年から優勝者に対する賞金額を1.00 億 JPYにしたのも笹川の発案であり、当時プロスポーツ界における一大会での最高賞金として話題を呼んだ。
なお、この競艇事業の収益は日本財団の主要な財源となっているが、その資金源については「賭博事業から得られた資金」として批判的な見解も存在する。
2009年3月、彼は同連合会名誉会長を退任した。
4.9. 特定の社会問題への取り組み
笹川陽平は、特定の社会問題に対しても積極的に関与し、その見解と行動を示している。
- 性同一性障害を持つ選手への対応**: 2002年3月、全国モーターボート競走会連合会で記者会見が行われ、性同一性障害者に悩む女性選手であった安藤千夏を、今後男性選手として登録してレースに出場させることを発表した。同連合会は当初、性同一性障害者による性別変更を認めない方針だったが、笹川が本人の人権を重く見て、登録変更を決断した。これはスポーツ界で性別の変更が認められる極めて珍しい事例であり、読売新聞は、日本精神神経学会の「性同一性障害」特別委員長である中島豊爾・岡山県立岡山病院長の「競技スポーツの世界でこうしたケースは聞いたことがない。性別の戸籍変更が認められないなど、性同一性障害の社会的理解や認知が進まない現状で、この決断は大変すばらしい」とのコメントを掲載し、その対応を評価した。
- アニメ映画におけるハンセン病差別表現への抗議**: 2012年1月、アメリカのソニー・ピクチャーズ アニメーションなどが制作し、海外で放映予定のアニメ映画「The Pirates! Band of Misfits」の本編と予告編に、ハンセン病への差別表現があることが判明した。ハンセン病患者や元患者に対する誤解、偏見、差別を助長する恐れがあると考えた笹川は、直ちに制作会社とその親会社に対し、当該箇所の修正・削除を求める抗議文を送付。後日、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの副会長から、差別的な表現を削除したとの回答があった。
- 中国政府に対するハンセン病患者入国禁止措置への抗議**: 2008年、北京オリンピック開催を前に、北京オリンピック組織委員会が公表した「オリンピック期間における外国人の出入国、中国滞在期間に関する法律指針」でハンセン病患者の入国が禁止された。笹川は即座に胡錦濤総書記やジャック・ロゲ国際オリンピック委員会委員長らに対し、法律指針の撤回を求め、オリンピック開催前に撤回された。この背景には、同年6月に国連人権理事会で日本政府が提案した「ハンセン病患者、回復者、家族に対する差別撤廃決議」が全会一致で採択され、中国政府も共同提案国として名を連ねていたにもかかわらず、法律指針でハンセン病患者を差別したことがあるとされている。
4.10. 中国との関係
笹川陽平は、中国との関係構築にも長年尽力している。1987年には、日中間の医学・保健分野での相互理解と友好を促進するために「笹川医学奨学金プログラム」を設立し、2,000人以上の中国人医師を日本で研修させた。また、日本語図書を中国の大学に寄贈する教育・研究図書プロジェクトも実施している。
世界69の大学に設置されているヤングリーダー奨学基金は、中国に10校ある。さらに、笹川日中友好基金は101.00 億 JPYの基金規模を有し、日中間の民間交流基金としては最大規模を誇る。この基金は、1989年の天安門事件により中国が国際的に孤立し、政治レベルで日中関係が冷え切った中で、民間レベルで両国関係をつなぐために設立されたものである。
笹川は、1985年の鄧小平中央軍事委員会主席(当時)をはじめ、胡耀邦総書記(当時、1986年)、楊尚昆国家主席(当時、1990年)、朱鎔基首相(当時、1997年)など、中国の歴代要人と会談を重ねてきた。現在の胡錦濤総書記とは、1994年に中央政治局常務委員時代に会っている。これらの要人に対して、笹川は常に媚びることなく、率直に意見を述べてきたとされる。彼の著書『二千年の歴史を鑑として』(日本僑報社)や2005年11月5日の南京大学でのスピーチ(『日本財団会長 笹川陽平ブログ』に全文掲載[http://blog.canpan.info/sasakawa/archive/20051109 笹川陽平ブログ(2005年11月9日)])では、日中間の歴史的背景や役割、将来のあるべき関係などについて、中国人相手に決して迎合することなく、事実や現状、歴史を述べ、中国人にとって耳の痛い話も含め、臆することなく意見を主張する姿勢を貫いてきた。
また、2004年には、ヤングリーダー奨学基金の設置校である蘭州大学が、基金の100.00 万 USD(当時約1.20 億 JPY)を現地投資信託会社で無断運用し失敗、回収不能になった際、直ちに胡錦濤総書記や王毅駐日大使(当時)などに書簡を送り説明を求め、中国政府を通じて蘭州大学の奨学金を元に戻すよう協力を要請した。また、記者会見を開催し報道機関に事実を説明した。2006年11月、王大使からの返答の書簡で「教育省から全額を元に戻すことが確認された。この問題によって生じたマイナスの影響について大変遺憾に思う」とされ、後日、日本財団に対し、大学側からも入金の連絡があった(現在は経営陣が一新され、従来通り奨学金プログラムが実施されている)。
5. 考え方と哲学
笹川陽平の多岐にわたる活動の根底には、彼独自の思想と哲学が存在する。
彼は、現代社会の複雑な問題には協調的アプローチが不可欠であると強く信じている。この信念に基づき、政治、政府、学術、民間といった多様なセクターを巻き込んだ広範なネットワークを構築し、問題解決に取り組んできた。フォーラム2000の運営はその典型であり、世界中の専門家や著名人が集まり、地球規模の課題について議論する場を提供している。
笹川は、自らを社会起業家と位置づけている。これは、単に慈善活動を行うだけでなく、社会問題に対して持続可能で革新的な解決策を模索し、実行していく姿勢を意味する。彼の国際援助活動が「食料安全保障」「医療」「教育」という生活に不可欠な分野に焦点を当てていることや、国内で政府の政策が及ばない分野に重点を置いていることは、この社会起業家精神の表れである。
特に、ハンセン病の制圧活動においては、医学的側面だけでなく、患者・回復者が直面する人権問題としての側面を強く提唱してきた。これは、彼が差別や偏見といった社会構造的な問題に深く切り込み、人々の尊厳を守ることに強い信念を抱いていることを示している。国連人権理事会での決議採択への貢献や、インドでの支援財団設立は、この人権擁護への強い信念が具体的な行動として結実したものである。
また、彼は公益活動における情報公開の重要性を強調し、自身の活動や考えをブログで日々公開している。これは、社会全体が公益活動に参加するべきだという彼の考えと、企業の社会的責任(CSR)活動を推進し、国、自治体、NPO、企業が一体となって共通の利益を創出する社会を目指すという彼の哲学を反映している。
6. 受賞・栄典
笹川陽平は、その多大な社会貢献活動が国内外で高く評価され、数々の賞や勲章、名誉学位を授与されている。
- 1989年 グラン・オフィシェ・ロードル・デュ・モノー賞(トーゴ共和国)

- 1995年 ジブチ共和国ラ・グランド・エトワール勲章
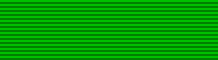
- 1996年
- 1997年 中国衛生賞(中華人民共和国)
- 1998年
- WHOヘルス・フォア・オール金賞
- ヨルダン・ハシミテ王国功労勲章一等
- 2000年
- 2001年
- ヴァーツラフ・ハヴェル記念名誉賞(チェコ共和国)
- ミレニアム・ガンディー賞(国際ハンセン病連合)
- 2003年
- 2004年 読売国際協力賞(日本)
- 2006年
- 外国人マリ共和国国家勲章コマンドール

- 国際ガンディー賞(インド)
- ハンセン病患者へのスティグマと差別をなくすためのグローバルアピール開始
- 外国人マリ共和国国家勲章コマンドール
- 2007年
- フィリピン沿岸警備隊名誉章
- モンゴル国北極星勲章
- マラッカ・シンガポール海峡保護のための航行援助基金設立
- 2008年 ハンセン病患者の人権に関する日本政府親善大使に就任
- 2009年 ASEAN事務局-日本財団ハンセン病と人間の尊厳プロジェクト開始
- 2010年
- ロシア自然科学アカデミー名誉会員
- ロシア正教会総主教勲位
- マレーシア功労勲章コマンダー
- エチオピア連邦民主共和国ミレニアム・ゴールドメダル
- 東ティモール民主共和国東ティモール勲章
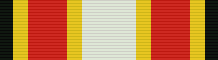
- アイスランド共和国ファルコン勲章

- スウェーデン王国北極星勲章コマンドール1等

- デンマーク王国ダンネブロ勲章

- ノルウェー王国功労勲章コマンドー章

- フィンランド白薔薇勲章コマンダー章

- ノーマン・ボーローグ・メダル
- 2011年
- 中央アフリカ共和国功労勲章コマンドール賞
- カンボジア王国友好勲章大十字賞

- 東京-ワシントン対話を開始
- 中央アフリカ共和国功労勲章コマンドール賞
- 2013年 セルビア共和国功労金賞
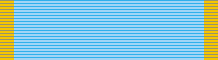
- 2013年 ベトナム友好勲章

- 2014年 国際法曹協会法の支配賞
- 2015年 国際海事機関国際海事賞
- 2016年 ブルガリア科学アカデミー名誉メダル
- 2017年
- WHOヘルス・フォー・オール金賞
- ヤギェウォ大学Plus ratio quam vis Medal(知は力より強しメダル)
- 国際看護師協会保健人権大賞
- ユネスコ政府間海洋学委員会オーシャンズエイト賞
- 2018年
- 2019年
- ガンディー平和賞
- 文化庁長官表彰
- 旭日大綬章
- 文化功労者
- 第35回正論大賞
- 2021年 エクアドル共和国国家勲章グラン・オフィシアル章
6.1. 名誉学位
- 2000年
- 2003年
- 中国医科大学名誉教授
- モンゴル国・経済アカデミー名誉博士
- 2004年
- 中国・上海海事大学名誉教授
- 世界海事大学名誉博士(スウェーデン)
- 中国・黒龍大学名誉教授
- 中国哈爾浜医科大学名誉教授
- 2005年
- インド・ジャタプール大学名誉博士
- 国際海事大学連合名誉会長
- 2006年
- 中国・大連海事大学名誉教授
- 2007年
- カンボジア大学名誉博士
- 中国・貴州大学栄誉博士
- ロチェスター工科大学名誉博士(アメリカ合衆国)
- 2008年
- 平和大学名誉博士(コスタリカ)
- 中国・大連外国語学院名誉教授
- 2009年
- 中国・雲南大学名誉教授
- 2010年
- ロシア自然科学アカデミー名誉会員
- 2012年
- 2013年
- ヨーク大学名誉博士号(イギリス)
- 2016年
- ソフィア大学名誉博士号(ブルガリア)
- 2017年
- ミネソタ大学名誉法学博士号(アメリカ合衆国)
- 2018年
- モンゴル工業技術大学名誉博士号
- 吉林大学顧問教授号(中国)
- 2019年
- アテネオ・デ・マニラ大学名誉博士号(フィリピン)
- 2023年
- ベオグラード大学名誉博士号(セルビア)
7. 著書
笹川陽平は、自身の活動や思想について複数の著書を執筆している。
- 『地球を駆ける-世界のハンセン病の現場から』(工作舎、2021年)
- 『愛する祖国へ』(産経新聞出版、2016年)
- 『紳士の「品格」2』(PHP研究所、2015年)
- 『残心』(幻冬舎、2014年)
- 『紳士の「品格」』(PHP研究所、2012年)
- 『隣人・中国人に言っておきたいこと』(PHP研究所、2010年)
- 『不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い』(明石書店、2010年)
- 『若者よ、世界に翔(はばた)け!』(PHP研究所、2009年)
- 『人間として生きてほしいから』(海竜社、2008年)
- 『この国、あの国』(産経新聞社、2004年)
- 『世界のハンセン病がなくなる日』(明石書店、2004年)
- 『二千年の歴史を鑑として』(日本僑報社、2003年)
- 『外務省の知らない世界の"素顔"』(産経新聞社、1998年)
- 『My Struggle against Leprosy』(Festina Lente Japan、2019年)
- 『No Matter Where the Journey Takes Me: One Man's Quest for a Leprosy-Free World』(Hurst、2019年)
8. 評価と影響
笹川陽平の活動は、その広範さと影響力から、国内外で様々な評価を受けている。
彼の最大の功績の一つは、ハンセン病の制圧と患者・回復者への差別撤廃に向けた長年の取り組みである。世界保健機関(WHO)の特別大使として、彼は多剤併用療法(MDT)の普及に貢献し、世界のハンセン病患者数を劇的に減少させた。さらに、ハンセン病を単なる医学的問題ではなく、人権問題として国際社会に提起し、国連人権理事会での決議採択に導いたことは、その影響の大きさを物語っている。この活動は、国際ガンディー賞など数々の国際的な賞によっても認められている。
社会起業家としての側面も高く評価されている。チェルノブイリ被害児童支援、アフリカの食糧増産運動、グローバル奨学金ネットワークの構築など、彼の主導するプロジェクトは、政府や既存の国際機関が十分に手が届かない分野において、持続可能な解決策を模索し、実行してきた。政治、政府、学術、民間といった多様なセクターを巻き込む協調的アプローチは、現代の複雑な社会問題に対する有効な解決モデルとして注目されている。
一方で、彼の活動、特にミャンマーへの関与については、議論を呼ぶ点も存在する。彼はミャンマー国民和解担当日本政府代表として、長年同国の平和プロセスに関与し、学校建設などの支援を行ってきた。しかし、2021年ミャンマー軍事クーデター後も、国軍最高司令官との対話を継続していることに対し、一部のメディアや専門家からは、その役割の曖昧さや、クーデター政権に正当性を与えることにつながるのではないかという批判が提起されている。この点は、彼の活動が持つ複雑な政治的・人権的側面を示している。
また、日本財団の主要な財源が競艇事業の収益であること、そして東日本大震災復興支援においてフィリップモリスからの寄付を受け入れたことなど、資金源や協力関係の選択についても、社会的な議論の対象となることがある。これらの批判に対し、笹川は自身のブログなどで見解を表明し、活動の透明性を高める努力をしている。
総じて、笹川陽平は、ハンセン病制圧や国際協力、国内福祉といった分野で顕著な業績を挙げ、そのリーダーシップと社会起業家精神は高く評価されている。同時に、彼の活動は、特にミャンマー問題のように、国際政治や人権の複雑な文脈の中で常に客観的な評価と議論の対象となっており、後世に多大な遺産と問いを残している。